アレクサンダー・フレミングは細菌を滅ぼすべく実験を重ねて抗生物質を発見したわけではなかった。それは本当に偶然の産物だった。雑菌が混入してしまったために培養地が破壊されたシャーレを清掃しようとしていたフレミングは、邪魔者の青カビが培養地にぽっかりと穴を開けていることを不思議に思った。顕微鏡を覗いてみると、青カビから出る体液によって細菌の成長が阻害されているように見えた。それから十年が経ち、ペニシリンは実用化された。その画期的な薬は、産業革命以降最大限に高まっていた人口増加圧を果てしない勢いで押し上げた。それはあの星で二十世紀最大の発見といわれた。
講義が終わってざわついている教室の中で、滅菌工学部生のヤキ・ムはしばらく考え込んでいたが、恋人のアースラに声をかけられて頬杖から顔をあげた。
——ヤキ、まだティムるのが怖いの?
——怖い? と、ヤキはムキになって答えた。別に怖くはないさ。俺たちが兵役に行く頃には、ドクトルも進化して、どんな菌にだって耐性ができている。先生も言ってたろ。人類はもう、偶然さえコントロールしはじめてる。
アースラはほどよくそばかすをまぶした頬をへこませて、おどけてみせた。変に怯えたって仕方がなかった。ヤキもアースラも大学を卒業したら、地球へ行くことになっているのだから。
——今期の試験が終わったら、アダプタつけてタイタンにでも行こう。それぐらいの与信金は貰えるだろ? それに、お前もあと二人ぐらい産んでからじゃないと兵役に間に合わないだろうし。
——え、私もう兵役免除してるよ? もう六人産んだから。
——五人? まだ三人じゃなかったっけ。
——ああ、最初は三つ子だったし、三回目が双子だったから。
ヤキはあからさまに残念そうな顔をしたのだろう、アースラは、でもヤキの子供も産むつもりだよ、と肩に手を回した。それも、できれば女の子を。アースラから娘が生まれるという想像が、帰ることのない兵役に向かうヤキを励ました。
*
三年が経ち、0・8ミリ以上の血管にドクトルをちりばめたヤキ・ムは、地球帰還師団の第三中隊配属の二等兵としてシャトルに乗っていた。結局のところアースラとの間に生まれたのは男の子で、その後ヤキが子をなすことはなかった。胤というのはいささか頼りない結果だったが、いまとなってはどうでもいいことだった。
シャトルが離陸し、身体が軽くなって巡航モードに入った。ベルトが解かれるよりはやく、トム・ミルス伍長が船の中心をすーっと泳ぎ進んだ。
——本隊は降下し次第、南米経由で南極を目指す。大隊と合流できなかった場合は、各自転送体系に切り替えろ。緯度七十未満で巨菌どもと出会ったら命はないと思え。お前らヒヨッコどもにできることは何もないぞ。噂では、精子をぶっかけると死ぬらしいからな、襲われてアイスクリームみたいに溶ける前にマスでもかけるかもしれないぞ。もしかしたら、それを見た火星の女どもが妊娠するかもしれん。どうした? 笑うところだぞ?
隊の中に笑うものはなかった。すでに二回も火星への帰還を果たしている伍長は、歴戦の猛者であるとともに、三文字もあるその苗字から窺い知れる通り、名家の出だ。ヤキたちのような二等兵とは質の違うドクトルを埋めこんでいるはずだし、たぶん本隊も彼を優先的に救うのだろう。そんな冷ややかな視線に気づいたのか、伍長は新兵の中から手近な者を選んで、煽るようにまくし立てた。おい貴様、歯は磨いたか? 虫バイキンがお前の口からお前のことを裏切るかもしれないぞ? ほら息を吐いてみろ! 臭い! 消毒してやるから口を開けろ……おきまりの新兵いじめが続き、結局のところ、その新兵は伍長が機内に放った小便の玉を口で吸い取ることを余儀なくされた。半ば泣き出しそうになりながら、無重力にさすらう黄色い水玉をパクパクをくわえて回る様を見て、伍長は笑い転げた。
——この隊は全滅するだろうね。
キムの隣に座っていたソル・ングがほどなくして呟いた。毒学部で首席だったという彼もまた、育ちの悪さ(といっても、ヤキよりは苗字が長いのだが)のせいで、死地に赴くことになっていた。
——なあ、ヤキ、お前子供は何人残した? 突然訪ねられて、隠すものでもないとは思ったが、正直に一人だけ、それも男の子、と答えた。
——そうか。俺はゼロなんだよな。
——ゼロ? お前はゲイなのか?
——いや、なんていうか、巡り合わせだよ。たまたま運がなかった。好きな子はいたんだけどね。ずっとその子のことを好きだったのがまずかった。
——しかしその子もひどいな。別に一人ぐらい、普通は産んでくれるだろう。いつから好きだったんだ? 十歳?
——どうだろう、覚えてないな……たぶん五歳ぐらいじゃないか? ソルはそう言いながら少し泣きそうな仕草を見せた。たぶん、ずっと生涯をかけてその子のことを愛したのだろう。そしてそれは結局叶わなかった。そう考えると、アースラはずいぶん優しい女だったのかもしれない。
ホーマン軌道に合流して戦略物資を受け取るまでの一ヶ月間、ヤキはソルとよく話した。二十一年の人生をかけて叶わなかった恋について、ああすればよかったとか、こうすればよかったとか、そういうくだらない仮定の話だ。七人の胤を残して結局一人も女の子が生まれなかったペコも加わり、コクーンへの降下まではあっという間だった。
*
マルスリア歴二五六年の五月、ヤキの乗るVAT1332号は地球への降下を開始した。サム・ホイヤー衛星からの砲撃によってわずかに穴が空いたコクーンの合間を塗って、高度一万三千メートルまで降りて行く。薄暗い繭の中に太陽光が降り注ぐと、着陸地点の菌どもは死滅して緑の地表がむき出しになる。大気圏の下を覆う菌の雲がその穴を修復し、地球がふたたび闇に包まれるまで三時間、その間に胞子を噴出する世界樹を五〇キロ四方で死滅させなければならない。もし失敗すればその時点で第三十四次回帰作戦は失敗となり、本隊は二十に及ぶ小隊を見捨てて火星へと一時撤退を行う。作戦成功後は、当初の予定どおり、着陸地点である南米大陸からもっとも菌の薄い南極大陸を目指し、徒歩で移動。帯水によって膨れ上がった黴海の森を抜け、南極大陸にたどり着いたのち、滅菌のためのコロニーを築く。太陽光充電設備ソラライザーを築くことができれば、この三十年続いた回帰作戦はその成功の端緒を掴んだことになる。
効果開始後から十八時間が経って、ヤキ・ムはまだ行軍を続けていた。黴海の森までは後わずか、リオ・グランデ海脈の絶壁を踏破しようというところだった。薬莢はまだ豊富だが、おそろしく喉が渇いていた。時折、胸の写真を握りしめた。ソルがその生涯をかけて愛したボラータの写真。珍しい褐色の肌と黒い目をしたボラータに愛していると伝えてくれというのがソルの最後の言葉だった。二本目のユグドラシルに着火剤をふりかけている最中、ソルはずれたマスクの右側頭部から侵入した黒カビの高速膨張によって頭半分が熟れすぎたメロンのようになって死んだ。ドクトルの移植を行い、血中の淀みが吹き払われて行くのを感じながら、たしかにヤキはソルが「愛していると伝えてくれ」というのを聞いた気がした。
黴海の森では、立ち込める瘴気の中で何人かが倒れていった。強壮を誇った一等兵のベン・ゴイも肺をやられ、弓のように体をしならせて死んだ。十人いた小隊はもう三人しか残っていなかった。スティンギー・ボールが吹き出す瘴気にやられ、一人また一人と死んでいった。
——ほら、ペニシリン野郎ども! マチュピチュ基地が見えてきたぞ! ミルス一個師団さまの一番乗りだ!
そうやって空元気を出して叫ぶミルス伍長が指す先には、かつてはこの星に住んでいた人類が海の突端に作った遺跡が、こんもりと菌をまとった山塊となっていた。ヤキの果たすべき仕事は、あの基地を奪回することとだ。
山脈は果てしなく高かった。かつては冒険者たちを飲み込み、鯱や鯨といった巨大生物の死骸が降り積もった海の底から、大陸の端にあった専従者たちの遺跡が薄い影になっていた。
*
——いったい、発見とはなんだろう? そんなもの見つけなければよかったのでは?
ヤキ・ムは奪還した南極の地に弱く降り注ぐ太陽の光を両肩に感じながら、お湯を飲んでいた。黴海に咲くスティンギー・ボールやモールド・ツリーを漉して作った水だ。自動免疫最大化ボットであるドクトルは胸郭に集中してある。喉越しは悪くないが、そのあとから立ち上るカビの匂いがどうしようもなく臭かった。
白夜が終わり、半年が経つと明けない夜が来る。その前に少なくともリエスコ島までは回復しなければならない。
——いったい、発見とはなんだろう。ふたたびヤキは呟いた。そもそも、フレミングがペニシリンを発見しなければ、ここまで菌が強くなることはなかった。殺すことのできない菌が猛威を振るい、火星の植民地が唯一の人類の避難所となった。それから、人類は火星という過酷な環境で人口を回復する手段として、女は子を産み、男は戦った。まるで精子みたいだ、とヤキは思った。
ヤキは火星から持ってきた滅菌学の教科書をときおり開いた。というのも、地球でできることなど何一つなかったからだ。培養地を防衛し、援軍が届くまでの何ヶ月かを南極のベースで過ごしている。それはもしかしたら半年かもしれないし、もう援軍はこないのかもしれない。さして意思も持たない風に基地に襲いかかって来る菌を焼き払いながら、それでもやはり教科書を読むたびに、フレミングはあのときうっかりペニシリンを発見するべきではなかったのでは、と疑わずにいられなかった。シャーレの中に青カビをこぼさなければ、こんなことにならなかった。そう思うたび、ヤキは胸ポケットに入ったボラータの写真を握りしめた。もうアースラの顔も思い出せなかった。
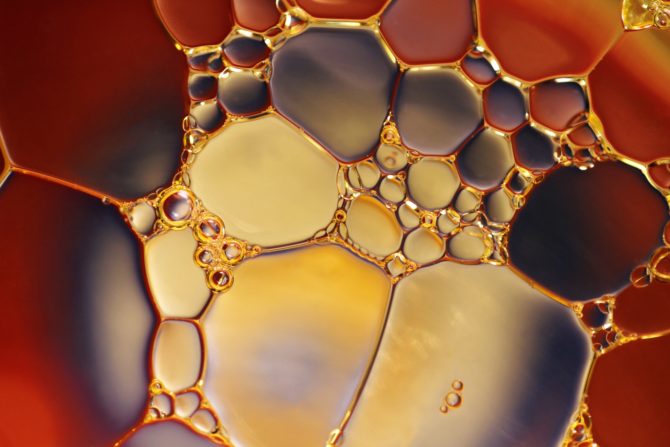






















よたか 投稿者 | 2017-10-20 13:11
『復活の日』の南極基地の様子や、腐海の森を行くナウシカを思い浮かべてました。
菌はなんらかの栄養分がないと繁殖できないので、どんどん枯渇していってしまうのでしょうね。
でも栄養が枯渇しても、火星で繁殖した人間が来て栄養を補給してくれるから大丈夫といった感じかもしれませんね。
縹 壱和 投稿者 | 2017-10-20 21:25
人を救うペニシリンが、人を過酷な状況に陥らせているというのが、皮肉だなと思いました。
科学は苦手で、難しそうだと思いましたが、面白かったです!
斧田小夜 投稿者 | 2017-10-20 23:21
面白かったです。たしかに誰も悪くない星間戦争でした。
いっそのこと帰還計画を一千年くらいストップすればたぶん菌は死滅すると思いますが、わざわざ栄養になりにいってしまうのは人間の業というやつなんでしょうか?
藤城孝輔 投稿者 | 2017-10-21 16:55
今回の合評会作品ではSFとして最も読みごたえがあった。苗字の字数と社会階級との相関関係や生殖に対する考え方などのディテールが世界観を支えているのだと思う。「ヤキはムキになって~」のようなダジャレの不意打ちもいい。
ただ、この世界観は設定にしても登場人物の多さにしても、もともと10枚に収まるサイズのものではないと思う。そのため、制限字数に無理やり押し込めているという印象を強く受けた。例えば、「ティムる」という造語は雰囲気を出してはいるが意味はよく分からないままであり、ベン・ゴイは一度だけの言及で片付けられてしまい、ペコはどうなったかさえ分からない。最後から二番目の段落におけるあらすじのような背景説明は、物語をまとめるために仕方なく挿入されている感じがする。もっと長い形で読みたい作品だ。