最後は逆にコーランだよ、と呟いて、感人は言い返したような気になっているらしかった。
「でも、結局山谷で慈善事業やってるのって、キリスト教ぐらいじゃないですか?」
タカハシは言い返すつもりはなく率直に返事を返しただけだったが、一度でも反論の構えを取ると次の矢を構えずにいられない質だった。
「イスラム教ってあんまり見ないし、神社仏閣は中高年相手の商売ですよね。今日だって、炊き出しのお知らせ出してるのは、キリスト教会しかなかったじゃないですか」
ほんとうに、言い包めてやろうというつもりはない。「どの宗教がもっとも文学的に重要か」というテーマにも興味はなかった。カントは前髪の影に隠れるようにして俯きながらビールを煽った。焼き鳥屋が出したビールのコップは小さく、すぐに空になった。カントはコップを見つめ、KIRINという文字をおまじないのように二度撫ぜた。
「炊き出しとか、そういう世俗的な意味とは違うんじゃないの。俺ぐらいアルやってるとさ、イスラム教のありがたみがわかるんだよ。酒なんてあんま飲むもんじゃないって」
言われたタカハシは、隣にいた悠太に、アルってなんですか、と尋ねた。聞かれた悠太は自信なさげに目をうろつかせてから、アルコールのことじゃねえの、と答えた。そして、言い訳めいた囁き声で、どう、こいつ面白いでしょ、と耳打ちした。タカハシは、はあ、と曖昧に同意しながら、カントを見た。カントはスーツを着ていたが、ワイシャツの襟元がひどく汚れていて、下着の黒いTシャツも透けていた。
「でも、コーランにはアルコールの禁止は明文化されてないはずですよ」
タカハシは終わりかけた会話を再開させた。それはまた反論の響きを持った。
「でもねえ、タカハシくん、大事なのはそこらへんの明文化されてないガチャガチャ感? そうでもなきゃ、小説なんて書かないでしょ?」
「誰がですか?」
「そりゃ、決まってるでしょう?」
カントはそう言うと、立てた片膝に肘を乗せ、親指で自分を指した。カウンターに座ったニッカポッカの男が、攻撃的な目で見ていた。なぜコーランのアルコールに関する記述が曖昧だという理由で、カントが小説を書かねばならないことになるのか。タカハシは説明を求めなかった。その病気めいた論理は、三十過ぎの小説家志望が掲げそうなものだった。
「最近の小説家って、カントくんみたいに酒飲んで夜更かしするイメージじゃなくて、朝早く起きて書くらしいですよ。意外とマジメなんですって。アーヴィングとか」
「マーウィン?」と、カントは不審な動きで身を乗り出した。「誰それ? ロシア?」
「アメリカですよ」
「ああ、アメリカ。チャンドラーとかの一派でしょ」
タカハシは否定しようと思ったが、小説を書くには情報の正確性など必要なかったので、そこら辺です、とお茶を濁した。カントは満足げに笑った。危機を脱した、という安堵が口元の皺に覗いていた。
「しかし、タカハシくんも知ってるねえ。俺もチャンドラーはアルだからギリ読んでるけど、かなりマニアックだよ。書いてるでしょ? 小説」
「別に書いてないですよ。ねえ?」
タカハシが隣に座った悠太に尋ねると、そうだよ、という笑いが返ってきた。
「タカハシは単に調べものが好きなんだよ。俺も、論文書くときに足立区と港区のペットの犬種の違いを調べてもらったことあるぜ。ボツだったけど」
「あ、あれボツになっちゃったんですか」
悠太はタカハシの肩に手を置き、ごめぇん、と甘えた。
「勿体ないねえ」とカントは腕を組んだ。「タカハシくんが書いてれば、俺と二人で太宰と安吾風にブイブイ言わせられたのに。なんで書かないの?」
「なんでって……書かないのに理由なんてあるんですか? カントくんだって、理由があって書いてるわけじゃないでしょ?」
「俺の場合、十八でロックするために東京に出てきて、それから小説書くようになったんだよね」
「あ、音楽に挫折して、小説に変更したんだ」
タカハシは思ったことをそのまま言った。カウンターで飲んでいた男が、挑む目つきでこちらを見た。さっきから、この席の会話を気にしているようだった。なにかが挑発的なのかもしれなかった。それが自分なのか、それともカントなのかはわからなかった。
カントはアルコールが喉を刺す痛みを堪えるような顔をして、いや、ヒバリが死ぬのを見てさ、と話し始めた。
ヒバリというのは、カントが十八の時分に長崎から一緒に上京してきた親友だという。上京を機に、今日から俺は小柴雲雀な、と改名宣言したらしい。太宰治の『パンドラの匣』の登場人物名を唐突に名乗るぐらいだから、カントが太宰に傾倒するようになったのも、しょうがないことだったそうだ。そのヒバリは重度のアル中で、二十七の若さで死んだ。死ぬまでに幾度も行われた手術のせいで、ヒバリの遺体はパッチワークのようになっていたらしい。
「晩年のヒバリはヤバかったよ」と、カントは思い出し笑いを浮かべながらいった。「ずっと同じ曲ばっかり聴いてた。壁にはGAOの『サヨナラ』が三枚も飾ってあったからね。エイメン」
胸の前で十字を切るカントを見て、タカハシは思わず笑った。悠太がすかさず、ね、この話、ウケるっしょ、と突っ込んだ。
「懐かしいですね、GAOって」
「しかも、そのCDって、昔のシングルだからさ、あの細長いヤツなんだよね。いやあ、あいつもレイナード・スキナードみたいな泥臭い南部ロックを志して上京したのに、最後はGAOだったからね」
笑うカントを、タカハシは偉いと思った。親友が死んだ話を笑ってできるメンタリティがどんなものか、タカハシがこれまで生きた時間は教えてくれなかった。
焼き鳥屋を出ると、打ち解けるにはうってつけの時間が過ぎていた。すっかり上機嫌になったカントが山谷の町を案内してくれた。東京にもスラムがあると聞き、前々から行ってみたいと思っていた街だったが、想像以上の感慨をもたらした。すれ違う女は強姦を恐れて道の端まで避けて走り、三十秒に一度ほどパトカーのサイレンが聞こえてくる。路傍に座る男が突然声をかけてきて、パチンコで負けたと悔しがっては金をせびる。悠太は、これネタになるでしょ、と呟いた。
「フィールドワークを論文にまとめて新書として売り込めば、出版されるんじゃないですか」
「そうだよ、ギャグみたいだろ?」
そう応じた悠太は、人生が、と付け加えた。年末の寒い時節だった。吐く息は白く、なにがしかの深刻さがその顔に宿っていた。悠太も大学院に落ち続けたまま二十八歳になり、追いつめられていた。博士研究員はおろか、大学院にさえ受かっていなかった。タカハシはその事態の深刻さを感じ取った。が、感じ取っただけだった。まだ何者でもなく、何者にもなろうとしていないというのに、その深刻さを共有することはできなかった。
「この先のさ、労働出張所ってところに、俺の知り合いのルンペンがいるから」と、先頭を歩いていたカントが振り向いて言った。「ちょっと会ってこうよ」
「お、来たねえ。ボスキャラ登場じゃん」
悠太が答えた。
「ある意味、この町のボスだからねえ。自称だけど」
「でも、大丈夫なんですか。そんな人に会って。ヤクザとかじゃないんですか」
「まあ、タカハシくん、心配しないでよ。俺も一時期都落ちして浜松に住んでた頃は、下手に自警団気取ってて、ブラジル人引き連れてたからね」
「なんですか、自警団って」
「夜中にさ、竹刀持ってパトロールするんだよ、街を。俺、剣道やってたからねえ、あんときは凄かったよ。ガイジンってさ、必要以上に武道を恐れるからね。俺が今回東京に出てくるとき、全員浜松駅で敬礼して見送ってたからね」
タカハシは思わず疑う目をした。カントはせいぜい中背といったところで、身体の線は細い。とてもブラジル人を率いていそうには見えなかった。
「カント! それ小説に書けるよ」
悠太は夜のスラム街で大の字になってはしゃいだ。都営住宅のベランダから、人影が見下ろしていた。とかくリアクションの大きな男だった。タカハシは彼が社会学の研究者としてより、お笑い芸人として大成するのではないかと密かに思っていた。
「まあ、見ればわかるからさ。いざとなったら、俺が盾になって二人を守るよ。刺せオラー、ってね」
カントは両手を広げて腰を振った。刺せ、オラー! 哄笑が壁に当たって虚勢になった。玉姫保育園にぐるりと巡らされた高い壁には、園児たちの描いた絵に落書がされていた。闇夜の中だったから、水色の地色で醜悪に浮き立った。
保育園の裏手にある労働出張所の軒下で、初老のホームレスに会い、手土産として持って行ったワンカップを渡した。ホームレスはワルだった昔の話をしながら、ワンカップを一息で飲み干した。ものの三秒とかからずに飲み干すと、カントが負けていられないと同じペースで飲み干した。アルコールについてだけは譲れないようだった。親友を殺したものに魅せられているのか。口の端から日本酒の雫を滴らしてワンカップを煽るカントは、どう控えめに見ても社会不適合者だったが、ある種、文学者としての凄みを秘めているようにも見えた。
意地の張り合いがエスカレートして、大袈裟に買い込んだ二十本のワンカップはすべて空になってしまった。そこら中に瓶が転がり、日本酒の甘い匂いが立ち込めていた。ホームレスの話はどんどん怪しくなり、しまいには元警察官だったのか、元ヤクザだったのか、設定が行方不明になってしまった。タカハシは、ヤクザもマフィアも始まりは自警団だったんですよね、と薀蓄を垂れ、話を合わせようとしたが、ホームレスはただひたすら拳銃を撃つときの心得——肘を抑えて下を狙え!——を繰り返すだけだった。
鯨飲して気が大きくなったらしいたカントは、酔い潰れたそのホームレスを段ボールハウスに手荒く押し込むと、おぼつかない足取りで、酔いどれ天使! と叫びながら、さらに歩き出した。
「次、どこに行くんですか」
タカハシが尋ねると、カントは肩を組んできた。
「敬語はやめようぜ、兄弟」
吐息に揮発したアルコールが混じっていた。この男はそう遠くないうちに死ぬな、という暗いひらめきがタカハシを打った。そして、カントが、教会に行こう、と言ったことで、その確信はますます強まった。
教会といっても普通の一軒家で、居間では宿無しらしい男たちがモソモソと食事を取っていた。伏し目勝ちで、酔客を一瞥さえしなかった。泥酔していて失礼じゃないかと危惧したが、カントも知らない顔ではないらしく、静かに受け入れられた。カントは再びコーランに関する話を蒸し返したが、タカハシにはなにを言っているのか上手く聞き取れなかった。机の上にあるチゲの煮込みには、冷えた脂が白く固まっていた。ときおり、炊き出しを食べる男たちがちらりとこちらを見ているのがわかった。だが、彼らは決して話しかけようとはしなかった。それがひどく居辛くさせた。
「カント、もう行かねえ? 迷惑だし」
興ざめしたらしい悠太が言った。仰向けにひっくり返ってキリストを罵っていたカントは、む、ああ、と起き上がった。片目が充血していた。起きざまにその目を激しくこすったせいで、ますます赤くなった。
もう帰ろう、ということになっていたのだが、カントは最後に自分が泊まっているドヤを見せると言い張った。タカハシも悠太もこれ以上何かを見たいとは思わなかったのだが、念を押すカントに根負けした。知識を増やすことにだけ喜びを感じるタカハシも、社会学の研究をしている悠太も、スラムのドヤ——宿をひっくり返した日雇い労働者の隠語——を見たくないといえば嘘になる。それに、これから一緒に住むことになるカントが、これまでどんなところに住んでいたのかは知っておくべきだった。
カントが泊まっているドヤは、泪橋交差点からすぐのところにあった。一泊二四〇〇円だが、この界隈では安くないという。三畳間に置かれたベッドに、三人で横並びに座った。枕元の棚には谷崎潤一郎全集の六巻と岩波文庫のコーランが置かれていて、一番上にニコちゃんマークの灰皿があった。テレビにはスポーツタオルがかけられていて、もしかしたら執筆の邪魔にならないよう見えなくしているのかもしれなかった。
三人はひとしきり家賃や部屋割りについて話し合った。一人三万二千円を払うことで、八万円の家賃と、高熱費その他に充てることになった。タカハシはその家賃であの部屋に住めることのメリットをまくし立てた。家賃に含まれる朝日新聞・固定電話・インターネットADSL接続、風呂トイレ別、追い焚き可能なバランス釜、はじめから付いている家具、各部屋についたエアコン、南向きの大きなベランダ、そこからは教会の十字架と、春には桜が見える……。タカハシが嬉々としてまくし立てていると、一人カントは急に黙り込み、俯いた。
「泣いてるんですか?」
「いや、違うよ」
カントはそう言うと、ズボンの太腿あたりで手を拭い、握手を求めた。
「よろしく頼むよ、兄弟」
「うん、よろしく」
タカハシはその手を握った。兄弟、という言い方には無断で背筋を撫で回される不快なむずがゆさがあった。
カントと同居することに決まってから、なんでそんな変な奴と、と不思議がる声は聞かれたし、当のカントも、よく俺みたいな輩と一緒に住もうと決めたねえ、と居間のソファにふんぞり返って感心した。
「タカハシは変な奴への耐性が強いからさ」と、悠太が注釈を入れた。「俺がここに来る前に住んでた丸毛くんも、すげえ変わってたよ。俺、一回だけ会ったことあるけど」
「ああ、聞いたよ。丸毛くんも太宰好きだったんだって?」
「好きだったよ」と、タカハシは答えた。「工学部だったけど、俺より文学詳しかったから」
「超エリートだったんだぜ」と、悠太がさらに注釈を入れた。「偏差値八〇ぐらいあったんだってさ」
「凄いねえ、それ。逆にアホなんじゃないかってぐらいだねえ。タカハシくんもいるし、俺、乞食同然だから、申し訳なくて土下座しちゃうよ」
「カント、俺の気持ちがわかったろ?」
「まあねえ。プレッシャーが凄いよ」
「あ、そうなんだ」
タカハシは同居人である悠太の発言を聞き、そこまで不快な思いをさせていたのかと心配になった。
「いや、いい意味でだよ?」と、カントがすぐにかぶせる。「俺みたいなゴミは、プレッシャーがないと、小説、書かないからね。でも、タカハシくんも、俺やら、悠太やら、丸毛くんとやらじゃなくってさ、もっとまともな人間と住めたんじゃないの? 天下の帝大を卒業してるんだから」
「でも、同級生でまっとうに生きてる奴はたくさん金貰ってるから、生活レベルが合わないんだよ。ルームシェアって言っても、一人十万ずつ出して、代官山に住むとか、そういうブルジョワ的なアイデアしか出てこないから」
「いや、そうじゃなくてさ」と、カントが反論しようと不安げに身を乗り出したところ、悠太がかぶせた。「カントが言いたいのは、タカハシだったら、自分で稼いでいい所に住めるってことだろ?」
「そうそう」と、カントは浮かせた腰をソファに沈めた。「タカハシくんなら、六本木ヒルズあたりに住もうと思えば、住めたんじゃないの? こんな、北千住のボロマンションじゃなくてさ」
「いや、金儲けっていうのは、独得の嗅覚が必要だよ。アメリカの二千万プレイヤーは、週に九十時間ぐらい働くらしいからね。俺はせいぜい三十時間が限度だよ」
タカハシがそう言うと、カントと悠太は、でもねえ、といった具合に顔を見合わせた。しかし、タカハシはありもしない儲け話よりも、この部屋のことで頭が塞がっていた。
「でも、そんなボロいかな? 築二十年だけど、ちゃんと掃除してるし」
「いや、もちろん、いい意味でだよ?」と、カントは反論を恐れたのか、急に饒舌になった。「タカハシくんの掃除は完璧だしねえ。俺からしたら、お城に住んでるみたいな気分だけどさ、そこは敢えて言うけど、タカハシくんには門番がいるような家が似合うんじゃないかと」
カントに尋ねられ、タカハシは黙り込んだ。よく聞かれることだったが、いまだ明白な答えはなかった。
以前に同居していた丸毛は、タカハシを中産遊民と呼んだ。極度に飽きっぽく、好奇心と整理欲以外の欲望をほとんど持っていなかった。「調べる」と「整頓する」という二つの動詞が、彼の生活を支配していた。その二つの欲は、中産階級出の彼を東大には受からせたが、金持ちにはしなかった。一番好きな場所は、図書館やインターネット・フォーラムだった。日本十進分類法によって並べられた書架や、優秀な情報設計者によってカテゴリ分けされたトピックスは、タカハシの欲望を激しく刺激した。平日にフラフラと図書館に行ったり、ネットサーフィンをし続けるためには、固定費である家賃を極力切り詰め、働く時間を少しでも少なくしなければならなかった。タカハシは月に七日しか働かず、収入はわずかに十万円だったが、それで特に不満ということもなかった。
「俺って極度に飽きっぽいから、普通の仕事が続かないんだよね」と、タカハシはカントに答えた。「貧乏でも特に困ったことないし」
「そうかなあ、なんでだろうねえ」
「俺もそこが不思議なんだよなあ」と、悠太が言った。「いっつもなんか調べものしてるじゃん。普通、目標がなきゃ、そこまでできねえと思うんだけど。お前なら大学院ぐらい受かるだろ」
「調べ物してると楽しいじゃないですか。それだけですよ。その都度、小さな目標を見つけて生きてますよ。来年はもう二十八だけど」
「ときにタカハシくん」
カントはそう言うと、腕を組んで黙り込んだ。発言を待っても返ってこないので、悠太と二人でじりじりしていると、カントの顔に人を見透かした笑みが浮かんだ。
「本当に書いてないのかい? 小説」
「書いてないよ」
なんだ、という落胆と共に、タカハシは答えた。もっと調べ甲斐のある質問が来るのかと思っていた。
「ほんとかい?」と、カントは前髪の下から覗き込むように訝った。「タカハシくんは仏文科だったよね。東京帝大の仏文科といえば、太宰が出てるわけだし、逆に、文学の志があったんじゃ?」
「文学は好きだよ。東大って進学先を選べるから。本当は経済学部に行こうと思ってたんだけど、前の同居人だった丸毛が太宰好きだからお前が俺の代わりに行ってくれって頼まれて、フランス文学科に行ったんだよ。まあ、理系の丸毛でも文転っていう制度を使えば仏文に行けたんだから、代わりの意味もよくわからないんだけど」
「じゃあ、フランス文学にはかなり詳しいんだね」
「文学だけを勉強してたわけじゃないけどね。毎日フラフラと、気の向くままに調べ物してたよ」
「調べ物って、なにを?」
「そうだね」と、タカハシは大学の情報棟に立ち込めていたパソコンの排気の匂いを甘やかに回想しながら答えた。「丸毛と一緒に、神経とネットワークの接続に関する研究が、世界的にどれだけ進んでいるか調べてた時は熱かったなあ。丸毛は畑違いだったけど、理系だったから詳しくて助かったよ」
「ちょっと、それ、文学とぜんぜん関係ないじゃん!」
「まあ、遊んでたようなもんだよ」
そう言いながら、大学時代のタカハシは大真面目に勉強していたつもりだった。生来のグロテスクなマジメさを発揮して、ジャンル横断的かつ体系的に書物を渉猟した。弁論術や民俗学、天体物理に家政学と、すべての学問に手を出し、ついに何一つ身につけることなく大学を卒業した。潰しの利かない変り種の多かった仏文科ではあったが、タカハシの向こう見ずな人生設計は周囲をやきもきさせ、とりわけ彼の将来に「末は博士か大臣か」式の純朴な期待をしていた親戚一同の落胆は大きかった。就職もせず、アルバイトだけで食いつなぎ、何をしているかというと、「出現可能性のあるメディア形態とそれに応じた人間意識の変容性」とか、「経済交換におけるミスマッチを減らして永久機関的な経済を設立する不偏経済学」などという壮大な問題の調査ばかりしている彼は、学歴社会のユダであった。タカハシからすれば自分こそが学問の王道を歩んでいるという確信があったのだが、誰にも理解されないので言わないことにしていた。
「まあ、東大に入ることと社会的な成功は必ずしも比例しないよ。丸毛もそうだったし」
「丸毛くんは小説書いてないの?」
「書いてたけど、大学四年の頃に断筆宣言して、普通に就職したよ。村田製作所っていうメーカーに」
「どこそこ? 凄いの?」
「電子部品の最大手だよ。パソコンの部品で世界シェアの半分とか、それなりの電子機器の中には大体入ってるようなメーカー」と、タカハシはカントの無知に驚きながらも答えた。「丸毛は変わった奴だったけど、話とか面白かったし成績も優秀だったから、普通に内定を勝ち取ってたよ」
「凄いねえ。俺らみたいな凡人がする就職とは、全然違うねえ。殿上人の就職だよ。俺の地元のダチとかは、そういうメーカーの下請け工場に就職できたら、八つ墓村みたいにハチマキ巻いてバンザイ三唱だからねえ」
カントが腕を組み、再び自虐へと溺れそうになると、悠太が励ますように肩を叩いた。
「でもさ、丸毛くんの会社の辞め方、すごいぜ。これ、小説のネタになるからさ、聞かせてもらえよ」
「いいねえ、聞かせてよ」
「いいけど、どっちがネタとして使うかは、話し合って決めてくださいね」
あらたまって言われると、少し得意にならないではなかった。これまで、タカハシは丸毛の話をして、驚かれなかったことは一度もなかった。
「まず、丸毛はさっき言ったとおり、ものすごい勉強できる奴だったんだよ。大学でもトップの成績で、しかも授業をほとんど出ないでそれだから。理系だとどうしても出席しないと点がつかない授業も多いんだけど、それでもほとんど授業に出ないで高得点とってた。高校生のときにフランスにも一年留学してたから、フランス語もできたよ。それこそ、仏文科の俺より」
カントが、やるねえ、と嘆息した。
「で、就職なんて、試験と大して変わんないじゃん。だもんで、いいとこの内定取ったわけなんだけど、なんか、一年目の研修でシンガポールか何かに行ったら、現地でオールディシ症候群を発症したとかいって遁走しちゃったんだよ」
「なに?」と、カントが尋ねた。「オールドなんだって?」
「フランス語で『ここではないどこか症候群』って意味。丸毛が考えた病気なんで、知らないのが当たり前だよね。俺もしばらくそういう病気がホントにあるって信じてたけど、調べたら存在しないみたい。とにかく、発症すると全身に蕁麻疹が出てきて、痒くてたまらない。それこそ、いてもたっても。で、移動すると治まるらしい」
「凄いねえ。エリートのかかる病気は凡人と違うねえ」と、カントが言った。「それで遁走してどうしたの」
「帰りの飛行機の搭乗時刻にも現れなくて、捜索願やなにやらで周囲が大騒ぎをして。俺のとこにも警察から電話かかってきたし。で、一週間後だったかな、パリのネットカフェから『もう辞めます』っていうメールを上司に送りつけたんだって。なぜか俺にもCCで送りつけてきたよ」
「パリ?」
「そう。研修先のシンガポールから勝手に国際線に乗ってパリに行っちゃったんだよ」
「なんでパリなの?」
「だって、俺にフランス文学科行けっていったぐらいだから。パリは聖地でしょ」
悠太が爆笑し、カントこのネタ小説に書けるよギャグだよ、と叫んだ。カントもまた、書けるねえ、と同意した。
「で、丸毛が僕を誘って、ここに住むことにしたんですよ。実家帰りたくないから、一緒に住んで家賃を節約しようって」
「丸毛くんは何してたの?」
「はじめは弁護士になるって言ってたんだけど、次に司法書士、行政書士ってだんだん変えていって、結局一回も試験受けなかったよ。通信教育のテキストもわんさか届いたけど、全部未開封のまんまで。俺が資源ゴミに出したときに、新品すぎて指切ったから。その後はなんか、税理士事務所にバイトで入ったけど、研修二週間で辞めちゃったよ。なんか領収書なくして怒られた瞬間に辞表を書いたんだって」
「な、カント、これ絶対書けるだろ! 鉄板のネタだろ、コレ」
「たしかに、これは凄いねえ。俺も駄目ガンジーって言われてきたけど、そこまでの駄目エリートは聞いたことないよ」
「まあ、結局なにも身に付けないで実家の岐阜に帰ったけどね。最後はなぜか、俺が悪いことになってたよ」
「その気持ちはわかるよ」と、カントが言った。「俺も晩年のヒバリとはメチャクチャ仲悪かったからねえ。世界がそこだけになっちゃうんだよ」
「みたいだね。自分の分の昼飯作ってたら、ズルいぞとか怒られたし。なんで俺のを作らないんだって。ありえない被害妄想だったよ」
「まあ、タカハシくんもそういう経緯なら、俺みたいな奴と住むのも抵抗ないだろうねえ。悠太もあまり人見知りしないし」
「あれ、悠太さんとは前から知り合いだったんじゃないの?」
タカハシが尋ねると、悠太とカントは顔を見合わせ、いや、と答えた。この間に山谷で飲んだのが二回目だという。悠太がフィールドワークのネタを求めて、誰か面白い奴はいないか、と尋ねまわった結果、パチンコ屋で馴染みになったあの焼き鳥屋のマスターに紹介されたのがカントだった。カントが悠太と知り合ってから、この家に転がり込むまで、三週間ほどしか経っていなかったし、その繋がりもあるかなきかのものだった。
タカハシは少し考え込んだ。しかし、少ししか考えなかった。悠太だって二ヶ月の短期バイトで一緒だったという程度の仲で一緒に住み始めたのだから、大して変わらなかった。
「まあ、いいや。別に家賃払ってくれれば」
「家賃に関しては心配しないでよ。肝臓売ってでも払うからさ。俺のγ・GTPは千五百超えてるけどね」
平日の真昼間に男三人で白いソファに腰をかけてそんな話をしていることを、タカハシは楽しいことだと思っていたから、彼女の山田が顔をしかめるのがよく理解できなかった。二年も付き合っているというのに一向に同棲が始まる気配もなく、彼女としての自分を差し置いて、丸毛やら悠太やらカントやら、ケッタイな男ばかりが転がり込んでくる。タカハシと山田が寝る布団はシングルなのに、居間には二人がけのソファが二脚もある。風呂場の脱衣所にあるラックは三段だが、上からタカハシ用、悠太用、カント用で、山田が化粧品を置くスペースはない。トイレには生理用品を置く隙間がないほどトイレットペーパーの束が並び、ほんの少しの隙間があっても、尿石を強力に溶かす洗浄剤が詰められている。この部屋に、自分の居場所はない――山田はそう主張した。が、山田は彼女だった。タカハシと同居人の生活はきっちりと区分されていたが、山田はタカハシの生活空間を自由に使うことができる。それはいいことじゃないか――タカハシは何度か説明したが、理解してもらえなかった。
怒りの表情も作らずに、タカハシの部屋でふるふると布団に包まっていた。山田は滅多にタカハシの部屋から出なかった。トイレと風呂ぐらいだった。食事でさえ、居間のコーヒーテーブルではなく、タカハシが作ったものをタカハシの部屋に持ってきて、床で食べた。こういうとき、タカハシは、この間取りで合ってるじゃないか、と思った。
宇田川ビルの四〇一号室はもともと丸毛と二人で住み始めた部屋だったから、間取りは2DKだった。洋室と和室は繋がっておらず、居間から入るようになっていた。タカハシはカントがこの部屋に来ると決まってから、詳細な間取り図を引いていた。七畳ある居間には、ソファやらコーヒーテーブルやら、様々なものが詰まっていたが、それをなんとかレイアウトして、カント用のスペースを作る予定だった。将来的な計画では、カントが寝るための空間をパーテーションで区切ることになっていた。が、カントは悠太の部屋に住むことになった。
男二人で同じ六畳間に生活していたら殺し合いに発展しかねない、とは転がり込んできたカントの言だ。俺もヒバリと住んでた頃は四六時中お互いを殺すことばかり考えてたからねえ、密室トリックならいつでも思いつくよ、と危惧したのだが、悠太の方が大丈夫だと言い張った。カントの荷物はスーツケース一つと竹刀一本だったから、無理のないことではなかった。タカハシは自分が持っていたもう一組の布団をカントに貸した。
本人の言い出したことだからと、悠太の自主性を尊重してみたのだが、山田と一年ぐらいコツコツ二人でお金を貯めて実現させたオーストラリア一ヶ月の旅から帰ってみると、悠太はいなくなっていた。部屋には縄張りを広げたカントが大の字になっていて、お土産のカンガルー・ジャーキーを渡すと、悠太、実家に帰ったよ、と平然と言ってのけた。前の同居人の丸毛もかなり唐突に出て行ったから、同居人がいなくなったという事件そのものには驚かなかった。それよりも、出て行くにあたってはそれなりに話し合いの場が持たれるのが普通だと思っていたから、同居人が突然いなくなることが二度連続だったことに面喰らった。何かが悪いのかもしれなかったが、その正体は漠として見えないため、とりあえず目の前の問題を片付けてしまおうと、三日後に迫っていた家賃の督促メールを悠太に送った。返信はすぐにあった。
「まあ、悠太にも色々言い分はあるからさ」
悠太から届いたメールの返信を眺めて呆然としているタカハシに向けて、カントが注釈を入れた。タカハシはメールに書いてある文面をよく理解できなかった。
やっぱりな。そうきたか。
俺を見るとき、目が$マークになってたよ。俺をこの部屋に誘ったのも、家賃を節約するためぐらいにしか思ってなかったんだろ?
おまえはそうやって、他人を自分のために都合よく利用することしか考えてないんだよ。
家事をやってやったとか言うなよ。俺は一回も頼んでないぜ。
いつか、俺が鍋料理作ったとき、タッパに移してレンジで温めろとか言ったよな。俺はメンドクさかったから、そのまま鍋に入れっぱなしにして、ガスで何度も温めた。そのせいで、鍋に焦げがついた。あのとき、なんでおまえは黙ったまま、アルミたわしで焦げを落とした? シャリシャリいう音が聞こえてたんだよ。なんで一言、「焦げがつくから」って言わない? 俺だって馬鹿じゃないんだよ。
おまえは、他人を馬鹿にしてるんだよ。もう耐えられない。
「まあ、そういう風に思うというのはわからないでもないんだけど……」と、タカハシはメールの文字サイズを最大にして、なんとかその意味を汲み取ろうとした。「この、最終的に俺が悪いという結論になるのは、なんでなの? 他人と住んでると研究が捗らなくて、ストレスが溜まるのかな?」
「いや、タカハシくん、それは違うよ。逆に、ハハーっと思ってるからこそ、だよ」
なにがどうなって、「逆に、ハハーっと」なのか。なにが他人に嫌味ったらしい土下座をさせうるのか、タカハシにはまったく心当たりがなかった。
「俺もだてに駄目ガンジーと呼ばれてないからさ。悠太の気持ちは十分わかるよ」
丸毛もこの部屋を出て行くときに、タカハシの無神経さを指弾する檄文を残していった。生活にまつわる七面倒くさい一切合財をほとんど引き受けながら、タカハシは非難され、しかもそれが三票。なんなんだこの共感は、という厭世的な気分に捉われながらも、タカハシは一応自分にも非があったのかもしれないと、殊勝に反省した。
「鍋磨くのとかはともかく、ゴミ捨てや掃除、そういうのは悠太さんにとってはメリットでしかないと思うんだけど、余計なお世話だったのかな?」
「いや、それはそうだよ。もちろん、タカハシくんが捨ててくれなかったら、ここは逆にゴミ屋敷だったんじゃないの? でも、あえて言うけど、そこが悠太のかわいいところでさ。ゴミ捨てしてもらって悪いな、と思った瞬間に、その罪悪感を捨てたくなるんだよ。太宰の言葉を借りれば、そんな恥知らずの事はもう言うな! ってところだろうね」
恥知らずと言われてみると、さすがに衝撃的で、タカハシは自己弁護のための推論をいくつか積み上げた。
まず思い浮かんだのは、金銭的な理由だった。そして、タカハシは、なにかを思いつくと、それがそのまま真なりとなるように論を進める資だった。
悠太は大学院進学の志を捨てないために、タカハシと同じぐらいの頻度でしか働いていなかった。企業にとってみたら雇用調整の安全弁でしかない不安定な仕事に就き、月わずか十一万円の収入である。家賃が二人折半で四万円、水道光熱費が五千円、携帯電話代がおろかにも一万円、国民年金が一万三千五百円、保険やらなんやらで六千円、自炊をしなければ安く見積もっても食費が三万円……お小遣いが残るのは五千五百円。
短期バイトで出会ったあと、一番最初に遊びに行ったのが悠太の卒業した一橋大学国立キャンパスの学食だった。二浪して入った社会学部を二留して卒業した悠太は、大学院試験に二回落ちている。東大の社会学部へ志望を変えたそうだが、それも一回落ちている。タカハシは大学院のシステムをよく知らなかったが、東大には社会人学生もいたから、年齢による足切りのようなものはないのだろう。ただ、現時点で悠太は大学卒業後キャリアを積むことなく二十八歳になろうとしている。早い人なら博士課程後期の終わりも見えてくる頃だ。実際、研究の内容というのもまとまった文章の形で見たことはなく、以前に論文誌に投稿したという話も、もしかしたら嘘なのかもしれなかった。悠太はシャワーを浴びている時に奇声を発することがたまにあった。
「なんだかんだいって、悠太さんも苦しかったのかな。生きて行くのが」
「いやあ、俺も彼の気持ちはわかるからさ、タカハシくんもあんまり悪く言わないでやってくれよ」
「悪くは言わないけど、最後の月、家賃払ってないでしょ。カントくんが来てから、三分の一になったのに」
「まあ、悠太もある意味駄々っ子だから。しかし、タカハシくん、敢えてそこは許してやってよ。タカハシくんにも、少しは原因があるし」
「やっぱり、何か原因があるのかな?」
「もちろん、逆の意味でね。悠太はこれだからさ」
カントはそういうと、揉み手をした。悠太が実際に揉み手をしたことなど一度もなかったが、カントの見立てではそうなのだという。自虐的なネタで笑いを取りに行くのは、粛々然と世界に対して頭を垂れて生きていることを意味するのではなく、己に許された「ダメ」という最後の刃を振りかざしているということらしかった。
「逆にね、ああいう奴の方がプライド高いからさ。タカハシくんもわりとプライド高い方だけど、逆に悠太の方がプライド高いからね」
自尊心に関するカントの持論を聞き、タカハシには腑に落ちるものがあった。悠太の実家は文京区の住宅街にある。詳細は知らないが、中小企業のオーナーである実家は決して貧しくはなく、ともすればボンボンの部類に属した。その悠太にとって、北千住の工場街のようなところで暮らすことは、零落を自ら引き受けることを意味する。恵まれている人間が社会学のフィールドワークを行うときの当事者性のなさ、つまり物見遊山的な感覚は東大の社会学部の教授に見抜かれているのかもしれなかった。創作が生活の破綻を要求するという私小説作家的な世界の住人であるカントにしてみれば、自分の出生に足を引っ張られる悠太に対する同情のようなものがあったのかもしれなかった。
「悠太さんも色々ジレンマあったのかもね」
「いや、そんなに大袈裟なものじゃないよ」
「違うの?」
「単に駄目人間だからでしょ。タカハシくんも、下手に帝大出てるから、そこらへんの機微はわかんないでしょ。こういう、ガッチャガチャな人間関係」
「いや、悠太さんも一橋出てるんだから大して変わらないでしょ」
「そこは逆にさ、一橋という学歴に拘泥しているだけと思うのが優しさでしょ」
カントは腕組みをしながら、聖職者のような顔をした。そうだと言われれば自分が悪いような気もした。カントが着ているスーツはくたびれて、次の秋を迎える頃には虫食いだらけになっていそうだった。悠太の分の家賃は、家主であるタカハシが払うことになった。
ともあれ、三人暮らしをするはずが、得体の知れない喧嘩別れになって、ガッチャガチャになった気持ち悪い人間関係が多少はシンプルになり、過ごしやすいといえばそうなのだが、掃除当番のタカハシは少しだけうんざりした。カントが寝る部屋は、悠太がいた頃よりもさらに汚れていった。畳には煙草の焦げ跡がつき、布団には信じがたい量のシミがあった。悠太がいた頃は布団にシーツを敷いていたのだが、カントは布団の上に直接寝た。布団も干さなかったし、無精者の習いとして、眠るまで酒を飲んでは、起き抜けに枕元のビール瓶を蹴っ飛ばして畳を汚した。風呂もあまり入らず、パジャマも持っていなかったから、布団の上に裸で寝て、念入りにベトつかせた。そうした数々の無頼を続けた結果、カントの部屋は汚物の聖域となった。
タカハシは布団のクリーニングを打診したが、カントは五千円の出費を惜しみ、逆に俺に合ってるよ、と言い張った。元はタカハシの布団だから、それなら自分でやるしかないと悲壮な決意をしたが、洗濯機には入りきらなかった。となると、浴槽で洗う以外に方法はない。一人では何だからと、遊びに来た山田を誘って、洗剤や漂白剤を混ぜたぬるま湯に布団を浸し、ジャブジャブと揉み洗いをした。五回も揉むと、風呂のお湯は真っ茶色になった。洗剤は泡立たず、界面活性力がすでになくなったようだった。腕まくりをして一緒に押していた山田は、おええ、と呟くと、シャワーで腕を洗い出した。
「ちょっと、こんな汚い人と一緒に住んでんの?」
山田はもう布団揉みを手伝うことなく風呂場に立ち尽くしていた。人が二人もいると、浴室はいかにも狭かった。山田の顔には汗に濡れた髪が束になって貼りつき、いかにも生活者といった風貌になっていた。
「風呂は三日に一遍ぐらい入るけどさ、シーツ敷かないからね。こうなるよ」
タカハシは風呂の栓を抜いた。茶色い水が浴室の床に溢れた。山田は再び、おええ、と言いながら、タカハシの肩を掴んでよじ登った。
「もうやだ! なにあの汚物! 人でさえない!」
山田は叫んだ。声の響きに応じて、天井に溜まっていた水滴が一滴落ちた。落ちた雫は汚水の濁流に飲み込まれた。タカハシは波紋がかき消される様をじっと見つめた。
「他の人じゃ駄目なの? もうちょっと清潔な人、いるでしょ?」
「そうはいっても、この部屋に住むような知り合いってなかなかいないからなあ」
「私、こんなに汚くないよ!」
肩にしがみついたまま泣きべそをかく山田の言葉が震えていて、ああそうか、と思い出した。
「一緒に住むのは、もうちょっと先だよ」
はっと顔を上げ、山田は考える表情になった。普段はくっきりと美しい二重の瞼が、三重になっていた。タカハシの真意を汲みかねているようだった。
タカハシは悠太と住み始めた頃、山田にそれとなく詰問されたことがあった。いじけやすい性格だったから、率直に尋ねることはしないのだが、派遣の仕事でも地味に職責が上がり、今では単なるエクセルの入力だけではなく、アルバイトのシフト管理用のシートさえ作るようになった、月給は額面で二十五万を超える——などなど、自分と一緒に住むメリットを遠まわしに提案するのだが、タカハシは山田と一緒に住むことが丸毛や悠太との共生とはまったく違った意味を持つことを確信していた。
タカハシは好奇心と整理欲ばかりだったから、性欲はそれほど強くなく、女にモテたいとも思っていなかった。結婚するなら山田以外とは考えていなかった。しかし、自分の好きなこと——調査と整理——を続けるためには、計算され尽くした生活設計が必要であり、それによると、タカハシが週二回の労働で二十五万円を稼げるようになった頃か、現在二十四歳の山田が二十九歳になる頃が同棲のタイミングだった。
なぜそのタイミングが適切なのかという根拠を問われても、タカハシはきちんとした根拠を述べることができた。いったん説明を聞き終えると、山田は小憎らしいというようにじたばたと頭をかいてから、幾つか反論した。それに対してタカハシが補足説明をする。その繰り返しだった。
山田もまた、カントや悠太が尋ねたように、タカハシの収入が上がる可能性について尋ねた。しかし、タカハシは現在の生活スタイルを変えるつもりは毛頭なく、目下のところ、技術翻訳やライターのような高い技術を要する仕事をすることも稀にあったが、徹夜仕事や長い拘束を要さない適切なボリュームのものでなくてはならず、営業のための労力もかけるつもりはなかった。家にいるだけで適切なボリュームのフリー案件が迷い込んでくるためには、それなりの習熟が必要だが、焦って習熟することもしなかった。結果的に時間が必要であり、時が熟すれば、どんな職種であれ、それなりの収入を得られるようになるはずだった。
また、山田二十九歳時点を同棲のタイミングとしたのは、それが山田にとってのクリティカル・ポイントになるからだった。山田はそれなりに顔も整い、控えめに美人と分類することもできたから、常にタカハシ以外の男と一緒になるという選択肢も残されていた。しかし、仮に二十九歳以降になってから急に別れることになった場合、山田の女としての人生でこうむる損失は計り知れない。もちろん、結婚が人生のすべてではないが、二十九歳になった時点で同棲を始めてしまい、タカハシの山田に対する態度を固定してしまった方が、山田にとってわかりやすいはずだった。
タカハシの思い描く青写真では、収入面から見た同棲開始時点も、年齢面から見た同棲開始時点も、ほぼ同じ時期になるはずだった。だから、もし山田が本当に自分と添い遂げたいと思っているのなら、単に信じて待っていればいいだけだった。説明をすれば、山田は必ず、わかった、と頷いた。泣き腫らした目で、下唇を突き出して、子供のような同意の仕方だった。山田はおそらく、最後の「信じて待つ」という言葉だけ理解している。タカハシは想像した。そして、同棲とはいよいよとんでもないことだ、と警戒し、より入念に人生の計画を練るのだった。
「もう疲れたから、やんなくていい?」
浴槽のお湯を三回入れ替え、これからすすぎをするという段になって、山田が呟いた。心底疲れたという顔をしていた。
「いいよ。部屋で休んでなよ」
山田は軽く頷くと、亡霊のように俯いたまま、部屋へと戻った。タカハシはお湯を溜め、中に入れた布団を踏みしだいた。三度ほどすすぐと、泡は出なくなった。シミは消えなかったが、ねっとりとした匂いはなくなった。
取り出した布団を絞り切ることは難しかったから、そのまま干してしまうことにした。幸い、まだ陽は高かったし、数日は晴れが続く予報だった。びしょ濡れの布団を圧縮袋に包んで持ち上げると、凄まじい重さだった。難儀しながら居間と洋室を駆けぬけ、ベランダまで出ると、それを欄干にかけた。水がぼたぼたと下に落ちた。水に打たれたコンクリートは、黒く染まった。まるで、局地的に雨を降らせているようだった。
「見ろよ、すごい水だ」
タカハシは山田に話しかけた。山田は布団に包まったまま、一瞬だけ顔を覗かせた。大きな目が真っ赤に腫れていた。布団の中でふるふるとべそをかいていたようだが、タカハシはこれもよくなるための痛みと捨て置いた。




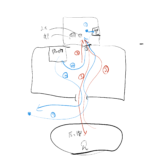
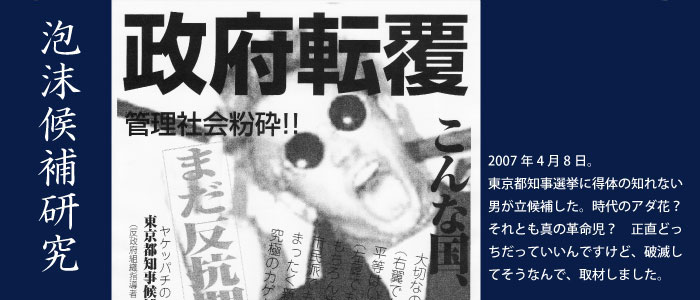




















"フェイタル・コネクション(1)"へのコメント 0件