Chapter Three……方舟
三‐三 聖者の帰還
宗光は種村の遺体をいつまでも見つめていた。すぐに水葬しなかったのは、必ずしも疲れのせいではない。スコールで水を飲み、少しは体力を回復していたから、一番の理由はもう少し傍にいたいという思いである。今まで一同を鼓舞し続けた種村に対して反論や愚痴を言いはすれど、誰もが彼に縋っていたのだ。とりわけ、一世一代の大事業である南洋周遊の根幹部分を任せようと思っていた宗光にとって、その悲しみは一機だった。
宗光は船底に文字を彫った――「偉大なる紳士 種村興一船長 太平洋に眠る 大正十一年七月二十八日」。自分の刻んだ文字が消えないように、何度も小刀でなぞりながら、宗光は沈没から経過した二十日という日々を思った。
夕暮れになってようやく種村を水葬に付した。遺体は堅くなっていたが、四肢は棒切れのように萎え、思ったよりもずっと軽い。しばらく沈まずにいた種村の遺体は、波間を漂い、頭から徐々に沈んでいった。宗光は、自分も死ぬ時、あんな風に頭から沈んで行くのかと思った。ここ数日、自分の死に様を想像する癖がついていた。
黒い塊が幾つか、艇内に飛び込んできた。飛び魚だった。魚が跳ねる様をぼんやりと眺めていた宗光は、慌ててそれらを掴まえ、腹から齧りついた。腸の味がじわりと口内に広がり、生き物の血の味が鼻から抜ける。それは彼の中に微かな炎を灯した。目玉を吸い取る。鰭を毟り、骨ごと齧る。口の中を何箇所か切ったが、そんな事は関係無かった。気付けば、あっという間に一匹を平らげていた。
ふと我に帰り、他の二人に相談もせず一匹を食べてしまった事に焦ったが、よく数えたらちょうど三匹で、ほっと胸を撫で下ろした。
「おい、起きい。食い物じゃ」
船べりにだらしなく寄りかかっていたみつと水夫は、振り向いて飛び魚を認めると、宗光と同じようにむしゃぶりついた。彼らにもまだ、生きようという本能が残っていた。
幸運はそれだけで終わらなかった。水夫がカツオ鳥を捕まえたのである。カモメより一回り大きく、人を警戒する事を知らないその鳥は、船べりに寄りかかっていた水夫の目の前に降り立った。水夫は何の気なしにひょいと手を伸ばし、その足を掴んだ。カツオ鳥を掴んだ瞬間、水夫の目に力が宿り、生き生きと鳥を押さえ込んだ。羽音で事態に気付いた宗光も、すぐに傍に寄って首を捻った。
久々の肉と血で幸福を味わった宗光は、腹休めをしながら、カツオ鳥が近いという事は陸地が近いという事だ、と思い立った。海流任せに三〇〇海里を進むなどという事はありえない。だが、これらの幸運は宿命じみている。無茶だとわかっていても、宗光はそれを二人に伝えずにはいられなかった。
「種村氏ィが命と引き換えに、儂らを助けようとしてくれとるんじゃ」と、宗光は言った。二人はその迷信を嘲るでもなく、穏やかな微笑を浮かべて船べりに寄りかかっていた。
それからも暫時、海は凪いだ。恐ろしい凪である。宗光は「悪魔の凪」という言葉を思い出しさえした。
太平洋という海は、いつも波が立っている。初夏が一番穏やかであるが、基本的にはよく荒れる。その点、瀬戸内とは比べ物にならない。それでも、ごく希に恐ろしく静かな凪があるという。どこまでも続く水の砂漠で、空には雲一つ無く、風も吹かない。完全に時間が止まってしまうのである。その水鏡を見ていると、思わず身を投げてしまう船乗りがいるという。それを異国の船乗りは「悪魔の凪」と呼んだ。
「悪魔の凪か」
そう呟きながら、宗光は船側に上体をもたげ、静かな海を見た。
飢えが死神のように付きまとっていた。それが苦痛という時点はとうに通り越した。猛烈な乾きは、口中に苦味として残る。舌は堅くなり、ざらついた石のように口蓋をぶつかる。指で口内をほじくれば、白い塊が取れた。喉が張り付き、呼吸も滞った。柳井小町と謳われたみつの美貌さえ、今は見る影も無い。眼窩は窪み、膨よかな頬は削げた。顔色の悪さと日焼けが相俟って、奇妙な泥土色の肌をしていた。唇はもはや青黒くなり、干からびた海鼠にも似ていた。飢えと乾きは彼等を同じような顔に仕立てた。
種村が灯してくれた希望の炎も、もはや潰えた。死ぬにはいい頃合である。ほとんど同じ栄養状態で過ごした種村が死んでから、それほど多くの食料を口にした訳ではない。死ぬのもそう遠くないだろう。じっと、恐ろしく凪いだ海を見つめた。瀬戸内でも見た事の無い、残酷なほどの美しさだった。
それでも諦められなかった。空しく死んでいった仲間達を思うと、自ら海に飛び込む事などできない。
自死の誘惑と、生きようという使命感と。その葛藤がどれぐらい続いただろうか。
その水面にとぷりと浮かんだ顔があった。つぶらな瞳でじっと宗光を見ている。ほんとうは彼等の窮状をわかっているのに、もったいぶって助けようとしない、狡い純真をその表情に賛えている。絶望に慣れた人間の交渉下手から、宗光はその顔をじっと見つめていた。
それが海豚だという事に気付いたのは、疳高く耳の奥に響く鳴き声を聞いてからである。宗光は種村の残したトランクに躙り寄り、拳銃を取り出した。それから、船べりに身を乗り出し、海豚に照準を合わせる。
海豚は徐々に近づいて来た。ゆっくりと、聖者のように。引き金を引いた。乾いた銃声と海豚の哭き声が、耳の奥で弾けた。
肩を叩かれ、振り向くとみつがのしかかっていた。海鼠のような唇が(どないしはった)と動く。宗光はもう一度海を見た。海面に煙のような朱がたなびいていた。
宗光は艇内の櫓を拾い上げ、海豚の胴を叩き寄せた。そうしている間も水夫を呼び起こし、縄を胴に回させる。回った縄の一端を櫓受けの輪索に結び、もう一端を引っ張った。運良く縄は海豚の両ひれに引っかかっている。船べりに足をかけ、全身全霊で縄を引く。
子供の海豚だったのが幸いしたか、なんとか持ち上げることができた。どん、と大きな音を立てて海豚が転がり込むと、船は揺れた。まるで喜びに揺れているようであった。
すぐさま長谷浦の残した包丁で海豚の頭の付け根を三箇所刺し、その血を吸った。栄養不足の身体を血のありがたみが駆け巡った。身体が火照り、細胞の一つ一つが沸き立つような感じがした。魂ごとずれ出てしまいそうな昂揚。生きられる気がした。四方には島影一つ見えない。が、生きなくてはならないような気がした。
種村が死んでから誰も漕ごうとしなかった櫓を手に、ゆっくりと漕ぎ出す。避難艇は凪いだ海を滑るように進む。
疲れたら、海豚の解体に励んだ。皮を剥ぎ、脂肪の層を取り出す。脂肪は細かく切り分け、海水に浸して食べた。喉は乾いたが、それ以上に油の旨味が堪えられない。味はカツオ鳥の比ではなかった。唾が溢れるように出た。海豚の引き上げで体力を使い果たし、ぐったりとしていた水夫も、脂肪を口に押し込めば、急に目を見開いて貪り食った。それはみつも同様である。脂肪でぬらぬらと光る唇は、少しだけ潤いを取り戻し、往時のように艶めいた。肉の部分は海水に憑けてから天日に干し、保存食とした。三人分とすれば、十日は保つ量である。
僥倖は続いた。海豚を撃った翌日に雨が降り、なんとか清水を補給することができた。これであと十日、絶対に生きる事ができる。宗光は当ても無い「絶対」という言葉に深い安堵を覚えた。



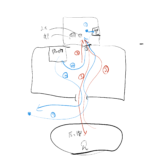
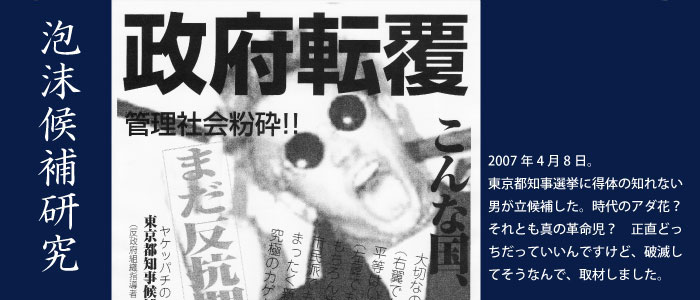



















"方舟謝肉祭(13)"へのコメント 0件