『棄民世代 政府に見捨てられた氷河期世代が日本を滅ぼす』の著者である藤田孝典はソーシャルワーカーとして、大学教員やNPO法人の理事として、貧困問題に関する活動を行っている。Colabo問題で仁藤夢乃とやりあっているのを目にした方も多いかもしれないが、本来は貧困問題の専門家である。
本書で藤田は「ロスジェネ」や「氷河期世代」という呼び方ではなく、あえて自身も属するその世代を「棄民世代」と呼んでいる。
あえて言おう。どうしようもない政府が上から目線で「人生再設計第一世代」というなら、我々は「棄民世代」である、と。あなたたちがずっと大事にしてこなかったし、一貫して政府や社会から見捨てられて世代である、と。
藤田孝典『棄民世代 政府に見捨てられた氷河期世代が日本を滅ぼす』SBクリエイティブ、2020年、P.7
つまり、ロスジェネという世代は政治的な産物だという意見である。本書ではロスジェネの抱える苦境と、その将来的な問題、そして政治の責任について論じている。以下に論点を箇条書きで記す。
- いのちの電話にかけてくる世代で2008年はロスジェネが多かったが、2018年でも相変わらずロスジェネが多い。死にたい人たちのボリュームゾーンがそのまま歳を重ねている。
- 非正規労働者が多いのは小泉構造改革以降に常態化したが、ロスジェネ世代の平均年収は相対的に他の年代と比べて少ない。新卒で正社員になれず、非正規労働から転職する「後から正社員」パターンが多いのも特徴。
- ロスジェネ世代のニート・ひきこもりは多く、しかも増え続けている。
- ロスジェネ世代が働けなくなる頃、生活保護受給者は60万人を突破すると予想されている。年金も破綻する。
- 介護の問題。いくつかの側面が存在する。
- 2025年問題……ロスジェネ世代の親(団塊世代)が全員後期高齢者(75歳以上)になる。つまり、日本史上最大の要介護集団が日本に誕生する。
- 2050年問題……ロスジェネ世代(⊃団塊ジュニア世代)が後期高齢者になる。人口現象社会において、最後のボリュームゾーンが要介護集団になり、しかも彼ら/彼女らは貧乏である。
- 8050問題……80歳の親が50歳の引きこもりの面倒を見る。同時に引きこもりが親を介護することにもなる。共倒れが危惧される。
- 少子化問題。これはすでに確定してしまったが、ロスジェネは第二次ベビーブーム世代を含んでいるが、もし彼ら/彼女らは第三次ベビーブームを起こせなかった。金がないので結婚できなかったのが大きな原因。
- 労働者の非正規化を推し進めた先駆者は中曽根康弘で、最大の戦犯は小泉・竹中。特に藤田は政商・竹中平蔵をパブリック・エネミーとして強く批判している。
- 無敵の人。家族も持たず、まともな職もないので、失う物がなにもない人たちが犯罪に手をそめる。黒子のバスケ脅迫事件の犯人がこの言葉を広めたが、秋葉原連続殺傷事件、スクールバス襲撃事件、京アニ放火事件などもロスジェネ世代である。
本書で興味深かったのは、国鉄民営化を推し進めた中曽根が目指していたのが「民営化による効率化」ではなく、「労働組合の弱体化」だったということである。新保守主義の中曽根はこれを公言しており、社会民主主義の票田であった労働組合を叩くことが目的だった。安倍晋三と自民党が統一教会と深く関わったきっかけは「反共」だった、というのはすでに明らかになりつつあるが、左翼的な価値観を叩くためという単純な理由で自民党が戦い続けているという史観は間違っていないのかもしれない。政治家がそれぐらい単純な生き物だと考えると、ディープステートを信じる議員がいてもおかしくはない。ちなみに、安倍暗殺犯もまたロスジェネ世代である。
本書ではロスジェネ内においてもさらに男女格差があることが触れられている。これは特に男性の書き手がロスジェネ世代を論じるにあたって注意すべき点である。たとえば、ロスジェネの「弱者男性」が自身の苦境についてくだくだしく述べても、別の世代の女性の方が個別具体的には苦労している可能性が高いからである。もちろん、自分より苦労している人がいたら不平不満をいってはいけないかというとそんなことはないのだが、この観点を見落とすと反論されやすい、つまり穴の多い文章に見える可能性が高い。
また、これは「正社員/非正規労働者」や「大卒/高卒/中卒」といった人々の間でも世代をまたぐと一気に共感されづらくなる。すでに取り上げた『ロスジェネの逆襲』では、バブル期入社組親会社の半沢VS就職氷河期子会社の森山という対立だったので比較属性がわかりやすいが、バブル世代でAmazonの配達員をする独身女性VSロスジェネ世代のIT企業正社員既婚男性だと後者の方が恵まれているように見える。どの世代にもいろんな人がいるのが世代論の難しいところだが、何かを書く際には注意した方がいいだろう。たとえば、半沢VS森山の比較で言えば、親会社のモデル三菱UFJ銀行の平均年収よりも子会社の三菱UFJモルガン・スタンレー証券の方が平均年収が高かったりする。これは前者に一般職・事務職が多い一方、後者には投資銀行業務があり、その社員の年収がとても高いからだ。こうした個別のちょっとした違いによって世代論は簡単に無効化されてしまう。
2010年代後半から「いよいよロスジェネやばいのでは?」と政府も思い始め、そもそも就職氷河期世代という名前がよくないということで「人生再設計第一世代」という正式名称が決められた。奈良時代に弓削道鏡と対立した和気清麻呂が姉の広虫とともにそれぞれ「穢麻呂」「狭虫」と改名させれて流刑された故事を思い出させる。言霊信仰は日本に深く根付いているのだ。もちろん、名前を変えても実態は変わらないので、「教育で管理職としての能力を身につけて地方に移住してもらう」という無茶苦茶なプランしか出てこない。藤田はこの政府の「支援」を強く批判している。入り口をちょいちょいと整えたらうまくいくものでもないのだ。
本書で藤田はロスジェネ世代の救済策についていくつか提言しているのだが、それは実際に本書を読んで確かめてみてほしい。いずれにせよ、創作をするにあたってはこの「見捨てられた世代」という設定は興味深い。他の世代が急に目覚めて「ロスジェネはかわいそうだ、助けてあげよう」となることは絶対にないので、自助努力(自己責任!)によって自らを救済しなければならない。では、どうやって連帯するのだろう? 非正規労働者による組合というのはわりと現実的な集団として存在しているが、それ以外の属性で連帯するのは難しそうだ。連帯可能性については真剣に検討する余地がありそうだ。
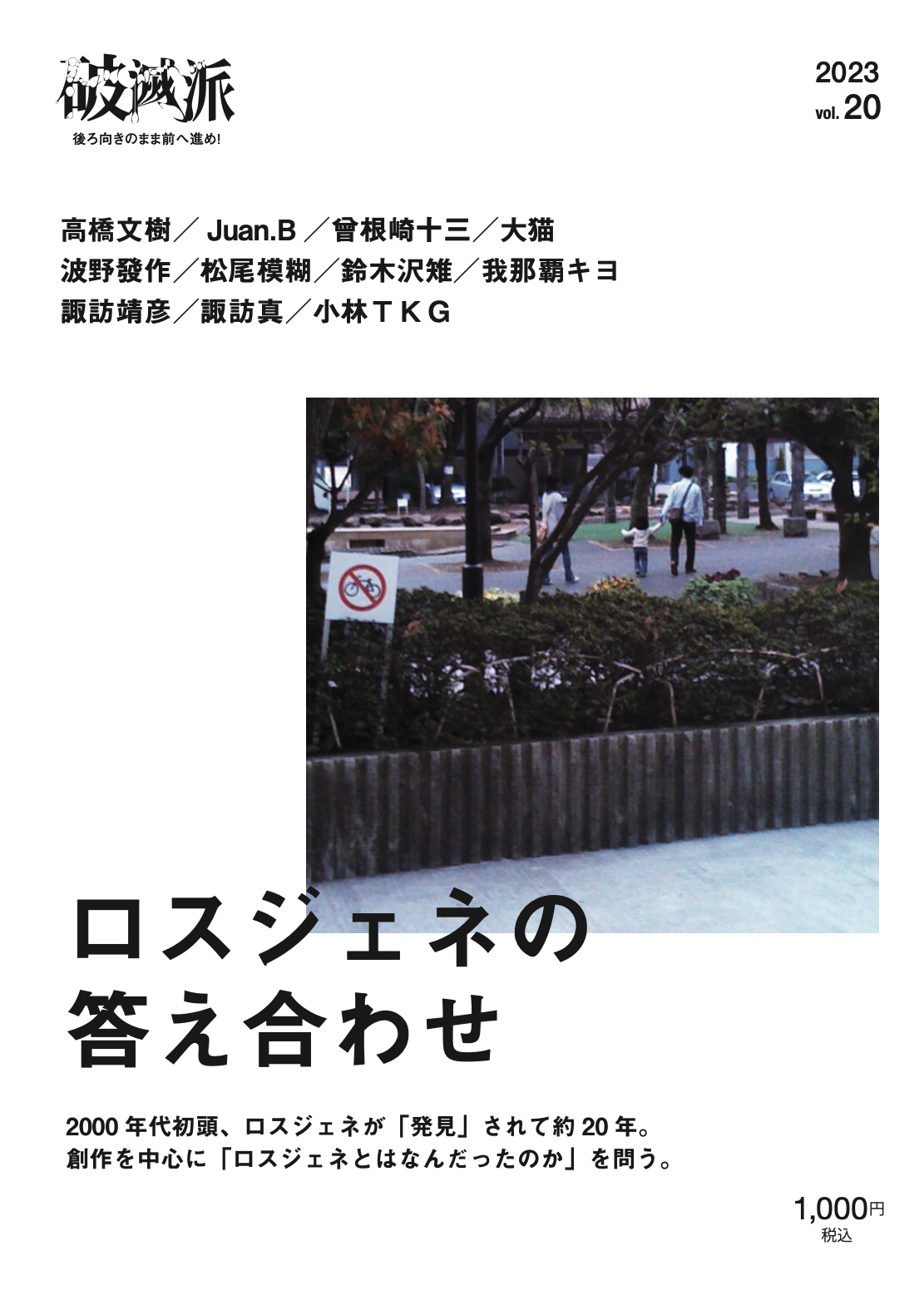





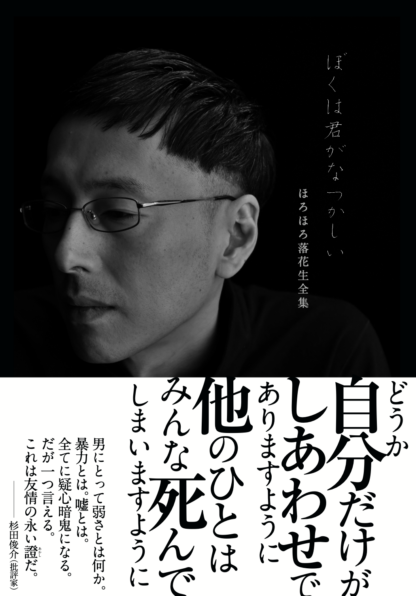
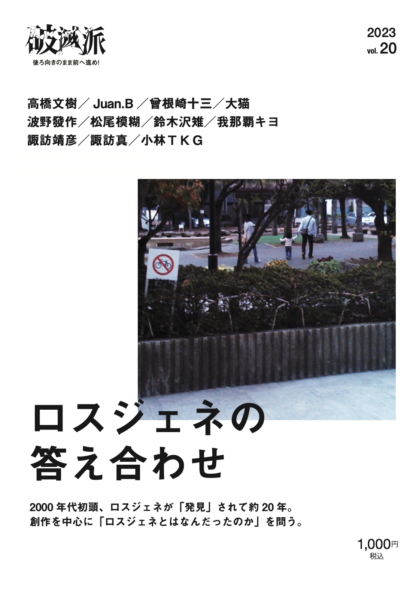
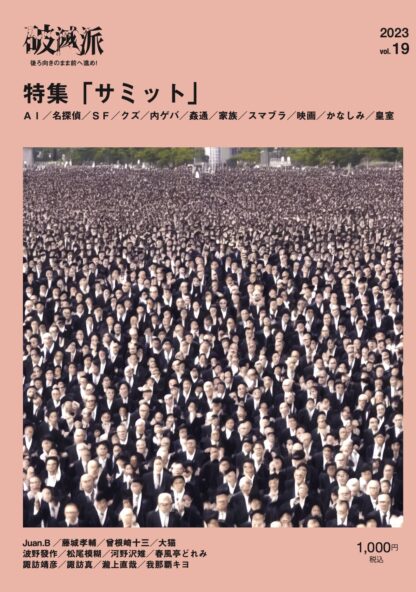
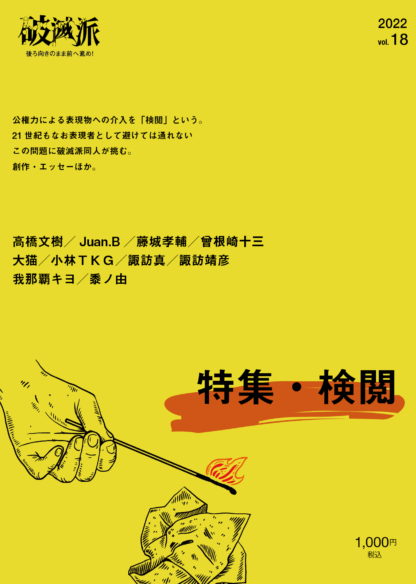
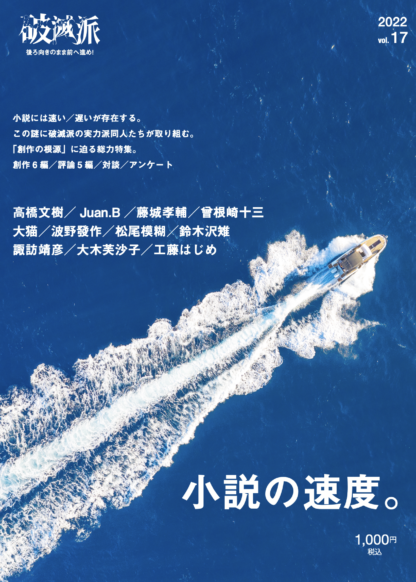













"ロスジェネ議論用参考文献紹介その3『棄民世代』"へのコメント 0件