ペットを飼う。信じられないかもしれませんが、ただそれだけのことが、私達夫婦にとっては決心しがたいことでした。ペットがいたらさぞかし幸せだろうという話が、夫婦の間で何度も繰り返されるだけなのです。不妊完治の見込みが薄く、日々の生活で汲々となっている私達が迎えられる家族といえば、ペットぐらいしかいないというのに、です。
「猫って楽そうだけどなあ、いきなり家出するっていうからなあ」
「犬は懐くんでしょ? 死ぬときに辛いよね」
「魚は飼い主のことわかんないだろうなあ」
周囲のペットを飼っている人に聞いて回っては、それはいい、飼おうなどと家に帰り、知りもしない欠点をあげつらって先延ばしにする。なんでもいいからペットが欲しいと言っていたくせに、いざ決めるとなると、尻込みしてしまう。決めるというただそれだけのことができず、私達夫婦は新しい家族への思慕を募らせていきました。
ドッグシェルターや保健所にだって、何度も行ったのです。檻の中でせわしく吠える犬達を見て、心の底から同情を覚え、ああ、この子を助けてあげたい、私達の家族として、叶うことのなかった愛を与えてあげたい。そう願うのです。願いながら、決められないのでした。私達はもじもじしながら、シェルターのボランティアや保健所の係員に向かって、「また来ますので」と頭を垂れました。みんな優しい方達でしたから、「決心がついたらまた来てください」と、笑顔を向けてくれました。帰路、行き場無く、電車の吊革を弄んで、「次は絶対決めようね」などと言い合いました。絶対。決心。決める。みな、私達には手の届かない言葉でした。私達の生活では、決心が良い種となったことは一度もなかったのです。
その癖、情報収集だけは周到でした。私達は、よく本を読みました。『ねこのきもち』、『いぬのきもち』などといった雑誌を手にとっては、ああでもない、こうでもないと言い合いました。それも、図書館の雑誌コーナーで。私達のつましい収入では、おいそれと雑誌を買うことなどできません。そんな私達が一二六〇円も出して買ったのですから、「THE PIG Photo Book」は単なる一書籍に止まりませんでした。
ええ、とても素敵な本でした。小さな豚が、つやつやと愛らしい鼻を向けて、こちらを窺うようにしているのです。薄い桃色の鼻は余りにも愛らしく、卑猥でさえありました。白ミニブタの肌は透き通り、真新しい絹を纏っているよう。黒ミニブタの肌はしっとりと深みを帯び、水に濡れた炭のように艶めいていました。丸い胴に宝石のような肌を纏ったミニブタが転げまわっている姿は、寄る辺ない夫婦にとって、どれほどの助けとなったでしょうか。
「この鼻、ヤバいなあ。こんなのでくんくんされたら、たまんないだろ」
「そうね。もう何もいらないわ」
「だよなあ。飼うか」
「アリだよね。どうしよっか」
「だよなあ。どうすっかなあ」
私達は二人で覗き見ていた本を閉じると、お互いの先を急ぐようにしてレジへと走りました。書店員さんがレジを打ち、金額を請求する間も、私達は、そんな会話を続けました。本屋さんの困った表情を見てはじめて、私達は痩せた財布からお金を出しました。
その本が手に入ってから、私達は毎日ミニブタのことを考え続けました。あれほど決めることの苦手だった私達が、もう飼うつもりでいたのです。「ペットを飼う」から「ミニブタを飼う」へ。そっと入り込んできた決心でした。
ところが、飼うと決めても、私達にはどこでミニブタを買ったらいいのか、皆目わからないのです。私一人でバスに乗り、国道沿いのペットショップに行っても、「ないよ」と言われればそれっきり。もじもじしておしまいです。忙しい夫がたまについてきても、夫は「ほんとうに? ないんですか?」などと喧嘩腰になってしまうのです。「THE PIG Photo Book」を何度も読み返して、どこかにミニブタの入手先がないかと探したものですが、ついに編集部に電話をする勇気は出ませんでした。
そんな風にしてミニブタへの思慕を悶々と募らせていた私達が、美豚ちゃんと――ええ、これは私達が飼ったミニブタの名前なのですが――出会ったのは、夏の宵、私達の住む堤下での夏祭りでした。私達には趣味らしい趣味がありませんでしたから、バザーやら祭りやら、堤下のようにありきたりな住宅街の催し事でも勇んで出かけたのです。その夏祭りも私達夫婦は長らく楽しみにしていて、中学生の頃から大事にとっておいた浴衣などを引っ張り出し、帯で締め付けた胸を躍らせながら、夫と共に向かったのでした。
夏祭りの雰囲気というものは、切ないような、楽しいような、艶っぽいものです。夫はお面を斜に乗せた頭をきょろきょろさせながら、リンゴ飴などを齧りました。私は童心に返った夫の顔を見つめながら、そこに日々のささやかな幸福を見出していたのです。
夏祭りの行われている公園を一回りした頃でしょうか。折りよく、目の前のブランコを占領していた子供たちが駆けて行きました。夫婦にもなってブランコというのも気が咎めますが、腰をかけ、懐かしいねフフフ、と笑みなど漏らしながら、少しずつ漕ぎ足に力を込めていくと、夫は無邪気にも立ち漕ぎを始めました。所詮子供の乗り物です。ほんの五漕ぎもすると、夫の身体が水平になるまで高々と上がりました。
「やめなよ、危ないじゃん」
私は窘めるのですが、それが夫の童心に火をつけるらしく、漕ぎ足に力が入ってしまいます。ブランコの鎖がたわみ、降りるときにがしゃんと鳴りました。私はますます怖くなり、「やめなよお」と呟きました。夫はやめるどころか漕ぐ足に力を入れ、そしてついには夜空に放り出されたのでした。ああ、また堕胎る。私は夫の死と、それに続く暗い日々を想像しました。
「なんだあれ!」
夫は死ぬどころか、着地するなり元気よく叫びました。そして、呆然とする私を置いたまま、先ほどの子供達と同じ方角へと駆けていきます。動揺から自分を取り戻して見ると、夫の行く先にはそれこそ黒山と呼んでいい人だかりができていたのでした。私は夫を追い、その人だかりの後ろにちょこんとくっつきました。
「どうしたの?」
「ほら、見てみろよ!」
震える夫の指先には、ミニブタがいるのでした。ミニブタの入っているカゴには「特等」という看板がつけられていました。
「すいません、この豚は景品ですか?」
夫はテキ屋のおじさんに尋ねました。
「ああ、そうだよ。流行のミニブタだからな。買ったら十万ぐらいするぜ。あの招き猫を落としたら、プレゼント!」
それからの夫の鬼気迫る様を、私は上手く伝えることができません。私達はその日、年金の振込み日が近いということもあって、三万円近くの現金を持っていました。夫はそのすべてを注ぎ込み、とても動きそうにない招き猫を狙い続けたのです。三百円で五発でしたから、夫は五百発を黙々と打ち続けたのでした。はじめは応援していた人達も、一人去り、二人去り、二百発目を終える頃には数人が残るのみとなりました。いまや、痛ましい想いだけが囁きに乗って伝わってきました。射的銃のコルク弾が招き猫を、かん、と哀切に鳴らしました。私は恥ずかしくて、すぐにでもその場を立ち去りたい気持ちになりました。が、夫はそれでも黙々と招き猫を撃ち続けています。せめて同じ場所に当てれば落ちもしようというのか、招き猫の手だけを狙っているのが悲しかったのをよく覚えています。やがて、夫はすべての弾を撃ち終えました。
「おい、おかしいんじゃねえか!」
観衆の一人がそう叫びました。神経質そうな眼鏡をかけた、少し怖い感じのおじさんでした。テキ屋のおじさんが「どこがだよ」と言い返すと、眼鏡のおじさんは激昂した風に叫びました。
「何発撃ったと思ってんだよ! ケチケチすんじゃねえ」
眼鏡のおじさんの怒号に応じたように、残った観衆から「そうだそうだ」と大合唱が沸き起こりました。はじめは威勢良く反論していたテキ屋のおじさんも、次第に元気がなくなり、ついにはミニブタの入ったカゴを差し出しました。眼鏡のおじさんは「よかったな」と言いながら、夫の肩を叩きました。
帰路、私達夫婦はカゴを抱きながら、人の温かさにむせび泣きました。これが、私達と美豚の出会いです。
背中に十字の模様が幾つもあるという理由で美豚と名づけられたメス豚は、私達の生活に潤いをもたらしました。
私はコンビニでのパートが終わると、廃棄のお弁当を持ち返り、美豚に与えました。美豚は短い尻尾をくるんと丸め、お弁当を食べました。あっという間に平らげると、もっとくれと言わんばかりに鼻を押し付けてきました。美豚のまだ柔らかい鼻が膝に押し付けられてくしゃりとなると、月並ですが、心の底から生きててよかったと思いました。それは夫も同じらしく、水道屋での仕事を終えて帰ってくると、美豚にむしゃぶりつくようにして、抱きかかえました。夫の動きは一々力強いので、美豚はすっかり怯えてしまい、その腕から逃れようと短い足をひょこひょこと動かしました。
美豚の成長は、夏の草花のようでした。たぶん、テキ屋のおじさんにはかわいがられなかったのでしょう、来た頃は痩せていましたが、どんどん膨よかな体型になっていきました。もちろん、私達は美豚を家畜の豚と同じには考えていません。コンビニの廃棄弁当を一つあげたら、それ以上はお預けにしていました。食いしん坊の美豚は私の足元へ転がり、怒ったようにブヒッと鳴きました。本当に、子供がむずかるように、鳴いたのです。
一月も経った頃だったでしょうか。息せき切って帰ってきた夫が、蒼い顔で呟きました。
「ミニブタってのは、大きくなるらしいぜ。杉山さんがミニじゃねえぞって教えてくれたんだ」
「大きくなるって、どんぐらい?」
「五十キロぐらいにはなるってよ」
夫の上司である杉山係長がインターネットで調べてくれた情報によると、ミニブタというのは通常の豚と比べて小さいだけで、夫が伝えた程度の大きさに成長するようです。私の体重が四十五キロほどでしたから、同じぐらいの体重です。
「どうしようか……」
と、夫は目を泳がせました。考えがよからぬ方へ行っているようでした。
「どうしようって、大丈夫よ。ちょっと食いしん坊な女の子が一人いると思えば」
「そうかなあ」
「そうよ。それにほら、どうせ私達は子供を作るつもりだったでしょう。大きくなったら、そんなものよ」
夫はしばらく黙り込んでいましたが、懸念を振り払うように「そうだよな!」と叫びました。愚かで、年若く、浅はかな私達でしたが、新たな家族を受け入れる心がまえだけは持っていました。
もともとは「THE PIG Photo Book」を読んでその愛らしさに撃たれたことがきっかけだったのですが、美豚は成長するにつれ、写真集に乗っていたミニブタのような美しさを失いました。薄桃色だった肌はくすみ、体毛も柔毛とは呼びがたくなっていました。口角には常に涎の泡がありました。しかし、写真と一口に言っても、すべての真実を写すわけではありません。美豚には、生身の、体温を持った愛おしさがあった――それが私達の知る真実でした。
とはいえ、私達が美豚の成長を頬笑んで見ていられたあの三ヶ月が過ぎてしまったということもまた、真実でした。
美豚の体重は五十キロを超え、六十キロ、七十キロと増えて行きました。なにか病気にでもなったのではないかとも疑いましたが、廃棄のお弁当に栄養がありすぎるのだろう、などと無理に納得していました。しかし、美豚の体重が百キロを超えた頃になって、ようやく気づいたのです。美豚は、ミニブタではないのではないか、と。
人は私達の愚かさを笑うでしょうか。テキ屋の景品を言葉通りにミニブタと信じ込み、手に負えない獣を飼ってしまった、よく確かめもせず、と。浅はかといえばそうなのでしょう。しかし、浅はかさは、私達に押された烙印であると同時に、絆でもあったのです。
私達が結ばれたのは、私が十五歳、夫が十六歳のときでした。右も左もわからない二人が、思うままに愛し合って、そして身篭りました。そんな歳でしたから、堕ろせと周囲は言いましたが、夫はあの明るい行動力と断固とした楽天主義で子供を育てようと言ってくれたのです。私達は勘当同然で家を出ました。夫は水道管工事の職場でのアルバイト。私も年齢を偽り、大きくなるお腹を隠しながら、人には言えないようなところで働きました。ローンも組めず、家だっておいそれとは借りられない。私達は世界を敵に回したのでした。いえ、知らず知らずのうちに、自分達がそう仕向けたのかもしれません。
世界のすべてに対する敵意は、私達に与えられるはずだった小さな命が奪われたことで、ますます強まったように思います。私達の赤ちゃんは、私のお腹の中で縊れて死にました。稽留流産というものでした。私が子供を産むためには、ひどく確率の低い手術を受けなければならないとのことでした。さりとて、今さら自分達が子供に戻ることもできません。私達は、すべてを失い、雨もりの修繕をするように生きてきました。
浅はかであることによって結ばれた私達にとって、美豚を手放すことなど、とてもできませんでした。
私達は幾つかの約束をしました。美豚の成長をきちんと見守ること。そして、ミニブタの美豚は私達よりも早く死んでしまうけれども、それを受け入れること。それは世間の片隅でひっそりと生きる私達にとって、毎日思い返すべき憲法のようなものでした。
百キロを超えた美豚との生活は、地獄といっていいものでした。住んでいるのは小さな二間のアパートです。古い建物で人気が無いためにペット可という条件だったのですが、それも中型犬程度の大きさに限るということでした。美豚が小さい頃はなんの問題も無かったのですが、痒い背中を柱に擦りつけるだけで、住人たちから不信がられました。
「お宅のミニブタって、ちょっとうるさくない?」
そんな苦情を言われては、謝って回るのです。幸い、美豚の立てる騒音に関しては私がアパートの周りを毎日掃除することでなんとかなりましたが、他にも問題は山ほどありました。百キロもの体重です。コンビニの廃棄弁当だけでは間に合わず、ドッグフードを買い与えてみたのですが、人間の食べ物に慣れてしまった美豚は少し匂いを嗅いだきりで、ブヒッと不満の声を漏らしました。私は日中の勤務ですから、勤務時間中の廃棄は少ないのです。真夜中の日付が代わる頃コンビニまで出かけ、夜勤の人に廃棄を貰って帰る日々が続きました。そして、夜中に布団にもぐりこんでくる美豚。ストレスからか、柱を齧る美豚。トイレこそ決まった場所でしましたが、砂は一日で総入れ替えになってしまいます。歩く力が凄まじく、畳はところどころむしれ、毛羽立ってしまいました。
それでも、私達は美豚と共に生きることを選ぼうとしていたのです。世の中には障碍を持つ子供さんでも精いっぱい愛している親御さん達がいらっしゃいます。子供を持つとはそういうことだ、私達夫婦はお互いを励ましあいながら、美豚と共に生きていました。
誰にも迷惑などかけなかった、といえば嘘になります。住民の方々にも迷惑はかけたでしょうし、夜勤の方も店長の目を盗んで廃棄を分けてくださったわけですから。でも、それだけならば、私達は美豚と共に生きて行くことができたのです。恥を忍ぶぐらいならば。
美豚にはこの家に来たときから一つの癖がありました。一人ぼっちの時間が長く続くと、帰ってきた人に飛びつくのです。ブヒッと鳴きながら嬉しそうに駆け寄ってくる様は、子供なら可愛いのですが、いまや百キロを超える巨体です。これは豚を飼うに当たってぜひとも躾けておかなくてはならない点だということを、パソコンを持っている夫の上司が教えてくれていたのでした。私はそれに従い、手を挙げると美豚がお座りをするように躾けたのでした。
ところが、その日はなぜか、美豚が止まらなかったのです。先に帰ったのが夫だったからでしょうか。確かに夫が私より早く帰ることはほとんどなかったのですが、これまでもそんな事は起きませんでした。もしかしたら美豚が私達を救うために……。今でもそう思います。
ともかく、美豚はその巨体で帰宅した夫に飛びつき、肋骨を骨折させたのでした。夫の仕事は水道管の修理で、膝をついたり、物を運んだり、何かと身体を動かすのです。夫を十六で雇ってくれた優しい会社でしたから、夫を首にはせず、一時的に内勤の仕事を与えてくれました。それでも、夫に向いた仕事ではありません。いつまでもそうしているわけにはいきませんでした。
「どうすっかなあ。またこういうことがあったら困るよなあ」
夫はきっと不安になったのでしょう。事の次第を上司の杉山係長に相談しました。様子を見に来た杉山係長は、美豚の姿を見て絶句しました。百キロもある巨体が、狭い二間のアパートで寝ているのです。ふて腐れたように眠る美豚をしばらく眺めた後、係長は真面目な顔で言いました。
「これは、処分するしかないね。人間に危害を加えた後じゃ」
「大丈夫ですよ! もう少したったら大きな家に引っ越して……」
そう言いながら、夫の声は肋骨を庇ってあえぐように細っていきます。
「とにかく、私も協力するから、君達も考えておいてくれ」
冷酷な言葉を残して去って行った杉山係長でしたが、色々と奔走して下さったようです。動物園での引き取りを頼んで下さったということは、後に聞きました。私達夫婦も色んな道を模索しましたが、蓄豚である美豚には、引き受け手などないのでした。
「おまえ、美豚を殺せるか」
夫が尋ねました。私はただただ首を振りました。我が子として育てようと決心した美豚を屠ることなどできるはずがありません。とはいえ、生きるだけで精一杯の私達が、美豚に合わせて生活を築くなど、とてもできそうにありません。私達はいまや自分よりも大きくなってしまった美豚を抱え、泣きました。きっと、察していたのでしょう。美豚はその巨体を精一杯小さく丸め、健気に甘えてくるのでした。
やがて、私達は精肉店に向かいました。そこの店主は老齢ですが、屠殺と食肉解体の心得があるそうなのです。事情を聞くと、二つ返事で協力してくれました。肉屋さんにも、昔に牛との悲しい別れがあったのだそうです。誰でも、そんな悲しみの一つや二つを抱えて生きているのかもしれません。
別れの朝が訪れました。僅か数百メートルの散歩を初夏の清々しい空気が色彩ります。家の外に出ることなど叶わない美豚でしたが、その日ばかりは大人しく私達の後をついてきました。物言わぬ澄んだ瞳で。家を出るとき、ドアで背中をかきながらブヒッと言ったのが、私達の聞いた最後の言葉になりました。
三日後、狭い我が家に山ほどの豚肉が届きました。白い脂が輝く肉の塊でした。冷凍庫には入りきらず、三食すべて豚料理にしても食べ切れそうにありません。しかし、それをすべて食べきるのが美豚にできるせめてもの償いでした。
私は肩ロースのブロックを取り出し、それを厚切りにし、筋を叩き、下味をつけて、次々とフライパンの上に乗せていきました。甘い煙が漂って、脂の爆ぜる音がします。桃のように瑞々しい肉から少しずつ赤味がぬけていき、きゅっと引き締まりました。
調理を終え、皿に盛ったポークソテーを食卓に置くと、夫は端っこにナイフを入れ、口に運びました。
「なんだ、これ。あー、なんでこんなに美味いんだろう」
夫は額に手を当てていました。口の端が震えていました。
「美豚は高座豚だったんだって。ブランド豚よ」
と、私はつとめて明るく言いました。
「そっか。やっぱり美豚は由緒正しい豚だったんだな」
私達はたくさんのポークソテーを、次から次へと口に運びました。親馬鹿と呼ぶのは正しいのでしょうか、ともかく美味しい肉でした。ビタミンBと入れ替わりに、たくさんの涙が出て行きました。言葉を飾るのは苦手です。美味しい肉でした。ただそれだけが、本当の気持ちです。





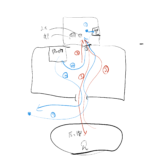
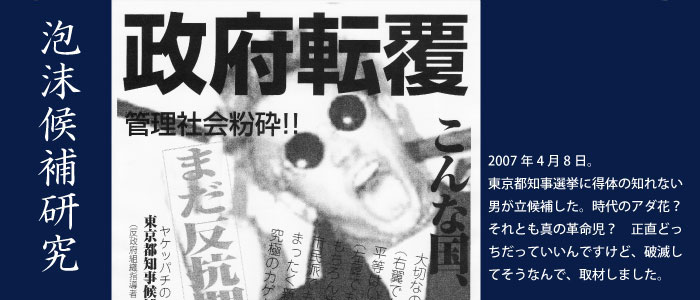



















"泣きながら、ポークソテー"へのコメント 0件