並河はとても雰囲気のいい喫茶店を見つけた。温もりを感じるテーブルや程よい苦味のブレンドコーヒー、聞こえるか聞こえないかの淡く漂う音楽、優しげに微笑みながらあくまで真剣にコーヒーを淹れる幼げな女のマスター。すべてがこれ以上ないほどの空気を持っていた。
彼は窓際の席に座り、コーヒーを二口ほど飲み、少し泣いた。コーヒーはこれ以上ないというほど適切に苦かった。それは人生の苦しさを教えてくれるような味だった。そう、自分はこんな風に人生を味わってはいけないのだ。そういったことを許された人間ではないのだ。そう思うと、涙が洪水のように溢れそうだった。自分がこんなところで泣き出すことを許された人間ではないということを、彼はよく知っていた。
並河は無機質なダムのことを想像した。アメリカの、北の方にある、誰も住まない僻地の徹底的に合理化されたダムのことを。そのダムは貯水率が百パーセントを超えるより先に、少しずつ水を排出する。出ているのかいないのか、注意深く見つめなければわからないほどわずかに。激情が水面のように静かに収まってゆくのを感じた。コーヒーをすする。舌の付け根に僅かな苦みが残り、水分が胃へと流れ込んでいく。ダムの排水をイメージする。いましがた流れ込んだ水は、涙腺へと駆け上がっていかず、どことも知れない場所へ溶け込む。彼は煙草を手に取り、火をつける。勢い良く吸い込み、煙が熱を保ったまま全身に染み渡るのをイメージする。煙の熱が先ほど散らばった水分を気化させてしまう。その作業を十分に繰り返すと、灰皿で煙草を揉み消す。か細い悲鳴のような煙さえ出なくなるまで、じっくりと。それが済むと、煙草の箱にBICのライターをしまう。この一連の作業は彼がこの二年のあいだに身につけた技術だった。いつのまにか煙草のパッケージも変わっていた。
「今年は熊手、出すんですか?」
とつぜん話しかけられて振り向くと、中年の女性が驚いたような顔をしてから、すぐに「あら、ごめんなさい。知り合いの人に似ていたから」ときまり悪そうに笑った。
「いえ、いいですよ」と、並河は答えた。カップはかすかな音を立てて皿に置かれた。拒絶するような音色だった。
「あら、この辺の人じゃない?」
「ええ、転職で越して来たので」
「そう」
女性は並河について幾つか質問をした。いつ越して来たのか、仕事は何をやっているか、独身か、出身はどこか、などのあたりさわりのない質問だった。並河はそのまま答え、それが自然に聞こえるだろうか、と不安に思った。最大の難所は「なぜこんなところに越してきたのか」という質問だったが、これに関して並河は正答を用意していた。
「僕は碁盤目状の街が好きなんですよ」
そう切り出すと、並河は口が滑らかに動き出すのを感じた。つい先ほどまで頬にあった引きつりのようなものが溶かされていく。碁盤目状の道は歩いていて気持ちいい。どの方角になにがあるか、いつだってすぐにわかる。整然とした街並を歩くということは、母に抱かれているような安心感がある。
「あなたはとてもインテリジェントね」
女性はそのように総括した。ラベンダー色のニットの胸元には、細い鎖のネックレスが光っていた。
「そうですか? インテリと言われたのははじめてですけど」
「いいえ、intelligentよ」と、女性は正確な英語のlで言い直した。「インテリっていうのとはちょっと違う。なんかね、感情がないのよ」
ぶしつけに言われても、並河は驚いたり怒ったりするより、怯えが先に来るのだった。胸の震えをコーヒーで押し流そうとしたが、カップを挙げるときに手が奮え、カチャカチャと鳴った。感情を意図的に押し殺す人生を選んだことで、怯える人間になってしまっていた。
「そう見えます?」
「ええ、ごめんなさい。でも、そういう人多いのよ。見て」
女性はアイラインを濃く引いた目で並河をじっと見てから、肩に下げていた鞄をまさぐった。そして、白いA4のコピー用紙に印刷された紙を数枚差し出した。
「最近は感情をうまく出せない人が増えていて」と、女性は切り出した。「そういうのを持って生まれたものだと思ってしまうんだけど、ほんとうは違うのね。トレーニング次第で変われるのね」
並河は差し出されたA4用紙をよく眺めた。アメリカ初の黒人大統領に吹き出しがあてられていて、そこには”We can chage!”と大書されていた。並河はほんの少しの侮蔑と大きな安堵を覚えた。バレたわけではなかったのだ。女性が相変わらず話を続け、それが彼女の主催する自己啓発セミナーへの勧誘であるという鬱陶しい事実でさえ、並河にとってはありがたかった。人は変われる? やり直せる? 遅過ぎることなんてない? そうだろう。人生において決定的なことをしていないうちならば、それはすべてそうだろう。問題はそうしたことが原理的に可能かどうかではない。やり直すことが常に可能とは限らないということだ。そして、並河は自分がいまそのときにないということをよく知っていた。
「ちょっといいかしら?」
そう言って女性が並河の前の席に座ろうとした、まさにそのときだった。
「三田さん、その辺にしといてよ」
声の主はカウンターにいた女のマスターだった。
「そのお客さん、困ってるでしょ? うちではそういうのやめて」
女性はきまり悪そうな顔をして、反論しかけたが、すぐに無理だと悟ったのか、並河に「でも、迷惑じゃないわよね?」と尋ねた。どう答えたものかと思案しているうちに、マスターが「ほら、嫌だってさ」と追い込んだ。三田さんというらしい女性は、ふて腐れた仕草でチラシをしまい、そそくさと別の席に座った。そして、ずっとここで獲物を待っていたのだろう、とうに冷めてしまったカップに何度か口をつけてからレジへ向かった。
「ごめんね。ああいう人もいるから」






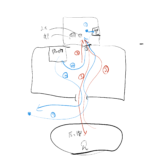
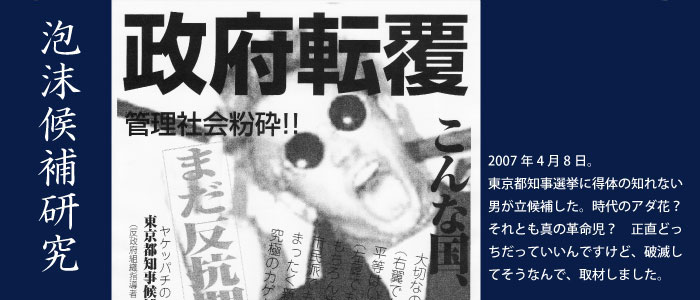



















"いい曲だけど名前は知らない"へのコメント 0件