当時の俺は山本さんが突如に発現した強烈なリーダーシップにあてられ、申し出のあったすべての人を受け入れようと考えていた。カズたちがうちに来る一日前にも、会社の後輩であるコンタ――近藤太一という名前だからコンタ――を受け入れていた。コンタは二十五歳で、ついこの間に情報工学系の大学院を修士で終えたばかりの秀才であり、株式会社ビーアウェアでも期待の新人だったのだが、そこはやはり中小零細に就職する人材として一癖も二癖も持っていた。まず、趣味としてコスプレをするのだが、選ぶキャラはいつも女で、ようするに男の娘だ。twitterのアイコンも女装コスプレで、一人称が「わたし」だったりする。「オネエか」と問いただす無神経な奴はどこにでもいるものだが、以前そう聞かれた時に恋愛対象は女だと言い張っていた。かと思えば、飲み会の席ではクニャクニャと身体をくねらせてしなだれかかってきたりして、なんというか、セクシャリティが曖昧な奴なのだ。
そんなわけで、俺はカズと同居を始める前にすでに誰かを受け入れていたわけで、カズがうちに避難してくるとなっても「オネエに女子高生が加わるだけだろ、どんと来い」と思っていたのだが、完全に想定外だったのは、カズはまだ女子高生で、家族と一緒に来るという当たり前の事実だった。
幕張本郷の駅までカズを迎えに行くと、改札にはスーツケースを2つもったおじさんと、恨めしげにリュックのストラップを握りしめた小学生ぐらいのガキがセットでついてきていた。カズはさっぱりとしたジーンズにブロックチェックのネルシャツというやぼったい格好で、なんだか中学生ぐらいに見えた。確かに、これぐらいの歳の子供ならば、避難するときは当然家族と一緒だろう——と俺は妙に納得しながら、ロータリーに駐めてあったVitzのトランクにスーツケースを詰めた。
「お父さん、なんの仕事しているんですか」
「奥さんは来ないんですか」
「よくこんなところまで避難してきましたね、他にあてはなかったんですか」
いま思えば不安のせいだろう、家までわずか五分のドライブで俺は不躾な質問をまくし立てた。まるで圧迫面接だったが、カズの父はそれが不当だという感じでもなく、恐縮しきりで答えた。それによると、大田区の業務用冷蔵庫業者に勤める三苫満(四十二歳)は岐阜県出身で専門学校卒業に上京、いまの会社に勤め始めた。二十四歳のときに結婚して一男一女を傭けるも、三十六歳の時に妻と死別。少し悩んだが、子どもたちのためにも再婚を決意、パート勤務の中国人女性からの紹介を通じてティエン・リンを二度目の伴侶に選んだ。リンとは不仲というわけではないが、今回のパニックが起きてすぐ実家の山東省に帰っていた。東京の状況次第では、呼び寄せてもらう手はずになっている。したがって、三苫家が世話になるのは東京が壊滅的な状況になるか、事態が収束するかのいずれかで、どちらにせよそう時間はかからないはずだ。
ドライブが終わるまで、話していたのは満さんと俺だけだった。なんだかんだいって、おじさん同志の方が話しやすかったのだろう。カズと弟のナオは黙ったままだった。
家に着くと、俺は三苫家を部屋へと案内した。メゾネットの間取りは2LDK+ウォークインクローゼットだったが、六畳間を占拠していたコンタはクローゼット住まいへと格下げとなり、六畳間が三苫家の根城となっていた。
「とりあえず、俺はこれから仕事に行くんで、自由に過ごしてください。合鍵も渡しとくんで。ワイファイも勝手に繋いでいいっすよ。承久のLANってやつが飛んでるんで。パスワードはgotoba1221です」
「ワイファイってなんでしょうか」と、満さんは尋ねた。
「無線のインターネット接続ですよ。スマホとか繋げる用の。通信料かかんないし、早いから便利っすよ。もしわかんなかったら、娘さんとかに聞いてください。わかるよな?」
俺が尋ねると、カズは小さく頷いた。
「スーパーとかも適当にググって見つけてください。冷蔵庫勝手に使っていいんで。近くにサミットあるから、そこが便利ですよ」
「あの、車は……お借りしてもいいんでしょうか」
「すいません、あれレンタカーなんですよ。事故とかあるとメンドイんで、必要だったらそこら辺のカーシェアで借りてもらっていいですか。ググればわかるんで」と、俺はそこまで言うと、スマホの画面をちらっと見た。遅れることは伝えてあったが、家でダラダラしていてもしょうがない。「わかんないことあったら、LINEで聞いてください。娘さんがわかるんで。なっ」
カズは再び小さく頷いた。以前会った時は生意気だったが、ずいぶん従順な様子に変わっている。親の前だとそんなもんなのだろう。満さんは他にも色々と聞きたいことがあるようだったが、あいにく俺はわからない奴にアレコレ説明するのが嫌いだ。居場所を提供しただけですでに俺は善行をなしているのに、さらに調べればわかるようなことまで教えてやらなければいけないようでは、税金を正しく収めた人間に追徴課税をするようなものだ。そんなわけで、俺は善意の累進課税から逃れるために職場へと向かった。
ビーアウェアでは半数ぐらいの社員が出勤していた。自宅待機の人間もチャットに常駐しており、リモートでも働くことはできる。不思議なもので、こんな状況になっても普通に仕事は存在するのだ。俺たちはすべての業務を停止して危機管理システムvultureのメンテナンスを行っていたが、営業担当の奴らなんかは案外やることがないので、顧客対応を行っていた。新規に仕事を取っても開発者たちはvultureにかかりっきりで手が空かないけれども、ピンチはチャンス、なんらかの大口案件が舞い込んでくるかもしれない。
と、営業担当の河合というヤツが俺に声をかけてきた。マーケティングを強みとしていて、まあ言うなれば顧客の広告出稿を手伝っている男だ。営業にしてはちょっとコミュニケーション能力がない感じなのだが、仲良くなった人にはとても懐くタイプのネコ型おじさんだ。
「ちょっと、藤さん、いいすか、これ」河合は左手に載せたMacbookの画面を俺に見せた。Googleの広告管理ツールが表示されている。「このRPMめっちゃ上がってるじゃないですか」
「RPMってなんだっけ?」
「一〇〇〇PVあたりの広告収益ですよ。ほら、すごいでしょ。このサイト、一二◯◯円超えてますよ」
「ああ、そっか。普通は多くて五〇〇円ぐらいだっけ? なんでこんな多いの」
「そうなんすよ」と、河合は嬉しそうに身を乗り出した。河合は知識のない客にカラクリを教えるのが大好きだから、俺に話せて嬉しいのだろう。「いまって東京から避難する人すごい増えてるんですよ。藤さんの家にも来たんでしょ?」
「来たよ。子供二人とその親父さんと、あとコンタ」
「でしょ? みんなそうなんですよ。でね、いまって広告にこういう不動産の売買、新築一軒家、空き家斡旋とかがバンバン出稿されてて、クリック単価がめちゃ上がってるんです」
「そうなんだ」
「そうっすよ!」と、河合は俺の肩を叩いた。「いまこの業界の人にとっては激アツなんですよ。家なんて一ヶ月に一件も売れたらいいじゃないですか。それがいまはバカ売れですよ。しかも、成約額がでかいから、単価も結構ありえないことになってて。住友不動産とか、あのあたりが地方の土地買いまくってますよ」
確かに、言われてみればそうだ。これだけ多くの人が移動することはあまりない。ゲルマン民族大移動も引っ越しの玉突き事故みたいなものだし、特定の目的をもって引っ越すということはそれだけの事件なのだ。俺みたいに善意で部屋を提供する奴もいるにはいるだろうが、普通に金を持ってたら引っ越すだろう。
「頭いいヤツがいるよな」と、俺は口をすぼめた。「家賃取ろうかな」
そこまで言うと、河合は「vultureに広告貼りましょうよ」と急に真面目な顔になった。そんなことをしていいのだろうか? 元々は慈善事業というか、この混乱した状況で俺たちも何かできるのではないかという気持ちからvultureを作ったわけで、ユーザーもそう思っているだろう。
「炎上とかすんじゃねえの。ダイジョブか?」
「いや、それはマジで大丈夫です。というのは、みんな急いでるんで」
「まあ、俺は別にいいけどさ。炎上しても。でも、一応山本さんに確認する事案だろ、これ」
俺がそう言うと、河合はすぐさま山本さんのところへ行き、事情を説明した。山本さんははじめ渋っていたが、月額五十万は固いという河合の発案を聞き、揺らいだようだった。俺は山本さんのその姿を見ても別に失望しなかった。ビーアウェアがvultureを無償で提供していても、サーバ代やらこうして開発に携わっている人間の給料やらはかかっているわけだ。無償で使えるままにするために広告収益を稼ごうとするのは持続可能性の観点からまったく正しい。
結局、vultureに広告が実装されることになった。それまでスマホ画面の右下には地図のコントローラーがついていたのだが、そのすぐ下に広告を置いた。河合によると、この位置が一番目につきやすいということだ。実装自体はそんなに難しくなかったので、俺たちはすぐにGoogleの管理画面を開いた。vultureに広告実装機能をつけることは、社内的にも注目度が高かったので、ディスプレイの前にはほとんど全社員が集まった。表示されたRPMは一八◯◯円。おーっ、という歓声が上がった。vultureの一日あたりページビューは二〇万。ということは、一日あたり三六万円が入ることになる。月間で一〇八〇万だ。これはちょっと、なにがしかの数字だった。
「これで上場目指しませんか?」
河合が得意げに言った。山本さんも嬉しさ半分、驚き半分といった表情で、ネクタイの剣先をくるくるとこね回している。たしかに、河合が言った「上場」という響きは魅力的だった。ビーアウェアは顧客のサポートをする起業だったが、当時のIT起業のほとんどが抱いていた「自社サービスで稼ぎたい」という夢を密かに抱えていたからだ。俺たち開発者もみな、ITを非人間的だとか言ってバカにするジジイより、自分たちの製品を愛してくれるユーザーに向き合っていたいと思っていた。
「いや、まじで行けますって。PV十倍にしたら上場できますよ。年間売上十億超えるし」
河合が畳み掛けると、山本さんは「あ、はい」と答えた。そのユーモラスな社畜感に俺たちはゲラゲラと声を揃えて笑った。
そう、あの夜に、俺達はそんな明るい雰囲気で過ごしていたわけだ。
夜八時ぐらいになって、カズからLINEが届いた。
——まだ帰ってこないの?
なぜ好きにしていいといったのに、家主が帰るかどうかを気にしているのか。そもそも、家主なんていない方が家族水入らずでいいだろう。俺はすぐさま熊のブラウンが仕事をバリバリ片付けているスタンプを送った。
——水炊き作っちゃったんだけど
カズはそのメッセージのあと、プルプルと顔を覆って泣いているウサギのコニーのスタンプを送ってきた。なんというか、もしかしたらこのJKは俺と一緒に飯を食いたいのだろうか? それとも、家を追い出されないために媚を売っているのだろうか? そんな感じで悩んでいると、コンタが俺の席まで来て、「もう帰らないと可哀想ですよ」と肘で俺をツンツンした。
「なにおまえ、カズのLINE知ってんの?」
「えー、だって、今朝あったじゃないですかー」
「いや、おまえら二分ぐらいしか話してなくない?」
「私、ほら、ID検索超早いんで」
「いや、知らねーし」
というわけで、なんだかよくわからないが、俺はコンタと一緒に水炊きを食べるべく帰路についた。
玄関に入ると、座卓の周りを囲んだ三苫家がぱっと顔を上げた。俺は自分が待たれていたのだということにそのときはじめて気づいた。三苫家に打算があろうがなかろうが、こいつらは俺と飯を食いたかったのだ。俺を飯に誘う人間は山本さん以外この世に存在しなかったので、正直いって心底嬉しかった。
「おかえりー」
カズは奥二重の細い目を緩やかに曲げて言った。座卓には糖質ゼロの発泡酒が二つ置かれていて、たぶん俺とコンタの分だった。満さんはすでに缶を持って飲み始めていた。
「あれ、糖質ゼロ?」
俺はなんと言っていいかわからなくて、とりあえず目の前に見えた状況を説明した。すると、親父の満さんが「いや、僕が痛風でね、カズはいっつもこういうビール買ってくるんですよ」と付け加えた。すると、カズは「そうなのー」と目を伏せながら缶ビールのプルタブを開け、俺に「はいっ」と手渡した。なんとなくビールを受け取った俺の右手人差し指にカズの親指が当たった。カズは何も言わないで次のビールを開け、コンタに渡した。
「結婚しよう」
俺は思わず呟いていた。弟のナオが声変わり前の中学一年生らしく甲高い声で「はあ?」と叫んだ。
「いや、家族っていいいな的な意味でね。俺も結婚して家族持ちたいな的な意味でね」と、俺はすかさず付け加えた。「あと、お前の声初めて聞いたわ」
ナオの顔が一瞬で赤くなった。なんだ中学生かわいいな、と俺が思ったその瞬間だった。それまで黙ってスマホをいじっていたコンタがスマホをぽんとテーブルに置いた。
「これ、ヤバいですよ」
スマホには代々木公園でのデモが映っていた。たぶん誰かがYoutubeかなにかで動画を流しているのだ。ここ二日ほど、代々木公園に人が集まって、デモだかなんだかよくわからないお祭りを繰り広げていたから、おそらくその動画だった。画面には明らかにゾンビ的なヤツが映っていた。肌が黒くて、動きがせわしないヤツだ。これはおそらくゾンビ列車と同じ事態になりそうな感じだった。ただゾンビ列車と違うのは、ゾンビっぽいヤツの割合がかなり高そうなことだった。
「これ、たぶん閾値超えますよ」
情報工学を修め、統計の知識も豊富なコンタはそういうと、動画を閉じてvultureの画面を開いた。俺たちは画面をじっと眺めた。温めなおした水炊きがふつふつと湯気を立てていた。なんで俺、もうすぐ夏なのに鍋食おうとしてんだろ——俺は地図を眺めながらそんなことを考えていた。と、東京西部に赤い小さな点がポワンと生まれた。その点は瞬く間に大きくなり、すぐに山手線を覆った。それから拡大の速度が遅くなったが、コンタが「ほらね」といった瞬間にはあっという間に海浜幕張まで到達した。ヤバさは関東平野を覆っていた。









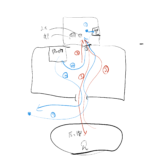
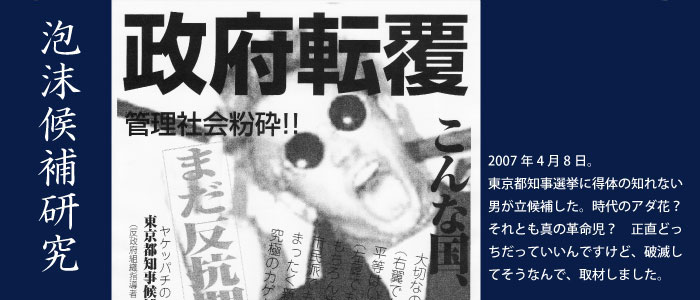



















"はつこいオブ・ザ・デッド(6)"へのコメント 0件