東京大学本郷キャンパスに法文1号館という建物があって、文学部の授業はそこで行われることが多かった。かなり古い建物で、トイレにはフェルマーの最終定理が落書きされており、廊下には革張りのベンチシートと灰皿が置いてあった。そうしたベンチに腰掛けて授業の開始を待つのが、新しいキャンパスに移ったばかりの私の新しい習慣だった。二十世紀最後の年で、私は大学三年生だった。
東大では三年に上がるときに進学振り分けという選考分けシステムがある。入学時は文Ⅰ・文Ⅱ・文Ⅲという漠然とした区分で全員が教養学部生として二年間を過ごす。教養学部には小学校から高校まであった学級が存在しており、私は文Ⅲ十三組だった。三年生から成績に応じて進学先の学部学科を選ぶことができ、たとえば文学部言語文化学科フランス語フランス文学専修という長ったらしい名前の学科へと所属が変わる。つまり、東大では大学三年生になるとクラス替えが起きるのである。
二十五名ほどいる仏文科の三年生のうち、同じクラスの出身者は三人程度、上級生や大学院生を含め、これから知り合っていかなければならない人の方が多かった。もう二十歳を超えていたが、新しい環境というのは、面映いような、心細いような感触をもたらす。
夏休み前の時期だったと思うが、私は授業開始前に教室前の廊下にあるベンチで煙草を吸っていた。すると、ほろほろ落花生――当時はまだ花藤義和だった――が現れた。私は彼とあまり話したことがなかった。ただ、彼が変わった人間だということだけはすでに知っていた。
仏文科進学時の初顔合わせで新入生自己紹介があったのだが、花藤は「私は太宰治や小林秀雄、大江健三郎が在籍したという理由だけで仏文を選んだのであり、純粋に仏文卒という肩書きが欲しいだけです。フランス語、フランス文学にはまったく興味がありません」と言ってのけた。私は怒られるのではないかと危惧したが、教授陣は苦笑いをするだけで、もしかしたらこういう挑発的な学生には慣れているのかもしれなかった。その後に開催された懇親会では詩を朗読し、「貴様達は決して出納掛以上ではない!」と言い放って参加者を驚かせた。なかなか才気走った奴だと思ったが、あとで聞いたところ自作の詩ではなく、中原中也「聖浄白眼」を朗読しただけだったらしい。ともかく、そんな事件があったので、進学早々、花藤は「本物の文学に情熱を燃やしている攻撃的な奴」というキャラクターが定着していた。
教室前のベンチに座った花藤と「おう」と軽い挨拶を交わし、煙草を吸い始めた。ふと彼の手元を見ると、講談社文庫『ノルウェイの森』を持っていた。カバーが外されていたので、上下巻のどちらだったかはわからなかった。
「おまえ、春樹とか読むんだ」
私はその言葉に若干の侮蔑を含めていたかも知れない。別に村上春樹を読んでいるのは構わない。しかし、詩を書いているだとか、こんなくだらない大学はもうすぐ辞めるだとか、頓狂なことばかり言っていたくせに、村上春樹を読んでいるというのは、なんというか、普通だった。しかし、私のあざけりはその後に続いた言葉で浅はかさへと変わってしまった。
「俺、もう百回読んでるから」
「なんでそんな読むんだよ」と、私はすぐに尋ねた。
「彼女、死んでるし」
返答に窮した。私は「百回」という明らかな誇張にツッコミを入れてやるつもりでいたのだが、彼女が死んでいるのなら、私にはそこに踏み込む権利はない。『ノルウェイの森』でヒロインの直子が自死するように、花藤の彼女が死んでしまったのなら、百回読むこともあるだろう。その後、私はどんな会話をしていたのか覚えていない。
徐々に仏文科の同級生たちとも打ち解け、飲みにいく回数も増えた。花藤は体が弱いというか、線が細いというか、背は高いのだがいつも具合が悪そうで、初夏でもウールのコートを着込んでいた。「自分は躁鬱病と分裂病を患っている」とも言っており、たとえば飲み会が三回あったとしたら、そのうちの二回はドタキャンする、という感じだった。仏文科の夏合宿では同級生女子に、「おまえは男にチヤホヤされて世の中をこすく渡り歩こうとしている」などとからみ酒をして泣かせていた。なんというか、中学生の不良がするような悪事を大学生になってからあらためて履修しているようなところがあった。それでも仏文科にはそうした人間を許容する雰囲気があった。
徐々に親交を深めていき、私と花藤、そして油田はよくつるむようになった。夏休みが明けた頃、花藤の家に泊まりにいく機会があった。本郷キャンパスからほど近い白山のワンルームには本棚と机ぐらいしかなく、窓際には花藤が彫刻刀で彫ったという木彫りの男根像があった。奮発して買ったサントリーリザーブのボトルを開け、恋愛の話になった。花藤の彼女である亜津佐は自死したという話だったが、実のところ、単に別れただけだという。別れたという事実が受け止められなくて死んだと言っていたのか、と私は合点した。このときにはすでに、花藤の文学的修辞というか、大袈裟な物言いをする癖を理解しつつあったので、男女の別れを死と表現するのが彼の文体だと私は考えていた。別れの原因は「ひどい裏切り」だったそうである。そのひどい裏切りというのはなんだったのかというと、別に浮気をしていたわけではない。二度ほど狂言自殺があったそうだが、それも別れの直接的な原因ではないらしい。
「亜津佐は両性具有だったんだよ」
花藤は別れの理由について聞き慣れない言葉を発した。私は「何を言ってるんだコイツ?」と思った。
「たまにいるらしい。十万人に一人とか」
そういう生物学的な状態が存在しているということはわかる。だが、彼女が両性具有だったから別れたというケースは初耳だった。ちょうどその一年半ほど前に平野啓一郎が両性具有を扱った『日蝕』で芥川賞を獲っていた。もしかしたら、文学的流行に乗っかり、花藤流の文体で何かを表現しているのか? 私は判断を保留した。嘘だとも本当だとも言わなかった。
その後、花藤によって笹川亜津佐との馴れ初めが語られた――。
大学に合格し、福井から上京した花藤は、東大教養学部のある駒場キャンパスにほど近い浜田山で一人暮らしを始めた。ゴールデンウィーク明け、一件の間違い電話がかかってきた。そのときはすぐに切ったが、再び間違い電話がかかってきたので少し話した、というのも相手は女性だったからだ。同じ都内にある学習院大学に通っている同い年とのことだった。運命的な符号。また電話しようと約束した。
それから何度か電話で話すだけの関係が数ヶ月が続いた。会いたいということになった。亜津佐は条件付きで受け入れたが、その条件とは次の通りである――亜津佐は幼い頃に男子大学生に強姦され、視線恐怖症なので、目隠しをして会ってほしい。そして、急に動かれると怖いので、動いたり、自分に触れようとしないでほしい。花藤はこの条件を受け入れた。目隠しをしているとなると、外出するわけにはいかないので花藤の家に亜津佐が来ることになった。
家で目隠しをしたまま会うわけだから、花藤は基本的に何もできない。ただ会話をするだけである。パスタを作ってもらって食べさせてもらったり、それこそ村上春樹的な他愛ない大学生の交際が始まった。もちろん、目隠しをしていることを除けば。
ほどなくして、花藤は童貞を失った。目隠しをしたままなので難易度の高いセックスではあったろうが、亜津佐が導くままに済ませることができた。
そのまま二年の交際が続いた。つまり、大学一年生の六月から、本郷キャンパスに移った大学三年生までである。その間、二度の狂言自殺があり、二度めのときは電話の向こう側で睡眠薬を飲んだ亜津佐を案じる花藤は、ほとんど発狂しかけ、浜田山にあった警察署に「彼女を助けてください!」と駆け込みさえした。対応した警察官は二名いて、そのうち一名が「こいつ、コレか?」と同僚に耳打ちし、こめかみのあたりに人差し指を向けてくるくると回すジェスチャーを見せた。クルクルパー認定された花藤は、友人が迎えに来るまで、そのまま警察署に留め置かれた。
目隠しをしたまま会い続けるという異常な交際に疲れた花藤は、ついに目隠しを外して会うよう懇願した。約束の新宿には中年男性が現れた。亜津佐はどこに? 目の前の中年男性が、亜津佐の声で説明した。亜津佐は両性具有である。男性器と女性器が両方あり、男女の間に生きてきた。視線恐怖症だと騙していたのはほんとうに悪かったと思っている――
話を聴き終えて、私は「よくできている」と感じた。創作の、彼の文体のすべてがつまっている。こうした話は考えつくことが難しい。天才だとさえ感じた。同じく話を聞いていた油田は口をあんぐりと開けていた。「うーん」「まあ」と悩みつつ、何も感想を言わなかった。その後、花藤はもりしげというロリコン系エロ漫画家の単行本を何冊か持ってきて、「これが文学を超えているから読め」と読書会を始めた。
この亜津佐にまつわる秘密を聞いたとき、私は端的に嘘だと断じた。油田はこの件について評価を下すのを曖昧かつ巧妙に避けていた。私は隙あらばその嘘を暴いてやろうと決意した。他にも仲のよい友人は何人かいたが、亜津佐について話したのは私と油田だけのようだった。
その後、私は折に触れ亜津佐について調査をした。花藤の家で酒宴を開いたとき、彼の携帯を覗き見ると、亜津佐からのメールが残っていた。私はこのとき、亜津佐は実在したのか、と感じた。たとえば、別に携帯を契約しておいて自分にあててメールを送るようなこともできなくはない。ただ、登山用具を買うために筑摩書房版ドストエフスキー全集を神保町で売り払うような金欠生活をしている花藤が、わざわざそんな工作をするはずがない。亜津佐はどうも実在するのだ。翌朝、私は携帯のメールを盗み見たことを詫びた。
ほんとうに両性具有のおっさんというのは存在するのだろうか。私は図書館で調べてみた。両性具有というのはたとえばインドのヒジュラーのように文化的・宗教的に認知された存在を除けば、医学的に「性分化疾患」と呼ばれるケース――男性器と女性期の判別がつきづらい症例――がわずかにある程度だ。その多くは男性器と女性器が両方あるのではなく、たとえば内臓は女性(子宮がある)だが外性器は男性(ペニスがある)で陰門があるわけではない、という状態で、両方の性器を備えていることは稀だった。男性器と女性器を備えた真性半陰陽と呼ばれる症例は治療が必要で、大抵は女性として外性器を形成すると予後がよい。これは、生物の身体がベースを雌としていること(男にも不要な乳首がある)を考えると、納得がいく。ただ、これらの治療は生後すぐに行われることが多く、そのまま生育しても男性器・女性器ともに発育不全なままで、セックスはできない。つまり、エロ漫画のふたなり――成長した男性器と女性器が両方くっついている状態――は現実には皆無と言ってよい。すると、花藤が目隠しをかなぐり捨てて目撃した中年男性は、両性具有でもなんでもなく、純粋なゲイの中年男性だったのではなかったか。地方から上京してくる世間知らずの大学生に片っ端から電話をかけ、口車に乗った童貞青年を毒牙にかけていたのではないか。当時は連絡先の載った高校の卒業文集や大学のクラス連絡網が名簿会社で売られており、週刊誌には有名大学合格者の氏名や出身校が掲載されているほどプライバシー意識の希薄な社会だった。そうなると、若い少年の男根を肛門に吸い込みたいと思っているゲイの中年男性にとって、片っ端から電話をかけて嘘八百を連ねることは、十分に対価に見合う行為だったのではないか? 私は中年男性の気持ちになって考えてみた。上京する新大学生の名簿を買う。片っ端から電話をかける。春先から何百件と。その中の一人にたまたま世間知らずの東大生がいて、浜田山のワンルームで目隠しをしたまま自分を待つことに同意する。声音を少し高くして、パスタを作り、キスをする。若いペニスを口に含み、肛門にくわえこむ。相手が目隠しを外したがったら、電話口で狂言自殺をする。秘密は守らせる。どれほど心が踊ったことだろう。
私はこの推理を花藤に告げた。おまえは間違い電話という偶然から両性具有と二年付き合ったのではなく、ゲイのおっさんに騙されていたのだ! 花藤は「そうなんだよ」と答えた。その可能性があるんだよ、でも声とか完全に女なんだ――彼はまだ、両性具有ということに少なからず固執していた。なんでも、別れたあとも何度か会っているという。一緒にカラオケに行ったときは、亜津佐が松田聖子の「渚のバルコニー」を原曲キーで歌いきった。一緒に映画『ハンニバル』を見に行った。新宿十二社温泉―― かつて新宿にあったお湯が真っ黒な温泉――の男湯に亜津佐と一緒に入り、求められるがまま洗い場でフェラチオをさせた。なんかもういいや、という諦めに似た気持ちが花藤を支配していた。
それ以上追求しなかった。というのも、両性具有だと思い続けた方が、彼のダメージは少ないからだ。真実を追い求めたところで、それに向き合うのは私ではなかった。
この亜津佐事件について、仏文科の友人たちはおそらく嘘だと思っていただろう。口止めされていたというのもあって、しつこく確かめることはなかったが、起きた事態の深刻さを周囲がわかっていないという苛立ちに似た感情が私の中で燻り続けた。
大学四年生になると、それまで友達付き合いの悪かった花藤が徐々に周囲と打ち解け始めた。私達の教養学部時代のクラスメイトが降年――東大では進学振り分けで希望の学科に進むだけの成績を得られない場合、二年生の後期から一年生の後期に自ら身分を変更できる、留年ならぬ降年という変わった制度があった――して仏文科に進学してきて活況を呈したこと、そして、花藤を文学的にオルグすることで攻撃的な態度を取らせていた先輩が卒業したこと、それらの理由が大きかったと思う。
私たちは飲みに出かけたり、忙しく過ごした。交友関係は仏文科以外にも広まっていった。そして、リョウという花藤の古い友人と出会った。
彼は年下だったが、都内の私大に通っており、当時の言葉で言えばギャル男のような印象を受けた。花藤が家庭教師をしていた縁で知り合ったという。ほかでもない、彼が浜田山警察署クルクルパー事件で身元引き受け人になった友人だという。私はリョウに真相を問いただした。リョウは私が花藤と出会うより前、つまり亜津佐事件の渦中に花藤と親交があったわけだし、なにより、私に対して嘘をつくメリットがない。リョウはまず、浜田山の警察署に行ったことは事実だと認めた。亜津佐と会ったことはないが、電話で話したことがあるという。あれが女の声だと信じてしまうのは、わからなくないということだった。アニメ声だったそうである。私は高校時代に柔道部だったが、カラオケに行ったとき異常に声の高い男の後輩が華原朋美の“I’m Proud”を原曲キーで歌うのを聴いたことがあったので、そこに違和感はなかった。つまり、女性経験のない花藤が電話や目隠しセックスをしているときに相手が男だと気づかなかったことに論理的齟齬はないわけだ。
大学四年の夏が始まる頃、仏文科のほとんどは留年を決め込んでいた。たしか、就職を決めたのは四人だけで、大学院に進学した五名ほどを含めても、二十四人いる同級生の半数以上がモラトリアムにとどまる結果となった。これは東大の仏文科がそういう雰囲気の学科だったということもあるだろうが、それよりも就職氷河期だったという世相が大きいだろう。内定率は低く、そもそも大手企業が新卒募集をしていないということさえあった。こんな悪い状況で安く身を売ることもないだろう、というのが東大に限らず大学生の共通認識だった。人生の日曜日は延長されたわけだ。私個人のことに関していえば、大学四年の夏には幻冬者NET文学賞を受賞して作家デビューしていたので、浮世離れした感じは周囲に比べてずっと強かっただろう。
猶予期間が延びた気安さの続くある夜、私たちは荻窪にある長岡さんという同級生の家で飲んでいた。長岡さんは東大法学部を出たのちに国交省を定年まで勤め上げ、退官後に東大仏文科に学士入学をしてきた同級生だった。長岡さんにとって私たちは子供のような存在で、東大に合格するほどの学力がありながら、モラトリアムを限界まで擦り倒そうとする私たちが痛快だったのだろう、色々とよくしてもらった。長岡夫妻には子供がいなかったこともその理由の一端だったかもしれない。荻窪の長岡邸を深夜の一時頃に去り、私は終電がすでにないことに気づいた。てっきり朝まで飲むものだと思い込んでいた私は、花藤に「このあとどうする?」と尋ねたが、彼は家に帰るつもりらしかった。なるほど、白山の自宅ならなんとか帰れるだろう。しかし、千葉の実家住まいの私はどうする? 花藤は私を泊めることに難色を示した。多くの人と深夜まで飲んだ結果、人当たりしたのだろう。花藤は半ば逃げるように「俺の知り合いの家に泊めてもらえるか聞いてみるよ」といって、携帯電話で交渉を始めた。なんでも、花藤の元彼女の家が西荻窪あたりにあるらしく、そこに泊めてもらえるそうである。自分の元カノの家に友人を泊まらせるということが果たして可能なのかどうか、私は訝ったが、あっさりオーケーが出た。
その「元カノ」について、私は話を聞いたことがあった。リョウの友人か何かで、花藤がリョウの付き添いで見舞いにいったとき、白い病衣で点滴棒によりかかってよたよた歩く姿が『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイを思わせ、「いいな」と思って告白したそうである。その交際は数週間ほどしか続かなかったそうだが、こうして「友人を泊めてほしい」と頼んで受け入れてくれるぐらいだから、それなりに深い仲ではあったのだろう。付き合っていた時期は大学三年生の冬頃で、つまり、亜津佐と別れてから初めてできた彼女だった。
私は花藤を荻窪の駅で見送ってから、その元カノの家に向かった。携帯電話の番号を教えてもらっていたので、近くまで歩いた。どこで待ち合わせたのか、私はまったく覚えていないが、ファミリーマートの前か何かだったと思う。蘇我鏡花というその女性は、薄いグレーのスウェットを来て私を待っていた。薄着だったので、秋だったのだろう。十月とか、それぐらいだ。私たちはコンビニで夜食と酒を買い、彼女の家に向かった。私はその道すがら、鏡花のことを観察した。それまで花藤の女の趣味というのはある程度知っていたつもりだが、話に聞いていた「点滴棒につかまってよろめく女」とはずいぶん違っていた。まず、鏡花は髪こそ黒かったが、ざっくりと胸元のあいたボートネックのスウェットを着ていて、初対面の男を家に泊めるにはずいぶん無警戒だった。彼女の住むワンルームに入ると、彼女は私のスペースを確保するためにあれこれと散らかったものを脇に片付けてくれたが、そのときにも胸の谷間から下着が覗いていた。ずいぶん違うな、と私は改めて思った。こういう女性はいる。別に私を誘っているというわけではないのだろう、ただ単に無防備なのだ。だが、花藤の好みの女というのは、こういうタイプではなかったのではないか? キャミソールとホットパンツより、白いワンピース。クラブミュージックではなくクラシック音楽。阿部和重を読むぐらいなら、せめて三島由紀夫。茶髪より黒髪。ギャルよりも文学少女。要するに、そういうのが花藤の好みだったわけだ。鏡花は都内の私大に通う女子大生だったが、専門学校を出て一度就職してから大学に入り直しているので、私や花藤より年上だった。なんでも、消費者金融のような怪しげな企業に就職したが、その違法な業務内容に違和感を感じ、やはり学がないとダメだと一念発起し、大学に入り直したのだった。鏡花はそのわずかな年の差を度外視しても、母性が感じられた。花藤の好きそうな、白いワンピースで清流に足を浸したまま文庫本を読む黒髪の儚げな文学少女とは、かけ離れていた。
お互いが何者であるかについて、私と鏡花は話した。花藤がずいぶん私のことを話していたのだろう、打ち解けるのは早かった。私は酔い覚ましに買っておいた緑のたぬきをかきこみ、ひと段落をつくと、どうして花藤と付き合ったのかについて尋ねた。インタビューのような慎重さで挑んだのだが、私がいちばん尋ねたかったことはあっさりと回答を得た。たしかに、鏡花と花藤は付き合っていた。告白してきたのは花藤で、十二月に付き合って、クリスマスプレゼントにアクセサリーを貰ったあと別れた。別れを切り出したのは花藤からで、別れたあとにプレゼントの箱を開いたから、訳がわからなかったそうだ。いかにも花藤らしいエピソードだったが、私にとって意外だったのは、鏡花がその思い出を肯定的に受け止めていそうなことだった。私は亜津佐の件について知っているか尋ねた。鏡花は知っているといえば知っているし、知らないようでもあった。私はさらに踏み込んで、花藤とセックスしたかどうか聞いた。彼女はあっさりと「したよ」と教えてくれた。「一回だけだけどね」
その夜、私は鏡花の横たわるシングルベッド横の床に寝そべりながら、彼女と朝まで話をした。その後の人生の計画などについての話が主だった。
後日、私は花藤と大学で会い、「どうだった?」と聞かれた。どう、というのは、私が彼女と寝たかどうかを聞いているのだろうと判断した。素直に否定しても面白くないので、私は尋ね返した。
「おまえこそ、鏡花が童貞をささげた相手なんだろ? おっさんのケツの穴と若い女のマンコは違ったんじゃないか?」
花藤はふふっと笑い、「ぜんぜん違ったよ」と付け加えた。それはそうだろう。この時点で、彼が亜津佐の両性具有を嘘として受け止めていることが明らかになった。亜津佐と最後に会ったのは上野にある高級中華の東天紅で、食事をご馳走されたということも聞いた。その食事はお詫びだったらしい。なんのお詫びかというと、騙していたことについてだ。
「それでどうするんだよ。亜津佐のことを」
私は尋ねた。花藤は答えは曖昧なものだった。復讐はしてやりたい。そうしないと、いまよりも前に進めない。が、いまは忘れたい。亜津佐の本名はマスダコウジというらしいが、名前以外何もわからない。
私は「復讐すべし」という安易な助言を思いとどまった。花藤は強姦されたようなものだった。性別を偽って性行為をするのが刑事事件として立件しうるのか、私には知識がなかったが、倫理的にはかなり悪いことに違いない。だが、性被害にあった側がそれを訴えるというのも、なかなか難しい。女性であっても性被害に遭って泣き寝入りするケースが少なくないと聞くし、花藤の場合は男性であるがゆえになおさら訴え辛いという心理的な枷もあっただろう。それに、この事実を知っている者は少なく、信じている者はさらに少ない。長くは続かなかったとはいえ、花藤には鏡花というまっとうな本物の女性の恋人ができたこともあった。忘れる、というのも選択肢の一つであるように思えた。
その後、大学四年の終わりに書いた「ぱるんちょ祭り」という作品に、亜津佐が登場していた。間違い電話のくだりは、花藤から聞いていた通りの展開が描かれていた。作中、私は「不美樹」という名前で「ウフィ。ウカァ。」と妙な笑い方で登場させられていたし、大学の同級生の何人かも同様に戯画化されて描かれていた。村上春樹と大正文学のミックスのような文体で、昏さはあるのだが、道化じみた明るさもあった。花藤にとって亜津佐の事件はフィクションに描かれるものとして昇華されたのだと私は信じ込んでいた。
――続く
※続きは『ぼくは君がなつかしい ほろほろ落花生全集』でお読みいただけます。



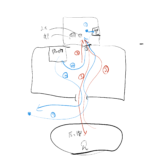
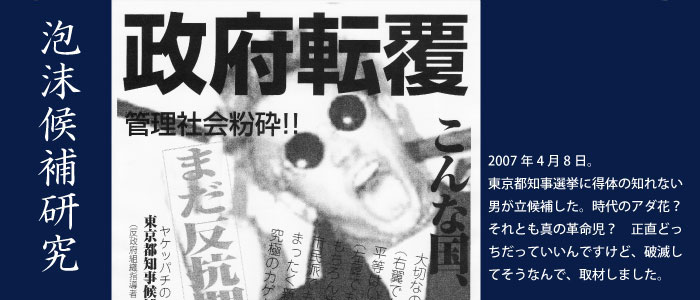



















"コール・ミー(抄)"へのコメント 0件