八ヶ岳の麓にある富士見町には縄文中期の遺跡が多く点在する。Wikipediaの記述にも多くある通り、湧水の多かったことが文明の発展を支えたのだろう。今回はそんな井戸尻遺跡群の中心地にある井戸尻考古館と井戸尻遺跡を訪問した。
井戸尻考古館
井戸尻考古館には多くの出土品が並んでいる。縄文中期ということもあり、出土品には様々なバリエーションが存在する。
- 外観。
- レプリカも含まれているが、実際の出土品も多い。
- 中葉に限るが、様々な時代の土器が見られる。
- 出土したときの写真。
- 様々な石器。簡素な作りだが、あれば役に立つものだ。
- 双眼やカエルの手など、複雑な文様の土器。
他にも重要文化財はいくつかあったのだが、写真を撮ることを禁じられていたので、ご容赦いだたきたい。いわゆるビーナス像などの珍しい出土品も見ることができる。
井戸尻遺跡では、大量の出土品を見ることで、縄文も中期になれば相当な文化成熟度を迎えていたということが理解できるだろう。また、山間部という、ともすれば文明の発達が遅れていたと思ってしまいがちな地域でも、これほどの文化が栄えていたという事実は、縄文小説を書く上で重要なリミッターとなるだろう。
とはいえ、一万年超を超える縄文時代において、中期というのはすでにかなり時代がたった頃である。その宗教・技術・文化など含め、様々な想像が可能だろう。
井戸尻遺跡
井戸尻考古館のすぐそばに井戸尻遺跡がある。遺跡といっても、ほぼ原っぱであり、中央に竪穴式住居のレプリカが建てられている。
遺跡あるあるとして「復元した住居があまりにも立派」という問題がある。この住居も内部がロフト作りになっており、木彫りの階段さえおいてあった。こうした遺跡は近隣住民にとってある種の偶像として存在する。定期的な集まりなどもこの場で開催されるのだろう。そのため、現代の価値観に照らし合わせて居住性を高めようとしてしまうせいで、やや史実に即さない仕上がりになってしまうことが多いようだ。
遺跡自体は実際に発掘された場所がそのまま野ざらしになっている。住居跡の竪穴にぽつんの看板が打ち立てられ、その下は雑草が生い茂っている。縄文時代の竪穴式住居では集落内の同じような場所で少しずつ違った場所に家を建てることを加曽利貝塚訪問記でお伝えしたが、長野県でもその例に漏れないようだ。
*
以上、井戸尻遺跡のレポートをお届けした。縄文の成熟を一望するという意味でも、井戸尻遺跡を訪問しておくと役に立つだろう。また、各地の縄文イベントに関する情報もポスターやフライヤーなどで手に入るので、一度足を運んでみてはいかがだろうか。
















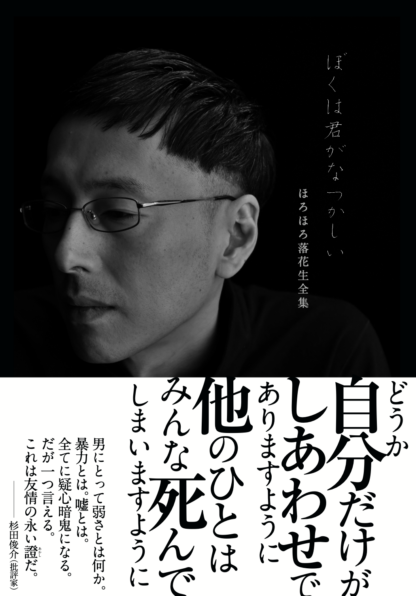
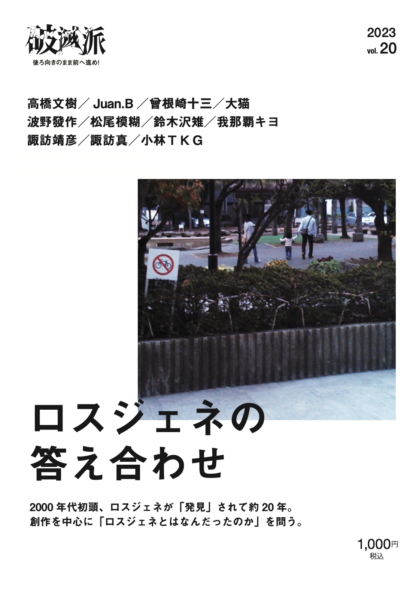
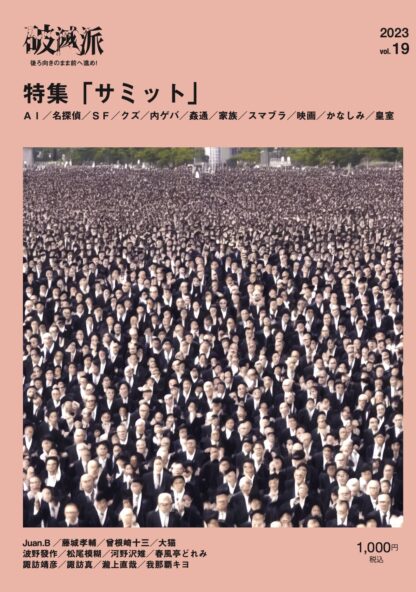
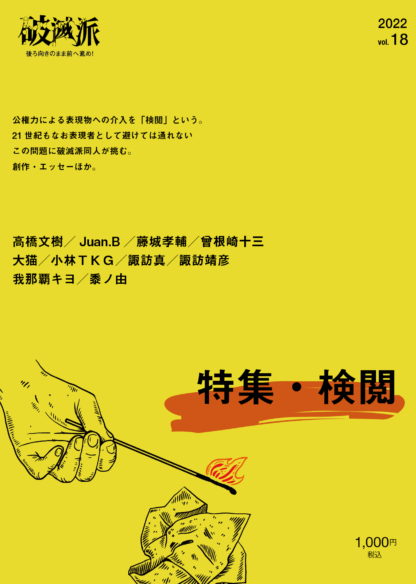
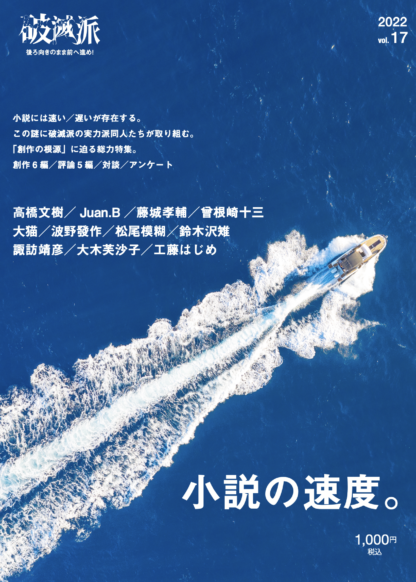













"井戸尻遺跡訪問記"へのコメント 0件