鷹橋が白いバモスを運転して国道十四号をひた走っていたのは、ひとえに彼の運営する出版社途絶派の書籍の余りを受け取るためであり、平成も初期の頃に製造されたオンボロの軽バンの荷台は余った在庫を受け取るためにスッカラカンにしてあった。印刷会社から取次の大和書店へ在庫二六〇〇冊を送ってもらい、余った四百冊あまりを大和書店から持ち帰るのだが、それもこれも輸送費を節約するためのいじましい工夫である。行きは錦糸町で首都高を降り、帰りは小松川まで下道で行くのは、わずか五百円だかそこいらの高速代を渋ってのことだった。
その道すがら、海野優斗からLINE通話があった。ハンズフリーの設定にしてあるので電話に出ると「マズいことになった」と開口一番、優斗が言った。まただ。彼が「マズいことになった」という話を切り出す場合、それはなにかしら頼みごとがあるのだが、素直に頭を下げて物を頼むということが一切できないので、長々と「それがいかにマズいことか」というネタ*1をするのだが、まとめてしまえば一行にも満たないことを彼一流の修辞でもって大袈裟に膨らましているだけなのであって、やはり自業自得のくだらない出来事が発端なのだ。
ことの起こりはこうだ。まず、優斗は九州のとある都市で同居の女性との住まいをネコの育て方で揉めて追い出された故にルンペンとなり、生活保護になった訳である。*2十一万だかの保護費から家賃や共同費を抜くと生活はかつかつだ。生意気にも県民共済に入っており、それは死亡保険金を大親友である鷹橋とその子供たちに受け取ってもらうためと嘯いている。彼がエピゴーネンしているデヴィット・リー・ロスの名言「俺はバックミラーを見ない」から大きく逸脱している。*3ともかく、優斗には金がない。そんな生活の中、今年二〇二二年のはじめの頃、生活給付金が十万円入ってきた。一昨年に給付された国民一律給付とは異なり、生活保護叩きにつながりそうなのであまり大々的に報道されなかったが、ともかく一時的に金が入ったわけだ。気が大きくなった優斗は、彼が「寮」と呼ぶ生活保護の施設に入居しているルンペン*4に金を貸してやった。優斗が入居しているアパートは生活保護者支援団体の借り上げで、ある種のサナトリウム的な施設になっているのだが、そこでの暮らしにどうも気が滅入るという若いルンペン*5がいた。名前は仮にAとしておこう。このAはどうあっても施設を出たい、一人暮らしをすれば生活を立て直すことができる、と主張するわけだが、そのナイーブな主張は一笑に付されることなく、一時の大金を得て気が大きくなっていた優斗の偽善者*6心をくすぐったのである。隙あらばB*7ぶりたい優斗は、施設に入居する被生活保護者たちにカンパしてやろうと持ちかけ、十二万円*8を集めたのだ。その十二万円で無事に一人暮らしをはじめたAからそろそろ金を返してもらおうとなったのが丁度、桜桃忌の夜半過ぎ。*9優斗は代表として――このB*10ヅラをすぐしたがるのも彼のどうしようもない点なのだが、とにかくAが一人暮らしをするアパートへ向かった。Aは「ここに金銭はあります」と云った。中身は確認しなかったが……。*11ここで優斗は気を大きくし、「パーティーと行こうぜ」とばかりに自身の金銭にて酒を買い込み、痛飲した。そして眠りこけ、目を覚ますと、Aの姿は封筒ともども消えていたそうだ。携帯に電話をしてもシカトされている状態で、連絡がつかなくなった。待っていても戻らないので翌日、再度訪問したら、持参していたバッグが玄関のノブに吊るしてあった。
「俺は本当にツいていないんだよ」
と、通話でB精神論*12をこぼす優斗の声に嫌な響きを感じた。『賭博黙示録カイジ』のようなこの話の展開を先回りして予想すると、どうも鷹橋に十二万円を貸して欲しそうなのだ。なかなか借り銭について言い出さず、マズいことになった、とばかり繰り返しているが、要は優斗の呼びかけに応じた二人の出資者*13からAが金を持ち逃げしたのは優斗のせいだということになっており、寮の管理者からも「金銭トラブルを起こしたヤツ」という扱いになった*14そうだ。結果、懲罰的に僻地の精神病院に強制入院させられる、という状況まで追い詰められたらしい。優斗がこうして自分の窮状について大袈裟、隣三件のネタについて語り、「そんなに困ってるなら金を貸そうか」と助け舟を出すのを待っているという蛇蝎のごとき習性を常のパターンでとうに見抜いていた鷹橋は「もうすぐ大和書店に着くから切るわ、あとで話そう」と通話を打ち切った。
大和書房では、途絶派の出した書籍が山積みになって待っていた。大和書店の新刊取次部の鈴本が「これみんな取次に納品する分ですよ」と示した。これから、途絶派の本が全国の書店やネット通販の倉庫に向けて旅立っていくわけだ。鷹橋は納品分以外の在庫をバモスに積み替えると、礼を言って大和書店を後にした。まだまだやることは沢山あり、残っている在庫をなんとかして売り捌かねばならないのだ。帰りは下道の国道十四号をひた走り、小松川インターから京葉道路に乗った。荷台では四百冊の書籍が高速道路の継ぎ目を拾ってかすかに揺れる。一度に運ぶ量としては大したことはないが、宅配便を使うとそれなりの額になるので、これでも節約になるのである。一時間ほどで倉庫代わりに使っている実家に着き、段ボールに詰まった書籍を運び入れた。
夕方になると鷹橋は家族と共に夕食を取る。夕食が六時からというのは鷹橋にとってはかなり早いのだが、コロナ禍になって家でのみ仕事をするようになってから受け入れている習慣だった。子沢山の鷹橋家では、四人の子供達を急かして夕飯を食べさせても一時間半ぐらいかかる。それから食器洗いや風呂の準備などして家事を少し手伝う。八時ぐらいになると再び書斎に戻り、寝るまでの仕事を再開するのだ。残る家事といえば犬の散歩で、一時間はかかる散歩の友はポケモンGOと本の朗読サービス、オーディブルだった。だが、この晩は優斗による所謂、マズいことになった攻撃が鷹橋とポケモンの息抜きを奪うのだった。
「それで結局、いくら貸せばいいの?」
また通話の最初からネタ*15を訴え始めた優斗を制する形で鷹橋は言った。優斗は「十二万円」と答えた。
「そりゃおかしい。そもそも三人*16でカンパして集めた金だろ。なんで俺が全員分を補填しなきゃいけないんだよ。内訳は?」
「まず、俺が八万五千円。で、ヤスが二万五千円で、他の一人が一万円*17」
「だったら三万五千円でいいじゃん。要はカンパした奴らが怒ってて、そいつらに言い訳するための*18金が必要なんでしょ」
「いや、それだと俺の今月の生活費がないんだよ」
「なんでなくなるんだよ。もともと給付金で入ったあぶく銭だろ? それがないと今月暮らせないってのがまず変なんだよ」
「それはさ、鷹橋君、八万五千円返ってくるはずだったからさ」
「だからそれをあてにするんじゃねえよ。カイジか。そもそも生活保護の十一万できっちり暮らせるようにしないと、東京に戻るだなんて叶うわけない」
優斗はぐうの音も出ないといった感じで黙り込んだ。優斗はいつか東京に戻るという主張を繰り返しており、それは生活保護のケースワーカーからも「労働に励もうとしないかぎり、夢みたいなこと言ってはならず」*19と窘められるほど無謀なことだったのだ。そもそも優斗が九州で生活保護を受けているのは、地方は仕事がないからとかそういうレベルの理由ではない。優斗はこの十年ほど、遊び感覚以外でまともに働いたことがなく、常に誰かに寄生して生きてきたのだ。そんな優斗が自活して上京できるなど、ケースワーカーでなくとも信じないだろう。
「だいたい、他の奴らに返す金は待って貰えばいいじゃんか。土下座するなりしてさ」
「それだと、俺が山奥の熊本脳病院に下手したら送られちゃうんだよ」
「行けばいいじゃん、熊本。ネタになるよ。その罰として精神病院にぶち込まれるって話、少なくとも俺は聞いてみたいし」
「いや、それは無理だよ」
肝心のところで顔を出す優斗の常人プラウド*20に呆れながら、鷹橋は質問を変えた。
「ヤスってやつは優斗くんと仲いいんでしょ? だったら待ってくれるんじゃない」
「ヤスは大丈夫なんだけどさ。カンパしたもう一人がガチの刑務所帰りでさ。そいつとかは無理だね」
「無理って何? ビビってんの? いいじゃん、刺せオラー! って突っ込んでけば。得意でしょ」
「いや、ホンモノは違うよ。逆に信用を重んじるしね。*21鷹橋くん」
「なんにせよ、十二万円のうちで優斗くんの金は八万五千円なんでしょ? だったら、俺が金を貸すにしても三万五千円でいいはずじゃん。要するに、偉そうにカンパ募った奴が借り逃げされたってんでそいつらは怒ってるわけだし、そいつらに渡す金だけ工面すれば済むよ」
「いや、そうなんだけど、俺もほら、生活費がさ」
「生活費って……もともとその八万五千円の出どころは、コロナ禍の給付金十万円なんだから、生活費と関係ないじゃん。保護費は毎月十一万貰ってるんだから、それでなんとかしなよ」
「諸々と引かれて手元に残るのは約五万。それに残るのは、そこはほら、君がルンペンハウスっていうぐらいだからさ。貸した金が返ってくるってなったら、そりゃもうガーッつって。みんな、返さないと餓死するから」
鷹橋は「ガーッつって」という言葉で優斗が表現したことがすぐにわかった。寮の住民は皆なんらかの依存症だ。アルコールであれ、ギャンブルであれ、薬物にしろ、依存対象に金を注ぎ込んでしまう。優斗は自分がお人好しゆえ生活保護の先輩たちによくタカられてしまうと言い逃れることが多かったが、なんのことはない、彼もまた他人の歓心を買うという人生の一大事なるイベントのために飲み代を奢ってしまうのだ。Bだから。生活保護がカツカツになるという結果だけは、入金日にパチンコ屋に走り、その残りの五万円だかの全てを失うギャンブル依存症も、居酒屋で奢ってしまうアルコール依存症も、大して変わらない。ガーッと金を使ってしまうのだ。
「とにかく、十二万円はダメ」と、鷹橋は言った。「優斗くんの取り分の八万五千円だけ貸すよ」
「いや、それじゃ足りないんだ。あいつらも金が返ってくるのをアテにしてるから」
「はっきり言うけどさ、そいつらも優斗くんが金に困ったら俺に頼ってるの、知ってるわけでしょ? だからそいつらも優斗くんを絞ってんじゃないの。コイツ*22絞り上げればお友達がお金払ってくれるってさ」
「いや、君の名前はヤスにしか言ってない」
「だから、名前知ってるかなんかどうでもいいんだよ。俺はそいつらが俺のことどう思ってるかわかるよ。馬鹿にしてるだろうね。結局、優斗くんは調子乗ってB*23ぶったせいで、俺まで舐められてんだよ」
「申し訳ない」
優斗はそれきり黙った。弁明を待っている間に、散歩中だった愛犬のブッフォンがぐっと両足を踏ん張って、見事なサイズの糞を放り出していた。
「まあいいや、じゃあ幾らだったらいいの?」
再び鷹橋が問いかけると、優斗は携帯代、共済の掛金、カードローンの返済などを一つ一つ数え上げ、「十万円!」とどこか決然とした調子で言い放った。まるで鷹橋の給金を決める雇い主であるかのような、決然である。この性向が彼の問題の解決を決定的に困難にしているのだ。
「じゃあ、八万円ね」と、鷹橋は答えた。「足りない二万は万引きでもなんでもして、どうにかしてくれる?」
「犯罪はしないけど、*24わかった」
「わかったじゃねえだろ。ありがとうございます、だろ」
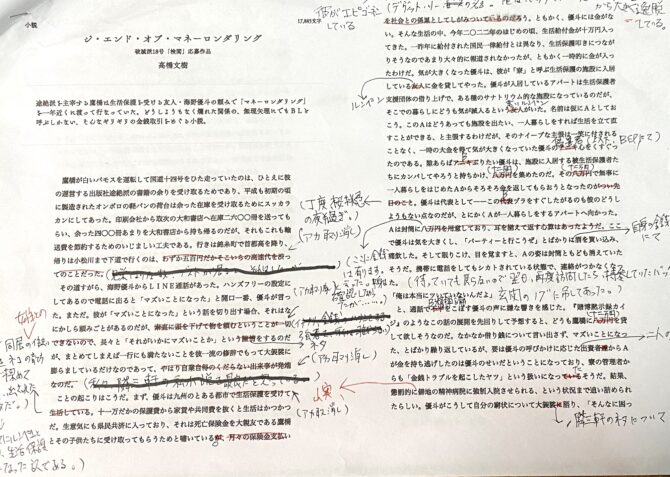























"ジ・エンド・オブ・マネーロンダリング"へのコメント 0件