私は能見武彦の運転するアウディiXに乗って、緑深い山道を進んでいた。赤く艶めいたボンネットの上を、木漏れ日が通り過ぎていく。武彦は少し濃いめに注文した季節外れのホットコーヒーをすすりながら、ゆっくりと目を閉じた。癖っ毛に覆われた彼の頭をヘッドレストが優しげに包む。おそらく、そのとき武彦の頭脳は、自分を待っている再会がどのようなものであるかについて思いを巡らせたことだろう。幾つもの回想が頭をよぎったはずだ。彼がいま再会しようとしている人との別れから、とても長い時間が流れていた。
やがてアウディiXは自動運転を停止し、マニュアルモードに切り替わった。
「私はこの瞬間が好きなんですよ」
武彦によれば、「この瞬間」とは、機械が音を上げる瞬間のことらしい。自分にも何かが残されているという、発見の気持ちがある。
——この先は行き止まりです。マニュアルモードに切り替えます。
アウディがそう言ったのは、なんのことはない、前方を落石が塞いでいるからだった。谷側の道路の幅は、なるほど、この車がギリギリ通れるかどうかというところだった。だが、ほんの半世紀前は、ちょっと慎重になるだけでこうした道をすり抜けられたものだ。武彦は静かにアクセルを踏み込んだ。二、三十センチは余裕がある。すれ違う瞬間、私の座る助手席から花崗岩質の表面がよく見えた。灰色の中に混じる白が、なにかの符丁であるかのようにその存在を輝かせた。たった数十センチ先で、と気を大きくしたのか、武彦は自動運転再開を断った。
「若い頃はまだ自動運転なんてなかったですからね。当時付き合ってた彼女とカーシェアして海に行ったら、同級生がマイカーで来た時があってね。銀色のジャガーでした。私のヨーロッパ車好きはそのときからですよ。もっとも、いまではヨーロッパなどという枠組み自体が意味をなしませんがね」
少し強めにアクセルを踏み、峠を越えると九十九折の下りに入った。何度か落石の跡があったが、幸い通れないほどではなかった。眼前を塞いでいた木々の枝々がまばらになるころ、盆地の真ん中に集落が見えてきた。とはいえ、もう廃墟になった場所だ。規則正しい草原のキルト織は、そこがかつて耕作地だったことを示していた。
ふと、武彦はアシスタントに尋ねた。
「この土地の歴史は?」
アシスタントはインジケーターをくるりと回しながら、語り始めた。
——この土地は山梨県上野原市です。縄文時代の遺跡が多く発見されていますが、弥生時代に入り、一度衰退します。その後、平安時代より都留郡と呼ばれましたが、戦国時代には国境の土地として外交問題が発生しました。江戸時代に甲州街道が開通すると宿が設置され賑わいました。特色のある地域は相模川、棡原地区です。これらの地域について説明しますか?
「いや、いい。最盛期の人口は?」
——約三万人です。二〇〇〇年代初頭に達成されました。二〇三五年に行政緩和区域に指定され、その後の定住認定者はいません。
武彦はそのまま集落の中を進んだ。何軒か朽ちたままの家が残っており、もれなくコンクリート製だった。もうだいぶ前、法改正によって、価値がないと見なされた木造建築物は行政の判断で取り壊されることに決まったのだが、石造建築物は打ち壊しの労から空家規制法の対象からはずれていた。草木の中にコンクリートの家屋が建っている光景には郷愁を誘うものがある。廃村巡りのツアーが人気だというのもうなずける話だった。
やがて、とりわけ緑の深い場所を通りかかると、そこがかつて神社だったことが見て取れた。石造建築物と同じく、宗教施設もまた取り壊しの難から逃れたのだった。
「ちょっとビデオを撮ってくれませんか」
武彦は私に向き直ると、恥ずかしそうに言った。彼は無心論者だったが、古びた神社に参るというアイデアが気に入ったらしかった。手水舎の柱に私が立ち、カメラを持った。フォロー撮影モードなので、とくに技術は必要ない。小銭などもちろん持っていなかったので、地面になかば埋まっていた玉砂利の泥を払い落とした。おそらく、賽銭箱に向かってお参りをするいい絵が取れるだろう。沈黙の侘しさに、賽銭箱の鳴る音が彩りを添えるだろう。
何度かリハーサルを終え、本番テイクが終わると、武彦は映像をチェックした。どうも、少し肩を張りすぎている。神事に赴く人間はもっと畏まっていなければならない。幾つか気になる点はあるようだったが、この時代特有の堪え性のなさが彼をもまた捉えたようだった。
「まあ、いいでしょう。公開します」
シェアボタンを押すと、アップロード完了を示すピキーンという音が鳴った。と同時に、私達の背後で物音がした。振り向くと、背後に立っていたのは痩せぎすの少年だった。肌はくろぐろと焼けており、健康的な度合いを通り過ぎていた。なにより、行政緩和地域に少年がいることは珍しい。少なくとも鹿や猪よりは。武彦は「君はどこの集落の子かな?」と興奮して話しかけた。だが、少年は聞き取りづらい言葉で返すだけだった。どうやら、神社で動画を取るという行為に対して怒っているようだ。それが宗教上の理由によるものなのか、それとも私たちが彼らの生活圏において部外者だからなのかはわからなかった。およそ、少年の言葉には論旨のようなものが存在せず、カウンセラーに恨みつらみを述べる精神病患者といった風だった。少年は散々言い募った末、私たちがカメラをしまうのを見届けてようやく安心したようだった。
「棄民と話したのははじめてですが」と、武彦は言った。「あそこまで言葉が通じなくなるものですね。驚きましたよ」
私が「棄民」という差別的な表現を改めるよう忠告すると、武彦は肩をすくめて見せた。彼のように訓練された経営者が火元になりそうな失言をすることは珍しい。
「失礼、本音は語彙に滲みますからね。しかしですね、ヨーロッパの歴史を思い出しますよ。フランス、ドイツとイタリアはもともと同じ国だったでしょう? それが分裂して一世紀も経つと言葉が通じなくなりました。それと同じことが、いまこの国では起こっているんです」
私は武彦に最新の研究仮説を伝えようとしたがやめた。最新の研究によれば、フランク王国分裂から六十年で独仏伊の言語が分かれたという説はくつがえされており、それよりも中央集権メディアの不在と政権交代による辺境方言の採用がドラスティックな言語分裂の要因であり、そもそもフランス語とイタリア語は言語学的観点からするとほとんど変わらない。
「しかしよく考えれば、フランス語とイタリア語がわかれるよりも長い時間は経っているわけですからね」
私がそう言うと、武彦は深く頷いてみせた。実際にそれよりも長い時間が経っていた。過疎化の進んだ見込みのない地域を自治体の行政管理区域から外し、徹底した機械化による監視によって国防上のリスク低減にのみ注力するという行政緩和のアイデアが実現してからもう七十年近くが経過していた。
「昔のことを思い出しまたよ」と、武彦は再び乗り込んだアウディのハンドルを握りながら呟いた。「私はまだ小さくて、東北に住む遠縁の親戚の家に家族で二週間ぐらい滞在したのです。そこには老いたお婆さんがいて——もっとも、いまの私より若いんですがね——なにか色々と話すのですが、まったく意味がわからないんですよ。ちょうどさっきの少年と同じです。ですがね、その家を去る頃にはもう話を聞き取れるようになっていたんですよ。耳が慣れたんでしょうね。人間の能力というのは不思議なものです」
武彦は盆地を横切るように運転しながら、幾つか補足した。言語の分裂という中世的状況や、対話による意思疎通性の向上、人類は時間を重ねてもあまり成長しないということ、ついには見捨てられた過疎地に好んで住み着く人々への共感などなど。いつしか車は盆地を抜け、再び林道に入った。先ほどよりも緑が深く、ひんやりとした山の冷気が換気装置越しに伝わってきた。
「でもまあそういう意味では」と武彦は呟いた。「私はこれから子供時代と同じようなことをすればいいのでしょうね」
時間をかけて共通言語を取り戻していくことはそれほど難しくないという主張を武彦は続けた。武彦が幼かった頃はそうしたことがないではなかった。強い方言を使う人は多くいたし、その方言を保ったまま社会的に成功する人も多くいた。特に武彦が子供だった頃の東北地方——いまでは地域全体が行政緩和指定された地域——などはとりわけそうだった。わけのわからぬ言葉を喋る人たちもまた、自分たちの生活や歴史や愛や正義について自分なりに語っていた。まだこの国にはそうした人々の言葉を尊重する文化があり、たとえばある言語の話者に共通の辞書が編まれもした。少なくとも、理解しようと思えばすることができる——武彦はそうした素朴な信念がまだ生き残っていた時代に育ったのだった。
*
能見武彦はこの国の歴史のある部分において重要な地位を占めている。あまり語られることはないが、計量経済学者国枝優希によってなされた統計調査によれば、武彦のなした業績は二十二世紀の日本人で四位である。彼が尽力した「医療目的以外の輸血」、「生成血液の販売」および「代替臓器の大量製造」は二十二世紀を迎えた人類にとっていまだ三種の神器となっている。あまりにも当たり前に普及しているので、我々は気付かないが、それらの技術が確立する前、人々はそのように生きていなかったのだ。
能見武彦は二〇二〇年代に隆盛を極めた医療起業ブームの駒の一つに過ぎなかった。彼がはじめての会社を作ったのは不惑を迎えた頃、二十代前半でなければ起業は遅すぎると言われた時代だった。医者向けの保険商品を販売するファイナンシャル・プランナーであった武彦は、高次晴というスポーツ医師を顧客に持ったことから、徐々に起業の志を持ち始めた。高は大学病院に所属する医師であったが、その副業としてフィットネスジムを経営していた。そのジムの売りは、当時のプロスポーツ界でドーピングとみなされていた輸血を積極的に取り入れたトレーニングだった。栄養素制御の技術を生活面から制御しようという呪術的な技術(食生活の改善・運動の習慣化)が跋扈していた時代において、体組織の置換という真理に到達した高の慧眼に武彦は関心した。高の経営するジムはマグレブ地方およびイランからの買い入れによって売血を確保したが、経営面では常に風評との戦いだった。当時は体組織に対する過剰な信仰があり、中でも血に関しての思い入れは強く根付いていた。高は自身の経営するスポーツジムをプロスポーツ界に認めさせることに執心していたが、武彦は体組織置換型のフィットネスを健康増進施設と位置づけ、厚生労働省の認可を得るよう働きかけた。推薦人を集めることのできなかった高は、武彦に株式の三十%を譲り渡すことに同意する。この後十年に渡り、高と武彦はともにグレーゾーンのビジネスを行う仲間として共に歩むのだが、その関係は高の心筋梗塞によって幕を閉じる。高は輸血を行わないまま、彼の言葉によれば「産まれたままの身一つ」のまま、五十二歳の若さで病に倒れた。武彦にとってわずかに年上だったにすぎない高が当時の三大疾病にたやすく捉えられたことは、自説の正しさを裏付けた。体組織の交換は生物にとってもっとも効率のよい延命治療であり、人類が唯一血眼になる価値がある、と。高は臨終間際、株式のさらに二十%を武彦に譲渡した。
それから五年に渡り、順調に事業を成長させていた武彦に契機が訪れた。二〇三二年に開催されたティクリート会議である。二十一世紀の幕開けから世界を不安に陥れていた中東の混乱は、トルコおよびイランを盟主とする中東砂漠会議の成立によってようやく幕を閉じた。この和平会談によって、イランからの血液供給量がわずかな間に減ることも明らかであり、事実三年の間に公式供給量は三十分の一になった。もしなにもしなければ事業は跡形もなく消え去っただろうが、武彦はこのわずかな間に生成血液を実用可能な段階まで仕上げていた。
生成血液は前述の国枝優希によれば、武彦のもっとも重要な功績の一つである。体組織置換技術においてもっとも簡素な血液を人工的に作るというアイデアは、科学史的にいえば中国の謝永久によってもたらされたことになっているが、より正確にいえば、大学生の頃に謝がアルバイトをしていたのが武彦の経営する研究施設だったのである。ティクリート会議の四年前から、武彦はすでに生成血液のアイデアを若者たちに託していたのだった。謝の作った生成血液はRNSの稚拙な模倣を大量に生成して破棄するという冒涜的アイデアによって学術的にはながらく無視されてきたが、発表から六十七年を経た一昨年、ついにノーベル医学賞を受賞した。中国にとって念願の百人目のノーベル賞受賞者であった。
生成血液の実用化からわずか九年後、武彦の経営する健康増進施設モーティックは新たな子会社として日本臓器を設立する。プレスリリースで発表された写真は、その扇情的なビジュアルでセンセーションを巻き起こした。薄暗い工場の中、液体に浸された赤黒い臓器が艶かしく光りながら白衣の青年達による入念なチェックを受けている。この写真は人々の心を確かにざわつかせたが、もう反対運動などは起きなかった。この時代、二〇六〇年代にはすでに体組織置換技術によって恩恵を得ている人の方が多かった。半世紀前の人々が新しい機械の出現に心を躍らせたように、この頃にはもう、新しい体組織こそが人々の心を躍らせたのだ。新しい臓器はついに人々を癌の恐怖から救った。これにより、先進一七カ国の平均寿命は百二十年に伸びた。事実、武彦はその生きる実例である。彼は今年、百二十歳になる。彼はほんの三十年前なら免許を取り上げられた年齢だ。
*
アウディiXはその艶めいた赤いボンネットに木漏れ日を映しながら、緑深い林道を進んだ。これまでは自動運転が挫折する瞬間を心待ちにしている風だった武彦は、もうすでに深い感情の襞へと入りこんでいるようだった。彼はいま息子に会いに来ていた。武彦はその生涯のほとんどを彼の会社モーティックの繁栄に捧げた。多くの先進的ビジネスマンがそうだったように、彼もまた家庭を蔑ろにした。すべてをかなぐり捨ててでも戦わなければいけない戦いが彼にはあり、幸せな家庭にとってそれは無用なものだった。いや、彼の息子である能見遥にとって、それは単なる家庭の不和ではなかったかもしれない。単に父親が忙しく、家庭を疎かにしたというだけではなかったろう。
遥は武彦が五〇歳の時に生まれた息子で、武彦にとっては三男にあたった。当時はまだ「遅い子供」という扱いになったが、武彦は遥を可愛がった。ほとんど公知の事実として、遥は不実の子であり、武彦が経営するフィットネス・ジムのトレーナーとの間にできた子供だった。かなり明確に、武彦は「子供は健康な母体から生まれるべきである」という信念を抱いており、彼の妻もそれを忌避しなかった。トレーナーである女性は、水泳のオリンピック候補になったことがあり、材料の新鮮さという観点から武彦に選ばれ、当時としてはかなり屈辱的だった複数の母の役割を引き受ける代償に、フィットネス・ジムの取締役となった。
遥は中学校の頃からイギリスに留学し、イートン・カレッジに入った。成績はすこぶる良好で、信じがたいほど手足の長かった母親譲りの体格を持っていた。アジア人に対する蔑みの目を十分にはねのけるだけの資質を持ち、あらゆる偏見から自由な人気者となった。とりわけ、優しく目尻の下がった切れ長のアーモンドアイは、誰からも好かれるほど十分にチャーミングだった。遥は17歳でマサチューセッツ工科大学への飛び級を決めた。専攻は遺伝生物学——まさに父親の仕事の主力——になるはずだった。
大学へ一年通った後、遥は休学をしてビジネスを始めることになる。それは武彦の望んだような方向と少し異なり、遺伝農学だった。遥は父親の申し出を断り、ベンチャーキャピタルから六〇〇万ドルの出資を受けると、遺伝子工学を利用した大規模農業を行う会社を立ち上げた。当初はネスレやJTといったコングロマリットの前では無力と馬鹿にされたが、苦戦しつつもそれなりに拡大を見せ、難民キャンプに提供するパッケージの工夫など、メディアを魅了する手法で売り上げを拡大していった。そして、創業からわずか二年でIPOを果たすのだが、驚くべきことに創業者である遥は経営陣から退いた。そして、MITも退学して、姿を消すのである。
「遥からは明確に絶縁されたというわけではないんですがね」
と、武彦はアウディiXのシートに深く腰をかけながら、眠りにつくような表情で呟いた。一二〇歳という高齢でなお若々しさを保つ彼の魂の殻とでも呼ぶべきものがポロポロと剥がれ落ちていくようだった。
「遥は高校生の時分まで柔道をやっていたんですよ。それが、椎間板ヘルニアになりましてね。練習をしたらその分栄養を補給しなければいけないのだから、私は生成血液を使うよう勧めていたのです。しかし、遥はなぜか意固地でしてね。結局手術が必要になるほど悪化しました。手術は成功しましたが、その後の成績は芳しく無く、三年生の全米予選では州大会ベスト4という記録でした。私は敗北に打ちひしがれた彼を叱りました。なぜ親のいうことを聞かなかったのだ、とね」
武彦は腕組みをすると完全に目を瞑った。アウディのタイヤがアスファルトをなぜる静かな音だけが響いた。
「遥は二十歳のとき、突然休学を申し出たんですよ。ボランティアとして世界を回りたいと言って。当時はそれが大学生にとって普通のことでしたから、私は快諾しました。しかし、それっきり戻ってきませんでした。私はタイの米国大使館に連絡したり、色々と手をつくしましたが、結局はいまに至るまで見つけることはできませんでした。いや、正確には探そうともしませんでした。五〇年も会いに来なかったので……なにもなかったというわけではないのでしょう……ああ、インターバルだ」
「インターバル」という言葉を発した直後、武彦はあくびを噛み締め、寝息を立て始めた。彼がいま手がけている定期的な睡眠を管理する睡眠拍動がアクティブになったらしかった。
私はインジケーターに到着予定時刻と武彦の起床時間との差分を尋ねた。インジケーターはくるりと回ると、その時間がマイナスであることを告げた。私はその方が良いような気がしていた。武彦が五十年の時を経て息子と再会する前に、私があれこれ尋ねるべきではないような気がしたから。
アウティiXはところどころ禿げたアスファルトの林道に差し掛かった。このすぐ先に能見遥の築いたコミューンがあるはずだった。盆地から再び信州の山深い地域へと向かう隘路のような場所に集落はあるらしかった。利水がゆきとどき、よい米が作られる。打ち捨てられたウィスキーの蒸留所が、コミューンの中心的な施設となっている。遠くから蒸留所を眺めると、木々の間から覗く尖塔が古びた中世の城のように見えた。私も美しい緑の写真を見たことがある。時が止まった緑萌える美しい森で、能見遥はゆっくりと死のうとしていた。
蒸留所に停車してからも武彦が目を覚ます気配はなかった。あるいは、その惰眠が彼なりの逃避なのかもしれなかった。車内には武彦の寝息しか聞こえず、冷たく湿った森の空気がそっと私達を包んでいた。私は車を降りると、蒸留所の入り口へ向かった。ファサードには遥の作ったコミューンの名称「人生観測隊」が大きな枕木に刻まれていた。人の生き方はそれぞれだな、と私は月並みな感想を抱いた。世界を変えたといっていい実業家の息子として生まれ、また自信もその才能と地位を受け継いでいたにも関わらず、それを全て捨ててしまうような人間がこの世には存在するのだ。
「なんかした?」
ファサードの前で立っていた私に少女が話しかけてきた。「なにか要ですか」と訪ねているのだろう。赤いスウェットに身を包んだ彼女が向ける自警的な眼差しは、このコミューンがこれまで永らえてきた数十年に築いた心理的城壁の硬さそのものだった。
「能見さんという方に会いに来たのです」
少女は「ハア?」と苛立ち混じりの声を上げるとファサードの奥に消えていった。ほどなくして、ファサードの奥から三人の青年が現れた。青年たちは私の目的についてかなり警戒しているらしく、色々と問いただした。おそらく南米の血が混じっているらしいスキンヘッドの青年は腰に山刀をぶら下げていた。結局、私はその青年の暗い目の輝きに怯え、正直に能見遥の父が彼に会いに来たことを暴露してしまった。
「へぇ、それはめでたい!」
マチェーテの青年はそう叫ぶと、すぐに「ジージ呼んでこよう」と走り去った。しばらく経つと、ファサードの奥から痩せ細った手足の長い老人が姿を表した。ジージと呼ばれたその老人こそが能見遥であり、その姿は私に強い違和感を覚えさせた。Tシャツの裾から覗く筋肉の落ちたしみだらけの腕、麦わら帽子の下に隠れた白髪、そして何よりも深い皺の刻まれた顔。たるんだまぶたの下に落ち窪んだように見える暗い瞳は、父である能見武彦の若々しい表情と符合しなかった。どう控えめに考えても、こちらの老人こそが能見武彦の父であるとしか思えなかった。
「ようこそいらっしゃいました。能見遥です」
遥は麦わら帽子を脱ぐと、ほほ笑みを浮かべた。
「はじめまして。ハジメ・ウィットモアと申します」
しばし沈黙が続いたが、私は今回が取材であることを正直に言っていいのかどうか悩み続けていた。それよりもまず、武彦が自分から言うべきではなかったか。その逡巡のうちに、私は背後に武彦が立っているのを認めた。眠りから目覚めたらしかった。武彦はゆっくりとこちらに歩み寄ると、私の隣に立ち「能見武彦です」と告げた。遥の表情は微動だにしなかった。老いの暗闇の中へ感情のすべてを押し殺してしまったように私には見えた。
「遥、父さんだ」
武彦もまた、私と同様の不安を抱えたのだろう、確認するかのように宣言した。いや、彼の不安は私よりもずっと強かっただろう。自分よりもずっと年老いた息子を前にしてしまったら、自分が父親なのだという信念は容易に揺らぐ。
「はい、お久しぶりです」
遥はそう答えると、麦わら帽子をさっと上げた。薄くなった頭髪が汗で張り付き地肌が見えていた。
「お前に謝りたくて、来たんだ」
再び武彦が言った。遥は「謝る?」と問い返した後、ふっと微笑みを浮かべた。
「そんな必要はないですよ。私たちは親子ですから」
再び表情を老いのベールに隠してしまった遥の言葉からは、どんな感情も読み取れなかった。武彦は明らかに狼狽していた。泣き出しそうにも見えた。父子の間に流れた空白の五十年がその重みで武彦を窒息させようとしていた。
「いまから孫が初めて井戸を掘るんです。よかったら見に来ませんか。あなたにとっても曾孫ですし」
そう言うと、遥は振り返って歩き出した。足を引きずった歩き方で、おそらく彼は腰が悪いままこの歳を迎えたのだった。
私達は遥について蒸留所の裏手にある丘を下った。一段低くなった土地には何人かが遥待っており、その中の一人、十五歳ぐらいの少年が筒状の器具を持って神妙な面持ちで座っていた。白いタンクトップで、そこから覗く腕は少年らしく頼りない筋肉で覆われていた。
「ジージ、やるぜ」
丘を降りて喘いでいた武彦がしゃがみ込むと、少年が持っていた筒状の器具を地面に刺した。そして、尻尾の部分にあるゼンマイ式のハンドルを回し始めると、先端が少しずつ地面にめり込んでいく。カリカリと土を削ぐ音がする。
「ここでは、こうやって井戸を掘るようにしてるんですよ」と、遥が言った。「それが大人の第一歩ということです」
しばらくすると、少年はハンドルを巻く手を止め、器具の中央部分を引き抜くようにした。すると、削られた土がドサッと出てくる。土を捨てると、少年は再びハンドルを回した。
「どれぐらいで掘れるんですか」
私が尋ねると、遥は「さあ、もしかしたら水脈はないかもしれんしね」とこともなげに答え、いたずらっぽく笑った。
「水脈の見つけ方なんて、聞けばわかるんだが、聞かんようにして掘り当てるのがここの流儀なんですわ。まあ、そこらじゅう地下水通ってますから、多くても三回掘れば当たりますよ。掘れんかったら大人になれんということです」
武彦は相変わらず黙ったまま、曾孫の井戸掘りを眺めていた。
「父さんも、よかったら座りませんか。積もる話もありますし」
武彦は息子に促される形で隣にしゃがみこんだ。なにかを話しているらしかったが、私からは聞こえなかった。武彦がなにを感じ、何を思ったのかは、後から彼に尋ねればよかった。いまはただ、五十年の空白を埋める会話——もしかしたらそんなものは不可能なのかもしれないが——に水を差すつもりはなかった。二人は視線を合わせず、控えめな会話を続けていた。遥は穏やかに微笑を浮かべ、武彦は感情を抑えるような苦しげな顔をしていた。
二時間ほど経った頃、少年は井戸掘り器を引き抜いた。日が少し傾き始めていたが、まだ作業は続けられるほどには十分明るかった。
「ジージ、ここ、出ないじゃろ」
少年は遥に尋ねた。
「まだわからんぞ。出るかもしれん」
「あとどんだけ?」
「知らん。出ないかも知らん」
「なんじゃーもー」
少年は地面にひっくり返った。そして、仰向けのまま息を整えると、再び立ち上がって井戸掘りを再開した。濡れた背中にはびっしりと泥がついたが、作業を続けるうちに白く乾いていった。
そのまま暗くなり、その日の作業は終了となった。これ以降、少年の井戸掘りが見守られることはない。彼はたった一人で井戸を掘り続ける。時間の工面も自分で行う。勉学の合間や遊びの誘惑など、生きる上で訪れるすべての合間を縫って井戸を掘り続け、見事掘り当てた時に祝宴が開かれるそうだった。
武彦と私は夕飯の誘いを辞し、再びアウディに乗り込んだ。車に乗る直前、武彦と遥は短い握手を交わした。
東京に戻るまでの三時間を私はインタビューにあてるつもりだったが、聞き出せたことは多くなかった。武彦の顔に浮かんでいるのは、再会の喜びというより、深い苦悶だった。
「あいつがね、言うんですよ。愛しているものを数えてくださいって、それがあなたのすべてですって。どういう意味か、わかります?」
別れ際、武彦は私に尋ねた。私は「わからない」と答えた。いや、正確にはそのままの意味だと思ったのだ。そこに付け加えるべき言葉は何もなかった。武彦はなぜ、それをわからないと思ったのだろうか。結局、その答えを聞く機会は訪れなかった。武彦が自ら命を断ったからだ。
*
能見武彦は私に死後予約送信のメールを残している。あの短い父子の再会の中で、遥の余生が残り少ないことを知った彼は、もう自分が生きているべきではないと悟ったそうだ。人類の寿命というものに対して画期的な行いをした彼が、「親が死に子が死に」といったレベルの感傷で命を断ったという事実は、驚くべきことだ。そのメールには葛藤や後悔、深い悲しみ、無力感といった、若者のすべてが書いてあった。その一節を引用する。
人は役割の変化でしか成長しない
以上で、能見武彦に関する報告を終わる。偉大なる一人物の最後はこのようなものであるのかもしれない。だが、それとはまた別の何かが存在しているような気もする。武彦が自分の人生を間違っていると感じたであろうこと、そして、自分がもう生きていてはいけないと感じたであろうこと。単なる自己処罰感情とは異なる、ある種の目的意識のようなものが人類には存在しており、私たちはそれを克服していないのではないだろうか。





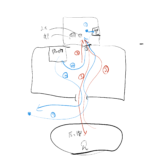
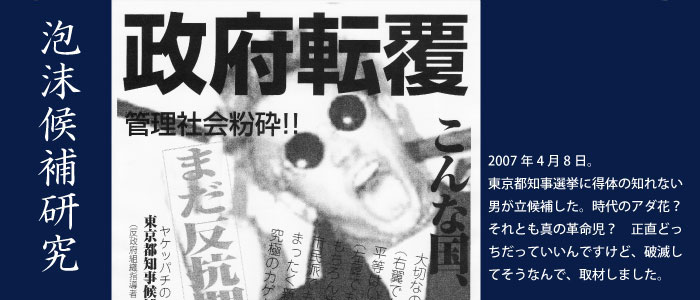




















"若者のすべて"へのコメント 0件