Prologue……前‐テクスト
これは血のことに関する小説だ。いつも頭の片隅にあった、遠い血のことについての。
血のことについて書こうとする途端、僕はある根源的な問いの前で立ち止まってしまう。血とはいったい何なのか? それは何を意味しているのか? その問いはあまりにも根源的すぎて、頭の中に暗い墨を注入されたような気分になる。血のこと?
答えなんてない……などと、物分りのいい答えで終わらせて、遊びにでも行きたくなる。面倒なことは誰だって嫌いだ。でも、遊びに出ようとヴァンズのスニーカーに足を突っ込んだ瞬間、僕は思い出す。いやいや、こうじゃない。こうやって、血のことは語られなくなってしまうんだ。
その答えづらさはたぶん、血のことがいろんな意味で使われるからだろう。陰惨なことや、遺伝に関すること、崇高なことや、また宿命について。
だから、こんな曖昧な結論をつけても文句は出ないだろう――血とはどうやら、いくつかであるようだ。追い詰めることのできる唯一ではなく、捉えきれないいくつか。
さて、そういう性質を持った血のこと、それも自分の血のことについて書くとは、言うなれば、「完璧な自伝」を書くということでもある。「単なる自伝」ではなく、「完璧な自伝」。
人は自分の行為を選びとり、その集積が個人的な歴史となる。そして、それを再編集すれば「単なる自伝」ができるわけだが、実はその完成の向こう側に大きな分水嶺がある。それが血のことだ。自分ではいかんともしがたいもの。与えられたものであるがゆえに選択の余地などなく、それでいながら、その後の選択のほとんどを決定してしまっているもの。
本当の意味で自らのすべてを書きたいと思うのなら、「単なる自伝」だけでは間に合わない。出生に始まる個人的な歴史を書き、そしてまた、その前史である血のことを書かなくてはならない。そうやって「完璧な自伝」ができあがる。うんざりするような道のりではあるけれども。
ともかく、血のことについて書かれたこの小説もまた、それ自体の前史からはじめなければならない。要するに、どうしてこの小説がこうして書かれつつあることになったのかという歴史。
血のことはいつもいくつかだから、何から書き出すか迷うところだ。
ここは一つ、昔ながらの習慣に従うことにして、語り手の自己紹介といこう。実際、この小説は語り手であるこの「僕」に多くを因っている。「僕」とは誰であり、どうして「僕」はこの小説を書くことになったのか――こういった古典的な前口上の必要性は、わりと馬鹿にできないものだ。
○「僕」とは誰か?
Call me grave digger. ――僕のことは墓堀り人と呼んで貰おう……と、ハーマン・メルヴィル風に書き出したいところだが、それは時期尚早というものだ。「僕」とは「二十世紀の墓堀り人」を目指して目下奮闘中の語り手に他ならず、実際に「僕」がそうであるかどうかは、この小説の完成を待たねばならない。もしもこの小説が成功に終われば――「小説の成功」がどんなものか、その問に答えるためだけでもゆうに一冊の本が書けてしまうが、とにかく、その暁には、「僕」が「二十世紀の墓堀り人」となった、ということになる。言い換えれば、これは「二十世紀の墓堀り人」を目指す「僕」の成長小説とも言えるだろう。
以上、語り手としての「僕」について説明したので、もう十分のような気もするけれど、念のため、簡潔に特徴を記す。
二十六歳の日本人男子。二十一世紀にもなったというのに前世紀の遺物である小説を書いている稀有な人物。著書は今(二○○五年末現在)のところ、数年前に出した一冊のみ。小説など時代遅れだ、そろそろ資格でも取るか、と斜に構えつつ、絶対唯一のものとして信頼を置いてもいる。いわゆる「古典」が好きという権威主義的なところがあり、現代小説など見向きもしない風だが、実際は文壇事情を気にしてちょくちょく目を通している。
生来の健康体ゆえに、無遠慮で突き放したところがある。文章から得られる印象ほどには不快な人物ではなく、いままで付き合った女の子の写真をすべて取っておくようなナイーヴな一面もある。どんな人間かが想像できない場合は、任意の特徴を与えてもらってかまわない。あらゆる人は取替え可能だと思っており、その原則が自分にも適用されうることを意にも介さない人物。
これだけではまだ憶え辛い、という場合を危惧して、さらに外見的特徴も挙げておく。
まず一点。常にボーダー柄を身につけている。「僕」の衣服はどれか一つが必ずボーダーで、一見して見当たらない場合は、パンツか靴下、あるいはアンダーシャツがボーダーである。ボーダーは「僕」にとって一つの宣言であり、祖母から受け継いだ「縞状力学」を示すものである。「縞状力学」については後述する。
もう一点。かつて「僕」は自分のパブリックイメージを確認するため、友人に「俺を主演に映画を取るとしたら、どんな役柄にする?」と尋ね回ったことがあるが、十三人中八人が「殺し屋」と答えた。また、高校時代、物理実験室へ向かって廊下を歩いていただけなのに、同級生女子が「なんか怒ってるの?」と尋ねてきたことがある。これらのエピソードからわかるように、「僕」は良く言えば精悍、悪く言えば恐い顔をしている。とりわけ、少し三白眼気味の目は鷲のように鋭く、冷たい。
以上の二点が映画的(=小説を読みなれていない人にもわかりやすい)特徴である。
なお、正直にいうと、「私」という一人称を名乗るか、本名で三人称として書くか、そのどちらかにしたいのだが、それは文学的現状を考えるとあまり文学的ではない――つまり、「今っぽくない」ので、「僕」は「僕」になった。
○なぜ小説を書くことにしたのか?
作家は最後の仕事である……などと真面目に信じ込んでいるわけではないけれど、有り体にいえば、「他に何もすることがなかったから」の一言につきる。
僕は長い間、というより、生まれてからずっと、みんな(=身の回りの五、六人)がどうやって生き方を決定しているのか、不思議でならなかった。虚無主義者というわけではない。僕はよく人から無感動といわれるのだが、実はそうではなく、わりとなんでも面白がる質である。
仕事としては、ほんとうになんでもよかった。演技(俳優、教師、ホスト)でも、操作(機械工、音楽家、写真家)でも、移動(ツアーコンダクター、探検家、ゴルファー)でも、整理(経理事務、清掃業、葬儀屋)でも、友達ごっこ(飲食業、営業、政治家)でも、離脱(フリーター、僧侶、冒険者)でも……。
こんなことを書くと大多数の人に怒られるだろうし、また実際に何人かの友達を怒らせもしたのだが、ほんとうにそう思うんだから仕方がない。僕から言わせて貰えば、ある特定の時期(学校の卒業だとか、貯金の切れる期日だとか)に追い立てられて、用意された選択肢に逃げ込んでしまえば、逃亡と引き換えの生き辛さがあるのは当然だ。人生のすべての選択に取り返しがつかないということは、小学生だって知っている。慎重に慎重を期さねばならない。
ともかく、僕がいくつになっても「なんでもいいや」と思ってしまうのは、生来の飽き性が原因だった。つまり、どれもちょっとずつ体験したかったということだ。実際に、僕は色々なバイトに携わり、この仕事は大体こんな感じか、とわかった瞬間に辞めていた。
これは致命的な欠陥である。高度資本主義経済の現代社会において、どのジャンルも職業にするためにはある程度の専門化が求められた。マックス・ヴェーバー言うところの「天職」だ。
そうはいっても嫌なものは嫌、何とかして天に唾する方法はないか――そう考えた僕が辿り着いたのは、小説を書くことだった。
大学に残って文学教授になるという方法も考えたが、やはり小説でなくてはならない。学術論文というのは、参考文献がどうたら、引用元がどうたら、翻訳語の選択がどうたらと、こまごました制約の上に成り立っている。おいそれとテーマを変えることも難しい。仮にも教師である以上、「法学部に入れなかったから文学部に来たんス」なんていう偏差値足らずの非文学的学生も相手にしなくちゃならない。
その点、小説は自由だった。小説は言葉という漠然としたもの以外、何も求めなかった。「手を変え品を変え」という点において、小説に勝る表現技法は一つもない。
また、潰しが利かないという点も気にならなかった。新人賞受賞者が有頂天になって会社を辞めてしまい、悲惨な末路を辿るというのは文芸の世界でよく囁かれる悲劇だが、僕はそもそも悲劇だと思わなかった。これからの時代、労働者の使い捨てはどんどん増え、その見返りにバイト採用が増えるだろう。身命を賭して辛い正社員になるぐらいなら、死なない程度にバイトをしながら小説にすべてを捧ぐ、という生き方にシフトしてしまった方が辛くはない。人生で一番辛いのはやりたいことがないということだ、たぶん。それに、フリーターを続ければ、それなりに習熟度は上がるものだ。どの職場に行っても、一流の非熟練労働者として働く、というような。
また、僕は経済的な生い立ちからも、そういう生活に耐える自信があった。「幸い」といっていいのかはわからないが、僕は幼い頃から貧乏で、親子三人で川の字で寝た経験もあった。自慢じゃないが、一度も金持ちになったことはない。貧乏慣れしているのである。
貧乏さえ恐くなければ、好きなことだけやって生きればいい。そんなこんなで、甘い考えもあるにはあったが、僕は「小説を書く」という行為を人生のベスト・チョイスとして選び取った。
○なぜ小説の題材として「血のこと」を選んだのか?
一度でも創作じみた行為に挑んだものならわかるだろうが、徒手空拳の苦しみというものがある。
僕は小説家になると決めてすぐ、小さな賞を取った。かなり順調な滑り出しだったといっていいだろう。その癖、僕はそれを驚きもせず、「まあ、こんなもんだろ」と本気で思っていた。
はじめはポンポンと作品ができたが、それらは立て続けにボツを食らった。三年ほどが過ぎ、僕はついに作品の構想が出づらくなっているのを感じた。それまでは始めから終わりまで滞りなく沸き出た小説が、喉に引っかかった痰のようになったのである。
それでもまだ書き続けたが、ついにあの死屍累々の壁が目前にあると気付いたのである。「書くことがない」と書かれた巨大な壁。
こうなると自由が一番苦しい。小説には何を書いてもいいはずなのに、それができないのだ。書くべき唯一のことはもう「書くことがないということ」しかない――などと、才能のない作家志望者が十人いたら十人は思いつきそうなことに取り組むこととなった。もちろん、それは何十年も書きつづけてようやく到達する境地で、僕の手には負えなかった。僕は八方塞がりの中で茫然自失していた。
無為に日々だけが過ぎていく中、ある編集者は僕に向かって「小説書きたいだけなら、ホームページでも作って発表すればいいじゃないか」といった。もっともである。
しかし、もしも僕がキャワイイ女の子だったら、彼はそこまで見も蓋もないことをいわなかっただろう。それは常に、どんな作家にだっていえる言葉だからだ。世の中には、いってはならないことがいくつかある。反戦論者の僕でさえ、ミサイルを扱う某M菱商事に努める友人を「死の商人」呼ばわりしたことはない。
これは事実上の引退宣告だった。その癖、彼は僕に年賀状を送ってきたりするのだ。はたして僕を売り出す気があるのかないのか、まったくわからないまま、僕は彼に小説を送り続けた。
大衆時代に文学を志す人間は、すべてその類のくびきに繋がれている。僕はひとまず(ひとまず!)その苦しさから逃れようと、何か売れる小説は書けないか、と画策するようになった。そんなことをしても、自分らしさを捨て、ちらちらと脇見をするようになるだけだ。キャッチーな特徴もなく、かといって大衆にも媚びきれず、得体の知れない合成獣そのものである。結果として、僕は薹の立った新人として煙たがられている。「またぶ厚い原稿持って来やがった!」という具合に。
とはいえ、努力というものはそれほど恩知らずじゃない。費やした分だけ返ってくるものがあるのだ。
僕が見出したのは、私小説の持つ底力だった。
小説の技量というものは、時間とともに向上していく。たくさん読み、たくさん書けばいいのだから。が、そうではない何か(編集者はいつも「何かが足りない」という)を獲得するためには、その作家にとって切実なもの、のっぴきならないものをこめなければならない。一番いいのは、「自分」という自分にとっても最も切実な存在について書けばいいのである。
とりわけ、出自に関するハンディキャップのようなものがある作家は図抜けていた。いかにも、「書くべきこと」という気がする。それはアメリカを代表する作家の多くがユダヤ人だということでもわかるだろう。
どうやら、キーワードは血だ――僕はそんなことを考えるようになった。とはいえ、自分の血族に凄い人がいたという話など聞いたことがない。方針は決まったが、現状は好転していなかった。
それでも、あまり思いつめない性格が幸いしてか、すぐに逆転の発想を編み出した。「書くべきこと」を見つければいいんだ。そして、僕は自らの血にのっぴきならない部分、書かれるべき部分を探すことになった。
○「血のこと」とは具体的に何か?
いくつかである血のことを一言でいうのは難しいが、それはある一人の人物に深く関わっている。「宗おじさん」だ。
彼は僕から遡って、母方の大伯父にあたる。つまり、祖父の兄だ。祖父は五人兄弟の末弟で、一つ上の兄ともども出征せずに済んだが、二番目と三番目は戦死してしまっている。曾祖父もまた出征せずに済んだけれど、戦争のゴタゴタで飢え死にした。曾祖母は戦後すぐに病没している。つまり、先の大戦を生き残ったのは、長男の宗おじさんと四男、そして末っ子の祖父だけだった。
彼のことを僕が知ったのは、まったくの偶然による。というより、それは仕組まれた偶然だったというべきだろう。
そもそもからして、僕は祖父が五人兄弟だということを知らず、四人兄弟だと教えられていた。上の二人は戦死してしまい、下の二人だけがかろうじて生き残ったというわけだ。祖父の一つ上の兄とは交際も多く、お年玉を貰ったこともある。てっきり、うちは親戚仲がいいと思い込んでいた。つまはじきにされていた人間がいたなんて、思いもよらなかったのである。
ひょんなことから知ることとなり、そしてまた、決して語られることのなかった長兄について、僕は大いに興味を持った。これは何かあるぞ、と。
もちろん、血のことはそれで終わりではない。何せ、「完璧な自伝」でなくてはならないのだ。他にも色々あるのだが、それは後述することとしよう。
さて、これでこの小説の前史は終わりだから本編に入ろう……といいたいところだが、そうもいかない。というのは、あくまで私見だけれども、小説とは長い言い訳に他ならないからだ。これから僕が繰り広げるのは、「この小説がどれほど読むに値するか」という長大な言い訳であるだろう。その根拠としては、僕が四項目にわけて挙げた「この小説出生までの歴史」つまり「この小説が書かれてしまったことへの言い訳」に補遺として加える形で、第五項目として書いてもいい。いやいや、出し惜しむまでもない。これは僕の小説なんだから。書いちゃえ。
○補遺?
これまで僕は何度か「書くべきこと」という言葉を用いてきた。しかし、正直にいおう。僕はカントのいうところの「仮限的命法」を信じない。「書くべきこと」などない。
たとえば、ある小説家がいたとしよう。差別的な待遇を受け続けた昏い血を引く者だ。彼はそのことについてどうしても書かずにはいられず、そして、実際に書いた。その小説群は評価された。
だが、真相はそれと少し異なる。彼は血を同じくしない。かろうじて、家族というか、地を共にしただけだ。だが、彼は地を血にまで昇華させた。それがまるで「書くべきこと」であるかのように見せるだけの技術を身に付けた。
小説の良し悪し――いや、散文の良し悪し――いや、言葉の良し悪しは、それがどれほど言い訳に長けているかによる。「この言葉は聞くに値しますよ」という言い訳。この意見に反対する人にも何度か出会ったことがあるが、そういう人は「言い訳とはなんなのか」という根源的な問いについて考えたことがないのだ。まったく言い訳に聞こえないのが、最良の言い訳なのだから。
さて、「補遺?」などという蛇足を付け加えた正直のついでにいってしまおう。僕はすでに言い訳に向いていない。自分で自分の隠していた戦略を明かしてしまったからだ。ほとんどの戦略は、バレていないときにだけ効力を発揮する。
だが、本当に真摯な書き手ならば、そうするのではないだろうか。手の内がバレているなど、大いに結構。世界のホームラン王である王貞治は、「王シフト」なるものをしかれて警戒されたその右方向に、なおホームランを叩きこんだではないか。僕もまた、そうすべきだ。
なぜというに、もうすべての小説は書かれてしまっている。まだ書き加えることがあるとすれば、すべてが終わったあとから始めなくてはならない。
――(続く)



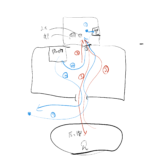
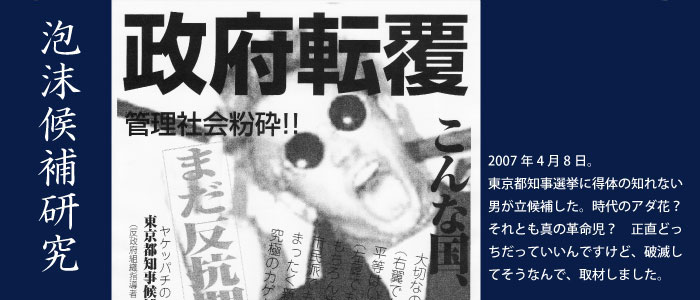



















"方舟謝肉祭(1)"へのコメント 0件