はじめて恋人ができたのは、高校生の頃だ。同じ学校のクラスメイトだった。サルみたいなつんつるてんのショートカットで、同級生からはよくからかわれていたが、実は女女した身体つきで、性格もジンベイザメみたいに穏やかだった。「ぼく」と彼女はお互いをどう扱っていいかもよくわからなくて、まごついてばかりだった。素人臭い計画を立てては、身体中しゃちほこばって実行に移した。デート一つでも、それは大事件だった。
やがてセックスをするチャンスが訪れた。父は出張で家を空け、一軒家にぼく一人だった。彼女は親に適当な嘘をついて泊まりに来る。そういう計画だった。
無事ことを済ませると、安心感から、ぼくは猛烈な自分語りを始めた。今思えば、あれは若さゆえの暴走だったのだけれど、そうする必然性を感じていた。彼女も彼女で、あまり自分のことを語らないぼくが話してくれたことが嬉しかったらしく、「もっと話して」と先をせがんだ。ぼくは笑いながら凄惨な家族史を話した。
「お母さんとかお姉ちゃんってどんな人だったの?」
ぼくは興奮の極地に達した。裸のままの彼女をつれて一階に降り、仏間へ通した。彼女は少しびっくりしていたが、線香をあげてくれるよう頼むと、面白がって応じてくれた。少し興奮もしているみたいだった。
「なんか罰当たりだね」と、彼女は笑いながら言った。
「そんなわけないだろ。うちの母さんも喜んでくれるよ。息子の晴れ舞台なんだから」
「じゃあ、それが晴れ姿?」
彼女はぼくの裸を指して、笑いを漏らした。ぼくはわりかしまじめな顔を作り(というより、本当にまじめな気持ちだったんだが)、「生まれたまんまの姿だろ」と答えた。
それから、アルバムを見てほしくて、押入れから引っ張り出した。赤い皮の装丁が杜の写真だけを集めたもので、母の写真は緑皮の装丁のアルバムに家族の写真として収められていた。彼女はアルバムをめくる前、「寒い」と言った。十月の夜は裸で過ごすには寒すぎる。
「こうすれば寒くない?」
「あ、少し」
そう答えたのは少女にありがちな遠慮からで、本当は嫌だったんだろう。それでも、その時のぼくには、裸で彼女を抱きかかえながらアルバムを一緒に眺めることがどうしても必要だったのだ。
神妙な面持ちで杜のアルバムを繰っていた彼女は、それが予想外の余白を残して終わっていることにショックを覚えたらしく、何度か見返した。やがて観念したというように手を止め、一枚の写真を指差した。
「これかわいいね」
それは杜が生まれたばかりのぼくを抱いている写真だった。
「杜が死んだのはこのすぐ後だよ。俺は憶えてないけど」
打ちひしがれたようなため息が漏れた。彼女の背中が縮こまる。自分の不幸をかさに誰かを傷つけようなんて思わないけれど、ぼくは彼女がぼくの悲しみを背負ってくれることを願っていた。全部とは言わないまでも。
足早にアルバムを通り過ぎると、彼女はぼくの胸に寄りかかってきた。ぼくは彼女の顔を両手で挟むと、こちらに向かせ、額にキスをした。無理な姿勢が辛かったせいか、彼女はぼくの手を振り切った。
「嫌?」
「嫌じゃないよ」
その半年後、ぼくは彼女に「重たいから」とフられることになった。それほど悲しいとは思わなかった。ただ、少しも重さを我慢してくれなかった彼女にがっかりしただけだった。
母はぼくが大怪我で寝込んでいると、よくそうやって額にキスをしてくれた。当時は鬱陶しいと思ったものだけれど、母が亡くなった後は慕わしさと共に蘇る。ねっとりとした密着に飢えていたのだろう。だれかれかまわず親しくしたいと思うほど図々しくないけれど、少なくとも恋人だけはそういう存在でなくちゃならなかった。
結局、ぼくは相手がその「重さ」に耐える体力を持つまで待つことはできず、それから出会うすべての恋人に対して期待することを止めた(いや、それは真実だろうか? 私はいつだってものほしげな顔をしていなかったか? まだやり直せるのではないかと?)。
結婚する前の両親がどんな恋人同士だったのか?――私はそれを知らない。両親以前の彼らを想像する試みすら、頭を掠めたことがない。自分の無関心に愕然とするし、何より、両親達にかつて恋人同士だったと思わせるような素振りのなかったことが切ない。
親戚の伯母さんから両親の馴れ初めを聞いたことはあったが、父が会社の友人と一緒に草野球をした時に来ていたうちの一人が母だったというだけだ。私がそれを尋ねても、父は昔話をしようとしない。
「そうやって機会を探さないと、当時は会社の同僚かお見合いぐらいしかなかったからな」
父はすぐに一般論に辿り着き、私達は言葉を失った。
それもしかたのないことかもしれない。回想はある意味で小説的技法だ。父には詩的才能はおろか、そういう散文的なところさえまるでなかった。思考方法はアルゴリズムみたいだった。もちろん、金融の世界に進んだぐらいだから、仕事には活きるのだろう。ただ、仕事のためや、生まれつきというより、やはり生き残るために幼い頃勝ち取った能力だと思う。そういうものがなくては人生を生き抜くことはできない。あまりにも救いのない小説が読むに堪えないように。
その点、母はもっと感情的で、その仕草は古典悲劇のヒロインじみて大仰に見えることがあった。本人の話では、子供の頃から病弱だったせいか、小さい頃からもてたらしい。母親がもてたという情報は、当の息子にとってけったいな話のような気もするけれど、たぶん二割引ぐらいで本当だったのだろう。
両親の印象から、二人の恋人時代の風景を想像してみること――私は独居房でよくそんなことを試した。空想の中の二人は、とても仲睦まじかった。手をつないで歩いたこともあっただろう。私の記憶にそんな光景はないけれど、たぶん合っていると思う。父はたぶん、そういうこともちゃんとできる人間だったのだ。
仲睦まじい恋人同士が、どうやってあの両親になったのか。私の想像力はそこまで及ばない。ヒントになるような記憶は、父の友人が遊びに来たときのものだ。
来客は快活な男だった。ひっくり返って足をバタバタさせたり、あるいは奇声を上げて笑い転げた。「ぼく」は彼を大いに気に入った。しかし、すぐに敵意を抱いた。
来客は打ち解けてくると、母の名前を呼んだのだ。「***さん」と、ぼくの知らない名前で。ぼくが尋ねると、母は「結婚する前の名前よ」と答えた。
ある種の敗北感に打ちひしがれたぼくは、その男に何度も質問をぶつけた。どんなお仕事をしているの? どこに住んでるの? お嫁さんはいるの?
来客はそのどれにも答えなかった。ぼくは質問を沢山すれば、沢山の鼠が猫を食い殺すみたいに、この来客の手から母を取り戻せる気がした。
「さあ、どうだろうな。あててごらんよ」
ぼくは彼の職業をあてようとした。お医者さん、お巡りさん、おもちゃ屋さん、運転手さん……。しかし、十も数えないうちにぼくの知っている職業は尽きた。
「君はキュリアス・ボーイだね」
来客は職業を教えずに、ぼくを評した。意味はわからなかったが、侮辱の言葉の気がした。ぼくはほとんど怒ってしまい、問い詰めた。でも、来客は教えてくれなかった。
「K、もうやめなさい。***君が困ってるわ」
ぼくは母が来客の名前をいかにも親しげに呼んだことで、泣き出してしまった。大人たちはおろおろするより、溜息をついた。
ぼくは最後の砦である父の元へ駆けより、来客を追い返してもらおうとした。
「なんでそんなことで泣くんだ!」
父は怒鳴った。その声が少し大きかったため、母が諫めた。二人は喧嘩を始めた。ぼくは火がついたように泣き出した。
慌てた来客はすぐに外へ出て、ぼくにおもちゃを買ってきてくれた。ぼくは彼を許したふりをして、次の日の朝、家の外の、駅へ向かう道端へ目立つように捨てておいた。
私がまだ小さかった頃の父母は、一見すれば、ただ長く連れ添っただけの関係にも見えた。うんざりするような諍いだけがよく起こり、単なる静寂だけが平安だった。それでも、そこには私の想像が及ばない、ある種の繋がりがあったのだろうか。
『夫婦とは、お互いの悪行を果てしなく吸い込む不気味な沼のことだ』――ある憂鬱症の老作家がそんなことを書いていたはずだ。
私とミユキもそんな風になりえたのだろうか? 不幸の重さにつぶされないよう鈍感に生き続けてきた私が? もっとひどいことになった気がする。結局は失敗だった、ということになっただろう。それでもたぶん、私にはミユキしかいなかったのだ。選択肢はどっちみち一つしかないのだから。



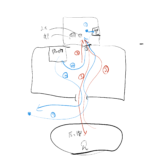
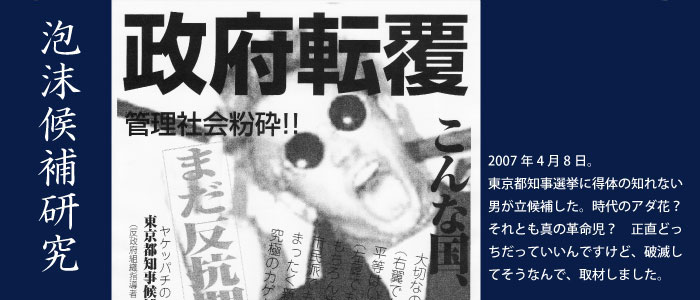




















"ここにいるよ(21)"へのコメント 0件