ひきこもりは川原で三週間を過ごした。
それだけの時間があれば、生活無能者にもなんとなく生活の骨が掴めて来る。なにせ金がかからない。家賃が無いだけでも、精神的負担がずいぶん違う。五十君と暮らした2DKなど、贅沢の極みだったと悔やまれる。
しかし、冬は本気を出してひきこもりの骨をギリギリ絞った。寒いのをどうしようもなくて、近くにある被服工場の裏から盗んだ。それがまたどれもこれも仕掛品で、ボタンやチャックが無い。留められないから羽織ってみるが、フリンジ付きの革ジャンの上から出来損ないのオッサンジャンパーでは、訳が解らない。
寒いのは酒が無いからだ。仕事は鉄の手伝いを何度かやったが、あまりに実入りが悪いので、変な蛸部屋で泊まりの仕事をやってみた。
北千住の河原町は尾崎豊が怪死した町で、その逸話のおどろおどろしさを納得させるかのように、小さな寄せ場がある。早朝には老いた日雇い労働者が列をなし、当然のことながら手配師もいるのだが、その手合いが河原でぼおっとしている若い男を捕まえては仕事に誘うのである。ものは試しと乗ってみたところ、二トントラックの荷台に乗せられて、北関東あたりの山奥に連れて行かれた。プレハブ小屋に寝泊りして、深い穴を掘って、底をコンクリートで固めた。二泊の予定が四泊で、しかも宿泊代だ何だと差っ引かれたが、二万円を現生で貰えば腹も立たなくなるのが悲しい。それだけあれば、一月は何とかなる算段なのだが、ひきこもりの目当ては酒だ。日本酒だと糖尿になる、健康には気を使わなきゃ、と、ウィスキーのペットボトルを両脇に抱えて、いそいそと商店街を逃げ去り、キャップの裏まで舐めるような飲み方をした。
一時金が堕落を呼ぶと、ひたひたとどこまでもついて来る。ひきこもりは河川敷の社交でも一流の堕落人間になった。俺は死にたくなった、などと臆面も無く言い放つ。五十君には通じなかったその手も、鉄のように純朴な人間には効果がある。
「情けねえことを言う奴とは、もう話さねえな」
そう言って顔を茹で蛸にして、ぷいと去ってしまうのだが、日が落ちると檻の近くを彷徨しだす。檻を開けると、おお居た居た、と芒の藪に手招きして、包んで貰ったばかりだという肉鍋をコップ酒に添える。寝る以外に用の無い鉄の家は手狭なため、庭と呼びたいような空き地に即席の座席が設けられている。発泡スチロール容器の蓋を開けると、湯気の中で黄土色の汁が白い輪の中で身を縮めている。レンゲで一掬いして、川風に冷まされる前に頬張る。鼻から漏らした息が、白くなる。
「な、美味えだろ?」
「美味えっすね」
「捨てたもんじゃねえだろ」
人生も、とは言わない。鉄はからから笑って、自分の容器から肉鍋をよそい分けてくれる。間をおいてから優しくなるのだ。
ひきこもりの悪どさは、自分が許されていると思っているところだ。なるほど、死にはしない。それは誰もが知っている。真正面な同情心の持ち主なら、死ねとは言わず、少し困る。その困惑に付け込んで、悪びれない。その狡さを指摘されたら、俺だって解ってんだ、と開き直る。それでも許されている、という次第である。
「怖いですね」
チョウさんは悪どさをそう評した。相手を圧し、跪かせる怖さではない。ずるずると足に絡み、腐らせる類の怖さだという。ひきこもりがそれを聞いて怒ったのは、その内容が当たっていたからというより、分析されたことの屈辱からだった。分析や批評を蛇蝎のごとく嫌うのが私小説家の条件だと天から思い込んでいる。
「俺だって解ってんすよ。でも、あんただって狡いじゃないか」
安酒の酔いで高ぶったひきこもりは、そう言いながら、壁面を覆う書棚を指した。チョウさんはタイ人へと視線を落としたまま、ぼそりと呟いた。
「自分で狡いと認めるほど狡くはないですがね」
「俺の方がマジだよ。チョウさんはブルジョワだ。ブルジョワなのに物見遊山でここにいるんだ」
五十君なら、こういうことを言った後、「亀夫くんはブルジョワとインテリの意味を単純な国語のレベルで間違えてるね」と真面目過ぎる一重まぶたで言うのだが、チョウさんは反意の欠片さえ見せない。
「まあ、決め付けられては返す言葉がないですね。何でブルジョワと思ったのかは解りませんが」
年長者の使う敬語は、ひきこもりを苛立たせた。激昂寸前の笑いが顔に浮かび、おへへい、と威嚇の声が漏れる。
「こんだけ本を読む乞食がどこにいるんすか。なんでこんなにしこしこお勉強しちゃったんすか。本だけじゃ解らないことだってあるんすよ」
「私なんかより読書家はたくさんいますよ」
タイ人の上に覆いかぶさるようだったチョウさんは、くるりと振り向いた。その顔には色が無く、幾つもの感情の起伏を押し殺した風の平板さがあった。整地された古戦場を訪れた時の、敬虔なざわめきが胸に蘇る。
「それにそう思うのなら」と、チョウさんは付け加えた。「本を書くのなんて止めたらいい。本がそんなものでしかないんならね。君は君の体験とやらを生きればいいでしょう」
チョウさんは無色の瞳を再度タイ人の上に落とした。ひきこもりは痛いところを突かれ、踞った。五十君に何度も突かれて多少は強くなっていたつもりの経験至上主義も、違った人に違った風に突かれればやはり痛い。しかも「乞食」という言葉にありったけの悪意を込めたというのに、華麗に受け流されたことが痛手を深くした。
踞っていると、タイ人が目を覚ました。拗音が多い言葉を呟く。チョウさんは傍らにあるケトルを取って、注ぎ口を咥えさせた。タイ人の喉仏は鳴きながら蠢いた。
「水って言ったんすか」
「さあ」
「タイ語解るんじゃないんすか」
「解りませんよ。ただ、こんな時に自動車免許とか、政界再編とか言う訳が無いですから」
自虐以外をユーモアと解さないひきこもりは、真面目腐った顔つきでタイ人の飲みっぷりを眺めた。まだ二十歳そこそこらしいタイ人の喉は、垢に汚れてはいたが、毛が生えていなかった。
ひきこもりは立ち上がり、扉を開けた。すると、チョウさんが呼びかけた。
「ちなみに、まだ彼がタイ人かどうかはわかりませんよ。完全に意識が戻るまでは。何でも一緒くたにするのは、どうもね」
ひきこもりは、すいません、と謝ってからその場を辞した。その謝罪の根拠はなんなのだと自問しながら芒の藪を脱けていると、途中、手首を大きく切った。鉄に貰った軍手と袖の間が十センチほどの細い傷になった。消毒がてらにぺろりと舐めたが、両脇の皮膚が冬の乾きに縮んで、ひりひりと痛んだ。オイオイ。誰かの世話をしたかった。世話になるだけじゃなく、自分だって誰かを世話したいと無性に思った。
ラッパズボンのポケットをまさぐって、金勘定をしてみた。貨幣が綺麗に一つずつ、一円玉だけ申し訳無さそうに七枚もあって、千六百七十二円だった。手塩にかけた娘を女衒に渡す積もりで種を買い、農業でも始めてみようかと思ったが、適当な空き地が無い。では動物だと兎屋に相談するが、兎屋はその切実さを違った風に理解して、いつもの押し問答が始まる。
「そんなこといいから、働けよ。若えんだから。おまえ、こんなとこにいつまでもいるな」
「働いたって、書けるようにならないっすよ」
「そうか、でも、働かなきゃ働かないで、書くことないだろ」
ひきこもりはぐふっと唸りながら、視線を落とした。兎屋は兎に犬の餌をやっている。彼が空き缶を拾い、その収入の幾らかを食い潰した兎たちが肥えていく。それぞれのリズムで律動する白い鼻を見ていると、苛立ってきた。ひくひくひくひく、妙に可愛らしい。それに腹が立つ。
「あるよ、書くことは」
三十男の不貞腐れは無関心しか買わないが、兎屋は優しい。薄汚れたダウンジャケットの襟元から、小さな顔で覗き上げる。
「じゃあ、早く働いて、家を借りて、そこで書け。こんなとこじゃ書けねえだろ」
「逆に、ここの方が書けるんだって。解る?」
鉄の口癖で同意を求め、フェンスの檻を指差した。兎屋は妄言を聞き流す軽やかさで肩を竦め、傍にいた兎を撫でた。気持ち良さそうに瞼を閉じると、赤い瞳が白の中に消えた。あんな顔をしてみたいと羨んだら、ますます憎たらしくなってきた。
「いいか、俺は書くよ。一週間だ。名人の陶芸みたいな短編を書いてやるよ」
ひきこもりが放兎場から踵を返すと、その勢いに怯えた兎たちがわっと散った。兎屋はこらっと鋭く怒鳴った。兎は相当な臆病者だという。もしかしたら何匹か死ぬかもしれない。しかし、死への怯えは、ひきこもりに予感をもたらすだけだった。感情の暗闇が小説の成功をもたらすと思っていた。



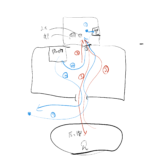
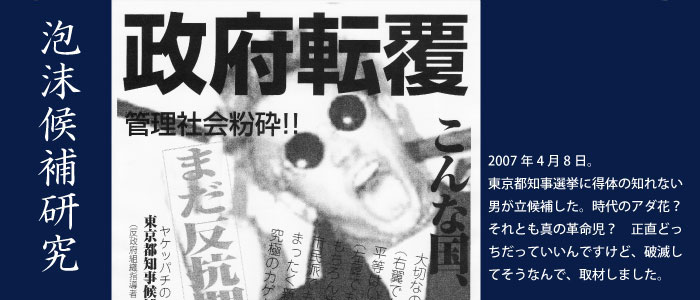



















"怖いねえ"へのコメント 0件