タカハシは平穏無事でいれば大体のことはどうでもよかった。悠太襲来の事件があったあと、あらためてその確信を深めた。やっぱり平和が一番だな、と山田に話すと、意外だね、という答えが返ってきた。
「丸毛くんと住んでた頃は、ご飯とか全部作ってあげてたから、めんどくさい人と住むのが好きなのかと思ってた」
「メシに関しては作っちゃった方が楽じゃん」
山田は、あ? と聞き返した。山田はよく、タカハシに問い返した。タカハシの話は六割も理解できないと言っていた。そんな二人が一緒にいることがそのまま世界の素晴らしさだと、タカハシは何度も説き伏せたが、山田はそれも理解しなかった。
「だってさ、メシとかを完全に二等分するのって、難しいだろ。たとえば俺が料理作ったら幾らとか、どうやって決めるんだよ」
「時給にすればいいじゃん」
「でも、そうすると、品質担保が必要になるだろ。その時給の正当性を保証しなきゃならない」
「そんなの二人で決めればよくない?」
「ルールが決まっても、料理に失敗したら、ケチつけられるだろ」
山田はしばらく黙り込んだ。そして、私と住んでもそうなの、と尋ねた。
「そんなことないよ。ただ丸毛とかカントくんとか、みんな他人だからさ」
山田は、おおお、と感情を持て余し気味に呻くと、頭をガシガシとかいた。何本もの毛が抜けて、絨緞の毛に絡まった。山田の髪の毛は太く、執念深い。タカハシは身体を伸ばし、布団から出ることなくカーペットコロコロを取った。三往復も転がせば、びっしりと髪がついた。山田は辱められた表情でロール紙をはがし、ゴミ箱に向かって投げた。あまりに強く投げたので、それは高く舞い上がり、タカハシの使っている五年もののノートPCの上に落ちた。何かがうまくいかなかった。
とにかく、カントが平穏を乱す元凶だった。定職にも就かず、テレアポのバイトで日銭を稼いでは、後先を考えずに使ってしまう。そして自棄になり、得体の知れない面倒を起こす。この宇田川ビル四〇一号室において、カントは危険な不確定要素だった。なんとかして、カントを小説へと集中させる必要があった。
カントは今日日珍しく、手書きをしていた。小学校で使うような緑罫のB5版原稿用紙を持って、鉛筆で書く。しかも机を持っていないから、万年床に座って地べたに書くか、居間のソファに座ってピーチ材のローテーブルに書くか、どっちみち低い姿勢を続けなければならなかった。そんなやり方では腰が痛くなってしまうし、長くは書けない。必要なのはノートパソコンだった。あれなら膝の上に置いても書ける。
居間のソファでとろとろと酔っていたカントを熱心に説き伏せると、カントは笑いながら、「でも、これがねえ」と、親指と人差し指を摺り合わせた。
「所詮、アルに消えちゃうからね。俺、生まれてから一回も貯金したことないし」
「でも、どうせワープロソフトしか使わないんでしょ。だったら、中古でも五万ぐらいだよ」
「へえ、そんなに安いんだ」
「そうだよ。アキバのソフマップとかで買えばいいじゃん。俺が一緒に行ってあげるよ」
一緒に、と言った瞬間、カントはいかにも嬉しそうに笑った。
秋葉原に来るというのは、メイド喫茶が流行り始めた頃に物見遊山で来て以来だった。カントも新し物好きではあったが、家電やオタク文化とは縁遠い生活を送っていた。事実、カントを小説に集中させて平穏な生活を取り戻したいという目的を持つタカハシと異なり、カントにとって秋葉原の人ごみは疲れるだけらしく、昭和通りを横に入ったところにある児童公園で煙草を吹かしていた。我慢の利かない男たちが、路上喫煙の反則金を恐れて公園に入り浸っていた。タカハシが煙草を吸い終えるのを待っていると、カントは吸殻を砂場に差し込み、胸の前で十字を切った。
「じゃあ、行こうか」
「どうする? 一応、新品も見てみる?」
「いやあ、俺はタカハシくんを全面的に信頼してるからさ。逆にすべて任せるよ」
ヤニと歯垢で真っ黄色になった歯を覗かせて、カントは笑った。
「じゃあ、ソフマップからにしよう」
二人でソフマップの中古パソコン2号店に入ると、タカハシは適当に三つほど選んだ。タカハシが選んだPCは、どれも残飯のようにラッピングされ、ドブ鼠色の弁当箱に似ていた。カントはその三台を何度か見比べてから、急に渋い顔をした。
「逆に聞くけど、タカハシくんはどれがいいと思うの?」
「このNECのがいいと思うんだけど」
「なるほどねえ。こっちのはなんで駄目なの?」
カントはIBMのパソコンを指した。
「性能は大して変わんないよ。ただ、俺、これがあんまり好きじゃないんだよ」
タカハシはキーボードの真ん中にある赤いトラックポイントを指した。
「確かにデキモノ風だね」
「いや、見栄えじゃなくて、単に使いづらいんだよね。マウス代わりとしては。これが好きな人もいるらしいけど」
「タカハシくんはこっちのが好きかい?」
カントはそう云いながら、いかにも迷った風にNECパソコンのタッチパッドを撫ぜた。
「まあ、カントくんがどう感じるかはわからないけど。それって、叩くとクリックの代わりになるからね」
「で、どうなの、他の性能的には」
「入ってるワープロソフトは一緒だよ。まあ、CPUはIBMの方がいいみたいだけど……大して変わんないよ。違いはマウスポインタぐらい。あとは信頼性? どれぐらい変わるのかは、わかんないけど」
そう言ってから、カントはパソコンを決めるまでに三時間を要した。豆粒か板かという瑣細なことで悩むのではない。怖くて窺うのだ。顎に手をあてて、さも深刻に悩んでいるのは、パソコンではなく、何かを決めるということに対して、手を差し伸べて欲しいからだった。
結局、カントが買ったのは一番はじめにタカハシが目星をつけたNECだった。タカハシはカントがあまりに「大丈夫かな」と訊くので、いい加減に嫌になって「そんなの自分で決めろよ」とむくれた。それがカントを追いつめた形になり、ついに購入へと落着した。カントは心証回復でもしようと思ったのか、唯でさえパソコンを買って痩せた財布から、焼肉を奢った。それはおそらく、カントが「パソコンを買うから」と長崎の母にねだった金だった。
「まあ、好きなもん食ってよ」
罪悪感。鷹揚に言いながら自分はキムチをつまむだけのカントを見て、タカハシはことさらにその言葉を思った。カントは生きていることが悪いと思っているようだった。
「今日はタカハシくんに時間を使わせちゃって、悪いと思ってるからさ」
「まあ、いいよ。そんなに気にしなくても。俺もカントくんがこれで小説をバリバリ書いてくれたら、時間の無駄なんて思わないからさ」
カントはキムチを落とした。箸の扱いが下手だった。逆手で握るようにして持つ。掃除当番であるタカハシは、一度だけ指摘したことがあったが、小さい頃から一人で食事を取ることが多かったから、と言われて以来、何も言わずに掃除当番を引き受けることにしていた。
「何か、他に手伝ってほしいことない?」
「いいのかい?」
「いいよ。下調べぐらいなら、すぐできるから」
「確かに、俺とタカハシくんで書けば、無敵だからね」
カントはそう言うと、これまで一度として語ることのなかった小説の構想について、話しはじめた。カントとタカハシを思わせる二人組が長崎に向かい、ガッチャガチャの狂態を演じるという設定だった。
「ガッチャガチャって何?」
「いや、俺も相当考えてるよ。逆にタカハシくん、どう書かれても怒らないでよ」
「別にいいよ」
カントはニヤニヤしながら、これは絶対イケるよ、と呟いた。
「でも、旅行して終わりなの?」
「いや、途中からグラバーが出てきてさ。時代を跨いだ純文学にするつもりなんだよね」





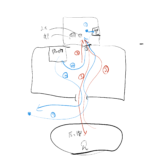
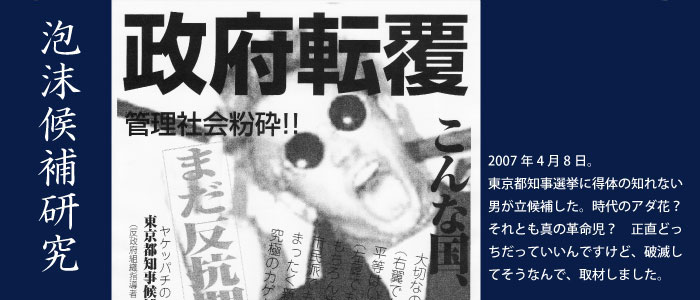



















"フェイタル・コネクション(3)"へのコメント 0件