カントが居間でとろとろと酔っている間、タカハシは丸毛から引き受けた仕事に没頭した。この仕事を終えて十五万円が入れば、とりあえず来月分の家賃にはなる。カントは先月の家賃も未納で、親に無心した金も使い切ってしまっていたから、どんなに早くても家賃八万円の振込みには間に合わなかった。となると、タカハシがその分を補填するしかない。幸い、十五万円もあれば二人が生活していくには事欠かない。
タカハシはプログラミング言語とデータベース言語の本に六千円を投資し、十五万円を得るためにキーボードを叩き出した。さすがに一月で仕上げるといってしまったのは無理があり、文法や制御構文などの原則は一日で覚えられたが、言語に特有の機能や拡張機能を理解するのに手間取った。毎日三、四時間しか眠らずにパソコンに向かっていなければならなかった。
山田はタカハシがプログラマを目指し始めたと勘違いし、大丈夫、体壊さない? と眉を顰めながら、甲斐甲斐しく身辺の世話を焼いた。嬉しそうだった。山田は毛の量が多く、いつも季節の変わり目の犬みたいだったから、彼女が掃除機をかけた側から毛が落ちていった。タカハシは部品化したプログラムが相互に問題なく動くことを確かめると、カーペットコロコロに手を伸ばし、山田の毛を巻き取った。女の長い毛を巻き取ったコロコロは、古いシートを捨てるのが面倒だった。
タカハシはほとんど部屋にこもっていたので、カントを見ることがなかった。夜の三時になると、やはり奇声が聞こえた。こいつ、弱えー! 山田は布団の中で不安げに、あの人大丈夫、と尋ねてきたが、その眉根には以前のような底知れない不信がなかった。タカハシが働いている姿を見て、安心しているらしかった。こんな姿を見せなくても、自分の計画に間違いはなかったのにと、タカハシは信用の得難さに改めて驚いた。
三週間がたち、コミュニティサイトがだいぶできあがった。そこでは寄る辺ない文系大学院生たちが、自分の職能を披露することができる。翻訳なり、調査協力なり、登録しておけばなんらかの仕事を受注することができる。場合によっては、自分一人でこなせない仕事を仲間と外注しあうこともできる。価格体系は明瞭で、食うに困らない程度の収入を得ることを目指す。まだ決済手段を提供できてはいないが、マッチングできるだけでも大したものだろう。IT大国アメリカにもクレイグリストという掲示板サイトがあって大人気だという。サイトの名前はユーソフィアだ。無い、知恵。タカハシはこの諧謔に一人笑い、自分が一端のパソコンオタクになった気がした。
それまではウェブ上に公開せず、家にあるオンボロパソコンで開発を続けていたが、そろそろ公開された場所で検証をしなくてはならなかった。が、アップロードしてみても、画面が真白で何も映らない。どうもデータベース接続がうまくいかず、ああ、接続先ホストの設定を間違えたんだな、とエラーメッセージを表示すると、”401: Fatal Connection Error” と表示されていた。ローカル環境では問題なく動いていたものが、公開した場所に置かれた途端に致命的な接続エラーを起こし、しかも、そのエラーナンバーが部屋番号と同じ401だったという事実は、とても示唆的であり、文学的な暗喩の一つとして使えるような気がしたので、カントの部屋に向かった。
見て見て、といわんばかりの勢いで検証用URLを入力し、カントのノートパソコンに表示されたエラー画面を指差したタカハシは、これ俺たちの人生のことじゃない? と言った。
「まあ、ある意味そうだねえ。こいつ、機械のくせに、真実、言っちゃうねえ」
「ねえ、凄い一致でしょ! これは小説に書けるよ。使ってよ」
「いや、パソコンってほんと凄いねえ」
カントはむしろ観念した風で、自虐の一つも歌わなかった。タカハシが煽り立てても、カントの顔は暗い縁から戻ってこない。いつもの悪い癖で言いすぎてしまったのかもしれないと反省していると、カントは別のページを開いた。
「あ、カントくん、mixiやってるんだ」
「いや、大貧民で知り合った主婦に誘われてさ」
「へえ、やるじゃん。不倫するの? 悠太さんもチャットで知り合った主婦に会いに京都まで行ってたよ。地方の主婦って暇だから、けっこう欲求不満みたいだよ」
「いや、そうじゃなくて」
いつももなら不貞行為に対して、それゴミじゃん、と大激怒するはずのカントはあくまで素っ気無く、タッチパッドを動かしてmixiの画面を操作していた。タッチパッドの周りは手垢がついていて、うっすらと凹んでいた。
「やりこんでるね」
「このさ、マクシム・ドカンってやつ」と、カントは画面に表示されたサムネイル画像を指した。「たまたまmixiで出会ったんだけど、ほら、前にタカハシくんに言った、ヤク中の奴なんだよね」
「ああ、クラブかなんかでカントくんを煽って、ファイトクラブ的に全員でボコろうとした奴?」
カントはこれまで何度も小説のネタを話したことがあり、その中の一つがこの「ファイトクラブごっこ」だった。なんでも友人に誘われてクラブに遊びに行ったところ、そこではなぜかカントを皆でボコボコにする計画になっていた、というエピソードだ。友人グループの中の良心的な一人にこっそり、このあとお前、遊びでボコられるぞ、と教えてもらい、トイレに逃げ込み籠城を一晩決めこんでことなきを得たそうだ。タカハシはその話を聞いたとき、それって友達なの、といぶかったものだった。
「そう。こないだ、出身地で検索かけてたらたまたま見つけてさ」
「マイミクになったの? カントくんをボコらせようとしてきた奴なのに?」
「あの頃はこいつもヤクやってたからねえ。しかも冷たい方の」
カントはそう言うと、マクシム・ドカンのプロフィールを表示した。
自分は器の小さい人間だった。
三年ほど前、そのことにやっと気づき、都落ち。育った故郷も悪くないと気づく。
最近はクサ(食用)やキノコ(食用)を山で採り、テンプラにして食している。このまま自然と触れ合いながら生きて行ければいいなあ。
殊勝な自己紹介は、カントの物語とだいぶ違った。タカハシは、ちょっと貸して、とマクシム・ドカンのマイミクを検索していった。マクシム・ドカンについての紹介文を書いているマイミクもいたが、「素敵なニート」「ほっとけない。前世は息子だったに違いない」「襟足がキュートです。切っちゃダメだよ!」などといったぬるま湯的コミュニケーション用語が飛び交うだけだった。戸惑いがタカハシを無口にした。
「あいつももう三十一だからねえ。前は俺もおまえもオールマンのデュアンとオークリーみたいにバイクで事故死しようとか言ってたけど」
「あ、仲好かったんだ。でも、カントくんバイクの免許持ってないでしょ」
「うん、俺が免許持ってたら、絶対人殺すからねえ」
「あ、偉い。そこらへんの判断力がただのアル中じゃないね」
「まあねえ、しかし、長崎じゃ車ないと就職できないからねえ。ヤバいねえ」
「カントくんでも将来を考えるんだね」
カントは小さく頷くと、厚く塗り重ねられた沈滞を振り払うように、mixiの足あと画面へと遷移した。
「ところで、タカハシくん、見てよ」
カントが指さした足あとリストには、厖大な数が残っていた。一日に百人以上がカントのページを見ている計算になる。
「凄いじゃん、なんでこんなに見に来んの」
「いやあ、世間が俺をほっとかないよ」
「たしかにねえ、カントくんぐらいダメな人もなかなかいないからね。凄いよ」
「いやいや、タカハシくん、そこは逆にけなすとこだよ。どんだけ人がいいの?」




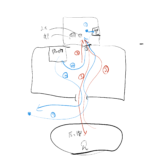
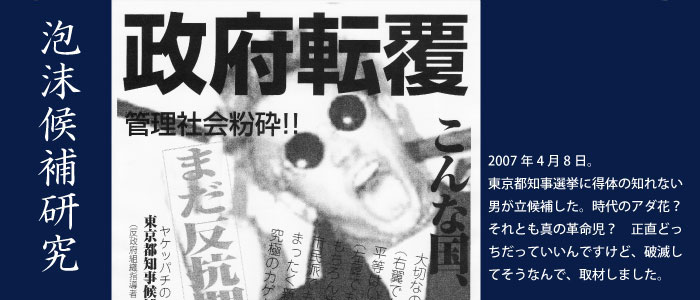




















"フェイタル・コネクション(4)"へのコメント 0件