この章を読み進めて初めて読者は、ジョイスが″声″を手に入れたのだと確信する。小説における声は、著者の文体であり、小説内での語り口である。これが物語の世界観、時代背景、イメージ喚起、共感度に至るまでほぼ全てを左右すると言ってもいいだろう。アーシュラ・K・ル=グウィンは
わたしはこの言葉を素直に実用面から、〈物語を聞かせる単数または複数の声〉つまり語りの声という意で用いている。
と声について説明している(『文体の舵を取れ ル=グウィンの小説教室』大久保ゆう訳、フィルムアート社)。ジョイス自身を投影したディーダラスとしては、前作で語りつくしていたはずだ。ミスタ・ブルームという語り手は、新たに小説内に燦然と輝く声の持ち主として立ち現れた。
前章でもミスタ・ブルームは移り気な様子を見せていたが、この章では彼が密かにヘンリー・フラワーという偽名でマーサという女性と文通していることが分かる。彼が――おいたさん――と呼ばれる文面から、どういう女性か、二人の盛り上がり具合まで示される。しかも――P・S 奥さんがどんな香水をつけているのかぜひ教えてね。知りたいの。――という追伸まで書かれていて、恐怖を感じる。そして、ミスタ・ブルームは薬局で石鹸を購入してトルコ風呂へと向かう。この奔放さはモリーの裏切りの前触れとしてフックになっている。






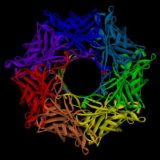





















"五章 食蓮人たち"へのコメント 0件