あるところに四方、周りを山で囲まれた貧しい集落がありました。そこは耕しても耕しても土が弱く、畑の作物が育たないそんな場所でした。どれだけ苦労して作物を植え、それを大きく育つように手を加えても育たない。一向に育たない。そんな場所でした。一生懸命にがんばっても、がんばってがんばっても、報われない。そんな場所でした。
ですから、そこに住む人々はいつも苦労していました。なにせ自分達が食べるものでさえろくに無いのです。満足とは言わない、少しでもいい。それさえも大変な場所でした。
そんなところですから、そこでは常に人の死の匂いがしました。どの家も老いた父母が死んでも葬式に出すお金もありませんでした。そもそもお寺さえないのです。そこに住む誰も経文の一つも知りませんでした。山に生えている木を切って自分達で作った粗末な棺に体を折り畳むようにして入れて土に穴を掘って埋めるしかありません。それから目を瞑って胸の前で手を合わせるだけでした。また若い者にしても、死は決して無関係な事ではありませんでした。食べるものも無く、お金もなく、どの家々も粗末な造りでした。それだから怪我や病気になる事もしょっちゅうありました。そのまま死んでしまう人もいました。ようやく生まれてきた子供さえ、すぐに死んでしまう事が珍しくありませんでした。そんなことは当たり前でした。もう人々はそんな事があっても、あまり驚きませんでした。誰も彼も、自分がどうして生きているのかわかりませんでした。皆が疲れた顔をしていました。
懸命に土を耕しても、土は一向に育たない。土が育たないから作物も育たない。それだからお金も無い。毎日食べるものだって無い。お金が無いから他の場所に行くことも出来ない。それでもその集落を出て行ったものはいます。いました。しかし帰ってきたものは一人としていません。それにそもそも、ここから出たところで、余所に行ったところでどうなるというのか。どこだって同じようなものだろう。どこに行っても今と同じように生きづらいのは変わらないだろう。
畑の作物が満足にとれないその集落では四方を囲んだ山々にほんの少し実るものだけが、そこに住む人々を辛うじて生きながらえさせていました。しかしこの実りも、毎年あるとは限りません。ある時とない時がありました。全くない年もありました。その年は集落を包んだ死の匂いが特に強くなりました。あぜ道で倒れて死んでいるものがいました。集落の外れにある木で首を括っているものもいました。二人で山の中にある崖から飛び降りたものもいます。
うまれかわったらしあわせになりたい
その崖の近くに沢山の石を乗せた文が残っており、そう書かれていました。
でも、もううまれたくない
震えるそれらの字は血で書かれていました。
※
その集落のある家には年老いた母親と、息子が二人で暮らしていました。父親はいませんでした。
「こんだどごで生きるごどなばでぎね」
そう言って、息子がまだ幼い頃でした。家を出て行ったきりです。それっきり何の音沙汰もありませんでした。果たしていま生きているのか、死んでいるのかそれもわかりませんでした。
その親子も例外なく日々の生活に苦しんでいました。二人で畑を耕して、山で山菜やらキノコやら木の実やらがとれていた時はまだ何とかなっていましたが、年のせいでしょうか、母親の足腰が悪くなり満足に歩けないようになってからは本当に苦しくなりました。
「すまねえ、私のこの足がちゃんとうごげばいいんたけど」
「おっかあ、そんだ事いうなだ」
息子は一人になっても一生懸命畑を耕しましたが、どれだけ頑張ってもその成果はほんの、ほんの、微々たるものでした。それだから山に入って山菜やら木の実をとるしかありません。山の中を流れる小川で小魚、ちっちぇけえ小魚やらコケのついた沢蟹を取って食べるしかありません。しかしそれでも、息子が必死になって畑を耕し、足を棒にして山を歩き回っても、それでも毎日満足に食べる分はありませんでした。
「おめえ、これもけえ」
「おっかあが食べでねえでねが」
「私だば、もう腹こいっぺえだ」
母親はそういっては自分の分も息子に食べさせていました。ただでさえ食べ物が満足に無いのに、息子がやっとこさ採ってきた食べ物さえ母親は息子に食べさせようとして、母親のもともと痩せていた体はさらに痩せ、髪も抜けて、やがてろくに目も開けられないようになって、衰えていきました。
そんなある日のことでした。
家に老いた母親を残して山に入った息子は、
「ここさ、こげだ道あったべが……」
そこに不思議な道が出来ているのを見つけました。山を登る一本道、それだって獣道の様な道でしたが、いつもその一本の、そんなに高くない山の山頂に延びて向こうの山に降りていくだけ道です。そこから枝が分かれるようにしてもう一本の道が伸びていました。
息子はそれを一目見てなんとなく気持ち悪いと感じました。山頂に向かう道とは違って下っていくように見える道でした。小川のある方向とも違います。もう何度となくその山に通った息子ですが、そんな道今まで見たことありませんでした。しかし、その分かれ道に立って耳を澄ますと、向こうから、その下っていく道の向こうからは、
「なんだあ……」
かすかに、かすかに、かすかに何か聞こえてくるのです。なにか、なにかの、なんだか、なんとなく楽し気な音の連なり、そんな音が聞こえてくるのです。しかし、その場所からは風や木々の音で満足に聞くことができません。あれはなんだろうか。笛の音だろうか。琴の音だろうか。でも、なにか、確かに聞こえてくるのでした。その音を聞いているとまるで、
まるで、
まるで、
まるで、
息子は山で採ったものを持って今来た道を一目散に走って家に戻りました。
「おめ、なしただ、なした」
家に帰りつくなり、肩で息をしながら手桶に水を汲んで飲む息子に母親は聞きました。ろくに歩けなくなったのにその息子の元に這うようにして近づいていって足に縋りつくようにして聞きました。
「おっかあ、おっかあ、あの……」
息子は今しがた山であったことを話しました。
そしてそれを全部話し終えると、母親はようやく安心したような顔つきになって、穏やかな顔つきになって言いました。
「それだばあれだ。おめが山こさ、いたずらされだんだ。ちょっかいかけられだんだな」
「おらあ、そんたごと、山さ入ってがら今まで一回もねがったけど」
「山こっていうのはそんた場所だがらな。そういうどごろだから。今まで一回もねがっだとしても、そういうごどもあるどごろだしゃ」
そう母親に言われて息子が安心すると、息子は母親をいつも座っている場所に運んでから、いつものように夕餉を作り始めました。その日もまた、いつもと同じく粗末な食事でした。そして母親はその日、いつにもまして食べませんでした。
※
夜中になってふと息子が目を覚ますと、隣で寝ていたはずの母親が布団から居なくなっていました。息子は夜中に目を覚ますと、手で隣を触って確認するようにしているのです。ですから真っ暗闇の中でしたがそれがすぐにわかりました。母親の布団は空になっていました。
「おっかあ、おっかあ」
息子は飛び起きて土間に降り、家の入口に立てかけてるだけの扉、木の板をどかしました。夜の空には雲一つなく、その中にポツンと一つまん丸の月が出ていました。その月明かりで家の中を確認しました。
「おっかあ、どごさいっただ」
やはり母親はどこにもいませんでした。しかし母親の寝ていた布団の枕元に何か、紙切れが一枚あるのを見つけました。それを乱暴に、掴みかかるように飛びついてから、外に出て月明かりの下で確認すると、
けっしてくるな
そこにはそう書かれていました。その時です、裸足だった息子の足元の地面でした。そこに、その足元の地面に這ったような、何かが這ったような、移動したような跡を見つけたのでした。
「おっかあ、おっかあ」
その跡を追って息子は走りました。その跡はどうやら山に延びているようでした。いつも息子が山菜採りなどで入っていたあの山でした。その日、不思議な分かれ道を見つけたあの山でした。走っている息子の頭の中では母との思い出が浮かんでは消え、浮かんでは消えてを繰り返していました。
まだ子供の頃、満足に畑仕事が出来ない自分に鍬の持ち方を教えてくれた母。一緒に山菜を採りに山に入った母。二人で一生懸命になって畑を耕したこと。その年は山の実りがいつもに比べると多く、柿がとれたので干し柿にしたこと。渋い山ブドウを二人で食べたこと。滅多にとれないヤマメがとれたので囲炉裏で焼いて二人で食べたこと。老いた母親。満足に歩けなくなった母親。食べることさえできなくなりつつある母親。もう立つことさえできなくなりつつある母親。
母親の這った跡を追いかけて息子も山に入りました。月明かりが道を照らし周りの木々を照らし、風がざわざわと吹いていました。
※
そうして走って山を登り、息子はあの、前の日に見た分かれ道のところまでやってきました。這った跡はその下っていく分かれ道の方に続いていました。
夜になっているからでしょうか。その先からは、昼間に聞いた時よりも大きな音が、音色が聞こえてきていました。それに何かボヤっと火の明かりのようなものも見えました。
「おっかあ、おっかあ」
息子はその道を走って下りました。
「おっかあ、どこさいる、おっかあ」
大声を出して母親を呼びながらその道を走って下って一つ曲がり角を曲がったらすぐでした。
そこは、そこには、山の渓谷のような場所が広がっていました。息子が知ってる小川とは全然違う。広い渓谷に出たのです。そしてそこには沢山の人が居ました。見たことも無い数の人でした。大きな音で音楽が流れていました。至る所にかがり火が立っており明るくなっていました。中央にはひときわ大きな火が、櫓でしょうか。それが燃え盛っていました。まるでお祭りの様でした。櫓のまわりでは人々が輪のようになって踊っていました。
「あらあ、来たのお?」
声がしたのでそちらを見ると、そこには母親が立っていました。しかしその母親は今の母親とは違って若く、それから見たことも無いべべを着ていました。そしてしっかりとした足取りで立って歩いていました。
「おっかあ、これは」
「来るなって言ったのにい。まあいいわ、せっかく来たんだから、あんたもこっちに来なさい」
「なんだ、なんなんだ、これは」
「いいから来なさいな。ここでみんなで楽しくやってるんだから。食べ物食べてお酒飲んで、音楽流して踊るの楽しいわよお」
母親はそういって腰をくねらせました。
「音楽……」
「そう、これは昔の曲だけどね。水カンのエンゲルっていう曲」
「なした、なしただ、なに言ってんだ、おっかあ」
息子には訳が分かりません。何も、何一つわかりませんでした。訳が分からなくなって彼は元来た道を引き返しました。母親がこちらに来る前に走って引き返しました。
「あ、ちょっと、気が済んだら来なさいよ。待ってるから」
背中に母親の若い声が聞こえてきました。
※
息子は一人で分かれ道まで戻り、そのままその山を登り始めました。そう高くない山です。月明かりに照らされて見えづらいですが、足元も何とか見えます。そしてあっという間に山頂に到着しました。
「ふう」
夜は、
そこにあった岩の一つに腰かけて、彼はそこから周りを眺めました。真夜中です。月明かりがあるとはいえ、ちょっと離れるともう真っ暗です。その山の頂上からは真っ暗な世界しか見えませんでした。
息子はそこで先ほどの事を考えました。
夜は、
どうしてあんなことになったのか、あそこに居た母親はもう知っている母親ではなかった。立って歩いていた。若くなっていた。皴も無かった。あれはいったい何なのか。しかしいくら考えても何もわかりません。母親が言っていた、山はそういう所だ。という、それ以外何一つ、何も浮かんではきませんでした。どれほど考えてみても一切何もわかりませんでした。
夜は、
その場所で周りを、世界を、真っ暗な世界を見ていると、まるで世界に自分だけしかいないような。そんな気持ちになるのでした。
それから彼は母親との記憶を思い出そうとしました。しかしもう母親との記憶も思い出も何も浮かんでは来ませんでした。
夜は、
夜は深い。夜は深い。夜は深い。夜は深い。
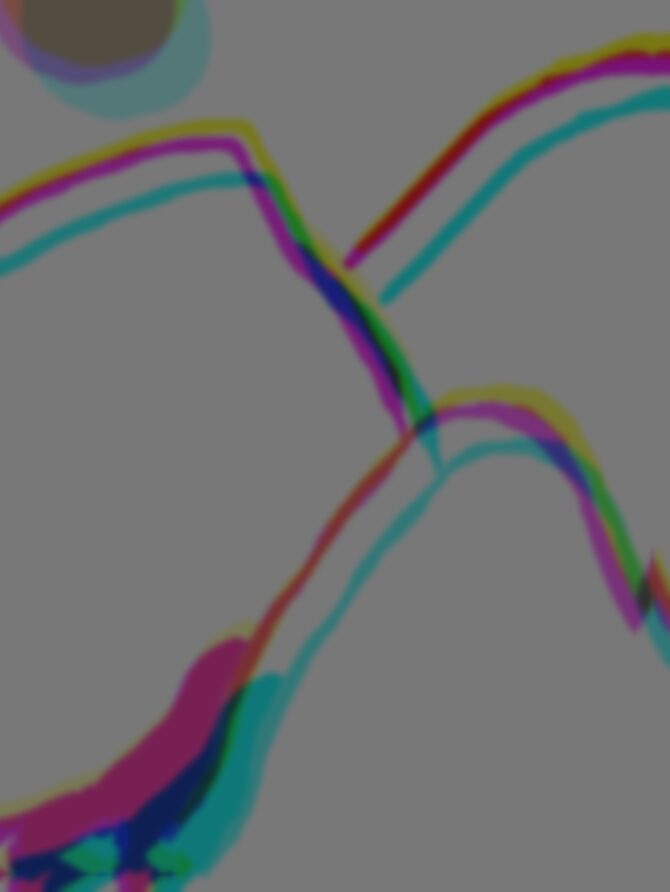






















"捨山渓:ディレクターズカット"へのコメント 0件