木こりのランドルトは体が円になっていました。まえに立つと大きな口だけのおばけ、よこに立つと黒い棒に見えました。
それだけではありません。ランドルトの体は、好きなところに切れこみをつくることができました。自分でそうしたいと願わなくても、病気になったり、うっかり転んだときにもなりました。
この見た目のせいで、ランドルトは村のみんなからいじめられていました。
「上!」
誰かにこういわれたら、ランドルトは思わず自分の体をさわります。それを見て、村の人たち(ほとんどはこども)はげらげら笑いました。
「とんまのランドルトは上も知らない。右も知らない。左も知らない。それでも木こりはできちゃうよ。とまった木はどこにも逃げない」
ランドルトはいやな気持ちになり、さっさと森へ行こうとします。
しかし、こどもは見逃してくれません。
「おい、わっかやろう!」
ひどい言葉といっしょに、こどもの一人が小石を投げます。当たれば痛いでしょうが、風がぴゅーぴゅー通る、まんなかのないランドルトに命中することはありません。
さぞがっかりするかと思いきや、少年はにやにやしていました。当たればその日一日英雄になれます。外れたとしても、みんなで笑えばいいのです。
ランドルトは、こういうことにもうなれっこでした。斧を担ぎなおし、地面を見ながら足ばやに人の群れから離れます。
村から森に行くとちゅうには酒場があります。そこの入り口に、いつもきまって村長さんがいました。壁によりかかり、あわれなランドルトが通りすぎるのを見ながら、気の毒そうな顔をつくります。この表情は村長さんのとくい技でした。
「あいつも本当にかわいそうだなあ」
村長さんはこういっただけでノドがかわき、ジョッキのお酒を飲みました。
「なに、あんな体してるほうが悪いんだ」
独り言のつもりでしたが、隣でイスに座る靴屋が応じました。
「体は神さまからもらったもんだから、どうしようもないだろう」
「それでもよ、ありゃ人間にはとても見えん」
靴屋は靴をはかない人間がきらいでした。
「わしはね、あいつがひとりものだからいかんと思っとる。せめて嫁がいて、家族を持てば、りっぱになるはずなんだが」
「村長もひどい冗談をいう。あんなわっかやろうの子どもなんか、誰がほしがるってんだ?どんなのが転がりでてくるか、わかったもんじゃねえ」
「だがね、いつまでもあのまんまじゃ、あまりにふびんだ。村いちばんの働きものだっていうのに」
「じゃあ村長は、じぶんとこの娘をくれてやるのかい?」
靴屋はお酒が入ったときのクセで、木靴をどんどんと踏みならしました。
「わしの娘じゃなくても、他に娘っこはたくさん……」
「ほうれ、いやなんじゃないか。わっかやろうなんか、ひとりでいるのがお似合いだ」
「うーん」
村長さんはそれ以上なにもいわず、お酒を飲みほしました。村長さんにも立場というものがあったのです。
酒場の話しあいが終わるころには、ランドルトは村を出ていました。野原をとぼとぼ歩き、オオカミの遠吠えが聞こえてくると、そこはすでに森のなかです。
ランドルトの腕ならどんな木でも切れるのですが、人のにおい、けはいが感じられない奥ふかくに入っていくのが日課でした。
今日も手ごろな木を一本見つけました。準備体操もそこそこにオノで切っていきます。
カーン、カーン。ランドルトはこの音がいちばん好きでした。村のみんなもやればいいのに。この音を聞けば、いじわるしたい気分もどこかに消えるだろう。単純なランドルトはそんなことを考えながら、すこしも休まず働きました。
木が倒れまであと三振りというところまできて、ランドルトはぴたりと手をとめて、耳をすましました。誰かによばれた気がしたのです。一回目は、そら耳だと思いました。けれど、二回、三回と続いたら気のせいではありません。
「右!」
その声は方向をさけんでいました。ランドルトはびくっとしましたが、自分の体を見ませんでした。
「右!」
村のやつだな、だまされんぞ!
ランドルトはぎゅっと目をつぶりました。そのすぐ後に、大きな音がしました。鉄ぽうの音です。
「右といっとるだろう」
おっかなびっくり右を見てみると、ランドルトの足もとには死んだヘビがいました。ランドルトは恥ずかしくなりました。
「こいつは毒持ちだ。かまれたらさいご、お空にいっちまうぞ」
ランドルトがふりかえると、そこには狩人がいました。狩人は森に小屋をたてて、ひとりで住んでいます。森でのくらしはランドルトも夢みていました。けれど、どれだけひどい扱いを受けても、さびしいところでくらす勇気はなかったのです。
「なんとお礼をいったらいいか」
「気にするな。おれはためし撃ちがしたかっただけよ」
狩人は鉄ぽうを見せびらかしました。あちこちが金でぴかぴかしており、本体につかわれた木も頑丈そうでした。
「そんな鉄ぽう、見たことねえな」
ランドルトは感心しました。
「あたりまえだ。みやこから仕入れた、新しい鉄ぽうだからよ」
狩人はたてつづけに三発うちました。しげみに隠れていた二羽のアナウサギがばたりとたおれました。
ランドルトはまた感心しそうになりましたが、やめました。狩人が人助けと鉄ぽう自慢のために、村ののけ者と話すわけがないからです。
「鉄ぽうはすげえもんだけど、日が落ちるまえにこの木、切らねえといけねえから」
ランドルトはオノを拾いました。
「木なんかいつでも切れるだろう。それよりおれと、狩りをしよう。楽しいぞ」
「でも、オノしか持ってねえからむりだよ」
ランドルトの落ちこむ顔を見て、狩人がげらげら笑いました。
「おめえに鉄ぽうはいらねえ。その体で獣をとっつかまえりゃいい」
話を聞けば聞くほど、狩人はひどい考えを持っていました。ランドルトがふしぎな体で、クマの首をしめたり、オオカミの脚にからみつく。そのあいだに鉄ぽうで始末すれば、狩りが楽になるというのです。
「さいきん、ハンスが死んじまってよ。犬ころを探しとるときに、おめえさんの顔がうかんじまったと、こういうわけよ」
ランドルトは泣きそうになりました。だれもいなければ、おそらく泣いていたでしょう。
「おれと組まねえか」
ランドルトは木にむかってオノを振りました。
「返事くらいしろよ」
「やらねえ。そんなおっかねえこと、やらねえ」
「一回やるだけならいいだろ。楽しいかもしれんぞ」
狩人がランドルトの肩に手を置きます。やさしくふりほどけばよかったのですが、不機嫌なランドルトはつい乱暴な動きをしてしまいました。そのせいで、オノの刃先が狩人の顔をかすめたのです。
ランドルトはすぐにあやまりましたが、自分より弱い人間に反抗され、狩人はすっかりおかんむりでした。
「わっかやろうのくせに!」
狩人は地面に一発うちました。
「粉挽屋のイボ! 牧師のあばずれ妻! 鼻くそ人形! てめえの皮で壁かざりをつくってやる!」
狩人の怒りは、もはやおさまりません。ランドルトはぞっとして、大事なオノを投げすて逃げました。
どこにそれだけのタマを持っていたのでしょうか。どこまで逃げても、狩人はご自慢の鉄ぽうをうってきます。枝がおれ、幹にあながあき、小鳥がちいさなわが子をのこして旅だちます。ランドルトは気が気でありませんでした。
どれくらい走ったかわかりません。ランドルトはくたくたでした。
「そこだ!」
たまはランドルトの円のふちギリギリに当たりました。痛みというよりびっくりして、ランドルトは体勢をくずしました。すぐうしろが斜面になっており、転んで、滑って、その先の泉にザブンと落ちてしまいました。
ゆらゆら揺れて水の外が見えにくいですが、狩人がいるのはわかりました。たまがひゅんひゅん飛んできます。それに当たるくらいなら、とランドルトは底にむかっておよぎました。
地獄まで続いていそうな、ふかいふかい泉でした。ランドルトは恐くなって水面に戻ろうかと思いました。でも上には、怒りでわれをわすれた狩人がいます。おぼれて死ぬのと、鉄ぽうで死ぬのと、どちらがいいか。まよっているうちに、ランドルトは空気をつかいきってしまいました。
うすれゆく意識のなかで、ランドルトの頭におもいでが浮かびました。どれもこれも、いやなことで、ろくなものではありませんでした。
このまま死のう。ランドルトはあきらめて目をつむりましたが、大量の泡がジャマをしてきます。自分は吐いていないのに、なぜ? ふしぎにおもって泡の出る方向に目をむけます。
そこにはたいそう美しい女性がいました。沈むランドルトにあわせて、ゆっくり泳ぎながら、泡をだしてなにやらしゃべっています。
ああ、まぼろしだ。これは死んだ。
ランドルトは絶望しましたが、さっきから息ぐるしくないことに気づきました。どうやら女性の泡のおかげで、息ができているようです。
ランドルトは、女性がなにをいっているのか、気になりました。でもここは水のなか、ゴポゴポする音ばかりで、まったくわかりません。
しびれをきらしたのか、女性がランドルトを引きよせ、耳のちかくでゴポゴポしゃべりました。ようやく聞きとれました。
「わたしは泉の精。あなた、オノはもっていないの? 金や銀のオノがありますよ」
「もってない! いらない!」
ランドルトは泡を飛ばしてこたえました。
「もっていないのに、飛びこんだのですか?」
「しかたなく入ったんだ」
「オノのない人に用はありません。ここから出ていってください」
泉の精はランドルトをむんずとつかまえます。
「まってくれ! 水からでたら死んでしまう!」
「ここにいても、けっきょく死にますよ」
ランドルトはだまって泡をはきました。
「出るに出られぬ事情があるようですね」
「実は、そうなんだ。村に居場所がなくて、いじめられて、ころされかけて」
「人間は、自分とちがうものがとにかくきらいですから」
「こんな体じゃなかったら、楽なのに」
泉の精は微笑んで、ランドルトの曲線をなでました。
「なんだか、あなたがかわいそうになってきました。おてつだいしてあげましょう」
「金のオノならいらねえぞ」
「それは聞きました。わたし、物質を変換させる能力があるのです。村人どもに一泡ふかせることもできますよ」
「ブッシツ? ヘンカン?」
「あなたに、しんぴの光を」
泉の精がランドルトの体をなでまわすと、黒色がうすくなり、発光しました。
「光は体を軽くします。どうですか、まえより身軽になったでしょう?」
ランドルトは頭を上に向けました。すると、体がかってに上に行こうとします。
「これはすごい」
「その体でどこへなりと行ってください」
「ありがとう、泉の精さん。うまれかわった気分だ」
「ただし、光らせすぎると命がみじかくなりますから、それだけ注意してください」
ランドルトはぐぐぐ、と力を入れて楕円になると、鉄ぽうのたまよりも速く、泉から飛びだしました。
「あいつらめ、こんなおれを見たら腰ぬかすぞ」
ランドルトはどこへでも行けましたが、まずは落としまえをつけてやろうと思ったのです。あたりはすっかり暗くなっていましたが、自分が光っているなら迷いっこありません。
回転をつけるとさらに速くとべることに気づき、いそいで村へといそぎます。うまく動けず、木にぶつかることもありましたが、ランドルトは傷ひとつつかず、木のほうがたおれました。そこからはよけずにどんどん木をなぎたおし、とちゅうにあった小屋もなぎたおして、ランドルトは村のひろばにつきました。
夜が昼のようにあかるくなったせいで、村は大こんらんです。たしかめようにも、窓から見える光の輪がぶきみだったので、おとなたちはぐずぐずしていました。けれど、こどもたちは興味しんしん、寝まきのまま、ひろばにあつまってきました。
「なんだろう」
「ひかってる」
「さわれるかな?」
「さわりたくないや」
こどもたちが話しているところに、おとなたちがやってきました。先頭には村長さんがいました。みんなが光の輪について、あれこれ自分のかんがえを話しましたが、村長さんには正体がわかっていたのです。
「おまえ、ランドルトなのか?」
答えとして、いっそう強く光りました。
「そうか……」
これは確かにランドルトだとわかった村長さんは、いそいで子どもたちにゲンコツをくれてやりました。
「おまえたち、神のつかいになんてことを! このお方はな、神さまのうしろを照らす、ありがたぁぁぁいお光なんだぞ! わしはまえから、こいつは人とちがうなにかがあるとにらんでおったがやっぱりそうだった! さあおまえたち、ざんげしろ、いまなら天バツがくだらんかも知れんぞ!」
痛みとおそろしさで泣きべそをかいた子どもたちはひざまずきました。
「ごめんなさい、ランドルト」
「ゆるして、ランドルト」
「もうわっかやろうと、ぜったいいいません」
村長さんは手をさすりながら、うんうんうなずきました。そして、村のおとなたちを順番に見ていきました。
「おまえたちも、ガキどもと同じだろう。おまえたちは、ランドルトになにをした。むしする、ばかにする、あまりにひどくて、わしはまともにこやつの顔を見れんかった」
「いやでも、村長だって」
「恥を知れ!」
靴屋の発言はさえぎられました。
「本当にいいのか? いまならまだランドルト、この光の輪さまは許してくださるぞ!」
ランドルトはまた光りました。じかに見るのがつらくなるほどの明るさです。
村のみんなはこれまでランドルトにやってきたことを告白しました。多すぎて、告白というより、おまじないかなにかに聞こえました。
それを見て気分を良くした村長さんは、娘の肩をぽんぽん叩いてから、ランドルトにいいました。
「ランドルト、これがみんなの気もちだ。どうか許してくれ」
子どもも、おとなも、ひれ伏している。こんな楽しい光景を見たことは、人生でいちどもありませんでした。あたまの興奮はからだに伝わり、かげんができなくなりました。
するとどうでしょう。ランドルトの黒い線はじょじょに消えていきます。
「おお、天に帰られるのか! みなのもの、みのがすな!」
村長さんの言葉を聞いて、村人ぜんいんが目を見ひらきます。
「右」
誰かがぽつりとつぶやきました。
「下だ」
「左」
「右上」
「右ななめ下」
言葉にならないおつげが隠れているとでもいうのでしょうか。村人は自分の目にうつる、穴の開いた方向を口にしました。
「上!」
「上よりの右!」
「真下!」
「真上!」
「真右!」
「真左!」
村人たちの声がおおきくなるにつれて、からだは光にのまれていきます。ランドルトはもう、自分のこと、村のこと、すべてがどうでも良くなりました。でも、しあわせなこの気持ちだけは、知れて良かったとおもいました。
円がなくなったとき、ランドルトは世界のどこにでもある光になりました。ただ、それは神さまが与えてくれた天の光とおなじ強さでやみをつらぬき、ほんの一瞬だけですが地上の太陽となったのです。
それきり村人たちは目が見えなくなりました。それでも、ありがたい光の輪が忘れられないのか、朝は広場に集まり、右を向いたり、上を向いたりして、祈りをささげる姿が王国中の関心を集め、いまでは観光の目玉となっています。
〈了〉

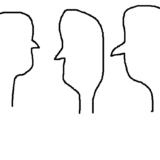




















"木こりのランドルト"へのコメント 0件