四角が見える。四角は近くに見え、あるいは遠くに見える。次の瞬間、四角は球体のなかに滑り込み、白いハイライトになる。
球面上で四角は引き伸ばされ、縮められる。それは回転もしないし、揺れもしない。それは、瞳に映った棺桶の形だ。われわれはそこに引き寄せられる。
遠雷の光はここまで届かない。
ゆえに、ハイライトの反射は破れない。回転しない。揺れもしない。
時折、屋根から垂れ落ちてくる雨粒がつむじ風によって、窓一面に吹きつけられていた。稲妻が光り、そして鳴るたびに、窓の傍にある大きなモミが光を浴びていた。家の中から見えるのは、部屋の明かりに照らされた窓を流れる雨と、時たま姿を見せるモミの木だけで、それ以外は真っ暗な闇だった。家族はとうに寝室に入っている。外の天気が天気なだけに、それほど音に気を使う必要もないのだが、それでも、なるだけ静かに、大きな物音を立てぬように心掛けながら、音楽教師は机に向かっていた。
あらかじめ分けておいたカセットテープを適当に一本選んではデッキに入れ、それを聴いている間に日付や曲名をラベルに記入し、聴き終えたら取り出してそれを貼る。教師はその作業を繰り返していた。貼り終わったテープはケースにしまい、事務机の上にある棚に並べていく。デッキとヘッドフォンを繋ぐ自作のケーブルは何メートルもあるもので、床にとぐろを巻いていた。テープは一週間分の量があり、ラベルを剥がした台紙で屑籠はすぐに一杯になった。
小休憩がてら、教師は台所へ屑籠を持っていった。長いケーブルのおかげで、曲を聴きながら「踊り」を休めることなく家中を歩き回ることができる。これらの作業は誰にも見られたくない、教師のひそかな楽しみであった。
籠の中見を空にし、自室へ戻ろうとしたときにふと、鏡に目がいった。それは、流し台の脇に置かれた洗面用の大きな三面鏡で、左右の鏡は閉じられており、真ん中の鏡だけが台所を映し出していた。その中には、目の下に隈のできた中年の小太りの男が無精髭を生やしてぼんやりと立っている。教師はそれを見つめながら、ゆっくりと屑籠を鼓のように肩まで持ち上げ、底をぽん、と叩いてみた。しかしそれは実際には、ぼふ、と音を立てるばかりか荒い網目が軋むような感触しかせず、かさかさと手の平にどうしようもない虚無感しかもたらさなかった。
“ぽんと、鳴ったらな”
節をつけて心の中で歌い、そして途端にしゃがみこみ、鏡の中から姿を消してみせた。
“いま、おれは鏡に映っていない、中年の太っちょ男だそ。一瞬前までは鏡に映っていた中年男。わははは。鏡なんぞにおれの姿など映させてたまるものか。不完全燃焼したストーブのように、ただただ害悪なものなのだぞいまのおれは。それとも完全無欠の要塞にたった一匹向かう子豚ちゃんだといってもいい。わははは”
教師はにんまりとしてしゃがんだ体勢のままお尻を振ってじりじりと自室へ戻っていった。明日は休みで、夜更かしができる。教師はそう思うたび、一層可笑しくなった。
“おれは歌を教えて、家族を養う子豚ちゃん! 夜は暗い。子豚ちゃんは夜がぜんぜん怖くない! こうやってケーブルをくるくる巻き取るところなんて、まるで子豚ちゃんの釣りのよう! 台所から何が釣れる? ただただケーブルをからめとる! 歌が釣れる。わははは。歌はずうっと流れてる!”
ねじれたケーブルをすべて巻き取り終え、教師は机に戻った。
ヘッドフォンから聞こえてくる歌声に教師は大変満足していた。教師の教え子たちは、なかなか元気よく、そしてのびやかに歌うものだと思った。ピアノ伴奏者も実に良い。
手を休め聴き入っていると、丁度、雨脚が激しくなりはじめた。その音は、歌声とほとんど同じぐらいの大きさになっていった。教師は疲れを取るためなんの考えもなしに、目をつむった。すると突如として錯覚を覚えた。まるで家の外から教え子たちの歌声とピアノの伴奏が聞こえてきたような気がしたのだ。モミの下に教え子たちが集まって歌っている。皆一様におそろいの青いレインコートを着て、雨が目に入ろうが口に入ろうがお構いなしに素晴らしい合唱をしている。そんな光景が見えた。真っ暗闇なのにもかかわらず、モミの下に生徒一人ひとりの顔が浮かぶ。即席で庭石と板を利用して階段状のステージも組んでいる。皆の顔がよく見える。皆の開いた口は背景と同じく真っ黒けだ。しかし、その口からは素晴らしい歌声が流れている。
“いいぞいいぞ”
教師は手探りでペンを持ち、生徒たちが歌う歌詞を生徒たちの歌う速度に合わせて、書類の裏に目を閉じたまま書き写した。曲は転調に差し掛かり、この曲のテーマでいうところの夜から朝へのメロディへと移行していくあたりだった。教師はとっさに我を忘れて叫んだ。
「夜が明け、 新しい朝が訪れて、頚木の上で羽を休める大鳥になった気分のようにだ! そう、そう、そうだ!」
教師は興奮して目を見開いた。そこにあったのは、ぐちゃぐちゃに混じり合いながら書かれていた判別の困難な歌詞だった。それはまるで今晩のこの風景、または教師自身の心象そのもののようだと思い、教師は嬉々として眺めた。ちょっと持ち上げて透かしてみると、おもてに印刷された文字と混じり合って、さらに良い感じがした。
“この曲の、真の楽譜はこんな感じかもしれない!”
幻の楽譜に合わせて、ティンパニを叩くように教師は幻のタクトを振り下ろした。
「三年二組/道を歩けば/○月×日」
「三年二組/麗しき雨/○月×日」
「三年二組/旅人ケルスの朝/○月×日」
「三年二組/馬蹄/」
“「馬蹄」は普段のピアノに加えてドラムセットが入るから、皆まだ勝手が少しわからないようだ。ぶう。そういえばさっき台所へ行ったとき、ついでにコーヒーを淹れてくればよかった。子豚ちゃんはコーヒーが飲みたいな。それにしても、先程からなんだかノイズが混じっている。明らかにバスドラムとは違う、なにやら戸板を叩くようなそんな音だ。こりゃあ誰かが録音中にマイクを触っていたな。まったく! 子豚ちゃんの大事な録音機材を!”
どんどん、というノイズに教師は不快感をおぼえて、デッキのヴォリュームを少し絞った。
その時だった。車のエンジン音が、雨音に混じってうっすらと聞こえてきた。そして、誰かが家の戸を本当にどんどんと叩いている音がした。
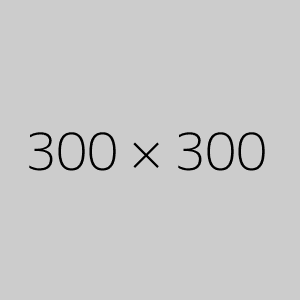























"馬蹄の半夜"へのコメント 0件