朝、目覚めると私の片足が義足なのです。いつからでしょう。私は混乱しました。しかし出会った頃からずっとそうだった、その前のことは知らないが、と叔母も彼女の息子もいうのでした。季節は移り変わり、いくつもの冬の朝を今年も知りました。きらきらなにかの光る夢を見たあとの朝です。いつもと変わりのない雪の朝。静かな朝。都心の記録にしては、例年よりはるかに雪が多いそうです。それは、とても寒い朝でもありました。寒波――。そういった言葉を舌で転がして、黙り込んでいました。しばらくするとどこかで車のドアの閉まる音がしたので、圧が残響となって部屋のなかで膨らみ、やがては消えました。その残響の消音具合で、ははあ、やはり雪が積もっているなと直感しました。今度はその音を喉の奥でモグモグと真似てみました。だん。ばん。だふう。ばふう。ん……。もはやその音自体よりも、部屋を、一時的に二十畳ぐらいにさせたようなぽつんとした残響のほうを真似るほうが似ているようでありました。いや、それは当然だった。ぽつんとしていたのは、私のほうだったからだ。自分を中心として、だだっ広い部屋のなかで一人いるような気がしたのです。寒空の下、雪に埋もれた車を私は想像しました。走っている生身の車――たとえば銀色の乗用車――よりも、ごろんと真っ白な積雪のなかで眠った色形もわからぬ車のほうを想起したのはなぜでしょう。やはり、ぽつん、があったからでしょうか。どんな錯覚だろうと思い、これをみんなにも聞かせようと思いました。まだ、何か夢の中にいるようでしたが、立ち上がり部屋を出たからかもしれません、話の腰を折ったように、ようやくそこで夢は糸のちぎれた凧のように消えていきました。そんな役に立たない夢に、本当に私は心底、悔しい思いをしたのか。何かが体を拒絶させます。それとも、まだ夢の糸はどこかに結ばれているのか。廊下の途中で立ち止まって、私は傍にあった電話機に少し触れてから深呼吸をしました。頭のなかでばかり考えているせいか、舌はまだ喉の奥に引っ込んでいる気がして、夢の中で体感した、生身の肉体と、貨物列車の風になりきらない音との混じり具合や、それから、私が故郷からこの家にやってきた時に荷物を詰め込んで持ってきた、今も探せばこの家の何処かにあるはずの鞄の夢のことを思いました。夢の中で、鞄の中身はなんだったろうか。開けられれば、何が入っていたかきっと知れたはずだったろう。手紙か。野球ボールか。まさか林檎ではあるまい、それは出来過ぎている。あるいは私の片方の足か。
「ふうん。それより、夢のなかで手にしたものと目覚めてから手にしているものが同じじゃないのは何故ですか? 僕また今朝、夢を見たんです。夢のなかでは僕に妹ができたんですけど、起きてみるとこいつ、弟の足が僕の胸の上に乗っかってたんです。かわいい妹が、こいつの足。これってなんなんですか?」
甥の兄のほうがそう尋ねます。洗面台の前で、会った時です。
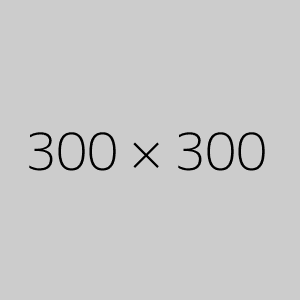























"おはようと言う"へのコメント 0件