同書は村上春樹という世界的な文学者が映画と自身の文学作品の映画化にどう向き合ってきたか、そして村上作品はいかにして映画化されてきたか、というアダプテーションを巡る研究である。いわゆる「受容史研究」とでも言えば良いだろうか。
本書では最初期の村上の映画批評の仕事から、『風の歌を聞け』のようにインディーズ映画として需要された初期、『ノルウェイの森』『バーニング』(「納屋を焼く」の映画化)、最近の『ドライブ・マイ・カー』における成功までほぼすべての映画についても取り上げている。村上春樹が映画からどのように影響を受け、それを作品に生かしたかという逆方向のアダプテーションに関する研究も興味深い。
とりわけチャーミングな一節は同書のタイトルにまつわる解説だ。少し長いが面白いので引用しておく。
明里が指摘するとおり、村上にはこれらの映画批評の仕事を意図的に「消し去りたがっている」ふしが見られる。初期に書かれた映画批評の大半は一九九〇年〜一九九一年と二〇〇二年〜二〇〇三年に刊行された「全作品」集にも収録されることなく、単行本にもまとめられていない。また、村上の唯一の映画本といえる『映画をめぐる冒険』は長らく絶版のままとなっている。村上はラジオ番組『村上RADIO』(二〇一八年〜)でディスクジョッキーとして自分の愛好する音楽を紹介し、『村上T 僕の愛したTシャツたち』(二〇二〇年)ではTシャツのコレクションの一部を披露している。だが、彼が今後「村上シネマ」というタイトルの本を出す可能性は、きわめて低いだろう(だからこそ、本書のタイトルに使うことにした)。
同書、P19
村上春樹の自身の映画批評に対する態度を見抜いて卓抜なタイトルをつけるのは、痛快であるとともにやや「いじわる」でもある。こうした藤城のするどい(かつ、いじわるな)分析眼はそこかしこに見られるので、関心することも多いだろう。村上春樹ファン、映画ファンだけでなく、「著名な文学作品がどのように映像として受容されていくのか」に興味がある方におすすめだ。
また、破滅派の読者の中には藤城のフィクション作品を読み、その技巧的なレベルの高さや合評会で毎回文字数ぴったりに収める几帳面さに驚いた人も少なくないはずだ。ある意味、藤城の本業である映画(表象文化)研究を読むことでその仕事の幅広さに驚かれるのではないか。
近年は『「ドライブ・マイ・カー」論』に寄稿するなど、映画関連の仕事が増えている藤城だが、『村上シネマ』はその中でも金字塔となりそうな予感がする。個人的には「破滅派の蓮實重彦」としてフィクションの執筆に復帰するのも楽しみにしたい。




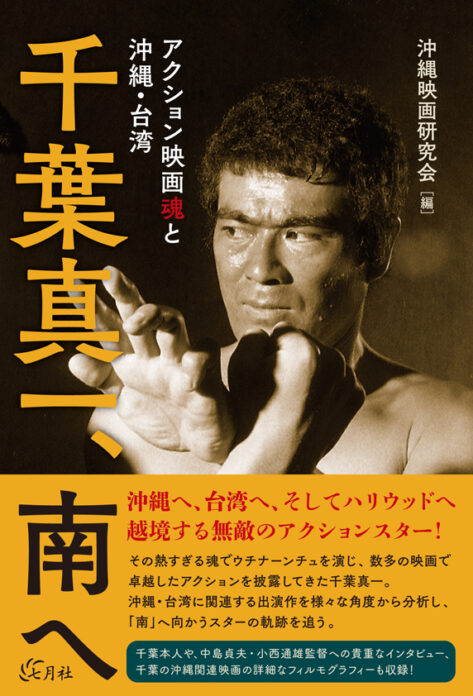




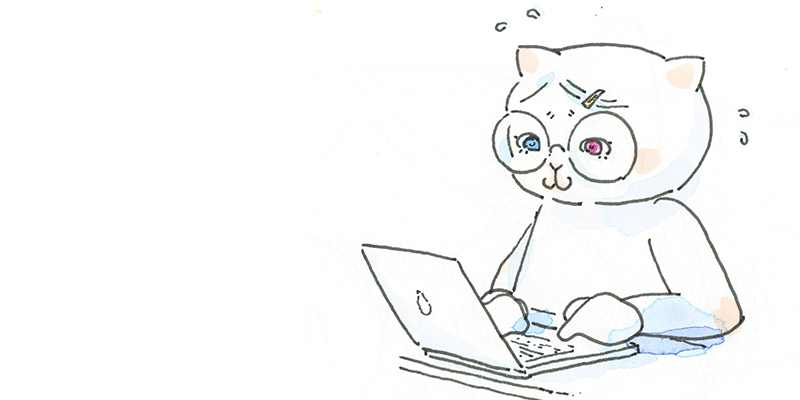
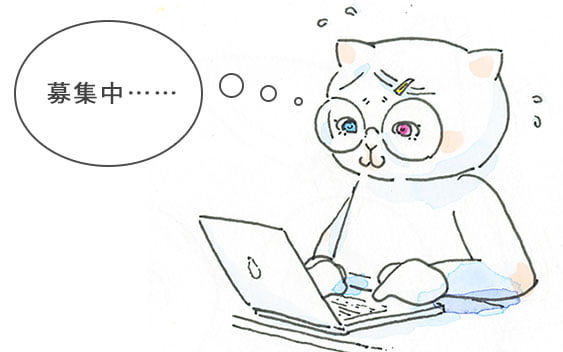












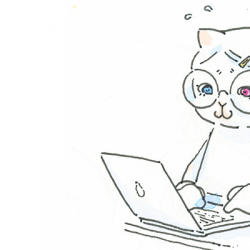














コメント Facebookコメントが利用できます