ヤマシは終りなき夢を見ているらしい。
夕刻のローカルニュースは、ぼくが視聴を許されている数少ないテレビ番組のひとつだ。いつものように灰青色の画面をぼんやり眺めていたら、とうに朽ちたはずの記憶が蠢き出した……
- ……憔悴しきった様子ながら、カメラに向かい不敵な笑みを浮かべる老人。彼は二週間前ひとりで山に入った。帰宅せず連絡がとれなくなったため、アパートの管理人が警察に届け出た。折からの悪天候もあり捜索は難航を極めたが、この日彼は飄然と山麓の農家にあらわれ一杯の水を乞うた。偶然別の取材で近くにいたテレビ・クルーがその姿を捉えたのだ。生還できたことは途方もなくよろこばしい奇跡だが、そもそも山菜採りのシーズンではないし高齢者が単独で登るような山でもない。驚嘆すべき生命力のこの老人がいったいなにを目的に入山したのか、周囲は首をかしげているという……
明けがた、ぼくは冷たい汗にまみれてめざめた。巡回するワンさんの靴音を耳にしながら、夢で古びた獣皮のにおいを嗅いだことに気づいた。差し潮のような過去がひたひたと打ち寄せてきた。
ZZZ
ヤマシという呼び名は『山師』を想起させるけれど、これは全き偶然である。山師とは深山に分け入って木樵や金掘りを生業とする人のことを指す、と辞書にある。ついでにペテン師やサギ師など、うさんくさい輩という意味もあわせ持つ。
往時の北海道は意欲的な山師にとっての理想郷だったそうだ。枯れ木なら無償で払い下げになるというので、ほいほいと枯れ木を『製造』した山師たちがいた。各地にある焼山という地名の多くはその名残りだそうだ。盗伐沢という率直な地名も、ひたむきな資質の山師に由来するらしい。かつて人跡まれな深山を舞台に大盗伐を成し遂げた男がいた。莫大な資産を手にいれた彼は山中に公権力のおよばぬ一大帝国を築きあげた。官吏がはるばる調査にやってきても、みな酒漬けにして追い返したという。何度調べに入っても同じで、ついにはウヤムヤにしてしまったというから驚く。この話には、元大臣の誰某は彼の孫であるというオチまでついている。
ある町がゴールドラッシュに沸いたころは、とれた砂金をサイダー瓶につめて町へ降りてきて、量り売りの酒屋でとめどなく飲みつづけ瓶が空になるとふたたび山へ戻っていく、まるで西部劇みたいな山師たちの姿が見られたという。
ゴールドラッシュ……夢の残滓のような逸話はもはや神話めいているけれど、黄金神話は無造作に時代を越境する。
「南クリル四島は国後、択捉両島を中心に金、銀などの鉱脈が眠る資源の宝庫であり、ロシア政府は四島を含むクリル諸島の資源開発を戦略目標として推進すべきである」……概略だが、かつてロシアの天然資源相が出した声明だ。領土問題への牽制を込めていたのは当然としても、金銀の宝庫というのは事実なのだろうか。
幕藩体制下の金山開発は一六三一年以降すべて津軽海峡以北で行われたそうだが、その歴史は異様なまでに血生臭い。松前藩が金山経営に着手するとともに海峡を渡って金掘りが大挙流入、蝦夷地は空前のゴールドラッシュに沸いた。当時、金掘りには多くのキリシタンが含まれていた。島原の乱ののち強化された禁教体制に抗しきれず、それまで彼らを庇護してきた松前藩は一六三九年、キリシタンの金掘り百六名を斬首した。
金山開発は森林や河川を大きく改変してしまう。さらに金掘りたちによる目に余る所行もあった。一六六九年に勃発した『シャクシャインの戦い』において、シャクシャイン軍のおもな攻撃対象には金掘りも含まれていた。
ある一族が語り継いできた伝承に、つぎのようなものがあるという。……松前の金堀りが金を採掘するため川底をさらい川を濁らせてしまうので、また彼らのあまりに不浄な行為のため、鮭が川へ戻らなくなってしまった。流域の各コタンの首長たちが強く抗議すると、松前側から「たいへん申しわけなかった。ついては詫びの酒宴を催したい」という丁重な招きがあったので、首長たちは連れ立って出掛けたが、そのままだれひとり帰ってこなかった。盛大な酒宴の席で前後不覚に酔いつぶされたあげく、全員陥穴に突き落とされたのだ……
つい近年まで、ある鉄道駅の構内に得体のしれぬ大きな穴跡があり、子どもたちは厳しく注意されてきたという、あそこには絶対に近寄ってはいけない、もし近くを通っても穴のほうを見てはいけない、と。
松前藩にまつわる伝承には、陥穴や釣り天井、酒や食物に混ぜた毒によるものなど、残虐で狡猾な騙し討ちが頻繁に登場する。『シャクシャインの戦い』は松前側の和議の申し入れにシャクシャインが応じ終結を迎えたが、一六七二年十月二十三日、和睦を祝う酒宴のさなか、したたかに酔ったシャクシャインはあっけなく討たれてしまう。同時におもな首長たち七四名もいっせいに斬殺された。
当時の松前藩は交易と金山経営が財源の二本柱であり、このふたつがなければ藩として成り立たなかった。金採掘の途絶を怖れるあまり邪魔者を排除する意図があったことは想像に難くない。それは和議の酒宴を和平成就の全き証しとする古来不変の不文律すら、たやすく踏みにじった。
血生臭い強欲神話は無造作に時代を越境する。
朔風吹き荒ぶ田舎町、そのはずれに佇む小さな丘。……幕末のころ、荒海に出没しては諸藩の御用船を襲う弁慶丸という名の海賊船があった。ご多分に漏れず積荷をごっそり奪われた松前藩はみずからの威信を保つため全軍船を動員した。しかし事前にこれを察知した弁慶丸はただちに松前沖を出帆し逃走、船は数日間大嵐に翻弄されたあげく、いずこともしれぬ海岸に座礁してしまった。やむなく海賊たちは数十万両の財宝を陸揚げし、ヒグマの気配に怯え虻蚊に悩まされながら原生林を迷走、疲労困憊の果て偶然発見した奇妙な丘の洞穴に全財宝を隠匿し、体力の回復を待つことにした。ほっと安堵したのもつかのま、思いがけぬ内紛が生じ、もとより気性の荒い海賊たちは凄惨な死闘を繰り広げたすえほとんどの者が落命、致命傷を負ったわずかな生き残りもときを待たず死に絶えた……と伝えられている。
時代はくだり、戦後まもないころ。地元の郷土史家のもとに突然ひとりの青年があらわれ、自分は弁慶丸の船長の孫であると名乗ったという。祖父の遺言にしたがって財宝を探しにやってきたというのだ。青年はその後十年あまり丘周辺を探ったものの、いつの時代のものとも知れぬ十数体の人骨を掘り出しただけで、財宝らしきものはついに発見できなかった。しかし彼は落胆する様子もなく、船長に造反した海賊の一派がひそかに別の場所に移し隠したにちがいない、自分は一生をかけてもそれを探しだしてみせる、たとえ自分一代では無理でも、自分の子あるいは孫がきっと見つけだしてくれるにちがいない、と語ったという。
ZZZ
一刻も早くここを脱出しなければ……言い知れぬ焦燥に駆られたぼくは、高校を卒業すると明確な将来設計もないまま札幌の専門学校に進学した。ヤマシと出会う二年前のことになる。内心では東京へ出たかったのだけれど担任の薦めに逆らうほどの熱意はなかった。必要なお金を母がどんな思いでかき集めてくれたのか、それを自分がどう感じていたかは、もう憶えていない。いますぐこの町を逃れ出たい……あのころのぼくにあったのは矢も楯もたまらぬ切迫感だけだった。
ひとり暮らしをはじめるにあたり、まずは実入りのよいバイトを探し求めたぼくは、週四日ススキノの24時間スーパーで深夜勤務することに決めた。コンビニが台頭する以前の話である。週四で深夜だなんて無謀という自覚はあったものの、高給の魅力には抗えなかった。
あのころぼくの目に映ったススキノは、酔客をはじめ多彩な人びとの熱気と吐息でいつも靄がかって見えた。スーパーのとなりに事務所を構える筋者、活気に満ちた水商売や風俗業の面々、憑かれたように前のめりな客引きたち、闇の抜け道を知り尽くしたタクシー運転手、威風堂々たる老優みたいなホームレス、そして冥がりに蠢く得体の知れぬ輩……終りなき夜の主役たる彼らは、残酷な天候や苛烈な世過ぎから逃れるつかのまの避難所として深夜スーパーを利用した。
バイトに就いて最初に度肝を抜かれた客は、となりの組事務所に出入りする若い衆のひとりだった……正確にいうと彼は客ではなかった。入店するなりレジ横のボックスからタバコのカートンを無造作に取り出し、あっけにとられた周囲を尻目にそのまま悠然と帰ってしまったのだ。しかもそれは一度限りのことではなかった。深夜店長の鯔岩さんは元捜査四課という触れ込みだったけれど、昼光に晒せぬ制約を抱えていたらしい。なにかと多難な立地の店舗だったことはたしかである。
風俗嬢は温かみのあるタイプが多かったが、まれに厄介な手合いもいた。レジを打っていると、ポイントをオマケしろとゴネ出す。やんわり断ると、ケチくさいこというなと大声を張りあげる。ケチくさいのはどっちだと思いつつ放っておくと、聞くに耐えない悪罵を店じゅうに轟かせる。臨界点ぎりぎりのところで鯔岩店長が駆けつける。
万引きを捕まえるのは得意だった。どういうわけか、しばしば犯行現場に出くわすのだ。店内を見渡し「あ。こいつ、やりそうだな」と目をつけると、ほぼまちがいなく、そいつはやらかした。小学生のとき、親戚のアル中じじいが法事のさなか薄笑いしながらぼくに耳打ちしたことがある。「あのな、いいこと教えてやるわ、おまえの父親はな、運まかせのケチなコソ泥だったんだぞ」。万引きに遭遇するたび、あのときのやり場のない感情がよみがえった。みじめったらしいコソ泥なんか絶対に許せない。捕まえた万引き犯はすぐに鯔岩店長に引き渡したけれど、ここだけの話、ぼくなりの私的制裁を加えひそかに懲らしめてやった奴も少なくない。
ぼくがもっとも苦手だったのは泥酔客だ。絡まれるのは日増しに慣れたけれど、店内を吐瀉物で汚されることには猛烈な腹立ちを抑えられなかった。あと始末はこっちの役目なのだ。そういえば、ぼくの父親もどうしようもない飲んだくれだったそうだ。祖父が遺した貴重な郷土史料すらすべて安酒に換えてしまったという。そのせいもあるだろう、みっともない醜態を晒す酔っぱらいは大嫌いだった。正体なく泥酔しているさまを見さだめ、ぼくなりの私的制裁を加え懲らしめてやった奴も少なくない。
酔っぱらいといえば、とある未明の出来事が思い出される。つい先刻までの忙しさがまるで嘘のように静まり返った店内に、いきなり怒号が轟いた。特売の即席ラーメンを積み上げたコーナーあたりからだった。どうやら泥酔客のケンカらしい。酔っぱらい同士の揉めごとも日常茶飯事だった。バイト仲間の鯒島と目くばせし、同時にため息を洩らした。うんざりだったけれど仕方がない。鯔岩店長は仮眠中だった。ふたりで様子を見にいくと、大量に散らばった即席ラーメンとともに全身黒ずくめの若者が床にノビていた。その傍らで仁王立ちした巨漢が荒い息を吐いていたが、ぼくたちに気づくときまり悪そうに目を伏せた。濃いアイラインが汗に光っていた。「ごめん、迷惑かけちゃった。チンピラがナメたことぬかすもんだからさ、つい。でもたいしたケガはさせてないわよ、いま外に放りだしてくる」そういって呻く若者の手首を掴みずるずる引きずっていった。まるでマンガのワンシーンだった。
「ぜったい空手か少林寺かじってやがるぞ、あのバケモノオカマ」巨大な背中を目で追いながら鯒島がつぶやいた。
ほとんど早朝といってよい時間帯、鯱華は巨躯を恥じるかのようにいつもひっそり来店した。購入するのは見切り品の弁当や惣菜が多かった。
「見た目だけで十分笑わせてくれるのによ、あいつのセコさったら爆笑もんだよな、きょうも半額シール貼ったチンケなカマボコさらに値切りやがった、ありゃそうとう貯め込んでやがるぞ」鯒島があざ笑うとおり、鯱華の吝嗇ぶりはあからさまだった。
あのころぼくの住まいはススキノ南端、六畳一間風呂なし共同トイレのおんぼろアパートで、鯱華は同じ建物の住人だった。バカげた羞恥心からぼくはそれを周囲に伏せていた。鯱華も店内ではそんな素振りは微塵も見せなかった。いま思い返すと鯱華の度量の大きさと自分の愚かしさにたじろぐ。
「あんた学生? なんの勉強してんの」
はじめてアパートの玄関で鉢合わせしぼくはたとき、鯱華はそう声をかけてくれた。それ以来言葉を交わす仲になったものの、おたがい生活時間が違うので滅多に見かけることはなかった。むしろ未明のスーパーマーケットで顔をあわせる機会が多かったのだ。鯱華は職業柄か外見にはお金をかけているようだけど、そのほかは徹底して切り詰めているらしかった。
ぼくはというと、ひとり暮らしをはじめて半年経つころには、授業に課題制作そして週四日の深夜バイトでへとへとに疲れきっていた。なにより慢性的な睡眠不足だった。それでもバイトを辞める気はなかった。母からのわずかな仕送りだけでは全然お金が足りない。バイトあがりにくすねる売場の弁当がなかったら食事すらままならない。この世はお金がなければなにひとつ思いどおりにならないところだ。いずれちゃんと就職でき、それなりの収入を得られるとしても、それまではあと一年半もある。こんな無茶な生活つづけていけるだろうか。そのうち身体を壊してしまうかもしれない。そもそもなぜぼくは母ひとり子ひとりの生家を離れ、われながら不明瞭な進路を選択したのだろう。ぼくが想い描く自分自身の未来とは、いったいどんなものなのか……なによりいつも悩まされているこの薄気味悪いモヤモヤはなんなのだろう……あのころのぼくはわけのわからない亡霊にがんじがらめに囚われていた……いや、もちろんほんとうはわかっていた。それは亡霊なんかではなかった。ほんとうはただひたすら怖かっただけだ。底知れぬ闇のような自分自身が怖かっただけなのだ。どす黒いモヤモヤに押し潰されそうになるたび、ぼくは無理やり思考を封じ、描きかけのキャンバスにむかった。それは当時熱中していたバスキアもどきの絵だった。
そんなある日、鯔岩店長がぼくの顔をしげしげと覗き込んだ。
「いつも疲れて眠そうだけど、今日はまた一段とくたびれた顔してるなあ」
午前三時。客足が途絶えた店内でのことだった。
「えっ、そうですか……うーん、きのうちょっとイヤなことがあったんで、そのせいかな」
とっさにぼくは苦々しい表情をつくっていた。
「イヤなこと、ね。学校でかい」
「……ええ、まあ、なんだかバカみたいな話なんですけど……教室で妙な騒ぎがあったもんで」
「ふうん、騒ぎか」鯔岩店長の声は気遣わしげな響きを帯びた。少し後悔したけれど思わず出た言葉は引っ込めようがない。
「ま、それほど大げさなことじゃないんですよ、なんか授業中いきなり喚きだした奴がいたもんで、それで教室がザワついちゃったんです、ほんのちょっと」
「なに喚いてたんだい」
「……えっと、セカンドバッグ盗まれたとか、なんとか……」
「盗まれた、セカンドバッグをねえ、さぞ貴重品が入ってたんだろうなあ」
「詳しいことはよくわからないけど、新古のクレスタ手に入るんだとか、現金一括なんだとか、きのうからバカでかい声で自慢してましたけどね」
「そりゃ大変だ、で、結局どうなったんだい」
「ほんというと、みんな真剣に取り合わなかったんですよ、そいつ、ふだんから呆れるほど鈍くさいし不用心な奴なんで……落とし物や忘れ物なんて日常茶飯事だし、カバンなんかいままで何度も失くしてるんですよ、こないだなんて財布盗まれたって大騒ぎしたあげく家に置きっぱなしだったこともあって、だから、ほーらまた始まったぞってみんなで笑いものにしちゃったんです、ホンネいうとこんな奴に泥棒あつかいされる筋合いないぞって感じ……で、総スカン喰らったもんで、そいつ、しまいにはどこに置き忘れてきたのかなあ、なんて頭かかえ込んじゃって……なんだかちょっぴり可哀想な気もしたけど、まあ自業自得ですよね」
「なるほどね、そういう人間いるよなあ、危なっかしくてハタ迷惑で、でもまあ、それほど心配してやる必要ないタイプだな、そのうち自覚も芽生えるだろうよ、心配するとしたら、むしろきみみたいな人間だな、おれにいわせると」
「え、いきなりなにいってんすか、店長ぉ」素っ頓狂におどけてみせると、鯔岩さんは大笑いした。「ま、なんでも気楽に笑いとばすのがいちばんさ、あんまりキバったってロクなことないからなあ人生」
つぎの日、目をさますとうす汚れた窓から弱い西日が射していた。万年床のなかで迷ったすえ本日の授業は無断欠席と決めた。こんな日は悪魔ですら寝過ごしているにちがいない。あっけらかんと高い空が胸に沁みる小春日和だった。バイトのシフトも入っていないので、これからのんびり湯に浸かろうと思いついた。ちょうど一番風呂の時間だ。あのころ銭湯代は二百円ほどだったと思う。アパートを出ると、ひと目を惹く二人連れのうしろ姿に出会った。はちきれそうなタイトスカートの巨漢と小柄な金髪ビリケン頭。このみごとな凸凹コンビも銭湯へ向かう途中だった。
あのころ、あの界隈では男湯にスカートという取り合わせは奇異ではなかった。脱衣場で鯱華は嬉しそうに連れを紹介してくれた。このたび同じ店で働くことになった古くからの友人だそうだ。ちっぽけな金髪ビリケンは年季の入った酒焼け声で「鯖奈ですう、よろしくねえ」と値踏みするような金壷まなこで笑いかけた、と記憶している。これが鯖奈との出会いだったと思うが、じつはあやふやだ。たしかその前後、鯔岩店長に誘われて鯱華の店で飲んだことがあり、そのときが鯖奈との初対面だったような気もする。それともやはりあの店へ行ったのは、銭湯でふたりに会ったあとのことだっただろうか。いまとなっては時系列があいまいだ。おぼつかない記憶は、アルコールと紫煙と脂粉の混濁した温気、耳をつんざく哄笑と卑語、猥雑で超現実的なショータイム、朝までつづく妖しい饗宴のせいで、ぼく自身あいまいな次元へ横滑りしたせいかとも思う。
鯔岩店長とふたりで鯱華の勤める店に行ったのは間違いない。驚いたことに鯔岩さんはすでに常連で「このての店がこんなに楽しいなんて、この年齢になるまで知らなかったよ」と照れ笑いした。もちろんぼくも『このての店』ははじめてだったし、そもそもアルコールすら初体験みたいなものだったが、われながら呆れたことに、あんなに嫌悪していたはずの酔っぱらいの一員にあっさりと加わった。鯱華と同じアパートの住人であることはたちまち周囲に知れ渡った。
その後、頻繁に凸凹コンビは連れ立って未明のスーパーマーケットに現れたし、鯱華の部屋に鯖奈が出入りするようにもなった。学校をサボったぼくが仲間入りすることもあった。平日の真っ昼間、おんぼろアパート六畳間宴会に参加するのは文句なしに楽しい経験だった。凸凹コンビの話術は抱腹絶倒だったし、鯱華が長年あたためてきた夢を打ち明けてくれたのもそんな座でのことだった。夢のためにコツコツお金を貯めてきたのだそうだ。
「もうじきなの、かなりイイ線いってんのよ開業資金のメド。んでもって、開店したらさ、あたし絶対に雇ってもらうんだ」鯖奈が酔眼を泳がせた。
「あら、もちろんよ、あんたにゃバリバリ稼いでもらうからね、覚悟しといてよ、ガンガンこき使うつもりだからさ」鯱華は頬を紅潮させ、ひと息に缶酎ハイを呷った。
いずれオープンする鯱華ママの店の名前を提案し合い、ぼくたちは大いに盛りあがった。それぞれふざけたネーミングを披露しバカ笑いしたあげく、ぼくは尋ねた。「ほんとはもう決めてるんでしょ、よかったら教えてよ、いま」
「まあね、いくつか考えてはいるんだけどさ、いまのところ第一候補は『エンドレス・ナイト』ってんだけど、どうかしらね」と鯱華。
「ふうん、なんかイイ感じ、響きがいいね、おぼえやすいし」
「それって、日本語にするとなんて意味なのさ、オールナイトってこと? あ、これも日本語じゃないのか」けたたましく笑いながら鯖奈は自分のビリケン頭を小突いた。
「日本語にするとしたら、終りなき夜ってとこかしらね」照れくさそうに鯱華はつぶやいた。
「へえ、なんか、ますますイイ感じ」とぼく。
「そうかな……そういえばあんた、デザイナーのタマゴだったわよね、オープンするときはさ、お店のロゴだの招待状だの、あんたがつくってよ、ご祝儀がわりにさ」
「そうだね、光栄だなあ、ぜひそうさせてもらうよ」
「あたしのイメージにぴったりなやつにしてよね、とびっきりゴージャスで最高にセクシーなやつよ」と鯱華が笑うと「わんさか客がきて、たんまりお金落としていく縁起のいいやつよぉ」鯖奈がダミ声を張りあげた。
ZZZ
前略
お元気でお過ごしのことと思います。
あなたというひとはお正月も夏休みも帰らず、電話で声を聞かせてくれることもなければ、こうして手紙を書き送ってもまったくなしのつぶて、まあ、みごとに首尾一貫したひとですね。なにをいまさらとお思いでしょうけど。
それでもあなたは無事に暮らしていることと信じています。悪い知らせが届かないかぎりそう信じるしかありません。あなたを産み育てたのはこのわたしです。ただ信じるよりほか手だてはないものと観念しています。
さて、愚痴を書き連ねるのがこの手紙の目的ではありません。きょうはあなたにご報告したいことがあってペンを執りました。
昨晩おそく、鰆子さんが亡くなったのです。鱈金ストアのひとり娘、あの鰆子さんです。彼女は二年あまり過ごした病室をとうとう旅立ってしまいました。ご両親の嘆きようをことこまかに書き伝えるつもりはありません。幼なじみのあなたには十分想像つくはずです。お悔やみのために帰ってこいともあえて申しません。ただ彼女が亡くなった事実をお知らせするためだけにこの手紙を書いています。
あの夏、校舎の窓から転落し脊髄を傷めて以来、ずっと鰆子さんは寝たきりだったわけですが、可愛い声までほぼ失ってしまったのはあなたもご存知でしょう。それでもご両親によると、ほんのときおり、ある程度はっきりした言葉を発することがあったそうです。そんなとき鰆子さんはしきりに「自分は誤って窓から落ちたのではないし、もちろんみずからの意思で飛び降りたわけでもない、うしろからだれかに突き落とされたのだ」、そんなふうに訴えたそうです。でも痛ましい事故として処理されてずいぶん経ってしまいましたし、もとより目撃者がいたわけでもありませんから、ご両親にはどうすることもできません。まして、わたしになにかをいう権利や義務などありません。ただいたずらに時間が過ぎ、鰆子さんは旅立ってしまいました。くりかえすようですが、わたしにはなにもいうすべなどありません。ただ、あれだけ蝶よ花よと大切に金をかけた箱入り娘がこんなことになっちまうなんて、たとえどんだけイヤミったらしい成金夫婦だろうと、さすがに哀れすぎて慰め言葉のかけようもないわ、なんて思うのみです。
けさの壊別は昨日までがまるで嘘のように高くて碧い空がひろがっています。そちらはどうですか。さて、わたしはこの手紙を投函したら、いつもどおり鱈金ストアに出勤するつもりです。これから大忙しです。やるべきことが山積みなのです。店主夫婦がまるっきりフヌケになっちまったもんで、あの店を切り盛りできる人間はわたしだけなのです。
それでは、くれぐれも健康に留意し勉強に励んでくださいね。
草々
追伸
そうそう、こないだ、ふと思いついてあなたの部屋を大掃除していたら、押入の天袋の隅にふしぎなものをみつけてしまいました。とても可愛らしい、いかにもハイティーンの女の子が好みそうなブランドのバッグです。思わず中身をあらためましたが、もうなにも入っていませんでした。あなたには不要なものと判断し処分しました。勝手な行為、どうぞご容赦ください。
ZZZ
あたりまえだけど、人間だれだって矛盾のかたまりだ。首尾一貫した言動や個性なんて、いまどき虚構のなかですらお目にかかれないと思う。以前、ワンさんが教えてくれたけれど、アインシュタインの言葉にこんなのがあるそうだ、いわく……ひとは海のようなもの、あるときは穏やかで平和的だけど、あるときは時化て悪意に満ちています。ちなみに海同様、ひともほとんど水で構成されています……
ふいに心のなかに荒れ狂う激浪を指して『業』と呼ぶひとがいる。とてつもなく邪悪な怒濤に呑み込まれたとき、ひとはどうすべきなのだろう……なにをいいたいかというと……つまり……どうも考えがまとまらない、考えはじめると頭が痛くなってくる……最近ますますひどくなってきた……でもとにかく考えてみよう、たとえばきっかけはなんだろう、思いがけず『業』なんて言葉について考えはじめるきっかけ……まるで連想ゲームみたいだけど……それは卑しく……いがらっぽい……不穏な……酒焼け声……金壷まなこ……あまりに不用心……衝動……あさましくて……古びた獣皮のにおい……どうしようもない……闇……卑しくて……
古びた獣皮のにおい……鯱華のポーチ……馬具職人だった祖父の形見で貴重な逸品なの……鯱華はそのなかに通帳や実印を入れていた。
あの日、鯱華の部屋でポーチを手に考えこんでいた金髪ビリケン頭。引き出しの奥にそれを戻して振り向いたとき、半開きだったドア越しのぼくと目があったのだ。
しばらくして、雪を被った笠地蔵みたいな鯱華が帰ってきた。「おおさむっ、ごめんごめん待たせたわね、さ出掛けましょ、外はものすごい雪になってきたわよ」
ZZZ
あの大雪の夜、凸凹コンビはぼくの就職を祝って心尽くしの宴を張ってくれたのだった。
われながらまぐれ当たりと思った。僥倖といったら謙遜しすぎだろうか。思いのほかすんなり内定が決まったのだ。たとえ吹けばとぶような零細企業だろうと、来春からぼくはレッキとした会社員になる。だれにも恥じることない、まっとうな社会人になるのだ、このぼくは。
もちろん、ここぞとばかりにずいぶん飲んだ、はずだ。大量の浮かれ酒のせいでふいに激烈な尿意をおぼえ破裂寸前の膀胱かかえ仄暗いカウンターにゆらり双手つき鯱華とおぼしき巨躯越しナマズ髭ママに慌ただしくトイレの在処訊ねれば、ええっお便所れふってえ、えっとおそこのドア開けてまっふぐいったらあ、まがりかろにぶつかるからあ、それ右にまがってえ、ふぐ左手にせまい階段あるのれえ、それまっふぐおりたらあ、あっ、らっしゃいあせえ、おひさひぶりい、あ、ちょい鰆子ひゃん鰆子ひゃん、おふたりさまお席ごあんないひてくれるう……あれえ、ろこまれせつめえひたっけえ、あ、えっとお、たひか突きあたりのお、右から二番目りゃなかったかひらあ、あらあ、それとも三番目らったっけえ、あれえっ、どっちだったかひらあなんてなぜか憧憬にも似た驚愕面尻目に冥闇ススキノ雑居ビル最深奥部いっかな約束の地へ到達できぬはどうしたことであろうずいぶん変てこりんな造作のビルであるいったいどの次元にトリップしたというのか次第にのっぴきならぬ状況に陥りつつある膀胱かかえ酔眼蹌踉ススキノ迷宮彷徨ええいっここかとがらり障子戸開ければ乱痴気騒ぎ淫猥なる無礼講の間はたまたここかと思えば魑魅魍魎へべれけ痴情座敷ええいどこだどこだ便所はいったいどこだっ酔客のがなり声うおんうおんこだまする混沌の坩堝もはや一刻の猶予もならぬ切迫の事態おお我が膀胱よ如何なる星の下に生まれけむ冷や汗たらあり目の前まっちろ次のかどまがってもしや到達できぬならばついに万事休す……おおっあったあった便所のとびらがあった、我が約束の楽園、人類の最終到達地、突きあたりの黒い引き戸に手をかけむこうが
わ
に倒
れ込むと同時にビリケンには気づいたのだったがそれというのもこの素っ頓狂な金髪ケチな運まかせのコソ泥よろしく半世紀まえのアニメ主題歌わめき散らしまるでそこを祝祭空間と見なすがごとく狂騒的に脱衣場跳ねまわるものだから、そこらじゅうの乱籠ぶっとび褌やら股引やら猿股やら捨手古やらかろやかに舞いあがり心象の在処次第では華麗とも見紛うばかりふわらふわら頭上に降りそそぐありさまだったのでイヤでもビリケン頭に目を瞠らざるを得なかったのであり、同時にちらり目の端に捉えたかぎりでは舞いあがり降りそそぐ雑多で貧乏くさい肌着類のなかにかぎりなく淡雪めいた桃色かいま見えたことから察するにどうやらここは混浴なのであろうか心もち緊張しつつ粛々と脱衣現世に転げ堕ちた際同様丸裸無一物いざ浴場へいざなう巨大ガラス扉に手をかければ驚愕の高いたかい天井かこぉーんかこぉーん反響する風呂桶の音むっと熱く白く蒸気寄辺なく立ちすくむ裸身直撃巨大公衆浴場ならではの白日夢感慨に浸るまもなく股間をしたたっとくぐり抜けていったは脱衣場の狂騒そのままに浴場へと突撃ビリケンまだほとんど目もなじまずただ蒸気の横溢する空間いったい如何ほどの面積および配置の在りようかまったく判らぬのにあれほどまでに禍々しく無秩序に行動しては危険至極と案ずるまもなく大浴場ならではの反響音に混じり不吉な衝撃音ならびに疳高い絶叫凄惨な余韻伴い足裏から頭頂へイッキに駆け上ったものだからいわぬこっちゃないタイル床に足すべらせみごとなビリケンみごとに華華しく床面に打ちすえしばし仰臥バンザイ金壷まなこで虚空を睨んだあげくやおら起きあがりまるで何ごともなかったかのごとく歌いわめきつつ朝霧のごとき蒸気立ちこめる彼方へ去ったには驚き呆れたものの他人のふり見て我がふり直せ我が母の教え給いし確然たる戒め過剰なまでに貪欲に浮かれ騒いでは必ずや激烈なるしっぺ返しに遭遇せん事必定との警告的表象であろう気をひき締め注意深くそろりそろり一歩また一歩浴場内最深部へ歩みをすすめればようよう我が視界開け濃霧めいた白蒸気緞帳のごとく掻きわけ全体の様子判りかけてきたので多少安堵したものの公立小学校体育館めいた広大な浴場手前半分ほど赤い蛇口青い蛇口ずらり連なる洗い場スペース湯船はさらに後方に位置するらしく蒸気の彼方此方ぼんやり見えかくれするは驚愕の場面ドッヂボオルに興ずる男女児童の群れ、黒光りする将棋盤挟み一手のあいまに手ぬぐいで背をぴしゃりのご隠居連、通路の真ん中に寝そべり丼鉢の沢庵つまみ無尽講に余念のない主婦団、仄暗き一隅に背丸め子守唄口ずさみつつ専心繕物に精出す萎びた老婆等、それぞれ愉悦満喫の様子ではあるもののなにしろ広すぎていったい如何ほどの人数この空間に存在するや判然とせぬうえ照明届かず幽たる片隅には井戸のポンプ操りブリキ洗濯板らしきにむかう黒影やら蒸気に混入して焼魚の煙丼鉢の触れあう音さらに薄汚れたちゃぶ台だの家具什器だの万年床だのかいま見え甚だしきはずいぶん以前から捨て置かれたままと思しき新生児渺々と泣きいさつ声間歇的に響いたりすればさすがに気色悪いことこの上無し極力洗い場の薄明るい辺のみそろり往くよう心がけ信じ難いほど多数の蠢く気配まざまざ感ずるもののそのほとんどは朦朧と影のごとしあまつさえ迸る情欲にまかせ若い男女の睦み合うさまなど幻か現かあまりに判然とし難く強いて無関心装い通り過ぎ往けどもいけども思いおもいにタイル上にくつろぐ影蠢くばかりそれでいて驚くばかり高い天井大浴場ならではの反響音かこぉーんかこぉーん眠たげに轟き夢遊悦楽こそ味わえるもののどうやらこの広大無辺たる浴場のどこにも腰を落ち着ける場所無くすなわちそれほどまでの混雑ぶり群衆の影蠢き辺りに充ち芋洗うがごとき盛況ならば我が身洗おうにも如何ともし難いではないか次第にいがいが苛立ち兆しこの際マナーに反するもののさきに湯船に浸かろうではないかタイル上ぺたぺた歩みをすすめ前方はるか彼方間違いなく浴槽実在するらしいのだこれほど宏壮なる大浴場なのだから当然それは途方もなく巨大な湯船にちがいなく沸き立つウキウキ気分嗚呼はやく茫洋たる大海のごとき湯に身を投ずる愉悦に浸りたいそわそわ昂揚しかしここで浮き足立てば先ほどの金髪ビリケンの二の舞ここは自重自戒気をひき締め過剰なまでに抜足差足摺足そういえばあの金壷まなこいまごろどのあたりで銭勘定ちらり脳裏をかすめハタと気づいた驚愕あの矮小なるビリケンたしかこの手にかけすでに亡きものとしたのではなかったか……アッ、オレハ、ヒトゴロシ、ダッタ……はたしてあれは夢かうつつかマボロシか細い首筋にかけたおのれの指の感触まざまざアッ、オレハ、ヒトゴロシダッタノダ、吹雪の橋から投げ捨てた屍体の残映古びた獣皮のにおいダカラひとの通帳印鑑手にしたトテいまどき他人がカンタンに引き出せるわけないでしょうに強欲ニ目眩んだビリケンはたしてあれは夢かうつつか虚構か事実オレハ、ヒトゴロシ時系列あ、いまい往けどもいけども浴槽にたどりつくこと叶わずどこまでも朝霧のごとき蒸気と群衆の影蠢く洗い場つづくはどうしたことであろうひょっとして想像はるかに超える広大さ一体如何ばかりの総面積誇る大浴場か途方に暮れきってみれば最前から無理にムリに意識の最下層に押しやっていたもはや万事休すの懐かしき根源的欲求すなわち尿意がぜん意識最上層に躍りいで来たぞきたぞさらにはご都合よろしく高さ五十×幅三十×全長九十センチメートル絢爛たる檜製の舟形便器にはや跨りつつある己が態勢すでに尿意耐え難くしてそのうえ何ということであろうこの状況から推察するにこの際イッキに排便まで為すつもりか影のごとき蒸気纏い判然とせぬものの舟形便器の底あたりちろちろ水流の気配すなわちこれ水洗式おまるであるか周囲は白蒸気のなか黒影のごとき群衆蠢き高いたかーい天井かこぉーんかこぉーん大浴場特有の反響音轟く檜舞台檜製舟形おまるに跨る己が足裏紛うことなきタイル床の感触公衆浴場という甚だパブリックな場において不特定多数の眼前において排尿もしくは排便あるいはその両方というまさに究極の極私的行為敢行すべきかそれとも堪え難きを堪えここはひとまず速やかに思いとどまるべきかすでにヒトゴロシの大罪犯しておきながらなにを躊躇しておるのかオレハ、ヒ、トゴロシ次第に切迫決壊しつつある膀胱かかえ迷いに迷
迷
迷
迷
はっと気づけば茜さす逢魔がとき。久しく住みなじんだ小部屋。終りなき夢の翳振り払い、なにはともあれ久遠の大放出とばかり長きながき快楽を伴う迸りののち、ふらつく頭かかえほっとひと息。唖、よかった夢だった、ぼくはビリケン殺してないのだ、なんと酷い悪夢だったことよ、ぼくはけっしてビリケンなんか殺してはいなかった……待てよ、それじゃ、ぼくはなにをしたんだ、いったいなにをして、こうしてぼくはここにいるのだろう……記憶をすこし、すこしずつ解きほぐしていけば……かなりあいまいだけど……思い出せる、かもしれない……まずはヤマシと出会ったころを思い出してみよう、あれからずいぶん長いこと経つんだな、たしかディレクターなんて呼ばれるひとは四人いたっけ、ヤマシはそのなかのひとりだった。
ZZZ
まことにめでたくも、このぼくが就職できた広告制作会社。そこでディレクターを務めていたのがヤマシだった。山蝦蛄さんという不思議な苗字は、若手社員のあいだで中途半端に短縮された。
前代未聞の好景気到来に世間がザワつきはじめたころだった。いまでは信じ難いけれど、世界一の経済大国というフレーズが臆面もなく飛び交っていた。象徴的なテレビコマーシャルのひとつを憶えている。海外アーティストがカタコトの日本語で一言つぶやくだけのもので、そのギャラが億単位というので大きな話題だった。もちろん、ぼくが身を置いたのはそんなのとはまったく異次元の世界だった。
ヤマシは当時としては『らしくない』広告デザイナーだったと思う。クライアントと接する機会が多いとはいえ、いつも堅苦しい銀行員みたいなスーツ姿だった。ほかのディレクターたちがTシャツに褪せたジーンズでどこへでも出掛けるなか、自分のスタイルを貫き通す彼は十分に特異な存在だった。ヘアスタイルはなぜか丸刈りで、それもいまどきのそれとは違い、妙な表現だが昔ながらの折り目正しい坊主頭だった。全体的な印象はまるで近衛兵みたいだった。これも妙な表現とは思うけれど、そんな形容しか思いつかない。背筋をピンと伸ばし閲兵式みたいに足を運んでいた姿を思い出す。デスクに向かうときもシャンとした姿勢を保ちつづけ、度の強い黒縁眼鏡の奥の眼差しは遠い彼方を見つめているみたいだった。
仕事には徹底して理詰めなタイプで、どんな状況でも自分のペースを崩さなかった。部下に対しては必要以上に厳しくも甘くもなく、淡々と指示を出し淡々と自分の仕事に取り組むひとだった。ほかのディレクター連とはなにかと意見が対立しているように見えたが、ぼくは直感的にヤマシのほうを信頼していた。
彼は他人のうわさ話や詮索をとてもきらうひとだった。あるとき、ぼくと同期の女性社員がいきなり泣き出したことがある。版下作業をしながら肩を震わせ泣き崩れたのだ。周囲はあっけにとられて遠巻きに見守るだけだったが、無言で立ち上がったヤマシは彼女の背にそっと手を置き外へ連れ出した。しばらくして戻ってきたのはヤマシだけだった。いったいなにがあったんですかと口々に訊ねても、彼はいつもの口調で「さあねえ」と応え、それ以上の詮索をいっさい受けつけなかった。それきり彼女は会社を辞めてしまい二度と顔を見ることはなかった。いったい彼女になにがあったのだろう。じつのところヤマシにも謎のままだったようだ。とてもおとなしい女の子で、昼休みにひっそりとアガサ・クリスティを読んでいた横顔を憶えている。秘密をかかえたまま彼女は去った。ぼくは内心ホッとしていた。あんなこと訴えられていたらと思うとゾッとする。
あのころの零細広告制作会社は度はずれた日々の連続だった。男女おかまいなく徹夜は日常茶飯事だったし、仕事がひと段落すれば夜食をかき込み失神したみたいに狭い休憩室で雑魚寝、そして再び充血した目でデスクにかじりつき翌朝を迎える、そんな毎日をみんな当たり前のことと思っていた。だからこそなのか、若手の多い職場はつねに一触即発、鬱屈と逸脱の気配に充ちていたようにも思う。闇に葬られた性的災禍はいうに及ばず、さまざまな局面で簡単にタガは外れた。ある深夜、全紙版の広告版下をズタズタに破り棄てた同僚がいた。デジタル化前夜、手作業全盛時のことである。やっと完成させたばかりの当日下版予定の版下だった。彼はそのまま哄笑とともに職場を去っていった。得意先の横柄な担当者を殴り倒した猛者もいた。周囲が必死で押しとどめたものの、あとで彼は「奴の出方次第じゃ、おれマジでヤッちまうつもりだったさ」とサバイバルナイフを見せてくれた。T定規をデスクに叩きつけ高らかに宣言した同僚もいる。「こんなバカバカしい仕事もうやめた、おれ東京行くぞ、おまえら知ってるか、東京で運び屋やればひと晩で三百万になるんだぞ」。ローン破綻した同僚もいた。そんな時間がいったいどこにあったのか、彼は無茶なローンを組んで身動きとれなくなるまで買物にのめり込んだ。進退窮まった彼を社長が親元に引き渡したのだが、社長の後日談によると、アパートの彼の部屋は梱包されたままの家電製品の山に埋もれていたそうだ。だれもが得体のしれぬ激浪の渦に呑みこまれていたようだ。
ヤマシと他のディレクターたちとの溝は日を追い深まっていった。それは具体的な業務内容や福利厚生、会社としてのあり方にまでおよんでいたらしい。資金繰りに駆けずり回る社長がどう考えていたのかはよくわからない。ヤマシが導入を提案するまでディレクター連の脳内にタイムカードという単語が存在しなかったことはたしかだ。自分たちだって被雇用者なのに、彼らは「そんなもの、この業界には必要ないよ」と一笑に付した。また彼らのひとりは若手社員にこういい放った。「おまえら会社で息してるだけで、ひとりあたま月ン十万経費かかってるんだからな、よくおぼえとけよ」。それ以来、ひそかに鼻をつまみ呼吸を止めるしぐさが社内で流行した。いっぽうで「搾取されるばっかでワリにあわないよなあ、おれもう独立しちまおっかな」が口癖のディレクターもいた。そのための行動を起こす様子は一向になかったけれど。
夏も盛りのある日、急遽大きなイベントのコンペに参加することが決まり、ヤマシをチーフとしてプロジェクトチームが編成された。ぼくもメンバーのひとりに加えられた。従来に増してハードな毎日がはじまった。連日どんよりと肌寒い記録的冷夏の年だった。月も星も見えない暗澹たる深夜、またこのまま朝を迎えるのかと自己憐憫に陥ったぼくは、ふと糸が切れたみたいにデスクに突っ伏してしまった。となりの席の同僚はやけくそが昂じたのかシモネタを喚き散らしつつ写植文字を切り貼りしていた。午前三時を過ぎ窓外が仄白くなったころ、ぼくはふいに身震いしながら顔を上げた。呆けた視線のさきが黒縁眼鏡の奥の眼差しとぶつかった。「みんな、ちょっとひと休みしようよ」滑舌よく提案すると、ヤマシは昼間と変わりない歩調で休憩室へ向かった。全員がぞろぞろ従ったあとも、ぼくはひとり冷たく流れる夜明けの雲を見つめていた。
しばらくしてヤマシだけが戻ってきた。ぼくの様子を気遣ってくれたのだろうか。近くの椅子に姿勢よく腰を下ろし無言でコーヒーカップを手渡してくれた。そのまま沈黙がつづいた。熱くて苦いコーヒーがゆっくりと冷えきった心身を温めてくれた。
「疲れるよねえ、まったく」窓外を見つめながらポツリとヤマシが洩らした。自分の目にはまるで疲れを知らないひとに映る……思わず正直な印象を打ち明けると、「ぼくだって疲れてるんだよ」彼は苦笑しつつコーヒーを啜った。そして唐突に「きみには夢があるかな」と、こちらを見つめた。あまりの不意打ちにとっさに返す言葉がなかった。
「……夢って……あの、眠っているときにみる、あれ、ですか」
「ちがうよ、そっちじゃなくてさ、自分自身の将来の希望っていうか願いっていうのか、つまり夢だよ夢。ぼくにはあるんだよ、ここだけの話、長いことあたためてきた夢がさ。だからこんな無茶苦茶な毎日、なんとか持ちこたえてるんだよ」
「……はあ」
彼の眼差しはゆっくりと雲の流れを追った。「自分なりの夢っていうか、なにか特別なモチベーションでもなかったらさ、こんな生活つづくわけないよ、どう考えたって。で、ぼくの場合おおかた決心ついたしさ、そろそろ本気で自分の夢に賭けてみようかなこれからの人生、なんて思ってるんだけどさ、どうかなあ」
どうやら、ぼくではなく自分自身に向かって語りかけているらしい。
「とりあえず、このまま独身をとおすとしたらさ、たとえ年収百万くらいでも、なんとか生きてはいけるんだよなあ」
「……はあ」
「住み込みの造材現場だとさ、だいたいそれくらいが相場らしいんだよ、いま」
「はあ……」ぼくが勝手に思い込んでいた人物像は音もなく崩れはじめていた。
「じつはね、おどろくなかれ、ぼくのひいじいさんてひとはさ、海賊船の船長だったんだよ。あっ、これはほかのみんなには内緒だよ、ぜったい」その視線はどんよりした雲を突きぬけ、彼だけのはるかなる天空を見つめていた。ヤマシがいうには、造材現場というのは財宝を隠匿するに相応しい深山を渡り歩く仕事なので、夢の実現の手段として一石二鳥と思われる……のだそうだ。
その後、コンペの仕事はどうにか乗りきったものの、ぼくの気分は滅入るいっぽうだった。いま思うと、コップの水がついに溢れてしまった状態だったのだろう。会社に向かう気力がすっかり失せていた。それでも無理やり自分を奮いたたせ、なんとか職場までたどりつくのだが、心身ともに重苦しくてたまらなかった。そんな自分自身に当惑しきっていた。おなじころ、同僚の不倫絡みの傷害沙汰や経理社員によるいじましい着服発覚、怒り狂った父親が深夜に怒鳴り込んできた『うちの娘を何時まで働かせる気だ』騒動などが立てつづけに起きたが、周囲の祝祭じみたドタバタをよそにぼくは自分自身の闇の底に蹲りつづけた。そしてある朝、とうとう起きあがることができず、そのままずるずる欠勤しつづけた。
ZZZ
「ちゃんと食べなきゃ死んじゃうわよ、あんた」
野太い険のある声におそるおそる毛布から顔を覗かせると、濃いアイラインのすき間からこちらを見つめるふたつの瞳にぶつかった。「ほら、これ買ってきてやったからさ、無理にでも腹に詰め込みな」
のっそりと布団から這い出し、ありがたく鯱華の好意に甘え、テイクアウトの弁当をかき込んだ。ひさしぶりに胃に入れる温かい食べものだった。
「お茶っ葉も湯呑みもないんだね、あんたの部屋、しょうもないねえ、あたしんちから持ってくるか」
初日に電話連絡した記憶はかろうじてあるものの会社を休んで今日で何日目なのか、自分でもわからなかった。いつ寝ていつ起きてるのかすらはっきりしなかった。
鯱華が淹れてくれたぬるいお茶を啜ると、なぜか母の顔がありありと脳裏に浮かんだ。安っぽい茶葉の香りが故郷を思い出させるのだろう。ちっぽけな丘から見下ろす寒々しい風景、なにもかもが死に絶えたような侘しい田舎町。そういえば鯱華の出身地はどこなんだろう。いままで一度も訊いたことはなかった。
「あんた、ここんとこテレビも新聞も見てないんだよね」湯呑みを膝に置くと鯱華は奇妙な目つきでぼくを見た。「鯔岩さん、死んじゃうかもしれないわよ」
ぼくの故郷は運まかせのケチなコソ泥が死んだ町である。
「ゆうべのニュースじゃ大ケガっていってたけどさ、けさの新聞には意識不明の重体って書いてあった」
深夜スーパーの裏口で鯔岩店長は襲われた。鯔岩さんは必死で抵抗し金庫の鍵が入ったバッグを手放さなかった。
「どうやら一週間前のパチンコ換金所殺人と同一犯らしいってさ」
運まかせのずさんな手口。ふいに鯱華の口もとをよぎったのは厭悪それとも嘲笑か。ぼくは心のなかで冷えびえした町並みを思い描いていた。そうだ、今度あの風景を描いてみよう、妙に迫力ある絵になるかもしれない、いままでどうして思いつかなかったのかな、あの町を描くことを。ちっぽけな丘を迂回するようにモノクロームの川が流れている、丘の麓には小さな橋、幼いころから数えきれないほど渡った古くてみすぼらしい橋、川面めがけて人形を投げ棄てた橋……ある日ふいに友だちのランドセルにぶら下がっているキャラクター人形が欲しくなった。どうしても欲しくて、なにがなんでも自分のものにしたくてたまらなくなった。背筋をつらぬくような懐かしさに似た衝動。だれもいない教室で乱暴にそれを引きちぎりズボンのポケットに入れた。そのまま教室から駆け出しひと息に橋の上までたどりつくと、まわりにだれもいないことをたしかめ、そっとポケットから取り出した。あらためてよく見ると、それはうす汚ないつまらない人形だった。なんだか不吉で忌まわしいものにすら見えてきた。寂寥感のような寒気に汗がすうっと引いた。こんなもの、どうしてあんなにも欲しかったのだろう。自分でもわけがわからず、しだいに怒りの感情が込みあげてきた。怒声とも悲鳴ともつかぬ金切り声とともにそれを川面に投げ棄てた。冷たい灰色の流れにのまれ、キャラクター人形はすぐに見えなくなった……
「……で、きのう手紙が届いたんだけどさ、このあたしに手紙なんて、いったいどこのどいつかしらって思うわよね」気がつくと醒めぎわの夢みたいな声音で鯱華がつぶやいていた。「鯖奈のやつ、けっこう元気にしてるみたい」このときまだ鯱華は、ポーチを盗んだのが鯖奈と思い込んでいた。通帳と印鑑が入ったポーチ、古びた獣皮のにおい……
「すぐ利用停止にしたけどさ、どだいあんなもの盗ったって、あたし以外の人間におろせるわけないのにさ、欲に目がくらむと虫けら以下のバカになっちまうんだねえ、どいつもこいつも」
当然だけど、鯖奈は手紙のなかでポーチについてはなにも触れず、惚れた男を追って出奔したことだけを鯱華に詫びていたそうだ。
「とどのつまり男には逃げられちまうし、なんとか新しい仕事に就いたけど、毎日さびしくて、みじめで、いまは本当に後悔しています、だってさ、ほんとみじめったらしいバカだよね、あいつ」湯呑みに目を落としたまま鯱華は小さく笑った。「……いつだったかテレビで見た古くさい深夜映画いまだに頭にこびりついてんだけどさ、たしかキム・ノヴァクだかって女優がさ、うす汚いシケた路地裏で『みじめな毎日』がどうのこうのってグチってる場面があったのよ、みごとに辛気くさい仏頂面でさ、あ〜ら、こりゃまるっきりあたしらじゃないって噴きだしちゃった、真夜中にひとりで大笑いしちゃったわよ、考えてみたらさ、あたしの知ってる連中だいたいそんなもんじゃない、みんな周りと自分だましながら『みじめな毎日』やり過ごしてんじゃない、そう考えたらさ、どいつもこいつも好きなようにやったらいいじゃない、しまいにゃ、みんなとことん勝手にしやがれって気分になっちゃった」。
あのときの鯱華はなにもかも面倒そうで、自分の店を持つ夢すらどうでもよくなったみたいに見えた。現在のぼくは、あのときの鯱華に教えてあげたい気持ちでいっぱいだ。未来はこんなふうになっているんだよ、と。それというのも、ついさっき鯱華本人がぼくに宛てた手紙をワンさんが手渡してくれたのだ。その手紙によると、このたび鯱華はセリョージャ・パクというひとと結婚したそうだ。こんな年齢になってしまったけれど正式に同性婚が認められる時代になんとか間に合いました、と嬉しそうに文面が踊っている。とはいえ日々の生活は相変わらず難儀している様子だ。強欲と暗愚で国民を蹂躙した権力は滅びたものの、目端の利くひとたちは世界中に散ってしまい、残されたあたしたち……いまや公用語が三つというこの国で……あたしたちはまぎれもないマイノリティなのです、と鯱華は書いている。ちなみにぼくはいま、ワンさんに彼の母語を少しずつ習っているところだ。外界で活用できる見込みなどないのに、現世での残り時間もわずかだというのに。
鯱華の手紙はこうつづいている。長い歳月そこにいるあなたにはピンとこないでしょうけれど、あたしたちはほんとうに苦しい毎日を送っています。なにもかも困難な時勢なのです、少数者にとっては。いまこそ不屈の闘志で先住権を勝ちとった民族に学ぶべき、なんて、すっとぼけたことをいうひともいるけれど、あたしたちにそんな智慧と力があるでしょうか、残念だけどとてもそうは思えません……
それでも鯱華はささやかなコミュニティのなかでなんとか自分の店を切り盛りし、セリョージャと肩寄せ仲睦まじく暮らしている様子だ。
ZZZ
あのころへ戻ろう。思い出すべきことは、さほど残っていない。虚構もひとのいのちも終りは唐突にやってくるだろう。まるでふいに断ち切られる夢みたいに。
ようやく会社に復帰できた次の週、ヤマシはコンペの慰労会を提案した。よせばいいのに、ぼくは重い足を引きずって居酒屋の末席に連なった。そして宴もたけなわのころ、片隅へぼくを呼び寄せた彼は秘密めかしてそれを見せてくれた。手のひら大のうす汚れた皮革の切れ端。ぺらぺらの縁は手擦れで黒光りしていた。古びた獣皮のにおいがした。
ヤマシは黒縁眼鏡をきらめかせ、これこそなによりの証拠なのだとささやいた。「ひいじいさんの形見なんだ、エゾシカの皮でできた財宝袋の一部でね、本来の大きさは米俵くらいかな、いやいや、もっとあるかな、うん、なんたって数十万両だからね、ひいじいさんはさ、なんとかこれだけ残してくれたんだよ、あとは子孫が見つけだしてくれるって確信してたんだなあ、きっと」うす汚れた獣皮の切れ端を愛おしげに撫でながら、彼は遠い眼差しで微笑んだ。黒縁眼鏡のレンズがふいに荒くれ海賊のアイパッチに見えた。
深夜、ぼくは酷い高熱にうなされた。古びた獣皮のにおいに苛まれ七転八倒した。酒席など断ればよかったのだ。なぜ執拗にあのにおいにつきまとわれるのだろう。引き出しの奥のポーチなら橋の上から投げ棄てたはずなのに……なにやら部下にこまごまと指示していたヤマシがいきなり振り向き遠い眼差しで微笑んだ。その坊主頭のてっぺんがパカッと割れ、エゾシカの皮袋を背負った海賊が跳び出してきた。次から次へと大勢の海賊たちが跳び出してきた。きらめく黄金がぎっしり詰まった皮袋を背に、ゲラゲラ大笑いしながら。あまりのバカバカしさにぼくもつられて笑ってしまった。大笑いに笑い、涙が滲んだ。それは目醒めたのちも乾かなかった。
つぎの日、ぼくは職場で倒れ、そのまま入院した。そのあと自分の身に起きた出来事をはっきりとは憶えていない。かなり年月を経てから、かつての同僚が語ってくれたところによると、その後ヤマシとディレクター連の溝はさらに深まったそうだ。社長の信頼はどちらかというとヤマシ側にあったらしい。みずからの資質に思い悩んでいた社長はヤマシに共同経営を持ちかけた。狂騒的な社内の空気はいっそう喧しくなり、お気に入りの部下を集めてなにやら画策するもの、ヤケになって仕事を放り出すものなど、ディレクターたちはそれぞれに騒がしかったし、いっぽう若い連中はこのわびしい企業ドラマの成りゆきを興味津々見守った。当のヤマシはかかえていた仕事を淡々と片付け、短時間社長と一室にこもったのち社員の前にあらわれ、滑舌よく会社を去ることを宣言したそうだ。ちっぽけな会社に身を沈める生きかたと先祖がかすめとった財宝を探し求める人生は、当然のことながら彼にとって比較するまでもなかった。
そしていまもヤマシは終りなき夢を見ている。このケチな運まかせの世界のどこかで。
ZZZ
そしてもうじき、ぼくは終りなき夢から解放される。
…………………………………………………………………………………
◎参考資料
※海保嶺夫「近世の北海道」教育社歴史新書
※更科源蔵「アイヌと日本人 伝承による交渉史」NHKブックス
※更科源蔵「北海道繪本」「続々北海道繪本」さろるん書房
※アガサ・クリスティー、乾信一郎訳「終りなき夜に生れつく」ハヤカワ文庫












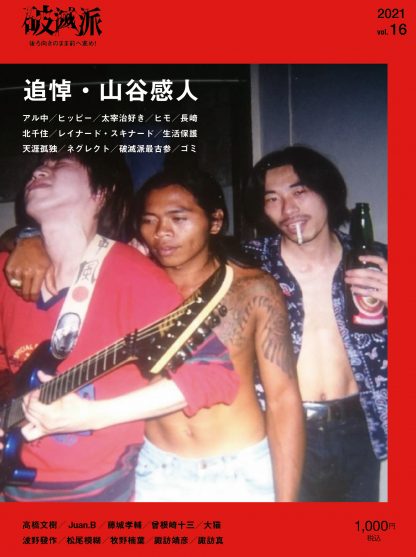













"終りなき夢"へのコメント 0件