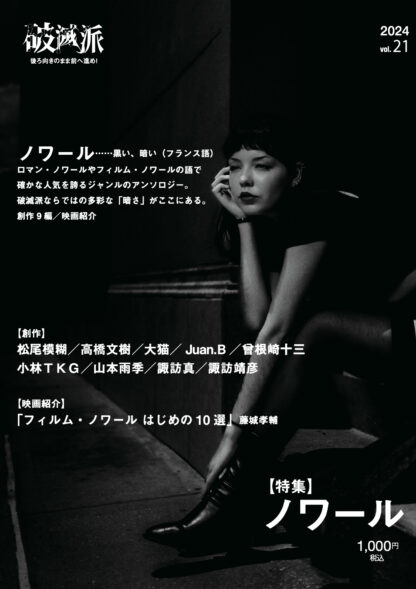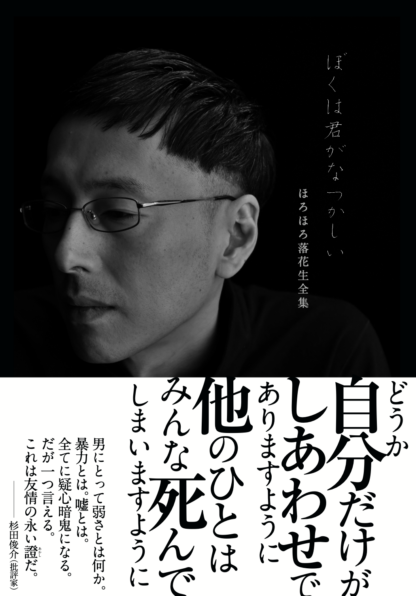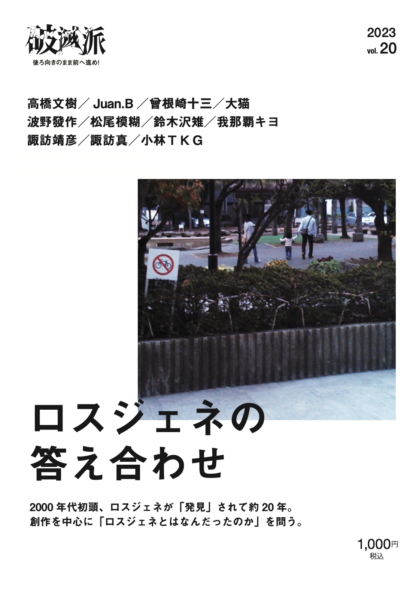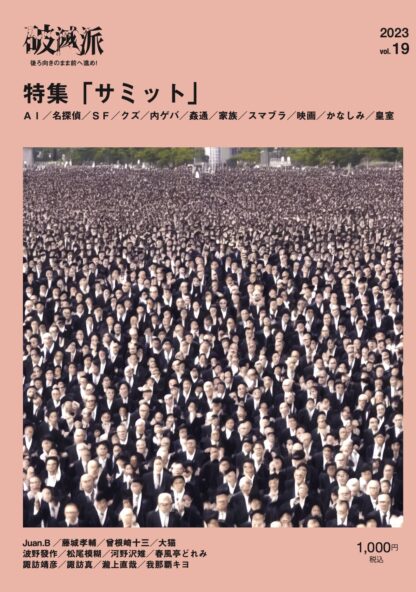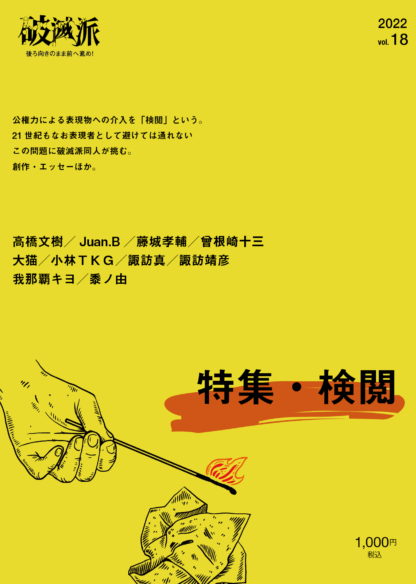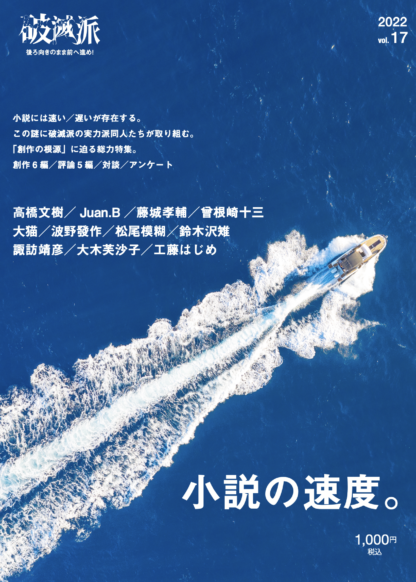-
『大人の童話(五)』――織田作之助 小説
- 7年前
- 1,679文字
織田作之助『大人の童話』はこれにて完結。この終幕を貴方は予想していたでしょうか。余情はあれど、余りにも短いので短編集『素顔』のあとがき、その他関連文章も載せました。初出は大谷晃一氏の著書によると…
-
『大人の童話(四)』――織田作之助 小説
- 7年前
- 2,698文字
大和川で砂金が採れる、という新聞記事は実際にあったのでしょうか。大谷晃一氏の著書によると「十四、五年に作之助は日本工業新聞記者で大阪鉱山監督局に詰めていた。17年に同局の文化委員になった。」と、…
-
『大人の童話(三)』――織田作之助 小説
- 7年前
- 2,318文字
この作品、オダサクが書いた物では無いという可能性はどうでしょう。「ですます調」なのがこの作品の大きな特徴であり、オダサクの流れるような饒舌体からするとかなり違和感があります。他の作品でこのような…
-
『大人の童話(二)』――織田作之助 小説
- 7年前
- 2,708文字
4行目の「擔ぎ思」は間違いなのでしょう、『底本織田作之助全集』では「担ぎ屋」に改められています。三吉の「担ぎ屋」という設定に関しては、昭和12年頃オダサクの妹・登美子の夫・西沢多四郎の呉服の行商…
-
『大人の童話(一)』――織田作之助 小説
- 7年前
- 2,468文字
出来る限り1943年1月発行の作品集『素顔』(撰書堂)の本文ママ。二点之繞は再現出来ませんでした。図書館の倉庫の隅に追いやられた『底本織田作之助全集』では新字体に改められています。この作品は初出…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について⑨~ エセー
- 7年前
- 3,298文字
太宰治、坂口安吾、織田作之助の無頼派3人衆の作品を指して「大人の童話」と言われることがあります。実にしっくりくる言葉ではないでしょうか。彼らの特性は戯れに童話を作り出すことなのだと思います。正に…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について⑧~ エセー
- 7年前
- 3,293文字
オダサクは世界を変えるつもりなんて全く無かったし、何かを訴えたかったわけでもないでしょう。教科書に載るなんてもってのほか。むしろ不名誉です。「どや、おもろいやろ。もっともっと書いたるでぇ。」と、…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について⑦~ エセー
- 8年前
- 3,322文字
小説の歴史の始まりを坪内逍遥の『小説神髄』とするならば、それは1885年のこと。オダサクの時代はそれから5,60年しか経っていないわけです。もちろんその間にも沢山の天才が生まれたわけですが、面白…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について⑥~ エセー
- 8年前
- 5,197文字
坂口安吾も実に文章が上手い。僕は「無頼派」という言い方よりも「戯作派」という言葉の方が好きなんです。確かに坂口・太宰・織田の三人は個性としては「無頼派」でしたが、その文学的特性は文章の巧みさにあ…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について⑤~ エセー
- 8年前
- 5,270文字
こう書いてますが、『可能性の文学』は面白いです。オダサクの作家人生のダイジェストのようなものだと思います。そんなものを死の直前に書き上げるなんて、オダサクには自分の運命が分かっていたのでしょうか…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について④~ エセー
- 8年前
- 4,746文字
70年の時を経て、オダサクは火の鳥の如く復活を遂げようしています。「文豪ストレイドッグス」、「文豪とアルケミスト」でその名前が知られ、電子書籍によって作品が身近になりました。これは本当に10年前…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について③~ エセー
- 8年前
- 4,281文字
オダサクといえば代表作は『夫婦善哉』。「文豪ストレイドッグス」コラボカバーの『天衣無縫』は、『夫婦善哉』からそのタイトルを奪ったという点において非常に価値が高いわけです。この70年間、誰もできな…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について②~ エセー
- 8年前
- 4,332文字
オダサクの命日が十日戎で、尾崎紅葉と福沢諭吉の誕生日と同じだとは知りませんでした。この文章は10年ほど前に書いたものに手を加えているので、内容が大分古いです。オダサクを囲む環境は当時からは想像も…
-
Natural Born Fairies ~織田作之助について①~ エセー
- 8年前
- 5,330文字
織田作之助が亡くなったのは、今からちょうど70年前。享年は今の僕と同じ33歳。最近なんだかオダサクの人気が上がってるみたいですね。『夫婦善哉』の続編や、未発表原稿が見つかったり、ドラマ化されたり…