我々は、顔によって人を、人間を認識している。友人、家族、機嫌、敵意。その感覚は、空間認識に頼るあやふやなものでありながら、シリアルナンバーの様に揺るぎない。
体のてっぺんに、顔がついているのではなく、顔の下に、体がぶら下がっている。顔に体が付随し、人格が付着している。そうやって、我々は人間を感じている。全ての渦の中心は、顔に違いない。初対面の人間に、恐怖にしろ、一目惚れにしろ、何か揺らぎを感じることがあるとすれば、まずはその顔からだろう。
稀に、ただ素通りに街をすれ違う夥しい人々の中に、美醜を問わず、何かしらの印象を心に残す人間がいる。例えば、この男の顔だ。
男の顔は、鋭利だった。振りかざす爪の様に、剥き出す牙の様に、近寄り難い気配があった。ただ、鼻が尖っていたり、目つきが殺気立っていたわけではない。実際、やけに綺麗な色白の肌に、薄い体毛と、彼は中性的な嫋やかささえ持っていた。
肉食獣の如く威圧的だったのは、造形では無く、印象だった。己の表面が薄い皮膜でしかないことを思い出させるその顔。平原に裸を吹きさらしている事を思い出させるその顔。ことに対峙した者に、威圧的な印象を与えた。
しかしひとたび微笑めば、顔全体がぐしゃりと歪み、人好きをする柔和な男に見える。彼が人間と話す際、常時振り撒いている笑顔のおかげで、恐ろしい印象はすぐに影に隠れた。彼はそれを、はっきりと自覚し、鼠取りのチーズのように扱った。
そのせいで、彼と関係する人間は誰でも、雪山遭難中に見つけた小屋のような安堵を覚えた。己を拒否するかに見えた、目の前で開いてゆく堅牢な城門。これのおかげで、彼の罪は捗った。
我々の顔は、人間の顔でありながら、同時に動物の顔でもある。生活がいかに、樹海や沼地、挫滅や炎症から遠ざかろうと、人間はその二重の顔から逃れることは決して出来ない。例えば、化粧は動物の顔を、人間の顔へと近づけるが、化粧というものはむしろ、孔雀や太陽の美しさに倣っている様に。寝ているとき、驚いたとき、激怒したとき、つまりは顔から意識が離れるときに、我々の顔は、動物の顔に戻る。
しかし彼には、普通の人間の持たない、もう一種類の、第三の顔があった。物の顔だ。彼が特殊な条件下で見せるその真顔は、マネキンの様に血の気の無い顔を持っていた。
開かれた丸い目は、ガラスの様に光を反射させ、眼窩の中から、何か別の生物が外を覗き込んでいる様な居心地の悪さを感じさせた。いつも軽やかに笑顔を作る薄い唇は、ピッタリと閉じ、捕食者然とした赤い舌は、磨かれた白い歯の奥で、他人の心の底を計算する嘘を画策していた。彼の犠牲者が最後に見る顔は、この、物の顔だった。
髭の薄い顎を、返り血の映える白い指が這う。マッチのリンの香りの染み付いた指先。そんな男の指は、今、せっせと金庫の暗証番号を打ち込んでいた。中には、通帳、現金等、家計関連の道具が一式。鋼鉄の防護扉は、男の用いてきた力など一切通じなかった。
金は、全て穴の下に眠る女が管理してきていた。男は、家庭に関する殆どの管理に関与しておらず、家の備品に関して、恐ろしく無知だった。それでも、まさか十数桁の暗証番号を、記憶だけを頼りに管理しているとは思いもしなかった。女の部屋を探っても、暗証番号を記録したものは出てこない。所有者を失った金庫は、どうにも頑なに開かなかった。テンキーを弄びながら、男は、実のところ、自分はこの家にとって部外者であったことを感じていた。
業者は最後の手段だ。男はそう考えた、杜撰な死体遺棄や、魅力の薄い客をこの家に招き入れることから、解錠依頼には、強い抵抗を感じていた。やがて、微かな記憶を頼りに試みた、朝から5度の失敗によって金庫にはロックが掛かった。そこで、洗濯機を回すことを考えた。しかし、ここでも男はつまずいた。種々色々のボタンを見回すが、使用法がよくわからない。男は、己が生活の初心者であることを痛感した。
家庭を監督してみると、あちらこちらに目がいく様になった。桟の埃、ゴミの分別、そしてあの、切れた電球だ。男は、生活への無関心と、女の持っていたマメな気質が相まって、そんな場所の電球にはついぞ、気が付かなかった。仮に意識下で気がついていても、認識することがなかった。それほど、この家の家事は、徹底されていた。男も女も、生活の恒常性を好んだ。あらゆる点で違った二人も、ここにおいては、同様だった。あの日を境に、電球と共に暮れてしまった白夜。早々に明かりを灯さなければ。男はそう考えた。
喫緊の財政の問題はあるが、ともかく家事の着手とクールダウンを兼ねて、電球でも買いに行こう。そう考え、コートを羽織り、玄関の扉を開けた。
雪が薄く積もり、庭は一夜にして様相を変えていた。色の差別も、凹凸も、そしてあの穴も、全て磨き落とされ、ただ白く真っ平らな平面が続く。男は、目に映る全てのものが他人のものであるかのような錯覚を覚えた。慌てて己の痕跡を付けるように、足跡をつけて街の方へ歩いた。
男は、ゆったりとした足取りで、大通りと自宅を繋ぐ、無理をすれば緑道と呼べなくも無い路地を歩いてゆく。
じっくりと、猟師が罠の動作性を確かめる様に、アスファルトを踏みしめながら。道の向こうには、街の方へ出る際、毎度通りがかる公園があった。年老いて、痩せこけたあの公園。今日の雪化粧は、あのひび割れた皮膚にも乗っているのだろうか。しばらく歩いていると、例の公園の前に古い自転車が停められているのが見えた。男が公園を覗き込むと、古い木に背をもたれ、タバコをふかす男がいた。
「珍しいな。この辺りに人がいるのは。」
彼は足を止めて、声を掛ける。
「あ、ああ、申し訳ない。最近、吸えるところが少なくって。」
タバコを咥えた男は、一瞬驚いた顔をして、罰が悪そうに、答える。目を仕切りに瞬かせた。裾の長い汚れたベージュのレインコートに、下はジャージ姿。鬢には、白いものが混じる。風采の上がらない。そんな形容句が、具現化した様な男だった。男は、頭を下げながら、慌てて地面に捨てた吸い殻を拾い始めた。
「どうしてこんなところへ?」
「いやあ、珍しく雪が降ったでしょう。5年程ぶりかな?景色が綺麗でね。こんな年でも、少し嬉しくなって、一人で散歩していたんです。」
「子供たちはもう、一緒に散歩してくれる様な歳じゃ無いですしね。ああ、妻は年齢関係なくダメですけど。」そういって照れ笑いをする。
「どうせなら、いつもは歩かない場所を歩いてみようと思って、迷い込んできました。そこで、緑の多い、あつらえ向きの公園を見つけた。街で吸えないタバコでも吸ってやろうと思って。まあ、そんな所です。」
「なるほど。雪は、街の様相を変えるからね。迷い込む、か。確かにここは、営業だの訪問販売だの、社会的な動機から、入ってくる様な場所では無いからね。だから、人なんて滅多に来ない。」
「そんなあなたも散歩ですか?」
「ああ、殆どそんなもんだ。奥に住んでいてね。妻が起きてこないもんだから、久々に、家の用事を手伝っていたんだが、あちこちガタがきていてね。歩いて街の方に買い物を。」
「かつては近くに、社宅団地があったんだ。不況から、もぬけの殻になってしまったけどね。その時分には、ここも賑やかな声が聞けていたらしい。」
彼は、そう言って、遠い目で辺りを眺めた。
「今では、お化けでも出てきそうだ。」
草臥れた中年の男も、同じように視線を泳がせる。
「その通り。この公園自体は、役割を終えているよ。街に代謝されたのさ。もはや廃墟と言える。あそこに見える、サビの塊になったゴミ箱と同じ様に、打ち捨てられた存在だ。捨てられたゴミ箱ほど哀愁を誘うものはないな。ただね、僕がいるんだから、ここは未だに居住区なんだ。どうか不作法はやめてくれ。亡霊は嫌煙家ではないが、僕は嫌う。」
「いや、本当に申し訳ない。」
節目がちに男は謝罪を繰り返した。
「まあ、拾って帰るならいいさ。」
「この辺りに住んでいるのは、あなただけ?」
拳の中にある吸い殻の罪悪感から話を逸らす様に、慌てて沈黙を埋める。
「……今はそうだ。」
彼の目が、鈍く光り始めた。
「そう遠く無い最近まで、もう少し人がいたけどね。」
「どこかへ引っ越してしまったんですか?」
「ああ、遠くへ行った。ここには何も無いからね。ここの虚無に気が付いたんだろう。」
男は笑う。
「それなら、初めからわかりそうなもんですがね。」
「いやいや、生活も、人間関係も、長い間付き合って初めて、自分に徹底的にそぐわないことが分かりきることがあるだろう。」
「なるほど。」
「まあ、社会に参加しようという人間の住む様な場所じゃないのさ。」
「そうでしょうね。居住ならもっと適した場所が。いや、失礼。」
「いいんだ。事実さ。」
「あなたは、なぜ、こんな変わった場所に?ああ、なんの他意も無い。ただの好奇心ですよ。」
「そうだな。まず、持ち家であることを差し引いても、ここには、ある種の魅力があるんだ。なんといってもそれだね。いや、主観的なものでは無いんだけれど。ここには、魔力があってね。魅力を感じる人間がいるらしい。」
「なんと言うのかな。無軌道な動機の先端が、ここに入り込むんだ。」
「目的が無く、それでも目的地を探している人間。広い意味での若者だな。そんな若者人間は、ここへ迷い込む。何故だろうな。」
「まあ、君も、その手合いだろう。」
レインコートのファスナーを締めながら、男は笑った。
「そんな、酔狂な人々との交流が、楽しいといえば楽しいんだ。子を持たない生活人の、ささやかかつ古風な楽しみだ。」
「そうですか。」
「皆、入ってきた理由はなんとなくだ。しかし、『なんとなく』の奥には、実は豊潤な、そして切実な何かが隠れていることが少なく無い。」
「なるほど。少しわかります。」
男は、顔つきに似つかわしくない真剣な顔をする。
彼は、この道に入ってくる人間の特徴について説明している最中、レインコートの男が自分の足元を見つめているのに気がついた。靴を見ると、くるぶしの下辺り、たしかに、2.3適の血痕が付着している。目線を上げると、同時に男と目が合った。
「ああ、ペンキがついてしまっているな。」
彼は慌てもせず、淡々と言い訳をした。
「ガタが来ているのは外壁でしたか。赤とはハイセンスですな。」
男は、安堵した様に笑う。
「…………。」
「うん。そうだな。どうだろう。君、僕のうちに寄っていかないか?どうせ暇なら、コーヒーでも啜りながら、君の持て余したなんとなくを聞かせてくれないか?妻は無口だが、コーヒーを入れるのがうまいんだ。」
「寒い冬に熱いコーヒーですか。魅力的なお誘いだ。」
「ご招待、感謝します。いや、実はね、何となく散歩していたというのは方便なんです。少し悩みごとをしていたんですよ。いや、大切な人へのプレゼントというやつですね。ただ、それが難しい。一体、何を贈ったもんか。もう殆ど捜索ですわ。ここへ来て、頭の中を探っておったんですけど、さっぱり見当が付きませんね。逆に、僕があなたに見つかってしまう始末ですわ。」
肩をすくめて、拳の中を見せる。
「やっぱり一人はダメです。うちに帰って探してみます。なにより、妻をほっぽらかして一人でコーヒーをご馳走されたとあっては、怒られます。帰宅が遅くなった辻褄を合わせるのも、得意じゃない。作り話をするほど、器用でも無いもんでね。」
自嘲的に微笑んだ。
「……そうか。……残念だ。」
「良い贈り物が見つかると良いね。」
「応援ありがとうございます。あなたの為にも頑張りますわ。」
男は、一際、目尻を下げる。男は、自転車にまたがり、振り返りながら別れの挨拶を付け加えた。
「そういえば、街の方で放火があったらしいですね。」
「ああ、どうやらそうらしいね。」
「今は季節からも、火災の助長を受ける。持ち家なら、尚更気をつけてくださいね。」
「ああ、ありがとう。君も、火種の扱いは慎重に。」
タバコを吸うジェスチャーをして見せる。
男は苦笑混じりに頭を下げ、街の方へ去って行った。男と入れ違いに、通りに風が吹き込んだ。
「そういえば、家庭菜園の世話もしなくてはな。」
男は再び歩き出した。
男は、血痕以外、嘘をつかなかった。嘘をつかないことが、この罠の内壁の装飾に適していると知っていた。蟻はどこかへ去って行ったが、再び訪れるであろうことは、わかっていた。
あの蟻は、蜜を舐めた。ここの、猛毒の蜜を舐めた。蟻は、行き先を仲間の蟻に伝えない。なんの得もしないこんな場所を目指す事に負い目を感じるし、その必要もないからだ。その上、ここの蜜は、独り占めすることに価値がある。必ず、あの蟻はここへ戻ってくる。
そうだ。忘れないよう、日記につけなくては。蟻を罠にかける上で、会話を記録する事は、とても肝心な事だ。アドリブとはいえセリフなんだからな。ああ、そうだ。そういえば、日記も見ていないぞ。意外に、生活は大変だな。若い頃を思い出す様だ。
男は、狭い路地の入り口に立った。蜜の香りが漂う、蟻地獄の入り口。冷えた空気の中を、車が交差する。男は、コートに手を入れ、左右の道路を見渡した。
「さて、電気屋はどっちだっけ。」












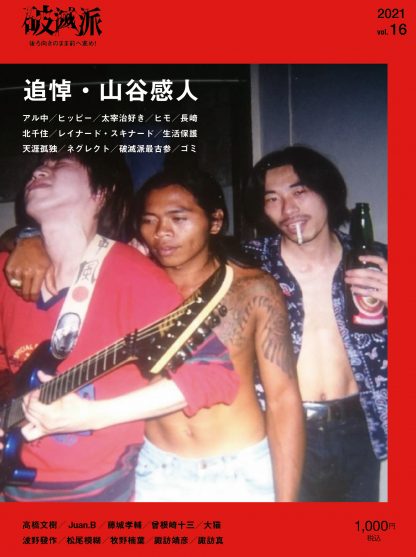













"詐称者"へのコメント 0件