単調な、モノトーンの人生だった。
そう言い切れば、僕の人生はもっとつまらなくなる。とにかく平凡で、平地だった。
山も無ければ谷も無い。それを羨む人は、皆谷がある。
隣の芝生は青く見える。例えそれが自分より劣っていようが。
人が羨む姿を蔑み、自分は自分を否定する。
そんな平坦な毎日だった。
いつも通りの通学路、いつも通りの風景。過疎化が進むこの街に、僕は住んでいる。
全ての色が白黒に見える。
それは僕が卑屈だから? それも正しいと言える。
変化が無い空間に、変化を求める。それもおこがましい。
せめて、誰かが僕に何かをしてくれれば。そう思う。
「・・・・・・ねえ」
夕暮れの時。全体の風景が茜色に染まっていた時間だった。
その瞬間に、春の生暖かい風が僕の頬を撫でた。
背後から声が聞こえた。
それはとても甘く、刺激的で、とても危険な雰囲気を感じた。
その声の方を向く。
「・・・・・・飴食べるう?」
僕の目の前に、僕より少し大きく見える、赤髪の大人が立っていた。
僕の目の前に気配も無く近付いて、声をかけてきたらしい。
黒いフードを被って、見かけは明らかに不審者だ。普通なら逃げ出す程の、異常な歪んだ雰囲気がある。
まるで、現実世界に入り込んできた、異質な世界の存在。現実に元から居たはずなのに。
その人の掌の上には、ラップで包まれた丸い物体があった。
その物体は夕陽の光を受けて橙色に光っている。
その中には、その人と同じ様な、赤色の飴があった。堂々と。
「・・・・・・」
なんとも言えない、重い沈黙が続く。その理由は単純で、僕がその人を拒んでいるから。
それ以上は無い。強いて言うなら、僕は生まれて初めて、学校でたまに聞く様な、最近増えている不審者と遭遇した。第三種接近遭遇。
僕はその人を真っ直ぐ見て、狂気的な目をゆっくり見つめながら、後ろに下がった。
その時、その人がぽつりと、しかしはっきりとした僕への意識を投げかけて、言った。
「いらないなら、置いていくよー」
胸に、電撃が走った。
その言葉を言った後、その人はアスファルトの上に、先程の飴を丁寧に置いて、風が吹いたタイミングに合わせる様に、くるりと軽快に背を向けて、パーカーに手を突っ込んで、さも気分が良い様に、夕陽に向かって歩いていった。
この空間には、僕一人と、その人が置いていった飴があるのみだった。
このまま立ち去るのがここでの一番の良識的行動だっただろう。全人類がそうする。
だが僕の常識的な心の奥底に、まるでヘドロみたいにへばりつく、非常識で、異常的な欲求が、僕の行動の一つを確かに刺激したのだろう。
僕は何の偶然か、飴に近付いたのだ。
それはまるで、いつもの道をそれて、寄り道するような。
それはまるで、卵パックに包まれる卵を、手前から取る所を、奥から取るような。
そんな偶然だ。僕にとっては。
そして、高鳴る心臓を抑えながら、僕は飴を拾った。
それは想像していたより、ずっと重かった。
夕陽の光に照らされて、その飴は真っ赤に透けて煌めいていた。
僕はまた偶然、飴をズボンのポケットに突っ込んで、歩き出した。その人と同じ方向に。
夕陽は沈んでいた。
タワーマンションの玄関が僕を出迎える。上を見れば、地球の天井まで届きそうなタワーが見える。
僕は玄関の仰々しい銀色のドアの操作盤に鍵をかざし、そのままエレベーターで上まで駆け上がった。
薄暗い部屋の電気をつけた。無機質な点滅を繰り返して、白色の光が部屋を包み込んだ。
鞄を無造作に放り出して、僕は真っ先に机の方に向かった。
「おそくなります。チンしてたべてね」
と、走り書きされていた。隣に使ったであろう百均のボールペンが転がっていた。
僕は軽く溜息をついた。普段からこんな調子だ。
満たされてはいない。腹八分目。
丸いこの字を見ると、母親の顔を嫌でも思い出す。その顔は霧に隠れてぼやけている。
母親の声をふと思い出そうとしても、何も思い浮かばない。勝手に、学校の担任の声で、先程の文も読み上げられてしまう。
僕は悪くない。悪いのは母さんだ。
こんな親不孝者に僕をしたのも、きっと母さんなんだ。
僕は高級電子レンジを乱暴に開けて、器を入れた。
唸る様な音が流れ始めた。僕は静かにソファに座り、天を見上げた。
白色の天井が睨んでいる。
温めた肉じゃがを食べ終えた。怠惰な満腹感が僕を満たした。
ベッドに寝転がった。
薄暗い部屋。今は照明をつけるのも、体が動かない。気だるげな悪魔が僕を引っ張っている。
無意識にポケットに手を突っ込んだ。
その時、ガサリと何か感触を感じた。
それを取り出してみる。
あの時、その人から貰った飴だった。
今度は窓からの月光に飴が光る。僕はこれから逃げられない。その人からの呪縛に首を縛られている気分だ。
あの現実に無理矢理入り込んできたような、異質な立ち姿、黒いフード、そしてそこから見えた大きくつり上がった口角。ファストフード店のマスコットキャラクターを想起するような、赤い髪。
その全てがフラッシュバックして、いつも僕の脳内に現れるのだ。あの甘い声を出しながら。
飴は、好きだ。
小さい頃から、色んな飴を買ってもらっては、食べていた。特に好きだったのが、りんご味。
そのリンゴ味の飴は、似たような赤色をしていて。
まるでその人からの飴が、化けの皮を被っている様だ。
・・・・・・でも、僕は心に小さく、例えるなら千ピースのパズルの一ピース程の大きさの。
好奇心が芽生えているのだ。
この飴を舐めたら、一体僕はどうなってしまうのだろう?
もしかしたら、毒が入っていて、楽に死ねるかもしれない。この生活にさらばと手を振れるかもしれない。
いや、更にどうだ?
またその人に会えたら。僕のモノトーンの日常に、あの赤い色が染まるかもしれない。
いくら危険な目にあっても、僕にはそっちの方がよく思える。
僕はベッドから立ち上がった。
飴をじっと見る。相変わらず、赤く光って僕を誘惑している。
大きく息を吸う。心臓が体験した事が無い程、バクバクと鳴っている。今にも爆発してしまいそうだ。
乱雑に包装されている、ラップを外す。
飴が少し手にくっついている。
それを、ゆっくりと僕の中に入れた。
僕は、芽の様な好奇心に巻き付かれ、堕ちた。
イチゴ味だった。
結局翌日になっても親は帰ってこなかったし、雨を食べても特に異常は起きなかった。
あの飴は正真正銘のただの飴だった様だ。
例えるなら、警報が出ることを期待して待っていた台風が、被害を出さずに過ぎ去った様な気分だ。
僕は軽くため息をついた。
七キログラムのリュックサックを背負って、皆がにこやかに、僕だけを疎外する様に歩く通学路を歩き。
授業では、適当に手を挙げて。
思ってもいない意見を述べて。
結局タイミングが合わず、その人の事は言えずじまいだった。
そして、昨日と全く同じ時間、同じ道を通った。
夕焼けがまた昨日と同じ様に、茜色に街を染める。
まるで、夕陽が昨日のその人との出会いを無理矢理にでも思い出させようとしている様だ。
あの強烈な光景が頭から消えない。
帰って頭痛薬を飲もうとした。そうしてうつろに歩いていた。
「・・・・・・やあ」
何だか、あの時の光景がフラッシュバックした。
いや、それも当たり前。
あの時の声と全く同じだ。
「あの飴、食べてくれた? 食べてくれてたら、お兄さん、とっても嬉しいんだけどなあ」
僕は後ろを振り返れずにいた。昨日より圧が強くなっている気がする。
「またあげるね、君可愛いから♪」
その人が背後から耳元でそう言うと、僕のリュックサックが がしりと掴まれる感触がした。
かなり力が強い。
そうすると、リュックサックのチャックが、その人の手によってジリジリと上げられていく感触を感じた。
「ここに入れとくね」
そして、リュックサックの中をまさぐられ、その人が持っていた飴が中に入れられていくのが分かった。
しばらくして、またリュックサックを掴まれて、チャックを閉められた。
「よっし!」
そう大きな声で言われると、バシッとリュックサックを叩かれた。反動で少し前に転びかけた。
その隙で、僕は無意識の内にその人の方を向いた。
僕はその時、前までの不気味で異質なイメージが少し飛んだ。
その人は、不審者という言葉とは似ても似つかない程の、純粋な笑顔をしていた。
例えるならば、初めての小学校に通う小学一年生。例えるならば、飛び立つ事を夢見ているペンギン。
その笑顔は、僕がその人を不審者だと思わせる事を許さなかった。
「じゃね」
そして、その人は去っていった。手を振りながら。極めて純真に。
家の中、また孤独に一人考える。
あの人は、何故僕に付きまとうのか。
あの声がまた、僕の中に流れ出す。
「またあげるね、君可愛いから――」
昨日とは少し違った。不気味さが薄れて、何だか優しく感じた。
それは僕が狂ったからだと言われるかもしれないが。だが僕はそれを否定も出来ない。
自分の事を善だと思っていても、知らぬ間に悪に堕ちたりしている事もあるのだ。
自分が思っている事が全て正しいとは限らない。
僕がその人に惹かれている・・・・・・?
そんな事は有り得ない。と信じたい。
いや、相手はただの不審者。そこまで友好的な関係になる必要も無い。むしろなってはいけない。
そうだ、その通りだ。
頭を自分ではたいて、僕は意気揚々と気持ちを切り替え、宿題をしようと鞄から筆箱を取り出そうとした。
その時だった。
中を漁る僕の手に、硬い感触が襲った。
小さく、硬く、丸い。
僕はそれを取り出す。無意識の中。
「・・・・・・」
忘れていた。僕はあの呪縛から開放されたと、思い込んでいただけだった。
先程の通りだ。
自分が思っている事が全て正しいとは限らない。
手には確かにあの飴が握られていた。
赤く、またラップに包まれている。
昨日と全く同じだ。気持ち悪い程。
その人は、また自分に、飴を食べてもらいたい。
そう言っていた。
その理由は分からない。何故僕を選んだのかさえ。それこそ、ただ僕が目に付いただけなのかもしれない。
僕も、ただ偶然その人と会っただけ。だから飴を渡された。
そのめぐり合わせは運命か、必然か。
僕はこれをどう処理すれば?
親は仕事で忙しく、友達は少ない。
僕には、誰も相談相手がいない。だから自分で解決するしか無い。
昨日の事を考えると、あの飴はただの飴だった。
その人はただ飴配りをしたに過ぎない。大阪には飴を渡してくるおばちゃんもいる。
接触の仕方がおかしいだけなのかもしれない。
本質は何も変わらない。
僕はいつかの学校でこう言われた。
初めて学校という環境を知ってすぐの頃。窓から差し込む日光と、教室の甘酸っぱい香りが漂う中、新任の担任はこう言っていた。
「もし、皆さんが町で誰かに声をかけられて、助けてほしいと言われたら、その人を助けてあげなきゃいけませんよ」
その先生は若い新任の女性だった。
騒ぐ生徒達を、自身の声の大きさと、邪魔をさせない威圧で、あんな話をよくしていた記憶がある。
そして一年後、ベテランの男性教師がこう言った。
授業を踏まえ、イカのお寿司という言葉を混じえて。
「うん、まず最初にイカのお寿司のイカだな。このイカは、行かない。知らない人について行ってはダメだぞ。先生との約束だ」
その先生は、子供を良くも悪くも、実年齢より小さく見る癖があったので、生徒からたいそう嫌われていた。
だが、特徴的な声は未だに耳に張り付いている。
人間不信になりかけていた僕からしてみれば、その事はあまりにも滑稽で、馬鹿馬鹿しかった。
そして、あまりにおかしかった。
大人は皆、正しい訳じゃないのだと。大人の言う事実が二つ存在している時点で。
この矛盾を、僕はどう処分しよう?
自分が言うのも何だが、子供に重い責任を背負わせている。
事実を自分で決めろと。
知らない人に親切にしなさい。
知らない人にはついて行くな。
信じる権利は子供に握られ。
これ以上は僕も限界かもしれない。奇妙な存在に干渉し過ぎたかもしれない。
僕は干渉を続ければ、自分自身も奇妙な存在になってしまう予感がしていた。
だから、これでお終いだ。
飴を胃の中に沈め、そしてもう二度とその人には近付かない。
そうしよう。
飴とも、その人ともおさらばして、現実の世界へ戻ろう。現実の、つまらない人になろう。
そうするのは少し惜しいけど。
あの飴の甘ったるい感触が舌に、朝になっても張り付いていた。
朝になっても親はおらず。僕は相手を求める様に、テレビをつけて、明るい笑顔で中継をしている女子アナを見ていた。
下校の道を少し変えた。あの夕陽が見える場所から、少し開けた道を通る事にした。
呪縛から離れようとしている僕を、僕が意気地無しと笑っている気がする。
心の中に、悪い僕が居て。
いつも僕を嘲笑う。
僕はそれに頭を下げて、屈服する日々。
そうしなければ自分が崩れてしまうのだ。
悪の自分が目覚めて、常識から外れてしまう。
出来るだけ下を見て歩く。そうすると、視界には石だけが映る。
誰も何も干渉しない。頼むから放っておいて欲しい。
孤独を望む訳じゃない。平常を望んでいるのだ。
下を向いていた僕の前に衝撃が走った。
誰かにぶつかった。
ようやく前を向く。そうすると、僕の目の前に、僕と同じ中学の制服を着た男子3人が居た。
「これはこれは、孤独の王子様ぁ」
確かこいつらは、学校で僕の事を、よく変なあだ名で呼んできていた。
僕が実質一人暮らしをしている事から、孤独。そしてなまじっか頭がいいから、王子様。
何回か暴力を振るわれた事もあった。
誰も居ない放課後、トイレに呼び出されて、弱者を虐めてリンチ。
そうしなければ自分を保てないのだ。いえば僕よりも弱者。
頬を殴られる衝撃を喰らえば、視界が歪んだ。
腹を殴られれば、この世界から空気が消える。
あの時の傷は未だに残っている。頬にはカッターナイフで切りつけられた切り傷が、僕の目の当たりを貫いている。
腹を見れば、青あざがあった。
あれ以来、関わらない様にしていたのだが。
神は僕を消したいらしい。
「ぶつかってくるなんて、いい度胸じゃねえか。俺達に復讐か?」
ニヤニヤと薄気味悪く、僕の方を見つめてくる。
僕には彼等が悪魔に見える。
人の事を理解出来ず、ただ自分の欲求の為に平気で人を傷付ける悪魔。
僕は深呼吸をして、平常を貫こうとしていた。
「返事しろよ! ああ!? 王子様ァ!」
胸ぐらを掴まれて、僕の体は宙に浮く。
身長差があって、抵抗が出来ない。
そして、あの時のトラウマが脳の奥底から飛んで来た。
カッターナイフの刃が出る、ガリガリという音が聞こえた瞬間、僕の心臓が急に活動を早くし始め。
「左眼もやられたいか!?」
咄嗟に左眼を手で塞いだ。傷がついている右眼があらわになった。
居もしない救世主の存在を祈る。
だがもう遅い。この状況を創り出したのは、他でもない、僕なのだから。
身を任せようと、力を抜いた。
その時、僕の耳から、ダダダという大きな黒いブーツの足音が聞こえた。
そしてそれを感じた後。
「・・・・・・? ぐはあ!」
真ん中の男子の右側に居た男子がいきなり前に吹っ飛んだ。
「!? 何だよ!」
思わず、カッターナイフの男子も僕を離し、僕はアスファルトの下に落ちた。
背中をさすりながら、僕は吹っ飛んだ男子の方を見た。
その僕の目の前には。
「・・・・・・俺の子だよ」
その人だ。
赤い髪をかきあげて、酷く冷たい目をしていた。
ドロップキックを喰らわされた男子は、身動き出来ずに倒れていた。
「・・・・・・誰だよ、この人・・・・・・」
男子の顔は、真っ青に歪んでいた。目の前の現実に理解が追いついていない。
「・・・・・・手ェ、だすなよ」
そう呟くと、その人は僕にカッターナイフを突きつけていた男子に、ドロップキックを喰らわせた。
「うぐっ」
声にならない声をあげて、その男子は僕の視界から消えた。
そして代わりに、その人が前に現れた。
ブーツのドロップキックの痛みは想像したくもない。
「・・・・・・ふう」
一息つくと、その人はパーカーのフードを直した。
「・・・・・・ひい」
攻撃を喰らわなかった一人は走って逃げだし、残りの二人は地面を這いながら、ここから逃げていった。
僕はその人の方を見上げた。
目が合うと、その人は僕の方へ駆け寄り、僕の肩を両腕で掴んだ。
「大丈夫!? 怪我は無い?」
「・・・・・・はい」
そうとしか、言い様が無い。
「・・・・・・良かった・・・・・・災難だったねえ」
そう言いながらその人は、僕の制服を手ではらい、塵を取っていた。
「・・・・・・僕」
そう言いかけた時、その人は僕の事を大きい腕で抱きしめた。
パーカー越しに心臓の音が伝わる。
体温が暖かい。
「・・・・・・自分を否定する様な事言わないで。生きてるだけで偉い。それでいいじゃん。・・・・・・誰も愛してくれないなら」
その人は顔を上げた。
「俺が愛すから。君の存在が必要だって事、どうか忘れないで」
そう言い残し、その人は僕の頭を優しく撫でた後、立ち去って行った。
残されたのは僕一人。呆然と地面にへばりつく。
その後、通行人に声をかけられ、僕は現実に戻った。
僕の脳内組織がエラーを起こした。
例えば、予定通りに着くはずだった路線バスが、渋滞で遅れた様な、そんな感覚だ。
まさか、こんな事になるとは。
僕の思考をかき混ぜてくる。
不審者で、僕を貶めようとしていた、そう思っていたのに。
その人は、僕を助けてしまった。
無意識下で、僕はその人を敵だと、思っていた。
現実と虚構の狭間。相容れられない存在。
何をやっても、その人の心理は理解出来ないと、思っていた。
思っていたのに。
人に備わっている良心、それがその人にも備わってしまっていた。
それはその人が現実の存在で、相容れられる存在だと・・・・・・。
悪夢が、本当は夢では無い。逃げられない。あの恐ろしい世界から。
夢なら、夢のままの方が良かった。
非現実的な物が、現実になる事程、ワクワクするが、恐ろしい物は無い。
僕はこの状況から、強制的にある事実を理解させられる。
それは、その人が傍から見ればただの飴を配っているお兄さん、という事になってしまった事。
非日常への好奇心は消え去ってしまっていたが、その人を僕が不審者として通報出来ないのがもどかしい。
いや、これは立派な声掛け事案だ。事案に立派な物は存在しないが。
だが、その人が何者であろうと、その人が僕の事を強引ながらも助けたという事実は変わりない。
子供に危害を加えたが。それも正当防衛か?
彼は何者なんだ? 敵なのか? 味方なのか?
中立という存在が、ここまで恐ろしく感じたのは初めてだ。
どっちつかず。それが一番恐ろしい。
なら、今、はっきりさせよう。
あの人の真意を聞き出そう。
それで、僕は駄目なら決別してしまおう。
そう心に誓い、布団に潜り込んだ。
デジャブ的な空気が立ちこめる夕方。
これは何回目の夕陽だったか。
前まで何気なく通っていたこの道が、今は現実と虚構の境界が緩む、不思議な空間に感じられる。
今更現実には戻れない。虚構の存在と混じってしまった。だから僕も現実の存在では無くなってしまった。
黒が混じった白はもう白には戻れないのと同じ様に。
でも今更後退しようと思わない。せめてここまで来たからには、もうこのもやもやとした現実と虚構の混じった世界におさらばしてしまおう。
そうして、夕陽を眺めていた。
初めてあの人と出会った時と同じ様に、ただただ前を向いている。
そして、背後から声が聞こえた。
前と同じ、背中に張り付くような声だ。
「やあ」
あの人だ。このままだとまた相手のペースに持ち込まれる。
僕はその前に言った。
初めて後ろに振り返り。
「ん?」
フードの奥から目が合った。穏やかな優しい目だった。
「・・・・・・何で、僕にそんなに執着するんですか」
僕は目を真っ直ぐ見て、そう言った。
その人は手を顎にあて、斜め上を見て、うーんと唸って、そして言った。
「・・・・・・うーん、強いて言うなら、・・・・・・君の事が心配だったんだよ」
予想だにしない答えだった。意識が歪みそうな衝撃。
「君って、さ。実はちょくちょく見てたんだけど、いっつも暗そうな顔してて、見てて悲しくなっちゃうんだよ」
僕の事を誰かが、気遣ってくれていたのか。
「・・・・・・だから、君と話したかったんだ、飴もその為。怖がらせてたらごめんね」
そして彼は少し悲しそうに笑った。
「・・・・・・あ」
嗚咽が漏れた。
自分はずっと、世界から干渉せず、そして誰からも気にされず、そして死んでいくと。
ずっと思っていた。僕は無意味で、無価値だと。
だが違った。
少なくとも、僕は、誰かから気にして貰えていた。
僕はその一人分だけ、価値があった。
世界に干渉していた。
僕はこの世界に存在していたのだった。
「・・・・・・お兄さん」
自然とそう呼びかけた。僕は。
「飴、ください」
そうとだけ、言った。それ以上の感謝の言葉が他にあるものか。
あのお兄さんは悪い人じゃなかった。
僕の事を心配して、そして助けてくれる。
あんなにも良い人だったなんて。
僕は過ちを犯してしまっていた様だ。
親切心を、踏みにじる訳にはいかない。
これからは、お兄さんと仲良くしよう。
お兄さんが僕を望んだのだから。
翌日から、僕とお兄さんの飴を通したコミュニケーションが始まった。
僕は夕方、あの道でお兄さんを待ち、そしてお兄さんが来れば、少し話をして、飴を渡され、別れる。
それだけの毎日。
だが僕はそれだけでも嬉しかった。
人と接せて、そして話して、普通に別れる。
僕に生きている価値がある、そして存在して良いのだと初めて思えた。
僕は生きている。
生きているんだ。
そして誰かに必要とされているんだ。
お兄さんがそれを教えてくれた。
僕はお兄さんのおかげで生きていた。
そんな日々がしばらく続いた。
毎日の様にお兄さんがくれる飴を舐める。
例えるなら、命という重りを支えている柱が、いつの間にかお兄さんの飴にすり変わっている様だ。
僕はお兄さんに生殺与奪を握られている。それでも僕は構わないと思える。
唯一の友人で、大人のお兄さん。
僕がお兄さんに必要とされている事を誇りに思う。
その日はいつもの特別な日だった。
夕暮れ、学校が終わりいつもの道を歩くと、そこにお兄さんが立っていた。
「おお、お疲れ様」
お兄さんはにこやかに手を振ってくれた。
風が吹くと、お兄さんの赤色の髪がなびいて見えた。
そして、すぐに走って、お兄さんの元へ行こうとした。
体勢を崩した。石も何も無いのに。
その瞬間に見えた景色は、水彩画を水で溶かしてグルグル回した様に歪む。
お兄さんの顔も見れないまま。
僕はその場に倒れた。
「――大丈夫・・・・・・?」
視界が闇に包まれていた中、お兄さんの声で目が覚める。
優しく甘い声が僕の脳内に反響した。
現実に引っ張られ、はっと起き上がった。
先程の夕日がもう沈んでいる。
「・・・・・・僕」
意識が朦朧として、力が入らない。
「送ってくよ」
お兄さんがさっとそう言うと、背中に僕を抱き、歩き始めた。
高い景色から沈んだ夕陽が見えた。
そして心地良い揺れに目を瞑ると、意識が地に落ちていった。
「――着いたよ」
お兄さんの声で目が覚めた。
「・・・・・・ああ、うん」
僕はお兄さんの背中から降りた。久しぶりの地上で、少しふらついた。
「お兄さん、ありがとう」
「うん、どういたしまして」
感謝もそこそこに伝え、家に帰ろうとした。
その時、お兄さんが後ろから言った。
「あ、そうだ。俺、身体にいい飴持ってるんだよ、君にあげる」
振り返ると、お兄さんが飴を投げてきた。
それを咄嗟に掴んだ。握った手の中を見ると、いつもとは違う、青色の飴があった。
赤色の飴とは対称的に、それは例えるならば小学五年生の夏休みの青空の様な色をしていた。
「じゃね」
お兄さんはそう言うと、パーカーのポケットに手を突っ込み、飄々と口笛を吹きながら歩いていった。
きよしこの夜のメロディが遠くから聞こえた。
「・・・・・・」
そのメロディに耳をすませながら、僕は青色の飴を口に入れた。
ソーダの爽やかな風味が口の中を支配した。
翌日の朝日を浴びると、僕の体調はすっかり元に戻っていると勘づいた。
本当にあの飴に効果があったらしい。
お兄さんがどんなものを配合させたのか知らないが、とにかくまずはお兄さんに感謝すべきだろう。
心の中でお兄さんに最大限の感謝を伝え、僕は朝の準備を始めた。
帰り道鼻歌を歌う。
行ける訳もない巴里に夢を見ている。
凱旋門を潜って、シャンゼリゼ通りを「Bonjour」と、人々に声をかけながら歩いている。
そして、目の前には、普段と変わらないお兄さんがいた。
「やあ、飴は効いた?」
「うん、ありがとう」
そう、いつもと変わらない会話だ。
だが、その快調な時間も一瞬だった様で。
あれから五日経つと、また僕はあの倦怠感に襲われた。
それをお兄さんに伝えると、お兄さんはまた、青色の飴を渡してくれた。
そうすると、すぐに体調が良くなる。
だが、日を重ねる毎にそのスパンが短くなっていった。
四日、三日、二日、と・・・・・・。
例えるならば重い重機に上から押し潰されている様な倦怠感が出るのだ。
また鼻血が最近よく出る。
鼻にいくらティッシュを詰めても、なかなか止まらない。
貧血気味からの倦怠感なのか?
僕はどうして、こんな目に?
学校は正直に言えば行きたくなかったが、休みの連絡を入れれば、また面倒な事になる。
「小坂くん大丈夫かい?」と声をかけられるだろう。それが嫌だ。
授業中、鼻を必死に押え、出血を止めていた。
そして、青い飴を貰って二日後。
給食の時間に、何となく歯茎に手を当てた。
何気なく指を見た。
僕の指が、真っ赤に染まっていた。
あのお兄さんの飴の様に、染まっていた。
「・・・・・・ぁ」
吐き気がする。
僕は、いつか読んだ漫画の内容を思い出した。
辛うじて原爆から逃れた主人公が、軍人のおじさんを抱えて歩く。
そして、原爆の症状で、おじさんは髪が抜け、死んでしまう。
そして、しばらくして主人公も、髪が抜けていく。
ワナワナと震えている。
僕も、彼の様になってしまうのか?
そうすると、震えが止まらない。
トイレに何も言わず駆け込んで、盛大に胃の中の内容物を便器に吐き出した。
その便器も赤色に染っていた。
「うああ、ああ」
声にならない声が喉を通った。
その日、ふらつきながら、いつもの道を通っていた。
夕陽の茜色が視界全体に広がっている。僕の目の前には茜色しか見えない。
茜色。茜色。茜色。
その茜色の地獄の中、お兄さんが立っていた。
こちらに向かおうともせず、ただ立っていた。
「・・・・・・ううう、おにいさ・・・・・・」
声を出そうとするが、その口からは血がたらたらと流れている。
声が血に遮断され、上手く出ない。
「・・・・・・もう大丈夫だよ」
お兄さんの元へ着くと、そうお兄さんは言い、僕を抱きしめた。
お兄さんのパーカーも、赤く染ってしまった事だろう。
「俺と、一緒に来て」
「・・・・・・う、ん」
上から、優しく、そして切ない声が聞こえる。
それは天国からの声なのか、お兄さんからの声なのか。
薄暗く、だが清潔にお兄さんの部屋はあった。
僕は、お兄さんのベッドに寝かされていた。
身体に力が入らない。もう動く事は出来ない。
例えるなら、僕はお兄さんの部屋に置かれている人形とほぼ同じだ。
「ねえねえ、新しい服買ったんだ、どう?」
「かっこいいね、いいと思う」
お兄さんが新しい服を自慢してきた。
お兄さんは何でも似合うな、と本心から思っている。
「・・・・・・ごめんね、殺鼠剤なんか使って」
「もういいよ」
ベランダに目を向けた。朝日が差し込んでいる。
「・・・・・・ずっと一緒にいようね、お兄さん」
僕がそう呟くと、お兄さんは静かに微笑んだ。
僕はお兄さんを求め。
お兄さんは僕を求めた。
それだけだ。
それなら、僕はお兄さんの元へ、ずっと、一生、いていたい。
なら、僕はこの体が動かなくて、お兄さんに介護される事になろうとも、僕はここにいよう。
それが、お兄さんの望む事なら。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
協力して頂いた、土部零仁(中村優志)氏からコメントを頂いております。
・・・・・・
山雪翔太さん著〈飴お兄さん〉のモデルをつとめさせていただきました。
きっかけは私の些細な自撮りを見た山雪さんとの会話です。
山雪さん「不審者みたいですね」
中村「飴食べる〜?」
そこから発想を膨らませた山雪さん、不審者のお兄さんと少年との共依存系物語を書きたいと仰いまして
まさか自分をモデルに小説が生まれるとは、驚きました。
物語を書き始めるにあたって、何か良いネタは無いかという会話をしていたときに
「飴に毒物(殺鼠剤)を仕込んでおいて、あとで解毒用の飴を渡すことを繰り返して依存させるのはどうだろう?」
というアイデアを起用していただきました。
さて、私の話はこれくらいで。
完成したとの旨を知り、嬉々として拝読させていただきましたが
やはり、山雪さんといえばリアルの情景描写です。
視界には文字しか入ってこないのに、その場面の空気の温度や湿度、匂いなどもハッキリと感じられます。
全体的にベットリとした、甘すぎる飴のようないやらしい感じ。
行けども果てども茜色、茜色。
真っ赤な夕日の中、ぬるりと吹く風の不気味で、それでもどこか懐かしいような雰囲気。
主人公の少年の、未来など期待できる気持ちにはなれないというような、キリがない日常に対する陰鬱さを重たく感じます。
なんだっていい。
何か、終止符がないか。
そんな気持ちを思春期の頃に、1度は感じるものですね。
そんな日々に突然現れたお兄さんは、真っ暗な夜に差し掛かるような少年の不安や抑鬱感に射した、日が完全に落ちる前の一瞬。
一番眩しい時間帯の夕日だったのでしょう。
儚くさりげない。
それでも、鮮烈で頭にこびりついて離れない。
単調だった少年の日々に、不協和音が混ざってしまったような気持ち悪さ。
嫌になるくらいつまらない和音であった日常を、変えてくれるのではないかと
彼を脅かす存在であった筈の〈お兄さん〉が、救世主にすら見えてくる。
後にも先にも引けず、今日は何が起こるのか? という期待しか、もはや考え付かない。
お兄さんと少年の、たった2人だけの、雑に上から真っ赤なマジックペンで塗った、ガラスドームのようですね。
彼らに、未来なんか無いほうがよかったのかもしれません。
今、その瞬間こそが全てであってそれしか知らないのだから。
そういう思いになりました。
いやあ、素晴らしい作品を読ませていただき、ありがとうございます。
山雪さんの、これからの作品にもワクワクしています。
中村優志
・・・・・・
今回作品を制作するにあたって、土部氏から素晴らしいアイデアを頂きました。
また今回の表紙を土部氏に製作して頂いております。美麗なイラストありがとうございます。
改めて、土部氏に多大なる感謝を。
この辺りで、さようなら。
土部氏のTwitter
土部 零仁
@artoct
DOBE
@Eureka0672
DoBe(どべ)
@DoBe_0811
中村優志
@Yu_shi_octopus

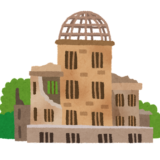





















"飴お兄さん"へのコメント 0件