男は笑った。それとは無関係に、彼女は泣いていた。笑い声や嬌声の中で独り瞳を枯らしていた。彼女は大切なものを失くし、大切なものは彼女を失くしたからだった。彼女の涙の流れていった方向には、小さな川が海へ向けて流れ、オタマジャクシが後ろ足を生やそうと懸命になっていた。彼女は涙で水彩画の様に滲んだ縁日の風景を、ぼうっと眺めた。幼児期特有の無心さで、ただ世界の生い茂る行手を見つめた。
彼女が母親と逸れたのも、この無心が原因だった。彼女は衝動的に大型の金魚すくいの水槽を覗き込んでいた。関心が途切れ後ろを振り返ると母親の姿は無く、横幕や吊り下げ旗の、色とりどりの虚空が広がっていた。そこに、見慣れた母親の右手は無かった。唐突に、彼女は世界を失った。空と陸と海を掴んでいた、その小さな手の平は季節外れの木枯らしに震え、彼女の見開かれた目には、伝手を失った夏の夜が、大海に揺れる漂流船の様に浮かんでいた。
いつもの公園に、中央の噴水を囲う様にして屋台が並んでいる。平時は観客の目を奪うあの華美な噴水は、今日は主役の座を奪われ、舞台のど真ん中でぽつんと端役に甘んじていた。代わりに蠢く人混みに、彼女は必死で目を凝らす。
立ち並ぶ賑やかな屋台は、彼女の記憶している限り、昨日にはなかったはずだった。店舗や建物の様なものは、地に生え、風や雷を防ぐものだと彼女は言葉を介さず認識していた。しかしこの屋台達は、むしろ風や雷の様に忽然と現れている。見渡す限りの乳歯の様に規則正しいこの屋台の連なりは、世界の果てまで続いている気がした。
知らない顔に知らない声。母親という呼吸器を失った彼女にとり、よく知る公園も、月の僻地と同じ様に真空に占められていた。
紫外線もブルーライトもよく知らない彼女の瞳は、祭りの光景を鮮明に写した。しかし眼路の限り、あの温かな後ろ姿は見えない。目が良く効くことがかえって恐怖心を大振りに煽った。彼女が冒険をするには、手足がまだ少し足りなかった。ふいに見上げた薄暗い空は、遠く高い。前後左右も、同じだけ、深く遠かった。
息を深く吸い込む。夏の夜は、その気になれば素手で生捕りにできそうな程立体的だった。肺がぬるい。彼女はともかく歩き出した。母親の居そうな色の方へ向けて。夜を掻き分け、喧騒を踏み鳴らした。彼女は世界とはぐれた一方で、今日初めて世界に歩み出た。
祭りは、誰をも拒否せず、老若男女が入り乱れた。誰しも持て余した夏を使い切るために、足りない夏を満たす為に、そこに訪れていた。人々は鍵(けん)になって常に全ての音階を鳴らし、絵の具になって十人十色を持ち寄り、ひたすらに空間は濃度を増した。やがてその籠った熱は夏に汗を噴かせ、大きな水滴となり、祭りとしてこの街に結ばれていた。
彼女は見惚れた。圧倒されながらも、取り掛かった。目や耳が手当たり次第に引っ掴んでは投げ込んでくる世の断片を受け止める為の器を、天から降って沸いた雨水を逃さない為の水瓶を拵えるかの様に、自分の内側に大急ぎで成形していった。
アスファルトを打つ500円玉の音。赤子を抱く男の腕を走る動脈。女の瞳に映る生まれたての恋心。畝る人の濁流。あれらが果たして、一体何処へ行く着くのか。彼女には皆目見当もつかなかった。泣く赤子を見て、彼女は、いつの日かこの公園で見た、子猫の死骸を思い出していた。死骸は突然現れたが、日が経つにつれ崩れ落ち、やがて土に還っていった。結局は、全ては定められた場所へ、流れ着くはずだった。自分も同じ様に刹那の物となって、祭りを転がって行った。
ここで彼女は、母親に追いつく前に疲れに追いつかれた。このまま立ち止まると、疲労が自分を抱き上げ、何処かへ攫っていくのではないかと思い、尚も歩いた。そんな時、後ろへと流れていく屋台の中に、母親の残像を見た気がした。不意に懐かしさが湧く。風に浮く綿毛は、タンポポの事を思い出した。
彼女は慌てて引き返し、屋台の前に立った。柔らかな明かりが彼女の顔を照らす。そこは、飴屋だった。派手なだけの装飾が取り囲むその中心に、母親の頬と見間違えた何かを見つけた。りんご飴だった。彼女は生まれて初めて、赤ではなく紅を見た。今日見た新たなものの内で、一際奥行きを見せたのがこのりんご飴だった。
母親とはぐれた、彼女の恐々とした心は、その林檎飴の照りによって洗い流された。彼女は、世界のきっかけを探し当てた。
彼女はりんご飴の前に立った。透明で薄い飴の層は彼女を映し、祭りを映し、世界を映し出した。さっきまで迷っていた道も、そこにあった。飴は、赤の濃淡だけで、つまり、飴だけの秩序に従い世界を映し出していた。彼女は、赤い風にワンピースの裾をなびかせながら、そのりんご飴の中へと今にも駆け出していけそうな気がした。
やがて掛けられた屋台の主の声に、彼女の放心は阻まれた。男は通り一遍の売り文句の後に、何かに気が付いたのか、いくつかの質問をした。彼女の辿々しい答えを聞き、男は頷きながら、奥の方から、りんご飴を出してきた。他のりんご飴よりも淡い色をしていた。
男は彼女の一瞬の身の上を案じたのか、この飴を条件付きで渡すという事を伝えた。男は『このあめをせけんにひろめたい』と言った。男は様々なことを語った気がするが、彼女が掴んだ条件なるものの要点はそこだった。この飴が、男にとって大切なものなのだということは分かった。母親に話そう。そう決め、彼女は頷いた。
元より、この感動を誰かに伝えたかった。願ってもない申し出だった。彼女は、母親にする冒険の土産話とりんご飴を手に入れた。
屋台の連なりを離れ、林に近いベンチに向かう。彼女の両手で揺れる煌々としたりんご飴は、酷暑に紅を引いた。
彼女は、独り占めにした世界をじっくりと眺めた。それは、彼女の目には宝石の様に映った。やがて、この宝石を頬張るなら、己を宝箱にすることが出来るという計算が立った。
躊躇は無かった。飴は煌めきと共に、鼻腔から逃げ出し、舌に溶けた。煙の様に逃げ続ける飴の背を追う彼女は、たとえ周りで、そっちのけにした現実世界が崩壊を始めていても、気が付かなかったろう。
『なつまつり』母親が、今夜の催しを指すのに発していた音を繰り返した。字面は分からないが、その音には、赤い色と熱がついた。
しばらく彼女は飴を舐め続けた。その無限に寄せる甘味の波に夢中になった。縮んでいく飴だけが、名残惜しさと共に時間の存在を彼女に伝えた。飴は、彼女の手によって、夏の夜の様に消えてしまった。
やがて、飴の層が終わると出てきた、リンゴの皮を少しづつ剥いで行った。果実が、白っぽく現れる。彼女にはそれが、人間の頭の形の様に感じられた。歯で削り取ると、舌の端で、新鮮な死の味を感じた気がした。気が付くと、白い果実には、髑髏そっくりの陰影がついていた。誰もの顔の裏側に隠し通された髑髏。死の後にだけ現れる、全てが過ぎ去ることで現れる髑髏を眺めた。
突然、爆音が胸を打ち、手元が鮮やかに照らされた。音の出所の方を見ると、空高くに花火が上がっていた。今日最後の新しいものが満を辞して現れた。
花火は、祭りを蒸留し抽出したような色を振りまいて、太陽の無い空に、根も茎も経由せず、満開に咲いていた。人々の体温で気化した祭りが、遂に空で焼けた。華やかさと儚さを両手に抱いて。
感想を巡らせる間も無く、表す為の語彙を探す間も無く、矢継ぎ早に花火は上がっては消えていった。
見るものの心に種をばら撒き、いつの日か、夏の思い出と共に心の情景に咲き返す、永遠の花。全てのものは、一瞬のうちに、後ろへ流れていく。彼女は、恋々として出揃った夏を眺めた。彼女は、いつの間にか泣いていた。
涙は、服を濡らした。全身はずぶ濡れになった。涙はやがて粘度を持ち、皮膚全体を覆う。彼女は、自分の体が溶け始めていることに気が付いた。それに気がついた途端に、少女は、飴のように、跡形も無く、地面を流れて行った。
彼女の右手にあった髑髏じみた食べかけの飴も次いで変化を始めた。円柱だった柄に節が出来、頚椎の様に鈍い棘が付いた。誰も見ていないのをいいことに、髑髏の飴は、少女になりかわっていた。
祭りは佳境を過ぎて、人々は帰路に就き始めた。
男が居た。男は少女の母親を連れ、ベンチに寄ってきていた。地面を流れる液体の近くで、少女がしゃがみ込んでいる。男が近づき手を振ると、少女はこちらに向かって立ち上がった。
少女はワンピースに固まった飴を振り払う動作を何度か繰り返した後、男を横切って、母親の方に駆け寄って行った。



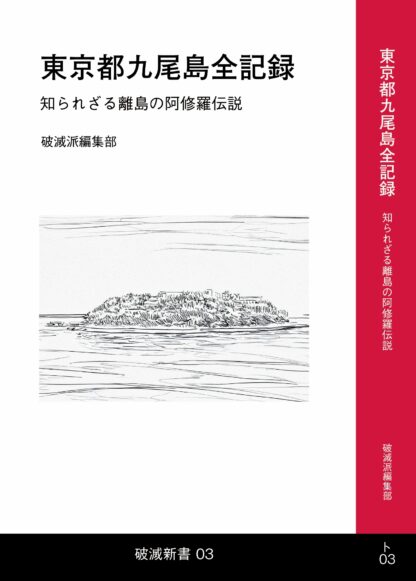








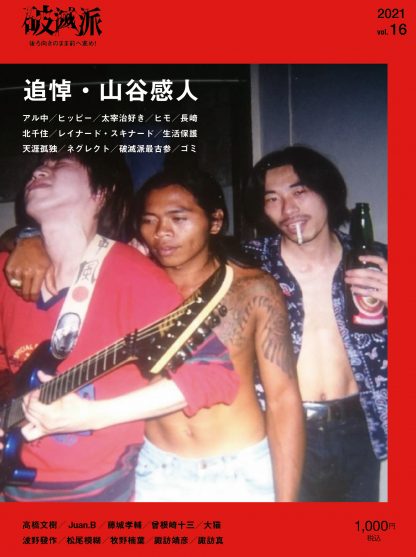












"髑髏飴"へのコメント 0件