エレナが華奢な腰をよじらせながらカミサマの上で喘ぐ。その透き通るような白髪が窓から入り込む光に反応し輝きながら揺れる。ベッドがきいぎいと歯軋りのような音を立てる。佳子は床に崩れている。分厚い眼鏡の奥から、その気怠い体勢とは真逆の、禍々しい眼差しが宙に向けられている、佳子は天井に向かって札束をぶわっと放り投げてみる。次の瞬間、佳子の前にずらと並べられた、この小さな部屋の資金を成り立たせている黄土色の腐った尿入りボトルの上に札が落ちてくる。その脇でヒロトは、とても小さな音を流して、静かに、佳子のスマホで物理の実験動画を観ている、そして隣に置いた鳥籠の中でくちばしを突き出している瑠璃色の相棒に向かってときどきちらりと感情を見せる。他の女たちは死んだように眠っていた。パシンパシンとエレナの骨盤がカミサマの足の付け根にぶつかる乾いた音が相変わらず響いていた……
風。
アパートの扉が開けられ、薬と煙草の入った袋を持って帰ってきた美陽はエレナのそのあられもない姿を見て突然に激昂した。しかしその合図は些細である。小さな、わけのわからない奇声、それは玩具のロボットが壊れていく最後の音、例えば、あの、『じじ……じじじ……』というものに近いものがあった、そうやって叫びながら、美陽はエレナを突き飛ばした。そして美陽はカミサマの首を本気で絞めた、エレナではなく。
佳子は唖然としてその風景を見つめた。煮えたぎる緊迫の匂いを嗅ぎ取って、女たちもそれを見つめていた。佳子は目の前の事件を拒絶し自分の空間に閉じこもっているヒロトを抱き寄せ、目を覆った。そしてもう一方の片手で散らばった札をかき集め、ジーンズのポケットに突っ込み、ヒロトを抱きかかえ鳥籠を引っ掴み佳子は外に走った、本格的に駆け出す前の佳子の目に入った、部屋の前のポストに突っ込まれていた茶封筒が異常な引力を放っていた……なぜかそれを残して行くことはできなかった! この部屋でなにが起こっていたのか? 「これ」は一体なんだったのか? その手紙をヒロトに持たせただ佳子はつんのめりながら走った……鳥が発狂したかのようにびちちちち! と興奮して泣き叫ぶその名残りがあの部屋まで響くようだった。佳子に強く抱かれながら、ヒロトはこの日、初めて自分の意志で泣いた。
「化け物! この化け物!」エレナは本当に火のように叫んだ、美陽の腕を必死にカミサマから引き剥がそうともがいた、でも、それは無駄だった。エレナがカミサマを守ろうとすればするほど美陽の腕の力は増していった。
ぐに、と歯を食いしばっていたカミサマの赤黒い顔から生気が零れ落ちたその決定的瞬間を、この部屋にいた女たちは目撃した。息の詰まる時間が流れた。女たちは黙っていた。ひたすらに黙っていた……亡霊のような足どりでエレナがトイレまで歩いていった。エレナは扉を開けたまま放尿した。その音で正気に戻った美陽はようやくカミサマの首から手を離した。リビングに戻ってきたエレナは何気ないいつもの様子で、ソファに投げられた、派手にデコレートされたスマホをいじり、そして、電話をかけ始めた。
「もしもし。人を殺しました」美陽はエレナを刺すように見た。女たちは荷物をまとめ始め、出て行く準備をしていた、ようやく、慌てている様子だった、
「殺したのはあたしです斎藤由里子二十七才無職です住所は世田谷区の三谷荘。首を絞めて殺しました全て全て全てオナニーでしたなんの聖なるものでもない卑俗極まりないものでしかありませんでした」
少し枯れた声でそう言ってからエレナはいきなりスマホを窓に向かって思い切り投げつけた。ばりんと簡単に窓は割れ、冬になる手前の冷酷な風が入ってきた。女たちはどんどん逃げ出していった。美陽は震えながら全裸のエレナを見た。その突き出た鎖骨、腰の反り、尻の湾曲、美陽がついに触れられなかったものが、二人の間の断絶を無情にも暴いた。エレナは嘘みたいに、美陽に、あのときの夏央莉を思い出させるみたいに、美しかった。
「行って」エレナは美陽に言った。美陽は首を振った。
「嫌だ」
「行ってよ!」エレナは絶叫した。その整った顔からは憤怒と、愛が、カミサマへの、いや、一人の男への愛が溢れているのを美陽は見てしまった。だから……だから……それから逃れるように美陽は走った、美陽は、そこから、走った。走ることしかできなかった……
*
お久しぶりです。急に手紙が書きたくなって。どうしてでしょう、話が通じるとは思っていないけれど、一番密度の濃い時間を共有したあなたに近況を聞いて欲しいのかもしれません。長い手紙になりそうです。
わたしはもうすぐ結婚し、なんと子どもまで産もうとしています。今から二年前、つまり十八歳のわたしが聞いたらとても信じられないでしょう。高校を中退してからすぐに、陳腐な怨恨しか抱けなかった田舎から飛び出して、適当な仕事をしながら世田谷のボロアパートに住んでいたわたしは、世界の全てを憎らしく思って、変な薬で頭を溶かして(あなたはよくご存知ですね)、いつもきりきりという音を立てる虚しさと共にあったのですから。そして遂に、あんな病的な事件まで引き起こした当の本人がなぜ夫とか子どもとか幸せとかそういった普通の、一般的な道へと進もうとしているのでしょう。いや、これは惚気ているわけでも自慢しているわけでもないんですよ。大体、どんな顔して。とあなたは言うでしょうね。ですが、別にわたしは幸せになれるとは到底思っていないし期待もしていない。結婚するというのは全く文化の違う人たちと家族になるということですから、当然問題もたくさんあります。それにわたしたち夫婦の関係は、後でお話ししますが、事情がかなり込み入っていてややこしいために、生活もそれに比例して困難なものになるでしょう。
だけど、わたしは結婚に関する素敵なイメージを未だ愚かにも持っているんですよ。二年前あなたたちと経験したあの疑似家族的な状況は結局、最悪な状態で破滅したわけですが、誰かと一緒にいるということが、どんな形であれ当時のわたしを支えていたことは確かなんです。その思い出が、結婚に少し期待を持ってしまう理由になっているんだとは思います。我ながら本当になにを言ってるんだ、とも思いますし、昔のようにあなたや他の人たちと今からもう一度一緒に暮したいとはもちろん微塵も思っていないのにも関わらず、です。なぜって、あの日々を思い返しても、ぼうっとした黒い霧が立ち込めていて、ずっと生きるか死ぬかどうするか考えて、あなたたちに見捨てられるかもしれない恐怖がいつもあって、あまり心地よいものではなかったからです。
当然、寂しかったり、悲しかったりしないと長い話を語ろうとは思いませんから、今わたしは人生における二度目の危機に瀕しているというわけです。マリッジブルーとか、そういう類のものではありません。端的にいえば、「この膨らんだお腹の中には確実に生命が宿っている」、という事実にわたしは耐えることができません。この子の存在そのもの、そして取り巻く環境がすでに複雑なものであるだけでなく、わたしの側にも、罪の意識とか、母性の欠如とか、そういうことがあるんです。まあでも、これは虐待されてきた子どもにありがちな悩みかもしれません。例えば……母性の欠如などと単純に言い切ってしまってよいかはわかりませんが、自分の生暖かいお腹に手を当てると、どんな化け物が生まれてくるんだろう、と、そういう風にしか思えないんです。昔、あなたに「この化け物」と言われたことを、未だに引きずっているのかもしれません。
そういったものを払拭するために、自分のこれまでの過去を振り返らなければならない気がするのです。どうか面白いように書く努力はしますから、暇なときにでも読んでください。
わたしは、富山県南砺市というところで生まれました。父親のリストラのため、家族が東京を離れその田舎に引っ越してきてから何年か後のことです。この場所は、全く都会ではありません。深い山に囲まれたそこは、やる気のない民宿が少し離れているところに二つあるだけの、観光地と言えるかどうかも不確かな場所です。ただ、夏は避暑地を求めた旅行客がぽつぽつと訪れてきました。
家族は五人です。旧友の紹介で、近くの中学校の事務職にようやくありついた父親鈴木正義と、独身時代東京のデパートでブランド服のバイヤーをしていた母親の佐織。そして母方の、認知症の祖母イクと、とんでもない美貌を持った姉の夏央莉、それからわたし、美陽。わたしの語るに値しない見た目について、あなたはよくご存知のはずですからあえてここに書く事はしません。そして、わたしたちの家族は、問題を絶えず生みだすためだけに集ったようなところがある、機能不全家族と呼ばれるものでした。
従って、その機能不全の理由は様々に交錯してはいました。例えば、祖母の進行していくだけの認知症や、自分のキャリアに比べ、夫の仕事に不満を持たざるをえなかった母のストレスからくるわたしへの虐待行為。見て見ぬふりを突き通す、父の過度に回避的な性格も問題であったことでしょう。だけれども、その中心はいつも、わたしと五つ年の離れた姉の夏央莉でした。夏央莉の、その恐るべき美貌はこの閉ざされた家庭という牢獄の、たったひとつの、強すぎる希望でした。しかしそれは表裏一体なものです。ですから、その、まわりの人間を滅ぼす毒のような美しさは、ぶくぶくと絶望を培養する核として、ただ、あっけらかんと存在していたのでした。
夏央莉の服はいつも、母親の過剰な熱心さによって東京のデパートから取り寄せられていました。彼女のしなやかな細長い手足を映えさせるハイカラな柄のワンピースの肩にはいつも鳶色の絹のような髪の、縛るようにぎっと結われた三つ編みがぶらさげられていました。眉毛の少し下できちんと揃えられた前髪の奥からは、死んだような、それでいて敗者の魅力をたたえた大きな瞳があって、それはまるでアンティークの精密な人形をガラスのケースから取り出して、無理やりに動かすよう、機械じかけにしたような奇妙な魅力がありました。
わたしが、まだ小学生のころでしょうか。五年生に上がる手前だったと思います。
学校の帰り、踏切を待っている中学生の夏央莉をふと見かけたことがありました。それは肌が薄く湿るような初夏の日でした。太陽を見上げるとわずかに緑がかった光が目を焼くのでした。夏央莉は、地面に転がっている小さな石を通過する電車に向かって必死に蹴り飛ばしている最中でした。そのとき、風がぶわりとやってきて、彼女の着ている制服の、濃い湖のような青のスカートを大きく揺らして、太ももの裏が露わになったのです。はっとしました、わたしはその一瞬を、食い千切るように見つめました、夏央莉は、そのわたしのいかり肩とは対照的な、華奢すぎるなで肩を大きく前面に倒して、つんのめるように、一心不乱に石を蹴り続けていました。青いスカート、白い太もも……。夏央莉は電車が通り過ぎてしまうまで、取り憑かれたようにその行為をやめませんでした。
ああ、ああ、なんて、ぎこちない。
なんて、ぶきような。もろい。
夏央莉がなにか動くたび、本当にギコギコという、ぜんまいが軋む音がする気がするようでした。
わたしは本当に、そう思いました。そして彼女の数メートル後ろをランドセルを背負ってとぼとぼと歩きながら、先ほどの痛いほど白い夏央莉の太ももの裏を、何度も何度もへんな気持ちで、頭の中に反芻させるのでした。そうすると、心臓のあたりがざわざわとするような、疼くような感じがするのがわかりました。そして、その日、わたしに初めての生理が、やってきました。
そして、一度、こんなことがありました。観光で来ていた映画のプロデューサーが、夏央莉に東京で女優にならないかと言ったそうです。自分のことにも、なににも、興味がない彼女はそれをあっさりと断ったようでしたが、後からそれを知った母親は猛り狂いました。
そこから、どうやら、彼女を有名な女優にするという夢が、母親のなかで生まれたようなのでした。それは結果的に母親自身を滅ぼすものとなっていくのでしたが……。
だからこそ、それからというもの、夏央莉は、いつ、誰に見られても、完璧なまでに美しいようにと、頭から爪の先までお金をかけられるようになりました。こんな田舎で。いつも母は惨めな甲殻類のように背中を丸めて、夏央莉の足の爪にヤスリをかけ続けていました。わたしは、そんな風景を見て、もちろん、劣等感を感じることはありましたけれど、そんな単純なものではありませんでした。わたしはその夏央莉の、今後自分の人生を必ず左右していく、見ているこちらの胸が痛くなるような、そんな美しさを、愛しました。それはもう、苛烈に。だからこそ、その『大事な』身体に傷をつけるわけにはいかない夏央莉の代わりに、母親に殴られ続けていても、どこかで平静を保っていられたのかもしれません。むしろ、夏央莉を守っているというように、ある種の誇りすら感じていたかもしれません。わたしは、同性愛者でした。
その話はおいおい語らざるをえませんから、今は姉の夏央莉の話をしましょう。
結局、美しい夏央莉は、『有名な女優』にも、なににも、なりませんでした。それどころか、夏央莉が中学生のとき、学校で体育教師をしていた長田章造という十五も年の離れた男と高校を卒業してからさっさと結婚して、普通の主婦になりました。
わたしは、父の葬式で故郷に戻ったとき、初めてそれを聞きました。くだらない、とは思ったけれど、じゃあ、なんでわたしがああまでして殴られなければならなかったのか? だって、そうではありませんか。夏央莉が『有名な女優』になるためにわたしは長い間、身代わりになっていたのではありませんでしたか。
母も、もう昔のような活力を失ってしまって、死んだようになっていました。
それに、その長田という男との結婚のいきさつがまた皮肉なものでした。わたしが母親のストレスからくる、尋常でないほどの虐待を受け続けていたのを見て、夏央莉は夏央莉なりに、悩んでいたというのです。そして、本人が言うには、どうやら軽く神経を病んでいたらしいのです。その相談に、乗っていたのが、他の誰でもない、長田という男でした。
わたしが夏央莉の代わりに殴られていたゆえに、彼女は長田と結婚し、普通の主婦になったのです。
くだらない。
なんのために、わたしは耐え続けていたのか。
夏央莉が『有名な女優』になるとか、わたしの愛が彼女に無事届いて、彼女もそれに気づいて、それで永遠にわたしのものになるとか……そんな、馬鹿げた、どうしようもなく稚拙なありえない理想が、それでも心では本気で願っていたものが、見事に打ち砕かれて、非情な現実が露になりました。
ともかく、それがわかって、わたしはひどい嵐のような愛憎を抱いた後、しばらく、呆然としてしまいました。あの、ガラスケースの中の煌びやかな人形は、万人に愛される価値があったのに、どこにでもいるような中年の男ひとりのものになってしまったのですから。
だけれども……今思えば、夏央莉が、一番賢かったのです。夏央莉を愛していたのなら、本当は、心の底から祝福して、喜ばねばならないことだったのです。だって、なにが、自分にとって一番幸せかというのが、わたしたち家族のうちでよくわかっていたのですから。父の葬式が終わった後、いかにも幸福そうな顔で、わたしにお茶を出してから、どこにでも売っているようなピンクのエプロンをなびかせて洗濯物を干している姿を見ると、心底、そう思ったのです。ああ、夏央莉も人間だったのだと。そんな当たり前のことを。人形であることを押しつけていた異常な家族をきっちり捨てて、自分の力で人生を動かしたのだと。わたしの愛した夏央莉はもう、どこにもいませんでした。その大きな瞳だって、昔の、死んだようなものではありませんでした、むしろ、生きる喜びに満ちあふれたものになりかわっていました。神様みたいに、なんの欠点もない、その美しい夏央莉は、ただの、愛する中年の男によってもたらされる幸せに穢れた、ただの一人のおんなでした。
どんなに殴られてもわたしは、一度だって泣きませんでした。それは、彼女を守らなければ、という絶対的な確固たる思い、そのためならどれだけだって、本当にどれだけだってわたしは傷ついたっていい、という自分なりの覚悟。そして、事実、夏央莉は傷ついていないではないか、という確信と誇りがあったからです。だけど、その、あまりに変わった夏央莉を見たとき、わたしは、人生で初めて涙を流しました。
わたしは敗北したのです。人生に。自分が、なにもかも初めから間違っていたのだと思ったのです。実際、ああ、やっぱり夏央莉はしっかりと傷ついていて、だからこそ自分に本当の意味での癒しをくれる長田と一緒になって幸せを掴んだのですから。わたしは結局、自分のことしか考えていなかったのではないか? その証拠に、わたしが流したのは嬉し涙でなかった。自分が報われなかったという虚無の涙でした。そんな涙を流してしまったことだって、余計に自己嫌悪に陥る原因になりました。なぜ喜べない? 夏央莉は幸せになったんだから、なったんだから……。
わたしが殴られて耐えていたことなんか夏央莉にとってはなんの助けにも、なっていなかったのではないか? 従ってわたしが身代わりのつもりで殴られていたことにこれっぽちの意味もなかったのではないか? 全ては無駄な傷ではなかったのか? 長田たったひとりいれば、夏央莉の問題は全て解決してしまったのですから。
ひたすらに暴力に耐えていたことが、夏央莉にとってなんの役にもたっていなかったとしたなら、つまり、彼女を守ることができなかったのなら、わたしの存在理由なんて、一切ないのです。別に、いらなかったんです。圧倒的に無価値なのです。それだけが、わたしの生を動かすただ一つのプロジェクトでした。なのに、自分勝手に、夏央莉のことを愛していたつもりになっていただけだというのが……。ただ、わたしは母親同様、歪んでいただけだったのです。この世で一番憎んでいた母親と、わたしは、夏央莉を苦しめていたという意味で同類だったのです。
自分の指針が、粉々になったのがわかりました。
なにも、わからなくなりました。
わたしは、夏央莉に今でもまだ、死んだ目をしていてほしかったのでしょうか。そんなエゴの塊でしかないのでしょうか。自分が夏央莉のボディーガードであるというちっぽけな称号、それだけのために?
一番、夏央莉の幸せを願っていたはずなのに……。もうなにもかも。
それで、自暴自棄な気持ちにさいなまれながら数日後、田舎から世田谷に帰る途中で、わたしは運命の男に出会ったのです。そう、カミサマに。あなたもよくご存知の。
偶然というべきでしょうか。その日は、わたしの十八歳の誕生日でした。
五年生にあがる前に踏切で見た青いスカート以降、わたしは幾度も幾度も夏央莉に触れてみたい、なんとか触れようと思い続けました、でも、そのときから自分が……女が好きであるということも怖かったしわけがわかりませんでした、そして日々の虐待のストレスから、一つ歯車が狂えばなにをしでかすかわからない自分の異常性の萌芽をうっすらと意識していました、だから……わたしは十六歳でさっさと高校を中退してしまい、スーパーで寡黙に働き上京資金を貯めてからなにもかもから逃げるように世田谷へやってきました。年齢もあり、形式上、世田谷の家の借主は父親でした。彼にしてもらったことはそれだけでしたがあなたに会えたのだから感謝しなければなりませんね、でもなぜ、それが世田谷だったのか、あの、一連の事件を引き起こしたあのアパートに引っ越したのか、未だに漠然としています。必然ではないし、そんな理由で、とあなたは怒るかもしれませんね。世田谷、という地名を知ったのは、おそらくテレビの番組か何かだったと思います。何せ、自分の半径五メートルのことにさえ気を配っていれば生きていけるような田舎だったものですから、それぐらいしか情報源がなかったのです。
昼間のバラエティ番組でしたから、お笑い芸人が何人かでロケをやって、世田谷の魅力を訪ね探す、というふうな趣旨のものだったと思います。これはよく覚えているのですが、まず世田谷の建物や、その景色がカメラの中に収められ、それからいきなり空のカットになったのです。
あっ、とわたしは思わずそのとき、声をあげました。それはわたしが小学四年生のときにみた、あの夏央莉のめくりあがったスカートの色と、同じように思えたからです。それはわたしの願いにすぎなかったかもしれません、だけどその頃はまだ、夏央莉は、わたしの愛した夏央莉でしたから、つまり、わたしのものには絶対ならない神様みたいな夏央莉でしたから。『この』世田谷にいけば。『この』世田谷にいけば、あの色をいつまででも肌で感じていられる、そんなような、純粋極まりない気持ちだったのは確かです。その半年後には、わたしは世田谷に住んでいました。本物には、怖くて手を触れられなかったから。
まだほんの子供でしたから、工場ぐらいしか働き口がありませんでした。しかも、それは夜間の仕事で、わたしは限りなく価値があると思って、きっと抱きしめられると思っていたその空の色とほとんど出会うことはありませんでした。だから、といっては言い訳がましいですね。わたしは、あなたもよく知っている通り、ひどい薬物中毒になりました。その薬は、薬局で買える市販のものでした。そのラベルは、あの青い夏央莉の色でした。愚かですね。
いつしか、わたしはどの時間も、その強固な薬物の酔いを感じていなければ不安になってゆきました。その薬を飲まなければ、もう夏央莉と離れてしまうような気がして。逆にいえば、その薬さえ飲んでいれば、夏央莉の近くにいられるような気がして。その酩酊のときだけ、瞼の裏に、一面に、あの日の青が、ぱっと広がるのでした。
ある勤務中の時です。わたしはその日、いつもの酩酊量より三倍もその薬を飲んでいました。つまり、何百錠ものオーバードーズをしてから出勤したのです。そして、わたしの見た目について軽く陰口を叩いた同僚の男に突如殴りかかったそうです。およそ一年半もの間、東京に出てきてすぐの、わけもわかっていないような小娘を、可哀想にと雇ってくれた工場長の顔を、あの沈んだ顔を、落胆した顔を、わたしは今でも忘れることができません。結果的にわたしは精神病院に入れられ、ダルク――薬物回復支援施設に通わなければならなくなりました。そういえば、誰かに暴行を働いたのは、あれが初めてでした。わたしは空が薄く白み始めた夜更けに警察が来て、パトカーに押し入れられたまさにそのとき、こんなに底の見えない、どうしようもない、虚しい思いを母もしていたのかと、そんな風に思いました。
あのダルクで、鼻につくような笑いを浮かべていたあなたに出会わなければ。
「大丈夫? お腹の具合は」
もうすぐわたしの夫になる人が会社から帰ってきました。わたしはテレビを見ながらこの手紙を書いています。
「うん、少し腰が重いけど」
「そっか。あとで軽く揉むから横になりなよ。これ、作ってくれたの、ご飯食べるね」
彼は冷蔵庫から缶ビールを取り出し、キッチンで飲み始めました。
「なに書いてるの? 手紙?」
「ちょっとね。昔の友人に。スーツ、ハンガーにかけるから貸してください」
彼はありがと、と言いながら歩いてきて、わたしにスーツを渡します。この部屋はあそこなんかより断然広くて、綺麗で、新築なのに、わたしはこの空間が、とても、怖い。彼の、そっと握りしめてくるようなあたたかい優しさが、怖い。このお腹の子は、彼の子ではありません。そして、それをまた彼も知っているのです。
この会議室のような部屋は頭が痛くなるほど冷えていた。
そのいけすかない女はずらりと並んだ席の一番前、わたしの二つ隣の席に座り、偉そうに腕と足を組んで歯を出しにやけていました。横顔しか見えませんでしたが。なにがおかしいのか、そのやけにへらへらした具合に、わたしは軽い憤りすら覚えました、もちろん薬の禁断症状もあって無性に苛々していたのは確かでしたが……うっすらと、ガムをくちゃくちゃと噛む耳障りな音が聞こえてきました。年は二十代後半といったところでしょうか。女は赤い水玉が吹き溢れる水色の派手なスカートを長細く白い足に通して。その椅子のすぐ下には、踵が壊れ、ところどころ禿げた銀色のピンヒールがだらりと二つ、腐った野菜のようにしなびていました。わたしは、その女の真っ白に染められた肩までの毛髪や、それを引き立たせるような、これ以上ないほどに通った華奢な鼻筋や真っ赤な口紅、鎖骨の浮き上がり具合に、興味をひかれなかったわけではない、いや、確かにわたしはこの瞬間からこの女に興味を持ったのでした。女は、ある意味で、とても、とても病的に美しかった。夏央莉とは全く違うのだけれども、惹きつけるようななにかを持っていた。こちらへおいでといやらしい匂いで昆虫を手招きしている、禍々しい模様をした食中植物のようです、この女は、自ら噴射機のようになって、まわりに毒気を撒き散らしている! そんな、異様極まりない佇まいをわたしは確かに感じとったのです。わたしは一瞬で、粘っこいそれにからめとられそうになった。この女はなにをやって、ダルクにいるのだろうか。覚せい剤、わたしのように合法麻薬? それとも、精神薬? この女は一体なんなんだ? もうわたしがダルクに入ってからかなり経ちましたが、それまでこの女のことは見たことがありませんでした。
隣の少女が立ち上がりました、顔立ちから推測するに、わたしより少しだけ年下で幼い感じがしました。ヤクのせいか顔はいやに土気色で、肉は削げ、目玉が飛び出しそうになっていましたが、それなりに可愛らしい顔をしていました。おそらく中学生でしょう。右手でどぶねずみ色のネルシャツの袖をつまんで、左手には紙を持っていました、そのなんの個性もない服が、余計に彼女を幼く、むきだしに、見せていました。どちらの爪もご丁寧に肉がはみ出るまで噛みちぎられていて、手は哀れな様子でぶるぶる震えて。どうやらその過剰な少女は紙に書かれた文字を読もうとしているようでした。このダルクでは、毎回のように、各々に課せられた宿題が出て、それを皆の前で発表しなければならないのです。
「……わたしがシャブに手を出したのは……どうしようもないアル中の母親を忘れるためで」儚げな声でそう言った後、自分で耐えきれなくなったのか、不快な思い出を想起したのか、少女は急にヒステリックになり、喉からしゃくりあげるようにだららららと涙を溢しはじめました、ビニル袋にガラス玉を大量に詰めこんで、上から思い切り叩きのめしたような煌めきを瞳に灯しながら。
まあこんなことは、このダルクミーティングではよくあることのようで、患者の誰も、その号泣を気にもとめないようでした。ですがわたしは、その彼女の泣き方に、異常に身体がむず痒くなって、そして、その、どうもわざとらしい感じに、さらに、目の縁のしっとりとした濡れ具合に、自分が少しだけ欲情したのを感じました。彼女の涙は、いかにも構ってほしい、と言わんばかりで、自分以外の他人全てを誘っているように見え、そんなだから、そのネルシャツが覆い隠してしまった本性の淫らな感じが、きっかけとなった啜り声によって一気に噴出しているような気がしたのです。自分がレズビアンというのは関係ないとは思うのですが。こんな真面目な話をしているときに不謹慎だけど、それはもう、どうしようもないほどに。
すると、あるドスのきいた尖った声が、少女の涙を遮りました。
「淫乱! 母親のせいにすんじゃねえ。あたしはあんたがなにしてたか知ってんだ。ラリって男とセックスしたかっただけだろうが!」
その声が会議室に響き渡った瞬間、それまで受講者同士のお喋りでぺちゃくちゃとざわめいていた場の空気が凍りに凍りました。と同時に、わたしはといえば、自分の考えが見透かされたようで、思わず心臓が止まりそうになりました。声の元は、あの、いけすかない女でした。
「発言者はそのまま続けてください。一番前の席のあなたは、落ち着いて黙って聞きなさい」
教壇に立っているつり目の、おそらく五十を超えたメンタル・セラピストが厳かに言いました。そのセラピストはダルク患者を明らかに囚人と同類だと認識していました。そのため、「処女ババア」と影で罵られ皆から嫌われていました。
「でも先生、」女は大げさな身振りで、セラピストに向かって媚びたように続けました。
「この女は元いた精神病院で、男性患者や医者を食いまくっていたことで有名なんです。シャブをダシにギシアンしてたんですよ。ただ気持ちよかったからハマった、それ以上でも以下でもない単純な話でしかないのに、なにを物事を複雑にしてるんでしょうか? 母親が可哀想ではありませんか? 事実と食い違ったことを宿題として発表することはいくらヤク中だといってもこのミーティングでは許されていないはずです」
受講者たちが馬鹿にしたような短い笑い声をぱらぱらと立て始めました。拍手すら起きました。
「静かに」
可哀想に、暇な狂人どものやり玉にあげられた彼女は、女をキッと睨みつけ、持っていた紙を手の中でぐしゃぐしゃに丸めてポケットにいれ、机を蹴飛ばして、それもまたわざとらしく。会場を出て行ってしまいました。ヒュー、と女は彼女の後姿へ口笛を吹いた後、
「メス豚!! 逃げやがって!!」
と、再び、あの鼻につく笑いを浮かべながら怒鳴りました。
「今日はここまで。寮に帰って、午後のプログラムの準備をするように」
セラピストは顔色ひとつ変えずに、そう言いました。受講者は、たらたらと文句や愚痴やら喜びやらを適当にぶつくさ呟きながら、一斉に席を立ち始めました。女はまだ席に座って、偉そうに手足を組んで、唇を歪めて笑っていました。そして、ガムを床に思い切り吐き捨てて、踵の壊れたピンヒールに足を突き入れました。
「お父さんが死んだ」
わたしは受話器越しの、その叔母の言葉を反芻しました。ダルクの洗濯室で皆のベッドシーツを洗っているときに、寮長が電話を持ってきたのです。
「お父さんが死んだ」
「そうよ。美陽ちゃんがそんな馬鹿げたことをしてくれてるときにね。あんたは一族の恥よ。恥です。恥以上の何ものでもないです。もう家族はバラバラだしおばあちゃんだってもう頭がまるで働いていないんだから。あんたの母さんも夏央莉のことがあって鬱の薬を飲んでるわ。とりあえず葬式には」
頭が、ぼうとしました。
そしてわたしはなにも考えないまま即座に電話を切ってしまっていました。わけがわかりませんでした。母が何故、いまさらわざわざ抗鬱剤を飲む必要がある? 人に何年も何年も虐待を働いてきたくせに全く病識のなかった母が? そして理由が夏央莉だというではありませんか。夏央莉になにがあった? ともかく、ヒステリックな叔母から浴びせかけられる、これみよがしな正論の毒針にもう耐えきれませんでした。その声の圧といったら。わたしが自分でわかっていることで追いつめてくる叔母の想像力のなさ。そして、本題の、父親の死に対しては……とりあえず、そう、とりあえず……わたしは、ふうん、と言ったのでした。父親の死に、なにも感じなかったからです。それに偽りはありません。だって、彼は事実、根本的なことをなにもしてくれなかった。ふ、う、ん、という、極めて無機質なひらがな音がわたしの口から排出されて、ただ空気と触れ合って、自分の耳に乾いて返ってきただけでした。
すぐに、それまでずっと聞こえていた、洗濯機が回転するガウンガウンという機械音がまた空間を満たしました。わたしはそれで我に返ってすぐさま、押しつけるように寮長に受話器を返しました。夏央莉。夏央莉。夏央莉。ねえ。なぜ? なにがあった?
寮長が戻っていく足音と入れ替わりで、背後からガムを噛む音がわずかに聞こえてきました。この音。ああ。大型の洗濯機に向かって立ち尽くしていたわたしは振り返りました。
そこにいたのは、あのいけすかない女でした。洗濯室の扉にもたれかかりながらガムをくちゃくちゃやって、右手からぐしゃぐしゃのベッドシーツをだらしなく垂らしていました。
「これ追加で」
わたしはこの女を本当に殺してやろうかと思いました。今は誰にも話しかけてほしくはなかった。いくらわたしが洗濯係だからといって頼み方だってもうちょっとあろうものを、洗濯時間に遅れたくせになにをこの女は偉そうに言っているのか。頭は夏央莉のことでいっぱいだった。
「煙草、欲しくない?」
女はひらひらとマルボロの赤を左手で振りました。ニコチン! そのパッケージを見た瞬間猛烈に吸いたくなりました、勿論ダルクでは、未成年のわたしは吸うことはできませんでしたが、世田谷に引っ越してからずっとヘビースモーカーだったのです。もうあの薬も手元にない。小さな逃げ場でいい。居場所が欲しい。
わたしは女の腕からベッドシーツをひったくって洗濯籠に投げ込んだあと、マルボロを奪って喫煙所に走りました。どれだけ寮長に怒鳴られたっていい。わたしのあまりの切迫した必死さを見たからなのか、乾いた女の笑い声が響いてきました。なにもかも、滅んでしまったらいいのに。
保護観察期間がすでに終了していたこと、また精神科医の判断により、葬式に行くために故郷へ戻る今このタイミングで、わたしはダルクから解放されることが決まりました。わたしは急いで荷物をまとめ、その晩には実家についていました。リュックサックの中には、途中の薬局で買ったあの薬が三箱入っていました。別に飲むために買ったわけではありません、これはお守りです。こんなものを飲まなくても。そして、いつでも、もうすでに手元にあると思ったら、その安心感で飲まずにいられると思ったからです。
実家は、見事に崩壊していました。
元々、実質的には崩壊しているようなものでしたが、もしかしたらそれは、危うかったけれども、絶妙なバランスの上に成り立っていたのかもしれません。なにもしない父親、殴る母親、殴られるわたし、美しい夏央莉と惚けた祖母。しかしわたしが世田谷に脱走して、その脆い橋はあっけなく崩れ落ちたようなのです。
通夜と葬式の準備でばたばたと走り回って電話をかけ続けている叔母。こんな大変な時だというのに「新人女優発掘オーディション」のビラを握りしめながら、抗鬱剤でオーバードーズして廊下でうわごとを呟いて寝そべっている母親。従って、惚けた祖母のおむつは糞尿まみれだというのに取り替えてもらえずに、むんむんとその悪臭が立ちこめていました。今夏央莉は少し離れたところに住んでいるようで、こちらへ向かっているとのことでしたが、そこで初めてわたしは叔母から彼女が結婚したことを聞きました。式は挙げていないようでしたが、なにも知らされていないことにまず呆然としました。
こんなに、荒れ果てているなんて。
安っぽい昼ドラマのような光景がいざ現実に迫ってくると、もはやグロテスクでしかありません。普通ならば、このような状況になったとき、善い精神を持った人間ならば、もう一度再生させようとか、力を合わせて乗り越えようとか、思うのかもしれません。だけど、わたしは若かったし、そもそも希望のないところに何も生まれはしません。どうすることもできない、という事実だけが身体に染み渡ってきました。
だから、わたしは、逃げました。
ひたすら、遠くへ、遠くへ。どこかへ。ただ、それだけ、願いました。
あなたは、きっと、そんなものは甘えでしかないんだと、怒るでしょう。でも、わたしだって、そんなことは、わかっているんです。痛いほど……。
葬式の帰り、夏央莉の家に少し寄って、前述の光景を目の当たりにして、完全に、わたしの心は折れきってしまいました。
世田谷に帰る高速バスの中で、あの薬を三箱全部飲みきりました。三百錠ほどでしょうか。遠くへ、遠くへ……。脳みその裏がきりきりと痛むのがわかります……縛るようでいて、それでも揺り籠めいた酩酊は全てを霞ませ、露なものを隠して、わたしを自分の外にそっと連れ出してくれるのでした……瞼の裏の青……バスがインターで停車し、休憩時間に喫煙所で煙草を吸っているとき、ふっと、死にたい、初めてそう思いました。
わたしの家に帰る途中にホームレスたちが小屋を作って住んでいる一角があります。吐瀉物を引っ掻き回して糖分をぶっかけたような、眩んでしまうような、甘ったるいまでに煮詰められた不浄の匂いが、あたりにぎちぎち立ちこめています。薬で五感がいつもより鋭くなっているから、余計かもしれません。聞いたら思わず身体をかきむしりたくなる、空き缶を大量に詰めたゴミ袋を引きずるずりずりとした音。蠅の羽音。わたしは、ここが大嫌いでした。死を感じるから……それでも、どうしてもその道を通らなければ、家には辿り着きません。先ほどわたしはまたいくつかの薬局を回って、あの薬を追加で五箱購入し、それを全部飲みきりました。レジを打っていた薬剤師の女が明らかに怪しげな目でわたしを見ていましたけれど、もうそんなことはどうでもよかった。大量の錠剤を一気飲みした時の、不快な、ざらざらとした感覚が喉を通り過ぎていきます……何度も嘔吐きながら。それでも吐いてはいけない。わたしは完全に薬に身体を支配されたら、首を吊ろうと思っていました。その方が恐怖を感じずにいれる、強気で逝ける、だから吐いたらいけない、決して。
その薬は眼にくることで有名でした。視覚が大きく歪み、上下にぶれ始めました。胸も詰まり始めました。呼吸が小刻みになってきました。わたしは、なんとか、その小屋の脇の細い道を辛うじて歩き続けていたし、息もしていたけれど、吐き気と、ふらつきと、終わりの見えない幻覚の渦に巻き込まれていました。あの薄暗い実家で。子供のわたしは壁に叩き付けられ、目を血走らせた母親にぶたれています。それを、現在の、潰れに潰れたわたしが後ろからじっと見ているのでした。この小道は、虐待の記憶をまざまざと繰り返す劇場と化していました。後ろから誰かの声が聞こえました。振り返っても誰もいません。幻聴も始まったようでした。わたしは、自分の命がぴりぴりと千切れていく瞬間を、その小さな音を、聞いたように思いました。なにもない、誰もいない場所へ行くためにこの薬を飲んでいるというのに、結局わたしは自分へ帰ってきているじゃないか? わたしは何のために金を払ったのでしょう。
「ばからしい!」わたしは頭をかきむしって、思わず叫びました……。
もう夕暮れでした。燃えたぎるような熱い橙色が迫り来て、その圧倒的さは、わたしの惨めな、それでも死ぬまで消えることのない孤独を、暴いてしまうようでした。
次の幻覚は、あの日の光景でした。機械音が唸るようにそこらじゅう、絶え間なく響いていた狭苦しい工場で、初めて同僚を殴った時……馬乗りになって、油じみた男の頬を拳で思いきり打ち付け続けた時のこと……わたしは思わず立ち止まって、歩くのをやめ、自分の痙攣した手を見ました。そして思い出したのです。あの時の男の肌のぬるい温度や湿りを。同時に気づきもしました。わたしは、この人生で、母親に殴られる時とあの時以外、誰にも、触れたことはなかったのだと。
幻覚から逃れたくて、わたしは首を横に振り続けながら再び歩き出しました。
人がいました。
仰向けになって、足を痙攣させた、ガリガリに痩せたそのホームレスはどうやら瀕死であるらしかった。他のホームレスは助けにもこない。ぐあんぐあんと揺れる視界の隙間に思わず入り込んできた男にわたしは手を伸ばしました、膝をついて、その男の上に倒れ込んだ。そして、思わず抱きしめてしまった。男は脅えたのか、声にもなっていないような叫び声をあげました。わたしは涙を流しました。そうか。わたしは、ただ、誰かと、ずっと、こうしたかっただけなのだ。
その瞬間、胃の奥から大量の液体がなだれ出てきたのがわかりました。男のずたぼろの服の上に吐瀉物がぶちまけられました。男はまた叫びだしました。わたしの頭は働くのをとっくにやめてしまっていましたが、誰かに見つかるのはまずいと思って、反射的にその口に手を当てました。自分の掌に男の吐息が、悲痛極まりない声の粒が、ぶつかるのがわかりました。それでも懲りずに叫び続ける男の目はどこか焦点が合っていませんでした。
「もしかして、目が見えない?」
男は叫び続けるだけで、答えは返ってきませんでしたが、その様子が全てを物語っていました。わたしは再び吐瀉物をぶちまけました。そして号泣しました。ああ、ああ、吐いてしまった、死ねなかった。死ねなかった。怖い、怖い。
「ねえ、目が、見えなくて、いいなあ」これは本心でした。
「無敵じゃない、きれいなことも辛いことも見えないじゃない、ねえ、いいなあ、いいなあ」わたしの涙は止まりそうにありませんでした。身体の奥底に必死に溜め込んできたこれまでの悲しみが噴き出すようにそれは流れ落ちてきました。
吐いたからか、ふらつきも少し治まってきました。だから、その病気で、目の見えない、軽石のような重さしかない男を、背負いました。男は叫ぶのをやめません。でも、わたしも男を降ろそうとは全く思いませんでした。そして、全ての力を振り絞って、わたしは、家まで、走り出しました。
背中の確かな温もりを感じながら、わたしは泣きながら走りました、もう夜でした、そして今、思ったのです。今、今だけは、幸せだ、と。人生で初めて本当に幸せなんだと、そう思ったんです。男は叫び続けます。幸せだ。男は叫び続けます。わたしは、男に、名前を付けました。カミサマ、と。
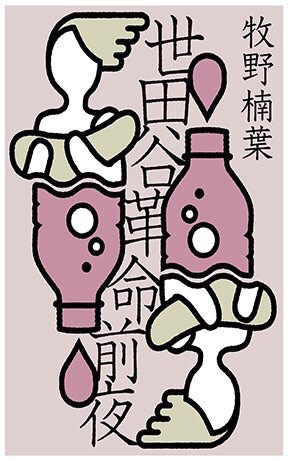




























"第一部"へのコメント 0件