「違う。」
僕が、口を開こうとするのを見て、男は、かぶりを振りながら言う。
「俺ではない。」
男は僕の片手にある携帯電話を見つめ、手で制した。
「やめとけよ。欲しかったんだろ。こういうのが。」
そうしていると、家の裏手から、園芸用の小さなスコップを手にした中年の男が現れた。僕たちを視界に認めた途端、急に立ち止まり、僕たち(3人?いや、2人と1体?)を順に眺め、興味深そうにこちらを見つめている。
男の瞳には、決意の夜明けか諦めの日暮れか、ともかく目に眩しい輝きがあった。
「やあ、いい天気だな。久々の雪で、家庭菜園がケアを必要としていてね。」
男は、一人語り始めた。
「君たち、そこで立ちすくむ以外の選択肢がほしいなら、わたしから一つ提案する。中に入ってコーヒーでも飲まないか?」
共犯、二人組の殺人鬼、犯罪集団。僕の頭には、いろんな言葉が浮かぶ。
「分かってる。ここへ来た程の君なら、入る。」
僕の耳元で、レインコートの男はそう告げた。
玄関を通り、招かれるままに入り込んだリビングは、恐れたほどの、光景ではなかった。どんな主婦がまな板を叩いていても不思議ではない、所謂ところの普通の部屋だった。どの家具を見渡しても、年季以外の、なんの痕跡もない。
例えば、この机だ。中央に据えられた、木製の大きな机。その隅には本が積まれている。団欒を支えるであろうこの机。仲の良い家族が食卓を囲む想像はできても、殺しの計画を立てる殺人鬼が齧り付いていたなんて、すこしも感じさせない。
僕は、ここに入る前、心のどこかで腹を括った。タイル敷の、壁の両側に手錠が繋がれた部屋。数々の拷問器具の並ぶ、血のシミだけが目立つ、殺風景な屠殺場。そんな、棺桶のような、さもなければ、子宮のような部屋を想像していた。
しかし、この部屋の雰囲気は、どちらにもそぐわない。現代の生活のように、生も死も感じない、中間色の色彩だった。正しく中間に収まっていながら、そのくせどちらの色も持っていない、陰影から弾き出された、異色の普通空間。僕は面食らった。部屋の隅にも、テレビの裏にも、世間と同じような正午が充満していた。
準備した前のめりを使いきれずに、ただ呆然と、普通の客のように、腑抜けて机のそばに佇むしかなかった。庭に向かってはめられた窓から見える昼は、明日の昼の様に、遥か遠くに見えた。
しかし、このレインコートの男は一体誰なんだ。台所に消えた男が殺人犯だとして、部屋を見回して、楽しそうにしているこの男は誰だ。この家の主は、僕を招き入れるときに、確かに君たちと言った。主の知らない男なのか?何が何だかわからない。
しばらくして、マグカップを携えた男が戻ってきた。それを僕たちの席にそれぞれ置き、ゆっくりとコーヒーを飲み始めた。男は、この普通の部屋に、春に春風が舞うかの如く、自然に溶け込んでいた。
僕は、マグカップを見つめる。客にコーヒーを飲ませたいから、コーヒーを出した。これを、そんな日常的な動機では捉えられない。僕にとって、都合の悪いものが入っているに違いない。彼の目的は何だ。はっきりとは分からない。いや、漠然とも分からない。
「生活上の都合はともかくとして、翼というものの第一義は、捕食者からの逃亡にあるらしい。どうやら鳥は、空を求めるのではなく、陸を怖がり、翼をはためかせるらしいんだな。」
しばらくの沈黙の後、男が突然口を開いた。
「ここで、聞いておきたい。強張った君と、嬉しそうな君。君たち二人組が、なんの目的があってここまで来たか知らないが……。」
「……なぜ逃げない?2人して、陸の秘密を知ったんだろう?」
「体に、特別な障害があるようにも見えない。それぞれ好きな所まで、逃げればいいだろう。」
僕は、男の顔を見る。男の目は、やはり太陽のようだった。太陽は明るく、偉大なものの比喩になる。しかし、ここで僕が言いたいのは、そんなことじゃない。僕が太陽を引き合いに出して表現したいのは、無差別だ、ということだ。誰しもを照らす太陽。しらみつぶしに、無差別。
「進めよう。君だって主演なんだ。」
隣の男の告げる、訳のわからない文句を半ば無視して、僕は尋ねる。
「何が入ってる?」
僕は、マグカップを見つめながらそう言う。
「そのカップの中に?コーヒーだ。」
男は、ニヤリとしながらそう答えた。
「毒、というものはだな、ただの物質だ。」
「或いは粉末だったり、液体だったり。形状は様々だが、ともかくなんの運動エネルギーも持たない。ただそこに、凪の様に静かに佇んでいるだけだ。しかし、生体に取り込まれればその途端、泡を吹いたり痙攣したり。大嵐を起こす。自殺、暗殺、サスペンス。人間の世界に、大きな揺らぎを与える。たった一滴で、湖を枯らす。人間、社会、国家。そして、住宅。複雑なものは往々にして、意外で極端な弱点を持っている。」
「……。」
「他人の家を訪れた時、もてなしに出されたものは、とっとと飲むものだ。飲まないまでも、フリでもいいから口を付ける。それが、まともな社会人の流儀だ。」
「一体なんだ。その無意味な礼儀は。嫌いなんだ。そういうのが。そんな退屈なやつは、僕は許さない。凪の呼ぶ嵐に吹かれてしまえ。」
初めて、男が、その真顔を見せる。
「あなたは誰だ。」
遂に捻り出した僕の言葉を、半ば知っていたように男は吹き出した。
「お邪魔します。あなたは誰ですか。か?人の家に訪ねてきておいて、それはないんじゃないか。」
「返事を返すよ。いらっしゃい。君はもう帰れない。」
男は笑う。
男の言葉は、銃身を通り、体にねじ込む鉛玉のように聞こえた。何も返せないでいると、地面に落ちる薬莢のような小音で、男は薄く笑う。早くも後悔し始めた。怖い。帰りたい。腹を括るなんて言葉、なんて不確かなんだ。
なんとなくわかる。この家の持ち主も、穴の秘密の製作者も、多分この男だ。ただ、硝煙の様に漂うこの沈黙は、男との合作ではない。僕自前の沈黙だ。それなら、あんたは誰だ。同じように、ただ、発生源は全く違う笑みを湛えたあんたは誰だ。殺人の共犯者でなくても、この沈黙の片棒を担いだのは間違いなくあんただ。そう感じて、隣の男を見た。レインコートの男は、ただ黙って、笑顔で返す。
「あなたは、犯人か?」
震える声帯を抑え、家の主人に問う。
「なぜ、そんなことをする?彼らが何をした?」
男は、呆れたようにため息をつく。
「私は逆に君に聞きたい。なぜ、そんなことを聞く?そもそも、犯人とはなんだ?事件なんて、起きたのか?君は、警察関係者なのか?君は、裁判官なのか?私を裁くのか?捕らえるのか?」
確かにそうだと思った。まず、この出来事は、事件としての認定を受けてはいない。だから、犯人とはならない。それなら。
「なぜ、彼女は死んだ?」
「なぜ?デリカシーがないな。君は。男女の関係の破綻を、そう易々と聞くもんじゃない。」
「私に、誰であってほしい?いいか?私が、君にとって誰であるかなんて、君の解釈次第だ。哺乳瓶で、人は殺せる。肉を裂く鋭いメスは、人を救う。意味はわかるか?」
「別に、彼女を知っていたわけでもあるまい。死体を偶然見つけたから、襟を正して隣人気取りか?彼女は、死んで初めて、君の人生に登場した。違うか?死ななければ、関心を持たない?生きているものには興味がないのか?」
何一つ、答えられなかった。ただ、なんとなく、僕と同じような疑問を持っているのかもしれないと思った。
「何が足りなかったから、そうなったんだ。」
嫌気の差した取り扱い説明を繰り返すような調子で、男は答える。
「出身地を知りたがるのは、最近の人間の、悪い癖だぞ。幼少期の体験がどうだ、トラウマがどうだ。子宮の間取り図にそんなに関心があるのか。それは再生産のロジックだぞ。同じものを同じ形で生み出したい時に使う思考だ。人にどこから来たのか尋ねるのは、コミュニケーションに手間取るときだけにしろ。私を生み出したいのか?それなら、理解出来る。そうなのか?」
「注釈や後書きに、どんな意味がある?本文を読めばいいだろう。まあ、一応真面目に答えると、君が知っているどんな夜よりも暗いところからだ。」
はぐらかして冗談を言っているのか、真面目に答えているのか分からなかった。そうして、しばらく僕の表情を見つめた後、にっこりと微笑む。
「くだらないことばかり聞くな。やり過ごすために、ここにきたのか。君が、普通の欲求を持った人間ではないことはわかる。答案用紙に、定められた答えを書き込む様な真似はよせ。」
「……なぜ、ここに来たのか。なぜ逃げないのか、分からない。でも、来なくてはならなかった。だから、来た。ここ以外の場所はもっと嫌だ。」
僕は、沈黙よりも、本音を選ぶことにした。
「その通りだ。」
男は真顔で答える。
「足りないものがあった。その存在感は、僕の中にある、どんな形のあるものよりも大きなものだった。空白の痕跡は、何よりも大きい。でも、それがなんなのかは、判然としない。ここに来れば、その浮き彫りになった空白が埋まらないまでも、なんなのかがわかる気がした。」
嘘ではなかった。
「そうか。」
「君は、ここに何かを捨てに来たんじゃないのか。私がいるんだ。当然、みんな、ここで何かを失う。そうじゃないんだな?君は切実に、何かを拾いに来た。」
「なんとなく、来てみただけだ。」
「そう。それだ。なんとなくさ。」
男は嬉しそうに、こちらを指差す。
「初めはそうだ。」
「今は違うと?」
「人間が、何かを拾えるとしたら、得られるのだとしたら、その場所は家庭だと思う。大体の人間がそうだと思う。でも、僕は違った。初めの器が無かったんだ。」
「そして、旅に出て、金を失う。社会に出て、心を失う。人生に向かい、魂を失う。これからそうなる。だから僕は、この屠殺場で、骨以外の何かを拾う。」
「まさか、家庭で得られなかったものを、ここで得ようと?」
男が、その滑稽を楽しそうに笑う。まあ、そうだろうと思う。
「あなたにとって、ここは、なんだ。」
「好立地でありながら、好発部位だ。」
「尖る街の先端であり、最奥の彼岸。」
「まあ結局、要するに、つまるところ、落とし穴だな。」
「ここは、あなたの砦なのか。」
「あるいは、凶器だな。」
「熱が、火のことだとは思わなかった。なぜ、火をつける?」
「熱……?」
「あの、年末の火災、あんたなんだろ。」
「ああ、あれは出張だよ。サラリーマンと同じ。」
「ちょっと、サラリーマンの真似をしてみたのさ。」
「人間の人生は、プラモデルと同じさ。決められたパーツに、決められた手順。同じ素材の同じ規格に、同じ塗料。取扱説明書に逆らわず、付け方さえ間違わなければ、予定通りの形に完成する。しかし、一度でも工程をミスれば、それでもう終わりだ。その後の造形は、全てチグハグになる。我々が手を合わせて乞い願うことは、パーツの中に、不良品が存在しないこと。中には、カラーリングで差をつける人間もいるね。それでもたかが表面だけのやりとり。所詮は似た様なものさ。」
「幸運なことに、私は、その我々の中に含まれない。我々は、君たちのための言葉だ。」
「僕は、余剰だ。ずっとそう思ってる。家族にも、街にも、社会にも、歴史にも、僕は、余剰の存在だ。成長していく、拡大していく余剰。子供の頃からそう思っていた。」
「そうか。」
「余計ならそれでよかった。余分ならそれでもよかった。脂肪のように、削ぎ落とせばそれで済むんだ。でも、ことは難しい。僕は、余剰なんだ。飢餓に備えた、余剰な脂肪なんだ。世界が、骸骨にならないための、予備の脂肪だ。」
「なるほど。」
「その余剰に、何か出来ることがあるなら……。」
「あるなら……?」
男が首を傾げ、先を促す。
「その先が、欲しい。」
男は、くじの二等を当てた時の顔で、笑う。
「なあ、運命を信じるか?なんらかの運命だ。人が、都合のいい偶然につける名前だ。」
「運命?」
「運命だ。深い深い縁だ。こめかみと弾丸。首とロープ、そして、家屋と炎。」
「宿命なら信じる。」
「自分がいつか捨てたものに、躓くこと。自分が崇めたものの周りを、ぐるぐる回っている途中で。」
「ほう。」
「だから僕は、何も出来ない。」
何も知らない。何もわからない。
「袖振り合うも、なんて言葉もある。宿命が、君をここまで引き連れてきた以上、なんらかの意味があるはずだ。」
僕は、静かに頷く。その時、レインコートの男が突然口を挟んだ。
「なあ待てよ。流石にそれは見過ごせない。これは、天が作った宿命じゃないぞ。」
僕は、男の方を見た。
「ここで俺が口を出すことは、誰にとってもいいことじゃないよな。なぜなら、俺はキャストじゃないからな。でも、それは流石に、作者の気を損ねるってもんさ。宿命を作ったのは、この俺だ。」
「突然喋り出したと思ったら、一体どうした?」
「なあ聞けよ。どうすればこれが、拍手に足る物語になるか。俺は考えたんだ。」
レインコートの男は、構わず続ける。
「興奮していてな。順を追えない、悪いな。俺は、全てを見たんだよ。お前の殺人や、家の裏手にあった新しいノート。あの女のことや、放火のことが事細かに書いてあったな。」
「そうなのか。」
「いや、しかしお前の無軌道ぶりには、辟易したぞ。立て続けな殺人。杜撰な処理。俺が膳立てしようにも、時間が無いと感じた。遅かれ早かれ、お前は警察に捕まる。そう思ったんだ。」
「ただ、それだけは許せん。ロードローラーで全てを真っ平らにして、みんなで仲良く真っ平らで、それで終わりか?そんなことは、誰も望んじゃいない。」
「そうだな。それで?」
男に促され、語気が強まる。
「そこで、探偵を探そうと思ったんだ。どうにかして、この殺人者と探偵の対決を実現させたかった。俺だけの物語。俺だけのミステリーサスペンスだ。」
僕の方を指差し、邪気たっぷりの笑顔を見せる。
「無理矢理連れてきたのでは意味がないのだ。探偵は、探偵の意思に基づいて、ここに辿り着かなくては。だから、探偵にここを探させよう。そう思った。そちらの方がいい。何かしらの痕跡を点々と残し、この穴まで導こう。」
合点はいく。釈然とはしない。
「居ることはわかっていたぞ。こちら側の人間が。お前はまんまと捜査を始めたんだな。例の火事の犯人だという証拠を掴むために。」
この男の言うことは嘘じゃ無い。あまりに出来過ぎだと、ずっと思っていた。
「あの手紙は、あんたのものか。」
「どうだった?一応、創作者志望だったんだけどな。」
「お前は、放火魔の特性も調べたはずだ。放火魔は現場に戻る。これはもはや定説だな。そこで、あの家が燃えるのをじっくりと観察できる、遠近様々な位置、そこに、手紙を置いた。隠す場所は、分かりづらい場所で良かった。こういう場合の、そういった物好きの費やす労力は計り知れない。しらみつぶしに証拠を探すだろうと思ってな。」
「あの供物の件も、あんたなのか。あれはなんの意味があるんだ。」
「ただの放火を誰が調べる?放火があった。ああ、物騒だな。これで終わりだ。なぜ、そんな捜索などする?今では人は無関心だ。近所の放火など、警戒はすれど興味など持たない。」
「なんらかの特殊性を持たせなければならなかったのさ。特別な何かがあったのだ、と思わせなければならなかった。そこであのステッカーだ。正直、それぐらいしか手が無かったんだよ。」
僕は日照り雨に打たれ、悔しさなのか、恥ずかしさなのか、自分でもよく分からない感傷にびしょ濡れになった。この男に反故にされた。一体何を……?
「……ただ、本当にそんな奴が出てくるとは思わなかったよ。実際、この件の俺の計画は、二段構えだったんだ。本命は、こいつの殺人プライベートビデオ。探偵の君の件は、オマケみたいなもんさ。」
尚も計画を楽しそうに捲し立てる男を呆然と見つめながら、散り散りになった僕の心は、ある感情に、集約を始めた。
「とまあ、こんなわけだ。それにしても、折角のシチュエーションなのに、くだらない共感ごっこのヒューマンドラマに落ち着こうとするなんてな。こんな早い段階で、カーテンコールをしなきゃならなくなった。」
「我慢してたものを吸わせてもらう。」
男は深く座り直し、タバコを咥える。
「亡霊は嫌煙家ではないんだろう?」
そう言って、男は目を瞬かせた。それを見て家の主は、合点が入った様に眉間に皺を寄せる。
「そうか。なるほどな。思い出したぞ。君は、ポイ捨ての。邪悪を隠すのがうまいな。それが君の特技か。」
「お久しぶり。あんときゃ焦ったぜ。」
「自分だけが上手だと思っていたか?何か、言いたいことは?」
「ここにきた時点よりも、部外者だな。」
「気の弱い青年と気の狂った殺人鬼。面白いものを見た。まさか、手を取り合おうとするとは思わなかったよ。少し早いが、この辺で幕引きさ。」
男は軽く流し、静かに詰め寄る。
「それで、どうするんだ?君の都合で自分の正体を明かした以上、この状況の打開責任は君にあるぞ。」
男はゴツゴツとした黒っぽい機械を取り出し、手元のスイッチを入れた。その先端には、鋭い音と共に電気が走る。
「この意味がわかるか?ここは、アメリカじゃない。」
「気の弱い青年よ、このスタンガンを持て。手を加えて、調整をキツくしてある。タイミングと箇所によっては、死ぬ可能性すらある。使うんじゃないぞ。」
僕は、逡巡した。男はそれを気取る。
「ならいい。ここに置く。その男が取らない様に見張ってろ。」
そう言って、男がスタンガンと称する機械を僕のそばに置いた。
「まともに考えろよ。殺人鬼だぞ。殺人鬼。まさか、外の女を忘れた訳じゃあるまい。この部屋にはいないかもしれないが、外の世界には警察がいて、裁判官がいて、そして牢獄がある。ちなみに処刑場もな。馬鹿をやれば、馬鹿を見る。いくら余剰でもそれぐらい分かるだろ。加担するか?しないよな。」
俺には、俺のプランがあるんだ。そう言って男は、スマホを操作し始めた。僕は、頭に血が上った。許可もなく撮影されると、こんなにも腹立たしいのはなぜだろう。自分のドラマを、勝手に切り出されることへの怒りなのか。
男は、僕が幾つかの失敗が重なれば行ってしまうかもしれない道の中央で、居直っていた。そう思った。突然、我慢がならなくなった。
「あなたは貧相だ。」
「体格の話か?容姿批判が、最初で最後の反撃か?」
男は一瞥もせず、スマホの録画機能を操作しながら答える。僕は、スタンガンを手に取った。
「あなたには、傷が少ない。そう思った。確かに、血まみれのくせに。登場人物じゃないっていうのは、一体どのドラマにだ?これは、誰かの作った物語じゃない。まして、あなたでは決してない。いいか?あなたは、あなたの物語に登場しなかった。」
「指人形のように、操ることが、創作だと思っているんだろ。ドラマを作ることだと思ってるんだろ。」
僕はこの時、息継ぎも忘れていた。
「不感の生み出す恐るべき苦痛に喘いだんだろ。ドラマに登場しないことに、誇りを持ってしまったんだろ。あなたは、僕と似ていて、僕の一番なりたくない姿をしているよ。」
「素晴らしい批評だ。なるほどその通りだ。じゃあ、どうする?病状はわかったな?どう治療する。どう治るつもりだ?」
「分からない。」
「知ってるよ。」
「お前のことなんて、分かってる。馬鹿みたいに探偵を気取って、こんなところまで迷い込んできやがって。いずれたどり着く場所は、ここだ。お前は、遅かれ早かれ、この泥沼に辿り着くのさ。俺は、死地の先輩さ。敬意を払え。」
「あなたは、ドラマの証拠を集めたと思ってる。違う。それは虚構の証拠だ。影のアリバイだ。あんたのそのレンズ。僕は嫌いだ。僕はここに等倍のレンズを拾いに来た。ミクロでも、マクロでもない。」
僕が饒舌なのは、自分と会話しているときだけだ。だから、今日はよく喋れる。
「このスタンガンが、その証拠だ。これが実銃なら、僕は、ここまで腹は立たなかった。威嚇の為の代物。虚仮脅しの暴力。こんなもの、くそくらえだ。痛みだけはごめんなんだろ?」
「よく分かってるな。正解だよ。なぜなら、お前もそうだからだ。」
「人を殴るなら、自分もちゃんと骨折しろ。」
僕は、男の首元にスタンガンの先端を押し当てた。すると男は、素っ頓狂な声をあげて倒れ込んだ。家の主が、喜劇の観客のように、拍手をして笑う。
「手前勝手に、高を括るからさ。それがお前の弱点だ。」
彼は、気を失った男の方へ語りかけた。そしてうめき声を上げる男の体を抱え、どこかへ連れて行こうとした。
「殺しはしない。ただ、家を汚されたくない。小便でも漏らされたら、それこそ殺してしまう。帰ってきたら、話の続きをしよう。」
彼は引き止めようとした僕に向かってそう言い、レインコートの男を引きずって行った。
僕は席につき、テーブルの上にある花を見た。枯れるのをただ待つだけの、その花を見た。僕は一体、なんのためにここまで来たんだったか。何がしたかった。何が欲しかった。さっき口をついて出た、等倍のレンズという言葉。
ここから運良く生き延びて、それが一体なんだというんだろうか。これから一生続く、枯渇したミイラの生活。枯れた喉がここを求めた以上、ここはきっとオアシスには違いないんだ。猛毒が混じってはいても。どこに顔を突っ込んで喉を潤すか、じっくりと見定めよう。僕を理解してくれそうな、彼のそばで。
僕は、花瓶に詰め込まれた、淡い黄色の花を見つめた。初めて、花というものをまじまじと見た。美しいと思った。どんな色の、どんな嵐に吹かれると、さらに美しいだろうか。そして、これはなんという名前の花なんだろう。
僕は、自分の服を見た。パーカーの袖の部分を見た。そこにはなにやらルーン文字のような文字が刺繍してあった。驚いた。こんな刺繍があったのか。思えば何年もきている服だ。
そうか。僕は、世界に興味が持てなかったんだ。だから、ここへ来たんだ。
「人を、理解したい。」
「それは難しいな。私は、難問だ。なんせ、私でも私を分かりかねている。」
僕は、男の真似をして、独り言を言った。
「なら、なぜ分からないか、分かりたい。」
僕は、目を開こうと思った。改めて、机を見渡した。そこには、例の哲学者の別著が連ねてあった。あそこには、別の線が?それとも、なんらかの書き込みがあるのか?僕はその本を、手に取った。何度も開かれたであろう表紙を開き、パラパラとめくる。書き込みは特に見えなかったが、裏表紙に、何かが貼り付けてあった。
日記を探すあなたへ。
まずは、秘密の暴露から始めます。あなたの日記を、うちの金庫に隠しました。なぜそんなことをしたのか、あの日記を書いたあなたなら、動機は予測がつくでしょう。この家のこと、私のこと、そして、人殺しのこと。たくさんのことが書いてありましたね。あんなにこれ見よがしに置いていたあの日記も、考えてみれば、全てに与せという、あなたからの提案だったのでしょう。私は、拒否します。最早、何もかも。
お金と情報。こんな立派な交渉の道具はあるでしょうか。あなたは、自首なんてしない。そんな、勝算の無い降伏なんて、絶対にしない。それだけは分かります。お金だけなら、あなたはどうにかするでしょう。また、浮雲の生活に戻っていくでしょう。でも、日記はどうでしょうか。きっとあなたは困り果てる。
わたしは、あなたを処刑台に送る代わりに、あなたを脅し、監視しながら、生きる。これしかありません。心がきまったその日に、私はあなたを脅迫するでしょう。その時は、どうか観念してください。
それでも、もしこの手紙を見つけてくれたなら、全てを渡します。どこかへ。私の耳も目も、心も届かない空の彼方へ消えてください。
自分の命を、人質に取れないことの悲しみは放っておいて、あなたのよく読む本の最後のページに、わたしの逡巡と決意を彷徨った道標をせめて。
そして、あなたと暮らした日々に、愛の全てを込めて。
✖︎✖︎✖︎より
暗証番号:✖︎✖︎✖︎✖︎✖︎✖︎✖︎✖︎✖︎
「さて、話の続きだ。アランの幸福論の続きだったか?」
男は体をさすりながら部屋に戻ってきた。
「マッチを貸してほしい。」
「あいつを温めに行くのか?凍死にはまだ早いぞ。まあ、構わない。ただ……。」
「なぜ泣いている?」
「答案用紙か。たしかに、答えは定められてるな。何を書いても……。国語は、得意だったんだ。いい点をとった。でも、記述だけは、点でダメだった。あれだけが足を引っ張ったんだ。」
男は頷く。
「ところで、✖︎✖︎✖︎さんて、誰だ?」
途端に表情が凍りつく。それを見て僕は、マッチを擦った。
「何を燃やしている?」
僕が火をつけた紙切れを見て、男は尋ねた。
「あなたが捨てたものだ。」
「手紙だよ。」
「待て。」
「話がしたい?」
「何を言っている?」
「わかるだろ。名前のこと。嘘なら、こんなこと知らない。」
「返せ。」
「あなたのものじゃない。あなたは捨てた。無論、僕のものでも無い。あなたは愛を軽んじた。酸素の如く、軽んじた。いくらでもあると思ってしまうから。」
僕の左手にあるスタンガンの先に、電気が走る。
「日記は、あの中にあるんだな?」
男は、伏し目がちにそう言う。
「なあ、朽ちて花開く物もあると思わないか?私は君を気に入った。殺しはしない。ここから逃げるのか?君が嫌がった、一番どうしようもないエンディングを迎えるのか?」
「気に入ったから、殺さない?そんなくだらない理由で?」
「金が、ないんだな。」
「それを飲め。」
僕は、目の前にあるマグカップを指差した。
「人の話は、ちゃんと最後まで聞くべきだ。ゴミを捨てたんじゃない。捨てるからゴミになるんだ。」
「僕は、よく列車に乗る。次の列車に遅れない様に、急いで乗る。駅に着けば、次の列車だ。また、次の列車に遅れない様に、急いで乗る。なぜ乗るか?次の列車に遅れない為だ。列車に乗る。乗り継いで、次の列車だ。そして、終着駅に着いた時、どこの景色も、心に残っていない。」
「何が入っているのかは、僕は知らない。完全に知らない。そして、僕は、あなたのことが、好きなのか嫌いなのかも分からない。だから飲め。あなたが、僕を容赦した量だけ、明日を迎える。あなたが僕に向けた悪意の量だけ、あなたは明日を失う。結果の知れた、跳弾のロシアンルーレットだ。」
「冷めてる。」
男は、いくつかの悔恨を口にし、一息にマグカップを空にした。僕は、しばらくして彼が卒倒するのを待って、家を出た。
泥から伸びる、女性の腕を見つめた。
僕は時計を見る。
僕は、街の方へ歩いていった。












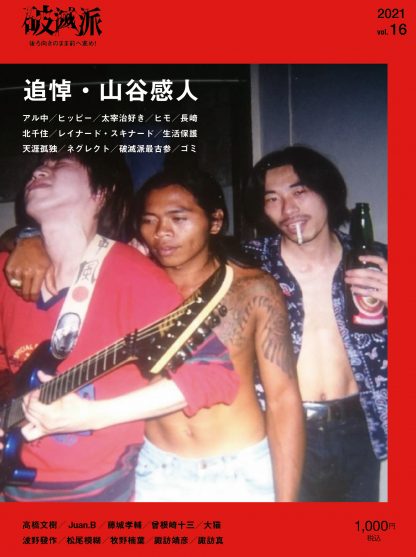













"脱落者"へのコメント 0件