この、飲み屋街でさえ人通りの消えた、夏の、光の届かない海の底の様な深夜。アスファルトを枕に、生温い34℃を掛け布団にして、女が1人道路に寝込んでいた。
目は明け方の様に半開きで、顔は、真昼の太陽の様に赤い。夕雲色の口紅を差した口の端から、雨の様に涎が滴った。彼女は独り、静かに痴態を演じていたが、この一部始終を、目撃している男がいた。いや、正しくは傍観だろうか。
彼女の寝転ぶ道路の際、テナント募集の看板の目立つ、コンクリート打ちの雑居ビルが立っていた。シミのこびりついた階段を上がると、殺風景な廊下が出てくる。いくつか並ぶ部屋の、汚れと朽ちが一番マシな扉の奥、1人の男が椅子に腰掛け、ベランダから安いタバコをふかしながら、彼女を見つめていた。片手にビデオカメラをぶら下げながら。
その目つきからは、別段なんの感情も伺うことは出来なかったが、完成したドミノを目前にしている様な、焦燥感と興奮を秘めた光が、乾いた瞳に微かに浮かぶ。
男は、女のことを知っていた。近くにある、小料理屋の経営者。よく笑い、よく喋る。差し障りの無い善人で、腰に持病を抱える中年の独身。男は、近くの居酒屋で皿洗いをやっている関係で、軽く世間話をしたこともあった。初めは、無関心から放置していた。特に貸している金も無い。
アルコールに右も左も奪われたいのなら、好きにすればいい。そう考えた。泥酔した人間なら、いままで何人も見た。しかし、道路に堂々と寝込む人間は初めてだった。
男は、女を具に観察した。司法解剖を行う監察医のように、彼女の身体を見渡した。実際の死体と違うのは、女はまだ死んではいないということと、今にも死にかけているということだった。肩から外れ、アスファルトに寝かされたブランドバッグ。はだけたコート。地面を掴む白い腕。
そのうち、何か愉快な出来事が起こる可能性から、彼女をわざと見落とすことにした。静かに部屋の電気も消して。獲物の多い森に罠を仕掛けたような気分で、携帯電話を開いてそばに置き、彼女を見つめた。
すると突然、道の向こう側から車のヘッドライトが光った。詳細は定かでは無いが、一台の軽自動車が、猪の様にスピードを上げて近づいてきていた。ああ、見つかってしまうのか。泥酔を心配され、起こされる?通行の阻害を咎められ、退けられる?それとも、救急車を呼ばれる?これで終わりか。男はそう思った。
しかし、男の落胆とは裏腹に、猪は罠にかかった。突進をやめず、女をまともに轢いた。一度跳ね飛ばした上、女に乗り上げた。女のシルエット通りに、車体は浮く。そして、猪は死んだ様に静止した後走り去っていった。男は110番をかけながら、臓腑の底から笑いが湧き上がるのを我慢出来なかった。女の、そして運転手の運命を握ったあの空白の数分。我が手中の、この透明なパズルピース。ビデオカメラのスイッチを切り、吸い終えたタバコのフィルターを、道路に向かって投げた。
男は、夏の夜のコンクリートジャングルでの狩りを思い出しながら、今にも雪に変わりそうな冷たい雨の降る外を眺めていた。男は、呟いた。
「退屈だ。」
男は、どうでも良かった。雨粒の一つ一つが。雨粒の打ち付ける街が。そこに住む人々が。何もかもがどうでもいいから、なんのドラマも生まれなかった。
男は昔から考えていた。人の世に、ドラマが消えたのはなぜだろうか。なぜ、こんなにも空虚な回廊が、どこまでも続いているのだろうか。いつの時代でも、感情は、激情は、誰でも持っていた。それでも、かつては感情は生まれたところへ戻った。区切りがあり、仕切りがあり、閉じられた空間の中で、的と矢尻は、同じ材料で、同時に作られた。
今では、感情の矢尻は、同じ的へは向かわない。ただ、対象があろうとなかろうと、放たれない限り感情は膨れ上がり、力は残る。矢尻は力の発散を求めて、やがて対象を探す様になる。お門違いの的を。男には、街のそこここに、震える矢尻の先端が見えた。引き絞られた感情と心情との矢尻だけが、街で尖りながら交錯していた。人々は気がついていた。的になってはいけない。万が一的になれば、謂れのない見ず知らずの矢尻が、己を目掛けて四方八方から飛んでくる。だから、人々は沈黙した。ますます、ドラマは遠のいた。
男の解釈はともかく、ドラマは手に入りはしなかった。だからといって、必要でないわけでもなかった。男は壮絶にドラマを求めた。しかし、真剣に生きなかった幾つもの昨日が、今日の、こののっぺりとしたドラマの無い23時を、呼び寄せていた。
いま、この沿道を塞いでいる落石は、いつか自分が投げた石によって引き起こされたことを知っていた。だからこそ男はそれを憎みもがいたが、それでも、この挫滅はどうしようも無かった。
そこで男は、ドラマを作ることを選んだ。
主人公になれないなら、せめて作者になろうとした。しかし、男は失敗した。ドラマは、内側に生きるよりも、外側から形成する方が、はるかに困難なことだった。男の人生に実はなかった。端から端まで虚で満たされていた。虚を憎みながら、虚の快楽に溺れた。
創作者、芸術家の道は細く険しい。それだけに、そこから落下した男は、まともに現実に打ちつけられ、男の心は、落下死体の様に変形した。男は、そのグロテスクな心を引きずり、残りの人生を過ごすハメになった。
泥酔した女の一件を始め、男は、時代の、世の隙間を針の様に求め、街を徘徊した。自分が神だと錯覚できる状況を、信徒の様に祈り願った。
街の間隙を、人々の罪を、物語としてビデオカメラに残すこと。これが彼の生活だった。彼は、それこそが、廃物と化した己を打破するものだと信じたが、結局のところ、単なる悪辣な操り人形師でしかなかった。
退屈な雨の夜。男は、矢尻と的を探しに、或いは、物語が生まれそうな場所へと自転車のサドルを跨いだ。ベージュのレインコートのフードの内側に、色素沈着のひどい白眼だけが浮かぶ。明るく、公に開かれた場所は、物語に適していない。均一で、刹那的で、包括的。そんな場所に用はなかった。出来るだけ、事情に満ち満ちた場所。当然の如く、男の色褪せた車輪は、より暗く、より狭い場所へと向かった。
街の中心部を抜け、ふらふらと、流れ弾の様にしばらくペダルを踏み続けていたところ、いつもの場所で、いつものため息をついた。長い信号待ちをしながら、空でも絵が描ける程見た光景を、恨めしそうに眺める。
低い山々から、商業施設の多い区画と住宅の集まる区画を二分する川が通り、その上を、名がついた橋が架けられている。橋の両端から道路が山形になっており、男は橋を通りかかるたび、億劫そうに立ち漕ぎをするのだった。
今日も、この場所だ。買い物以外に、あの橋を渡る用などない。それでも、目的も無く自転車を走らせる時はいつも、この場所へと駆り立てられた。なぜ、いつもここへ来る?もしかすると、帰りたくなるためか。男はそう思った。元より、具体的な目的地などないのだ。目的はあれど、そうそう見つかりはしない。家は退屈だ。外など億劫だ。この相反する意識の折り合いとして無意識に選んでいるのが、この半端な難所だったのか。
信号が青に変わり、男は橋への坂を、自転車を押しながら歩き始めた。橋を越え、住宅地側の区画をしばらく行くと、右手に県道から外れた道が伸びていた。木々が深く垂れ込み、奥には濃い闇が広がっている。
辛うじて車一台が通れるか否か程の小道が、いくつかに分かれている。そのうちの一本は山を回って急なカーブになっており、先は見えなかった。先を知っていなければ、行くことはない様な道だった。
男はこの辺りに住んで、十数年、街のほとんどは、視界に入れたはずだった。それでも、直接立ち行ったことのない場所は、いくらでもある。ここも、そのうちの一つだった。入り口にある家屋の玄関に、火の用心と印刷されたステッカーが貼ってあった。100均で売っているありふれたものだった。これは、物語の序章か、それとも終焉か。
雨が上がったのを見て、男は、自転車にまたがり、山沿いのカーブを進み始めた。時間帯のせいか、車の往来も無い。寂れた道を進んでいくと、その途中に、小さな公園があった。殺風景ではない。殺風景ではないが、豊潤でもない。
機能の密度を問うには、あまりにも場自体が朽ち果てた、風葬に晒した遺体の様な公園だった。その公園には、トイレさえ併設されておらず、当然明かりもない。雨上がりの靄が薄くかかり、なんとも形容し難い、稀な雰囲気を漂わせていた。
自治体に見放されたか、町内会の関係が薄いのか、こんな街の片隅に、誰からも忘れられた様に置き去りにされている、思い出の墓場。男は、いい舞台だと思った。自転車を降り、錆色の車止めを撫で、タバコに火をつける。煙を吸い込むたび、タバコの先端が、薄く辺りを照らした。地面の雑草帯から、青い、湿気た香りが上がってきていた。
ここなら、亡霊が出てきても驚かない。地面から、泥だらけの手が生えてこようと、ブランコの下に白い足が伸びていようと、なんら現実の反証にはならない。それほどの異空間だった。
心霊写真が現れたのは、カメラのおかげだ。しかし、心霊写真がなくなったのもまた、カメラのせいだ。男の探すドラマは、彼にとって亡霊の様な物だった。男は、撮影する様に、その風景に見惚れた。
目に付いた、用法の分からない、ドーム状の遊具に近づく。かくれんぼの鬼になった子供が、白骨化して裏に隠れている。自然にそんな想像をした。知らず知らずのうちに踏み込んだ、街を外れた道のそのすぐ奥には、驚くほど、豊潤な空間が広がっているらしかった。
虫の声もない暗闇の中、西側から、高い音が鳴った。そんなに遠くはない。何らかの金属音?木材を金槌で叩く音? ガリガリに痩せた骨と皮だけの子供たちが、缶蹴りでもやっているんだろうか。そう願う。
音の方へ近づき、耳を澄ませる。どうやら、公園を取り囲むフェンスの向こう側から、音は発生したらしい。蔦の絡まるフェンスの隙間から、目を凝らした。公園を超えたまばらな林の向こう、立方体に近い2階建ての家屋が見えた。その麓は玄関先のライトで、オレンジ色に照らし出されている。
ライトが照らし出していたのは、逆光の中で、人間らしきシルエットが何かを構えている様子だった。バットだろうか。よく見えない。取っ手の長い工具の様なものを肩に担ぎ、地面にある、穴の様なものにしきりに話しかけている。地面には、うっすらと、腕の様なものが見えた。しばらくすると、男が力一杯、工具を振り抜く。高い音がして、腕は消えた。あ、殺人だ。え、殺人だ。おお、殺人だ。さあ、レンズに亡霊が現れた。
荒い吐息が白くなって寒空に舞う。男が歓喜に打ち震えている中、殺人者は、穴に向かって、土を投げ込み始めた。そこで初めて、それはシャベルだとわかった。シャベルを立て、しばらく殺人者は佇むと、やがてカタツムリが身を引っ込む様にして、四角い殻の中に消えていった。矢尻だ。鋭く、毒と血錆のたっぷりと塗られた、矢尻だ。男は体を震わせた。撮影さえも忘れて。最高傑作が作れる。最高のドラマが。足りないキャストは誰だ。連れてこなければならない。良い的を。
空を見上げると、月が出ていた。月というものが、美しい景色から、物体へと変わってから、一体どれだけの月日が流れただろう。人が月に降り立って、何を失った。人は、月を、あまりに願いすぎた結果、あまりに愛してしまった結果、それをただの岩の塊に変えてしまった。馬鹿みたいに、その足を踏み込んでしまったばかりに。
「俺は、そんなヘマはしない。」
震える声で、男はつぶやく。
魔王には、勇者を。ヴィランにはスーパーヒーローを。そして、殺人者には、探偵を。男は、冬の夜を凍らせるような笑顔で笑った。












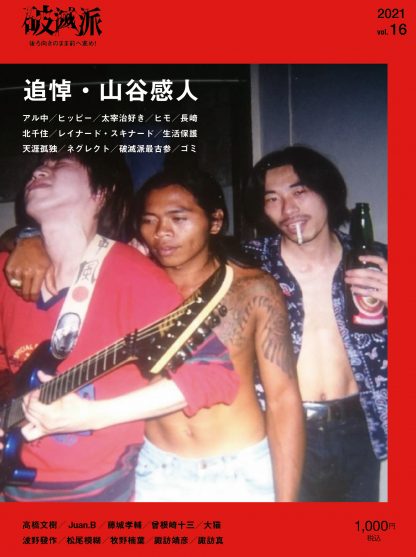













"作劇者"へのコメント 0件