深夜。台所。整ったうなじに柔らかい暖色のライトを浴びた彼女はつるりとした、極めて人工的な造形物であるスモーク味のサラダチキンをまじまじと見つめ、それを口に運ぼうとした、実際に運ぼうとしたのだ、しかしそのパッケージの底に溜まっている1ml程の黄土色の汁の方にビタと視線が張りついた。そしていきなりだ! いきなり、サラダチキン本体を叩きつけた。バいン、とゴム性の玩具が跳ね返るように……彼女は無表情で、水で流れ落ちなかった食器用洗剤の白濁したカスがびっしりとこびりついている銀色のシンクに何度も何度もそれを叩きつけた、ばイん、ばイん、……その鈍く、一方でとても軽い音は規則的な間隔でしばらく鳴り続ける。
なぜなら、広告業界で働く彼女は知っているからだ、世の中の全ての『ダイエット』サプリが意図的に創り出された完璧なデマであることを。彼女の一日はめまぐるしい、食事制限ダイエットをけなした後に糖質を取りまくって痩せる糖質活用ダイエットを勧め、その次は糖質活用ダイエットをけなしてケトン体ダイエットを勧めること、次は新たなダイエット菌を創り出しその二時間後にはまたそれをけなした新しいダイエット菌がエディタ上で創られることを。ウイルスのように無限増殖していくそれら、そしてその菌たちは存在もしない雑誌に掲載され権威を高められ存在もしない医者によって絶賛される。彼や彼女たちは液晶越しにあなたや彼女に当たり障りのない笑み、『不快』が完全に削り取られた親しみを向け続ける、うまくいけばそれはテレビで芸能人が絶賛しさらに莫大な利益を生む……その作業はある種のプロフェッショナルによって、残虐な手つきで速やかに行われる。ばいン、バいん……ばいん……
彼女は袋の底の濃縮液をちょうどすぐ脇にあったべこ、と歪に凹んだペットボトルに慎重に注いだ。7200kcalで1kgの脂肪がつくというのは科学的事実である。だがもはや、彼女には高タンパク低カロリーと謳われているサラダチキン本体ですらも信じることができなかった。もう、もう……自分のついてきた、そしてこれからもつきつづけなければならない欠点のない嘘が体に蓄積されぶつぶつと煮えたぎり、自爆が近いことを自覚していた、だから、そのペットボトルの底に溜まったわずかな濃縮液しか……それしか……彼女はシンクに佇む鶏肉の塊をゴミ箱に捨てた。
その朝は実に……傍若無人な晴れやかさだった、彼女がデスクにつくと同時に美しい栗色のボブカット——後輩はその濃い桃色のニットが本当に良く似合う、その素の性格の優しさにとても合っている、白い短パンから剥き出た健康的に焼けた脚が早々と走り寄ってきて、
「今日のiosのデブまじやばいっすよ……!」と言った。そう言いながらもなぜか彼女は嬉しげだった。これは毎日のように交わされている会話だった。彼女たちはもう正気のまま気が狂っていた。
「何? どっちの『ヤバい』? いい意味? 悪い意味? 朝起きたら爆死してた? 日予算飛んだ?」
「ちょっとスプレ真っ赤ですよ。地獄絵図ですよ全然売れてないっすよDサプリ全部。駄目っす。もうiosのデブ救いすぎましたかね? あれどっか消えた? 滅亡した? 昨日夜限界まで管理画面張り付いてたんですけどね、Androidのデブはいい感じで跳ねてるんですけど、……ちょっと先輩iosのデブ作ってくれません? 先輩、ほんとなんでも作れるじゃないですか、なんでも」不気味なほどからからと後輩は笑った。
「あのね作れたらもうとっくに作ってるわ、何、記事はあなたが書いたやつでしょ? どれ、見せてみ」彼女は背後の後輩のPC画面を見て、それから絶叫した。
「ダメだよこんなの! えっ」彼女はべろ、と目をひん剥いた。
「……すいません、いけるかと思ったんですけど……」
「全然ダメだよ! 脂肪破壊ビーム出せって言ってんじゃん! TOPだよ!? 何勉強してきたの? キレイすぎるよこんなの。わかんないよ、こんなんじゃ、伝わらないよ」
「毎日ビームだからユーザーも飽きるかなと思っていじったんですけど……」
「ビーム出さないならデブシャツのボタン飛ばせそれかおもいっきしデブの肉揺らせ、速度鬼速めて。それか3Dアニメだったらビフォーアフター通るんでしょ? とにかくTOPは『迫力』なんだよ、負けてるんだよこんなの最初から」彼女は昨晩のペットボトルを鞄から取り出して飲んだ。すぐに吐き出したいほど不味かった。空腹で大量に酒を飲んだ後にぐえぐえとえづきながら喉を通過していく胃液の味だ。
「そうっすよね……やっぱそうっすよね……すぐ直して審査出します。でももうあっちの運用にビームやめろって言われてるんっすよね、」
「ほんとあの運用担当使えねえな」
「どうしましょう? ……ってか、先輩毎朝サンマルクのブレンドなのに……なんですかそれ」
「……さぁ?」彼女はおぞましい笑いをした。
「なんだろうね?」ほんとなんなんだろうね? もう私もわからないよ。何もわからないんだよ、と言ったら……? 一番可愛がっている後輩にこの自分の弱みを見透かされたくなかった。
だが今日、いつも艶やかな朱のグロスで輝く後輩の唇が濃い紫にくすみ、その奥から濡れたパンが腐ったような匂い——つまり、明らかな病の匂いが漏れ出していることに彼女は気づいた。
再審査用にデブがスローモーションで痩せていくアニメを作るため、後輩のpcを彼女が弄り回しているとき……ぼんやり画面を眺めながら、
「私、昔摂食障害だったんですよ。まさにこのビフォーアフターの84.7kgから34.1kgが『普通』のことだったんです」と後輩が言った。
彼女にはいつも行くバーがある。椅子もない小さなその店で毎日瓶ビールを立って飲み、ウイスキーを飲み、酩酊して眠る。
「おお、久しぶりじゃん」でっぷり肥った男が扉を開けた彼女に向かって声をかけた。客はその男しかまだいなかった。男は彼女と同い年で最近競合会社に就職したと他の常連から聞いていた。彼女は適当な愛想でそれに返し、手招きされたので男の隣で瓶ビールを頼んだ。そしていつものように手酌でガンガン飲んだ。
「お前のやってることはな、詐欺だよ、」男はすでに泥酔していた。いつもより早く瓶を飲み終わったので彼女はウイスキーを頼んだ。こんなもの相手にしたら負けだ。お前も所詮同じ穴のムジナなのだ、そんなことは、誰よりも一番自分がわかってるよ。彼女は言い返さずニヘラニヘラしながら黙々とウイスキーを飲んだ。
「あれはお前が全部やってるんだろ、今統括なんだろ、偉い立場だって聞いたよ、自分で知らないかもしれないけど有名なんだよお前、『凄腕』だって」彼女はニヘラニヘラしてまたウイスキーを飲んだ。いつものように他の常連と今日の天気の話や世間話をしない分ペースが早まりニヘラニヘラしているだけなのでいつも頼む杯数を軽く超えていた。視界が横にぐらついてきた。
「お前も自分が肥ったり痩せたり忙しかったのによくあんなことできるよな、極悪人だよお前は、生活のために魂売って、小説はどうしたんだよ? 芥川賞獲るんじゃなかったのか?」男は醜く笑った。それは本当に、本当に醜かった。トゥルルルンルン、トゥルルルンルン、と彼女のiphoneが鳴った、喚き散らす男の隣で彼女はニヘラニヘラして電話に出た。
「ウィース。もしもしぃ」
「先輩!」弛んでいた彼女の背筋がバシッと張った。後輩の声は聞いたことがないほど切迫し尖っていた。
「私あの睡眠薬やっちゃって、あの、あの、今病院にいて、もうほんとごめんなさい今日夜画面貼りつけなくてでも本当は電話しちゃいけないくてもう電話取り上げられるんですど管理画面iosのデブだけiosのデブだけ先輩あ」ツーツーツー……ツー……
ウイスキーのグラスに汗のような水滴がいくつもついていた。
後輩が退職してから最初はまだサラダチキンの汁だけは飲んでいた。でも徐々に飲めなくなった。でも飲めないまでもなぜか溜めることだけはしていた。でもペットボトルの蓋ギリギリまでそれが完全に溜められたとき、なぜこの汁を溜めているのかが本当にわからなくなってから……彼女はサラダチキンの汁すら拒絶し、より無味乾燥なビタミン入りのカロリーゼロゼリーしか食べなくなった。ゼリーをくわえながらエディタ上に向かい、また新たな菌を作りだしていた。そして管理画面の数字を追い続け黒にすることだけを考えないともう、もう……彼女は煙草を吸いに立ち上がった、すると気づいた。職場の女性全員が昼なのに誰一人外に食べにいかず、それどころかまともな食事、いわゆるパスタやオムライス、または女性誌が切実に『オススメ』しているようないわゆる「インスタ映え」をする食を摂っていないことを。彼女たちのデスクには彼女と同じく大量のモンスターゼロカロリーの潰された空き缶があるだけだった。
殴り書きのような雲が優しく浮いていた。喫煙所の真向かいにある中学校のコートではいくつもの灰色のズボン足がボール目掛けて走り回っていた。同僚の男がそれを見ながら呑気に言った。
「えらく縦に長いコートだなぁ……」
確かに、やけに縦に長いコートだった。それは間違いなかった。
「ほんとですね」彼女は男子生徒の無邪気な試合を見ながら言った。
「ほんとに、縦に長いですね」
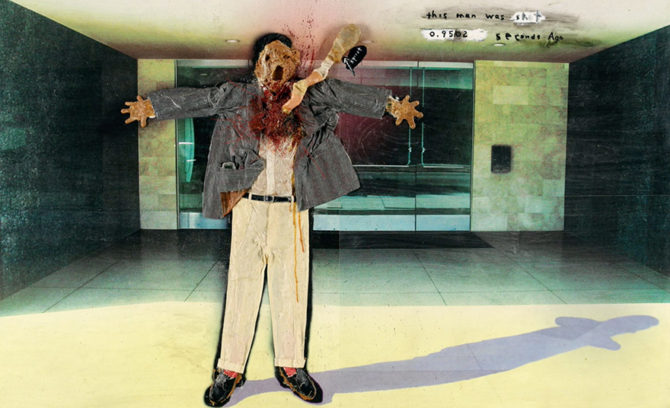






















長崎 朝 投稿者 | 2019-03-19 14:35
ばいん、バいんとエンジン音が聞こえてきそうな、馬力の高い作品だと思いました。独特の言語感覚と、パワーのある文章に襟首をひっつかまれ、「こっちだ、こっち」とぐいぐい連れていかれるような、言葉の持つ動力……。あるべきところに収まって死んでしまう言葉ではなく、裸形の、生のままの、グロテスクなまでの、未調理の言葉で書くということ、書かれ終わったものを読むというより、書いている行為そのものを読んでいるという感覚を味わうことができました。
駿瀬天馬 投稿者 | 2019-03-21 11:48
会話のHIPHOP感が読んでいて心地良かったです。
「ビーム出さないならデブシャツのボタン飛ばせそれかおもいっきしデブの肉揺らせ、速度鬼速めて」(YO!)
ラップバトルのように勢いがあって、且つしっかり感情が乗っていて不自然じゃない会話。勉強になりました。
(自分への、他人への)嘘と折り合いをつけることのできない怒りや苦しみを抱えつつ、でもどこかでもう諦めの境地にいるような主人公が救われてほしいなと思いながら読みました。救われてほしいなと思いつつ、救われないだろうなと思い、読んでいるこちらにも主人公の諦念が知らず浸食してきていたんだろうと思います。
健康的に焼けた脚を持つ後輩が辞めたのは、さすが健康的に焼けた脚を持っていた子なだけあるなぁ、と思いました。その辺の感慨をもう少し書いてほしかった気持ちと、でも書いてしまうと台無しになってしまうかもしれないなという気持ちが半々です。
春風亭どれみ 投稿者 | 2019-03-21 14:18
読んだ瞬間に、もしまだ未読でいらっしゃるなら、開高健の『太った』をすすめたくなりました。彼もまたサントリーのコピーライターで、自分のことを「文章を書く自動販売機」だと悩みながら、再び小説の世界にかえっていく人なので。無機質な3Dポリゴンに肉付けに勝手にストーリーを落とし込むのは、R25指定のお人形遊びなのかもしれません。
一希 零 投稿者 | 2019-03-22 17:01
最初に掲載されたバージョンを読んだときは、正直よくわからなかったのですが、少し書き直されたあとにもう一度読んで、内容がちゃんとわかりました。
この小説では、あるいは、まきのさんが何かしら職業を題材にされるときは、たとえそれを批判的に書きつつも、否定することはできない、あるいは、主人公自体がどっぷりとその内側に入り込んでしまって、それ自体に絶望を感じている、というような書かれ方をする気がして、僕はとても誠実な眼差しを感じます。単に否定するでもなく、かといって開き直るでもない、二項対立に回収されない感覚を描くところに文学を感じました。
桃春 投稿者 | 2019-03-23 02:57
スタッカート、変拍子を含む聞き慣れない忙しないテンポの音楽を聞いているように感じました。それゆえの臨場感はあるのですが、もう一工夫何かが欲しいなと思いました。
Blur Matsuo 編集者 | 2019-03-23 15:14
個人的に、牧野さんの作品で頻出するおバカで憎めない後輩キャラが大好きなのですが、この作品では彼女の闇が深くて主人公の苦悩がぼやけてしまったように感じました。字数が少ないので、もう少し長くなればいい塩梅になるのかもしれないとも思います。バいンやニヘラなど独特の擬音は好きでした。
Juan.B 編集者 | 2019-03-24 01:07
人のコンプレックスを操作することと自身の環境との生々しい相克を見せられた。しかし、この作品の登場人物は女や後輩、醜い男の数人だけではない。即ち、その広告やプロパガンダの対象となるであろう無数の人々も(我々かも知れぬ)、である。
この作品は恐らくレーニンの帝国主義論の応用である。帝国・資本主義は地球を分割し尽くし、瓦解して滅ぶ。広告はそのミクロでしかない。更に歯車と言うか輪転機(後輩)は常に取り換えられ、短いスパンで捨てられるノダ。エッヘン。
我々は広告を越えなければならぬ。それも、「我々は商業主義に毒されていル!」等と禁欲的に喚く様なバカではなく、広告やプロパガンダをむしろ食らい尽くしクチャクチャ咀嚼し俺達の体液で上書きする勢いでやらなければならぬ。「リベット打ちのロージー」(We can do itと腕を見せて軍需産業に貢いでるあのバカ女)のパクリみたいな広告、コカ・コーラのグチャグチャしたロゴフォント、フェラーリかポルシェの馬エンブレムの前で、退職届のコピーを紙飛行機にして遊ぶ!さらば資本主義!Arts and Crafts!
とここまで書いて俺も自分の行為が広告に操作されている気がしてきた……。
良い作品だった。後輩にはゆっくり休暇を取って欲しい。精神科医や生活保護の助けは全く恥ずかしいことではない。
退会したユーザー ゲスト | 2019-03-24 15:58
退会したユーザーのコメントは表示されません。
※管理者と投稿者には表示されます。
大猫 投稿者 | 2019-03-24 23:07
拝読しながら、牧野作品の登場人物は「水分」を貯めるのが好きなのかなと思いました。絞りカスのような水分を溜めること、「ダイエット」で騙される何千何万の浅ましい「デブ」、それを騙して金を巻き上げる自分の広告絵、他人を騙しながらも同じように極度に「デブ」を恐れていることにも自覚的で、どれも空しくてどれも醜い。
「ギョーカイ」に流されながらも流されることを潔しとしない主人公の最後の砦が「溜める水」なのでしょうか。ニヒラニヘラしながら酒をあおる彼女の心の一番脆いところはズタズタなのだろうなと想像しました。摂食障害の後輩も病み疲れて去って行き、周りの女たちは霞食ってる状態で、己のかけた呪いに自分でかかっている感が痛ましくも滑稽でもあります。よくここまで晒したな、あっぱれと言いたい。
諏訪靖彦 投稿者 | 2019-03-25 21:02
文章のテンポが良くて、躓くことなくスラッと読み進めていくことが出来ました。広告業の浅ましさと、仕事と小説の狭間で揺れる心理を感じる取ることが出来ました。
全然関係ないですが、タイトルを当初「ISOのデブ」と読み違えしまい「なんて破滅的なタイトルなんだ!」と思ったり思わなかったり。
Fujiki 投稿者 | 2019-03-26 01:27
この小説には登場人物こそ複数出てくるものの他者がいない。「自分が肥ったり痩せたり忙しかった」主人公自身の過去の姿の分身であるかのような後輩。主人公のことをなぜか知り尽くしていてまるで心の声のように彼女を責め立てる「肥った男」。サッカーのコートをめぐって、まるで『東京物語』の長年連れ添った夫婦のように主人公と反復的な会話をするだけの「同僚の男」。名前を与えられることもなく際限なく分裂していく自己の断片の数々に病的なおぞましさを感じた。だいぶ病んでるな……大丈夫か? ただ、なんでサラダチキンの汁(脂+ドレッシングってこと?)なんて気持ち悪い物をわざわざ飲むのかイマイチ理解できなかった私はおそらく本作のよい読者ではないのかもしれない。
波野發作 投稿者 | 2019-03-26 09:59
昨年糖尿病予備軍の宣告を受けてしばらくサラダチキンを常食するライフスタイルを送り少々減量できたのですが、NovelJamアフターの忙しさにかまけてストレスフルな日々を送ったところすっかりリバウンドしてしまい、減量開始を余裕で上回っております。本作を読んで、再度サラダチキンを食べねばならないと思いましたが、嫌だわ。