うちの近所には関東最大級だという縄文遺跡や縄文時代の遺構がぽつぽつ在るのです。そこから出た出土品を展示しているほか、遺跡そのものの上に竪穴式住居を建てて縄文時代の村を再現した埋蔵文化財センターも在ります。その再現された縄文の村には今は枯れていますが、たしか1970年代ぐらいまではまだ現役だったという湧き水もありました。
ここらへんは何の変哲もない郊外の住宅地ですが丘陵地で緑が多く、そのころの事を想像しやすいように思います(そのころと言っても何千年も前ですが)。かつて太古の人々が村を作って住んでいたところに今度は現代の人々のマンションや一戸建てが建ち並んでいると考えると少し変な気がしますが、実際にその関東最大級の縄文遺跡があったというところの半分は今大きなマンションが建っています。また縄文時代のストーンサークルもあります。それは当時の墓地で、ひざを折り曲げた形で埋葬された遺骨が出てきたそうです。
さて縄文時代の出土品といえばやはりあの縄文中期の、奇抜な造形で複雑な文様の施された土器でありまして、私も実はあれが大好きなのです。が、件の埋蔵文化財センターに足を運んでみても、どうもここいらではあまりめぼしいものは出土していないようなのです。そもそも展示スペースが広くないので収蔵品のごく一部を交代に展示しているのですが、特に感動を覚えるようなものを見た記憶がありません。けれどその中で個人的にお気に入りの土器がありました。それは造形はごく普通なのですが、奇妙なものがでかでかと描かれているのです。それは人間の形をしているようで少し違うようななにかが、「びよーん」という風に四肢を広げて跳びあがっているような、叫び声をあげているような姿でした。説明文によるとこれは何を表したものかはよくわからない、なにか精霊の姿かもしれない……というようなことでした。はじめてその土器を見たときはその呪術的な、けれどどこかユーモラスで超時代的なデザインがざっと五千年も前の人の手になるものであるというのがなんとも不思議に感じられました。これは一体なにを表現しているのか、こういうものを作ったり使ったりしていた人たちというのはどんなことを考えどんな神を信じていたのか? 自然と思考がそういう方向へ流れていきますが、同時にまたそこでストップします。なにせ五千年も昔のものとなっては考える手がかりすら無いからです。縄文時代の夜は暗かったんだろうな、――私はそんな間の抜けたことを思うだけでした。
けれど謎は解けました。それはどうやらカエルであったらしいのです。縄文土器の図録など何冊かぱらぱらめくってみますと、それは山梨県や長野県など関東の遺跡から出土した土器に多く見られるものらしく、さまざまなカエルの付いた土器の写真が載っていました。図録に収められるぐらいであれば逸品だからなのでしょうが、それらと比べるとわが「びよーん」の土器はあまり巧みなものではないのかもしれないと悲しくなりました。一目でカエルだとわからなかったのも作り手の拙さによるのではないか? いや、あれはあれで具象と抽象のはざまにあるより優れたデザインであるかもしれない。ともあれ何が描かれていたかはわかったにしろ、結局はわからないことの方が多いのでした。このカエルは何なのだろう、関東に住んでいた部族のトーテムででもあるのか? たぶん宗教的な意味が、いや宗教的なものでないとしても、きっとこのカエルにまつわる神話なり説話なりがあったはずなのだが……私は図録に収められた数々の土器の、偏執的と言っていいほど複雑な文様やとうてい実用的とは思えないグロテスクの域に入った造形に魅入られ見入りながらどこか歯がゆい気持ちでいました。
*
ところで私はわりと自信を持って言えますが、縄文土器が好きな人は九州装飾古墳も好きなのではないかと思います。
それぞれ全く別物でありながらこの二つには共通点がある――どちらも私達がぼんやり大雑把にイメージする「日本的な美意識」とは異質な強烈さを持っているのです。
もっとも、よく考えてみると縄文土器に関しては「日本的な美意識」から見て異質だったとしても何の不思議もないのです。いくら幾分かはその血を受け継いでいるとはいえ、渡来系が圧倒的なマジョリティである現代の日本人、というか大和民族、からすればあれらの土器を作った関東の縄文人というのは普通にほぼほぼ異民族でしょう。なので私達が異質なものを感じるのも当然と言えば当然です。では九州の装飾古墳はどうか。
装飾古墳それ自体は日本のあちこちにあり、関東にも多いらしいのですが、関東の古墳の壁画というのは実のところあまり関心を惹かれるものではありません。上記のようなワンダーを感じる装飾古墳は北九州に集中しています。古代の北九州は半島や大陸との交易がありました。なので、装飾古墳がどうにも日本的に思えなかった私は、これらは渡来人が描いたものなのではないかと思いました。実際、絵のモチーフに中国神話由来のものがあるというのもその考えを後押ししました。
ところがどうもそうではないらしい。もともと高句麗古墳の壁画を研究し、のちに装飾古墳の一つ一つに入って壁画を模写した日本画家の日下八光によれば、古墳内に壁画を描くという文化そのものは半島由来のものだと思うが、描いたのは日本人であろうという。なぜなら当時高句麗古墳にはすでにはるかに洗練された絵画が描かれていたからであり、渡来人が描いたのであればそのような絵画になっていたはずだからというのです。実際そういう洗練された絵画が高松塚古墳には描かれています。日下氏は日本にも古墳壁画があるという話を聞いて最初にそれら装飾古墳の絵を見たとき、そのあまりの幼稚さに幻滅したといいます。それらの絵は幼稚園児ぐらいの子供が描く絵と共通しているという指摘もあります。
とはいえ、二十世紀の美術を経た現代の目にはそれらの絵には新鮮な驚きがあります。個人的に好きなのは珍敷塚古墳、そして日下氏の手によって復元図として再現された田代太田古墳の絵ですが、特に前者からはなんとも不思議な印象を受けました。
それは何も知らずに最初に見ると、現代のあるいは近未来の港湾都市を描いたような絵に見えます。当時画材としては貴重だったという青の塗料で塗られた空を背景にビルが立ち並びその間になにかのランドマーク的な建造物がにょっきり立っている港に、舳先に鳥を乗せた舟が入っていくところを描いた絵に見えるのです。舟の上には太陽が照っている。それがなぜか嫌になるような「永遠」を感じさせるのです。
種明かしをするとビルのように見えるのは「靫」、弓矢を入れる武具で、奇妙な建造物に見えるのは蕨手文という名称を与えられた他の古墳とも共通した文様だとの事です。どちらも呪術的な意味で描かれているのだろうというのですが、やはり詳しいことはわからないらしい。けれどそう種明かしされた後も不思議な印象は変わりません。そして依然としてわからない事が多いのも変わりません。舟、舳先の鳥や右側に描かれたカエル(ここでもカエル!)などのモチーフから、船は死者の魂を乗せて「常世」の国へと向かっているのではというのですが、画題を説明した文献が残っているわけでもないので確かなことはわからないわけです。きっとこの絵にも今となっては知りようがない物語が付いていたはずなのですが。
*
もっとも文系人間である私が本当に興味があるのは、それらに付随していた物語がどんなものであったかというよりは、これらの表現が「文学」に翻訳されたとしたらそれはどんなものになるのだろうという事だったかもしれません。縄文中期の土器や九州装飾古墳のような強烈な印象を与え、従来の美意識と異なるような驚異を感じるようなもの、そんなものは日本の古典文学にあるだろうか? どうしてもそんな野暮なことを考えてしまいます。そもそも土器が大体5000年前のものとすると古墳の壁画はざっと1500年前、両者の間にはすでに3500年もの懸隔があり、壁画を描いた人にとっても関東の縄文人はすでに古代人だったわけで、同列に並べるのも変な話であるというのは承知の上でです。
とうぜん私の向かう先は『古事記』や『日本書紀』、『風土記』などになるわけですが、それらを紐解いてはみても私はどうも満たされないものを感じました。つまらないというのではなく、むしろ好きではあるのです。特に『日本書紀』は読みでがあって面白い。しかも、装飾古墳が描かれた同時代の伝承も記されている。が、そこに記された様々な伝承はすでにある洗練を経ており、例えていうなら弥生土器や高松塚古墳の絵のようにどこかつるっとしていて薄味なものという感じがするのです。
『延喜式』に収められた「出雲国造神賀詞」には、天孫降臨の前に偵察にでかけた天穂比命の言葉として
豊葦原の水穂の国は昼は五月蠅なす水沸き、夜は火瓮の如く光く神在り。石根・木立・青水沫も言問いて荒ぶる国なり
とあり、また『古今集』の序には
ちはやぶる神世には、歌の文字も定まらず、素直にして、事の心わきがたかりけらし
ともありますが、まさにそのちはやぶる神世の文学(文字も持ってない時代に文学なんぞ成立するのかという疑問はおいといて)は記されてないように思うのです。
ちなみに縄文土器も後期以降はずいぶん落ち着いたものになるし、装飾古墳も大陸色の濃い絵である竹原古墳のものあたりを最後に姿を消してしまうのですが、こういった美の伝統、と言ってよければ、それはどうしてここで途切れてしまったのか。こういった表現が主流になる歴史もありえたのか、それとも単にプリミティヴな段階のものとして乗り越えられていくものだったのか。
私はあきらめ悪くついには折口信夫の『死者の書』にも手を伸ばし、さらに藤井貞和の『古日本文学発生論』そしてそれを承けた谷川健一の『南島文学発生論』などに導かれ南島歌謡の世界まで覗いてみました。そして宮古島の古謡に触れたとき、私は折口信夫以来なぜ多くの人たちが、かなりの文化の違いにもかかわらず南西諸島に「古代日本」「原日本」を見たがるのかがわかるような気がしたのです。それは本土の大和人の勝手で気味の悪い思い入れに過ぎないにせよ、たしかに古墳時代、さらには弥生時代ぐらいの日本ではこんな歌が歌われこんな物語が伝えられていたのではないかという気がしてくるのです。成立年代としてははるかに新しい(「明治天皇」が歌われているものまであります)はずなのにです。また奄美諸島の説話のことなどもとても面白い。今ここで紹介する余裕は無いのですが、その世界は非常に興味深く幅広い。
しかし、私が自分の求めていた表現の片鱗らしきものを発見したのは、実は近代の作品においてでした。
*
たとえば次のような短歌をどう思われるでしょうか。
○あはれ見よ月光うつる山の雪は若き貴人の死蠟に似ずや
○黒板は赤き傷受け雲垂れてうすくらき日をすすり泣くなり
○西ぞらの黄金の一つ目うらめしくわれをながめてつとしずむなり
○巨いなる人のかばねを見んけはひ谷はまくろく刻まれにけり
○この坂は霧のなかよりおほいなる舌のごとくにあらはれにけり
○白きそらは一すじごとにわが髪を引くここちにてせまり来りぬ
○いざよひの月はつめたきくだものの匂をはなちあらはれにけり
連作としては、
○石投げなば雨ふるといううみの面はあまりに青くかなしかりけり
○泡つぶやく声こそかなしいざ逃げんみづうみの青の見るにたえねば
○うしろよりにらむものありうしろよりわれらをにらむ青きものあり
○星もなく赤き弦月ただひとり窓を落ち行くはただごとにあらず
○ちばしれるゆみはりの月わが窓にまよなかきたりて口をゆがむる
○月は夜の梢に落ちて見えざれどその悪相はなほわれにあり
○鳥さへもいまは啼かねばちばしれるかの一つ目はそらを去りしか
大量に引用してしまいましたが、これは宮澤賢治の少年時代の短歌です。歌人の佐藤通雅氏によると、これらの短歌は実は短歌としての体を成していないというのです。実際に岡井隆のように「ほとんどあきれはててしまったのを覚えている。(略)賢治が、こんなつまらない歌人だったとは!」という評価をする歌人もいます。どういう事かというと、短歌というものは「作者主体を主軸において、思いをのべることを基本とする形式」だからである。が、これらの短歌では主客転倒していて対象が主体として前面に押し出され、作者の心情すなわち一人称性が希薄であるからだと。佐藤氏はこれは彼の表現が三十一文字の短歌という定型に収まりきらないから起こる事態であり、実際に賢治はその後口語詩や童話に舞台を移したのだといいます。佐藤氏はこの特異性が生じる理由を、「賢治にあっては、一人称の像はかならずしも網膜に焦点を結ぶわけでなく、さらにかなたへとつきぬけてしまう」ことにあると考察します。
けれどそれはなんだかまだわかりにくい。佐藤氏はさらに佐々木幸綱を引用しながら考察を進め、賢治には〈見る〉ことによって対象を支配する発想が無いとし、「だから、彼の取り上げる山にも川にも木にも雲にも、〈われ〉から独立した魂が生じ、それ自体が自在に活動する」として最終的に「賢治のアニミズム」を指摘します。もっとも佐藤氏はこの言葉を使うのには慎重で、すぐ「いきなりその用語をもって解明しようとしては、飛躍がすぎる」と続けていますが。
佐藤氏がアニミズムという言葉を使うのに慎重になっているように見えるのは、それを言い出したら元も子も無いからというのがあるのかもしれません。よく日本文化の基層にあるのはアニミズムだとかいう話はあちこちで聞きますが、しかし正直なところ、私にはあまりピンと来なかったりします。それはたとえば私達の日常のなんでもないところで何の気なしにやっていることで、指摘されてみればまあアニミズム的感覚かなあというのがあるにはありますが、古典文学などにしても、能などには少しあるかもしれませんが、特にそこにアニミズムを感じたことがありません(もちろん何でもかんでも文学に反映するわけではないとは言えるでしょうが)。『古今集』『新古今集』には四季別に花鳥風月を詠んだ歌が大量に収められていますが、それらの自然はただ愛でる対象または心情を投影する対象ではないでしょうか。『万葉集』の国誉めの歌はアニミズムに由来しているのかもしれませんが、すでに形骸化したものを感じます。それらの中には私が賢治のまるでなってない短歌に感じた、自然なり事物なりそれ自体が意思をもって生きているかのような生々しい実感をもって、しかもしばしば得体の知れない異物として迫ってくるような表現というのは見当たらないように思います。明治の写生文にいたってはさらにアニミズムからは遠いでしょう。
そもそもこれは宮澤賢治自身の特異な感覚・センスにもとづく表現であって、アニミズムどうこうとは関係が無い可能性だってある。それに、これは次章で触れますが、私のこの探求はそもそもある危うさを孕んだものなのです。あまり深入りしない方がいいのかもしれない。私はそこでいったんあきらめ、不毛な探求を打ち切ってまた土器や古墳壁画の図録をぱらぱらめくるようになりました。けれどやがて土器と壁画に共通してみられる渦巻文とか蕨手文とかいう呼称を与えられている文様が、アイヌ文様と類似したものであるというのを知り、そこでふと本棚のどこかに岩波文庫の『アイヌ神謡集』があるのを思い出したのです。(つづく)
――――――――――――――――――――
主要引用・参考文献
『新版 縄文美術館』小川忠博他 平凡社 2018
『井戸尻の縄文土器8 総集編』 長野県富士見町教育委員会井戸尻考古館 2023
『装飾古墳』日下八光 朝日新聞社 1967
『装飾古墳の世界: 国立歴史民俗博物館開館10周年記念企画展示』 朝日新聞社 1993
『賢治短歌へ』佐藤通雅 洋々社 2007


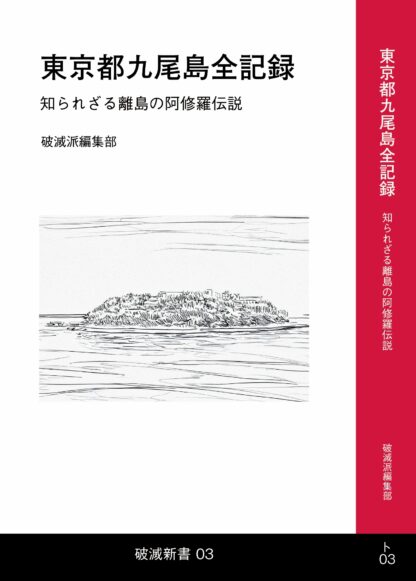








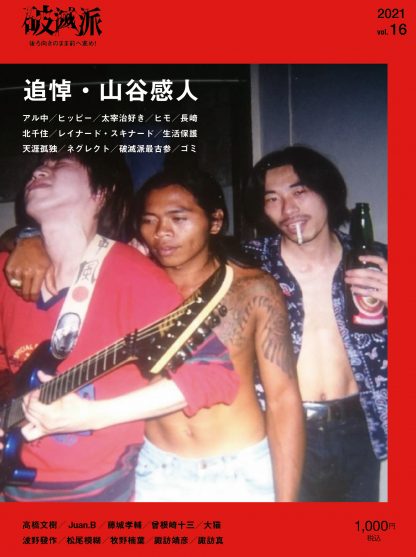












"1. カエルの土器、舟の壁画、それらに付随していたはずの物語について"へのコメント 0件