確か九月の初めくらいだったと思う。僕は去年中学校を卒業した後、それなりに頭の良い公立高校に通っていた。親に言われ、公立高校を選んだ。それしか無かった。
だがそこでの生活は悪い物では無い。皆親切だし、話も合う。充実はしていた。
そしてその頃は待ちに待った文化祭の準備で忙しく、帰ってきたのもそれなりに遅かった。でも特に不幸だとは思わない。
夕方、夕焼け色が空に塗られている。僕は電車から降りて、自転車を停めている駐輪場へと向かう。アディダスのリュックサックに荷物がいっぱい詰まっていて重い。まるでリュックサックに背負われている様だ。
イヤフォンで音楽を聴きながら、道を歩く。近くに線路が通っていて、僕の近くを普通電車がゆっくりと通過していく。それに合わせる様に秋の蝉が鳴く。
僕はふと前を見た。……何か、見覚えのある影が見える。
僕は少し走って、その後をつけた。そこには、高身長の青年と、その隣には僕と同じ位の背の青年。
高身長の青年。……間違いない。さっきまで僕は彼の存在を忘れていた。だが今この瞬間に思い出した。
僕と彼は親友だった。……ここでは彼を仮にKとしよう。
Kは低身長の僕が見上げなければ顔が見えない程背が高い男だった。僕とKは小学校からの友達で、帰りはよく共に帰っていた記憶がある。
Kは僕と同じ様な奴だった。本当に、身長以外はよく似ている男だと思う。小学校の時は毎日家に帰れば、携帯ゲームを持って行ってKの家に行くのが日課だった。
今でもKの家の匂いはよく覚えている。全体的に上等で……彼の家に入る度に、何となく小学生ながら格差という物を彼から学んでいた。
そうなると、やはり僕とKは違う人間だったのかもしれない。だがそれでも良かった。
Kは良い奴だったし……。何が何でも僕は彼と関係を持っていたかったのだ。それは当然の事だと思っている。
だが僕がKと話したのは夏休みに入る前が最後だ。しかも今彼は別の人と一緒に帰っている。今彼に気さくに「やあ」と話しかけられる様な状況では無い。
……今思えば、ここでさっさと話しかけて、無理矢理にでもKの友達とも話を合わせれば良かったと後悔している。
どうも僕の人生は、上手くいった事がある覚えが無い。そして今後も僕は人生で上手くいった、と思う事無く死んでいくのだろう。
僕はとにかく彼に気付かれない様に跡をつけた。
Kの少し茶色がかっていた髪は、汚い金色に染まっていた。髪が伸びて、肩までかかっている。僕がいつか見たあの優しげな後ろ姿は全く変わってしまっていた。
その揺れる髪の毛と、友達と楽しそうに、少し馬鹿げた笑い声を発する度に、僕は何となくKがあの時の純粋で知的なKでは無く、あの髪と同じように別の存在へと染まってしまったのだと察した。
それでも僕はKの内なる純粋さを信じた。もしかすると、彼はただただ鎧を身にまとっているだけで、それを取ってしまえば僕のよく知っているKになる。……そう信じた。
Kが先に駐輪場に入って、自転車を取りだした。僕も同じタイミングで駐輪場に入り、Kが先に行くのを待って、跡を付けた。
とにかく僕はKの鎧が外れる瞬間……。Kの友達と別れる瞬間を待つ事にした。そうすればKと自然に話せると思ったのだ。
Kは友達を横に並べ、自転車を押して歩き始める。僕はそれを十メートル程離れた地点からついて行く。これは何となく予想していた。Kの友達は自転車に乗っていなかったから。
やはりKは僕の事など眼中に無い様だ。余程その友達は良い仲間らしい。
でも別にそれでもいい。……ただ別れた後で僕に向かって手を振って、近付いてくれれば……。本当にそれだけで僕の心は満たされてしまうのだ。
しばらく道を進むと、Kは自転車の後ろに友達を載せ始めた。僕はその光景を見た時、何か言い様の無い衝撃を受けた。だがその衝撃は直ぐに失せてしまった。
自転車の二人乗り位、高校生なら誰でも一度はする事だ。そんなレベル。
なのに僕は何故こんなにも悲しいのだろう。何故こんなに失望の念に苛まれるのだろう。
……僕の中でKは、見た目は少し不真面目な感じをしているが、根は真面目で……それこそ犯罪行為の一つもしない様な奴だと思っていた。そんな彼が僕は好きだったし、誇りでもあった。真面目な友人。それだけで僕は満たされた。
だが今の彼は違う。
今の彼は、確かに偏差値の高い高校に通ってはいるが、ただの二人乗りをして、それなりの安っぽい青春を送る、安っぽい学生なのだ。
それを思うと、僕はどうしようもない現実に押しつぶされる感覚に陥るのだ。
僕の視線の先には、後ろの重さに翻弄され、蛇行運転をする彼の電動自転車が見える。夕焼けの光でそれは茜色に霞んで見えて、僕には到底輝いているとは思えなかった。
二人はどうやら登り坂を楽するために二人乗りをしていた様で、平坦になると友達は自転車を降りて、Kの横を走り始めた。
二人は信号を渡り、右側の歩道へと進み始める。もうこの際左側走行の理論はどうでもいい。ただ僕にはその光景が、まるで僕の薄汚れた重苦しい現実からKは離れ、素晴らしい友達とダイヤモンドの様に輝く人生を歩んでいく様に見えたのだ。
それを思うと、何故僕はこんなすぐ近くにKがいるのに馬鹿みたいに追跡なんかしたのだろう、僕なんかが何故こんなに勝ち組の様な人物と関係を持っていたのだろう、僕は何故この空間にいるのだろう。そう考えて止まらない。
そんな事をしている内にKと友達はどんどんとスピードを上げていく。やめてくれ。僕を置いていかないでくれ。
何故行くのだK。僕を置いていってしまうのかい、君は。
そう心の中で叫ぶ。
すると、Kと友達は右の歩道から脇の道へと逸れてしまった。
僕はその道を進み、遥か彼方へと消えていくKを観察した。……あの道は、僕は通った事が無い。あの道は僕には進めない。
……ついに僕はKに見捨てられた。
僕は自転車を走らせる。ただ走らせる。幸せな過去を消し去る様に。
僕は自転車のハンドルを手で何度も叩いた。自らのグツグツ煮えたぎって、だがその中身をぶちまけられない虚しさを消す様に何度も叩いた。だがそれは僕の中から消える事は無い。
僕の前には、原付で道を塞ぐ男が居た。僕はそれをジリジリジリ普段は使わない自転車のベルでそれをどける。何を、道を塞ぐ方が悪い。
僕の前には、逆走してくる親子連れの自転車二台が居た。僕はそれをジリジリジリ普段は使わない自転車のベルでそれをどける。何を、ちゃんと教育しない親が悪い。
僕はそうして帰り道を走った。僕の道に楯突く者を、あまりにも身勝手な意志で消し去っていった。
最後に僕に残ったのは、ただこの夏の終わりを告げるツクツクボウシの鳴き声のみであった。

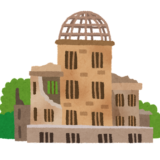





















"追跡"へのコメント 0件