ソクラテスよ。ムーシケーを創り、ムーシケーに励め。(『パイドン』(プラトン)60E)
ソクラテスは、どこまでも続くと思われる、長い柱廊を歩いていた。幅広く、天井の高い、柱廊だった。
この広大な柱廊が、東西南北、さらに天地に向かって、幾層にも連なっている。一体パルテノン神殿の、何十倍、何百倍の広さがあろうか。
余りに広大であったため、そこが夢の中だろうと薄々気付いていた。
「ここは一体、どこだろう?」――見慣れぬ景色だった。胸の高さ程の書棚が、何列も、大理石の床遥か彼方まで続いていた。
その全てに、巻物や冊子状の書物が、隙間なく詰まっていた。「自分は確か、監獄の硬い寝台に、足枷で繋がれて横になっていた筈だ。――明日、ワシは死ぬんだったな」
旧友のクリトンが、昨夕、デロス島へ遣わされていた祭典使節団の船が遂にペイライエウス(後の、ピレウス)に帰港したと、知らせてくれたのだ。これで、彼の死刑執行は、明日の夕刻と決した。
西暦紀元前399年、齢70のソクラテスは、アテナイの宗教裁判所に告発され、有罪の判決を受けた。量刑は、死刑と決まった。――彼の宿敵等による、謀略だった。デマゴーグ等に焚き付けられた衆愚が、裁判員として彼の運命を決した。“国法”の定めるところに、彼は黙々と従った。
クリトンに伴われて、愛妻のクサンティッペと、まだ赤ん坊の息子メネクセノスが、監獄のくぐり戸を抜け入ってきた。獄舎に繋がれて以来、30日ぶりの対面となった。
孫娘程も歳の離れたクサンティッペが、ソクラテスは可愛くて仕方が無い。時々彼に甘えるようなヒスを起こすが、遥か年上の包容力のある夫として、全てを包み込んでやる。彼女もまた、そんな夫に頼り切っている。――こうした二人の生活も、早20年の歳月を数え、三人の子供も儲けた。しかし今晩が、今生の別れとなる。
クサンティッペとクリトンは、手作りの料理やらワインやらを差し入れに持ってきていた。最後の晩餐を広げ、久し振りの豪勢な料理に舌鼓を打つ。妻の手作りの、魚や野菜や果物の料理。クリトンが奮発したらしい、極上のワイン。しばらく談笑した後、クリトンは帰っていった。家族水入らずで、一晩を過ごせと言い残して。死刑囚の最後の一晩は、大目に見る風習がアテナイにはある。
夜が更けてゆく。赤ん坊はしばしばぐずんで泣き出すが、その都度クサンティッペがあやし眠りに戻す。小さな灯し火のもと、夜の更けゆくに任せ、思い出話を語り尽くした。
手の中の巻かれたパピルス片に、ソクラテスは気付いた。
広げて、読んでみる。
『ソクラテスよ。ムーシケーを創り、ムーシケーに励め』
また、これか。――いささか呆れた。――明朝目覚めて、その後半日程で死ぬ身に、一体今さら何を期待しているというのだろう。
ソクラテスは、子供の頃からしばしば、夢や白日夢の中で、神託やダイモンの合図を受け取る事があった。それらはその時々、様々な内容だったが、この『ムーシケーを創り、ムーシケーに励め』というお告げだけは、若い頃から生涯を通して、その現われ方の手を変え品を変え、飽かず何度も繰り返されたのだった。――いつもは声として聞こえてくるのだが、今日はとうとう文書で言付けられた。
30日間の刑の執行猶予というのも、思えば不思議な巡り合わせだった。本来ならアテナイの刑の執行は、判決の翌日には行われてしまうのだ。――それが、アポロン神のどういう配慮か、彼の裁判の前日からデロス島のアポロン神詣での祭典が始まったのだった。この祭典はアテナイの英雄テセウスのミノタウロス退治を祝ったもので、毎年デロス島のアポロン神殿に供物を奉げる使節団の聖船が派遣されるが、祭の期間中、聖船がアテナイの外港ペイライエウスに帰還するまで、一切の血の穢れが禁止され、死刑の執行も延期される。――デルフォイの神託を受けて以来、ソクラテスは自分をアポロンの神託の使徒と思い定めてきたが、今まさにそのアポロン神により、寿命が引き伸ばされ、夜毎の神託の督促が自分を急かすのだった。
ムーシケーを創り、ムーシケーに励め。――ムーシケーとは、9柱のムーサの女神が司る、文学、音楽、舞踊、哲学、天文など、学芸全般を意味する。――自分は、長いこと、自らの哲学の営為を肯定し、激励する意味で、この神託が発せられているものと思い込んでいた。だが、死罪が決まった後も、無理矢理刑の執行を伸ばしてまで、相変わらずこの督促は続いていた。そこで、不安になった。――ムーシケーとは、自分のやってきた哲学活動とは別の、もっと直截にムーシケーと思われるもの、例えば詩作とか音楽とか、そうしたものを指すのではないのか? アポロンは、ずっとそうしたものの実行を命令し続けていたのではないか?
不安になった彼は、試しに詩を作ってみた。アポロン賛歌とか、アイソーポス(イソップ)の話に想を得た物語詩とか。それを、牢獄を訪ねてきた友人達に、披露した。
案の定、不評だった。――やるんじゃなかった!――ヘボい詩であり、物語だった。自分に詩才などカケラも無いことは、最初から分かっていた。彼は恥じ入り、後悔した。
パピルスの文言に、続きがあることに気付いた。
『ムーシケーが仕上がるまで、死ぬことまかりならぬ』
自分が余りに鈍いものだから、業をにやしたアポロンが、遂に強硬手段に打って出たのだろうか。――死の前夜の夢にまで神託を注ぎ込み、強引に事の決行を促し、死を差し止めるとまで言う。
今見ているこの夢の風景も、アポロンの神慮というべきものなのか? 今回の実力行使の有様からすると、この膨大な山野の草木の如き量の書物で埋め尽くされた空間、建物が、ワシが創り励むべきムーシケーと深く関わりがあるという事なのだろうか? この、パルテノンの何十倍、何百倍という広さに書物を一杯に詰め込んだ空間は、一体何なんだ?
「カリマコス殿」
彼を呼び止める声がした。
振り返ると、図書館長のアポロニウスだった。そのにやけた顔を見た途端、ソクラテスは思い出した。――自分は、今、ここで、このアレクサンドリアの学究の殿堂ムセイオンの付属大図書館の、主任司書カリマコスであったと。
これが、オルフェウス教やピタゴラス派の言う、輪廻転生というやつなのだろうか。死に際して、アポロンの神慮が、ソクラテスに来世の姿を夢見させているのだろうか。――ソクラテスに、戸惑いはなかった。夢の中の出来事だからだろう。ソクラテス、カリマコスの二人の人生を生きることに、何の矛盾も感じなかった。――ここでワシは、毎日毎日、膨大な量の書物を相手に、日々を送っているのだったな。
ムセイオン。ムーサ女神の神殿。ここで行われている学術研究こそは、文字通りのムーシケーである。では、来世のワシは、日々ムーシケーを創り、ムーシケーに励んでいるのか? アポロンの謎掛けは、これで解けたのか?
「目録作成の進捗状況は、いかがですかな? カリマコス殿」アポロニウスが、例の上っ調子のキーで続ける。
この、御機嫌取りが! カリマコスは苦々しく思う。どういう塩梅か、この上っ調子のゴマすり台詞と、プトレマイオス二世フィラデルフォスの耳との相性が、抜群に良いようなのだ。王の寵愛により、この無能なヘボ詩人が、第二代図書館長に任命されたのだった。
ロドス出身にもかかわらず、アポロニウスはアゴ髭を、イタリア半島のエトルリア人風に先を尖らせ、それをしばしばこれ見よがしに手慰んだ。対して北アフリカはキュレネ生まれのカリマコスは、モジャッとした巻き髭が顔の輪郭を覆い、仕事に窮するたびその中に指を突っ込み引っ張るのだった。
「順調に進んでおりますよ。図書館長殿。少しの障りもなく、捗っております。
ですが、王の御命令で、何しろナイルの洪水の如く、日々蔵書数が溢れ続けております。何時になったら、目録完成の日を迎えられますことやら」
プトレマイオス王家の書物漁りの様は、狂気の沙汰としか思えない。何しろ、市場に出た本は悉く買い漁る。アレクサンドリア港に出入りする船に積まれた書籍は、全てこれのコピーを取る(そしてしばしば、コピーの方を返却し、原本を手許に残す)。遂には、使者の到達出来る限りの国に使いを送り、あらゆる書物を送り届けて欲しいと乞う。遠くインド、セレス(中国)からも、ウチワヤシの葉や竹簡に書かれた、読むことも出来ぬ文字・言語の書物が大量に届いた。
アポロニウスは、「御精進あれ」と一言だけ言い残すと、カラカラと耳障りな笑い声を立てながら、カリマコスを抜き去り遥か前方の列柱の彼方へと消えていった。
図書館長の背中を無為に見送りながら、カリマコスは思った。――今の自分は、毎日書物を収集し続け、それらに次々目を通し、目録化することに、日々追われ、汲々としている。深く読み込み、考えに浸る事は一切せず、ただ要約し、分類するだけの、マシーン。――まるで、前世のソクラテスとは、正反対の生き方だな。――これが本当に、神意に適う“ムーシケー”、なのだろうか?
神殿の主、ムーサの女神達は、貪欲に書物を、己が肉体を、供物を求める。司書と呼ばれる自分達は、これら女神に仕える神官である。供物を世界中から掻き集め、女神達に奉げた。蔵書数は、はや百万巻に達しようとしていた。カオスが世界を産み落としたように、やみくもに集められた書物が、ムーシケーを産み落とすなどといった奇跡が、本当に起こり得るのだろうか。
そんなカオスの中で、カリマコスはカオスに最初の秩序を与える目録作りという作業に、既に延々何十年も没頭していた。『ピナケス』と呼ばれた目録は、既に百巻を越えていた。それらは、世界を写す書物を、その世界の秩序に合わせカテゴリー分けし、アルファベット順に並べ、適切な『摘要』を附してあった。――こうした膨大な作業の記憶に、ソクラテスは、アポロン神の陽光の許での大いなるめまいの如きものを覚えた。
ソクラテスは、アテナイでの書物を巡る熱狂を、思い返していた。
そもそもヘラス(ギリシャ)で文字が発明され、使われ出したのは、彼の時代のほんの2、3百年前からだった。(遥か以前、クレタやミケーネで“線文字”とも呼べる特殊な文字が使われていたが、とうに忘れ去られていた。)言い伝えでは、フェニキア人カドモスにより、文字はもたらされたという。そのためヘレネス(ギリシャ人)は、自分達が使っているアルファベットを、身も蓋もなく“フェニキア文字”と呼んでいた。母音を持たないフェニキア人の文字に触発されて、ギリシャ語を書き留めるためのものとして、考案されたのだった。
経済活動や公文書のために用いられたのは勿論だが、すぐに、ホメロスを始めとした叙事詩、叙情詩、悲劇、喜劇、神話、歴史、地理、哲学、医学、身辺雑記等々、といったものを盛った“書物”が登場した。――ソクラテスが中年になる頃には、既にアテナイ市内に相当数の“本屋”なる新しい商いが成立していた。彼等は、あるいはアゴラ(広場)に仮設のスタンドを出し、あるいはアクロポリスの麓の一画にまとまって出店し、新し物好きの客達を呼び寄せていた。新たに誕生した“読者”なる人種は、本屋の店頭にたむろし、物珍しい書物を見付けては果てしないお喋りに打ち興じ、倦む事を知らなかった。新刊本が発売されるとの予告が広まれば、目新しいものにすぐ飛び付く若い連中が、それを何としても手に入れようと、徹夜で行列を造り、野宿し、同好の志同士でバカ騒ぎして夜を明かし、その発売を今や遅しと待つのだった。書物を携行し、見せびらかしつつ歩くのが流行った。アゴラで、劇場で、ギュムナシオン(体育場)で、若者は一人が一巻、必ずといっていいほど本を持ち歩いた。遠出の旅先にすら、本は供をした。一種の流行、ファッションだった。高価なパピルスが大量に輸入された。一巻一ドラクマ以上する高価な書物が、飛ぶように売れた。一ドラクマは、庶民の2、3日分の収入に相当する。
ヘラスの当代の文化人達も、二派に割れた。文字という未知のものの可能性を賛美し、新規なものの取り込みに積極的な、――つまりはお調子者の、若者に媚を売る進歩的知識人。対して、口承や弁論や記憶や思索の伝統を重視し、新しく奇異なものの流行りを苦々しく思う守旧派の知識人。悲劇作家アイスキュロスは前者で、その作品『縛られたプロメテウス』中でも文字の発明を称賛した。ソクラテスは後者に属し、若い者、お調子者らが、深く考えもせず、それの危険も考慮せず、すぐに飛び付く様を、吊るされた餌に考えも無く食い付くマヌケな魚にたとえ、揶揄した。
たかだか2、30の記号で成り立つギリシャ・アルファベットは、はなはだ簡便で、その識字率はきわめて高かった。そのため、“読者層”と名付けられた新人類は、わずか2、3百年の内に、庶民の間にまで急速に拡大していった。
粗末なソクラテス宅で、仲間や弟子達を集め、シュンポシオン(飲み会)を開いた事があった。その時話題となったのが、これ、――文字と書物について、――だった。
ソクラテス家は建物はボロいが、敷地は結構広い。父親以来の石工をなりわいとし、中庭を工房兼用としているので、中空部分のスペースがそれなりにあるのだ。その中庭兼工房には、造りかけの石像がゴロゴロ転がっていた。
何しろあるじが、ほとんど働かず出歩いてばかりいる。日々アゴラやギュムナシオンで、誰彼構わず迷惑な討論を一方的に吹っ掛け、金にもならないパフォーマンスに明け暮れ、美少年の尻を追い掛け回して、油を売ることに忙しい。生業の石工はほとんどほっぽらかしなので、注文も途絶え、当然の帰結として、赤貧洗うが如き貧乏所帯だった。
そこへ何十人もの客を集めて、飲み会をやろうというのだから、妻のクサンティッペが怒りをぶつけてくるのも無理はない。一体料理の食材はどうするの。酒はどうするの。そんなもん、我が家には無いし、買出しに行こうにも先立つものがまるで無い。ソクラテスはその苦情を聞いて、優しくなだめた。「なあに、我が愛する妻よ。良くお聞き。――立派なものなど、出す必要はまるでないのだ。――もし我が真の友なら、どんな粗末なものを出されても、まるで意に介さないだろう。またもしそれで不満を言うようなら、そんな奴は友の資格は無い。――だからいずれにせよ、お前が気に病む事はまるでないのだ」――そんな慰めで彼の妻が納得したかどうかははなはだ疑問だが、その時も近所に住む金満家のクリトンが大量の飲食を差し入れてくれ、ソクラテスは大いに助かった。
クリネー(寝椅子)から優雅に手を延ばし、干しイチジクを摘み上げながら、エウテュデーモス青年が自説を披露した。彼はソクラテスの弟子中でも、その蔵書数は最右翼と自負していた。「また新しい書物を入手出来ました。このところ力を入れている、自然哲学系の新理論の本です。――イオニア諸学の流れを汲むもので、この考えを導入することで、今まで整合性に欠けていた各派の理論を一つにまとめる事が出来るのではないかと、大いに期待している次第です」
「それはよかった。吉報だ」ソクラテスはすかさず賛同した。「自然哲学の考えというのは、思い付くまま並べられたようなものが多くて、互いがどう関連しているのか、さっぱり見当付かない。――ワシも若い頃は、大いに自然哲学を学んだものだが、どうにも消化不良でとうとう撤退してしまったのだよ。――その、一つにまとめる新理論という奴を、是非とも御教授願えないかね」
エウテュデーモスは、師のソクラテスを前に、得意気だった。「アナクサゴラスの『ヌース(知性)』の理論と、ピタゴラス派の『数』の理論を合体させるのです。知性により理解される数の法則が、自然界も支配しているという考え方です。…………」
彼の話の内容に、周囲の参会者から次々質問や反論が飛び出した。テバイのケベスは、君のピタゴラス解釈はまるでピント外れだと攻撃した。アリストン三兄弟の次兄グラウコンは、自然哲学に一家言あり、微に入り細に入りエウテュデーモスを質問攻めにした。あまりに錯綜する激論の荒波に、エウテュデーモスはとうとう音を上げ、ソクラテスに助け舟を求めた。
「そうだな」ソクラテスはその特徴ある獅子鼻の下に愛嬌のあるシワを寄せ、弟子を優しく見詰めた。「書物での独学というのは、どうしても生硬なものとなる。――その本の著者は、まだ存命なのかね?」
「いいえ。故人です」
「そうか。それは残念だ。――この世にいないとなれば、なおさら思想は硬直化したものにならざるを得ない。――本にいくら呼び掛けたって、書いた本人のようには答えてくれないからね」
「ですが、既に亡くなった方の考えを知るには、――書物に頼るしかないかと、…………」
「それは、勿論だ。ワシも若い頃、いにしえの賢者達の書物を、よく研究したものだよ。――だが、そこまでなのだ。書物というのは、限界があるのだ。いかに多く集めようと、……」
「多くを書物から学ぶことは、無駄だと仰るのですか?」
「いや、そうじゃない。さっきも言った通り、ワシも若い頃、多くを書物から学んだ。そうした経験は充分に積んだ。――それは、釈迦に説法というものだよ」
「釈迦? どなたです、それは、……」
おっと、いかん。――これは、カリマコスの記憶だった。――インドの哲学者釈迦は、ソクラテスと生没年もほぼ同じ、全く同時代を生きた人のようだった。インドから届けられた経典にその記録があり、カリマコスが目録に分類したのだ。
「自然哲学は、自然を相手にした学問だ。――ならば、本ではなく、自然に尋ねた方が正解が返ってくるとは思わないかね」ソクラテスは、あわてて話を逸らした。「本に浸り、人の考えを自分の考えと思い込むと、それに囚われて抜け出せなくなる。多くの本を読み多くの人の考えを吸収したつもりになるが、その分ますます自分の考えはその後ろに後退し消え入ってしまう。本に頼って、記憶しようとしないから、記憶力が衰え、本から離れた時記憶はあいまいなものとなる。あいまいな記憶を材料に、消え入りそうな思考力でいくらあがいても、深く思考する事は出来ない。惨めな結果に終わるだけだよ。――ワシがしばしば文字や書物に頼ることに警鐘を鳴らすのは、そうした意味でだ。書物という補助具を使うことで、知性を鍛える事が疎かになり、知性の筋力を衰弱させてしまうのだ」
これが、知性についての、ヘラス伝統の考え方だった。文字や書物が侵攻を開始する以前の。つまり知性を、とことん使い倒すべき手段ではなく、全裸でフェアに鍛えられ、競われるべき筋肉の如き能力であると、考えていたようだ。――痩せたヘラスの土地で、広く浅く撒かれた土壌は何の収穫ももたらさない。たとえ狭くても、深く耕さなければ。――そんなワシが、こともあろうに書物の神を祭る神殿の神官に生まれ変わろうとは! 何という、皮肉だろう。――しかも、書物集めに振り回されているエウテュデーモスの生き方を、究極まで突き詰めたような人生である。
「ですが、自然に尋ねろと仰られても、――自然が返答してくれるとは、とても思えません」エウテュデーモスは今度は、シモンの方に視線を向けて、助けを求めた。
「ん?」無口なシモンは、この日初めて口を利いた。「記憶しろと言われても、オレは記憶力がからきし弱いからな。――まだ、自然に口を利かす方が、簡単だ」そう言うとシモンは、いつも持っている皮製のメモ帳をパラパラとめくってみせた。
靴屋のシモン。石工のソクラテスとは、気心の知れた職人仲間である。アゴラの端に、自宅兼工房を持っていて、靴屋を開いている。靴の他にも、馬具など革製品全般を扱う。アゴラに入るには年齢制限があり、その歳に達しないソクラテスの弟子達は、シモンの店にたむろする事が多かった。そのため、この靴屋が、ソクラテス派の自他共に認める“溜まり場”となっていた。ソクラテスは、この店を基地として、アゴラに出撃する訳である。――シモンはさっきから、ワインを水で割らず、生一本のまま飲むというスキタイ風の野蛮な飲み方をしていた。こうしないと、ちっとも酔いが回らないという。
「シモンさん。どうやって口を利かせるんです?」アリスティッポスが面白がって訊いた。
しばらくワインの器を口から離さなかったシモンは、長い時間をかけて器を卓に戻し、「そうさな。例えば、……」と宙を見上げながら言葉を選んだ。「この革ならば、まずは毒液に漬ける」と、いつもメモ帳や葦ペン、インク壺などをまとめて入れている、蓋付きの小さな革袋を指差した。「こっちならば」と、今度は皮製の紙を一枚摘んで引っ張り、「八方を縛り上げて張り付けにし、引っ張れるだけギュウギュウに引っ張り延ばすのさ。そして、表面を刃物で白くなるまでとことん削り上げる。――他にも、熱にさらす、ぶっ叩く、細かく切り刻む、――と、口を利かす方法はいろいろあるな」
「自然もそこまで責められれば、口を利かずにはおられまい」ソクラテスは、呆れたという風に肩をすくめながら、古い友に賛意を送った。「それにしても獣の皮のパピルスとは、随分古風なものを使っているな。ホメロスの時代には、そんなものもあったと聞くが」
「なあに、廃物利用だよ」さらに器に一杯あおって、シモンは答えた。「舶来のパピルスは、とにかく高いからな。こいつらは、余った皮の切れハシさ。そいつを有効利用しているんだ。作るのに手間が掛かるというんで廃れたらしいが、ウチは皮屋だ、作業の片手間についでに出来る」そうして作った獣皮紙を、四角く同じ大きさに裁断し、散乱しないよう革紐で括ってメモ用紙としていた。巻物しか見たことのないソクラテス派の面々には、一辺を綴じられた獣皮紙の束というのが、何とも珍しく思えた。シモンはそれと、葦ペンと、ニカワと墨を練ったインクを入れた壺とを、蓋付きの革袋に入れ、絶えず肩からぶら下げて持ち歩いていた。「オレは、物覚えが悪いからな」恥ずかしそうに小声で、また繰り返した。「こいつを何時でもサッと取り出して、何でもすぐさま書き付けとかないと、――アッという間に物忘れのヘビに噛み付かれちまうんだ」ヘビはしばしば、その脱皮が忘却と想起に譬えられた。――記憶力を知性の筆頭に上げる古代ギリシャでそう告白することは、自らの愚かさを認めること、つまりは敗北宣言に等しかった。
「しかしお陰で、『靴屋風』が読めるんじゃありませんか」アリスティッポスがすかさずシモンを持ち上げた。「あれは、面白いですよ。――今度自分も、あれを真似して何か書いてみようかな」
『靴屋風』とは、ソクラテスを主人公にした一連の対話劇である。といって“元ネタ”は、シモンの溜め込んだ大量のメモであり、それがそのまま使われているので、創作劇というよりはドキュメンタリーに近い。
アテナイきってのお騒がせ男、道化で知恵者の放蕩老人ソクラテスが、話題に上らない日はなかった。アゴラで道を急ぐ良識ある紳士諸兄に遠慮なく騒々しい議論を吹っ掛け、怒った相手に殴られ蹴られ、残り少ない髪をつかまれ引き摺り回される。ギュムナシオンで全裸の美少年達をしつこく口説き、ハエかアブの如く嫌われシッシッと追い立てられる。飛び切りの皮肉屋で、空っとぼけた不良ソフィストは、喜劇作家達に引っ張りだこで、彼を主人公にしたアリストファネスの『雲』がディオニュソス劇場で初演された時には、彼はそのクライマックスで仁王立ちに立ち上がり、全観客に向かって本物のソクラテスここにありと、大見得を切ってみせた。そんな“出し物”にされる事を、嫌悪したり困惑したりする風はまるでなく、むしろ噂になる事を楽しんでいるようで、“喜劇作家には、こちらから進んで話題にしてもらうべき”とまで公言していた。
そんな彼だから、長年の友人が包み隠さず公開した自分の言行録を、何ともこそばゆく、まるでいにしえの賢人に席を連ねたような居心地の悪さで、はにかみながら傍観していた。そこにはソクラテスの日々動き回る様が、事細かに、小気味よく活写されていた。シモンのメモをまとめたものがアテナイの巷に出回るや、その一語一句たがわぬ正確さに、さすがシモンと世評は高かったが、その正確さという文字のもたらす威力に、ソクラテスは嬉しく思いつつも何か空恐ろしいものを感じ取ってもいた。
『靴屋風』を巡って、シュンポシオンは盛り上がった。
『正義について』と題された『靴屋風』は、まるでヤクザ物の“出入り”を描いたルポルタージュさながらだった。
ある朝、ソクラテス派の面々がペリパトス(遊歩道)をそぞろ歩いていた時、向こうからやってくるソフィスト・ヒッピアスと、その取り巻きの一団とに、バッタリ鉢合わせしてしまった。たちまち、舌戦による乱闘となった。
“正義”について、大先生にぜひとも教えを乞いたいと、ソクラテスが戦いの狼煙を上げる。ヘラス中にその名を知られた万学の雄ヒッピアスは、ここで退くわけにはゆかぬ、その一騎打ちを受けて立つ。口汚く言い争っていた両軍が、一転沈黙のギャラリーと化す。
ソクラテスの“無限否定”のエンジンが、勢いを付け回転を始めた。ブラックホールの如く何物も生み出さないその無限の谷底に相手を引き擦り込もうとする。引き擦り込めれば、彼のフォール勝ちだ。――しかし一方大学者ヒッピアスも、そんなソクラテスの手口は既に百も承知である。ソクラテスの仕掛けてくる言語学上の定義の罠や論理学上のパラドックスの罠を、手練れの曲芸師よろしくギリギリで巧みに回避し、ブラックホールを周回しながら決して高度を下げない天体の如く、相手のパンチをことごとくかわし続ける。
不細工な、平べったいエイのような顔をした珍奇な老人が、立派な身なりのソフィストの大先生に挑みかかっている様が、何ともアンバランスで滑稽で、付近のストアやアゴラに暇潰しに来ている市民が周囲に段々群れ、“オレは醜男だけどこんなにスゴイんだ”と盛んにアピールしている方を判官びいきで応援しだし、それがまたソクラテス一党の若者達にはシビれてたまらない。
だがとうとう、こうした論争が午前中一杯も続き、マッチョな重装歩兵上がりのソクラテスの“無限エンジン”の前についに体力負けしたヒッピアスが、即答に窮する難問に乗り上げたところで休戦を申し出、後日ヒッピアスが再度アテナイを訪れた折の再戦を約束して、分水嶺で両麓に水が別れるが如くその日は両陣営とも互いに速やかに引き上げた。
悦楽の都アテナイに出稼ぎに来るソフィスト達は、ソクラテスがニコニコしながら愛想よく、かつ親しげに近付いてくるのを見ると、また来たかと身構え、渋い顔をする。またあの厄介ジジイの相手をして、時間を無駄にしなければならんのか、一銭の足しにもならないのに、と逃げ腰になる。――知者と評判の者達の権威をズタボロにする、知者の上をいく道化。若者達にとって、実に小気味のいい、付いて行きたくなるカリスマだった。
こうして『靴屋風』の記録は、ポリスの城壁の内外で、アゴラのきっぷのいい魚屋の店先で、裁判所のいかめしい門前で、どこでだろうと構わず、相手が誰だろうと構わず、挑発し、騒動を起こす、迷惑千万な、しかし一見愛嬌のある、すこぶる物騒な知的テロリストと、それを取り巻く享楽的で破壊的な若者達の生き様を、余すところなく描写し尽くしていた。そしてソクラテス一派の若いインテリ不良達は、師匠ソクラテスの真似をし、街行く紳士諸兄にイチャモンをつけ、大人を嘲笑い蔑んでは、溜飲を下げ、街の人々の怒りを買っていた。――だが、当時のアテナイには、まだそうした迷惑行為を許容するだけの“ゆとり”があった。
*
前405年、スパルタの常勝将軍リュサンドロスの奇襲攻撃を受け、アテナイ海軍は全滅した。(その少し前、戦場となったアイゴスポタモイの地に、不吉な空の石が降ってきたという。かのアナクサゴラスの説いた、天の物体である。)ペイライエウス港をリュサンドロス艦隊に、市壁周囲をスパルタ王パウサニアス率いる軍団に、それぞれ包囲封鎖されたアテナイは、飢餓に苦しみ抜いた末、翌年降伏した。後の世に言うペロポネソス大戦は、ここに終結した。
既に、アテナイ市とペイライエウス港を結ぶ“長城”の取り壊しが、始まっていた。それは、スパルタがアテナイに課した、多くの降伏条件の内の一つだった。ソクラテスはその有様を、自宅から市内に向かう途中、目撃した。占領軍の司令部から、不意の予期せぬ呼び出しを受けたのだ。
笛吹き女達の笛の伴奏に合わせ、男達が見上げるような壁の撤去作業を続けていた。女達は、リュサンドロスの艦隊からも、アテナイ市内からも、掻き集められた。ペロポネソス同盟の女達の吹く音色は軽快で、リュサンドロス麾下の者達はそのリズムに合わせ、陽気に石と土くれを取り除いていった。アテナイの女達の吹く音色は哀しげで、敗戦下の市民達は、その笛の音が彼等を鼓舞することもなく、悲愴な面持ちで、戸惑い戸惑い、しばしば作業の手も止まりがちだった。
占領軍は、アクロポリスの上に陣を敷いていた。元々山城だったアクロポリスは、攻めるに難く守るに易い。叛徒の奇襲に備え、占領統治するには最適の場所だった。
周囲を絶壁に取り巻かれ、たった一箇所しか登り口のない西側丘陵の坂道を、ソクラテスは登っていった。既にその坂道の途中から、道の左右にスパルタ兵が警備に就いている。兵士に呼び止められるたび、呼び出し状を見せ、ソクラテスは気の進まない重い歩みを進めた。
アクロポリスの入り口、プロピュライオンの城門に入ると、かつてソクラテス自身が刻み奉納したヘルメス像と女神カリス達の像が、製作者を出迎えた。スパルタ兵の数が一気に増した。忙しそうに駆け回り、作業し、号令し合っている。中央の広場から奥の広場にかけて、幕舎が幾つも連なっている。かつて聖域の全てを破壊したペルシア人と違って、信心深いラケダイモン人(広義のスパルタ人。スパルタ人は、自らをこう呼ぶ)は、さすがに神域内を荒らすような事はしない。最大の敬意を払っているようだった。
司令部はどこかと兵士の一人に尋ねると、奥の広場を指差した。登り口と正反対の真東、アクロポリス最奥の、パルテノン神殿正面に丁度相対する位置に、司令部の幕舎は陣取っていた。この辺りは、かつての山城の面影を残すペラスゴスの城壁が周囲を取り巻くように屹立し、崖下にはディオニュソス劇場の巨大な半円が覗ける。アリストファネスの『雲』も、かつてここで上演された。――振り返ると、パルテノン神殿正面破風の、女神アテナの像が目に飛び込んできた。ゼウスの額から飛び出し、今にもソクラテスに挑み掛からんとする勢いだった。神話が物語るアテナの誕生は、ペルシアの破壊から再生する、アテナイの新たな日の出を表わしていた。――だが、再生し飛び立つアテナを正面で待ち構えていたのは、アテナイを組み伏せたリュサンドロスの幕舎だったのだ。
呼び出された部屋でソクラテスを待ち受けていたのは、占領軍最高司令リュサンドロスその人だった。――リュサンドロスは、スパルタの古来の風習にのっとり、髪を長くし、顔の周りに見事なヒゲを蓄えていた。
「あなたがあの名に聞こえた、歴戦の勇士にして大哲学者のソクラテスさんですか。お会いできて光栄です」ソクラテスに近付き、にこやかに笑顔を見せながら握手を求めてきた。「なるほど、噂通りの面構えでいらっしゃる」戦場で鳴らしたソクラテスの腕力を子ども扱いするほどの勢いで、精力的に握った腕を振り回した。
部屋に同席している者の中に、見知った顔が幾人かいた。かつての彼の弟子、クリティアスやカルミデス達だった。彼等寡頭派の者達は、民主派に追われるようにして亡命していた筈だが、民主派政府が倒れ、帰国を果たしたらしい。亡命者の帰国を認めること、これもスパルタが降伏に際し、アテナイに課した条件の一つだった。
「先生。お久し振りです」「やあ、君達。もう帰っていたのか。――壮健そうで、何よりだ」占領軍司令に交わした握手の両腕を思い切り揺すられながら、何故こんな場所に彼等が、かつての弟子達が同席しているのか、ソクラテスは首を捻った。
手を離したリュサンドロスは、「感動のご対面も成ったところで、――今日お越しいただいた用件を、これからお話したい」部屋の中をゆっくり大きく廻るように歩き、大きな机の向こう側に戻った。
そして司令官用の背もたれ付きの豪華な椅子に腰を落とすと、机の上に組んだ両脚を乗せ、ふんぞり返って見せた。リュサンドロスの履くサンダルの裏が、ソクラテスから見えた。
「既にご存知のことと思うが、我輩はヘラスの各地で民主派を一掃し、志を同じくする方々にそれらポリスの国政を一任してまいりました」アテナイ海軍を殲滅した後、アテナイが降伏するまでの間、リュサンドロスは与えられた時間を無駄にすることなく、抜かり無く立ち回っていた。デロス同盟加盟国だったポリスを次々攻略し、そこに十人の同志からなる寡頭政権、つまりは“傀儡政権”を立て、自らの支配を磐石なものとしていった。既に本国スパルタの思惑を越え、今や全ヘラスがさながら“リュサンドロス帝国”の様相を呈しつつあったのだ。
「そして今回、アテナイにも三十人のアルコン(執政官)を、さらにペイライエウスにも十人のアルコンを、それぞれ置こうと思っている」ヘラス全土の覇王となりつつあるリュサンドロスは、おのれの計画に酔うように続けた。「既に同志クリティアス君達が、この提案を次の民会にかけるため、準備を進めているところだ」
用意された椅子に腰を下ろしながら、ソクラテスはかつての弟子達と覇王とを、交互に見較べた。この者達は、既に同志と呼び合う程の間柄なのだろうか。
「そこで、だ」覇王が、タイミングを見計らうように、厳かに告げた。「これが今日の話の本題なのだが、――」間を置いて、ソクラテスの目を、尊大に見下ろすように、ジッと見た。そして、後を継いだ。「あなたに、その三十人のアルコンの一人として、政権に参加していただきたいのだ。あなたを、政権の思想的バックボーンとして、最高顧問として、お迎えしたい。――これには、君を是非ともと、同志クリティアス君達から強い推薦があったことを、一言申し添えておこう」
突然の申し出に、ソクラテスは覇王の話の意味するところが、まるで理解できないでいた。クリティアスが、いたわるように、彼に助け舟を出すまで。
「先生こそは、我等の新政権の象徴たるに相応しいと、私から将軍閣下に強く申し出たのです。――先生はこれまで、アテナイ民主制の愚劣を執拗に暴き続け、スパルタの国風をことさら讃えてこられた。――スパルタの、質素であることを一顧だにせず、高みのみ見詰め続ける気風。死と常に背中合わせにありながら、無駄な弁論を徹底して削ぎ落とした生き方。これぞ人として生きる姿の理想だと、常々仰っておられた。――ですから、新政権が世に示す理想の代弁者として、我等の精神的支柱の地位に是非とも就任していただきたいのです」既に50代のクリティアスだが、若者のように目を輝かせてソクラテスを見詰め続け、熱弁を振るった。
スパルタの、“武士は食わねど、高楊枝”――確かにソクラテスの、日頃の身なりや物欲に執着せぬ様子は、スパルタ兵のそれにそっくりだった。彼がスパルタ好みを暗に表明していると捉えられても、仕方なかった。
“武士道は、死ぬことと見付けたり”――しかし、寡黙であることを最高の美徳とするスパルタとは正反対に、ソクラテスは底無しのお喋りだったが。
「だがね、――」とソクラテス。いつもの空とぼけた調子を取り戻しつつ、クリティアスの熱狂をはぐらかした。「君達もよく知っている通り、ワシは公的政治に関わりを持たないことを、モットーとして生きてきた。そこにこそ、ワシの哲学の拠って立つ地歩がある。――それを今さら、しかもこの歳になって、突然宗旨替えすることなんて出来ないよ。
君達の活躍を、陰ながら応援する事はやぶさかでないが。――公的な役職に付くことだけは、どうか固くご辞退申し上げたい」
反体制で皮肉屋のソクラテスはアテナイの親スパルタ不平分子達の偶像的存在と目されていた。そんな、若い頃“ソクラテスかぶれ”だった面々の中に、少年時代以来の弟子カルミデスもいた。クリティアスの従兄弟で十歳程年下の彼をクリティアスがソクラテスに紹介したのは、ポテイダイアの戦線から帰還した頃で、当時カルミデスは評判の美少年だった。以来、ソクラテスの愛弟子となった。
今も美丈夫と呼んでいい彼が、今度はクリティアスと交代し、目を少し潤ませながら、ソクラテスの説得にかかった。
「先生。思い出してください。――かつて、公衆の面前に出ることを恥ずかしがっていた私に、国政に参加する勇気を持てと鼓舞してくださったのは、先生ご自身ではなかったですか。ですから私は、こうして今、クリティアス達の考えに賛同し、新政権の活動に参与するつもりでおるのです。
ところが、その先生ご本人が、政治には距離を置くという。――これではまるきり、先生の日頃仰られている哲学的誠実に背反する、言動不一致というものではありませんか。
この期に及んで、――国家の敗北という事態にまで立ち至って、――それでもなお“ノンポリ”を決め込むなど、男子にあるまじき卑怯千万な態度と誹られても、何の弁解も出来ないでしょう。
今こそ、先生もまた、かつて私に勧められた事を、自ら実践なさる時です!!」
当時のヘラスでは、党派に参加しそして戦うことが、真っ当な市民の務めだと思われていた。どちらにも付かない中途半端な態度は、それ自体胡散臭いものと見られた。
愛弟子達の予期せぬ反乱に、ソクラテスはこれまで経験したことのない目眩と不安を感じた。「君まで言うか、カルミデス」思わず椅子から立ち上がった。だが気を取り直して、再び探るようにして着座した。「それでもやはり、申し訳ないが――ワシには無理だ。
ワシは、アブのように飛び回って、愚鈍な馬の如き体制にしつこく纏い付き、時々チクリと刺して、その惰眠を破る。それがワシの、やり方なのだ。それが、性に合っているのだ。――だから、どちらの体制下でも、どんな体制下でも、ワシは反体制を貫き、アブであり続ける。――決して、体制側の人間に、なる事はない」
親友の喜劇作家アリストファネスらと目が合った時、ニヤリと笑い合い無言の視線を交わすことがある。同じ“反体制屋”として、彼等と一番ウマが合ったように思う。何でも槍玉に挙げる、同じ種類の批判精神を共有していた。ただその批判の方法が、喜劇ではなく、人類初の“哲学”であったというに過ぎない。時の流行や威張りくさった奴等はもとより、仲間同士ですらからかい合うその精神。だが、こうしたものが理解できない“ヤボテン”が、あまりに多過ぎる。彼の弟子の中にすら。
彼がアテナイの民主制を批判したのは、彼がアテナイに住んでいたからに他ならない。もしスパルタに住んでいたら、スパルタの体制を皮肉っていたことだろう。だが、スパルタでそれをやれば、すぐさま妨害されるであろうことも、彼は充分承知していた。彼がアテナイの体制を批判できたのは、アテナイの体制あってのことだった。彼は、手放しでアテナイの民主制を賛美する気には到底なれなかったが、アテナイの気風を何よりも信頼し、愛していた。
「この非常時に、――敗戦という、未曾有の危機にぶち当たっても、――まだ言われるのか!!――反体制などという、愚にもつかぬ事を!!」
今度はクリティアスが立ち上がって、脇の小テーブルを拳で叩いた。怒りを紛らすように、自席の前を数歩行きつ戻りつした。
「体制も何も無い。強い指導力が、迷える牛や羊どもを、引っ張っていかなければならないのです。その牛や羊どもが戦争を指導した結果、自ら掘ってそこに落ち、出られなくなってしまった敗戦という大穴から、連中を引っ張り出してやらねば。――体制批判の出番など、まるでありません!」
かつて青年の頃のクリティアスは、周囲に消え難い印象を残す、物憂げな若者だった。今はその同じものが、どこか狂気を帯びた光として目に宿っていると、ソクラテスには思えた。――ペロポネソス戦争が戦われたこの三十年近い月日の間に、クリティアスの思想はソクラテスのそれとはまるでかけ離れた方向へと練り上げられていった。彼の過激な思想は、“徳”、“善”、“神”、“法”といったものは自然の摂理に反する人為的なものであり、“力”が支配する、弱肉強食の世界こそが正しい在り方である、との結論に辿り着いた。人の造ったコトワリに諾々と従う者は、“精神的奴隷”であるとし、否定した。力による支配は、全ての法や正義を踏みにじり、ルサンチマンを叩き潰す。先鋭化した少数のインテリ過激派は、“超人思想”に先鞭をつけ、初代ロベスピエール、元祖スタヴローギンとなった。ニヒリズムへと至る合理主義を産み落とした。若い頃から負けん気や自尊心の強かったこの弟子の中に、ソクラテスは哲学の暗黒面、深く秘められた黒い輝きに至る危うさを予感していた。
「それではいよいよ、ワシの出番は無い、ということではないかね?――それにもし、これまでに公的政治に首を突っ込んでいたなら、ワシはとうに葬り去られ、哲学の営みを続ける事も出来なかったことだろう。――分かってくれたまえ、君達」
「あなたはいつも、遠く離れた安全地帯から、ぬるくていやらしい批判をなさるばかりだ。昔から、そうだった。それではあたかも、戦場の遠くから矢を射掛けるばかりの、臆病な弓兵の如き所業だ。とても、白兵戦に踏み込む、勇猛な重装歩兵の振舞いとは思えません。既にソロンの法の時代から、ポリスの雌雄を決する党派争いに無関心を決め込む手合いは厳しく罰すべしとの決まりがあることを、まさかご存じないわけではありますまい」
「その言いようは、心外だ。ワシが重装歩兵として、おのが命を省みず、三度の厳しいいくさをいかに戦い抜いてきたかは、君等も充分に承知している筈だ」
「ですからこそ、――その同じ勇気を、――今度は政治の場で発揮していただきたいのです!」と、今度はカルミデス。「先生は以前、政治の場でも一度、その勇気を遺憾なく発揮なされた。あの、六人の提督が愚かしくも無残に処刑された、アルギヌーサイ沖海戦の折のことです。先生は、アテナイ中の衆愚を相手取り、ただ一人勇侠を示し対峙なされた。怒り狂う衆愚どもを尻目に、あの時のあなたのいかに輝いて見えたことか、……」
終戦の僅か二年前、常時劣勢だったアテナイは、アルギヌーサイ沖海戦で、久方振りの、そして最後の大勝利を収めた。この時、スパルタ側から和睦の申し出があった程である。だが、熱狂したアテナイの民衆は、何度も繰り返されたことだが、この和睦を蹴った。
さらにその熱狂は、熱さを保ったまま怒りへと変じた。折からの嵐により、戦場で漂流した兵士達を救助できなかった八人の提督を、極刑に処せと遺族達が騒ぎ立てたのである。これもいつもの事ながら、デマゴーグ達がこの怒りに油を注いだ。アテナイは、最後の大勝利をもたらした提督達の功績に報いるに、極刑を以ってした。
この時ソクラテスは、偶然にも国政審議会の五十人の執行委員の一人だった(別に自ら進んで公職に就いた訳ではなく、たまたま抽選の結果の成り行きだった。アテナイの政治は、万事がこの調子で執り行われていた)。八人の提督の内二人はアテナイに帰ってこなかった(大衆の習性を熟知していて、逃亡したのだろう)。残りの六人を、まとめて処刑せよと、大衆は騒ぎ立てた。しかしこれは、規則に反することだった。本来は慎重に一人一人審議し、判決が下されるべきものである。従って執行委員は、六人まとめての性急な裁判は認めなかった。ところが、今度は大衆は、ならばお前達も同罪として極刑に処するぞと、執行委員達を脅しにかかった。四十九人の執行委員が、この脅しに屈した。リンチをも怖れず、敢然と抵抗し続けたのは、ソクラテス唯一人だった。スジを、貫いた。
しかしソクラテスの抵抗もむなしく、六人は即刻処刑されてしまった。処刑し終えた途端、大衆の熱は冷めた。冷めて、猛烈に後悔した。後悔して、今度は攻撃の矛先をデマゴーグ達に向けた。
直接民主制下のアテナイでしばしば繰り返された、衆愚の暴走の一例である。執行委員として大衆を前に大立ち回りを演じるハメになったあの嫌な思い出を、ソクラテスは苦々しく噛み締めていた。あの、民主制の恥ともいうべき事件。暴徒が民主制の仮面を被って、民会を牛耳り国法を踏みにじった……。
「勇気か」ソクラテスは、言葉の意味を慎重に掴み取るように、おのが百戦錬磨の両手の平を睨むように見詰め続けた。「だが、熟慮も無しにただ飛び込むだけでは、“蛮勇”というものだ。“勇気”と“蛮勇”の区別、ここでじっくり吟味してみるのもよい。もしリュサンドロス閣下のお許しが下りるならば、……。
それに、民主制というものも、衆愚をうまく欺く者ばかりが権力を握るならば、確かに“詐欺師の政体”と呼んでも、そう的を外しちゃおらんだろう。――だがな、それの生み出した“独立自尊”の精神。かつてのヘラスにも、そして今のペルシア始めバルバロイどもの間にも無い、というか人類史上初めて今のヘラスに降臨したそれこそが、哲学の生まれる土壌、礎であるとも、ワシには思えるのだ。――確かに、大勢群れ徒党を組んだ大衆ほど、愚かなものはない。しかし、一人一人となった時、人がより良く生きるためには、自立せねばならず、である以上政治的にも自立していなければならず、となれば残念ながらどんなに愚かしくとも民主制以外には選択し得ないことになる。寡頭制でも、僭主制でも、勿論奴隷に身を落としても、ダメだ! より良く生きることを、各人が自覚して生きていく以上は。自立を放棄してはならない!
要は、大衆主義と、個人主義とに、民主主義を区分けするということだろうか。前者は衆愚政治に、後者は哲学に通じる、……」
「意外ですな! あなたの口から、民主制擁護論を聞こうとは!」と、ここでリュサンドロスが、師弟の論戦に久方振り割って入った、声の調子にかなりの棘を含ませつつ。それまでは、かつての師匠と弟子の私情を交えた言い争いを、面白そうにニヤニヤしながら見物していたのだが。「大戦中アテナイは、力に任せヘラスの全ポリスに、アテナイ流の民主制を“押し売り”し続けてきた。そうやって、自陣営の仲間、――というより子分ですな、――を増やそうとしてきたわけです。――戦後、この汚染を払拭するのに、我々がいかに骨を折ったことか」覇王は、おのが事業を自画自賛した。
「そうです。閣下の粉骨砕身の努力にもかかわらず、我々にはそう悠長に構えていられるゆとりはないのです」勢い込んで、クリティアスが後を継いだ。「民主主義者どもは、せっかく成った『スパルタの平和』を、是が非でも覆さんと、日夜暗躍し続けております。奴等がいかに戦いを望んでいるかは、先生もよくご存知でしょう。畢竟課題は、好戦的で戦闘継続を望む民主主義者どもを、いかに押さえ込むかに尽きるのです。このポリス内外の、いまだ残存する多くの敵を打ち破って、強行突破するしかないのです」
停戦講和は、何度も為される機運があった。戦況を有利に進めるスパルタ側が、むしろ乗り気だった。それらを悉く潰したのは、相変わらずのアテナイの衆愚だった。彼等は、戦争の熱気に浮かれ、祭の如く騒ぎ立て、平和の機会を悉く蹴り飛ばしたのだ。――ヘラスの民主制は元々戦争の産物だった。参戦する者だけが、すなわち参政権も得た。かつて騎馬を操る貴族のみが、戦闘可能だった。重装歩兵の装備を備えた自営農民や職人が、これに加わった。そしてヘラスには、エーゲ海が主戦場となるという特殊事情があった。そのため軍船の漕ぎ手の無産庶民も参政権を得るという新局面が開けた。参政権は、戦うと決めた以上文句は言うなと、有権者に覚悟を迫るための制度だった。つまりは、戦争のための道具だった。だが一方、それまでの少人数の馴れ合い政治と違い、多くの人を納得させるための開かれた、スジの通った“説得”が要求された。その事が弁論や哲学といった文化を開花させ、“真理の探究”に価値を持たせた。哲学は、エーゲ海と戦争の賜物だった。
「強行突破のためには、“力”に頼るしかありません。“徳”や“善”や“神”や“法”すら超越した、“力”です。――当面、“徳”や“善”や“神”や“法”には、引っ込んでいていただきたい」クリティアスの師への期待は、心底からの失望と憎悪へと、裏返ったようだった。「ですから、協力しろとは、もう申しません。――ですが、金輪際、邪魔はしないで戴きたい!!」
戦後の国政を決する民会が、リュサンドロスらの臨席の下、開かれた。穏健寡頭派のテラメネスが取り仕切る形で、議事は進行した。騒動屋のドラコンティデスが提案した“三十人”体制案に賛成するよう、テラメネスが市民に求めた。次いでリュサンドロスが壇上に立ち、もし諸君らが反対すれば、諸君らにとっては国政ではなく身の安全の方が問題となるだろうと、その龍顔から発する役者のようにメリハリの利いた声で脅した。議場の前列には、クリティアスを信奉する者達が警棒をぶら下げて並んでいた。さらに議場の外は、警備と称して占領軍の兵士らが埋めていた。かくして、急進派のクリティアス、穏健派のテラメネス、それに三十人にのし上がったドラコンティデス、エラトステネス、カリクレス等唾棄すべき奴等を含め、三十人体制が成立した。
ソクラテスら心ある市民は、民会とは名ばかりの茶番劇に我慢ならなかった。ある者は沈黙し投票を拒否し、ある者は怒りにまかせ席を蹴り、退出した。ソクラテスも、退出した者の一人だった。会場外を取り巻くスパルタ兵の陣形に切り込むように、その間を割って突破した。
――当初“三十人”は、訴訟常習者や街のチンピラ等を取り締まり、市民のご機嫌を取った。しかしすぐ、本性を表わし、民主派等反対勢力を取り締まり、捕え、処刑しだした。発言しようとする者の、口が塞がれた。密告と拷問と暴力が横行した。敵味方構わずの、暗殺とテロと粛清が頻発した。恐怖政治が、深化していった。そのため、彼等は“三十人僭主”と呼ばれるようになった。
民主派の者は、他ポリスへの亡命を余儀なくされた。亡命者をアテナイへ送還するよう、スパルタからヘラス全土に指令が発せられた。しかし、カルキス、テバイ、メガラ、アルゴスの各ポリスは、これに応じなかった。スパルタの独裁を、危惧し始めたためである。これらに蒔かれた種が、やがて民主制復活の大輪の花を咲かせることとなる。
棍棒や鞭をちらつかせた、ナチの突撃隊まがいの若者達が、街を徘徊し、反対する者に睨みを利かせた。クリティアス派の、私設軍隊だった。ただ行進するだけで、恐怖を撒き散らした。時には必要も無いのに、威嚇の暴力を街頭に刻み付けた。
――その若者達の振るう暴力が、ソクラテスにある光景を思い出させていた。――あれは十年程前、アガトン邸で催されたシュンポシオンへ赴く道中での出来事だった。不意の昏迷が彼を襲った。後でアガトン家の召使に聞いた話だと、隣の家の車寄せのスペースに入り込み、壁と睨めっこをし立ち尽くしていたそうだ。ほんの半時程の間のことだった。
ソクラテスはこうした、立ったままの金縛りに、襲われることがしばしばあった。そうした朦朧としたプシュケーの麻痺状態の中で、ダイモンはよく彼に白日夢を見せた。その多くは、金縛りが解けてしまうと、途端に跡形もなく消えてしまう類のものだったが、中には印象深く鮮明に憶えているものもある。アガトン邸の門前で見た白日夢はそうした例の一つで、余りの鮮明さに、十年経った“三十人”の時代にも、十五年経過した死を間近にした今も、手に取るように思い出せる。――それは、こんな幻だった。
――そこは、どこかヘラスと似ているが、しかし細かい部分が微妙に違う、地上のどこにあるかも分からない土地だった。建物の造り、その建材等、一見似ているが、よく見ると違う。木々も、草花も、見慣れたものもあるが、見覚えの無いものも混ざっている。そして人々の服装も、どこか異国風のものだった。何より、アテナイが大都会であるのに対し、今いるそこは貧相な農村だった。どこぞの、バルバロイの住む蛮地の片隅だろうか。人々の言語も、バルバロイのそれのようだったが、夢の中故だろう素直に理解できた。
その村で彼は、まだ十歳にも満たない、小さな少年だった。今、アレクサンドリア図書館の主任司書カリマコスであるのと同じように、この夢の中では、どこぞの寂れた村の、誰とも知れぬ一人の幼い子供だった。――粗末な服を着、裸足で、始終腹をすかせ、家の者に食い物をねだり、その都度叱られ、外で仲間達と駆けずり回り、悪さをして回り、その都度また村人達に怒鳴られた。
――その村に、何時の頃からか、“悪鬼”が住み着くようになった。悪鬼達は、棍棒をぶら下げ、村中をのし歩き、村人達を追い掛け回しては容赦なく打ち据え、村人達を従わせた。まるで夢の中に出てくる、黒い影のような悪鬼そのものだった。少年は、本当に彼等が夢の中から飛び出してきたのだろうと、当初思っていた。夢と起きている時の区別が、まるでつかなくなった。――これだ! ソクラテスは思った。あの時の悪鬼達と、今目の前を傍若無人に横切っていくクリティアスの私兵らと、そっくりだったのだ! 両者とも、暴力の支配する土地だった。一方は寒村であり、一方は大都会という違いはあったが。
丁度冷たい雨の続く寒い冬の頃だった。人々はただでさえ残り少ない食料や燃料の蓄えを細々と節約しいしい使っていたが、それらを悪鬼どもは情け容赦なく奪っていった。人々は立ち枯れしている草木や、廃屋の瓦礫の中や、殆ど形を留めない荒れたオリーブ畑やらから、口に入れられそうなものは拾い出し口に入れ、燃やせそうなものは掻き集め炉にくべ暖を取った。そうした枯れて固まった残骸は、さながら人の死体の一部のように見えた。現に村には、悪鬼達に撲殺された村人や少年のご近所さんや友人達の死骸が、所構わず転がり、そのまま埋葬もされず涸れて固まったり朽ちたりしていた。――少年は壁の落描きや地面の悪戯描きを好んで描いたが、この頃はバラバラになった死体と悪鬼らの暴力のシーンばかりを専ら描くようになった。
その悪鬼らが、ある時子供達を村の広場に集めた。――子供らに、輪を作らせる。その中心に、少年は奇妙なものを見た。――目を凝らすと、人の首だった。だが、動いている、何か叫んでいる。まだ、生きていた。不思議な光景を見て、少年はショックを受けた。地面の下に胴体が埋まっている、という所まで考えが及ばず、本当に首だけが畑の野菜のように大地から生えているのかと考えた。首だけの男の声が耳に届くと、聞き覚えのある声だった。男の顔は斜め前からしか見られなかったが(男は首を回せないようだった)、顔見知りの、よく子供ら相手に商いをしている干しアンズ売りのおじさんだった。――知り合いと分かって、さらに動揺が増すと同時に、人間というものは野菜のように畑で栽培し取れるものなのかと、ふと思った。自分も、兄弟達や父母も、仲間達も、皆畑で採れたのだろうか。
悪鬼の一人が演説を始めた。この男は背教者である、と糾弾した。よって石打ちの刑に処する、と宣言した。――悪鬼達は頻繁に、“背教”とか“邪信”とかいう、少年にはよく意味の分からない言葉を口にした。唸り声の一種のようにも聞こえた。これらを理由に、背教者を炙り出すためと称して、密告が奨励され拷問が公衆の面前で行われた。“三十人”のやり口とまるで変わらぬ事が、ここでも繰り返されている、ソクラテスは思った。村では、神を讃える歌、聖戦を鼓舞する音楽以外、民謡、童歌、労働歌等あらゆる歌や音楽や舞踊が禁じられた。子供達の遊びも禁じられた、戦争ごっこ以外は。恋愛も禁じられた、兵士を量産するため以外は。
悪鬼達が石を投げ始めた。そして子供達にも投げるよう強要した。子供達は、悪鬼に棍棒で小突かれ殴られ、泣きじゃくりながら石を投げ始めた。「やめてくれ!」とおじさんは叫んだ。「お前達にはいつも、甘くて美味しい干しアンズを売ってやったじゃないか!」顔をグシャグシャにしつつ子供達の投げた石が、おじさんの頭のこめかみに当たり、後頭部に当たり、鼻の付け根に当たった。その都度、血をにじませ、噴き出し、おじさんの首は前後左右に振れた。
ソクラテスの少年も、そこらのものをつかみ、目標も定めず投げ捨て続けた。自分が今、何をしているのか、――何か投げ付けているのか、それとも泳いででもいるのか、何故か必死にもがいているのか、――それすらも分からない程に、混乱していた。
気付くとおじさんの首は、目を剥いたまま、動かなくなっていた。石の当たった時だけ、オモチャの起き上がりこぼしのように揺れた。
そんな悪鬼の同類達が、アテナイの街中で猛威を振るう状況下でも、ソクラテスは具体的な政治的行動をとる事はしなかった。民主派の連中と共に亡命するでもなく、抵抗運動に参加するでもなく、“三十人”の政策を支持するでもなかった。彼は相変わらず、今まで通り町へと繰り出し、誰彼構わず捉まえては哲学問答を吹っ掛けた。が、捉まった相手方の反応が、今までとはまるで違っていた。これまでのように、気安く問答に応じてくれたり、迷惑そうに怒り出したりするのではなく、――オドオドと話の中身を言い澱んだり、すぐこそこそ逃げ出そうとしたりした。ソクラテスの哲学的営為は、延々空振りのまま終始した。
そうこうする内、“三十人”が本部としているトロス(円形堂)から、呼び出しが掛かった。トロスは、アゴラ西南角にある円形の建物で、本来なら審議会の五十人の当番執行委員がここに詰めることになっている。今は、“三十人”とその取り巻き達が居座り、周囲を私兵とスパルタ兵とが固めていた。アクロポリスに通ずる参拝道からも至近距離にあり、何か騒ぎが起きた時駐留軍兵士がすぐ駆け付けられるという配慮もあったのだろう。
クリティアスの執務室には、“三十人”の内のクリティアスとカリクレス、それにペイライエウスの“十人”の一人カルミデスもいた。
「相変わらず、街で問答を続けていらっしゃるようですな」忙しそうに執務執行中のクリティアスは、机の上の書類の束から殆ど顔を上げずに、かつての師に向かって言った。「“弁論術の教授を禁じる”という新法令が施行された事は、勿論ご存知でしょうに」
「ワシの問答が、弁論術の教授だと?」問い質した。
「そうです」ようやく顔を上げた。「我々がそう認定しました。今のアテナイでは、我々が認めれば、それが正しいのです。あなたがいかに、例の調子の問答で混ぜっ返そうとね」
ソクラテスの活動を、法を以って禁止するという。“三十人”への就任を断られた事への、意趣返しだろうか。
「それにあんたは、」と今度は、クリティアスの左隣りに立ったカリクレス。「我々の施政を、牛の数を減らし質を低下させる無能な牛飼いに譬えて、批判して廻っているそうじゃないか。ポリスの有能な市民を次々処刑したり亡命させたりして、市民の数を減らしポリスを劣化させていると言ってね。――政府を批判した連中がどんな目に合っているか、知らない訳じゃないだろうに」
「仕方なかろう」とソクラテスは、ここでクリティアスの仕事机の右隅に片手を突いて立っているカルミデスの方を、憐れみを求めるように見詰めつつ、弁解した。「前にも言った通り、ワシは批判し続けるアブだ。それがワシの生き方なのだ。刺される側にだって、決して不利益な訳ではない」
師の必死の弁明にカルミデスはただニコッと笑っただけだったが、返事は隣りのクリティアスの方から返ってきた。「ただ刺される馬ばかりだなどとは思いなさるな。アブの煩わしさに、反撃する活きのいい馬だっておりますよ。そんな馬がその気になれば、アブなど尻尾の一振りで叩き落されてしまう」
何でも批判したソクラテスだったが、その批判を許すアテナイの気風だけは、無批判に気に入っていた。だから、アテナイの軽率な民主制を批判し、スパルタの国風を持ち上げる事はあっても、決してアテナイを出奔する事はなかったし、滅多に遠出する事すらなかった。――その自由な気風そのものを、“三十人”の無節操な蛮風は壊してしまった。ここは既に、アテナイではなくなった。
「そうだよ、ソクラテス」カリクレスが言った。「アブなど、弱々しい生き物だ。力ある者が大目に見ている間は、好き勝手な事が出来るが、一たび機嫌を損ねれば、すぐに駆除される」
コンスル三人が交互に話し、ソクラテスは彼等と向かい合う、被尋問者の位置に立たされていた。同じ位置に、ずっと立たされ続けた。カルミデスが言った。「そうですよ、先生」まだにこやかに笑っていた。「数を減らされる牛の次の一頭が、先生ご自身にならないよう、用心してください」
ソクラテスは、自分の耳が幻聴を聞いたのかと、瞬間疑った。
――あの、――天使のようだった少年が、――年長の才長けた従兄弟に感化されたとはいえ、――こんな台詞を口にするとは!
六十代半ばとは思えぬ今も強靭な体躯が彼の姿勢を支えていたが、実のところ彼の心は既にくず折れ、その場にへたり込んでしまっていた。――あの、素直で忠実な生徒だった彼が、ソクラテスの教えを真っ直ぐに受け止め続けた彼が、――長い歳月の果て、こんな悪態をつく人物に成り果ててしまったとは。
ワシのこれまでの哲学は、教育は、――三十年以上に及ぶ、少年達やポリスをより良くしようとした努力は、――一体何だったのだ?!
少年達は悪鬼どもの親玉に成り果て、ポリスは悪鬼どもの巣食う地獄へと堕した。――“善”を求め、“徳”を求め、“真理”を探究した結果が、まるで逆の結末に至った。あたかも、ペルシア帝国から独立し続けるための全ヘラスの努力が、自らの内からリュサンドロス帝国を生み出してしまったように。
何という、ニガい果実だろうか。ワシが生涯掛けて、実らせたこの果実は。――これが、天命なのか。ゼウスの裁き、掟の神テミスの返答なのか。――こんなことなら、父親の跡を継いで、マメに石工をやっていた方が遥かにマシだった。そうすれば、貧乏状態に落ちることもなく、クサンティッペとも子供達とも、仲睦まじい家庭生活を送れていただろうに。――腐敗し、果肉が裂けて、垂れ下がり、飛び散り、ウジが湧いて、悪臭フンプンたる、こんな果実を手の上に乗せて立ち尽くすことになろうとは、……。
自宅に戻ったソクラテスの耳に、女部屋のかしましい女達の話し声が聞こえてきた。
ソクラテスの家のあるアロペケ区は、アテナイ市の南東郊外、ペイライエウスに次ぐアテナイの外港ファレロン港まで延びる長城のすぐ外側に位置した。大戦末期、ペロポネソス軍が市壁すぐ間近にまで迫り、一家は市内に避難していた。いくさが収まってすぐ自宅に戻ったが、貧乏所帯に乱入する賊のいる訳もなく、家屋も石像達も皆無事だった。
そして今、多くの男どもが逃げたり殺されたりし、市中に取り残された女や子供達は男手の無い難を逃れるべく放浪し、親類縁者を頼って身を寄せ合い、ソクラテス家もちょっとした避難所、寄り合い所と化していた。見知らぬ女達が大勢居候している(クサンティッペの知り合いではあるらしいが)。ソクラテスと顔を合わすと、ヒョコと頭を垂れるが、すぐまた女部屋に消えてしまう。そして、ヒソヒソと、あるいは大声で堂々と、亭主(ソクラテスも含めて)や男どもの、噂話や悪口に花が咲いているようだった。
食い扶持がかさみ、ますます困窮してきた。そのせいという訳でもないが、久方振り石を刻む仕事に精を出した。手持ち無沙汰だったからである。別に“三十人”の言い付けを守る気などさらさらなかったが、肝心の議論する相手が捉まらなくては、哲学的営為は成立しない。手慣れた業で無意識の内体を動かしていると、気分が落ち着く。嫌な事も忘れる。クサンティッペも、亭主が家にいて仕事をしているのを見て、その理由を問い質すこともなく、まずまず機嫌がいいようだった。
――それまで“三十人僭主”は、急進寡頭制のクリティアス派と、穏健寡頭制のテラメネス派との、連合政権だった。だが、次第に両者の対立は表面化し、フランス革命を二千年以上先取る情況を呈しつつあった。
テラメネスは、良く言えばバランス感覚のある中庸の政治家、悪く言えば日和見主義の男だった。フランス革命の、ダントン役を演じた。一方クリティアスは、当代随一の“理の人”といわれた。理が走る故、過激な“実行力”を伴った。彼は情を超越した初代ロベスピエールとなった、そのプロレタリアートに対する態度は、親・反まるで真逆だったが。
クリティアス派は、既成の寡頭制(門地や財産を重視する)には、元々敵対的だった。知的エリートのみを、その中核としていた。そこで、穏健寡頭制派に対しても、容赦の無い攻撃を始めた。参政権のある市民をエリート三千人のみに絞り、その他の者達を武装解除した。主要人物を、次々粛清していった。そして遂にテラメネスにも引導を渡す時がきた。テラメネスは謀略にはめられ、獄に繋がれた。日和見主義者の彼だが、この時ばかりは意気地を貫いた。最後に天を仰ぎ、神々よ、この有様を御照覧あれ、と呼び掛け、クリティアスを呪って、毒ニンジンの杯を煽って死んだ。
穏健派の多くが、また一斉に市外地に脱出した。市郊外は、難民で溢れた。彼等は、先に亡命した民主派と合流した。その中に、テラメネスの腹心だったアニュトスもいた。彼はその後民主制復興運動の指導者の一人となり、さらに後、ソクラテスを危険分子として宗教裁判所に告発することとなる。
“三十人”は三十人を大きく欠き、テラメネスを処刑した卑劣な冷血漢サテュロスらで欠員補充する事で、ますます残忍、凶暴になっていった。穏健派を切り捨て、いよいよクリティアス率いる急進派の独壇場となった。
だがこうなると、――人々の恨みを買い、多くの敵を造り、自分の足許をどんどん掘り崩して、味方を少数の精鋭のみに絞り込むと、――畢竟、自分の身を守ることすら危うくなる。自分で自分の首を締め上げているようなものである。
暗殺の脅威に晒されたクリティアスらは、身の安全を図るため、スパルタに駐留軍の大増員を要請した。もう彼等に頼るしかなかったのだ。しかしスパルタ側は、容易には首を縦に振らない。増員には膨大な経費を要する。そこで、駐留経費は“三十人”側が持つ事で、両者は合意した。
ヘラス全土を飛び回り多忙を極める覇王リュサンドロスに代わり、代官カリビオスが精鋭部隊と共に派遣された。この援軍を得て、“三十人”の所業はますます暴虐を極めた。まずさしあたり、駐留軍への“思いやり予算”を得るため、労働人口の大幅減で底を突いた国庫を立て直さなければならない。そのためには、市民の財産を没収するのが一番手っ取り早い。ついでに、邪魔者を殺して、その財産を奪えば、一石二鳥である。
多くの無実の市民・住民が、とりわけ富裕な居留外国人が、ターゲットとなった。裁判も弁明も無しで、連行され、処刑され、その財産が奪われた。つまり今や“三十人”という政府そのものが、一大“強盗”機関と化していた。
その“三十人”から、再度ソクラテスに呼び出しが掛かった。――家に閉じ籠り、女房や息子達と大人しくしているというのに、一体何の用事だろうか?
既に見知ったトロスのあの部屋へ入ると、来客は彼の他に四人いた。計五人、呼び出されたようだった。“三十人”の一人ペイソンが、重装歩兵用の盾を見せびらかしながら、しきりに自慢げに話していた。
「ペイライエウスにあるメトイコイ(居留外国人)どもの盾工場を差し押さえたんだ。――奴等、こいつを民主派の連中に横流ししようとしていやがった、……」
その件なら、既にソクラテスの耳にも入っていた。彼の友人、弁論作家リュシアスの家族の営む盾工場が“三十人”に襲われ、工場家財は没収、彼の兄でソクラテスの友人でもあるポレマルコスが殺され、リュシアス自身すんでのところで脱出しメガラに逃げ延びたという。――ミケーネ時代以来の歴史の積み上がった、錯綜しゴミゴミしたアテナイと違い、ペイライエウスは極最近港町として整備された計画都市であり、道も広く物資も潤沢で多くのメトイコイの富豪が軒を連ねていた。リュシアスの一家もその一つで、父親ケファロス以来の名家であり、当地で盾工場を営み、その製品や、財力にものをいわせて雇った傭兵などを密かに民主派に送り届け、支援していたのだ。
自慢話に際限の無いペイソンを制し、今や“三十人”の首魁となったクリティアスが、呼び付けた五人の市民の前を行きつ戻りつしながら用件を伝えた。
「さて、皆さん。不埒なメトイコイの処罰が済んだところで、今日皆さんにお集まりいただいたのは他でもありません。――皆さんにも市民としての義務を果たしていただく、という極当たり前の話です。すなわち、市民としての義務、出征と同じことです」
五人の内の一人が質問した。「我々に、騎兵や重装歩兵として、どこか外地へ出征せよと、――そう御命じなのですか?」
クリティアスはその男の方を見、言った。「いや。外地への出兵、という訳ではありません。国内での業務です」そしてわざわざソクラテスの方を振り向き、先を続けた。「実は、逮捕して連行して来てもらいたい者がいるのです。我々だけでは、とても手が廻りませんので」
「誰を?」恐る恐る、ソクラテスは問うた。
壁に掛かっている地図で、クリティアスはペイライエウス沖合いのサラミス島を指し示した。「ここに隠遁している、民主派の大立者レオンです」
ソクラテスは息を呑んだ。「それは、――サモスで将軍職を務めた、あのレオンのことか」サラミスのレオンは、徳望高い、民主派の大物だった。
「そうです。――我々にとって、最も危険な人物の一人です」
他の四人の間にも、動揺が走った。互いに、顔を見合わせている。
「あのような御仁を、――恥ずべきやり方で犠牲にするなど、あってはならないことだ!」ソクラテスは言いながら、全身が震えだした。震えが止まらなかった。「それを、お前達は、またぞろ裁判も弁明の機会も無しに、処刑しようというのだろう!」
「仕方ないのですよ、先生」クリティアスは静かに反駁した。「こういう政体の大変革が行われる時には、多くの人々が犠牲となるものです。仕方ないのです」この、自らの行為を正当化する言い訳は、クリティアスの口癖となり、以降死ぬまで呪文のように繰り返されたという。
ソクラテスはまだ震えていた。「ワシが散々、口を酸っぱくして訴え続けてきた“徳”や“正義”が、こんな鬼子を産み落とそうとは、――。ワシの“産婆術”とは、一体何だったのだ、――」
「おや、先生。それは心外ですな」クリティアスは相変わらず冷静だった。「私はあなたの教えに忠実に従って生きてきたまでですよ。これからも終生、そうする積もりです」
「この非道のどこに、“徳”や“正義”がある?――この政権にしても、当初少しは期待していたが、今や無能な牛飼いを通り越して、ただ奪うばかりの野盗の群だ!」ソクラテスは腹の底から呻いた。
「私があなたから学んだのは、“徳”や“正義”などというさかしらな人間のひねり出した傷の舐め合いのための方便ではありません。究極の良きもののため、最後の真理のために道を究める、その姿勢です。私こそあなたの一番弟子であると、お認めにはなりませんか? 是非とも認めていただきたいものだ」
この、残忍な独裁者が、師へも牙を向ける恩を知らぬ野獣が、ワシの一番弟子だと? あの口達者なソクラテスが、怒りでとうとう声を詰まらせてしまった。
師のそんな様子に、少し勝ち誇ったような薄笑いを浮かべながら、クリティアスは話を逸らした。
「まあそんな個人的な戯言は、いくら話しても埒が開きません。
それより、話を戻しましょう。――サラミスのレオンを捕え、連行して来ること、――これは、命令です。国法の発する、命令です」
「国法だと?」ようやく口の利けたソクラテス。
「そうです。――国法は、現在、私達が作成中なのですから。私達が決めた事が、すなわち国法です」“三十人”の民会で決せられた本来の選出目的は、国法を起草することだった。それ以外の施策は、法の起草が成るまでの、すべて過渡的経過措置だった。
“三十人”の私兵らに小突かれるようにして、市民五人は建物の外に連れ出された。これではまるで、連行役の者達が、連行されているように見えた。“三十人”の意図は明白だった。市民すべてを、とりわけソクラテスを、“共犯”に仕立てたいのである。最初の内“三十人”とその一派の者でやっていた市民の連れ去りが、今や一般市民を使役して行われるようになっていた。つまり、市民に市民を敵対させようというのが、連中の狙いだった。
周囲を警棒や鞭をぶら下げたチンピラどもに取り巻かれ監視されながら、五人はペイライエウスへ向かうペイライオス門をくぐる道をトボトボと歩き出した。が、アゴラから出てわずかも行かぬストラテゲイオン(将軍詰め所)の壁の前に差し掛かった辺りで、不意にソクラテスの歩みが鈍り、詰め所の壁と向き合ったまま、一歩も動かなくなってしまった。それどころか、上半身の動きも、顔の表情すら、あたかも大理石で彫られた如く、固まってしまった。――チンピラどもが怒鳴り散らし、小突き回したが、びくともしない。困り果て、かつその不気味さに耐え兼ねて、彼等は親分を呼びにやった。駆け付けたクリティアスはその小太りの老人のような石像を見るなり、「やれやれ、厄介だな」と言った。さらに「こうなったら、この人は、テコでも動かないんだ」誰に聞かすでもなく、口の中でブツブツそう呟き、――老人の石像一つを残して、残りの者達を連れサラミスへ向かうよう、子分どもに指示した。石像一つが、場違いな道端に、しかも通行人に背中を向けた姿勢のまま、ポツンと取り残された。
悪鬼達が、嫌がる子供達を並ばせ、隊列を組ませ、軍隊の真似事をさせていた。突撃や、槍突きや、投石の訓練を施し、子供達を小さな悪鬼に仕立て上げ、自分達の仲間の補充要員にしようと目論んでいるようだった。
そこに登場したのは、十年程前に白日夢の中に現れた、あの黒い影のような悪鬼どもに間違いなかった。場所も、悪鬼どもが支配する、同じあの村だったろう。とすると、今ワシが槍突きの訓練をさせられているこの少年も、あの時の少年と同じ少年、ということになるのだろうか?
その頃の少年の体験は、悪夢の中を連れ廻される恐怖、そのものだった。悪鬼に強制され、思いもつかない、色々な事をやらされた。少年は翻弄され、もみくちゃにされるしかなかった。その寒村に巣食う悪鬼達は、あらゆる悪徳を思い付き、それを楽しげに小気味良げに、子供達に実行するよう強要した。
そしてある日遂に、それが待っていた。――少年は、目隠しをされ、槍を持たされた。今度は何をやらされるのか、少年は強い不安を感じた。悪鬼の一人に手を引かれ、三十歩程歩かされ、槍で突くべき方向を指示された。“一気に、強く突け!”悪鬼の命令口調の怒声が、厳しく少年に浴びせられた。反射的に少年は、鋭く槍を突き立てた。――柔らかい何かに、槍の穂先がグズグズとめり込んでいく、手の平に戻ってくる不快な感触が、足許から襲う震えるような恐怖に変わり、少年の内側一杯に湧き立った。すべての思考が、消えた。
もう目隠しを取ってもいいぞ、と随伴した悪鬼が言った。恐る恐る邪魔者を取り去ると、目の前に転がっていたのは、真っ赤な血の海に全身横たわった、少年の家の隣りに住む親しいおばさんだった。彼女は猿轡を咬まされ手足を縛られていた。少年とは逆に、よく見えるよう目隠しをされる事はなかった。――そのおばさんには、野良仕事に忙しい母親に代わり、物心付いた頃から何くれとなく面倒を見てもらっていた。少年も母親同様に、慣れ親しみ甘えていた。甘く潰した果物を食べさせてもらい、一緒に水浴びをし、親に怒られた時は優しくかばってもくれた。今朝も、その懐の中で甘えてきたばかりだった。
少年は、槍を取り落とすこともなかった。あらゆる動作がとれず、停止していた。――そして、少年は(無論ソクラテスも)、その場で失神した。
ストラテゲイオンの壁と目が合っている自分に気付いた時、ソクラテスの心は少年同様悲しみのどん底に沈降していた。――やがて、周囲に自分以外誰もいないことを確認すると同時に、愛する者を自らの手に掛けた時の心情について立ち尽くした姿勢のまま考察した。
まるで、オイディプス。愛する者を、そうと知らずに自ら殺す。――オイディプスは、殺してから世界を見ぬよう目を潰したが、少年は、世界を見ぬよう目を塞がれて、愛する人を殺した。――その刹那、嵐の如く突如襲い来る、絶望。
ワシの絶望は、人生の大半をかけた哲学を、幾人かの弟子達により裏切られ、根底からひっくり返された、いわばマラトンの浜の伝令が走り抜いた距離の如く、長い長い絶望。対して少年のそれは、雷の如く、瞬時に全存在を打ち倒す絶望。――あるいは、サラミスのレオン殿殺害の片棒を、奴等の言う通り担がされていたなら、同じような急性の絶望を味わう羽目になっていたかも知れぬ。
幸いにも、今奴等の監視の目は、ここには無い。――このまま、逃亡してしまおうか。――いやしかし、愛するクサンティッペや息子達を置き去りにしてアテナイを離れるというのは、余りに忍びない。愛する者を失う嘆きは、今見てきたばかりではないか。それに、取り残された女達の悲惨は、我が家に居候する彼女らを見れば余りに明らかだ。
結局ソクラテスは、そのまま自宅に戻り、サボタージュを決め込んだ。“三十人”の“共犯”になる事を拒めば、今度は自分が“三十人”に狩られる側となる。何時奴等に踏み込まれても、不思議じゃない。
が、その後“三十人”からのコンタクトは、まるで無かった。あるいは“昔のよしみ”で、見逃してくれたのかもしれない。それとも、既に民主派の巻き返しが、近郊のフュレやペイライエウスで始まっていたから、ソクラテスなんぞに構っている暇がなくなったのか。
いずれにせよ、ソクラテスは“三十人”の厄災から逃げおおせた。しかしサラミスのレオンは、結局ソクラテス抜きで、捕縛され処刑されてしまった。
*
ソクラテスが、アポロンの求めるムーシケーを探し当てるために、図書館の多くの蔵書を開いて卓上に並べそれらの間をあちこち歩き廻りながら読み比べている所へ、ムセイオンに寄宿している知り合いの学者の一人が通り掛かった。「御精が出ますな。司書殿」と囁くように声を掛け、軽く会釈して通り過ぎていった。やがてその学者の後ろ姿が、図書館の柱廊に沿って壁沿いに設置された研究室の、彼に割り振られた部屋へと消えていくのを見送りながら、そういえばクリトンが、獄中のソクラテスを訪ねてきて“脱獄計画”について話す時も、あんな囁き声で話すのが常だったなと、ソクラテスは思い返していた。
《獄中のソクラテスの許に、クリトンが上物のワインを一壺抱えて面会に訪れた。
「やあ、クリトン。毎日ご苦労だね」ソクラテスは、枷がはめられ疼く足を擦りながら、旧友より先に声を掛けた。「獄吏連中も、よく気安く毎日の面会を許してくれるものだね」
「そりゃ、大分鼻薬を利かせたからな」クリトンは、悪戯っぽくニヤリと笑った。「明日からは、かなりの大人数が連日この牢獄に詰め掛け、君を取り囲んで講義をねだると思うよ。そう、話をつけてきた」
クリトンはワイン壺をソクラテスの傍に置きつつ、「それと、もう一つ」と小声で囁きかけた。「例の、“脱獄計画”の件だ。――根回しは順調に進みつつある。大船に乗ったつもりでいてくれ」――ソクラテスの牢は獄吏の詰め所のすぐ向かいにある。さすがにこんな話を聞かれちゃまずいので、小声にならざるを得ない。
実は、クリトンやアイスキネスをはじめ多くの仲間達により、ソクラテスを脱獄させ密かに国外へ逃亡させる計画が、準備されていた。獄吏や、十一人の刑務委員の何人かにまで、既に手を回し済みだった。――これには、裏の事情があった。元々アテナイ当局やアニュトス一派には、ソクラテスを刑死させるつもりははなから無かったのである。彼等はただ、邪魔者を厄介払い出来さえすればそれでよかったのだ。それにもし、ソクラテスの死にまで事が及べば、その反動もまた大きい。火の粉が、自分達の方にまで降り掛かってくる。だから彼等は、もしソクラテスが脱獄し行方をくらましても、見て見ぬ振りをするつもりでいた。いやむしろ、犯罪に犯罪を重ねた者として貶められる分、そっちの方が都合がよかった。――量刑を死刑に誘導し、あくまで刑死することにこだわり続けたのは、哲学的建前に固執したソクラテス自身であり、ソクラテス唯一人だったのである。
「テッタリア、か」ソクラテスは、独りごちた。まだ蛮風の残る土地だが、クリトン家のクセノス(異邦の客分)がいるそうで、そこへの亡命を勧められていた。アテナイの仲間だけでなく、テバイのシミアス、ケベスら異国人にも、ソクラテスを助けようという者は大勢いるらしく、逃避行は比較的容易に運ぶだろう。
テッタリアに着いたら、また以前のように、哲学的な生活を送ることが出来るだろうか?――ソクラテスは、夢想した。――遅れたテッタリアでのこと、最先進国のアテナイのようにはいかないだろうが、それでもこの五年間の閉塞状況から逃れられることを考えれば、遥かにマシだ。――このアテナイには、もはやワシの居場所は無い。アテナイは、敗戦により、すっかり変わってしまった。かつての自由な気風の崩れ去ったアテナイには、もはや何の未練もない。それに較べて国外では、ワシの名はまだまだネーム・バリューがあると聞く。昔の生活が、取り戻せるのではないか?――そして、かの地に落ち着いたら、クサンティッペや子供達を呼び寄せよう。妻は、生まれ故郷を離れ、また憎まれ口を叩くかもしれないが。ちっぽけな我が家は、そして無いにも等しい財産は、そのまま打っちゃってしまって何の問題も無い。アテナイ当局が没収するというなら、くれてやる。
「そうだ。テッタリアだ」と、クリトン。ワインを杯に注ぎ、ソクラテスに勧めつつ、「決心は、付いたか?」覚悟を迫った。
「まあ、待ってくれ。そう急かさんで。例のデロス行きの船が戻るには、まだ間がある。――それに、幾ら裏の根回しで事は容易に運びそうだといっても、表向きはあくまでも違法な脱獄だ。一般市民はそう思うだろうし、君達にもかなりの迷惑がかかるだろう」ソクラテスは、まだ決めかねていた。裁判で、啖呵を切った手前もある。もし脱獄し、言行不一致の行動を取れば、ワシの哲学者としての道義は地に落ちる。ワシの哲学は、根っこの部分から“信用”を失うだろう。
「迷惑など、気にするな。友の危機に命を張れなくて、それで男か!」クリトンが、何時になく男気を見せ、啖呵を切った。「それに、“命懸け”というのは、さすがに心配し過ぎだろう。せいぜい相応の出費と、少しの冒険心があれば、用は足りるさ」
敗戦来の五年間、アテナイ中の白い目、冷たい目に追われるようにして、ソクラテスは自宅に閉じ籠りがちとなった。あの、外を出歩くことを身上としていた彼にとって、この五年間は今の獄中生活と大差無いものに思えた。つまり今の生活は、その延長なのだ。この行き詰る状態から、脱したかった。
「そうだ。今度、クサンティッペさんの手料理も、一緒に持ってこよう。――いつぞや、君の家でやったシュンポシオンに出てきた、彼女の手料理を思い出すなあ。あれは、魅惑的な風味の、不思議な料理だった、……。――家族が懐かしくなれば、君の決心もいよいよ固まるだろう」杯を酌み交わしつつ、クリトンが断言するように言った。》
そのソクラテス家のシュンポシオンでは、クサンティッペがクリトン家の奴隷達と共に、自慢の手料理を大皿に盛り付け運んできたのだった。その日唯一の、ソクラテス家の料理だった。野草のハーブをふんだんに使った、イカ、貝、ウツボ等、魚介類の和え物だった。素朴だが、実に風変わりで、なかなかの一品だった。
「時々ワシは、ウチのかみさんはシビュラ(魔女)なんじゃないかと思うことがあるよ。野草や山の木の実なんぞを、実に巧みに使い分けるのだ。何でも母方の代々の家系に伝わっている“女部屋”の知恵なんだそうだが、――脱帽だ」その後ソクラテスの、かみさん自慢が続いた。
その時、扇状に並ぶクリネーのどこからか、「さすが、栗毛の馬は野生馬だ」と、囁く声が聞こえた。
その声が耳に入った途端、クサンティッペの機嫌が敷物を裏返したように悪くなった。クサンティッペには、“栗毛馬”という意味がある。野草料理と“じゃじゃ馬”を、かけたのである。
激情が一気に駆け上がったクサンティッペは、「この、――ゴクツブシどもが、――。ウチの穀物瓶を食い潰す、害虫どもが、――」と悪態をつき、泣きじゃくった。ソクラテスがすかさず女房の脇に寄り添い、慰めながら女部屋へ連れ帰った。「いやはや」とクリトン。「ソクラテスは、クサンティッペさんにベタ惚れだからなあ。――いい年をして若い女房をもらうと、――何とも、――」
ソクラテスが酒宴に戻ると、シモンが「“酒の精”を味わえ!」と、盛んに息巻いていた。既に相当に酔ったシモンは、ワイン壺を振り上げ、「オレはこの酒を、もっと濃くする事が出来る」と自慢した。
彼は工房から持参した小さな壺の中の液体を杯に注ぐと、廻し呑むよう強要した。まず試し飲みしたソクラテス派の若い面々が、次々、生まれて初めて見せるような、顔の中央に寄ったシワに、鼻も、口も、目も、全ての器官が埋没していくような、そんな表情をした。杯がソクラテスに廻り、彼は“酒の精”がまずとてつもなく香り高く、かつ鼻の奥を突いてくる事を知った。酒飲みのソクラテスは期待したが、次いで口に含むと、火を呑んだようになると思い知らされた。成る程、確かにとてつもなく、強い。だが、強いばかりで、ワインの芳しさは微塵も無い、どこかに飛んでしまっている。「エジプトやメソポタミアじゃ、あのナツメヤシの甘い実から、この酒の精を取り出し、飲むと、聞いた事がある。その製法を聞き出し、ワインで試してみたのだ」奥目で瞳がどこにあるのか分からないシモンが、ニッと笑ってさらに目を隠し、酒の精の入った壺を振ってみせた。
シモンのこうした技術には舌を巻く。同じ精製技術でエジプト産の黒い油を精製し、敵の攻城兵器やファランクス(密集方陣)を一瞬で火ダルマとし焼き払ったのを目撃した事がある。酔ったソクラテスは思いを巡らす。なめしや染色のため、薬液や毒液もよく使っているようだ。草木の知識に詳しいクサンティッペとは意見が合うらしく、「クサンティッペさんに教わった奴を、今試している」などと時たま言う事がある。二人のその手の親密さが、ソクラテスは面白くなかった。大体家から一歩も出られぬ良家の子女が、野草摘みなどとは想像もつかぬことだ。一体どんな育てられ方をしたのか。野草を摘んだ先祖とは、どういう女だったのだろう。シモンの店を溜まり場にしているのも、そうすればシモンを常時監視できるから、という思惑が無意識の内にある。
芳香を放つニンフのせいで、仲間内のシュンポシオンは狂乱の度合いが一気に増した。詩人気取りの小柄なアリストデモスが、大きなサイズのクリネーに身を持て余しつつ、イオニアの二人の酒仙詩人、アルカイオスとアナクレオンの酔狂詩を、熱烈に吟じ始めた。
*
リュサンドロス帝国は、あっけなく崩壊した。
彼の勢力のこれ以上の強大化を警戒したパウサニアス王が、“待った!”を掛けた。
『スキュタレー』と呼ばれる、スパルタのエニグマが彼の手元に届いた時点から、彼の覇道は暗転した。その暗号の命ずるところは、“本国への召還”であった。――全土の覇王も、本国へ戻れば、ただの一将軍に過ぎなかった。――リュサンドロスは結局、国家体制に服した人物としては、スキピオ・アフリカヌスに近い。後の項羽やスッラやカエサルといった、純粋な覇王にはなり切れなかった。時代がそれを許さなかった。
帝国の終焉が、アテナイの寡頭派と民主派の運命も、大きく反転させた。後ろ盾を無くしたクリティアス派は、脆くもついえた。クリティアスもカルミデスも、民主派との戦いのさなか、儚い朝露の如く戦場に消えた。
リュサンドロスとパウサニアス王の確執は、あくまでスパルタの“家庭内の事情”である。表向き同一歩調を取っているように見せて、実はその裏で王は覇王の足を引っ張っていた。だがその家庭内不和の影響は、ヘラス全土に及んだ。覇王の傀儡政権工作に対し、王はそれを元に戻すアンチ工作を展開した。――アテナイでも例外ではなく、勢力を盛り返した民主派が“三十人”政権を瓦解させた訳だが、それでもなお市内には“三十人”に従った寡頭派が多数居座り、頑として抵抗を続けていた。
政情を安定させ、リュサンドロスの影響力を根絶やしにするため、パウサニアス王は両者の和解を図った。だが、つい前日まで殺し合っていた市民同士が、今日の日が明けた途端遺恨を残さず和解するなどということが、果たして出来るものだろうか?――――そこで導入された離れ業が、――『アムネスティ』だった。
“アムネスティ”は、『大赦令』と訳される。本来、“忘れること”の意である。――その内容は、“三十人”の中核となった者を除き、全ての者の罪を問わない、というものだった。――つまり、そこまで無理矢理“和解”“宥和”し押さえ付けねば、和平の成り立ちようがない、そんな危うい均衡状態の上に、この和平は成立していたのである。実際、この大赦令を最初に犯した者は、即刻死刑に処されている。ここまでしなければ、即争いが再発火しかねない世情だったのだ。この処刑以降、表立った違反は一応収まった。
両派を含め、あらゆる市民の間に、敵意と、憎悪と、疑惑と、恐怖と、困惑の、物言わぬ視線が飛び交った。そして当然、久方振り街へ出たソクラテスは、そんな視線の十字砲火を浴びた。――“三十人”の時代が終わり、昔の生活が取り戻せるかと期待したのに、甘かった。市民達の視線は、告発していた。ソクラテスよ、オレ達が命の危険に晒され、アッティカの野を放浪している間、お前は市中で一体何をしていたのだ? のうのうと安楽に暮らし続け、逃れた者の財産を奪い、食い潰していたのか? なのに、オレ達が命懸けで復活させた民主制の恩恵を、言論の自由という恵みを、そんなお前が真っ先に享受しようというのか?
心の底に復讐心をたぎらせる、冷たい敵意剥き出しの視線を、スコールの如く浴びた。たまに少数の弟子達が寄り集まって彼を囲んでも、その外周を遥かに多数の民主派に取り巻かれ、威圧され、脅され、強制的に解散させられる始末だった。――建前上同じ民主制下とはいっても、それは以前の自由とゆとりとユーモアに満ちたアテナイとは似ても似つかないものに変じていた。
“三十人”の寡頭制下でも、復活した民主制下でも、ソクラテスは疎まれ、のけ者にされた。彼のユーモア溢れる哲学を市民が楽しみにしていた、あの豊かでゆとりあるアテナイは、もう戻ってこないのか。ビリビリした、神経症のような、ただ恐怖と憎悪のみがポリスの壁内に蔓延した状態が、何時まで続くのか。少なくとも、既に70歳のソクラテスにとって、彼が生きている内に事態が好転しそうな見込みは、まるで無いと思われた。――それでまた、意気消沈し、家に帰って石彫工房に閉じ籠ってしまうのだ。
アムネスティに守られているため、人々は表立って恨みを晴らすことが出来ない。アテナイ市民の間に、ますますフラストレーションが募っていった。――ガス抜きが必要だった。
そこで、アムネスティの対象とならぬ、いわば“抜け道”の理由をこじつけ、因縁をつける告訴が頻発した。“敗戦”や“三十人”の戦犯探しの“報復裁判”が、欺瞞のような告訴理由の許に、横行した。
そして、最後に残されたスケープゴートの目玉が、ソクラテスだった。戦犯探しをその源流へと遡っていくと、――最大の戦犯の二人、すなわち“三十人”のクリティアスと、敗戦最大の要因となったシケリア(シチリア)遠征を強行し、その後スパルタ、ペルシアと転々と寝返りを打ち続けた“変節漢”アルキビアデスと、――その両者を育て上げた師、あのソクラテスへと辿り着く。いわば、“大元の戦犯”である。この巨悪の元が血祭りに上げられるのは、時間の問題だった。
――そして遂に、その時はきた。ある日彼は、宗教裁判を管轄する、バシレウスの役所から呼び出しを受けた。
当時のアテナイの裁判は、たった一日のたった一回で、結審し判決が下る。裁判官はおらず、市民から抽選で選ばれた500人の裁判員が、原告被告双方の言い分を聞き、有罪無罪と量刑を多数決で決める。
ソクラテスは、ぞろぞろと入場してくる裁判員達の顔を、一人一人見定めていった。生真面目な、厳しい顔。惚けた、裁判になど興味のなさそうな顔。いかめしく裁く気満々の顔。知的に微笑む顔。日当目当てのアホ面。――彼等が、ソクラテスの今日相手せねばならぬ者達だった。
裁判員には日当が支払われる。以前は無償の奉仕活動だったが、それでは敬遠する者が多く希望者が集まらないので、一日の最低労役分の日当が支払われることになった。それでも、忙しい一般市民はやはり敬遠する。そこで、日当目当ての浮浪者もどきや、小遣い稼ぎの退役老人を、多数引き寄せることとなった。こういう連中が、ワシの“哲学”と“正義”を裁くのか。裁判員の顔を一つ一つ追いながら、ソクラテスは溜め息を漏らした。
ソクラテスは、当時最高の批評であり、思想表現の形式だった演劇を、遂に書かなかった(あるいは、詩才が無いから書けなかった)。大衆を相手としての表現を嫌った、演劇も、著作も、政治的弁舌も(その代わり、一対一のライブ・パフォーマンス、問答を好んだ)。一方通行で受け取るばかりの大衆が、暖簾に腕押しの、ぬかに釘の、そのくせこちらに害をなしてくる悪臭フンプンたるぬか床であると、確信していたからである。
大勢を前に弁じたことが、かつて一度だけあった。アルギヌーサイの海戦の六人の提督を擁護した時である。しかしあの時も、スジは貫いたが、それ以上喋る事はなかった。無駄だと分かっていたから。ソクラテスの反抗は、サボタージュという形を取ることが多かった。サラミスのレオンの時もそうだった。民会でも、ただ反対するだけで、ダンマリを決め込んだ。――しかし今回は、そういう訳にはいかなかった。弁論の終わった時は、すなわち自らの“死”を意味する。永遠のダンマリである。それに、弁明の持ち時間は、水時計により正確に割り振られていた。その間中、水の細く流れる間中は、喋り続ける義務があったのだ。
審議の中には、原告と一対一の問答形式の時間帯もあり、そうなれば相手を打ち負かす事はいともたやすい。この手のレスリングで、チャンピオンのソクラテスの右に出る者は、アテナイ中、いやヘラス中を探しても、見付からないだろう。ただ今回は、相手を打ち負かせばそれで終わり、というルールではない。打ち負かしても打ち負かしても勝ちではないという、変則ルールだった。全戦全勝しても、最後に500人の審判の、旗の多く上がった方が勝ちである。アゴラやギュムナシオンとは勝手が違う。相手は、答えてくれず、正すことも出来ず、それでいて彼の死命を制する強制力を持つ、“多数決”という、しばしば真理に反する、彼が人生で最も忌み嫌った方式そのものだった。
原告と被告の証人達も、それぞれのボックスに待機した。ソクラテス側のそこには、クリトンやアポロドロスやプラトンや、その他多くの仲間達や証人達が陣取り、ソクラテスと頻繁にアイ・コンタクトを取ろうとする。証人席の間に、水時計の瓶がセットされた。上の瓶から下の瓶へ水が流れ落ち、原告被告双方の弁論時間が、公正を期すため厳密に計られた。水の流れはしばしば、弁論以外の事務手続き時間を除外するため、また双方からの要請により、栓がされ止められた。
――ソクラテスの訴えられた罪状は、以下の三つだった。
一つ、国家の認める神々を信奉していない。
一つ、新しい神を導入している。
一つ、青年達を腐敗堕落させた。
この内一番目と二番目は、宗教裁判所に訴え出るための口実だった。そうでもしないと、アムネスティのくびきを突破出来なかったのだ。“敗戦”や“三十人”の思想的戦犯という理由付けでは、どうしてもアムネスティに抵触する。曖昧にぼかした、焦点を外した、告訴理由が必要だった。
問題は、三番目の罪状だった。ここでもまたアムネスティが邪魔をして、“敗戦”と“三十人”の二人の主犯、二人の不肖の弟子、アルキビアデスとクリティアスの名を具体的に書き込む事は出来ない。しかし仄めかすだけで、アテナイ市民なら誰でも彼等の名が念頭に浮かぶ。それが告訴人らの作戦だった。
その告訴人は、三人いた。主告訴人はメレトスで、他の二人はアニュトスとリュコンだった。この内メレトスとリュコンは殆ど無名の者で、ソクラテスもその名を知らなかった。
問題は、アニュトスだった。彼は、本業は皮革業を営むブルジョア層を代表する人物で、当時トラシュブロスらと並ぶアテナイの最有力者の一人だった。――以前、彼の息子の教育方針を巡って、ソクラテスと口論となったことがある。彼自身は、息子には自分の跡を継いで、堅実に実社会人として生きてもらいたいと願っていた。しかしソクラテスは、いつもの調子で俗世の生き方をバカにし、哲学的教養を身に付けさせる事を勧めた。だがアニュトスは、筋金入りのインテリ嫌いだった。典型的な中小企業経営者のワンマン・オヤジだった。だから、息子がインテリになって自分をバカにする事を、何よりも怖れていた。(実際の息子は、インテリになる代わりに、酒に溺れたダメ人間になってしまった。)――口論の果て、アニュトスがソクラテスに向かい、「君は軽々しく人の悪口を言い過ぎる。誰かの恨みを買わぬよう、気を付けた方がいいぞ」と捨て台詞を吐き、喧嘩別れとなった。その“誰か”が、言った本人となった。
アニュトスは、公私に渡る理由で、ソクラテスを陥れた。私怨については上記の通りだが、アテナイ政府を牽引する公職に付く身としても、“ソクラテス効果”を冷酷に計算していた。いまだ圧倒的力を保持する寡頭派、“三十人”の残党に対し、その精神的支柱ソクラテスを処刑することにより、強烈な“警告”のシグナルを発することが出来る、……。
瓶からの小さな滝が水面を打ち、ソクラテスの弁明が始まった。
開口一番、彼は、“この弁明中ワシは、どこまでも率直で正直であり続ける”、と宣言した。以降、弁明の間中、何度もこの同じ言葉を繰り返し、断り続けた。
――アテナイの民衆裁判で勝利するには、一定の技法があった。どこまでも庶民的な裁判員達を、納得させ、同情させ、いい気持ちにさせ、涙を誘い、共感させて味方に引き込む。友人リュシアスは、そうした弁論を創作する、法廷のプロだった。(盾工場を失い、口を糊するためプロ化せざるを得なかった、という事情もあるが。)ソクラテスに、裁判員達をものの見事に説得する弁論の草稿を書こうと申し出てきた。しかしソクラテスは、その申し出を断った。――せっかくの申し出、大変ありがたい。確かに君の書く名文なら、裁判員達を丸め込むのも容易だろう。しかしワシは、自分の流儀でやりたいのだ。その結果がたとえ、いつものように相手を怒らせることになろうともな。他人のものを借りず、ワシの流儀で貫く。それもまたワシの流儀だからだ。
彼は、この場での数十分間の言葉の固まりを、正真正銘人生最後の弁明にする積もりでいた。だから、他人からの借り物で事足りる訳など、さらさらなかった。全てを、自分流で通した。
敗戦以来口を噤まされた5年分の憂さを晴らすというところもあったが、それよりも、一世一代の、自らの考えと拠って立つもの、そしてその使命感の全てを、披瀝する絶好の機会だと考えた。だから、当たって砕けろの、文字通り最後っ屁の積もりで、異例中の異例なことだが、彼の側からだけ一方的に、喋りに喋った。アテナイの全てに向かって、素直に正直に、何も包み隠さず、思いっきり“弁明”し尽くした。
『お前は本当は、自殺したいんじゃないのか。ソクラテスよ』その時頭上から、裁判所の天井を突き抜け遥か天空から、不意にゼウスの声が落ちてきた。――見上げると、今自分達の演じている“法廷劇”の上空に、ゴンドラのようなものが浮かび、男が一人乗っている。ギリシャ劇で、デウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)という装置があり、神に扮した役者を機械で中空に吊るして出現させ神の裁定を下させる演出をするが、その装置である。
『お前は絶望のどん底に落ちている。神やダイモンがお前を裏切ったとすら思っている。――何か、言い訳があるかね?』男はさらに言った。――その口調には、聞き覚えがあった。彼の常連の、この五年間もっぱら彼と論争してきた、問答相手のものだった。普段の彼にどこか似ているが、遥かに辛辣で、手厳しく彼を問い詰めるそれだった。
“三十人”以降問答相手のいなくなった彼は、自分で自分に問答をつける癖がすっかり沁み付いてしまっていた。こうするしかなかったし、またいずれ再開されるだろう哲学活動を期して、トレーニングを積んでおく意味もあった。この、いわば自己内問答のもう一人の彼は、普段の彼より遥かに容赦が無かった。当然である、自分を相手にするのだ、何の遠慮がいるだろう。すなわち、普段のアテナイ市民を相手にした時の彼は、ユーモアを交えたり、下手に出たり、あれでも結構遠慮していたのである。
そのソクラテス似の、ヘチャな顔とズングリ短躯な老人が、ソクラテスの独壇場の法廷の長台詞に、神の如く割り込んでくるのだった。――壇上のソクラテスは、普段の彼の通り、平静で、快活で、高潔で、いつもの空っとぼけた態度を貫き通した。それは、不動心に到達した“大哲人”、一部の者の持つ彼のイメージそのままだった。――だが頭上からは、『そんなマヤカシで茶番の芝居、いつまで見せる積もりだ。白けるぞ』容赦なく裁きの声が降ってきた。
裁判員達や弟子達や、その他の多数詰め掛けた観客達相手に、変わらず演じつつ、ソクラテスは頭上を振り仰いで文句を付けた。「ワシが自殺したがっているだと? 神やダイモンを疑っているだと?――そこまで言うなら、ここへ降りて来い! 降りて、正々堂々と、決着を付けようではないか!」
だがゴンドラ上のソクラテスは、構わず喋り続けていた。『捨て鉢のお前は、死刑判決が出ようと、構わない気分なのだろう。いやむしろ、終焉を望む“自殺願望”すらある。その意味で、原告と被告の利害は一致している。――自暴自棄のお前は、これまでの全人生の自らの使命と思い込んできたものへの疑問と、それを与えた神やダイモンへの疑いで、心が膨れ上がり、はち切れそうなのだ。全てが終わっても、もう構わない、と思っている。七十歳の今から、やり直す訳にはいかないからな。もし叶うなら、死んで来世で人生をやり直せるのなら、そっちの方を選びたいというのが本音なのだろう?――否定できるか? ワシは、お前自身なのだぞ』
それらの言葉に滝の如く打たれ、いつもの彼にも増して、挑発的な言動、悪ふざけが過ぎる尊大さ、悪意ある皮肉、そうしたものが弁舌の随所に吹き出てしまう。それらを聞き、弟子達は今日の先生は何時になく絶好調だなと思い、告訴人達は怖気に凍りつつ憎悪をたぎらせ、裁判員や観客達は頻繁に唖然とさせられ度肝を抜かれた。
――――ソクラテスの弁明は、まず自己の立場の説明と、告訴者達を揶揄する批判の長広舌から始まった。続いて、国家の神々と新しい神を巡る、宗教論争が展開された。
主告訴者のメレトスが呼び出され、一問一答の相手をさせられた。たちまちメレトスは追い詰められた。――白日夢の中でお告げを下したり、注意を喚起したりするダイモンの事を、ソクラテスは以前から平然と公言していた。それどころか、その内容により、友人達に助言したり警告したりすることさえあった。告訴者達は、そこに言い掛かりをつけてきた。――メレトスよ。神々が、オリュンポスの山の上で痴話喧嘩をするというのか? イルカや、獅子や、人の姿をしているというのか?――それよりも、最も善であり、徳を湛えた“一者”を想像してみよ。“イデア”は、その一者の見る夢そのもの、とは思わないか。――とそこまで口に出掛かったが、言っても詮無い事と思い留まった。
次いで、青年達を腐敗堕落させた事の真偽が、俎上に載った。――自分は、“徳”と、“善き事”しか教えなかった。教えを受けた青年達が、その後それぞれどう成長するか。畑に植えられた苗の中にも、ほんの僅かだが、どうしても捻じ曲がって伸びてしまうものがあろう。『労働と日々』を書いた農民詩人ヘシオドスなら、これらの苗は間引いてしまうところだろう。だがアテナイは、これら捻じ曲がった苗を伸びるに任せた。間引く権限を持たない、最初に苗を植えた農民の罪が問えるだろうか。不可抗力ではないのか?
『懺悔したいのだろう? 心底では、取り返しのつかない罪に、怯えているのだ』またゴンドラ上から、チャチが入った。『たとえ良かれと思ってやってきた哲学の実践とはいえ、現実には告訴人らの言うように、若者らに悪影響を与え、ポリスに害を為す結果となってしまった、……。そう素直に認め、謝りたい気持ちで一杯なのだ、お前の本心は、……』――そんな事はない、そんな風には思っちゃいない。ソクラテスの哲学的自尊心は、ゴンドラの男の告発と真っ向から激突した。両者は、ギリギリと音を立ててせめぎ合った。――その時、裁判員の席に、クリティアスとカルミデスの顔が、見知らぬ者達に混ざり並んで座っているのが見て取れた。彼等はあの、こちらを冷たく見下す視線で、ソクラテスの有様をジッと見詰めていた。
――民主派の大衆が彼を影の戦犯と見做している事は、余りに自明だった。自分はどの体制にも批判を加えるアブのようなものだ、などと弁解しても、ポリスにとって耳障りなウザいアブを嫌悪し、アブの子供らのアブを越えたシビレエイの如き毒に半死半生の目に合わされた市民達に、どこまで通用するか。
それでもソクラテスは、いつもの彼のやり方、態度のままで、おちょくり、挑発し、皮肉を言い続けた。大人数を相手の演説に、段々声が掠れてきた。いつもは相手の目をジッと見据えて話す彼が、今日は壇上をグルグル歩き回ってせわしげに話した。しばしば、水時計を止めさせたり、証人を登壇させたりの、パフォーマンスを差し挟んだ。時たま、不意のめまいに襲われた。
――やがて、判決の時が来た。――そして、問答では告訴人らに圧勝の彼だったが、やはり票決は、280票対220票の僅差ながら、“有罪”と決した。
次いで、具体的刑の確定へと、審議は移る。原告側の死刑の求刑に対し、被告側は対案を出す事が出来る。死刑に対しては、国外追放か、多額の罰金が、穏当なところである。原告側も、国外追放あたりの落とし所を狙っていた。
『このままシオラシく、減刑を求める積もりか?――それでは余りに、お前らしくないぞ』票決が下るまでしばらく黙っていたゴンドラ上の男が、また騒ぎ出した。声が近いと思って見上げたら、いつの間にかゴンドラがほんの目の前にまで降りてきていた。もう一人の彼と、至近距離で目が合った。『やってしまえ! 言ってしまえ! お前が言いたくてならない事を!――舌の先まで出掛かって、ウズウズしているアレを!……』
とうとう、煽られるまま、最後の最後、ソクラテスは最大級の“ソクラテス流”をブチ上げてしまった。死刑に代わるべき、自らに科される刑罰は、『国家迎賓館での饗応』こそが相応しいと、言い放ったのである。『国家迎賓館での饗応』とは、外国の使節であるとか、武勲を立てた将軍であるとか、オリンピック競技の優勝者であるとかを、国家迎賓館にてその栄誉を讃えもてなす事である。つまり、ポリス共通の価値観の、最高の栄誉と賞賛こそが自分には相応しいと、ブチ上げたのだ。――これには、本来なら『国家迎賓館での饗応』に相応しい六人の提督を死刑にした民衆裁判への、悪意ある当てこすりが隠されていたのだが、裁判員達がそんな意図に気付くべくもなく、蜂の巣を突付いたようなざわめきが何時までも裁判員席を右へ左へと往復した。
『やった。やっちまった。とうとう言ってしまったぞ!』ゴンドラのソクラテスは、有頂天だった。『ブラボー!――よくやった、ソクラテス。――それでこそお前だ、我が片割れよ!』
――だがこの時は、さすがに邪魔が入った。ソクラテスの友人達が、騒ぎ出したのである。彼等は、そんな悪ふざけはやめてくれ、我々が一緒に金を出すから、罰金刑に提案し直してくれ、と言い立てた。
「済まんが、水時計を止めてくれ」ソクラテスは議事進行の時間を止めさせ、友人達の方に歩み寄り、彼等と話し合った。
やがて、折り合いが付いた。彼等の切なる願いに折れ、罰金刑に提案し直したのである。――その金額は、銀貨にして三十ムナ分だった。
再度票決が行われた。結果は、360対140で、『死刑』。無罪に投票した筈の裁判員の内80人が、今度は『死刑』に転じた。ソクラテスの度を越した悪ふざけが、とうとう彼等の堪忍袋の緒さえも切った。
判決後、ソクラテスはすぐ拘束され、牢に連行され、足枷をはめられた。足枷は鎖に繋がれ、その鎖はまた床に打ち込まれた柱に結び付けられていた。牢獄は、アゴラ南西部少し離れた位置にある。あの駐留軍時代、スパルタ兵が頻繁に行き来していた通勤路のすぐ脇である。
牢の数は、十に満たない。アテナイの刑罰は、罰金にせよ、追放にせよ、死刑にせよ、いずれも即刻執行されるものばかりで、『禁固刑』というものがないからである。ソクラテスの一ヶ月という拘留期間は、例外中の例外だった。その理由は、既に書いたように、デロスに派遣された祭典使節団の帰国を待ったためである。その一ヶ月という偶然が、彼の哲学に、そして全人類史に、思いもよらぬ新展開をもたらすこととなる。
クリトンの鼻薬のおかげで、プラトンら弟子達が、頻繁にソクラテスの牢を訪ねるようになっていた。暗い牢内が、さながら賑やかな教室と化した。
その最後の授業の間中、彼は、弟子達の不思議な高揚感に気付いていた。勿論、彼の刑死を、深く悲しんではいる。なのに、不思議な熱気がある。師の死が、何か研ぎ澄まされた崇高なものに、彼等には感じられているようなのだ。――こうした異様な熱気は、詩人志望のアポロドロスが、師の死に奉げるヘボい詩を素っ頓狂な声で歌い上げた時、遂に最高潮に達した。
『自らの哲学に殉教された、不屈のヘラクレスよ
これほど美しく、呪われた死の宣告に耐えた人は、世界のどこを見渡してもおるまいて
彼が、生涯準備をしてきた死、立派な死、幸福な死、神に祝福された死
偉大な精神力を天下に示し、不朽の名声を勝ち得た
不正を加えた者と、不正を加えられた者と、どちらも名を残す、人の心に残す、まるで逆の意味で
死こそが、最も強靭な石に永遠の彫り跡を刻み付ける、“ノミ”なのである(ワシの本業を讃えて、そう歌ってくれたのだろう。)』
どうやら弟子達は、ソクラテスの捨て鉢な自殺を、使命感に導かれての崇高な殉教と、美化してしまったらしい。何という、勘違いだろう。しかも、プラトンらによると、既に牢の外、市壁の外の文化人達にまで、そんな思い込みが浸透し出しているということだ、アポロドロスのヘボい詩と共に。何しろ、皆が“顔見知り”といっていいような、狭い世界のことである。
ヘーラクレース!
ヘーラクレース!
アポロドロスの朗読以来、その野暮ったい強靭な身体から、死して清らかなプシュケーへと(蝶の如く)脱皮したヘラクレスに倣って、牢獄の中では、師の事をそう呼び讃える歓声が、ひと頃飛び交いやまなかった。その都度、ソクラテスの講義は中断された。
この祭りの飾り付けのような馬鹿騒ぎは、一体何だろう。あの裁判での選択は、逆効果だったか。このまま死を以って祭り上げられてしまえば、著作者の既に死んだ本と同じだ。何も言えない本は、どのようにでも解釈されてしまう。いやワシの場合、自ら書き残した本が一冊も無いから、ますます始末に悪い。
熱に浮かされた弟子達が、夕刻の西日に急かされるように引き上げると(ソクラテスの房は建物の西側にあり、壁の高い位置に明り取り用の小さな窓があった)、一人ぼっちとなった彼は、オリーブ油の灯心一本のみの僅かな明かりの中で、物思いに耽った。
元々跡に何も残す積もりのない、アゴラやギュムナシオンでのワシの全否定のアドリブ芸哲学。何にでも“ノン”と言う、天邪鬼、皮肉屋のトリックスター、騒がし屋の道化奇人。盟友アリストファネスらの書いた喜劇と同根だが、彼等のそれの方が書き物として残る分、寿命は遥かに長い。
……筈だったのだが、――シモンの『靴屋風』以来、状況が一変した。加えて、今回の滑稽な刑死が、致命的な程の豪雨を降らせ、この流れを奔流に変えつつある。
『ならば、“脱獄”してしまえばいいではないか』鎖に繋がれたもう一人のソクラテスが、寝台の向こうから彼に話し掛けてきた。――この男も、彼と一緒に、ここまで連行され、足枷をはめられ、鎖に繋がれた。混み合った“貧者”のシュンポシオンでは、複数の者が一台のクリネーに雑魚寝するが、今では狭い寝床に同衾する仲である。『決心一つ変えれば、“崇高な死”だの“哲学のための殉教”だの、それら全てを“チャラ”に出来る。――元々が、“どうにでもなれ”という思いで臨んだ裁判だろう? 刑死にこだわる理由など、義理立てする借りなど、何も無い。全く同じ“どうにでもなれ”で、“脱獄”してしまって、さらさら構わない理屈だ。いやむしろその方が、過去の自分を全否定できる、かなぐり脱ぎ捨てられる。そのための、いい契機とすらなるだろう』
近頃頻繁に現れるこの男、知恵の者ダイモンの化身などとは到底思えない。そこでソクラテスは、ある伝承に辿り着いた。かつてアンドロギュノス(両性具有者)の居た時代、人間は、腕も四本、脚も四本、顔も二つで、二倍の体躯を誇っていたという。それが、神の裁きにより、二つに裂かれたとのことだ。そして、裂かれた片割れを本能的に求めると、伝承は付け加えている。――クサンティッペを愛しく思う時、この者こそ我が片割れかとの思いを強くするが、しかし若く可愛らしいクサンティッペが元我が半身であったというのはどうにも理屈に合わぬ。それより、アンドロギュノス以外にも、“男・男”、“女・女”の取り合わせの人間も太古には居たそうである。ならば、こやつこそ、その片割れではないのか。ここまでしつこく付き纏われると、そう思えてならなくなる。
「いや、待ってくれ!」ソクラテスは、もう一人に反論した。「あれほど裁判員らと敵対者の前で、大見得を切ったのだ。人民裁判の愚かさに、また大きな汚点を一つ残すことに成功したのだ。それを今さら、取り消すというのか? もし今脱獄するなら、あの量刑の時国外追放を選べば良かった事になる。どちらにしろ、結果は同じだった。むしろ、追放の方が合法で、それを今さら脱獄すれば、余りにみっともない違法行為だ。合法的に出来る事を、後で“心変わり”して、わざわざやり直したことになるのだからな。――奴等を持ち上げ、自分を貶める。そこまで、――哲学どころか、おのれのプライドや人格まで、――貶める勇気が、ワシに本当にあるのか?」
『おっちょこちょいな弟子達の、浮かれぶりを見ただろう』彼そっくりの片割れが、宿命のように言い返してきた。『あの見当違いにくすぐられてのむず痒さ、居心地の悪さに、これ以上耐えられるか?――戸惑ったり、不快に思ったりだけで済むなどと、気楽に構えてちゃいかん。早く正してやらんと、連中とんでもない所へ突っ走っていくぞ! クリティアスやアルキビアデスの、二の舞だ、……』
彼の心は揺れ動いた。日々、時々刻々、毎分毎秒、脱獄したものか、潔く死を迎えようか、思いがコロコロ入れ替わった。もう一人の自分と、次々立場をとっかえひっかえ、論難し尽くした。――弟子達と接する時は、あの裁判所の壇上での彼と同様、彼は非の打ち所のない“大賢人”だった。冷静で、明晰で、迷いの無い、誰からも後ろ指の差しようのない、今までと(この三十年間と)寸分変わらぬ“教師の鑑”だった。――だがその内幕では、延々自らと問答をし続けていた。脱獄するべきか、思い留まるべきか、それが問題だ。
《ソクラテスの足に巻き付いた枷を繁々と見下ろしつつ、「そいつが、……その足枷が、ネックなのだ」クリトンは深く溜め息を漏らした。
既に二十日以上の日々が経過していた。使節団の船が例年通り戻るとしたら(嵐などで船足を邪魔されなければ)、残りの日はあと十日もない。本来なら、ゆとりを残して、とっくに脱獄が完了していなければならない頃だった。
「そいつの鍵が、あれほど厳重に管理されているとは、正直思わなかった。昼も夜も、刑務委員の控え部屋に掲げられ、衆人環視の下に置かれているのだ。十一人の刑務委員と獄吏達、それに保管場所に立ち入る可能性のあるアルコンや役人達全員を買収しなければ、手に入らん。手に入っても、すぐバレる。――そんな事は、無論到底無理だ」クリトンは、ここでもう一つ、深い深い溜め息をついた。「さりとて、鍵無しで脱獄しようとすれば、その鎖を断ち切るか、繋いだ柱を壊すか引き抜くか、しなければならない。当然とんでもない音がたち、たちまち獄吏が駆け付けよう。――それとも、君の足の方を切ってしまおうか? それなら、大して音はたたんだろう。君が大声を上げなければ、だが、……」
「別に足の一本くらいは構わんが、……」とソクラテス。言いつつ、思った。クリトンが気安く請け負った脱獄計画だったが、いざ実行となると、具体的な暗礁が次々立ち現れ、大分難儀しているようだ。まだ脱獄すると決心したわけではないソクラテスだが、さすがに不安になってきた。選択肢の一つが潰され、選びようもなく未来が決定される、……。
「そこで、だ」話を切り替えるようにクリトンは、既にはずせないとわかった足枷から目を上げ、腰帯に挟んだ布袋から何やら取り出して、ソクラテスに見せた。「これを使おうかと思う」一本の、枯れ草だった。それを指先に摘んで、クリトンは掲げた。
「何だ? それは」ソクラテスは問うた。
「かのシモンの見付けた薬草だよ。強力な睡眠作用のある、……」
ソクラテスはその枯れ草を、ジッと見詰めた。工人仲間の盟友靴屋のシモンは、過度の飲酒がたたって既に他界していた。彼の遺産の一つのようだった。
「足枷の外される日が、ただ一日だけある。それは、いつだと思う?」とクリトン、少々おどけた調子で。
「さあ、――いつだったかな」これが外されるなんて事が、あるのだろうか。ソクラテスは悲しげに自分の足許を見遣った。
「死刑執行の日だよ」嬉しさと悲しさをない混ぜにしたように、クリトンが種明かしした。「死刑囚への温情で、当日の朝、外される筈だ。そしてその夕刻、刑は執行される。つまり最後の一日の、日の出ている間、安楽にさせてやろうという配慮だ。大抵の死刑囚は、その日一日、家族や友人や娼婦達を交えて、飲めや歌えでこの世の快楽を味わい尽くそうとする。まあ、快楽に溺れれば溺れる程、この世への未練は募るばかりで、最後はみっともない死に様を晒すわけだが。
だが君には、大宴会を楽しんでいる暇など無い。この時こそ、一世一代大勝負の時で、大忙しであろうから」
「待ってくれ」とソクラテス。「とすれば、――真っ昼間、それもアゴラが商売人達の掛け声で一番賑やかな時間帯に、脱獄する事になるじゃないか。――いくらなんでも、そりゃ無茶だよ」
「そこで、これさ」再度、枯れ草を摘み上げ、悪戯っぽく笑った。「最後の日、警備側には囚人達の馬鹿騒ぎを大目に見る習慣もあり、緩みが出る。加えて、――忘れちゃあいないか?――使節団の船が帰国するから、君の刑は執行されるのだ。市中も、使節団の帰国を祝して、長い厳粛な祈りの期間が無事終わってホッとして、やはりお祭り騒ぎの一日となるのさ。つまり、牢の内でも外でも、ポリス中が馬鹿騒ぎの一日なのだ。
少々突飛な策だが、そこでその馬鹿騒ぎに、こいつを一服盛ろうという訳だ。無論獄吏や刑務委員らにも、我々のシュンポシオンの振舞い酒を受けて味わってもらう。――結果、アテナイの街の殆どが、しばらくの間“シエスタ”に落ちる、……」
何とも大胆な計画過ぎて、ソクラテスは友の顔を見詰め唖然とした。彼一人の、人知れず決行される筈の脱獄が、ここまで大事になろうとは。
「呆れたよ。余りに大風呂敷過ぎて、……」そのドングリまなこを大きく見開いたまま、クリトンに言った。「君には、喜劇作家の素養があるな。それじゃまるで、アリストファネスあたりの書きそうな喜劇を、地で行く話じゃないか」――寝床の向こうではソクラテスの片割れが、アリストファネスの観客よろしく、喜び呆れ、大笑いしている。
シモンの捏ねた薬草は信用おけるとしても、そこから展開されるアテナイ全市を舞台とした大喜劇は、どうにも現実離れしていると思われた。そこで、言った。
「それに、ワシは、……」
「何だ?」と、水を差されたクリトン。
「ワシは最近思うのだ、……。脱獄というのは、自殺と同じなんじゃなかろうか、と」
「どういう意味だ?」虚を突かれたクリトンが、膝を乗り出した。
「もしオルフェウス教あたりが言うように、肉体がプシュケーの牢獄だとしたら、この世で生きるとは、神の下したもうた“刑罰”、ということになる。従って自殺とは、“神の牢獄からの脱獄”以外の何物でもない。だから自殺は、最も忌むべきものなのだ。
――としたら、その逆も言えよう。“脱獄”とは、自殺と同等に、最も忌むべきものなのではないか? 自殺自体は、簡単に出来るよ。つまりそこにこそ、神の罠があるということだ。脱獄を容易にし、我々に自由に選ばせているのだ、罪を償うか、逃げ出してより多く罪を重ねるか。――だから、たとえ脱獄可能だとしても、脱獄それ自体、自殺と同等の、“悪”ということになる。
そんな考えが、近頃頭に居座って、離れんのだ」
「この期に及んで、まだそんな事を言っているのか!」呆れたようにクリトンは、友を叱咤した。「君を牢獄にぶち込んだのは、――神ではない。アニュトス一派と、大衆の裁判員どもじゃないか!――それに、神は肉体という牢獄にプシュケーを収監し続けるとしても、アニュトスらは君を閉じ込め続ける気など無い。命を絶とうとしているのだ。その相手の思惑にウマウマ乗ってしまうのは、――それこそ“自殺”そのものじゃないか。
――いい加減で、決断してくれ!」
友に責められ、詰め寄られ、ソクラテスはクリトンを疲れたような目で見返した。――クリトンは続けた。
「既に仲間達が、この薬草を入手しようと山野を駆けずり回っているんだ。特にクサンティッペさんは、草木に詳しいから、先頭に立って薬草探しを指揮している。――それを、何を今さら、……」
あの甘えん坊で癇癪持ちのクサンティッペが、男どもの先頭に立って活躍しているとは! ソクラテスは、妻の躍動する姿を思い浮かべると、もうそれ以上の事は言えなくなった。
明り取りから西日が消え、その日も暮れようとしていた。》
先程壁沿いの研究室に消えていった学者が、再び姿を現した。大きな荷物を背負っていた。カリマコスと、目が合った。しばらく迷った風な様子を見せたのち、彼は言った。「……、見逃してくれ」
懇意にしている、解剖学の医学者だった。どうやら密かに、ムセイオンから出て行くつもりらしかった。
「アリストテレス師の建てられたかのリュケイオンなどの自由な気風に較べ、ここはあくまで“王立”の学問所だ。確かに生活環境は恵まれているが、何かと口うるさくて制約も多い。我々は王の威信を誇示するためのお飾りに過ぎず、気まぐれな王の顔色を伺って日々暮らさねばならん」学者は愚痴をこぼした。
ムセイオンの会員として王に認められれば、食住は保障され、金銭の給付を受け、おまけに免税された。学問をする環境は整っていた。だがそれは、同時に王の管理下に入ることを意味した。カゴの鳥状態を嫌って、脱走を試みる者はしばしばいた。円満に脱退できればよいが、王の機嫌を損ねた上強引に逃亡しようとして、捕えられる者もいた。先日もある学者が、王の寵愛を撥ね付けた上ライバルの王国の図書館に再就職しようとし、逃走の途中捕えられて処刑された。そんな事を思い出し、カリマコスは危惧の念を抱いた。
「アリストテレス師の父は医神アスクレピオスを祭る“国境を越えた医師団”の一員で、師もまた子供の頃から解剖学の手ほどきを受けていた」見詰め合ったまま、学者は不満を並べ立てた。「それを、この巨大な伽藍堂に巣食う無知な似非学者どもは、我等解剖学者のことを「医者ではなく、まるで肉屋だ」などと陰口を叩きおって!」思い付く限りの不満を、上ナイルの大滝の如く早口でまくし立て、止みそうもなかった。「王もムーサの神官達も、甘ったるい詩ばかりがお好みで(おっと失礼、司書殿も詩人でしたな)、実学には目を向けようとなさらん!」
散々に喋り散らした後、深く目を伏せたまま、学者は足早に立ち去った。
*
図書館の書棚には、『魂の癒しの場所』と刻印されている。エジプトの図書館の伝統に則ったものである。
さらに書棚の上に、著作者の胸像が、名前入りで据えられている。誰の作品がどの書棚にあるか一目で分かる、という工夫である。
目の前に並ぶ胸像群に、いつしか視線を奪われていた。
“フーム。出来は、イマイチだな。”出来栄えには、やはりウルサイ。ついつい、自分や父親の基準で、彫像を評価してしまう。ソクラテス家の工房の半端な石像と違い、こちらは全て完成し、しかも大きさといいスタイルといい均質に揃っている。
さっきから、見覚えのある顔が並んでいた。――プロタゴラス。プロディコス。ゴルギアス。ヒッピアス。パルメニデス。ゼノン。アナクサゴラス。テオドロス。…………
プロタゴラスとは、カリアス邸で、ヒッピアスやプロディコスも交えて、盛んにやり合ったな。重厚で、心に残る議論だった。
エレア派のパルメニデスにゼノンと話したのは、パンアテナイア祭の時のことで、ピュトドロス家でだった。これも、印象深く、思い出に残っている。
他にも、名前だけの確認だが、イオニア学派のタレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス、ピタゴラス、クセノファネス、ヘラクレイトスといった、古人達の胸像が並んでいた。
アテナイは、哲学後進地だった。――哲学はむしろ、イオニア、南イタリアといった、植民都市で発達した。それは、植民都市が自由な気風に溢れていたのに対し、ヘラス本土は古い部族の因習に縛られ沈滞していたからである。
ペルシア戦争が、こうした流れを逆転させてしまった。ペルシアに蹂躙されたイオニアは衰退し、反対に戦争に勝ち抜きデロス同盟の盟主となったアテナイは、繁栄の頂点を迎えた。
経済的富は爛熟したが洗練された知性では空白地帯のアテナイは、あたかも二千数百年後の某国の如く、ヘラス全土から名だたる学者、思想家、芸術家達を引き付け、アテナイは文字通り思想の坩堝と化した。アテナイのアゴラに突然生じた論壇は、とてつもなく騒がしく、戦闘的で、扇情的で、このアゴラの周囲だけで、全世界のほぼ総ての事が済んでしまう、と思える程だった。
民主制を指導した大政治家ペリクレスは、アナクサゴラスの影響で自然哲学の素養を積んだ。そして自分の弁論にもそれらを多く取り入れた。アナクサゴラスは、隕石という事実から、天体について新しい考えを持った。太陽を灼熱した金属、月を土くれの塊とした。月には丘や谷があって、居住可能と説いた。二千年後、ソクラテスに似た風貌の団子っ鼻の男が、ガラス玉を通して物を見る方法で、これらの事を確認した。若い頃のこうした流行が、ソクラテスにも影響を残した。
金銭と知性を等価交換する風潮が、金満家のアテナイ上流市民の間に蔓延した。ただ、等価交換のレートは、はなはだ主観的だった。アテナイの巨万の富が(といってもその多くは、デロス同盟の他ポリスから搾取したものであったが)、知性の教授と引き換えに国外流出した。
こうした中で鍛錬されたソクラテスは、純アテナイ産の最初の哲学者となった。
ソクラテスは、それら顔や名前を見知った人々の胸像の置いてある一画を見渡し、溜息をついた。――20ペーキュス(約10m)四方程の片隅に、彼の知っている全ての思想が収まっていたのだ!――この図書館の全収容面積に対し、この、歩いて数歩で通り過ぎてしまう程度の領域は、余りに狭い!――これをワシは、“全世界のほぼ総ての事が済んでしまう”総量だと、勝手に思い込んでいたのか!?――だとすれば、これこそが“目に見える無知”というものだ。
胸像群の中に、ソクラテス自身のそれはなかった。――当然である。彼は、何も書き残さなかったのだから。
その代わり、ごく身近に接した弟子や仲間達の顔が幾つもあった。アイスキネス、エウクレイデス、シミアス、クセノフォン、パイドン、アリスティッポス、アンティステネス等々。――ただし、そのどれもが、彼の知っている面影よりも随分と“老け顔”だった。
そんな胸像の一つが、ソクラテスに話し掛けてきた。「先生ではありませんか。――大変御無沙汰しております」よく見ると、アリストン三兄弟の末弟、アリストクレスだった。彼は肩幅が広く立派な体格をしていたため、“プラトン”とあだ名されていた(『プラテュス』は“広い”の意)。――ただし、ソクラテスの知っているプラトンはまだ二十代の青年だったが、胸像の彼は壮年期の重厚な面構えをしていた。「そのお姿。――一体どうなされたのですか?」胸像は続けた。
手の中で握り締めていたパピルス片に気付き、「聞いてくれたまえ、プラトン君。――実は、これなのだ」それを広げて胸像に見せつつ、ソクラテスは説明した。――生涯に渡っての神託のこと。ここが、死刑執行の前夜の夢の中であるらしいこと。自分は今ここで、大図書館のカリマコスという司書に生まれ変わり、書物を読み続けることに日々追われて暮らしていること、などなど……。
「フーム。――先生の生涯を賭けるに値するムーシケー、ですか。――それはまた何とも、大きなテーマですね」大理石像は、少年の頃の面影を覗かせながら、物思いに耽っている様子だった。
大理石像が押し固まる様を見て、ソクラテスはあわてて話題を変えた。――いずれこの問題については、随分と立派になったプラトンから再度意見を聞きたいが、今は別の関心事を聞き質したくてならなかった。――それは、彼はあの後、目覚めてから刑死したのか、それとも脱獄を果たしたのか、そうした彼自身の行く末についてだった。
「先生は、毒杯を煽られ亡くなられました。見事な御最期でした」プラトンは即座に答えた。
ソクラテスは、軽い衝撃を受けた。自分は、脱獄を断念したのか? それとも、失敗したのか?
「さあ。それは私には、分かりかねます」ソクラテスが恐る恐る尋ねると、プラトンの石像は意外だという風にぎこちなく首を捻り、「脱獄計画のあった事は私も承知していましたが、先生はその誘惑を敢然として突っぱね、見事な死を選び取られたのです。――ですから、それ以外の可能性について尋ねられても、私には知りようがありません。ただ先生の立派な御最期が、アテナイに見事な“哲学の花園”の季節を到来させたという事実しか。――それが、いわば『正史』とでも呼ぶべきものなのでしょう」
“正史”か。――ソクラテスは、口の中に何か苦い味を感じながら、その言葉をじっくり吟味した。――あの、“崇高な死”だの“哲学のための殉教”だののもたらした結末が、この“正史”とやら呼ぶべきものなのか?――そう断言されてしまうと、へそ曲がりなソクラテスは、ますますそれが気に入らなくなった。
ならば、その“正史”とやらでは、その後の哲学やアテナイの情勢は、どういうものになったのだろうか。プラトンは今さっき、『哲学の花園』という表現を使ったが、……それは、如何なるものか。――ソクラテスは、円熟した姿となった弟子に問うた。
プラトンの胸像は、書物の幾巻かを紐解くよう、ソクラテスを促した。それらに書かれた記録に沿って、プラトンは説明していった。(書物を読むより、君と話がしたいのだ、とソクラテスは言ったが、プラトンの胸像は、私はただの石の彫り物に過ぎません、私の話す言葉は、すなわちそれらの書物に書かれている事です、と答えた)
「先生の刑死後、敵方からソクラテス派と呼ばれた我々は、まあアテナイでは毎度のことですが、文字通り蜘蛛の子を散らすように、国外に亡命いたしました。外国出身の方々は当然祖国に帰り、パイドンもまたアテナイを捨て故郷エリスを目指しました。私も、数人の仲間とともに、メガラのエウクレイデスさんを頼って、ほとぼりが冷めるまでそこに身を隠しました。
その後アテナイでは、あなたの刑死を巡って、議論が大きく二つに割れました。――割れるならば、本来は判決を下す前に割れて、大いに討論すべき筋合いなのに、何でも早とちりで軽率に決めてから、後で後悔して大論争となる。これもまたアテナイでは、毎度のことです。今までに何度も、同じ事を繰り返し、失敗して、それでも学ばないのが、アテナイの民主主義というものでしょう。
先生を告発したアニュトス等に次いで、その5、6年程後、ソフィストのポリュクラテスが先生を批判する文章を発表して、アテナイで話題となっておりました。そこで、ぼつぼつアテナイに帰還しつつあった我々の間で、アニュトスやポリュクラテスに対抗して、先生の弁護をする著作を世に送り出そうという機運が高まっていったのです。
先生の真実の人となりと思想を世に知らしめるための作品で、シモンさんの『靴屋風』を真似て、皆“対話形式”の形を取りました」
「『靴屋風』? みんなであれを、書いたのか?」
「ええ。
私も、パイドンも、クセノフォンも、シミアスも、ケベスも、グラウコンも。――アイスキネスも、アンティステネスも、アリスティッポスも、エウクレイデスも。
クリトンさんも、書きました」
「クリトンまでも、か」創作活動などとは到底縁がないと思っていた幼馴染の名が突然上がったので、ソクラテスの鼓動は瞬間小さく跳ねた。
「総数では、300篇以上にもなると言われています。巷に溢れ出たこれらの情報量に圧倒され、遂にアニュトス、ポリュクラテス等は沈黙しました。そして気紛れなアテナイ市民達は、悪びれることもなく、今度はアニュトス等を追求し始めました。アニュトスは苦しい立場に追い込まれ、主犯のメレトスは妙な因縁をつけられて、とうとう刑死するハメになりました」
「奴等、アテナイ民衆の犠牲になったか。――人を呪わば穴二つ、かな」
プラトンの勧めで、数多い『靴屋風』の中から30篇程を抜き取り、閲覧机に並べてみた。巻物もあるが、後代の写本ほど、獣皮紙製の冊子状の本が数多くまぎれている。シモンのそれよりも洗練されてはいるが、間違いなく同じ造りである。
「何とも、いやはや、――」というのが、ソクラテスの感想の第一声だった。「ワシは一体、何人いるんだ?」
弟子達に映る自分が、その弟子一人一人によって、まるで違う姿である事を、ソクラテスは知った。――部分部分は似ているようでもあるが、それらをトータルすると、とんでもない怪物と化してしまう。
アンティステネスの対話編のソクラテスは、あらゆる快楽や贅沢を嫌い、ボロ服のみ身に纏い、それを洗濯もせず自身の体も洗わず、大瓶の中で暮らしていた。僭主が瓶の中の彼を覗き込んで、何か望みは無いかと問うたところ、日が当たらないからそこをどいてくれと答えたという。外出する時は裸足で、頭陀袋を背負い杖をつき、クズ拾いをしながら歩いた。犬の食べ残しのパン(シュンポシオンから掃き出された)をあさり、最後は生のタコを食べて当たって死んだ、となっていた。アンティステネスは『禁欲主義』を唱え、キュニコス派(犬儒派)の創始者となった。
アリスティッポスの作中の師は、それとは真逆に、陽気ではつらつとした大人(たいじん)で、御馳走や恋を追及することに人生を費やした。そんな師は、アテナイ一の人気者であった。アリスティッポスは、キュレネ派を開いた。
エウクレイデスの対話編の中の彼は、一転して、氷のように冷徹で、論理に執拗にうるさく、舌鋒鋭い論争家、として描かれていた。ヘラス中を行脚し(本物のソクラテスは、終生ほとんどアテナイから遠出した事がなかった)、行く先々の問答大会で連戦連勝、問答チャンピオンの名を欲しいままにした。エウクレイデスは、メガラ派の開祖となった。
クセノフォンの彼は、すっかり毒気を抜かれた“良いオジサン”になっていた。高徳で凡庸な教師、そのものであった。
そしてプラトンの対話編中の彼は、…………。
「プラトン君。――君の『靴屋風』の中のワシは、まるでピタゴラスの生まれ変わりのようではないかね。――何でこうまで『プシュケー』だ『不死』だを、連発せねばならぬのか」ソクラテスは愛弟子にクレームをつけた。
――いつしか、プラトンにつられるように、他の胸像達も次々勝手にお喋りを始めていた。そしてソクラテスに向かって、「先生。私の書いた先生こそ、最も先生の真意を伝えているものです」「いや。私の描いた先生こそが、生前の先生のお姿に適っている」「この在り様を支持すると、一言仰って下さい」「先生が世に示した生き方とはまさしくこれであると、お認め下さい」と、賛同を求めてくる。
丸写しのシモンから始まって、これ程までに多種多様なワシに分岐するものなのか。アゴラでのワシの即興劇は、人々にどう受け止められていたのだ?――だから、“書物”というのは“剣呑”なのだ。これでは、ムーシケーを創るどころか、自分が粗悪なムーシケーを量産するための、材料とされてしまう!
書き物により後世に伝わるワシとは、一体何者なのか?――総てを否定し跡に何も残さない筈の“無知の芸”が、本人の思惑にまるで反して、弟子達により記録され、固定化され、勝手に拡散発展し、次々と新規の哲学、弟子の弟子達、を生んでいく。弟子それぞれの、都合の良いソクラテス像が、広告塔として使われ、ソクラテス・ブランドとして確立し、弟子達間での“正統”争い、跡目相続の抗争が激しさを増していく。
これが、プラトンの言う『哲学の花園』なのか? “正史”のもたらしたものなのか? ソクラテスはますます、その“正史”とやらを全否定したくなってきた。
――「先生。お許し下さい」プラトンの胸像が弁解した。「これら私の著作には、先生が亡くなられてからの私の長い哲学遍歴が、抗いようもなく影を落としているのです」
「確かに。ワシが死刑判決を受けた時、君はまだ三十歳にも達していなかった」優しく許すように、ソクラテスは言った。「君はワシの弟子の中でも、最も若手の部類だ。ワシの死後も、長く哲学の道を歩む人生となった事だろう。――ピタゴラスの影響が色濃いということは、ピタゴラス派の人々と接触する機会が出来たのかね?」
「ハイ。アテナイ市がまだ政情不安な頃、私は積極的な外遊を志しました。三十代の、十年程の間です」プラトンの胸像は、遠くの思い出を引き出すように、ムセイオンの高い天井の薄暗がりを見詰めた。そして、話した。「まず、北アフリカのキュレネ、次いでエジプトへと渡りました。古い世界の知恵を、学ぼうと思ったのです。エジプトでは、土地のエジプト人、居留しているヘブライ人など、多くの民と、その思想・学問で、交流する事が出来ました。
分けてもヘブライの民は、多くの新規な発想を、私の哲学にもたらしてくれました。彼等の高潔で不思議な、絶対の唯一神。預言者らの口を突いて出た、膨大な啓示。熱と色艶のこもった、多様な文学。カドモスやタレスなどのフェニキア人は、かつて多くの東方の知恵をヘラスにもたらしましたが、同じカナンに住むヘブライの民も、古い知恵の宝庫と思われました。私は、彼等の神の名を使い物語を書くなど、この地で仕込んだ種を自らの哲学や著作の中で大いに開花させました。いずれこの返礼は、我々の哲学という形でお返しされるべきでしょう。そうやって、シーソーの如く、両者が互いに影響し合いながら発展できたら、人類の全英知の積み上げにどれほど貢献できることか、この上もなく喜ばしいことです。
さらにカナンを通ってペルシアにまで抜け、かの地のマゴス(呪術師)達にも会おうと企てましたが、折悪しく騒乱が起こり、この計画は断念しました」
ソクラテスはしばし、愛弟子の壮大な冒険に思いを馳せた。彼自身は、ヘラスはおろか、アテナイからすら殆ど出た事がなかった。彼に伍する思想家達は、向こうからやってきた。アテナイにいれば、対峙する相手に不足することはなかった。だがしかし、旅行家や探検家のように、話にのみ聞く地に自ら赴くというのは、哲学的喜びとはまた違う、知的好奇心を大いに掻き立ててくれる企てであった。それを実行したという若い弟子が、すこぶる羨ましかった。エジプトやカナンやカルデアやペルシア、そこには一体どのような知恵や学問が息づいている事だろうか。
「さらに、地中海を渡り、南イタリアやシケリア(シチリア)へ向かいました。ピタゴラス派の人々と交流したのは、かの地においてです」
そうしてプラトンは、しばらく押し黙った。――ソクラテスは、話がこれで終わってしまうのではないかと、少し不安になった。が、杞憂だった。
「彼等からも、大変多くの事を学びました」プラトンは話を再開した。「彼等はポリスで、学園を運営しておりました。規模の大きな学び舎でした。そこで、ピタゴラス派の徒を、育成していたのです。――さらに、ピタゴラス派の者が、ポリスの政治にまで積極的に参加していました。政治に、哲学を持ち込んでいたのです」
プラトンの示す書物を読み進めながら、ソクラテスは少なからず身震いした。政治への介入を極力敬遠していた彼の愛弟子が、その禁を破り飛翔しようとしている。――既に鬼籍に入ってしまっている自分には、その事をとやかく言う資格はない。ただそっと、彼の行く末を見守ってやることしか出来ないのだ。
「40歳の頃、アテナイに帰った私は、ピタゴラス学派を真似て学園を開設してみようと思い立ちました」胸像は続けた。「ギュムナシオン(公共体育場)を間借りして、学園は始まりました。ピタゴラス派の学園のように、専用の施設を建てる資金は到底ありませんからね。幾つかあるギュムナシオンの内、アカデメイアの森にあるそれを選びました。他のギュムナシオンがアテナイ市城壁のすぐ外にへばり付くようにして建っているのに対して、アカデメイアだけは市域から離れた所にある。周囲は神域だし、途中をケラメイコスの共同墓地に隔てられているのもいい。ケラメイコスには、先生の造られた石像もありましたね。静かな環境で、学究の地にはもってこいでしょう」
「アカデメイアの森か。それはいい選択だ」ソクラテスも、賛意を示した。「ワシもあそこには何度も出向いて、若い連中と問答を交わしたものだ。レスリングの取っ組み合いも、よくやった。集会部屋も浴場施設も充実しておる。とりわけ、市域から隔てられているので、余計な邪魔が入らない」
「お褒めいただき、光栄です。――学園の運営は順調に運び、多くの子供達、若者達を育み、優秀な人材を排出することが出来ました。
学園の近くに小さな私邸を構えまして、昼は学園で教育、夜は私邸で執筆といった具合に、充実した後半生を送る事が出来ました」
そうした“夜の慰み”が、多くの『靴屋風』を結実させた。プラトンは弟子の中でも、飛び抜けて多くソクラテスの『靴屋風』を書き残した。
*
プラトンがエジプト旅行の折深く交わったというヘブライの民は、現在の国際都市アレクサンドリアにおいても、地元エジプト人、支配層ギリシャ人と、伍する大勢力を占めている。街に居留する何万という人々は、徐々にギリシャ化し、ヘブライ語を忘れつつあった。そこで、聖典のギリシャ語訳が、試みられる事となった。
世に『70人訳』と呼ばれる偉業が達成される過程に、主任司書カリマコスは間近で立ち合った。大図書館の蔵書群に、また一つ巨大な山脈が隆起し並び立つ様を、驚異の念で見守っていた。プラトンも賛嘆して止まなかった、その完成仕立ての偉業に盛られた異民族の知恵の中に、あるいはムーシケーへのヒントが隠されているのではないかと、ソクラテスは『70人訳』のページをめくり、さらに各所に附された注釈を辿った。
その時である。――丁度、一つの注釈に導かれ、関連書物の一冊を紐解き、読み始めた刹那であった。
また、これか!――ソクラテスは呻いた。
立ったままの、“金縛り”である。
唐突に、カリマコスの不必要に長い袖口の衣装から伸びた腕で、書物のページを繰り掛けた姿勢のまま、動きが停止してしまった。――あの、アガトン家のシュンポシオンの前や、レオン逮捕の前のそれと同じ、ダイモンによるものだった。
70年の生涯の間、実に幾度も、ソクラテスはこれに襲われた。
今回もまた、同じダイモンの仕業だろうか。――体が突然、固まってしまうのである。――あるいは、長年石工を営んできた、家業の祟りででもあろうか。――動きが止まって、何分でも、何時間でも、石像のようにポーズを取ったままとなる。――それとも気付かぬ内、メデューサにひと睨みされたか。
不動姿勢の最長記録は、37歳でポテイダイアの包囲戦に参加した時だった。陣中で彼は、朝から同じ姿勢のまま立ち通しとなり、これが一昼夜続いた。翌朝、再び日を浴びる頃、金縛りは不意に解け、彼は何事もなかったようにその場を立ち去った。
金縛りの間、彼はダイモンの声を聞く事がしばしばあった。――極短いそれの時、ダイモンの合図は“禁止命令”の形を取った。何かしようとした瞬間、“ストップ!”、と静止させられるのである。長時間のそれは、茫洋として、白日夢を見ているようであり、動き出してからも何を告げられたのか、思い出せない事が多かった。――どうやらダイモンは、こちらの覚醒度合いに合わせて、命令形態を使い分けているらしい。はっきり意志し行動を起こそうとする時には、禁止のみを命ずる。夜の夢や長時間の白日夢の中では、神あるいはダイモンは、これから取るべき道について、もっと大きなビジョンを告げ知らせてくる。
ダイモンの合図は、しばしばソクラテスに、人生の針路変更を促した。――それは、何者か“良きダイモン”であると、彼は確信していた。自分に長く語り続けてきたこのダイモンを、ヘラスの神話の神々とはまた違う、賢明で善良な神であると、彼は信じて疑わなかった。
さてダイモンは、今回は何と言ってくるのだろう。彼は思った。この夢の神託絡みの、何か具体的にヒントになるような事だろうか。
――ところが、この時、カリマコスの体の彼に、ポテイダイア以来の強烈な金縛りを掛けてきたダイモンは、これまでのように“禁止”や“指示”の合図ではなく、思いもよらない言葉で話し掛けてきた。――全く、新しいパターンだった。それは、“疑問形”だったのだ。
「何故、私を迫害するのか?」――ダイモンはそう言った。
この質問にどう返答したらよいのか分からず、ソクラテスは聞き返した。
「あなたは、どなたですか?」
ダイモンはすかさず答えた。
「私は、あなたが迫害しているイエスである」
*
ポテイダイアの戦いは、ケルキューラの海戦とともに、ペロポネソス大戦の前哨戦となった。この二つの戦いが契機となり、大戦は幕を切って落とされた。そのポテイダイアの遠征に、ソクラテスは出征していた。当時、三十代後半だった。
冬は寒冷の地となるマケドニア方面を転戦していたソクラテスが、デロス同盟から離反したポテイダイアの地に到着したのは、緑の息吹の香る初夏の頃だった。到着するなり、大激戦となった。アテナイ勢は、指揮官カリアスを失ったが、戦闘では勝利を収め、ポテイダイア側を城内に封じ込める事に成功した。ポテイダイアは半島の付け根の地峡上に位置するが、その後南北に攻城壁を造られ、東西の海は軍船で行き来を遮断され、完全に封鎖されることとなった。――この後ポテイダイアは、二年半の籠城戦を持ちこたえた。しかし遂に人肉を食うまでの飢餓状態に陥り、アテナイに降伏する。
その築かれつつある攻城壁を見やりながら、ソクラテスは北の荒野に立ち尽くしていた。東の湾を挟んで遠くに見えるもう一つの半島から、すがすがしい朝日が昇らんとしていた。周囲には、アテナイ率いるデロス同盟軍の幕舎が点々と散らばっていた。だがまだ、戦友達の目覚めて動き出す気配はなかった。
ソクラテスは、この半年間の激戦の幾つかを、思い返していた。ある時は攻め、ある時は退いた。集団でぶつかる時、頑健な彼は、ファランクスの最も危険なポジション、最右翼の最前列を率先して努めた。兵糧が尽き、寒さで身動き取れなくなる持久戦にも、彼が最もよく耐えた。大激戦の中で、愛弟子のアルキビアデスを窮地から救い出し、賞賛を浴びたこともあった。――だが、彼の心を最も捉え、従って最も思い返されたのは、敗れた側、敗残の兵と、彼等が背後に残したポリスの住民達、の運命の方だった。話では、嫌という程聞かされてきた。しかしこうして実際に出征して、自らが手を下す側となり、敗残の兵と敗残のポリスを数多く生み出してみると、敗者の悲哀、勝者の罪悪感を、戦勝の都度身に沁みて思い知らされることとなった。――ペルシア戦争後、小さなイザコザは幾度もあった。スパルタ・コリントス等ペロポネソス勢との間に、そうした長い緊迫した冷戦状態が続いてきた。それが、ここへ来て、にわかに熱い戦いへと変じつつある。ここ北方の辺境地で、幾つもの小ポリスの、そしてその住民らの、哀れな末路を見てきた。財産を奪われ、追放され、しばしば奴隷とされ、最悪戦闘可能な男子は皆処刑されることもあった。そして、手を下しているのは、自分達攻め込んだ側の軍隊なのだ。
目の前のポテイダイアも、今は意気軒昂だが、どこまで持ちこたえられるか。運命に弄ばれた小ポリスらと、同じ運命の裁きを受けるのではなかろうか。そして、ヘラス全土も。アテナイを含めたヘラス全土が、熱い戦いの中で、やはり同じ運命の裁きを受け、のたうち苦しむことになるのではないか。――朝日を浴びつつ物思いに耽るソクラテスは、ついにプシュケーのみの存在となり、肉体への一切の気遣いを止めてしまった。起きだし、活動しだした戦友らは、まるで石像のごとく突っ立ったまま身動きしない、勇猛を謳われたかの勇士の奇妙な有り様に、ただ首を傾げるばかりだった。
少年達が、ゾロゾロと行軍していた。というよりも、ただ弛緩したまま、歩き続けていた。ソクラテスは、その中の一人だった。そこは、全く違う土地の、全く違う戦場だった。
歩きながらソクラテスは、ファリサイ人ツァドクの言った、“メルカバの秘儀”に心を捉われていた。――ここより南に数日歩いた土地は、砂漠と岩山ばかりの荒野で、瞑想に耽り神と対話するにはもってこいの場所だ。メッセネ派の多くの行者達が、ここで寝泊りし修行している。ファリサイ人ツァドクと名乗るその怪しげな行者は、こう説明した。やつがれも宗派を越えて彼等に混じり、瞑想三昧し、多くの秘法を会得した。その一つを、お前達に伝授してやろう。――『イザヤ書』や『エゼキエル書』に著された“神の乗り物・戦車(メルカバ)”を観想せよ、という。(その上に乗る神の御姿を、直接見る事は許されないから。)ゴランの山岳地帯に生えるという草の根を煎じた苦い汁を飲み、正座した両膝の間に頭を埋め込むように屈めた姿勢のまま、聖歌や聖典の言葉を唱え続ける。やがて、草の根の薬効が頭に廻り出すと、ツァドクの教えるメルカバの威容が眼前に現れた。それは、神秘的な獣達に引かれる、眩いばかりに輝く戦車だった。――少年達は、恍惚状態の中で神にまみえ、その時ツァドクの唱える反乱派の教義を、飢餓の身に滋養物が沁み込むように、少しの迷いも無く丸呑みにしていった。――だが、忘我の行が終わり、霊験あらたかなこの薬草の効果が切れると、今度はとてつもなく酷い頭痛と吐き気が襲ってきた。再度服用すると、それらは治まった。そこで、子供らは、この禁断症状から逃れるため、連続的に薬を服用し続け、恍惚状態と神を体験し、ツァドクの教えを反芻した。(またそうした行為が、宗教的に褒められるべき事とされ、強く勧められさえした。)
今、子供達は、雲の上を行くような足取りで、歩き続けている。薬草は、乾燥させた根を噛む事でも同様の薬効が得られ、戦場に到着するまでそれを噛み続ける事が奨励されていた。噛むと、あらゆる疲れと恐れが消えた。任務遂行だけに邁進できた。そして、条件反射で、メルカバが見え、反乱軍の教義が頭の中で繰り返された。
――間違いない! ソクラテスは確信した。――死を目前にした、刑死を明日に控えた今だからこそ、分かる。――首男に石を投げた子と、おぞましい手の感触に失神した子と、そして今薬物でふらつきながら行軍しているこの少年とは、同一人物だ。
だが、時間的順番は、逆さまだった。ポテイダイアの戦場で最初にダイモンが体験させた少年は、他の金縛りで見た彼より、むしろ年長だった。後のアガトン邸でのシュンポシオンの前や、サラミスのレオンを捕えに行く前の金縛りで、ダイモンの見せた子供達の方が、それ以前の彼がまだ幼かった頃の姿だったのだ。――今夢の中で、カリマコスを体験しているように、ワシは幾度となく同じ少年の生涯を断片的に体験してきたのだ。年恰好こそ違え、皆同じ少年だった。――あの懐かしい、ポテイダイアの野での、丸一昼夜に渡る幻視。それの意味するところが、まるで理解も解釈も出来ず、心の奥底にそのままずっと折り畳まれ、仕舞い込まれていた。今、それを、懐かしく思い返す。
丘の斜面から見下ろす平野に、数多くの幕屋が見えてきた。近付くと、見覚えのある、杖にヘビの絡み付いた紋章や、慈愛の笑みを浮かべる男神像が目に入ってきた。『ここは、安らぎを与える場所である』との、ヘラス文字の標語が、道なりに大きく掲げられている。アスクレピオス教団の、国境を越えた医師団のキャンプ場だった。――アスクレピオス教は、ヘラスその他で大いに栄え、信徒の治療団が全国を行脚していた。
長いキトン式の白衣に白頭巾の医師が、難民の患者が到着したと勘違いしたのか、迎えに出てきた。子供達の群を見るなり、恐怖の表情に変わった。先頭を行く子供らは、構わず医師に槍の穂先を突き立て、キャンプ場へと乱入していった。
少年兵らは、少年の故郷の村だけでなく、近傍十数村から掻き集められた混成部隊だった。反乱軍の大人達数名が、司令官となり指揮を取った。医療団の無抵抗主義を知っていたから、非力な少年兵だけで部隊を編成したのである。数名ずつに分かれ、各テントに次々押し入っていった。
医師達は一様に、恐れと戸惑いの表情を浮かべた。ただ彼等は、白衣に白頭巾、それに白い大きなマスクを付けて、目と、手先と、僅かの髪と耳のみしか露出させていなかったので、目元だけで表情の変化を読み取るのは難しかった。その眼差しは、本来なら治療の対象となるべき、患者として収容されるべき、荒廃した村々の心も体もボロボロになった子供達が、何故自分達を襲う側に廻るのか、理解出来ないという大きな疑問符を掲げ、少年達に訴え掛けてきた。(現に、患者の中には、村々から救い出された元少年兵が多数いた。)だが少年達は、薬草の効果で無表情のまま、医師達に、そしてベッドの上の患者達に、槍を突き立て、剣を振り下ろした。患者達もまた、既に異教徒の治療という邪教の魔術に汚染されていたから、殺して浄化する必要があった。
医師達は、不思議な呪文を唱えだした。それを口にすると、死ぬのが怖くなくなるらしかった。「医神アスクレピオス、その他の神々に誓う。人道・人命を敬い、自由民・奴隷などと分け隔てることなく、あらゆる人々に最善の医術を施す。生涯、純粋と神聖を貫き、仁術たる医道に我が身を奉げる。……」それは、“ヒポクラテスの誓い”と呼ばれるものだった。唱えながら、少年兵らを静かに見遣り、刺し殺されていった。
そんな医師達に容赦なく槍を突き立てつつ、ソクラテスはその感触に先日のポテイダイア軍との激戦を思い出していた。拙く、かつ非力な少年と、練達の手腕、剛健な筋力の歴戦のツワモノとの、違いはあるが。しかしそれが、今のソクラテスには、ごく僅かの差に思えてならなかった。貫く時の、切り下ろす時の、躊躇いと、ままよと振り払う迷いの突っ撥ねと、その後の苦い後悔とが、同じ種類のものであるという事実に較べれば。
ただ、今回の相手方は反撃してくる事がなく、悲しげな目で見返してくるばかりである。心の奥底で、目に涙を一杯に溜めつつ、少年は“突き”の動作を繰り返した。頭で鳴り響く、ツァドクの『異教徒を撲滅せよ!』の呪文に、リズムを合わせるように。
人への殺傷を果たし終えると、少年兵達は、医療器具や包帯や諸々のものをぶちまけ、アスクレピオスの紋章や偶像を破壊し、テントに火を放った。彼等の宗教の教義は、偶像を絶対に認めないという特殊なものだった。まあ、石工は失業するな、ソクラテスは苦笑いした。
近くのローマ兵の駐屯地から、救援の百人隊が駆け付けた。少年達は、隊列を作る間もなく、打たれ、散り散りに逃げた。医者達の骸に、子供がここまで酷い所業をし得るのかと、瞬間ローマ兵達はたじろぎ、立ち尽くした。だがすぐさま追撃に移り、今度は逃げ遅れた非力な少年達を無造作に撲殺していった。ソクラテスの周りでも、子供達が追われ、やみくもに逃走していた。キャンプから大分走った丘の中腹の藪の中にダイブし、ソクラテスとその周囲の子供達は、かろうじて難を逃れた。
ローマ兵の追撃は、丘を駆け登り、さらに続いた。少年達は、茂みを転々とつたい、より遠くへと逃げ延びようとした。茂みが入れ替わるたび、少年達は離散し、再び集合し、それまでいた者がいなくなり、新たに別の者が加わり、を繰り返した。
やがて、比較的濃い森の懐深くまで到達した時、ようやくローマ兵の追撃が止んだ。少年達は、自分と共に逃げた仲間を落ち着いて見廻し、その人数を確認することが出来た。少年を含め、十三人いた。
他の村の、見知らぬ者達ばかりだった。少年達の目は一様に、魚の鱗を被せたような、僅かな光も無い灰色だった。視線の焦点が絶えず彷徨い、決して互いに見詰め合おうとはしなかった。むしろ周囲の同類に怯え、警戒し合う様子だった。――きっと自分も同じ目をしているのだろう、少年は思った。
誰から言うでもなく、西に向かって歩き出した。西方に広がる荒野は、彼等の故郷の貧しい村々の点在する地である。対して東方のガリラヤ湖畔やヨルダン川河畔は、北のダマスカスと南のエルサレムを結ぶ南北の大動脈であり、ローマと大祭司勢力がガッチリと押さえていた。
しかし彼等の帰郷は、ローマ軍の執拗な残党狩りにより、行く手を遮られた。彼等は迂回に迂回を重ねたが、幾日もそうする内、自分が今どこにいるのか、果たして当初より西に進んだのか東に後退したのか、それすら分からなくなった。
食料と水はすぐ尽き(元々殆ど携行していなかった)、森の中でも僅かも見付からず、仕方なく人里へ出て手に入れることにした。
最初に様子を窺った村は、無人だった。というより、何ヶ月か何年か前に、放棄されたようだった。家畜の糞が積み上がり、汚物や汚水が人家の周囲を取り巻き、それらが固化していた。そして朽ちて干乾びた死体や、何者かに襲われた破壊の痕が、傷口を晒したまま形を留めていた。口に入れられる物は、何も無かった。
二つ目の村は、これも無人だったが、ほんの数分前まで人のいた気配が残っていた。どうやら少年達の接近を察知し、あわてて村人全員、村の外へ非難したらしい。――ごく僅かだが、まだ温かいレンズ豆のスープと焼いた魚が、食べかけのまま卓上に載っていた。少年達はそれを分け合い、腹の足しにした。塩焼きのアムヌン(ティラピア)の塩気が、この上ない滋味として、はらわたに沁みた。
三つ目の村に侵入する時は、この前の成り行きを学習し、むしろ村人を威嚇するように自分達の存在をチラつかせつつ接近した。狙い通り、ここでも村人は逃走した。――だが、すぐ侵入者が少年達だけだと気付いたようで、裏山から引き返してきて反撃に出た。少年らは、殴られ、棒で打たれ、逃げるところを石で追い討ちされた。
失敗に懲り、四つ目の村には用心しいしい、夜間に忍び込むことにした。納屋の裏手へ廻ると、魚の干し掛けの生臭い匂いが漂っていた。彼等はたまらず、魚を掴み取ると生のまま食べた。――やがて目が暗闇に慣れてくると、星明かりの下に、干物を作る作業中だったらしい女の死体が、魚を入れたカゴと共に転がっているのが見えてきた。闇の色でどす黒く死海産のタールのようだったが、明らかにまだ乾いても土に吸われてもいない鮮血に溺れ、屠られた供物のようだった。――少年らは警戒し、納屋の周囲を恐る恐る調べた。
村の中央に面した側に、さらに幾つか、体の一部はまだ生きているかもしれない、成り立ての死体が転がっていた。中央の広場の辺りに、焚き火の光が見え、騒ぐ男達の声がした。その内の数人が、酷く酔った千鳥足で、少年達のいる方へフラフラと近付いてきた。――少年達はあわてて引き返し、持てるだけの魚を持って、森の奥へと夢中で逃げた。
翌日、生の魚への未練が捨て切れず、少年達は再度村への潜入を試みた。――魚は、既に全部消えていた。しかし死体は、昨夜のまま、ただし陽光に彩色を施され、より生々しく転がっていた。そして野盗どもの群も、そのまま居座り(どうやら村のものを食い尽くすまで、居座り続ける気のようだ)、酔って破壊と略奪を繰り返していた。――少年らはそれ以上の収穫を諦め、森へ戻った。にえの獣の如き村人の血の海の死体は、昼の光の下では嫌でも目に入り、夜の闇の中では昼より鮮明に蘇った。
魚は、すぐに尽きた。少年達は、飢えと渇きで、油絞り機で身を捩られたように、痩せ細り、苦しみ抜いた。イチジクの大木が森の中で見付かったが、丁度収穫期を終えたところで一つの実も付けておらず、少年達は「お前は今後、一つの実も付けるな!」と口々に罵り、そのイチジクの木を呪った。
飢餓や渇きと、草の薬効が切れての禁断症状が、少年を交互に襲った。不思議なもので、飢餓や渇きに苦しんでいる時は、禁断症状を感じる事はあまりなかった。ところが飢餓や渇きが少し治まり身が落ち着くと、途端に吐き気や頭痛や酷い倦怠感が目を覚まし襲ってきた。
少年は薬草の入っていた袋の底を探り、残りカスを集めて口に含んだ。いとおしそうに、いつまでも噛んでいた。それさえ無くなると、袋を裏返し、その内側を噛んだりチューチュー吸ったりした。
食べた途端に吐き気がこみ上げた。飲んだ途端に渇きでひりついた。震えが来、体内の脈打ちに怯え、地面を転げ回ったかと思うと、虚脱して廃物のように蹲った。
どの少年も、多かれ少なかれ、似たような状態のようだった。彼等が無口だった原因の半分は、そこにあった。それでも、飢え・渇きと禁断症状を紛らすように、彼等はボソリボソリと、休み休み、それぞれの事を語り出した。
行動を共にする内、少年達の間に連帯感めいたものが芽生え始めていた。当初の死んだように無関心な白目から、互いに過剰な程依存し合う馴れ馴れしい粘着性を帯びた目の色へと変わっていった。薄暗い森に囲まれ、草地や倒木に腰を下ろして、少年らは傷を舐め合うように、自らの境遇を告白し合った。
「奴等、――耳、鼻、目、手、足、の順で切り落とすんだ。村人を並ばせといて、……」トマが言った。「村人を従わせるために、そうやって脅すんだ。切り落とす順は、戦闘力を保持するのに都合のいい所から、――という訳さ」
そう言うトマには、耳と鼻が無かった。そして、言われてみれば、彼等には体のどこか欠損した者が多かった。目や、耳や、鼻や、――片腕の無い者もいた。――ソクラテスの少年のような五体満足な者は、むしろ少数派だった。してみると、ウチの村の反乱勢力は、むしろ穏健な方だったのか、他村のそれと較べれば……、少年は思った。
「ウチの村では、順番が逆だった。――ウチは敵対側だったから、逆らえないように、足、手、目、鼻、耳の順で切り落としていった」と、片腕の無いヨハナンが言った。
「傘下の村では兵士となることを強制し、敵対する村からは子供達をさらってきて兵士に仕立てるんだ」ヨハナンの兄弟の、片目の無いヤコボが言った。
「そればかりじゃあない」頭を両手で抱え、苦しそうにうつ伏しながら、タダイが呻くように呟いた。「拉致した子の家族を、皆殺しにするんだよ。跡に未練が残らないように。――それどころか、子供本人に、両親を殺させることすらある。――僕も、家族を皆殺しにすると脅されて、父さんをこの手で殺した、……」
オレもだ、――ボクもだ、――と告白する者が何人もいた。ソクラテスの心に、隣家のおばさんの優しい笑顔が浮かび上がった。――そうやって、心を絶望で致命的に傷付け、普通の生活に戻れなくさせるのだろう。
「そんなのは、まだマシな方さ」皮肉な調子で薄ら笑いを浮かべながら、ユダ少年が仲間の話に割り込んできた。「オレの村を占領した奴等は、もっと狡猾だった。本人に傷付けさせた家族や村人を、わざと生かしとくんだ。家族や村人が子供を憎み、子供がもう二度と村へ帰れなくなるようにするためにな。――オレは、弟と妹を殺して、母さんの足を切り落とし、父さんの腕を切り落とした。そうしないと、家族全員を殺すと脅されたからだ。現に、家族全部を皆殺しにされた家が、何軒もあった。――だが、両親や、村の奴等は、オレの事を悪魔だと罵った。逆に、村人達に殺されそうになった。村を出て、連中の仲間になるしかなかった、……」――ユダの話が終わり、しばらく少年達は黙りこくった。
――やがて、ソクラテスの少年も話をするよう促された。「ヨシュア。お前はどういう体験をしてきたんだい。話を聞かせろよ」
少年は話した。村の多くの家族が離散したこと。アンズ売りのおじさんを石打ちで殺したこと。近所の親代わりのおばさんを、騙されて刺し殺したこと。
だが少年達の反応は、意外なものだった。少年の話に共感を示すどころか、むしろ強く反発してきた。――じゃあ、お前の家族は、みんな健在なんだ。傷一つ負っちゃあいないんだ。随分と、幸福なことだ。
少年達は、羨み、妬み、――憎しみを平然と口に出す者までいた。――“何て、不公平なんだ”“お前も、オレ達の所まで落ちちまえ!”
何人かの少年達の、赤黒い妬みと憎しみの目の色が少年に注がれ、残りの者は顔を見られたくない風に目を伏せていた。――そんな中で、一人シメオン少年が、突然怒りの声を上げた。「何て、――情け無い奴等ばかりなんだ!」シメオンは立ち上がり、グルリと仲間達を見廻した。「お前達の中には、――自分から進んで反乱に身を投じた者は、いないのか?」――マタイとバルトロマイが、賛同するように恐る恐る手を挙げた。
「そうだろう。自ら身を奉げた同志だって、ちゃんといるじゃないか。情け無い小判鮫どもばかりじゃあないんだ」シメオンはヨロヨロしつつも、拳をしっかりと握り締めた。「オレはこの手で、背教者どもも、同志の名を騙った裏切り者どもも、多くの奴等を石打ちで殺してきた。石打ちこそが、“トーラーの大儀”に従わぬ者達への、最も相応しい罰であり、見せしめだ。――そして、にっくきローマやギリシャの奴等とも、幾度もぶつかってきた。かつて先祖達が、呪うべきアッシリアやバビロニアとぶつかり、そして奴等が神罰により滅んでいったように、今またローマやギリシャもその同じ神罰により滅ぼされるだろう。――お前達は、ローマやギリシャが、憎くないのか?」
「それは、憎いさ。――奴等がこの約束の地に侵入して来なければ、僕らは平和に暮らしていた。奴等こそ悪魔の遣わした最大の元凶だ」とフィリポ。
「奴等は、妙な神や偶像や、禁忌の食い物や風習を押し付けてくる」と、ハルファヨも賛同した。
「だけどね、ボクはやっばり反乱派の連中も嫌いだ」アンデレが、意地を通すように力強く言った。「シメオンには悪いけどね。――連中は苦しみを取り除くどころか、――それを何十倍にも膨れ上がらせているよ。そんな状態を、楽しんでいるようにすら見える」
「それが、神の与えられた試練、ってものじゃないか!」シメオンがアンデレに、厳しく反駁した。「幸福を得る過程で、苦しみを味わわねばならないのは、世の常の事じゃないか!」
「それでもやっぱり、ボクはローマ・ギリシャも、反乱派の連中も、どっちも許せない!」――両者とも、退かなかった。
二人の睨み合いが続く中、最後にアンデレの兄ケファがボソリと言った。「オレは、――ローマ・ギリシャも、反乱派も、それどころかこの世の全てが、許せない。憎くてしょうがない。――こんな世界、丸ごと滅びてしまえばいいと、本気で思うことがしばしばある、……」
シメオンが呆れたように、「何て事を言うんだ。それは、悪魔の最悪の囁きだぞ。最も神を冒涜する言葉だ」
だがユダ少年は、ケファのこの言葉を聞き、我が意を得たりというようにニヤリと笑い、ヨシュア少年も、表情にこそ出さなかったが、内心深く賛同する自分を意識していた。
ようやく辿り着いた村で、少年達は大量のアムヌンの干物と山と積まれたパンを見付けた。どうやらその村は、ガリラヤ湖のアムヌンを加工する拠点だったようで、生産ラインも整った工場が幾つもあった。アムヌンの干物は、ここからユダヤの全土や、遠くローマにまで輸出されるのだろう。そしてパンは、工場労働者のための給食のようだった。――ただし、今目の前にある干物は、生乾きで腐っていた。パンも、その表面の殆どを色とりどりのカビが覆っていた。
川が村のすぐ裏手を流れていた。その川から工場まで水を引く用水路まであった。あるいはその川の水を魚の洗浄等の作業に用いているのかもしれない。――ただし、その川はワジ(枯川)だった。雨期には水が流れガリラヤ湖に注ぐが、乾期には干上がる。これから冬になり本格的な雨期が始まるが、今はまだハシリの水が僅かに流れ下っただけのようで、泥水があちこちの窪地に溜まっていた。
幸いなことに、村に人気は無かった。人がいれば、相当な資本が投下され、作業員もかなりの人数を抱え、警備も厳重だったことだろう。それが作業を途中で放棄したようにもぬけの殻になっているという事は、多分敵対勢力に襲撃され、一時的に非難したのだろう。ということは、いつ住民が戻ってくるとも限らない。
少年達は当初、食べることも飲むことも躊躇った。魚とパンは酷い臭いを発し、水は濁って土色をしていた。しかし、空腹には勝てず、魚とパンを選り分けてなるたけまともな所を食べ、水を掬い掬い少しでも透明な所を啜った。
その時ヨシュア少年が、素晴らしい事を思い付いた。――「ボクは魔法が使えるんだ」彼は言った。
「どんな魔法だい? ヨシュア」アンデレが訊いてきた。
「ボクが魚やパンを千切ると、千切ったカケラが元に戻って、幾らでも増えるんだ。――ボクが水を汲むと、汲んだ水がみんなワインになるんだ」
それを聞き、子供達は面白がって魚やパンや水を少年に献上し、少年はそれらを千切り、汲み、魔法のまじないを掛けるふりをした。
子供達は魔法遊びに打ち興じた。それは、随分と長いこと忘れていた、子供らしい遊びだった。――そして事実、魔法を掛けられた魚やパンは増えに増え、水はワインに変じた。魚やパンはこの上なく美味で、ワインは結婚式で最初に出されるもののように極上だった。
少年達は段々大胆になっていった。食べに食べ、飲みに飲み、空腹と渇きを癒した。持てるだけのものを持ち、その村を去った。
――しかしその晩から明け方にかけて、猛烈な腹痛と下痢が少年達を襲った。体内の全てが、出尽くしたように思えた。
フィリポとハルファヨは、加えて嘔吐と発熱に苦しんだ。三日間、二人はのたうち回った。フィリポは吐き続け、あらゆるものを受け付けず、遂に餓死した。ハルファヨは発疹に覆われ高熱に浮かされ、血尿と血便を出し続け、衰弱して死んだ。
皮肉にも、待ちに待ったワジの水が、二人が死んですぐ後から本格的に流れ始めた。それはたちまち、目を見張る程の水量となって、東方目指して流れ落ちていく。少年達は川に沿い、水を確保しつつ、上流目指して遡り始めた。――だがローマ軍も、同じ意図で、川に沿って河口へと下りようとしていた。鉢合わせを避け、完全武装のローマ兵をやり過ごそうとするが、身の安全を優先するとどうしても押し戻されざるを得ない。西の丘陵地から徐々に追い落とされるようにして、少年達は湿地の中へと足を踏み入れていった。
ガリラヤ湖は、海抜マイナス200mに位置する、世界で最も湖面の低い淡水湖である。ここからさらにレバノン川で南に下ると、海面下400mの死海に到達する。流れ下る水の、最後の到達点は、どうしても塩水湖となる。(最大の塩水湖は、“海”だ。)
当時は、湖岸は湿地帯が多かった。そして蚊が大量に発生した。その蚊が、風土病ともいうべきマラリアを媒介した。――春先ならば、神の国とも見まがう美しい花園となるガリラヤ湖畔だが、少年達が迷い込んだ時は季節が悪かった。蚊はまだ大群で生息し、雨が降り続き、強風が吹き始めて湖面は荒れ、寒さが急速に増して少年達を凍えさせた。
藪の中で好き放題食われたせいでもなかろうが、タダイとシメオンが発症した。多分、以前から病原虫を持っていたのだろう。二人とも、高熱に浮かされ、苦しみ、シメオンには出血斑が大量に出てうわ言を繰り返し、タダイは狂ったように暴れ出した。
悪霊に取り憑かれたのか、――少年達は恐れた。地元の人々は、こうした症状を、悪霊のせいにするのが常だった。丁度辿り着いた廃村に、廃屋となったシナゴーグがあった。この地のシナゴーグは、エルサレムの方、つまり南方に向けて、入り口が開いている。少年達は、もはや正気を保てなくなった二人を、その建物の中に閉じ込め外から入り口を封じた。そして、跪いて必死に神に祈った、どうか二人から悪霊を追い出して下さいと。
バルトロマイが、二人を看病すると言い出した。少年達は皆、やめとけ、悪霊がお前にも乗り移るぞ、と彼を止めた。しかしバルトロマイは、「ボクは将来、医者になりたいんだ」と言い、皆の忠告を聞かなかった。彼は、水と食料と、ワジの水で押し洗いした布を持ち、シナゴーグへ入っていった。
それから数日、バルトロマイの看護が続いた。しかし彼は、疲労の色を濃くし、見る見る痩せ細っていった。そら見たことか、お前にも悪霊が取り憑いたぞ、と少年達は口々に非難した。ソクラテスの少年は、見かねて、自分も手伝おうと声を掛けた。悪霊は恐ろしいが、村で戦傷病者を見慣れていたので、それほど抵抗は無かった。
バルトロマイに付き従い、堂の中に入って、小さな窓から漏れる光だけの薄暗がりの中で、バルトロマイの見様見真似で看護を始めた。
シメオンの熱い体を水に濡らした布で拭き、拘束されてもまだ暴れるタダイに薄い粥を飲ませる内、つい数週前薬草で頭の麻痺した自分が刺し殺したアスクレピオス教徒の医師達の働く姿が思い出されてきた。ふと気付くと、彼等医師達は看病する手を休め、少年の方を振り向いてその顔をジッと見詰め、そして口々に――これからは、殺された我々に代わり、殺したお前が病人達を看病しろ。――と、呪いのような言葉を呟き掛けてきた。
バルトロマイが、彼に言った。「君も大人になったら、医者になるのかい?」少年はしばらく考えてから、「ボクは、心の医者になりたいな」何気なく、そう答えた。
忙しく看護する二人を見て、他の少年達も、恐る恐る看護に加わり始めた。作業ははかどり、出来る事は全てやった。――だが、皆の努力もむなしく、タダイは狂い死にし、シメオンは“敬神”と“革命”をうわ言のように繰り返しながら、うなされつつ死んだ。
二人をシナゴーグの裏手に埋葬した彼等は、ようやく湿地を抜け、そして眼前に大きな町を見た。マグダラの町だった。
湖岸のマグダラは、湖から大量に水揚げされるアムヌンの加工業で栄えていた。以前見た村の加工場の、何十倍という規模だった。あるいはあの村も、ワジを遡ったマグダラの系列工場の一つだったのかもしれない。
マグダラは豊かな町だった。大きな家が道の両側に幾つも並んでいた。しかしその分、警備も厳重だった。ローマ兵や町の警備兵が、街頭の辻々に立ち、大通りをパトロールしていた。
少年達は裏山の木立の間に身を隠し、町の繁栄を見下ろした。中庭や小窓の中に覗ける、豊かで幸福そうな家庭があった。幼い子供達が、親や召使らにかしずかれ、何の屈託も無く無邪気に遊んでいた。
あいつらをかっさらって、オレ達の子分にしたらどうだろう。ケファが提案した。そいつぁ、いいアイデアだ。みっちり訓練して、筋金入りの革命闘士に鍛え上げてやろうぜ。ヨハナンが賛成した。
少年達はしばらくの間、この“素晴らしい計画”について、細部まで具体的に詳細に語り合い、大いに楽しんだ。しかし、腹の虫が激しく鳴り、優先して実行せねばならぬ別の計画があることを、思い知らされた。
湖の方へ目を転じると、町との接線が長大な船着場になっている。冬場の荒波を防ぐ長く堅牢な防波堤が建設され、その内側に幾十艘もの舟が係留されていた。
港の陸側には、大きな倉庫が幾棟も並んでいた。多分、輸出用の干し魚を、あそこに貯蔵しておくのだ。少年達は船着場を目指し、山の斜面を慎重に下りていった。
防波堤の付け根辺りのフェンスから侵入した。警備の者もいたが、何分敷地が広大過ぎて、とても目が届かないようだった。如何せん魚の量が多過ぎ、多少ネコに盗まれようが人に盗まれようが、大事とは考えていない様子である。
『汝、盗むなかれ』と戒律にあるが、こんな有り余る魚を大カゴ一杯分失敬するぐらい、神もお目こぼしして下さるだろう。いや、それどころか、異教徒どもに輸出する荷を掠め取るのだ。不埒にも、約束の地の実りが売り渡されるのを、妨げるのである。神は、お前ら、良くやったと、かえってお褒めの言葉を掛けて下さるやもしれぬ。――少年達は、魚の一杯詰まった大カゴに群がり、それの運び出しに最後の力を振り絞った。普段なら不快に感じるだろう生臭い臭いだが、この時の彼等には何とも食欲をそそる芳艶な香りとしか思えなかった。
周囲の見張りに付いていたマタイとトマが駆け戻ってきた。マタイが言った。警備隊が、こっちに近付いてくるぞ。トマが言った。舟遊びしている家族連れが、こっちを不審そうに見ているぞ。
彼等は計画を、第二作戦に切り替えた。もし獲物を陸伝いに安全地帯まで運び出せない時は、係留してある舟を奪って湖へ逃げる。そのための舟も、倉庫に侵入する前に物色してあった。
彼等の逃走ルートから最寄で、湖へすぐ出られる位置に係留されている無人の舟。漁船や輸送船のひしめく中、ガリラヤ湖に特徴的な鋭いへさきを外海へ向け、そのくせ船尾は荷が一杯積めるよう丸みを帯びている、軽快そうな小型輸送船だった。鋭いへさきは、冬場の荒波を乗り越えるための工夫で、軍船のそれを思わせ少年達のお気に召した。
大カゴを舟に運び入れる作業を、船着場から小さな男の子が物珍しげに見ていた。多分、さっきトマが報告した、舟遊びに来ている家族連れの子供だろう。
ケファが、目配せした。オイ、あの子供。さっきのアレを、実行しよう。
たちまち数人の少年が、男の子に飛び掛った。ケファが子供を小脇に抱え、舟に飛び移った。火の付いたように、子供が泣いた。
背後で、女の金切り声が上がった。少年達は舟のもやい綱を解き、一散に漕ぎ出した。家族者と、女の声を聞き付けた警備隊が、岸壁に鈴なりになり、こちらに罵声を浴びせてくる。
追っ手が、数艘の舟に分乗し、追跡しようとしていた。しかしその頃には、少年達の舟は防波堤の縁を越え、外洋に出つつあった。
――だが少年達には、重大な誤算があった。内陸の丘陵地育ちの彼等には、ガリラヤ湖の事を知っている者が、誰もいなかったのだ。――冬場に入ったガリラヤ湖は、ただ強風に荒波の厳しい湖というだけではない。その風向き、波の打つ向きが、瞬時に変わる、予測不能の突風と乱流の湖なのであった。だからベテランの漁師や船乗りでも、冬場は風向きや波の立ち方に最大の注意を払い、用心しいしい舟を操る。それでも、水難事故は多発する。ましてや、ズブの素人の少年達に、捌き切れる相手ではなかった。
たちまち、舟は大波でせり上がったところに、帆柱と舷側に逆向きの力を受け、横転した。少年達と、男の子と、そして魚の詰まったカゴは湖面へ放り出され、干乾びた魚は故郷の水を得て、居るべき所へと戻っていった。
少年のある者は湖に浮き、ある者は沈み、ある者は横倒しになった舟にしがみ付いていた。追っ手の舟が、迫っていた。――その時、舟にどうにかよじ登っていたトマが、何を血迷ったのか、突然湖面を走って逃げようとした。――彼は、生まれてこの方海も湖も知らず、こんなに大量の水というものを経験したことが無かったのだ。――たちまち、溺れて死んだ。
泳いで逃げようとするケファとアンデレの兄弟に、援軍に駆け付けた漁師の漁船が迫っていた。漁師達は手馴れた操船で二艘の舟に渡した網で、これら魚泥棒の誘拐犯らを手際よく包み込み、見事すなどった。活きのいい魚以上に激しく抵抗する二人の少年は、みなもの光を宝石を散りばめた如く輝かせたが、手を焼いた(網が破られそうで不安に思った)漁師達にカイでボコボコに打たれ、半死半生となり連行されていった。
ヨハナンとヤコボの二人の兄弟は、かろうじて岸まで泳ぎ切ったが、間の悪いことに彼等の上陸地点のそばで、漁民らが車座を作り魚網の繕いをしていた。その集団を突破しなければ、逃げ切る事は出来ない。二人は、必死の形相で、短い槍を構え突進していった。その様を見た腕っ節が自慢の漁師達は、網に結ぶ重りの石を二人目掛けて投げ始めた。石錘は、丁度握り易い大きさで、紐を通す穴が一つ開いている。石打ちには最適の得物だった。――雹の如く降り注ぐ石つぶてに打ち伏せられ、二人は遂に動かなくなった。
流木につかまり漂いながら、ソクラテスの少年はこれら光景の悉くを見ていた。惨劇が全て終わっても、湖の嵐は止まないどころか、その激しさをいよいよ増した。少年は湖の水を呪い、「黙れ! 静まれ!」と脅して、従わせようとした。しかし湖は、少年を嘲笑うような風切り音を交え、より一層厳しく少年を打ち、翻弄した。
生き残った四人は、マグダラの北方の葦原地帯に打ち上げられた。
その葦原は、“穢れの地”と呼ばれていた。何故なら、上陸してすぐの所に、熱病者達のための小屋掛けの隔離所があり、また丘一つ隔てた奥の谷には、癩者の部落があったからである。いずれも、悪霊憑きとして、村から追われた人々だった。――さらに、沼地を挟んで反対側には、異邦人用の豚を産する豚舎があった。ユダヤの民の目に留まらぬよう、隔離されて営まれていた。
少年達は、葦の茎のクッションに身を預け、回復を図った。一夜明け、東の空が白む頃、ようやく湖の水の毒気も抜け、体を動かすことが出来るようになった。
動けるようになると、また胃の腑が食い物を要求しだした。僅かに残っていた食料も、みなガリラヤ湖に奪われてしまった。
マタイが、いいものがあるぞ、と言って懐の中を探った。取り出したのは、一組の火打石だった。昨日倉庫で見張りに付いていた時、事務室の机の上に置いてあったのを失敬したという。
半生の魚に辟易していた四人の口から、涎が垂れた。乾燥した葦に火を付け、魚を焼いて食う。想像しただけで気が狂いそうだった。
すぐ湖に飛び込んだが、しかし漁具を持たない彼等に、素手で捕まる程湖の魚はのろまではなかった。栄養不足で疲れ易くなっていた彼等は、すぐに諦めた。
陸に戻った彼等の耳に、沼地の縁の豚舎の豚の、ブーブー啼く声が届いた。四人はその方向を見遣り、同時に同じ事を考えた。禁忌の肉。普段なら、思っただけで吐き気を催すそれだが、――禁忌の味は、焼いて立ち上る香ばしい煙といい、フツフツ音を立てる脂の甘みといい、――想像を超えてたまらなく美味だろう。
火打石をギュッと握り締めたマタイが、「アレを獲って、食おう」遂に言った。
言い出しっぺの彼を先頭に、豚舎に近付き、フェンスを乗り越えた。穢れた獣の恐ろしげな顔と臭い体に、彼等は恐る恐る摺り足で接近を試みた。
群から離れていた一匹に、彼等は一斉に飛び掛った。――が、豚の取り扱い方を知らないユダヤの民に挑み掛かられ、豚は火が付いたように怒り狂った。――そして四人の少年を易々と、遥か遠方へ弾き飛ばした。
豚の狂乱は、たちまち群全体に飛び火した。悪霊どもが乗り移ったように、少年達目掛けて突進してきた。彼等はあわててフェンス目掛けて引き返したが、火打石を握り締めたマタイのみ豚の焼肉の誘惑に勝てなかった。――彼は執拗に二股の蹄で踏み付けられ、最後はミンチとなって死んだ。
沼地の反対側まで逃げ延びた少年達は、マタイの惨い死のショックでしばらく口が利けなかった。葦の上に横たわり、身動き一つしなかった。
――午後の日の傾く頃、湖の方から舟を漕ぐ音がかすかに渡ってきた。――少年達が葦の穂先から首を出して覗くと、数人の男達の乗った一艘の舟が岸へと近付きつつあった。
少年達は警戒し、様子を窺った。――だが、追っ手ではなさそうだった。男達は上陸し、かなりの量の荷物を岩場に置いた。そして舟に引き返しそのまま湖の沖へと去っていった。
荷物は、大量の食料のようだった。魚やパンが、包みからはみ出して見えた。――少年達は、すぐに理解した。それらは、隔離された病人のための、差し入れだったのだ。病気や悪霊の感染を恐れ、届けた者は病人と接触することなく引き返したが、間を置いて病人達がこれを受け取りに浜に下りてくる手筈になっているのだろう。
あれを、くすねる事は出来ないか。至極当然ながら、少年達は皆そう考えた。病人達から奪うなど、見下げ果てた行いだ、などと考える余裕は彼等に無かった。――だが、食料が届く様子は、既に隔離部落から見張られていることだろう。彼等をうまく目眩まして、食料をくすねる方法があるだろうか。
「大丈夫だよ」と、バルトロマイが言った。「僕の顔を見て御覧よ」と、耳と鼻の無い顔をこちらに向けた。「この顔なら、癩者と思われても、不思議はないだろう?」――反乱軍に削がれたと、バルトロマイは話していた。だがそれを、疑う少年達もいた。あの落ち方、どうも変だ。それに、体のあちこちに妙なアザやデキモノもある。本当は、悪霊憑きなんじゃないのか? それで、医者になりたいなどと、言っているんじゃないか? 彼等はそんな風に陰口を囁き、バルトロマイを敬遠していた。
ソクラテスの少年とユダを葦の茂みに隠しておいて、バルトロマイは一人食料を取りに行った。荷物を開け、中味を物色し始めた。――その途端、熱病者の隔離小屋と、癩者の谷手前の丘の上に、思い掛けない程の数の人の群が出現した。病人らしからぬ勢いで、二組の群は差し入れの食料目掛けて突進してきた。――バルトロマイが、呆気に取られてそれらをただ見ていたのか、それとも自分を仲間だと思い込ませる自信があったのか、それは分からないが、とにかく彼は逃げることなくそこに立ち尽くしていた。そして、あっという間に大集団に飲み込まれた。
熱病者と癩者の集団は、普段からいがみ合っていた。一応の取り決めはあるが、少ない食料を巡りしばしば争いが起こった。しかも今回は、明らかに余所者が彼等に先んじて食い物を持ち去ろうとしていたので、なおさら気が立っていた。大乱闘となった。とりわけ、正体不明の余所者が標的とされた。
少年とユダが見ている前で、バルトロマイは病人達により八つ裂きにされた。葦束の陰から惨劇のシーンを窺う二人に、なすすべはなかった。バルトロマイが事切れた後も、熱病者と癩者の乱闘は狂ったように続き、彼等自身、自分が悪霊憑きだと思い込もうとしているのではないかと、疑わせるほどだった。
ヨシュアとユダは、気付かれぬようにその場を離れ、葦原の中を大きく迂回して、さらに北方の森の中まで何とか落ち延びた。
夜の森の大木に穿たれた空洞を祠に見立て、その暗闇に体を半分沈めるようにして少年は主に祈った。――主よ、あれほど無私にお仕えしたのに、メルカバの上で親しくお目通りいただいたのに、――今、何故私達を、これ程酷く仕打ちされ、お見捨てになるのですか!
そんな祈りを聞き、ユダ少年は、――死んでいった奴等は、みんな大バカだ。オレはトコトン生き抜いて、悪徳の限りを尽くして、この世の楽しみを味わい尽くしてやる。死んでいった奴等の分以上にな。……人々を貶め、この世を汚しに汚し、道連れにしてやる。――せせら笑いながら、仲間と世界を罵った。
少年は、抗った。――人々を全て、自分達少年兵のように貶めようというのか。被害者であり同時に加害者であるようにし、その仲間で世界を満たして、世界を汚し尽くそうというのか。そのルサンチマンは、サタンの誘惑そのものじゃないか。
サタンは、神の長男だろ。だから、神の正体を一番よく知っているのさ。――ユダは再度反駁した。――神なんか、何も見ちゃいない。見ていても、知らん顔だ。でなきゃ、何故あんな目に、オレ達が合う?
こんな悲しみと苦しみの中に置き去りにして、神はオレ達に何をさせようというのだ?――ツァドク達の言うように、異教徒を撲滅させようというのか? それでこっぴどく反撃されて殺されてしまえというのか? その狭間で苦しみもがけというのか? その苦しみの中で絶望だけが許され、神も世界も全てを呪いながら死んでいけというのか?――自らが呪われることが、神のお望みなのか?
オレは、家族を殺し傷付ける時、頭が混乱して意識があるのかどうかも分からなくなった。渡された斧で、何度も何度も、涙で目が塞がったまま、両親や兄弟を裂いた。――終わると、今度は自分が悪魔になっていた。少なくとも、家族や村人にとってはそうだった。疎まれ怖れられ憎まれ、オレは村を逃げた。今では反乱軍の中で、殺しに殺し、武勲を立て、出世していくのが望みだ。もし反乱軍が討伐されたら、次はローマ帝国内でうまく立ち回って出世してやる。トコトン生き抜いて、今の苦しみ悲しみの何万倍も、楽しみ尽くしてやるんだ。
――――二人は、仲違いした。それぞれ別行動で、食料を探すことになった。
少年は苛立っていた。ユダの存在が、不快でならず、許せなかった。それは、多分に空腹のせいもあった。
その苛立ちが、判断ミスを招いた。無用心に空き地に抜け出てしまい、警邏中のローマ軍の分隊に捕えられた。
こいつ、間違いなく反乱軍の子供部隊の、一人だぞ! 兵士達はそう決め付け、少年を引っ立てていこうとしたが、その時分隊長が部下達を引き止め、少年に一つ提案をした。「――お前。もし正直に仲間達の居所を白状したら、お前の罪は見逃してやろう。――」分隊長は、子供一人連れ帰ったのでは、余りに手柄が小さ過ぎる。ここは一つ、一網打尽にしてやろう、と考えたようだ。
少年が黙りこくって抵抗しているのを見、さらに言った。「褒美に、銀貨を三枚やろう。――お前のような者には、一生見ることもない大金だぞ」
別に銀貨に釣られた訳ではないが、少年はその申し出を承諾した。悪魔に取り憑かれたユダ。あんな奴、死んだ方が世のためだ、と怒りに任せそう思ったのだ。
分隊を引き連れ、森の中のもといた場所に戻った。――――そこに、ユダはまだいた。――――ただし、あの祠の大木で、首を吊って死んでいた。
それを見た少年は、手の中の銀貨三枚を分隊長に投げ付け、突然森の中へと飛び込み走って逃げた。殆ど一晩中、全力で走り続けた。自分の偽善を呪いながら、走りに走り、逃げに逃げた。――ユダを裏切り売った自分は、自殺したユダに較べて、もっと生きる価値が無いと思った。
夜が明ける頃、少年の逃走は、湖に遮られ、止まった。辿り着いたこここそが死に場所なのだと、少年は確信した。湖面の柔らかな波が、お前もユダの後を追い罪を償えと、少年を誘惑していた。
少年は、湖に、入水した。
空気が肺に入り、生まれ変わる心地を実感した。自分はまだ生きている、意識の戻った少年は、そう自覚した。
網に絡め取られ、引き上げられようとしているのが分かった。生きているという実感のもたらす無条件の幸福感と同時に、すなどられたケファやアンデレと同じ目に自分も合うのではないかと警戒し、少年は身構えた。網を手繰り寄せる舟上の老漁師が、「こいつぁ、驚いた。魚じゃあなく、人の子がかかるとはな!」言った。
老漁師は、湖北岸の村、カファルナウムに住まう者だった。少年を介抱し、食べ物をくれた。村へ戻り、寝床を与えてくれた。少年は、数週間振りに、ぐっすりと眠りに落ちた。
心地良い眠りから目を覚ますと、戸口で老漁師が誰かと話をしていた。少年は聞き耳を立てた。ありゃあワシの、漁師見習いの親戚の子だ。ただ暫く、預かっとるだけだよ。マヌケな奴で、足を踏み外して水の中へ落ちちまった。それで、溺れかかったのさ。老人は説明していた。
その言葉を裏付けるように、翌日から老人は、少年を連れて漁に出るようになった。老人の指図するまま、見様見真似で網を打った。網の繕いなど、細々した事を手伝った。あちこち漁場を移動し、湖北岸に土地勘を得た。これまでにない経験で、湖で魚をすなどる生活に愛着がどんどん膨らんでいった。村へ帰っても、敗残の兵として疎まれるだけだろう。それならいっそ、このままこの村で老人の子供として暮らしていこうか。そんな風に夢見ることすらあった。
老漁師は無口だった。しばしば、本当におしではないのか、と思わせる程に。食い物や、生活用具や、そうしたものを少年に指し示すだけで、次の行動を促した。普段の生活の場で、彼の声を聞くことは殆ど無かった。話をすることもなかった。自分についても語らず、少年の身の上話を聞こうともしなかった。――しかし、いつぞやの男と立ち話する時だけは、意外な程舌がよく廻った。男は、あの子は反乱派の子供兵なんじゃないか、と率直に疑いをぶつけてきた。目付きがすごく悪いと、噂する村人達がいる。国境を越えた医師団の人々をあやめた者らの、生き残りなんじゃないのか。まさかとは思うが、――かくまっている訳じゃあるまいな、……。男は、村役人らしかった。計三度、聞き取りに訪ねてきた。その都度、老人は同じ言い訳を繰り返し、きっぱりと男の疑惑を否定した。
神も、この老人のようだったら、よかったのに、……、少年は思った。――守られ、食べ物や寝床を与えられ、言葉は少ないが優しく見守られ、――自分も、他の十二人も、必死に守られ、救われたに違いない。
自分にとってのこの老漁師のような存在が現れず、消えていった十二人。彼等が生きた証を、唯一生き残った自分は、どう立てればいいのだろう。絶望に耐え切れず、利子を付けることなく神に命を返済したユダ。ユダは死ぬ以外に、何か出来る事はなかったのか? 入水から生き返った自分は、そんなユダに代わって、何をするのか? 漁労の手が止まった時、少年はそんな事をふと考えた。そうした事が、来る日も来る日も続いた。
十二人に対し、後ろめたくてならなかった。本来の自分は、被害者であり加害者である在り方を、同時に生きている。村へ戻れば、そうなる。ユダのように、家族からも村人からも、憎まれ疎まれるかもしれない。対してこの漁師の村では、どちらでもない。何者でもなく、生きられる。
だがそんな生き方を、救い主の老漁師が許さなかった。少年が癒えた頃、時が満ちたと言いたげに、漁に連れて行くことを拒否し、新しい服と食料を与えて、西方を指差した。その仕草を、ふるさとへ帰れという意思表示を、何度も繰り返し、崩さなかった。――少年は、仕方なく、彼の指示に従った。
ふるさとの村は、一家の者は、“何事も無かったように”少年を迎え入れた。“何事も無かったように”というのは、村に不在でも、そのまま村に居たとしても、どちらであろうと同じであるという“無関心さ”で、――という意味である。――村の人々は、そうした出来事に慣れ切っていた。少年のような何週間かの不在どころか、何年も姿を見せなかった者がヒョッコリ村に帰ってきても、やはり同じような無関心な反応を見せた。――ただ一人、弟のヤコボだけが、好奇の目で兄の冒険譚を聞きたがった。まだ幼い弟に真実を包み隠さず話す訳にはいかず、少年は数々の奇跡が自分達を救ってくれたという作り話をした。パンや魚が増え、水がワインに変わって、少年達の飢えや渇きを癒した。病人から悪霊が追い出され、見る見る完治した。湖面を走って渡り敵を驚かせ、恫喝の一声で湖の嵐を鎮めた。熱病者や癩者の村を訪れ、彼等を癒した。清い水で洗礼された者は生まれ変わり、人をすなどる老漁師の姿をした神の下で、しばし幸福に暮らすことが出来た。
ソクラテスが気付くと、数瞬前と変わらぬ朝日が目の前にあった。――ほんの数瞬の内に、一ヶ月以上にも及ぶ少年の逃避行の物語を、神はワシに語り尽くしたのか。――改めて、神の御業の偉大さに、ソクラテスは深く感じ入った。
アポロン神は、あるいはその使いのダイモンは、ワシに何を伝えたかったのだろう。あの十三人の少年達を見舞った悲劇。十二人の最後に付き合わされ、翻弄され続けた少年。神がワシにメッセージを送る時、それはワシの生き方と無縁でないことが殆どだ。あの少年達が、ワシの人生に、どう関わってくるというのだ?
ソクラテスは神に、昇る朝日に、感謝の祈りを奉げ、その場を立ち去った。――後で知ったのだが、実は彼はあの野原に、丸一昼夜立ち尽くしていたらしい。同盟軍に属するイオニアの兵士達が、酔狂にも一晩中彼の立ちぼうけの様を監視していたというのだ。とすると、彼が我に返って見た朝日は、実は翌朝の朝日だったということになる。
ポテイダイアの激戦地から生還したソクラテスは、その足でアクロポリス南麓にあるレスリングのトレーニング場に向かった。そこでは、多くの青年達と少年達が、鍛錬に汗を流していた。その中に古い友カイレフォンもいることを、ソクラテスは認めた。
カイレフォンも、ソクラテスに気付いたようだ。感動屋の彼は、ソクラテスに近付くなり手を握り、「よくぞご無事で、――。大変な激戦だったと聞いたよ。我々の知り合いも、大勢戦死したと、――」と早口でまくし立て、その後は声を詰まらせてしまった。
少年達もトレーニングを打ち切り、ソクラテスの周りに群がりだした。カイレフォンに誘導されるまま、皆口々にソクラテスの戦場での武勇伝を催促した。――その武勇伝につられるようにカイレフォンが、にっくきペロポネソスの奴等、ラケダイモン人にコリントス人、奴等に目に物見せてやる! 我等が同盟を裏切った者どもにも、厳しい懲罰を加えてやる! と威勢良くぶち上げた。それを聞き、少年達も屈託無く笑った。
その少年達の笑顔を見て、ソクラテスはガリラヤ湖畔を彷徨う十三人の少年兵達の事を思い出していた。既に街は、“開戦間近”、の高揚感で浮かれていた。何事につけ影響されやすいカイレフォンの頭の中は、早くも戦勝気分で一杯のようだった。だがそんな街の雰囲気に、ソクラテスは厳しく顔を曇らせた。あのポテイダイアの籠城市民達。ぎりぎりの耐乏生活に、彼等は耐え忍んでいた。あの十三人の少年兵達。一人、一人と、無残な最期を遂げ、脱落していった。――あれらと同じ目に、この子供らを合わすなど、余りに忍びない。アテナイの徴兵は十八歳からだが、世のコトワリの乱れた時、あの異邦の偶像否定者どものような境遇に落ちないという保証は、何も無い。
少年達を掻き分けて、一人の青年がソクラテスに近付いてきた。カライスクロスの子、クリティアスだった。少年の頃からのソクラテスの弟子で、弟子中一、二を争う俊英と噂されていた。「先生。お元気そうで、何よりです」言った。
高弟の登場に、ソクラテスの方も敬意を表して立ち上がった。「君こそ。――どうだね。哲学の方の精進は、怠りないかね?」
「ええ。――最近は外交交渉の緊迫化で、どうしても政務に時間を取られがちですが。――何とか時間を捻出して、……。
ところで、今日はいい所でお会いしました。――実は、先生が帰国されたら、相談に乗っていただきたかった者がおるのです」
「誰だい? それは」
「私の従兄弟で、カルミデスといいます。――確か前に、先生も一度会われた事があったと、記憶していますが」
「ああ。憶えているとも。あの頃はまだ、ほんの幼い子供だった。――そうすると今は、もう十代半ばぐらいになっているのか? 子供の成長というのは、速いものだ」
クリティアスが呼びにやり、トレーニング場の入り口辺りにざわめきが起きた。カルミデスとその取り巻きの一団が、入ってきた。
カルミデスは、並み居る少年達の中でも、一頭抜きん出、天使の様な輝きを放つ少年だった。周囲が自ずとその進路を開けるようで、ソクラテス、クリティアス、カイレフォンの所まで何の抵抗もなく進み入り、彼等の真ん中に腰を下ろした。カイレフォンが、聖なるものを見るように、目を細めた。――四半世紀余り後、“三十人”時代の末期、カイレフォンとクリティアス・カルミデスは、民主派と“三十人”派の雌雄を決する戦場で、敵味方に分かれて戦うことになる。そして、三人とも、その戦いで戦死した。
その天使の悩み事を、ソクラテスは聞くこととなった。――「実は、――“思慮深く、健全である”ように、日々心掛け、努めているのですが、それの意味する本質が、よく分からないのです。ただ世間でそう思われているイメージだけを、なぞっているに過ぎないと、思えてなりません。本質が分からぬまま、上っ面だけの演技をしている、役者のようです。――そんな事を悩み始めると、コメカミの上辺りが疼き出してきます。頭痛が治まらず、起きがけから憂鬱でたまりません」声変わりしたての不思議な和音の音色で、天使は告白した。
「それはイカンな。早速治療することとしよう」ソクラテスはカルミデスの頭に両手の平を押し当て、医師の診断の真似事をした。周囲から笑い声が漏れた。「フーム。君に必要なのは、“哲学的治療”のようだな。ワシの診立てでは、体の治療ではなく、プシュケーの治療こそ肝要と出た。頭痛の方は、そこから発する合併症、単なる気の迷いに過ぎん。――問題は、“思慮深い健全さ”の本質とは何か、それさえ解明されれば、君の病はたちどころに快癒するだろう」
「さすがの、“診立て”ですな」クリティアスが笑いながら、お追従を言った。「実は私も、彼に色々アドバイスしたのですが、――納得してもらえなかったようでしてね」少年特有の過剰な純粋さに、クリティアスも手を焼いているようだった。「それで先生を、お待ちしていた次第です」
「そうか。君でも敵城壁を崩せなかったのか。それは随分と難敵だな」ソクラテスは戦場帰りの伸び放題の無精ヒゲを、荒々しく揉みしごいた。「まず、個人でもポリス全体でも、“思慮深い健全さ”が高い徳目として求められる事は、直感的に是認される。しかしそれは、通り一遍の常識に過ぎん。肝心の“思慮深い健全さ”の正体が、不明のままなのだから。それでは余りに、心もとない。
という次第で、まずカルミデス、次いでクリティアス、君達の存念を思う存分聞かせてくれないか。それらを吟味することから、探求を始めよう」
まずカルミデスとソクラテス、次いでクリティアスとソクラテスの間に、縦横な問答が展開された。カイレフォンや少年達が見守り聞き耳を立てる内、早や日は西に傾き、プニュックスの丘とアレイオスパゴスの間に落ちつつある。
しかし、いつもと同じく、そうした探求が解答に辿り着く事は、遂に無かった。“思慮深い健全さ”が、“善い事”だとも、“何かの役に立つ”ものだとも、結論されなかった。やはりソクラテスの哲学は、“無知の知”に導くだけの、無限の差異を暴き続ける“否定の哲学”だった。
だが、その問答や探求の過程の、洞察の深さに感動したカルミデスは、以降ソクラテスの熱心な信奉者となり、忠実な愛弟子となる。“三十人”政権の成立時、裏切られたと思い込み、心に深い傷を負うその時まで。
ペロポネソス大戦の戦端が開かれ、ペロポネソス同盟軍は大挙してアテナイを首都とするアッティカ地方に攻め入ってきた。スパルタを中心とするペロポネソス同盟軍は、陸軍力に秀でている。アテナイを中心とするデロス同盟軍は、海軍力に秀でている。ペロポネソス半島と陸続きのアッティカを、敵陸軍の進攻から守る事は不可能だから、アテナイの指導者ペリクレスは、籠城戦を選択した。アッティカ全土の住民をアテナイ市内へ疎開させ、市への物資搬入はペイライエウス経由で海上から行う。そして優勢な海軍を使いペロポネソス半島を包囲し、海からのゲリラ的上陸攻撃を仕掛ける。
だがその戦略が、思いもよらぬ災厄まで市中に招き入れることとなった。――とにかくアッティカ全土の人口をアテナイ一市で引き受けるのだから、その人口密度は尋常ではない。アテナイとペイライエウスを結ぶ長城の内側にまで仮設の住居が建てられ、人々は肩寄せひしめくように何年も生活することとなった。――そして大量に物資の搬入されるペイライエウスから、あいつも上陸した。全人口の三分の一を殺すことになる、致死的疫病である。――さらにこの疫病で指導者ペリクレスまでが命を落とすこととなった。大戦の初頭アテナイは前頭葉を失い、以降頭脳の残った部分の命じるままさ迷い歩く事になる。
目の前で展開されるペロポネソス軍の焦土作戦と、初めて経験するパンデミックと、――アテナイ市民は恐慌状態に陥った。――ペリクレスの残りかすのような政治家達が、次々登壇した。――中でも、民主派のクレオンは、最初の過激なポピュリスト政治屋だった。それまでの政治家の演説は、礼儀正しく節度を保って行われたが、彼のそれは、壇上で声高に叫んだり、誰彼構わず罵倒したり、役者もどきのゼスチャーを交えたり、するものだった。そして、大言壮語し、民衆を激しい口調で煽り続け、極端な民主主義と主戦論とを説き続けた。つまり、ヒトラー型演説を創始した人物だった。以降この系譜は、クレオフォン、カリクラテス、等々と続く。
一方疫病は、数年に渡り猛威を振るい、その後も何度かぶり返した。
アテナイ人は、疫神であり医療の神でもあるアポロンを、その生誕地デロス島に祭った。疫病退散を願い、デロス全島を二度に渡り清めた。(一回目には、島の全ての墓地が取り払われ、島での出産および死が禁じられた。二回目には、全島民が移住させられ、島は無人となった。)
また、アポロンの息子で医療技術を受け継いだアスクレピオス神を勧請した。社は、アクロポリス南麓の、聖なる泉の湧く地に建立された。(境内には、眷属のヘビがうようよしていた。)
ソクラテスもこの疫病に罹患したが、幸い軽い症状だけで済んだ。アゴラ辺りでうつされたのだろう。家で少し寝込んだだけで治った。(当時の彼は、まだ独身だった。)
そのアゴラでは、大きなテントが張られ、医師達が頻繁に出入りして治療と看護に明け暮れていた。あちこちの空き地やギュムナシオンに医療テントが張られ、それでも足りずとうとうアゴラにまで進出してきた。もっと重篤となり、手の施しようがなくなると、プニュックスの丘の台地に移される。そして遂に動かなくなると、ディピュロン門を抜けケラメイコス墓地の仮設安置所に運び出された。
そのアゴラのテントで、陣頭指揮を取り立ち回る一人の若い医師を、ソクラテスは目撃した。まだ三十代の若さだが名医の誉れ高い、アスクレピオス教の一大拠点、医療のメッカ・コス島出身のヒポクラテスだった。彼もまた、アテナイに招かれていた。
患者達は高熱に浮かされ、地面に敷かれた布の上を殆ど裸でのた打ち回った。ある者は激しく痙攣し、ある者は頻繁に水を求め、ある者は吐くものが無くなっても吐き気に襲われた。ヒポクラテスらは患者の腫れ物の噴き出した皮膚を清浄に保ち、充分な水分を与えて廻り、さらに火で病の源を焼き殺す策を考案したが、どんなに精力的に働いても、ただの気休めに過ぎなかった。あらゆる薬が試されたが、どれが薬効を持つのか、皆目見当が付かなかった。
こうなると、神を敬おうと汚そうと、法を守ろうと破ろうと、どちらでも同じである。人々は刹那的となり、道徳心を投げ捨て、ポリスの規範は崩れ去った。ポピュリスト達のアジ演説だけが威勢がよかった。目の前の恐怖から逃れるために、クレオン達の雄叫びに歩調を合わせ、怒号を上げ続ける民衆達。彼等は、ポリスの内外に“敵”を求めた。和平の機運は、湧き上がるたびに庶民の怒号にかき消された。何かと口うるさく“徳”だ“修身”だと説く上流階級のお偉いさんや雇われ教師達を、目のかたきにし吊るし上げた。
クリティアス達は歯噛みしていた。これら、目先の利益と、安全と、僅かな優位を求め、価値を転倒させ、正義と真理の見えなくなっている大多数の者達に。そうした者等に反発し、強く軽蔑し、相反する冷たい怒りを内に燃やした。ソクラテスに、思いの丈をぶちまけた。「こういう時代こそ、かの“思慮深い健全さ”を、持ち続けなければいけないのではありませんか」――“思慮深い健全さ”。その正体は、いまだ未知のままだったが。
焦ってはいかんよ、クリティアス。ソクラテスは、クリティアスをなだめた。焦りは理性を曇らせる。こういう時はゆっくり時間をかけて“哲学”を醸成させ、その芳醇な思弁の力でアテナイを立て直すのだ。――クリティアスにもカルミデスにも、その他の弟子達や子供達にも、あのガリラヤ湖の十三人の少年兵のような悲惨な運命を辿らせたくはない。そのためにもワシは、“哲学”の確立に邁進せねばならん。イオニア派のような自然哲学ではなく、“人倫”を中心テーマに据えた、新しい哲学を。――だが、皮肉にも、そのソクラテスの哲学こそが青年を堕落させたと、後世烙印を押される事になるのだが。
クリティアスの悲憤は収まらなかった。あたかも、“思慮深い健全さ”の正体は、“内に秘めた冷たい怒り”であると、断定したとでも言いたげに。――ソクラテスは愛弟子の肩に手を掛けた。そして、ペリクレスの命で新装成ったパルテノンの正面破風を見上げるよう促した。そこには、アテナイを守護する女神アテナの峻厳に舞い上がる姿があり、見上げる二人と運命的に目が合った。――だが、その目を落とすと、今度は避けようもなく、遠くプニュックスの丘を覆い尽くす疫病人達の朽ちた寝床のモザイク模様が、二人の眼前に広がった。
もうアテナイの黄金時代は、終わったのかもしれません。クリティアスが、静かに師に告げた。パルテノン始め全てが眩く輝くような時代が終わり、屍累々たる荒野を突破せねばならぬ時代が始まったようにも思われます。こんな時代に、哲学の完成など可能なのでしょうか。我々は、最終的に、どこに到達することになるのでしょう?
――結局、“思慮深い健全さ”の本質は未知のまま、その正体は“内に秘めた冷たい怒り”なのであろうと見切り発車して、クリティアスは突っ走った。従兄弟のカルミデスも巻き込んで。一途に、最終解答を目指して、――。
《ソクラテスが目覚めると、クリトンが真剣な眼差しでソクラテスの寝顔をジッと見詰めている視線と、目が合った。――何事か? ソクラテスは、まどろみつつも、瞬間たじろいだ。
「何だ、一体? こんなに早く、……。――それとも、もう遅い時間なのか? 寝過ごしたか」ソクラテスの方から、尋ねた。
「いや、遅くはないよ。まだ夜明け前だからね。――あまり君が気持ちよさそうに眠っていたので、起こさずにいたのだ」クリトンが答えた。
「よく、看守君が入れてくれたね」
「鼻薬の効き目は絶大だからな」
「それならなお、……」ソクラテスは上半身を起こした。「何故こんな早くに、来たのだね?」
クリトンは立ち上がると、体を回し一度ソクラテスに背中を向けた。それからまた向き直り、返答した。
「実は、――悪い知らせがある。――それも、二つ、……」
ソクラテスには、ピンときた。「例の船が、いよいよ帰ってきたか」
「ああ、その通りだ」とクリトン。「スニオン岬を通過したとの報が、早馬で届いた。ということは、今日明日中にも、ペイライエウスに入港するだろう」
二人はしばらく無言のまま、この事実の意味を噛み締めていた。刑の執行は、船の帰投の翌日になることが多い。つまり、明日か、明後日だ。
「で、――もう一つの、悪い知らせとは?」気をとり直して、訊ねるソクラテス。
「脱獄計画の方だ。――例の、眠り薬の薬草の件だ」クリトンは、いつも持参する折りたたみ椅子に、改めて腰を下ろした。「八方手を尽くしたが、どうしても量が集まらない。クサンティッペさんなんか、阿修羅の如き形相で駆けずり回ったんだがね。――次善の策で、シモンの工房を引っ掻き回して、痺れ薬やら下剤やら、使えそうな薬草をありったけ掻き集めてみたが、それでも足りん。――毒草だけは、何故か大量にあった。アテナイ全市民を殺せそうな程の量がな。だが、まさか君一人を逃がすために、市民を大量虐殺するテロを引き起こす訳にもいくまい」クリトンは、困り果てたというような顔をし、肩をすくめた。
「そうか。――ダメだったか」クリトンの諦めが、ソクラテスにもうつった。だが、これで迷い無く、潔く死ねる、とも思った。
「――待ってくれ!――まだ、諦めるのは早い」クリトンが、硬い表情のまま、後を継いだ。「今日はその事を伝えに、こんな早くからやって来たのだ。――弟子や友人達にも、内緒にしておきたいからな」そして、いつぞやと同じく、腰袋から一本の枯草を取り出した。以前のそれと、同じもののように見えた。
「少々危険な方法だが、――今度はこれを使う」
「何だ? それは」いつぞやと同じやり取りが、繰り返された。
「憶えているだろう? シモンのやった実験を。――子鹿にこいつを飲ませて毒殺し、しばらくしてから生き返らせた。――つまり、仮死状態にする薬だ」
クリトンの言わんとしている事が、――ソクラテスには即座に理解できた。だが構わず、クリトンは説明を続けた。
「毒ニンジンの解毒薬は、既にある。だが、呑んで死ななければ、死ぬまで呑まされ続けるだけだ。しかしその時こいつを一緒に服用すれば、刑務委員の検死をパス出来る。――死体は自宅に持ち帰られ、葬儀が執り行われる。が、葬儀の最中、死体は忽然と消えてなくなる、という寸法だ。後日、テッタリアで君が暮らしているという噂が、アテナイの巷間で囁かれることとなるだろう」
「そんな噂が流れて、あるいはアテナイ当局がそれが事実と確認して、――君達はどう弁解するつもりだい?」
「さあな。――まあ、“神の起こした奇跡に違いない!”とか、“神々は、あの賢人の死を拒み、まだ精進せよと御命じになったのだろう”とか、空っとぼけておくよ、いつもの君みたいに。――世間の人々も、そんな“奇跡物語”で、納得してくれるだろうよ」
死者の復活など、神への冒涜ではなかろうか。――不死の神々に対し、死すべきものの筈の人間が、蘇る。――余りに薬効が冒涜的だったので、さすがのシモンもそれを公けに出来ず、秘密めかした暗号で獣皮紙の中に書き留めたのみだった。あの獣皮紙は、シモンの残した膨大な実験記録とともに、工房の書棚の上に積み上がっていた筈だが、その後どうなっただろうか、……。
……何も、そこまでしなくても、とソクラテスは思う。しかしその半面、そんな神の御業にも等しい奇跡を実現し、神やダイモンどもにひと泡吹かせてやるのも小気味よい、とも思った。――ダイモンは、過去彼の人生で、唯の一度も間違った忠告をしたことがなかった。ソクラテスは、自らのダイモンに全幅の信頼を置いていた。だが、それらがすべて、“マヤカシ”だったとしたら、どうだろうか。
ソクラテスはアポロンの神託を受けて以来、大戦中の堕ちていくアテナイを支え再建するため全力を傾注してきた。そしてダイモンは重要な局面の都度、ソクラテスに取るべき道を指し示した。――しかしそんな三十年に渡る蜜月が、敗戦後すべて覆された。彼の努力は悉く無駄であったことが、いやむしろ害毒でさえあったことが、明らかとなった。
そして、ワシの死後の未来史もまた、デタラメなワシの分身を多数生み出しその後の哲学史を惑乱するに至った。これらが、神々やダイモンの企んだ、“正史”となった。――さらに、そうだった。あのガリラヤの少年の味わった悲惨も、この“正史”の一部なのだった。
こんな“正史”は、無かったことにした方が、いいのではないか? チャラにして、――その後どう転ぶかは分からぬが、新しい未来に賭けた方が、まだマシでは?
――だが、うがった見方をすれば、それこそが、新しい未来に賭けることこそが、新たなムーシケーの創作であるとも取れる。――さながらナイルデルタの大氾濫が、ナイルの流れを全く別のものに変えてしまうように、ギリシャ哲学も、ヘレニズム諸国も、ローマ帝国も、西洋文明も、それに巻き込まれる他文明の悲劇も、全て一まとめに御破算にして、新しい流れへと未来史を書き換える。――これ程壮大な、“新たな”ムーシケーの創造が、他にあるだろうか?
『しかしそうすると、――奇妙な事にはならないか?』寝台の右隣りに胡坐をかいて座っていたソクラテスの片割れが、そこで思慮深げに口を挟んだ。『神は、ダイモンは、長年に渡り誤謬無くワシを導いてきた。だがそれが、丸ごと誤謬だったと知れた。それどころか、悪意を持って、ワシを騙し続けてきたのやもしれぬ。――だがその間、全く同時に平行して、奴等はムーシケーの創作も呼び掛け続けてきたのだ。――二つの、相矛盾する指針を、一緒に示し続けてきたことになる。ワシに詩才が無い如く、そもそも哲学的営為とムーシケーの創作とは、二律背反の関係なのに、……』
「こいつは、解毒薬とともに、毒ニンジンの杯に混ぜて一緒に飲むのが一番いい。それが叶いそうになかったら、酒に混ぜて、直前に飲んでおくか、直後にすぐに飲む。今生の酒を一杯飲ませてくれ、とか何とか言ってな」クリトンが手筈を説明していた。「シモンの実験は何十遍と繰り返されたが、一割程蘇生に失敗したようだった。被験体の体重や体調によるようだが、……。まあ、脱獄ともなれば、どの手段を選択しようとも、それなりの危険は伴うものだよ」説明は続いていたが、ソクラテスの耳には余り届いていなかった。
『そうだ。分かったぞ!』そこで突然、片割れが素っ頓狂な雄叫びを上げた。『神は、自信がないのだ! 確信が持てないのだよ!――あるいは、自己否定の神なのかも知らん。自らを、全否定したいのだ!
――だから、一方で“正史”に導きながら、同時に別の未来史の創作を促していた。つまり、“丸投げ”したいのだ。この世の将来の成り行きを、ワシに丸投げしようというのだ。――ワシに、“新しい神になれ”とでも命じる気か? “我が仕事を相続せよ”とでも告げているのか?』
「さて、そこでだ」クリトンが構わず喋り続けていた。目の前の友が何を思い巡らしているかなど、想像すら出来ず。「最後の日に持ち込む宴席用の酒壺に、問題の薬を濃く煎じた物を入れてくる。ホラ、昔君の家でやったシュンポシオンで、シモンがワインの蒸留したのを入れて持ってきた小壺があったろう? 憶えているかい? あれが奴さんの工房の棚の上から見付かったんで、あれを使う。後は、最後の酒宴の混乱の中で、酒杯に注げばいいだけだ、……」
「ワシに、責任が担い切れるだろうか、……」
「何だって?」突然、脱獄計画の説明を中断して発せられた友の言葉に、クリトンは問い返した。
「ワシに、新たなムーシケー創作の、責任が担い切れるか、……」
「新たなムーシケーって?」クリトンはしばらく考え、そして言った。「あの、ヘボいアイソーポスもどきの、詩のことか?」
「ああ、いや」ソクラテスは苦笑いして、弁解した。「脱獄に伴う責任を、担えるかと自問したのさ」
新しい未来は、“正史”のそれよりもっと悲惨なものになるかもしれない。何しろどうなるか、それを知るためのヒントがこの広い図書館のどこを探しても、微塵も見付からないのだ。そんな未来に、ワシの責任で、第一歩を踏み出せるのか?――神が“正史”に責任を持っているように、今度はワシが、新たな未来史、ムーシケーに責任を持たねばならない。ムーシケーの創作が、これほど大きな責任を伴うものだったとは、……。
『ならば、責任を逃れるか? またしても。――公人としての責任を散々逃れて生きてきた、これまでと同じように』片割れがまた言った。言いつつ、彼は腰を上げ、クリトンの指先から薬草を奪わんと試みるように、殆ど触れる程それに手を伸ばした。ドッペルゲンガーのその大胆な悪戯が、しばしソクラテスをあわてさせハラハラさせた。『神は、責任を取って決断せよと、迫っているのだろう?――そういう神自身は、責任をそっくりこっちに移し替えて、肩の荷を下ろそうとしているくせに』ますます大胆に振舞いつつ、片割れが彼にさらに迫った。『そんな神やダイモンに、義理立てするのは最早遠い過去の話だが――だからといって、お前はどこまで、いつまで、逃げ回り続ける積もりなのだ?』
「まだ、そんな事を迷っているのか!」クリトンが、上段から力ずくで切り下ろすように、ソクラテスの悩みを否定した。「誰も君の責任など、問いやしないよ。アテナイでも、テッタリアでも」
だがソクラテスの中では、かくの如く、またぞろ例の自己内問答が、グルグルと際限無く廻り始めていた。――クリトンの言う通りだ。この期に及んで、もう後二日三日しかないというのに(最後の夢の中の彼としては、もう半日しか残っていないというのに)、ワシはまだ決められないのか、……。
「じゃあ、こうしよう」クリトンが言った。「君は最後の日まで、迷っているがいい。――そして脱獄の当日、私が杯を君に渡す素振りをし、例の小壺に手を掛けたら、その時飲むか飲まぬか意思表示してくれ。
ただし、酒宴の始まる前に、白黒だけははっきりつけるとしよう。――酒宴が始まってからでは、何かと混乱する。それに小壺の中味を酒だと勘違いして、飲もうとする奴がきっと出てくる。――不慮の事故は、避けたいからね」》
*
「先程あなたが蘇らせたガリラヤ湖の幻視の中で、兄イエスから不思議な話を聞いた、弟のヤコボと申します」胸像の一つ、貧相な乞食坊主のなりをした中年男のそれが、不意にソクラテスに話し掛けてきた。
「イエス?――金縛りの中で呼び掛けてきた、あのダイモンの事か?」
「ハイ。――“イエス”は、ヨシュアのギリシャ語形。私の兄の事です」
「とすると、――ワシの幻視の中に過去幾度も現れ、我が人生に絡んできたあの少年は、あなたの兄上なのか。ダイモンとなったあなたの兄上が、少年時代の自分をワシに見せていた訳か」
「そうかもしれません」
「フーム。――すると、――ダイモンがそう呼び掛ける以上、何かワシのムーシケーのヒントになるようなものが、あなたの兄上の教えか人生の中に、あるという事なのだろうか」
「兄のする事は、私には計り知れません。ですが、その可能性は充分あるでしょう」
ソクラテスは迷い道の先に、希望の小さな光を見付けた気がした。プラトンを魅了した異民族の知恵の中に分け入る事は、無駄じゃなかった。
「ならば早速、あなたの兄上について教えてくれないか。ワシにはもう、夜明けまでの僅かな時間しか、残されていないのだ」
汚れ、やつれた面相の乞食坊主は、僅かに首を振り、ソクラテスの手元の書物を指し示した。
「今あなたが読まれていた、そしてその中で兄と出会った書物は、“新しい約束”と呼ばれるものです。『70人訳』のヘブライの聖典が“古い約束”であるのに対し、神の約束が更新されたという意味で“新しい”のです。
兄の事は、その書物と、それに関連する多くの典籍の中に、まとめられています。私と兄の、幼い頃からの思い出も、……」
「出来れば、――ダイモン・イエスから直に、話を聞きたいのだが、……」
「それは、無理です。――何故なら、兄は、あなたと同じで、自らは何も書き残さなかったのですから。
残された記録は、これもあなたと同じ、弟子達の書いたものばかりです」
「そうか」ソクラテスは、瞬間首をうなだれ、考え込んだ。「では、ワシの場合と、同じ危惧があるな。――ワシの弟子達は、好き勝手放題、ワシの教えを捻じ曲げ、おのれの考えに相応しいようにワシのイメージを捏ねくり回し、挙句それぞれの書物を書き残していった。それと同じ危惧が、ダイモン・イエスにもあるのではないか?」
「仰る心配、よく分かります。――実際、その“新約”の中にも、又聞きの又聞きにさらに編集を加えたような、随分と“粉飾”の甚だしいものが紛れ込んでいるのです。
ですからこそ、兄を幼い頃から直接見知っている私の書き残したものが、兄の本当の姿を一番正しく伝えていると、自負している次第です。――それに、この図書館の蔵書とて、永遠のものではありますまい。カリマコス司書殿達の書物の内容を後世にまで正しく伝えようとする努力もむなしく、いずれは私の書いたものもその他の多くのものも、焚書され、風呂の焚き付けにでもされる時代が来るやも知れません。言葉はすぐ空中に掻き消えてしまいますが、書物とて煙となって消えてしまう運命は同じです。ただ、一瞬か、しばらく持つか、の違いだけで。――そうなれば、あなたは弟子達の所業を嘆いておいでだが、それどころでは済まない。今より、もっと酷い事になる。あなたも、そして兄も、どんなとんでもない“悪魔”として後世に語り伝えられる事になるか、あるいはもしかするとどんな神聖な“神”として祭り上げられる事になるか、知れたものではありません。
ならばこそ、今、読める時に読むべきものをお読みになって、正しく判断していただきたいのです」
こうして、ヤコボの熱い勧めに促され、ソクラテスはダイモン・イエスの物語を、ダイモンがまだ無垢の少年の時代から読み進めることとなった。
「私と兄の生まれたナザレ村は、ガリラヤ南部の荒涼とした丘の上にある人口わずか数百足らずの寒村で、『地の民』と蔑称される零細農民ばかりの住む集落でした。村には、壊れかけた石と泥の家と、干乾びた耕作地しかなく、地の民は自給自足で何とか生活を成り立たせていました。地の民は勿論無学・文盲で、また教養を授けられる機会も持っていませんでした。村の共同小屋にアラム語の聖典が一冊保管されていましたが、読める者は誰もいません。
後世の福音書家達は、兄がベツレヘムで生まれたとか、エジプトへ一旦非難していたとか、好き勝手なことを書いていますが、勿論みんな大嘘です。これらは、ダビデの系譜を偽ったり、預言者の言葉に辻褄を合わせたり、出エジプトの故事になぞらえ勿体を付けたりと、つまりは悉く粉飾です。
本当の兄と、そして私達一家は、このナザレで生まれ、育ちました。そのまま、無学で、日々飢えと追いかけっこの貧農として、一生を終える筈でした。
ですが、丁度兄の生まれる少し前、決まりきった一生を激変させる事態が発生しました。――それまで長くユダヤを牛耳り、神殿などの建設事業に明け暮れていたあのヘロデ大王が、死んだのです。
ガリラヤ人は、子供の頃から戦の中で鍛えられ、成長すると戦士になり反逆者になると言われる程です。この地方は、エルサレムからも遠く、千年来根っからの反逆の気風みなぎる土地柄でした。あのソロモン王にすら、逆らったといいます。
ローマの傀儡だったヘロデ大王が死ぬと、早速自称メシアが次々出現し、ガリラヤ全土がローマに対し一斉蜂起しました。そして、ローマによる徹底的な報復、すなわち破壊と殺戮、を被りました。兄が10歳になる頃までのこの地は、暴力や略奪が横行する、地獄に最も近い場所でした。その記憶が、兄のトラウマになっていたのです。
当時叛徒達を組織立てていたのは、“ガリラヤのユダ”と呼ばれた指導者でした。彼は、かつてヘロデ大王がガリラヤ知事だった当時討伐した、叛徒のリーダー・ヒゼキヤの息子と伝えられる人物で、ガリラヤ地方の中心都市セッフォリスを襲い、そこの武具や軍事物資を略奪しました。セッフォリスは、ハスモン朝時代からガリラヤの行政の中心で、ヘロデ大王はここを軍の拠点とし、大量の武器や物資を蓄えていたのです。
ガリラヤのユダは、ツァドクという怪しげなファリサイ人を味方に引き入れ、ローマ人が行おうとした住民登録への反感を契機に、熱烈な敬神、反ローマで理論武装し、勢力を一気に拡大して、反対派を糾合いたしました。彼等は、“敬神攘夷の徒”、と呼び習わされました。
ユダの出現で、それまでの有象無象のメシア状態よりは、少しはましな反乱軍が組織・秩序立てられました。それまでは、野盗まがいのメシア達、預言者まがいのいかさま師達の、跋扈する時代だったのです。セッフォリス近郊のナザレ村は、取った取られたの最前線となり続けました。野盗や反乱派が奪い、ローマ軍や大祭司配下の兵が取り返す。これの繰り返しでした。支配者が入れ替わるたび、村人は忠誠を誓わされました。何度も簡単に宗旨替えし、上辺だけの忠誠と疑われた者は、拷問にかけられ、挙句殺されました。簡単に宗旨替えしない者は、拷問抜きで即殺されました。占領の都度、反対のことを唱えるラビが村々を廻り、各々の思想の宣布にこれ努めました。
シーソーごっこが繰り返されるたび、村を悲劇が襲いました。両陣営の支配は、苛烈さをエスカレートさせていきました。田畑は荒らされ、収穫物と女子供は奪われました。男は雑兵となることを強要されました。親しい人々、家族の者、親族の者、近所のおじさん、おばさんが、次々殺されました。最初の頃は、一人一人葬式を出していた村人も、その内そこら中死体だらけとなり、ただそれらの処理に日々追われるようになりました。半死体、かたわ者も増えました。(支配者が、恐怖を植え付けるため、生かしたまま手足を切り落とすのです。)かたわの家族も増えました。こうした、親を亡くした孤児達、子を亡くした親達、バラバラの家族、それに家を無くした者、居住者を亡くした廃屋が組み合わさり、“擬似家族”を構成しました。村人達は彼等を、憐れみと、ニセの家族と見下す蔑みの感情を持って、見詰めていました。しかし、“次は我が身”と思う恐れが、全ての声を沈黙させました。
支配者は、最初説得で、次いで恐怖で、村を服従させようとしました。逆らった者、考えを曲げなかった者の首を、次々切り落としていきました。切り落とした首を、村の広場の台の上に、幾十と並べて見せしめにしました。反乱軍が支配した時は、偶像の疑いのあるあらゆる絵や彫像を破壊し(子供のイタズラ描きまでも)、華美な服飾を禁止し(といって、はなから村にそんなものありゃしませんが)、華やかな歌や踊りまで禁止しました(こちらの方は、村人達にとって唯一の娯楽でした)。ローマ軍や大祭司達が支配した時は、次々と高い塀を巡らし、村人達を狭いスペースに押し込めて、自分達が良い土地や日当たりや水資源を独占しました。村人達が不満から暴動を起こすと、これを、子供の投石すらも、容赦なく弾圧し、村人を逐一監視し、家宅捜索し、武器を取り上げ、部屋を荒らし、ついでに食料まで奪っていきました。
裏切りと密告が横行しました。村人達は互いに、より親密になり、より疑念を持ち合いました。あらゆる人があらゆる人と敵対し、村を出る者も多く、ある者はセッフォリスやエルサレムで要人を暗殺し、金持ちの邸宅に放火し、ある者は異邦人の偶像を破壊して廻り、ある者は終末を唱えて人々の不安を煽り、ある者は神を捨ててローマ人の名を名乗り立身出世の野望を抱きました。
子供達が、村の広場に集められました。メシアであり、熱情的信仰の徒であるガリラヤのユダの名において、不信心者を石打ちの刑に処すると、宣告がなされました。見ると、広場の中央に、首が一つ地面から突き出ています。まだ生きていました。干しアンズ売りの、子供なら誰もが見知ったおじさんでした。首から下が、土の中に埋められていたのです。恐怖に目を見開き、口を半開きにした、怯えた首でした。
反乱軍の兵達が石を投げ始めました。子供達が目をそむけようとすると、剣で脅され、棒で叩かれ、見続けるよう強要されました。さらに、子供らにも石を投げるよう、司令官から命令が下りました。嫌がり泣きじゃくる子を容赦なく叩き伏せ、その手に石を握らすと、子供は当たりそうもない付近にそれを投げます。そうこうする内、石に打たれた男は目を剥いたまま死んでしまいました。
子供らはさらに、落とされた幾つもの首をささげて村中を練り歩くよう命ぜられたり、首蹴り競技で日々楽しく遊ぶよう迫られたりしました。兄は、そうした首蹴り遊びでは、同世代で村一番のエースでした。
動員した子供達を一人前の兵士にするため、反乱軍は訓練と洗脳に明け暮れました。木製の剣や槍を持たせ、軍事教練するのです。ある日兄は、目隠しをされ、手に槍を持たされ、的に向かって思い切り「突け!」と命じられました。突き出した槍先が、グズリと嫌な感触で何かにめり込むのが、手から伝わってきたといいます。目隠しを外すと、的は、猿轡を咬まされた近所の親しいおばさんでした。兄がものごころ付いた頃から、可愛がってくれていたおばさんでした。彼女の死体が、真っ赤な血の海に浸かっていました。その場で兄は、気を失いました。
ナザレと同様、近隣の村々も支配者がコロコロ入れ替わります。反乱軍の正規兵が、手強いローマ軍や大祭司の兵を相手にするのに対し、たまたま敵味方となった隣村の“懲罰”は、子供部隊に任されました。子供達は、家族を殺すと脅され、嫌々出陣するのです。
日頃親しくしている村同士の戦いとなりました。お互いに顔見知りで、顔を見合わせ納得ずくの視線が交差します。そんな事はお構い無しで、司令官が容赦なく攻撃をけしかけます。何とか一線を越す事は免れたものの、兄は、命ぜられるまま、容赦の無い暴力を振るったといいます。
幼児の頃からの不安な日々と、強要される軍務とが、兄の心を納屋掃除のボロ布の如くにしてしまいました。(兄だけではありませんが。多くの子供達が、同様な状態でした。)兄は毎夜まともに眠れず、眠ると内容を思い出せない悪夢で目覚めさせられました。日中でも、過去の恐怖のシーンが突然思い出され、瞬間白日夢にでも落ちたようにドキリとしました。食欲がなくなる一方、不意に吐き気に襲われます。心も動きも鈍麻していたものが、急に興奮し、活発に動き回り、しばしばおのが体の一部を痣が残るまで打ち続けます。そして、この癖は後年まで残りましたが、頻繁に“おねしょ”をするようになりました。
兄は、自分達を弾圧するギリシャ・ローマ勢力や大祭司ばかりか、自分達を守れないどころか利用しさえする反乱軍までも、激しく憎むようになりました。遂には、主の造りたもうた世界全体をも、呪うようになりました。それが、“悪魔の最大の誘惑”である事は、百も承知していました。ですが、当時判断力の鈍麻していた兄には、この誘惑に抗う術は何もなかったのです。
兄が、『マリアの息子』と呼ばれることに、強烈な疑念を持ち始めたのは、ある光景を見掛けた時からだったといいます。いつもの様に子供達は、廃墟の瓦礫の中をうろつき、ゴミあさりをしておりました。そこで兄は、ゴミの山の下のあぜ道を、ローマ兵に引っ立てられて近くの小屋へと連れ込まれる母マリアを見たのです。
実は兄の、ものごころ付いて最初に残った記憶が、母が誰とも知れぬ無頼の徒に乱暴されている光景だったといいます。半分赤ん坊のような子供の記憶ですから、実際に何があったのかは分かりません。ですが、そうした理由で、ローマ兵に引っ張られていく母を見た時、兄は強く反応したのです。
子供を呼ぶ時は、『父○○○の息子○○○』『父○○○の娘○○○』と呼ぶのが、当たり前の流儀です。兄ならば、『ヨセフの息子ヨシュア』と呼ばれるのが普通です。ところが当時あの地方では、『母○○○の息子(あるいは娘)○○○』と呼ばれることが、実に多かった。戦乱で男が若くして死んでしまうということもありましたが、村人達は、誰の息子(あるいは娘)と呼んでいいのか、確信が持てなかったのです。
強姦や密通は、当たり前の事でした。自分や家族のため、自ら身を売る者もいました。それどころか、恐ろしいことに、野盗まがいのメシア達の中には、兵士を量産するためという名目で、不義密通を奨励したり強要したりするという、律法破りの大罪を犯す者まで現れたのです。彼等は、女は組織の共有財産であると、主張して憚りませんでした。――戦士と村娘の結婚が、奨励されました。生めよ増やせよの容器たる女の数は多い程良く、占領地から拉致されてきた女達、さらには既婚女性まで離縁させられ、この容器に利用されました。何百何千組という、ガリラヤのユダに祝福された集団結婚式が、執り行われました。(残った女達は、容姿や年齢により値踏みされ、資金源とするため奴隷として売られました)
私達兄弟は、皆『マリアの息子(娘)○○○』と呼ばれておりました。のち聖家族といわれた兄弟達の、私も含め、誰が父ヨセフの本当の子で、誰がそうでないのか(野盗やローマ兵の子なのか)、誰にも分からなかったのです。そこで兄は、自分の出生時にも、同じような事があったのではと、深い疑念に囚われた訳です。母が兄を身ごもった当時は、丁度最初の動乱がピークに達する頃でした。村の古老から話を聞き、兄はその事を充分承知していました。
思い余った兄は、密かに父に訊きました。自分は本当に、あなたの息子なのですか。それとも、誰とも知れぬ、ローマ兵か、革命ゴロか、野盗の類の子なのですか、と。――しかし父ヨセフは、寛容な笑いを浮かべるばかりで、黙って答えようとはしませんでした。父の寛容さは、兄弟皆に対して平等でした。我々はその寛容さに包まれ、子供時代を過ごしてきたのです。一方母のマリアは、兄の疑念にそれとなく気付き、お前は正真正銘父ヨセフの子だ、決して父以外の誰の子でも無いと、涙ながらに訴えたといいます。のち兄が、春を売る女の悲劇に終生同情的だったのは、そんな幼少期の苦悩の反映かもしれません。父ヨセフの寛容さを、真似たのでしょう。
出生の事で悩んだ直後の兄は、苛烈で非情でした。丁度この頃アスクレピオス教徒の国境を越えた医師団が、ガリラヤ湖周辺で無料の奉仕活動中でした。異教徒撲滅の荒波に襲われ皆殺しにされたといいます。兄も、この時の襲撃に、率先して加わっておりました。
兄は、自分は“人の子”である、と名乗るのが口癖となりました。たとえ誰の子であろうと、人の子であることに変わりは無い、という思いを込めての名乗りでした。同時に病的に大地に唾を吐く癖がありました。子供時代のトラウマが、終生そうさせたのです。後の信徒達は、それを奇跡を起こす聖なる唾と誤って理解したようですが、本当は無意識の内、神の足台たる大地を呪う唾だったのです。
10年に及ぶ反乱が鎮圧されると、ガリラヤ地方は、ヘロデ大王の息子で、『狐』とあだ名されるヘロデ・アンティパス(あの、洗礼者ヨハネの首を落とした男です)、に分封領として与えられました。
アンティパスは、荒廃した領土の再建に乗り出しました。多くのヘレニズム風の都市や建築物を建て、新来の金持ち達を住まわせました。対して土着の『地の民』達は、沸騰する復興景気の中で、生産手段たる田畑は荒らされ、貧富の格差はますます広がり、新興都市に物資を送り込み都市生活を支える担い手となるか、それも出来なければ労働力の供給源として都市に出稼ぎに行って働くか、しかありませんでした。この時代最も必要とされたのは、次々新築される建築物のための建設労働者です。父も、そのような者の一人でした。元々村ではありきたりの農民だった父ですが、生来器用だったせいか、すぐに一頭抜きん出た職工となりました。
アンティパスがガリラヤ地方の首都と定め、そして自らも居住した復興都市『セッフォリス』は、ナザレ村から歩いてもすぐの場所にありました。やがて兄弟が増え、より多く食い扶持が必要になると、父は兄弟の上の方から順番に伴って、セッフォリスに出稼ぎに行くようになりました。
兄は当初、都市というものが珍しくて仕方なかったそうです。――そりゃそうでしょう。何も無いあんな寒村で、10年以上も育ってきたんですから。――父も、街に慣らすためか、簡単な仕事をさせたり、好きに遊ばせたり、かなり放任主義だったようです。
徐々に父や先輩達の技能を修得しつつ、――自由に動けた兄が興味を持って頻繁に通ったのは、近くのシナゴーグでした。ここでは、貧しい子供達にも、住み込みのラビが初等教育を施してくれていたのです。兄はここで、読み書きや算術をマスターしました。数年遅れて、私も後に続きました。この頃の兄はよく、あの先生のような、貧しい子供達に教える教師に自分もなりたいと、話していました。
今思えば、この時代が一番幸福だったような気がします。父は若く創建で、母はやさしく兄弟の面倒を見、兄や私達は自由に遊び、働き、そして学んでいました。
ある時兄は、大通りに面した大金持ちの館の、新築工事に駆り出されました。ヘレニスト(ギリシャかぶれの離散(ディアスポラ)ユダヤ人)の大商人の館でした。――かつてエジプトでは、寄留者のヘブライの民は奴隷扱いでした。アブラハムの頃のカナンでも、寄留した者は遠慮がちに住まっておりました。しかし当時この地では、寄留者こそが主のようでした。千年来ここに住まう者達は、彼等に仕える立場でした。
白い大理石製の豪勢な邸宅は、半ば以上が既に積み上がり終えていました。ですが、一度灰塵に帰し再建途上にある槌音も華やかな都市の、その固く踏みならされた平らな土地の下に、ガリラヤのユダら反乱軍の十字架上で朽ちた遺骸や、焼け落ちて跡形も無くなった旧セッフォリスの建て込んだ家々の瓦礫が、押し固められ恨みの声も発せられずに埋もれているのを、兄は心に刻むように承知していました。
何台もの荷車に積まれた縦長の石の固まりが、次々運び込まれてきました。厚手の布に包まれ木枠に固定されたそれらを、労働者達は一個数人掛かりで荷車から降ろし、館内に運び入れました。中庭の噴水の脇に設置し覆いを取ると、中からギリシャの女神の石像が現われました。それを見て、労働者達は苦笑しました。彼等の多くが、ほんの数年前まで反乱軍の一員として、異邦人の偶像を破壊すべくガリラヤ全土を駆け巡っていたのです。石像達は、労働者のボロ着よりも、遥かに高級な布をまとっていました。それは、緩衝材の役割に加え、偶像に直接手を触れたくないとする労働者へのせめてもの配慮でした。
石像は、中庭と、宴会場と、応接室の、三箇所に運び込まれました。中庭のそれは神々の像、宴会場のものは哲学者のそれ、応接室は皇帝の胸像、だったそうです。運びながら、兄は涙がにじみ出るのを、止められませんでした。宴会場に並べられたおびただしい数の哲学者達の像に心の中で唾棄しながら、とうとう兄は現場監督に「こんな様を神に知られたら、恐ろしい天罰が下るぞ!」と食って掛かってしまいました。
監督もまた、ユダヤ人でした。「仕方ないだろう」彼は弁解しました。「施主は、ローマ人やギリシャ人や、多くの異邦人と商取引があるのだ。その商売のため、客達を歓待するため、こうした小道具が必要なのだ。施主の注文なのだから、我々は逆らえない」
それでも兄は納得せず、聖典の言葉を次々引用し、荒れ野の熱風が吹き続ける如く非難し続けました。かつて反乱軍が全土で行ったように、そして今も潜伏した反乱分子が隙あらば決行するように、今にも石像達を打ち壊しそうな勢いでした。
「いい加減にしろ! 小僧!」監督の怒りも、兄のそれに煽られ頂点に達しつつありました。「これらの石像はな、かの“石工の神”ソクラテスの作品を模して作られた、由緒あるものなんだぞ! もし一つでも壊したら、お前の首百個でも弁償の利かない高価なものなんだ!」
「“石工の神”ソクラテス?――そんな奴、聞いたこと無い」兄は悪態をつきました。
その悪態を撥ね退けるように、監督はツカツカと数歩進み、立像の一つを指差して兄に告げました。「このお方こそ、“石工の神”ソクラテス様だ!」
ところが、その立像を見た途端、兄の火のような信仰の燃え盛る怒りが、ひょいと立ち消えてしまったのです。その像の男の姿を見て、兄は拍子抜けし、呆気に取られてただ見続けるしかありませんでした。あまりに“ヘチャ”で、ひょうきんな顔をした、小太りの男が立っていました。明らかに、他の堂々とし聡明そうな哲学者達とは異質で、一人だけ浮き上がっていました。それは、神々しい神でも、颯爽とした名工でもなく、それらから一番遠いように見えました。兄が怒りも忘れて、しばらく黙って立ち続けなければならなくなったのは、そんな突発的な事態を納得させるためでした。
監督が革袋から鞭を取り出しました。逆らう奴隷や労働者を痛め付けるには、これに限ります。ただ、それまでこの騒ぎを白い目で見ていた他の労働者達が、監督を睨むような目付きに変わり、三人、五人と兄のそばに寄り、監督と対峙するような格好となりました。それで、監督はそれ以上、動けなくなりました。これら日雇いの中に、反乱派のシンパがいると、当然監督は警戒して掛からねばなりません。
しばらく睨み合いが続きましたが、その時です。彼等の背中越しに、声が掛かりました。「少年(兄のことです)。それは違うぞ」振り向くと、ニヤニヤ薄笑いを浮かべた、長身の男が立っていました。「そのソクラテスは、“石工の神”なんかじゃない。――“哲学の王”だ」
また、妙な事を言い出す奴が現われたと、兄を始め皆が思いました。“石工の神”? “哲学の王”? ソクラテスとは、一体何者なんだ?
「確かに石工もしていたが、サボってばかりで、ほとんど作品も残っちゃあいない。まあ腕は、一流だったようだが。――それよりも、ギリシャの哲学の道で、その名を馳せている。王道を行くギリシャ哲学の、開祖と呼ぶべき存在だ」
「石工も哲学者もやっていたとは、どういうことだ? それに、この奇っ怪でこっけいな男が、本当に哲学者なのか? とても、信じられない」兄は今度は、この新たに現われた男の方に、食って掛かりました。
「人を見た目で判断してはいけない、少年。それでは、怪神シレノスの故事と同じだ。――いや、ソクラテスの場合、あの見た目こそは、彼に最も相応しいと言うべきか」
憎むべきギリシャ・ローマ文化の、その中核たるギリシャ哲学の、さらにまた開祖といえば、ヘブライの民が打倒すべき標的のその中心点にいるのが、この男だということになる。言わば、ヘブライの神の対極に位置する、悪魔の頭目の如きものだ。それが、こんな拍子抜けするような、奇妙で哀れな存在だったとは。今まで100%排除せねばならないと頭から決め付けていたギリシャ・ローマ文化の、そのど真ん中に、兄はこの時奇妙に捩れた興味を猛烈に感じたのです。
長身の男は、この近所で名の知れた、変わり者の学者でした。何でもアレクサンドリアのムセイオンの恵まれた環境でカゴの鳥になるのを嫌い、脱走してきたという噂でした。前を通り掛かり、何やらもめているのが気になって、遠慮もなくズカズカ入り込んできたのです。この学者もまた、立ち並ぶ石像達に、イチャモンを付けました。ただし、勿論偶像云々ではなく、並び方、立ち位置がおかしいというのです。一体、時代順に並んでいるのか? それとも、分野や学派別か? あるいは、師弟関係でか? どういう根拠、秩序で、こうした位置に配置されたのだ?
これには監督も、グーの音も出ませんでした。別に施主から特段の指示はなく、ただ見栄えと作業効率で並べただけだ、彼は弁明しました。
ならば、並べ直せ。見るべき者が見た時、この家の主は哲学に格別の造詣があるなと瞠目するような配置を、私が指示してやろう。学者は提案しました。
監督に、特に反対する理由はありませんでした。ただ、後でこの学者に一杯おごらなくちゃいけないなと、ふところ具合を少し心配しただけで。――そして、並べ直された見知らぬ哲学者達の位置関係を、一度見ただけで兄は全て記憶してしまいました。それを知った学者は、兄を“妙に賢い小僧”と呼んで気に入り、以来兄は書物だらけの学者の屋敷に入り浸るようになったのです」
*
ソクラテスは、自宅でのシュンポシオンの続きを、思い出していた。――さすがにしこたま飲んで、夜気に当たりたくなり、クリネーから立ち上がり中庭に出た。シモンと、弁論家のリュシアスも、彼のあとに続いた。二人とも、ソクラテスと同年輩の壮年である。若い連中は、まだ酒席に留まり、飲み続け、暴れ続けているようだ。
中庭に転がる彫り掛けの石像の中に、シレノスの坐像があった。太鼓腹をこちらに向けて、ニタニタ笑っている。ソクラテスがその前に立つと、双子のようにそっくりだった。もしかすると、自分をモデルにして、彫ったのかもしれない。
シレノスは、ディオニュソス神の従神で、ギョロ目に獅子鼻、禿げ上がった額に、小太りで太鼓腹の体躯、といったさえない老人の姿をした神で、つまりはソクラテスにそっくりだった。だがその外見も一皮剥けば、的確な予言を下すとてつもない賢者であった。そうした点でも、ソクラテスはしばしば、その外見・中身ともに、謎の道化神シレノスにたとえられる。
春の祭典ディオニュシア祭で、ディオニュソスの像の乗った山車を囲む仮装行列に、ソクラテスはしばしば何の仮装もせず普段通りの格好で紛れ込んだが、それだけで彼がシレノス役だという事は誰の目にも明らかだった。人気者のソクラテスには、毎年頼むぞと市民達から声が掛かり、本人もその役を大いに楽しんでいた。
「シレノスの光明にお伺いを立てたい」坐像を挟んで、ソクラテスと向かい合ったケファロスの息子リュシアスが、突然問うてきた。「先程の『靴屋風』、ヒッピアス殿との論戦の、真意や如何」シレノスの外見と中身の違いを際立たせるため、シレノスの木像を観音開きに開けると、中から光明の神の小さな像が現れるというシカケが、広くヘラス中に行き渡っていた。それと同じように、リュシアスの鋭い視線は、ソクラテスのヘラヘラした笑顔の奥底を暴こうとしているようだった。「“目には目を、歯には歯を”の応報の正義は、むしろ“不正”であると、あなたは吟味された。――だがそれは、あくまでも個人の立場。社会や法の側から見れば、果たして不正と言い得るのでしょうか」どうやらリュシアスは、ヒッピアスが休戦を申し出た議論の続きを、挑みたい風だった。
「と、言われると?」シレノスの像の隣に、これまた造り掛けの盲目のホメロス像が、転がっていた。
「“奴隷の正義”、とでも名付けねばならぬでしょうか。――あなたは、敵を害する事は、己を卑しめる事になり、つまりは不正であると結論された。だがそれでは、この現実世界で、敵に打ち負かされ、死ぬか、よくても奴隷の身分に落とされるかでしょう。自分では高潔さを保てたと満足しても、所詮は奴隷の身の唱える哲学に過ぎません。人々はそんな哲学に、耳を傾けるでしょうか」
「奴隷の正義とは、……。これは手厳しい」“正義”とは、敵味方の損害や利益のバランスを取ることでも、味方を利し敵を害することでもなく、ただ絶対の“善”や“徳”の基準に照らし、判断されるべきものである、とするのがソクラテスの主張だった。だがこうした考えは、それまでのヘラスの常識に、真っ向から対立した。「哲学者たる者、絶対の善や徳を目指すべき、という生き方はお気に召しませんか?」
「現実からあまりにかけ離れていると、申しているのです。――この戦乱の打ち続く世では、そうした意見に耳を貸す者は皆無でしょう。日々の戦いにいきり立った者達は、むしろ皆、あなたに非難の矢の嵐を降り注いでくると思いますよ」スパルタ勢力との戦いは、既に二十年近くに渡っていた。――ペルシアとの戦争。次いで、スパルタとの戦争。さらに、絶えることの無い、ポリス間のイザコザ。世は戦乱に満ち、戦乱の中に人の世はたゆたっている。――イエスの時代のかの地もまた同様だったと、ソクラテスは思い出し、嘆いた。巨大帝国ローマの辺縁部は、国境を巡り、属州の独立を巡り、争いが絶えなかった。中でもとりわけ、ヘブライの民は、思想や文化が同化される事を潔しとせず、そのため他民族に十倍する悲劇を繰り返した。
「そして、先程申し上げた、社会や法の側の問題がある。個人の信念は置くとして、――社会や法が平等の取り決めをしなければ、とても社会秩序もポリス間の講和も、達成できるものではない。これもまた“正義”と呼ばずして、何と呼びましょうか」
「ワシも重装歩兵として、ポリスの存続のため戦ってきた。決して、口先だけの平和主義者だとは、思われたくない。
だがね、――」
ソクラテスはシレノス像を、次いでホメロス像を指差した。
「このホメロスは、シレノスと共に注文されたもので、ディオニュソス劇場に奉納する予定なんだが、何時になったら仕上がることやら」閉じられたホメロスの両瞼を、こなれた石工の手付きで撫で回した。
「ホメロスの像を注文される度、ワシはつくづく思うのだ。これ程までに愛されるホメロスとその詩だが、彼にこれらの詩を作らせた真意は、どういうものだったのか、と。
普通には、英雄を称え、戦意を鼓舞するものだと思われているだろう。だがそれは、違うんじゃないか。その裏に隠された詩人の本当の気持ちを、皆分かっていないのではないか。ホメロスの顔を、口を、目を、そんな風に思い、呟きながら、ワシは一ノミ一ノミ彫っているのだ」
――コーン。カーン。コーン。カーン。――
ソクラテス宅のあるアロペケ区には、石工が多く住む。近くのヒュメトス山等から切り出される大理石を、ここで加工するのである。
そのため、こんな時間になってもまだ、ノミを石に打ち付ける音が、夜の闇に紛れて、方々から不意を打つように聞こえてくる。
――コーン。カーン。コーン。カーン。――
「ホメロスの、真意とは?」とリュシアス。
「それはな、――シーソー式に起こる戦、無限に連鎖する憎しみの、虚しさ、愚かしさ、ではなかろうか。
千年近く前も、今も、同じことを延々繰り返している。あらゆる時代、あらゆる場所を通じ。正義の遂行のし合い、復讐のし合い、意地の張り合い、メンツの立て合い。――これらを見せるのに、トロイアの大戦を題材に取ったのではないか。トロイアの良心を貫いた王子ヘクトル、絶頂から奈落へと転落した英雄アキレウス、理不尽な逆恨みをかった王女ポリュクセネー、友の身代わりとなった戦士パトロクロス。彼等の哀れな末路。勝者の側も、不義に仕返しされた総大将アガメムノン、放浪の運命に弄ばれた知将オデュッセウス、難破し遠い地へと漂着したヘレネの夫メネラオス。逃れるすべもなく、皆惨めな悲劇に落ちた。これらの連鎖が延々続くよう、促す神々。――こうした真実を、人々に、神々に、訴えたくて、彼は盲目の記憶力が蓄えられる限りの愚かな真実を、吟じ続けたのではないか」
「ですが、千年前からそうした事が詠われ続けているということは、それが文字通り“真実”だからでしょう。そうした、愚かしいことが。――愚かしいが、避けようの無い、“真実”だということなのです。――それを少しでも和らげるために、社会や法の“平等”という正義が、人の知恵として工夫されたのではないでしょうか」
「法はすなわち、人の知恵か。言葉は悪いが、“その場しのぎ”の。
だが哲学者の立場としては、絶対の法、絶対の善、絶対の徳を、信じたいところだ。人のプシュケーの追い求める、絶対で完全なそれらを。完璧な哲学者を、目指すのならね」ホメロスの瞼の閉じられているのを、さらに確認するように指を押し当てた。そして彫り掛けの石像に手を置いたまま、無口な大男の方を振り返った。
「シモン。君はどう思う?」
「そうさな」無口な大男は、またこのせりふから始めた。
靴屋のシモンは、靴でもサンダルでも、利用者の正確な足型を取ることで、一躍名を馳せた。それまでの、ただ革袋に包んで紐で縛るだけというチャチな靴ではなく、本当に履く者の足がスッポリ収まる絶妙に採寸された魔法のような靴なのだ。彼はさながら、革の彫刻師だった。たちまち、彼の店は大評判となった。サンダルも、革紐が巧みに編まれ、つま先とかかと部分がガードされた、それまでのサンダルとは一味も二味も違うものを工夫した。これでまた、彼の名はポリスの境界を越え、近隣全土に鳴り渡った。――ソクラテスにも、「サンダルを作ってやろう」と言って、足型を取って特注のものを作ってくれた。だが、あいにくなことに、ソクラテスは四季を通して裸足で過ごすことをモットーとしている男だった。特注のサンダルは、家の奥に大事に仕舞われ、とうとう終生主人の足を飾ることはなかった。
シモンはまた、諸々の薬を扱い、火を扱い、揚水ポンプや噴水で水を扱った。加工した水晶を通して物を見、歪んで見えたり大きく見えたりする事に気付き、ピラミッド(古代ギリシャの菓子)のようなそれに光を通して虹を出現させ、アゴラに集まった者達を仰天させた。
毛皮と琥珀を擦り合わせ、琥珀に毛クズが空中を吸い寄せられていく様を、飽かず眺めていた。鉄を引き付ける石を手に入れ、それに鉄を吸い付けたり、その周囲に砂鉄を撒き、砂鉄が不思議な模様を描く様を、丸一日子供のように無心になって見詰めていた。
シモンは武器も造った。鍛冶屋の打った物と組み合わせ、精巧な鎧兜、その他の具足を造った。さらに、どんな盾や鎧も木の葉のように貫く大弓、数十人の敵を一辺に射殺せる大量の矢を放つ装置、などを考案した。毒の液体や気体を撒き、強力な火力を持つ油を敵に浴びせた。これら武器は、おのがポリスを守り、栄誉を讃えられ、そして敵兵を大量に殺戮した。
かつてシモンは、大政治家ペリクレスに招かれたが、「オレは、人前で話すの苦手だから」と言って、その誘いを断ってしまった。そして、生涯一職人で通した。
以前小川のほとりで、パイドロス青年と交わした会話を思い出していた。
エジプトの発明の神、トート神を引き合いに出して、文字や書物の難点を教え諭した時だった。
トート神は、ヒエログリフの発明者でもある。己の発明した文字を自慢するトートに対し、神々の王アモン神は、文字の欠点を様々挙げ連ね、彼の自慢の鼻を折ったのだった。――その時、パイドロスが言った。「トート神って、まるで靴屋のシモンさんみたいですね」
結果は考えず、新規なもの、奇異なもの、驚くべきものを、何でもどんどん造ってしまう。発明しまくる。造り続ける。確かに、トート神とシモンとは、イメージがダブる。
そのシモンへの対抗意識ということもあって、ソクラテスは工人の道、自然哲学の道を諦め、知を愛する道を選んだ、というところがある。
「以前磯辺で、タコとイルカが格闘しているのを、見たことがある」
「ん? タコとイルカ?」
「そうだ。タコとイルカだ。
奴等、騙し合い、知恵比べをしていた。人に見られているとも、気付かずにな。――イルカの方は、明らかにタコを弄んでさえいた。――つまり奴等には、知恵がある。人間以外の者にも、神々は知恵を与えたもうたという訳だ。ということは、オリュンポスの神々は人の格好をしているが、イルカやタコの格好をした神も、いるって事だろうか。
そして、ソクラテス、お前がよく口にする人のプシュケーって奴だ。奴等にも、プシュケーがあるんだろうか。何しろ遊びを楽しみにする程の奴だ。あっても全く不思議じゃあない」
「シモン。君は一体、何が言いたいんだ?」
「つまり、お前の話してた、絶対の法、絶対の善、絶対の徳、という奴についてだ。それらは、絶対という以上、タコやイルカにも共通する筈だろう。――確かに、幾何学の真理は、奴等にも通じそうだが、善や徳まで通用するのか? 奴等は、“善”だの“徳”だの、言うだろうか?」
「それはつまり、善や徳は、絶対ではなく、相対的なものだ。“万物の尺度”は、人どころか、タコやイルカも含めて、それぞれでズレる。そういうことか?」
「まあ、そんな所でまとめてくれると、こっちも助かる」
無口なシモンとお喋りなソクラテス。だからといって、決してソクラテスは舌先三寸の男ではなかった。むしろ、口八丁手八丁と言えた。マッチョで、石工としての腕も相当なものだった。
三度出征し、幾つもの武勲を立てた。アクロポリスや、アカデメイアの森に続くケラメイコスの共同墓地には、ソクラテスやその父親の造った石像が幾つも立ち並んでいた。
それでも、職人として、自然哲学の探求者として、シモンには到底敵わないと、ソクラテスは観念していた。彼は、一部の人からは賢人と呼ばれ尊敬を集め(他の人々からは奇人と呼ばれ敬遠され)ていたが、実は工人として、職人仲間のシモンが羨ましくてならなかった。妬ましくさえ思えた。黙ったまま、魔法のように多くの新しい、不思議なものを生み出す、その腕と頭が。文字を使いこなす様や、その使い方の工夫も。――文字を生み出した者とは、こういう者の仲間だったんじゃなかろうか?!
「どうもさすがに、――2対1では、分が悪いな」呆れたように、ホメロスの英知の詰まった頭をなでつつ、ソクラテス。「リュシアス殿は人間社会から、シモンは人外の者から、ワシの“善”や“徳”の絶対性に攻め上って来る」
シモンが、どこから持ち出したかワイン壺を取り出し、作業台の上に置いた。「オレの事は、数に入れなくていいよ」言った。
「ご謙遜を。――ソクラテスさんともあろうお方が、……」と、これはリュシアス。「ですが、」と語を継いで、「ですが、もし平等の賞罰を与えぬとしたら、哲学者は、敵に対しどう応ずべきとお考えなのですか?――この場合、悪辣非道な敵を、想定いたしましょう。傍若無人で、どんな悪事も意に介さぬ、救いようのない敵を」と、意地悪な質問をしてくる。
ところがそんな質問に、ソクラテスはむしろ我が意を得たりとばかりに、身を乗り出してきた。「そこなのだ。――どんな敵でも、その徳を高めてやる。それこそが、ワシの考える復讐であり、哲学者の勝利なのだ。さすれば、おのれ自身の徳も高まる。――その反対に、敵が為した不正と同じ事を敵に仕返し、敵を害すれば、敵の徳を貶め、同時に我が身の徳も貶めることになる。それこそワシが、さっきから言いたかった事なのだ」
「分かりました。崇高な理想ですね。――敵の、徳を高める。――それこそが哲学者の果たすべき復讐であり、彼の勝利。納得いきます。まあ、実現は限りなく、不可能に近いでしょうが。
それでは一体、敵対的他者の徳を高めるとは、具体的にはどうやればいいのです? ――敵を、益するでもなし、害するでもなし、……。社会的法的に、平等に扱うでもなし、……」
「教育と感化、に尽きるだろう。――さっき女房を女部屋に連れ帰った時、ここに一発平手を食らったよ」と、ソクラテスは右頬を突き出し、撫でた。「クサンティッペに右の頬を打たれたら、左の頬も差し出せ! とワシは言いたいね。クサンティッペは左利きだからな」
呆れた風に身を引き、「それではますます、女房殿が付け上がりますな」とリュシアス。「確か『靴屋風』の中でも、同じような事をヒッピアス殿相手に仰ってられましたね。それで、ヒッピアスの腰巾着共の爆笑を買っていた。――『右の頬を殴られたら、左の頬も差し出せ』でしたっけ? 『盗人が財布を奪おうとしたら、バッグごと与えよ』というのもあったな。――あれらは、どこから着想されたのです?
やはり、クサンティッペさんですか?」
「そこまで、言わせるか?」ソクラテスはニヤリと笑い、「つまりは、害するのとは逆のやり方だ。――それらを飛び越して、相手に訴える、……」
「何とも、常軌を逸した訴え方ですな。クサンティッペさんにすら、手を焼いているのに。――完全なる哲人を目指す哲学の実践も、初手で躓いている」
「確かに、大変な困難だ。相手が哲学の土俵に上らなければ、その徳の向上も図り得ない。自分の女房すら、意のままにならないのだからな。――哲学の、共通の基盤を造り、それを広める。これこそすなわち“正義の実践”そのものだと思うが、自分の家庭内にすら広められないのが、実情だ。――分かってくれよ、リュシアス殿」
「まあ君らも、座って飲め」まだ飲み足りないのか、既に工房の腰掛に座って飲んでいたシモンが、二人にも座るよう勧めた。「『イリアス』の時代の古人は、クリネーではなく、腰掛に座って飲み食いしていたそうじゃないか。何とも無粋なことだが、オレはそこが気に入っている」
なみなみと注いだ水で割らないワインを、強引に回し飲みするようソクラテスに手渡した。そして言った。
「しかし、――そもそも何故、そこまで“善い事”をしたがる?――自分や相手を高めたり、徳を積んだり、――何故“善い事”は、“良い”んだ?」
「そう、言われても、……」とソクラテス。「それはつまり、“善”や“徳”は、それ自体で素直に“喜ばしいもの”、だからだろう。それこそ、これらのものが、存在の本質、中核であることの、証左だ」
「としたら、――“善い”から、“喜ばしいもの”なんじゃなくて、“喜ばしいもの”だから、“善いもの”ということか?」
「ン。何が言いたい?」手渡されたワインの杯を手に持ったまま、警戒して固まってしまったソクラテス。
「“善い事”をすると、気持ち良くなるのさ。丁度この、ワインを飲んだ時と同じように」窪んだ奥目をトロンとさせつつ、シモンは手の中のワイン壺を振った。「難破する船から、溺れかかった人を救う事を想像してみろ。――首尾よく救えれば、人々の賞賛が得られ、気持ちいい。だが、賞賛無しで、人知れずおこなったとしても、やはり気持ちいい。反対に、とてもじゃないが救い得ないと判断して見捨てた場合、それで非難される訳ではないが、それでも救い得なかったことが気にかかって、生涯記憶に留まることとなるだろう。――つまり、見返り無しで、それをやること自体が快楽であり、罰則無しで、それをやらなかったこと自体が不快なのだ。快楽だけで、充分な見返りとなるのだ」
「“善”は、快楽だと?――“快楽主義者”達と同じように、“善行”するのか?」
「そうだ。――丁度、美味いものを食ったり、美女や美少年とイチャついたりすると快楽が得られるように、人の本能の一つなのだ。――そういった意味では、確かに存在の本質には違いない。ただし、“この世”の本質ではなく、あくまで“人”の本質だがな」
「プシュケーに占める質において、肉体的な食欲や性欲と、“霊”的な“善”の快楽とを、同列に並べる事には、同意しかねる」
「本当にそうなのか? 食欲や性欲は肉体的で、“善”の快楽は霊的だなどと、言えるのか? そも、プシュケーと肉体とに、本当に区別があるのか?」――さらに、ソクラテスとリュシアスを巡って戻ってきた杯を奪い取るようにして、それにワインを注ぎ足しグイと一気にあおりながら、シモンは唐突な話で繋いだ。「今の、“善行”を快楽と化する話だが、――オレは近頃、奇妙な工夫が頭に浮かんで離れないんだ」
「奇妙な工夫、とは?」と、ソクラテス。シモンの“奇妙な工夫”は、ソクラテスがこの世で最も畏怖するものだった。
「発端は、ある戯曲を書き始めたことだ」分厚い唇を殆ど動かさず、くぐもった声でシモンは呟いた。「最初は、悲劇を書く積りでいた。ところがいつの間にか、喜劇になっていた。さらには、劇ですらなくなった、……」
「お前が作劇とは、驚いた!」ソクラテスは心底から、驚きを吐露した。「文芸創作と職人シモン、一番しっくり来ない取り合わせだぞ!」
「で、――どんな話なんです?」少し興味をそそられたらしく、リュシアスが先を促した。
「ああ。――あるゲームに、取り憑かれた男達の話だ。
男達は、そのゲームに耽溺し、逃れられなくなる。丁度、シーシュポスの岩転がしのようにな。日々の営みも忘れ、それに埋没する、……。
悲劇だろ?――だが、度を越せば、喜劇だろ?――そして、さらに度を越せば、人の営みですらなくなる。単なる算術と化すのだ」
「男達を捕えて放さぬ、そのヘレネの如きゲームとは、一体どんな?」と、ソクラテスとリュシアスが、ほぼ同時に。
「なあに、ゲームそのものは、単純過ぎる、取るに足らぬものだ。単なる点取りゲームだよ。
二人の男を衝立を隔てて座らせ二つの選択肢の内のどちらかを選ばせる。ゲームはゼウスが取り仕切っている。――両者が“天”を選べば、両者共に3ドラクマ与えられる。両者が“地”を選べば、両者共に1ドラクマ与えられる。だが、一方が“天”を選び他方が“地”を選んだ時、“地”を選んだ者には5ドラクマ与えられ“天”を選んだ者には何も与えられない。何回もゲームを繰り返し、より多くのドラクマ硬貨を稼いだ者の勝ちだ。
色々な人物が、取っ替え引っ替え登場し、このゲームに挑む。このアテナイに住む、あいつやらこいつやら、君等もすぐ念頭に浮かんでくる連中が、劇中の登場人物となり、ゲームで稼ぎ合いを演じる。そんな、劇だ」
「それは確かに、“悲劇”であり、“喜劇”だな。つまりは、“天”を選べば両者共稼げ、“地”を選べば両者共稼げない。しかし、相手が共に稼げる事を願って“天”を選ぶと見越し“地”を選べば、つまりは“裏切れ”ば、相手を貶め、自らはより稼ぐ事が出来るのだ」感慨深げに、額にしわを寄せつつ、ソクラテス。「で、そのゲーム、――誰が勝ったのだ?」
「誰だと思う?」窪みの内の目をさらに細めながら、イタズラっぽくシモンが問い返した。「誰が一番、長者になれたと思う?」
「それは勿論、至極簡単な理屈でしょう」ほんのしばらく思案し、リュシアスが答えた。「相手が“天”と“地”どちらを選ぶか分からぬ以上、確率で計算するしかありません。その場合“天”を選べば、3ドラクマと0ドラクマ、計3ドラクマ。“地”を選べば、5ドラクマと1ドラクマ、計6ドラクマ。結局、裏切り続けた者、相手を貶め続けた者の勝利だ」
「それは、リュシアス殿とも思えぬ短慮だな」ニヤリとし、ソクラテス。「演劇の何たるかを、見誤っている。――相手の者は、自然の一部ではない。独立した人間だ。複数の人間が舞台上でぶつかり合うからこそ、劇は盛り上がる。――相手もまた、その相手のやる事を見定め、自分の打つ手を決める。相手が“地”を出し続けるなら、自らも“地”を出し続け対抗することとなる。つまりは両者共、1ドラクマずつしか稼げず、共倒れとなる。――となれば、両者共“天”を出し続けることこそが、ゼウスの高みから見下ろす時、正解なのだ。つまりは“協調”し合う事こそが」
「それもまた単純に過ぎますな、ソクラテス」と反撃するリュシアス。「ならば、延々“協調”し合う中で、時折“裏切り”を交え稼ぎを上げた者が、より有利となるではありませんか。問題は、どういうタイミング、どういう頻度で“裏切り”を差し挟むかと、それに対して相手がどう反応してくるか、ですが」
二人のやり取りを、シモンは杯をあおりつつ、ニヤニヤしながら眺めていた。――それに気付いたソクラテスとリュシアスは、無駄な議論を止めた。そして、最初の質問に戻った。「で、誰が勝ったのだ?」
「勝ったのは、」楽しそうに杯を傾けつつ間を入れ、劇作家に相応しく勿体をつけた後、シモンが答えた。「クリトンの奴だったよ」
「クリトン?」キョトンとする、ソクラテスとリュシアス。
「並み居るアテナイの有象無象が……、ずる賢い奴、戦闘的な奴、能天気な奴、賢人を気取る奴と、あまたいるタイプの登場人物達が、延々プレーをし続け、そして最後に一番の長者となったのは、――あのクリトンだった。あの、お人好しのな。――確かに現実でも、奴は金持ちだが」
「正直者のクリトンが勝者とは、意外だったな」とソクラテス。「それでは、ワシが貧乏なのは、クリトンの逆だからか?」
「いやお前は、ただ働いていないだけじゃないか。つまり、ゲームに参加すらしていない」シモンは即座に切り返した。そして続けた。「クリトンの取った方法とは、ごく単純なものだ。――すなわち、普段は延々“協調”し続ける。だが、“裏切り”にあった時は、相手に同じ“裏切り”で“しっぺ返し”を食らわす。それだけなのだ。――それだけで、並み居るずる賢い奴や賢人気取りを打ち破って、一番の長者となったのだ。
さっきも言った通り、男達はこのゲームにのめり込んだ。シーシュポスの労苦のごとく、延々対戦を繰り返した。リーグ戦形式の対戦だ。そして、各人のトータルのドラクマ硬貨の枚数で、ゼウスのもと雌雄は決せられる。各人が、その性格に合った戦略を取り、そしてクリトンの協調的だが必要な時は“しっぺ返し”をする戦略が、勝利を収めた。
オレは一回ごとの対戦結果を、獣皮紙に書き付けていった。選択に偶然性が紛れ込む時は、その都度サイコロを振ってその目を読んだ。で、書き込み続け、サイコロを振り続け、それを何万回も辛抱強く繰り返し、悉くを集計した。集計した結果どもを突き合わせ、勝利者を判定した、ゼウスの如くな。劇が一回上演され、幕が下りるまでに、数ヶ月かかった。……」
「やれやれ。お前は一体何がしたいのだ。それが、“劇”か?」鉄を引き付ける石や、水晶を透過する光や、空中を漂う毛クズに没入するシモンを、ソクラテスは透かし見ていた。ありふれた作劇から脱線し、妙な試みの事しか考えられなくなったという今のシモンに。
だがリュシアスは、シモンの劇に、別の評価を与えた。「クリトンさんの戦略とは、すなわち互恵的協調と、相応の報復の、二点に尽きましょう。これこそ、人類が延々と歴史を積み重ね、まさに今辿り着いている、ゼウスの真理、思し召しに他なりません。――私が先程来述べている、“応報の正義”の、紛れも無い傍証たり得ましょう」彼は高らかに、勝利宣言した。
「確かに、クリトンの勝利は、リュシアスの主張を裏付ける、……とオレも、その時思った」シモンが話の後を継ぎ足した。「何万世代にも渡って、丁度このゲームと同じような生活を延々送っている内に、人間には、食うことや、寝ることや、セックスすることと同じように、協調することや報復することに快楽を感じる本能が沁み込んじまった、と考えても不思議じゃあない」
リュシアスはさらに胸を張った。「両頬を差し出す事が、この真理につけ込む余地はありますかな?」ソクラテスの方を、挑戦的に見た。
「まあ、待ってくれ、リュシアス」意気揚々たるリュシアスを、一時は彼の側に立つかと見えたシモンが、空の杯を掲げて制した。それから、愛しむように杯を再度満たし、ワインの方に注意を集めつつ、投げやりな調子でボソリと言った。「この劇には、第二幕があるのさ、……」
「第二幕?」と、新展開に興味をそそられ、ソクラテス。
「ああ、劇の続きだ」と、ワインの表面を舐めつつ、シモンは継いだ。「第二幕は、クリトンだらけのアテナイを、創作してみた。市民が全て、クリトンなのだ」
「クリトンだらけのアテナイ?――滑稽で、弱々しくて、不気味だな」とソクラテス。
「さっきのクリトン戦略同士のクリトンを、延々戦わせてみたのだ。そうしたところが、困ったことになった」余り困ってもなさそうに、相変わらずワインの表面を舐めることに夢中のシモン。「皆協調的にワキアイアイやっている中で、誰かが一たび、ほんの些細な事から偶発的に選択ミスをすると、――たちまち報復合戦に陥って収拾がつかなくなってしまうのだ。――そして、そうしたアテナイは、いわば泥沼の中に滅びる。――丁度今、延々と続くポリス間の報復合戦の中で、滅びつつあるヘラス全体と同じように、さながら写し絵のように、な。……」
ソクラテスとリュシアスは、期せずして同時に息を呑んだ。「ヘラス全体の写し絵のように、だと?」ポリス同士の報復合戦は、ヘラスに宿る、避け得ぬ脱し得ぬ、いわば宿業のような現実だった。リュシアスの唱えた真理の行き着く先は、そんな滅びの地獄だった。
「だがな、……救いは、ある」ワインの水面から目を上げたシモンは、二人にウインクして見せた。「まめなクリトン、まめにしっぺ返しするクリトンの中に、しっぺ返しをしばしばすっぽかすクリトン、いわば寛容なクリトンを混ぜるのだ。そうするとアテナイは、俄然生き生きとし、最盛期の姿を取り戻す。長期間の計算結果では、しっぺ返しの頻度は、三回に二回くらいがベストだとなった。残りの一回は、寛容に、相手の過ちを見逃してやるのだ」
「まさしく、それだよ!」と今度は、攻守所を変えたようにソクラテスが勝ち誇った。「両頬を差し出す余地が、出てきましたぞ。リュシアス殿。――たとえ報復が本能であろうとも、過度に本能の快楽に浸るのは、淫蕩に堕すること、シケリアや南イタリアにはびこる鯨飲馬食の蛮風に同じ、巡り巡っておのれや同族を滅ぼすこととなる」
「喜ぶのはまだ早いぞ、ソクラテス」息巻くソクラテスに、シモンはワインの杯と壺を手渡し、釘を刺した。「この劇には、さらに第三幕以降があるのだ」
「寛容なクリトンが、行き着いた真理ではないのか?」渡された杯と壺に両手を塞がれ、持て余しつつ立ち尽くすソクラテス。
「オレの探究心は止まぬ。――そんなことは、子供の頃からの“ダチ”のお前は、百も承知だろう」シモンは、自由になった両手で、今度は眠そうに両目を擦った。飲みくたびれたシモンがそのあと昏睡するのは、いつものパターンである。その先が知りたく、ソクラテスは焦った。「第三幕は、どうなったのだ?」訊いた。
「寛容なクリトンだらけのアテナイに、オレは様々な異分子や、偶発事を持ち込んだ。ゲームの形式も、二人対戦型では飽き足らず、不特定の多人数型を導入してみた。――つまり、より現実を反映した劇に、改変した訳だ」
シモンがコクリコクリし始めたので、ソクラテスはさらに焦った。「で、――劇中のアテナイは、どうなった?」
投げやりな調子で、シモンは答えた。「お人好しのクリトンだらけのアテナイは、狡猾な悪人が少人数紛れ込んだだけで、たちまち崩れ去ってしまったよ。――まめなクリトン、いわば警察官役を、これも少人数導入すると、何とか持ち直した。――他にも、色々なイレギュラーな条件を入れるたび、劇中のアテナイは流動化していった。つまりは、本物のアテナイと同じようにな」
ソクラテスはホッとしたように、杯と壺をシモンに返した。受け取ると、シモンはまた生一本のワインを飲み始めた。目が、覚めたようだ。
「だがな。劇が現実を映すのは、当たり前のことじゃないか。――だからこその、“劇”だ」ソクラテスは、諭すように言った。「お前流の真理の探求は、グルリ巡って、結局現実に戻ってしまったんだろう?」
まだ寝ぼけているのか、シモンは遂に壺に口を付け、それを傾け直接喉に流し込み始めた。そして、「オレが言いたかったのは、そんな事じゃあない。劇が現実を映すのは当たり前のことだし、作劇の思い付きなど単なる発端に過ぎん」言った。さらに、窪みの奥の目を見たこともない程に見開き、二人を睨み付けた。「いいかな、御両人。これまで話した通り、オレは延々、獣皮紙とサイコロを使って、計算し続けた。全くの、ルールに従ったオートマチックな計算だった。そこには、執筆者たるオレの思惑も、神の配慮も、入り込む余地が無かったのだ。つまり、プシュケー(魂)の介在のまるで無い、“善”だの“徳”だのとは無縁の、単なる数学的計算だった。丁度、ピタゴラス派が好んでやっている、幾何や算術のような、な」満足したのか、壺を作業台の上に戻した。
――石彫工房の薄暗がりの領域で、かなりの時間、沈黙と、身動きならない緊張とが、支配した。皆が共に、今のシモンの発言内容を吟味していた。そして、次に何と話し始めたらよいか、思案を重ねていた。
夜の闇に終止符を打つ打刻の音が、カッコウの夜鳴きのように遠くから届き、ソクラテスの石工の本能を目覚めさせた。それが彼に、三すくみを破らせた。
「ピタゴラス派が“真理”の比喩としてよく使う、『三平方の定理』。あれと同じような、数学上の定理だというのか。“徳”も、“正義”も。――証明は大分込み入り、手間を取らせるが、……」
「『三平方の定理』というよりは、むしろ“ハルモニア”の真理に適っている。時の止まった幾何ではなく、時間的な変化の中に“真理”が醸成される故にな」呼応するように、シモンが答えた。
「この世の真理、数学上の定理だとすれば、」遂に三人目のリュシアスも、話に戻ってきた。「人の世、人のプシュケーとは別個のもの、それより前から存在していた真理、――と、あなたは言いたい訳ですな」
「そうだとも、リュシアス」シモンはここでも即答した。「“真理”は“人”に、先んじてある。それは、数学的に証明された。『三平方の定理』のようにな。――とすれば、この“真理”は、さっき話したイルカやタコどもにとっても、“真理”ということだ。いずれ奴等も、“徳”や“正義”の本能を持ち、それらについてうるさく言い立てるようになるだろう。――そして人もまた、プシュケーだ何だと有り難がっているが、先に立つ法則に従って、イルカやタコの如く組み立てられた、一生物種に過ぎんということだ」
「フーム。人のプシュケーなんぞ、この世の諸々の材料や法則により組み立てられた、人造の神殿の如きものに過ぎんと、そう言いたい訳だな。そこに魂など、宿っていないと。――“唯物論者”達が聞いたら、泣いて喜びそうな説だな」と、ソクラテス。
「まだまだ、続きがあるぞ。そんなことでは容赦せん」勢い込むシモンが、両目を双子の満月の如く輝かせながら、続けた。「そこで最初に言った、頭から離れない“奇妙な工夫”に、戻るのだ」
最初にシモンがその言葉を口にした時の、かすかだが心底からの凍り付くような恐怖を、ソクラテスは思い出していた。――出来れば、聞きたくない。が、聞かない訳にはいかない事を、ソクラテスは重々承知していた。
「オレは何ヶ月も手間をかけて、三幕四幕と劇を書き綴っていった。それこそ、寝食を惜しむようにしてな。――その内、思い付いた。――こんな作業、機械にやらせればいいじゃないか!
つまりだ。何十何百もの歯車を噛み合わせ、そいつをハンドルでグリグリ廻すと、最初に設定したルールに従い、計算し続け、獣皮紙に記録し続ける、そんな機械だ。さらには、そうしたルールそのものの変更も、歯車が自動で噛み合わせを変え、オレが一々考え手を加えずとも、勝手にやっていくようにする。
さらに、考えた。――オレがハンドルを廻し続けるのも、面倒だ。こんな作業、人がわざわざやる程の事じゃない。――例えば、水車だ。水汲みや脱穀に使う水車に繋げば、延々無人で作業をし続けてくれる、川が流れ続ける限りな。何も、人が付いている必要など、無い。……」
「無人で計算し続けてくれる機械か」ソクラテスは、恐る恐る相槌を打った。「便利そうだな。ピタゴラス学派の連中に売り付けたら、きっと高く売れるぞ」
だがシモンは、友の相槌を無視し、先を続けていた。「この無人の機械を考え付いた時、ふと思ったのだ。――機械は、人もプシュケーも無しで、世界で起こる事を計算し続け、再現し続ける。――ならばこの世界も、造りはもっと遥かに上等だが、そうした自動機械と同類なんじゃないか?――人だプシュケーだ、徳だ正義だが、計算の結果はじき出されるものだとしたら、この世界もまた、延々と繰り返される計算の結果そうしたものを生み出してきたんじゃないか。――オレ達もまた、そうして計算されて獣皮紙の上に書き込まれた存在に過ぎん、ということになる……」
「プシュケー無しで廻り続ける世界、ですか。何とも殺風景な光景ですな」名文家をもってなるリュシアスは、筆を使う時と同じように、発する言葉を選ぶ時も、推敲しつつ、恐る恐る語った。
「いやはや、」とソクラテス。「また妙な事を、言い出したな。毎度の事だが」空とぼけた感想で、薄ら寒い震えをはぐらかした。
二人の反応を確かめてから、シモンは瞳の光を散らし、窪みの底に押し込めるいつもの大様な顔に戻った。
「世界を再現する機械などと、ゼウス神に聞かれたら、雷でも落とされそうな大それた話だったな。
――
まあ、夢みたいな、馬鹿げた話だよ。――笑ってくれ」
リュシアスはホッとしたように、本当に笑った。ソクラテスもつられて笑ったが、本当には笑えなかった。何故なら、この友がこういう事を言う時は、本当にそれを実現させかねない時だったからだ。
*
物思いから戻ると、ヤコボの話が続いていた。
「街で、あのローマ兵を、見掛けたのでした。あの、十年程前、母マリアを野良小屋へと連れ込んだ、ローマ兵です。今では出世し、百人隊長となっているようでした。
街角を部下を引き連れパトロールするこの男を見掛けた夜から、兄の“おねしょ”の癖がぶり返しました。十代半ばセッフォリス時代までずっと続いていたおねしょは、この頃ようやく治まったのですが、それが、内容を思い出せない悪夢と共に、ぶり返したのです。
かつて戦時下、村人から奪い続けたローマ。今も、農村・漁村から吸い上げ、搾り取り続ける都市。主を蔑ろにし、無数の偶像と神を蔓延らせる者達。それの代表者が、この百人隊長でした。――敵に奉仕する、地元生産者。蔑視される“地の民”。お高く取り澄ました離散ユダヤ人の新移住者と、千年来の土着民との確執。――反乱が鎮圧された今でも、現体制に不満を持つ者等のゲリラ的な集会、突発的なアジ演説は、跡を絶ちませんでした。彼等は、その熱烈さ加減を競い合いました。そして、『狐』(ヘロデ・アンティパス)の兵達に、その都度蹴散らされました。彼等は、“熱血者達”と呼ばれました。――シュプレヒコールを上げる者達の仲間に、兄もしばしば加わりました。反ギリシャ・ローマ。反異教。と同時に、金持ちを忌み嫌い、貧乏人に強い親しみを覚える、というのが当時の兄の素朴な心情でした(本人も飛び切りの貧乏人でしたから、至極当然なことですが)。
くだんの百人隊長を、兄は意識して監視し続けました。そして隊長の行動の規則性、ほぼ決まったパトロール・コースなどを洗い出しました。
隊長は、部下を四、五名伴い、不定期に三日に一回程のペースで、市中を見廻るようでした。市中警備用の軽装で、街中をほっつき歩くのを楽しんでいるように見えました。
酒場の出口で、客引きの酒場女をからかいながら、店の主人にワインを所望します。一杯ひっかけ、臭いイカのガルムで付け焼きした豚肉を摘み、いい気持ちになって部下ともども金を払わずに店を出ます。だが主人は、代金を要求しない、それどころか喜んでおごってやっている。酒場ばかりか、果物屋や乾物屋といった露天の店頭でも、売り子達が商品を隊長に進んで献上します。別に権力に媚びている様子もなく、彼等への無料のおすそ分けを心底喜んでいるようです。どうやら、隊長は、町衆から随分と慕われているようでした。――付かず離れず後を追う兄を、その慕われ様が、ますます苛立たせました。ナザレ村での、十年前の彼(等)の所業と、ダブったからです。隊長等は、あちこちの店や女や男等をからかいながら、込み入った市場の路地に分け入り練り歩いていきます。百人隊長のシンボルの羽飾りが、一歩ごと揺れ動きます。惨めな兄を嘲笑うように。兄の決意はいよいよ、痛々しく固まっていきました。
戦乱で破壊し尽くされた瓦礫を全て埋め込み整地された土表を、わざわざ掘り抜き、旧セッフォリスの市街の一部を復活させた発掘地がありました。とあるインスラ(集合住宅)一階最奥の部屋の納戸の床をぶち抜き、掘られた縦坑にハシゴが掛かっています。普段は床材の大理石の板で、蓋がされていました。
その地下の掘り返された洞窟は、反乱勢力のあるセクトのアジトになっておりました。そこへ、兄は降りていきました。前々から誘われていたのですが、百人隊長に出会って迷いが払拭され、遂に入党する決心がついたのです。
暗がりの中に、油壺の灯心が幾つか灯され、かすかな陰影を浮かび上がらせています。掘り返された瓦礫の街は、旧セッフォリスの庶民の住んだ市街地で、人々の生活の痕跡が、雑貨や食器類や子供の遊具やらが、散乱していました。かつて兄が遊んだようなオモチャの剣を拾い上げると、そこには、ガリラヤのユダに忠誠を誓い、ローマ人を殺す、という文言が書かれていました。
兄は、なけなしの一張羅で正装し、入党の儀に赴きました。セクトの幹部等も、襟を正して兄を出迎えました。要人暗殺をテーゼとする、テロリストのセクトでした。おぼろげな陰影のみで、顔もよく分からない頭目の自称メシアから、“シーカ”(短剣)を恭しく拝領するのが、入党の儀のクライマックスでした。それは、“剣による洗礼”と、呼ばれていました。
兄はこのセクトに特に思い入れがあった訳ではありません。ただ、扱いやすい短剣を手に入れたかっただけでした。だから、“メシア”がペラペラと喋る、ルーティーン化されたセクトのテーゼや“熱情”の告白も、白々しい思いで聴いていました。
“メシア”は、“司令室”と名付けられたその洞窟の、側面の壁を指し示し、そこに彫られた幾つもの名について説明しました。目の高さに彫られた名前達は、“殉教者”のそれ、とのことでした。一人一殺で、要人達を葬っていった“英雄”でした。対して、足元に上下逆さまに彫られた名前達は、密告者など“裏切り者”のそれでした。永く呪われるよう、この地下に名を刻み付けておくのだと、吐き捨てるように言いました。
“見え透いた脅し”、でした。それが兄に、ナザレでの奴等のやり口を思い出させました。――村人を“英雄”と“裏切り者”に峻別し、忠誠を競わせる。村に修復出来ない“クサビ”を打ち込み、支配する。恐怖で生活を失わせ、支配者に依存せざるを得なくさせる。親しい人を殺させ、絶望により兵士を作る。――組織幹部の些細な身振りや口調にも偽善性が滲み出ていると、兄には思われました。それらは、ナザレを支配し村人の犠牲の上に胡坐をかいていた彼等の先達と、瓜二つのものに見えました。兄は密かに歯噛みしました。
名簿の彫られた壁には、まだ町が生きていた時代の“イタズラ書き”が、幾つも残っていました。“メシア”が読み上げる“英雄”一人一人の業績を聴くふりをしながら、兄はそっちの“イタズラ書き”の方を読んでいました。
『豚食いのローマ人ども!』『大理石のウェヌス(ヴィーナス)に突っ込んで割礼しろ!』などと書かれています。『泥にまみれた土民ども』『隣人と交わらぬヘブルの民は、孤独の中で滅んでゆけ!』などともあります。アラム文字、ギリシャ文字、ラテン文字、色々な文字で勝手気ままに書き殴られていました。淫猥な、赤裸々な内容のものが、圧倒的に多かった。どうやらここは、“売春宿”の跡地であったようです。
兄は、イタズラ書きを読むのが面白くて、“メシア”の説教が終わった事にも気付かなかったそうです。それで、兄がいつまでも直立不動の姿勢を崩さなかったものだから、セクト内でのこの新参者の評判は、すこぶる上々だったとのことでした。
隊長一行は、家畜の公設落札市場で、足を止めました。そこは、生きた獣の臭いと、畜肉とスパイスと香木と排泄物と、各民族の体臭の、背教の臭いが入り混じり、むせ返るような場所でした。折りしも巨大な牡牛が競りに掛けられ、ローマ兵達はその赤銅色の巨体に見入っていました。
長い上着の下に忍ばせた短剣の柄を手の中で握り締めると、少年兵の頃の感触と記憶と殺戮の技巧とが、兄に蘇ってきました。久し振りの得物に、手が僅かに震えました。兄は、戸惑い、不快になり、しかし目の前の標的に注意を振り戻しました。
百人隊長は、戦闘時の金属製の鎧ではなく、皮製の軽快な鎧姿です。充分に体重を掛けられれば、シーカで簡単に刺し貫く事が出来そうです。兄は、意を決し、一歩を踏み出しました。
が、波立つ群衆の躍動に押し戻され、容易に近付く事が出来ません。そうこうする内、ローマ兵の一行は、家畜市場を後にしてしまいました。
見失わぬよう必死で後を追う兄は、少し丘を登った高級住宅街で兵士達を捉えました。離散ユダヤ人や異邦人達の、金持ちや貴族や上流の者達が住まうその地区は、純白の中に壁面のモザイクも色鮮やかな別天地でした。ヘロデ大王の再建したエルサレムの神殿は、遥か遠方からでもその光り輝く壮麗さを望む事が出来ました。所詮はギリシャ・ローマ風のハリボテじみた、造りたてのまがい物でしたが。その息子が造った新セッフォリスの町も、父の神殿に劣らずハリボテでした。アンティパス本人が、町の普請に出張っているところを、私も兄も、遠くから何度も見掛けました。旧セッフォリスに劣らず、体制批判や享楽的な落書きがすぐ白壁に溢れ、神経質なガリラヤの支配者はその都度陣頭指揮でそれを消しに掛かります。その腰の据わらぬコソコソした様を嘲り、兄は支配者を『狐』と呼び捨て、蔑みました。
邸宅街の石畳の大通りを、ローマ兵の一団はガヤガヤ談笑しながらそぞろ歩いていきます。ナザレ村には一キュービットも存在しない、石畳の道路でした。その上ナザレは、戦乱で崩壊したまま、復旧の気配も見えていませんでした。――百人隊長は、ローマ兵とはいっても、勿論生粋のローマ人ではなく、地元のローマ化した異民族、カイサリアの町に住むシリア系異民族の出でした。普段から何かとユダヤ人といがみ合っている民族でした。兵役に付き、百人隊長にまで成り上がったのです。その部下達も、ほとんどが同じ土地の出身者だったようです。
この辺りなら人通りも少なく、あっさり近付き復讐の目的を遂げられそうです。――が、そこで、兄はハタと、刺した後の対処の仕方を想定していなかったことに、気付きました。――暗殺を決行したら、その後は素早く人ゴミに紛れて痕跡を残さず消える。それが、兄の参加したセクトの、常套手段でした。暗殺者が下手に捕まれば、セクト中枢にまで危害が及びかねません。そうして捕まった時こそ、“英雄”と“裏切り者”が、仕分けられるとも言えます。いずれにせよセクトは、足の付く暗殺手法は認めていませんでした。暗殺の確実性と逃亡の可能性の二つを、兄は素早く天秤に掛けました。
さっきの競り市場で、決行しときゃ良かった! 兄は、後の祭りでしたが、激しく後悔しました。もっと早く、行動に移しておけば!――が、その後こうも考えました。――いや、むしろ、自分が刺したと、白日の下喧伝出来る方を、望むべきでは?――そうすれば、何故刺したのか、その理由を、――この男の罪状や、故郷ナザレ村で過去どういう惨状があったかを、――往来の人々に声高に告げ、糾弾し尽くす事が出来る。それは、人々の心に刻まれ、口伝えに、市中全域、さらにはガリラヤ、ユダヤ全土にまで、行き渡るだろう。
いや、待てよ。――そこでまた、別の考えが、兄の気勢を殺ぎました。――そんな告発をすれば、母マリアの被った悲劇を、広く公けにする事となる。大衆の記憶に植え付け、好奇の目に晒す事となる。それで、母の今後の人生はどうなるか、容易に想像がつこう。――ならば、復讐を諦めるのか。いや、ダメだ。断念など、到底無理だ。
やはり、足の付かない暗殺法を、選択すべきだろう。――兄の思考は、こうして一巡りしてしまいました。――人知れず、復讐を果たすべき手段を、と。
怪しまれぬよう距離を取り付け廻す内、警戒する気配のまるで無い男達は中央広場に達していました。市場程ではありませんが、人の往来でかなりの込みようです。犯行現場としては、格好のシチュエーションでした。――隊長は、大浴場の入り口前で、浴場のカマ焚き奴隷と立ち話を始めました。標的が、停まりました。
広場上空で、二本の巨大な水道橋が十文字に交差し、張り渡されています。その大浴場を始め、市中の隅々にまで上水を供給していました。その石造りの橋脚に身を隠しつつ、兄は隊長に接近を図りました。
そして、短剣を両手に固め、飛び出して相手に身を預けようとしたその瞬間、――突然上空の水道橋の一部が崩れ、そこから溢れ出た水が滝となって、――兄はそれを全身に被り、その場に立ち往生してしまいました。――兄はしばらく、何が起きたのか分かりませんでした。ずぶ濡れの全身を、ただ見下ろしていました。――ふと我に返り、自分が人々の注目を集める事を警戒しました。――が、周囲の群衆は、一向に兄の方を見向きもしません。今まで通り、各人勝手に、喋りかつ歩いているだけでした。
さらに数瞬後気付くと、服がいつの間にか乾いていました。ほんのさっきまで、まるで服ごと泳いだ後のように、濡れ鼠だったのに。――兄は、上空を、水道橋の崩落した辺りを、見上げました。石造りの橋は、崩れていませんでした。まるで何の損傷もなく、いつもの堅牢な姿のままでした。
どうやら、幻を見たようでした。まるで白日夢に落ちたかのように。兄は、混乱し、途方に暮れ、しばらく立ち尽くしていました。――が、自分に何が起こったのか、のんびり吟味している余裕はありませんでした。隊長等の一行を追跡せねばならぬという、使命を思い出したのです。
かの一行は、何も気に留める風もなく、広場の反対側の、贅沢な造りのローマ風劇場前に移動していました。広場を突っ切り、再度兄は接近を試みます。黄金比のウロコ状の模様の入った磨き上げられた広場の石畳が、その時人垣がモーセの奇跡の如く左右に割れ、兄の前に一本の道を開いたかに見えました。兄は、その道を進みます。――隊長は、劇場脇の水汲み場で、手を洗っていました。仲間から離れ、一人で背中をこちらに向けています。ようやく見せた仇の隙、兄はチャンスと見定め、歩みを一気に加速しました。
と、その時、今度は人でもなく水でもなく、鳥の群れが、兄の足を阻んだのです。それまで兄の目の前の広場でパン屑をついばんでいた小鳥達が、一斉に飛び立ち、兄の方に向かってきたのです。鳥達は、ほとんど兄にぶつかる程に体近くを掠め、そのまま上空に飛び去っていきました。兄は、またしても、立ち尽くしました。
が、これも幻覚だったと、すぐに気付きました。――小鳥達は、何事も無く、そのまま路上のパン屑をついばみ続けていたのです。
異教の神どもが、俺の妨害をしているのか!――兄は、悪態をつきました。――異邦人の魔術師が、どこぞで呪文を唱え、俺に幻覚を見せているのか!
異教の神々の像が、頭に浮かびました。その醜怪な群れが。ガリラヤやヘブライの地全土を破壊した、その凶暴な文化やローマ軍団が。酷い目に合った母や家族や村の人々の顔が、一人一人。そして、あの百人隊長。十年程前、まだ若かった母を強姦した、もしかすると兄弟の誰かの父親かもしれない、あの男のニヤついた顔が。――酷い目に合わされた者等に混じり、兄が酷い目に合わした者等の顔も、途切れ途切れに浮かびました。“懲罰”した、隣り村の者。制裁を加えた、ナザレ村の“裏切り者”の、知り合いのおじさん。“意外だ”という戸惑いの表情を浮かべつつ、兄を見返したその人々の顔。そして、瀕死の苦痛に歪む、アスクレピオス教団の医師の顔。
“敬神”と、“攘夷”こそが、貫くべき道だ! 滅びろ! 異教徒の、異邦人ども。その文化と、軍団。――兄は、革命思想と呪いの言葉を口走りながら、動き始めた百人隊長の姿を目で追いました。――余りに、“熱情”的になり過ぎている、と思いました。信仰に血をたぎらせるのは素晴らしいことですが、こういうたくらみを遂行する時は、もっと冷静であらねばし損じます。兄に、冷静さを取り戻そうという、判断が働きました。
兄が革命思想かぶれの様を見せた時、かの学者は、面白がりつつも、渋い顔を作って、兄に色々な書物を読むよう手渡したといいます。それらは主に、ギリシャ哲学関連の書物でした。それらを読むと、“攘夷”、“殉教”、“終末”に“神の国”と、熱くなっていた兄の思いが、ゆっくりと冷まされていきます。あたかも、“熱冷まし”を服用したかのようでした。特に、ソクラテスを巡る“靴屋風”は、兄のお気に入りでした。しばし論理の世界に遊び、兄は熱烈な信仰を忘れました。
今、余りの高ぶりに、兄は“靴屋風”の内容を思い出し、冷静になろうと努めました。“勇気について”、“名誉について”、“正義について”。ソクラテスは、何と言ったか。
手を洗い終えた百人隊長は、一人で噴水の周りをグルリと廻り始めました。海神プロテウスが口から吐き出す水が、人の背丈以上にまで舞い上がる噴水です。そこで兄は、噴水の反対側から廻り込み、出合い頭に隊長を刺そうと目論みました。
隊長の緩み切った顔が、目の前に来ました。目の下の大きなホクロまで見えます。“今だ”と、突き進みました。――が、今度は、それまで噴水の手摺にもたれ掛かっていた“いざり”が、突然跳ねるように立ち上がって、兄に抱き付いてきたのでした。
隊長が、擦れ違いつつ、“何だ、この若造は”といぶかしがる目付きで、兄をチラと見たといいます。兄は、見知らぬ男と抱き合ったまま、隊長をやり過ごすしかありませんでした。
しかしこれも、幻覚でした。――“いざり”は、噴水の縁で涼しげな霧を浴びながら、いざったままでした。――またも兄は、立ち尽くすしかありませんでした。涙が、滲み出てきました。
隊長はそのまま、近くの公衆便所に入ってしまいました。――ここの中ならば間違いなく殺せる、と兄の判断が働きました。狭いトイレなら、逃げようがありません。ですが、中に複数の人間がいるかもしれませんし、有料のトイレですから少なくとも料金徴収係の奴隷がいます。先程危惧した通り、彼の素性はすぐバレて、家族に迷惑をかけることになってしまうでしょう。それに、用を足すのに、銭など払う気には到底なれない。貧乏人は、路地裏で済ませれば、それで充分です。
そんな些細な理由付けをした兄ですが、実は目的遂行の気力がとうに萎えていました。――セクトのアジトの壁に彫られた“殉教者”と“裏切り者”とに(今の兄と同じように)それぞれどんな物語があったのだろう、と兄はボンヤリ考えていました。イタズラ書きなどに気を取られず“メシア”の説明を聞いときゃよかったと、兄はふと後悔しました。
さっき考えていた“靴屋風”の中にしばしば登場する、ソクラテスに『ストップ!』をかけるダイモンの啓示の事を、その時思い出しました。三たびの幻覚、ソクラテスのそれに、まるでそっくりじゃないか!――兄は、恐怖しました。そして、感謝しました。
さっきは異教の神の仕業と悪態をつきましたが、もしかすると、我等が主の思し召しなのかもしれません。――どういう意図なのかは計り知れませんが、――突いてはならぬ。殺してはならぬ。という、啓示なのでは、と。
それが本当に良かったのかどうか、その時の兄には到底判断つきかねましたが、兄は、百人隊長を刺さなかった事も、ソクラテスに出会えた事も、神に深く感謝しました。懐の短剣の突端にヘソの周囲を突付かれながら、兄は神への感謝と愛に打ち震えていました。
ですが、学者の住まいで万巻の書物に囲まれ、事件の一部始終を思い返す内、兄は再び悲しさと悔しさで、ブルブル身を震わせ、涙をボロボロと流し始めました。何とか気持ちを落ち着かせようと、手当たり次第に書物を紐解き、一方の震える手で短剣をまさぐり、もう一方の急く手で書物を繰りました。しかし、書かれている内容が、一向に頭に入ってきません。
涙ぐむ兄を見て、学者はその訳を訊きました。兄の苦悩を聞き取った後、“ならば、これがいい”と学者は、一冊の“靴屋風”を兄に手渡しました。それは、ペリパトスでの滑稽な論争を書き留めた、既に兄が五、六遍も読み返した覚えのある一巻でした。
「今読めば、新たな一巻として、読めるだろう」学者が言いました。――成る程、――既に一字一句記憶している筈なのに、違う話として、読めます。――最初、作中のソクラテスの、度を越したひょうきんさとふざけた対応に心底腹を立て、次いで、そうした演技の裏面の真意にのめり込むようにして、読んでいきます。
何故、ヒッピアスに一方的に喧嘩を売っておきながら、すぐに自ら負けを認める? 現実の、ポリス間の紛争や各種犯罪の裏に、より深い“正義”の真理を極めようとする欲求は、どこから来るのだ? ヒッピアスの取り巻きや、自分の金魚の糞や、アテナイの野次馬等無頼の徒達を、必要以上に煽り立て、騒ぎを大きくして楽しんでいるのか? 何故、ヒッピアスに右の頬を叩かせ、左の頬まで出す? 何故、戦わない? 百戦錬磨の名うての重装歩兵が。
兄はそれまでに、ソクラテスの対話編の全ては勿論、あらゆる哲学書を読み尽くしていました。それらは、以前はただぐぢゃーと、大量に群れ集っているだけの、一緒くたのものと見えていたのが、何時の頃からか各哲学者の石像達が、皆が皆違う神を信奉しているかのように、それぞれ別の物語を語るようになっていました。
そうした中でも、シモンの“靴屋風”は、兄の格別の“大好物”でした。そこでは、ソクラテスの真の姿が、一番生き生きと、踊っている、伝わってくると、思えたからです。
男らしくマッチョな重装歩兵のくせに、女々しくお喋りでみっともない、頬を突き出して媚を売るソクラテス。その作中のソクラテスに、兄は同化し、付き従っていきました。
既に何度も熟読しているこの話、頭では充分理解している積もりでした。――ですが、では実際に、今後あの百人隊長にどう対峙したらいいのか、というと、……。――敵を高める? そも、あの百人隊長を高めるなどということが、出来るのか? それは、かつての罪を懺悔させて、然る後哲学者として精進させる、といったプロセスを辿るのだろうか? とても、実行可能とは、思えない!
ムセイオン出の学者の持つ、哲学以外の多様な知識、歴史学、地誌学、民族学等々。それらも兄は学び、吸収していました。だから、ヘブライの民とその思想の特殊性も、多民族の中での傑出した様も、理解し、客観的に見られるようになっていました。――ですが、同時に、兄は、その特殊な民の一員で、そして中でもとりわけ信仰熱心の徒であった訳ですが。
そんな兄を脅し付けるように、哲学者の像達が、暗がりから浮き上がり、それぞれ動き出し、勝手にお喋りを始めました。わけてもソクラテスは、別格の異形を誇り、一人だけ飛び抜けて、目立っておりました。
本来ギリシャの思想に、我々は根強い反感を抱いています。ギリシャのあらゆるものが、ヘブライの民にとって憎むべき敵でした。ですが、憎みつつも、避けて過ごす事が出来ません。呼吸せざるを得ぬ、大気中の毒素のようなものです。従って次第に、その成分に慣らされていきました。――憎むべき。しかし、憎みつつも、愛着がある。――ムセイオン出のかの学者も、ヘレニストの離散ユダヤ人でしたから、典型的なそうした人物の一人でした。その強い憎しみと愛着の様を、学者は告白しました。彼は、ヘレニズム世界の知識を吸収しつつも、逆にムセイオンでヘブライの思想にベースを置いたおのが考えを広めようとした経験を、兄に語って聞かせました。彼の考えを、ムセイオンの学者の多くの者が受け入れ、多くの者が強く拒絶しました。
だから、土着のヘブライの民にとって、最大の敵たる“ローマ・ヘレニズム”だが、異民族がヘブライの思想を知って触発されたように、ヘブライの民がギリシャその他の思想を知って救われても、決して不思議な事じゃあない、学者は言いました。
知る事により救われる、石工の神・ソクラテス。――兄は、思いました。――兄は、圧倒的に多くの時間、ギリシャ文化に浸っていたために、嫌いながらも、その思考の枠組み、ベースは、ギリシャ的とならざるを得ませんでした。ヘブライ的、“罪の意識”、“自己犠牲”、“神との関係”等々を、ギリシャ的論理学や弁証法で、考え掘り下げ追及し、確信に至ることとなったのです。
愛嬌のある、“ヘチャ”な顔のソクラテスに、段々魅入られ、現実に彼に付き従った多くの弟子達と同じように、四百年遅れの“最後の弟子”として、付き従うようになりました。
“完全なる人間”?――すなわち、“哲学者”?――自分はそんな、ソクラテスのような存在に、なれるのだろうか? 兄は思いました。――ヒッピアスに対し、“完全なる人間”になって思考するよう求めたソクラテスが、自分にも同じ事を求めているように、語り掛けているように、思えてなりません。
完全なる人間、すなわち哲学者なら、敵を、あの百人隊長を、貶めるのではなく、高めるという。それすなわち、彼の復讐であり、勝利であるという。――逆に、哲学者、完全な人間でなければ、相手を貶め、従って自分も貶める。復讐を誓い、敵を許さなければ、憎しみにいつまでも心を捕えられる。死せる者にも等しい敵に、捕われ続け、自らも死んだ魂を持つ者となる。心が自由になることは、決してない。
兄は、聖典に記された、カナンの地を求めて以来の我が民族の攻防の連鎖の歴史を、思い返していました。部族間の攻防・復讐の連鎖は、聖典の中でも、カルデアからエジプトに至るこの古い土地の多くの民族の間で、抗いようのない、神の掟の如き、無明の“真理”でした。そうして、限りない攻防の中で、多くの民族が滅び、消え失せ、我が民族も何度も滅びの淵を彷徨い、今また大帝国ローマに反逆して新たな滅びの危機を迎えようとしていました。――哲学者となれば、完全な人間となれば、敵を許し高めれば、――この滅びの円環から脱し、昇華し、自らもまた開放され、心の自由を取り戻す事が出来るのか?
子供の時思い、そして今も捕われ続けている、最悪の悪魔の誘惑、“世界を呪い、その滅びを願う”。そんな“駄々っ子”のような衝動からの、脱出口となるのだろうか?
完全なる人間ならば、哲学者ならば、――敵を許し、復讐を放棄するばかりじゃあない、――敵の高まる事を願い、彼を教化する。――その手段として、“頬を差し出す”?――“犠牲の子羊として、自らを奉げる”?
確かに、いくら相手の教化が本意であろうと、ただ正義の鉄槌を下したのでは、元々俗な相手はますます反発し、貶められていくばかりだ。――頬を差し出す、自らを犠牲にすることは、――遥かにインパクトがある。
ソクラテスよ、あなたはそうたくらまれて、ヒッピアスに頬を差し出したのですか?――問う兄に、ソクラテスの石像が答えました。――確かにペリパトスで頬を差し出したが、実はその先例があったのじゃ。それはな、――クサンティッペに頬を叩かれた時――ワシは女房を叩き返すなどという事は到底思いもよらず、思わずもう一方の頬を突き出してしまったのじゃ。あたかも、こちらの側にももう一発張り手を下さい、と言わんばかりにな。
それは、――そんな事を思わずされたのは、――“愛”故ですか? 兄は問いました。
そうかも知らん。いや、そうに違いない。――ワシはクサンティッペを心底愛しておる。だから、あれ以外の行動は、取りようがなかったのだ。
――兄に、閃きがありました。――愛故に、――敵もまた、愛する者となるのですか?――妻ばかりでなく。――遂には、敵も、……。
兄は、『ホセア書』の言葉、“私が喜ぶのは愛であって、生贄ではない”、『レビ記』の言葉、“自分を愛するように、隣人を愛しなさい”などを、次々と思い出していました。――まるでこれらの言葉に、言葉という皮に、生きた中身が詰まったように思ったのです。
信仰は、信じる事から始まります。皮を、信じる事から始まります。中身の生き物は、後回しです。あるいは、皮に中身があることは、むしろ故意に忌避して、考えないようにします。下手をすると、皮への疑いが生じるからです。――ですが今、兄の中で、皮と中身とスッポリ一つにまとまった、一匹の生き物が新たに生まれ出たように実感されました。これこそが、神の飼育する“真理”という生き物の一匹に相応しいと、思われました。
「でかしたぞ!――若者よ!」思い掛けない程興奮しつつ、石の無表情な顔面をポッと赤らめ、ソクラテスの像が兄に語り掛けてきました。「君は今、――ヘラスの“徳”に、――ヘブライの“愛”の衣をまとわせたぞ!」
チンケで滑稽なシレノスの如き像の興奮の意味が、兄には最初分かりませんでした。シレノスはタラコ唇を震わせつつ、説明しました。――“徳”とは、おのれ自身の問題だ。そも、ギリシャ哲学では、自己の探求ばかりに関心が集まり、他者へのまなざし(態度)が致命的に欠落しているのだ。――それは、他者への態度(やはり、愛ではなく、善(徳)であるところの)も含め、全てのものに原因を求めるからだ。原因は、自己の問題としてしかありえない。だから、自己のみを掘り下げる。――対してヘブライでは、絶対神という他者が常に存在する。思うに、だから他者との関係を、考えずにはおられないのだ。他者との間に、“愛”の交わりを持ち込むのだ。
びっくりした兄は、即座に返答し返しました。「実は私は、今それと逆向きの事を考えていたのです」――「ホウ。逆向きとは?――四百年の時を隔てた、我が愛弟子よ」今度はソクラテスが、問い返しました。
「あなたの言葉で、ヘブライの教えの皮衣に、中身が詰まったように瞬間感じたのです」兄は説明しました。「ヘブライの神は、良き父ではありますが、絶対神であるが故に、その命令は絶対です。我々は原因を求めません。全ては、神からの命令として、降って来るからです。そうした考えを第一義として、実存として捉え、おのれを律する者もおります。しかし、ただ命ずるだけで、その機序を明らかにしない聖典の記述が、私には不備と感じられてなりませんでした。例えば、もし私が誰かを教化するような立場になった時、『汝の敵を愛せよ』とだけ唱えたとしたら、それは実践のみの上っ面だけの強要であり、信者たる聞き手の内面を高めることは出来ません。もしその内実を、原因を、すなわち天の父が完全であるように、我々も完全なものを目指すべきである、という中身を吹き込まねば、それは虚しい命令で終わってしまうのです」
「フーム。君の論は頷ける。――一言、ギリシャ哲学の側から助言させてもらえば、君達が“絶対”“唯一”の神を選んだ時点で、既に神に“中身”を盛っているのだ。でなければ、ギリシャ風の俗っぽい神々でも、“イワシの頭”ですら、神として拝んでもいい理屈だからな。先程の、信仰を実存として律する手合いならば、それで充分だろう。――だが、ひとたび中身を盛り込んだ以上、もう君達の思想は、それの内部構造、理由付けの探求から、逃れることは出来ない。考えること、哲学すること、からね」
「思い掛けないことです。――私の考えたヘブライの思想の充実と、あなたの考えたギリシャの思想の充実とが、方向を逆向きにし交差しつつも、実は同じものであったとは」
「君の手柄だ。若者よ。――崇高な正義を、愛へと昇華、脱皮させたのだ。――“神”という中心軸を挟んで、反転させ、翻訳してみせたのだ」
――“靴屋風”を手にしつつ、兄の表情が見る見る変化していくことに、学者は気付いていました。ほんのトイレで用足しする程の時間で、ソクラテスの話の中から、コイツは何を汲み出したのだ? 後でじっくり聞き質したいものだ、と学者は思いました。もしかすると、自分の今まで思いも付かなかった新たな解釈まで、コイツは到達したのかも知らんな。瞬間兄の顔をまぶしく見上げながら、学者は喜びと羨ましさで、心を躍らせました。
この時期の兄は、まるで恋する者のように、あなたに取り憑かれておりました。あなたのお話を、帰ってくるなり、散々喋り散らすのです。我々の睡眠は、半分は飯場で半分はナザレ村の我が家でといった調子でしたが、そのどちらでも、消灯されて随分と真夜中になるまで、兄はあなたの事について喋りまくるのです。今でも憶えています。例えば、こんな話です。――古よりの普遍的正義感として、目には目をのような、等価復讐の原理といったものがある。だがそれはおかしいと、ソクラテスは言う。もし最高の徳を備えている人がいるとすれば、彼はそうした復讐を悪として放棄する筈である。そして人間が、最高善を目指すべき存在であるとするなら、人類は等価復讐の連鎖を、克服すべきなのではないか。――あるいは、こんな話もあった。ソクラテス風の問答を以って、“律法”を研ぎ澄ますべきである。これには、『バビロニア人ヒレル』と呼ばれた、離散ユダヤ人ラビ・ヒレルの影響も大分あったようです。ヘラスの論理学で、“律法”を研ぎ澄まし、純粋なものを抽出するという。――あるいはまた、ソクラテスさんがしばしばダイモンの声を聞くと知って、自分も時々主の声を聞く、同じだ、と言って喜んでいました。
ローマ人を懲らしめる方法を考えていると、兄は言いました。それも、ただ害するのではなく、最高善に相応しく、聖典にある通り、“汝の隣人を愛する”ように愛を以って相手を教え諭し、悔い改めさせ高めてやる、そんな方法だ、と強調しました。――聖典に言う隣人とは、同胞の内の隣人のことで、異邦人が入るとはとても思えません。と私が反論すると、兄は、――ヘブライの思想は“他者”との関係、取り結びの配慮を、本来のテーマとして内包している。兄弟や同胞という言葉を我が民族内に留めるのは、神の真意に背くことになる、と独自の考えを披露しました。
しかし、踏みにじられたナザレ村の事を、私は忘れられません。と私がさらに言うと、それでは獣の復讐劇と同じだ。我々は神から、敵を許す機会という、最高の贈り物を戴いたのだ。自らを鍛え、高める好機なのだ、と答えました。
ならばどうやって、ローマ人を改心させ高みに導こうというのですか。一旦相手をとことん叩きのめし、然る後言う事を聞かすのですか。訊くと、――相手を目覚めさせる攻撃は、インパクトの強い程良い。ただ暴力で対抗し続ければ、相手はますます寝入ってしまう。そうではなく、自らを犠牲として差し出し、相手が目を覚ますように、相手に訴え掛けるのだ。その方が遥かにインパクトがある。さすれば、かつてローマに征服されたギリシャが、精神でローマを征服し返したように、今度はギリシャ・ローマに征服されたヘブライが、愛で征服し返す事が出来るだろう。
人は、本能的に知っている。近場の力は、近場だけのものであり、遠ざかれば冷めていく。対して、近場では無力なもの程、遠く離れればその淡い輝きと輪郭で全てを包み込む。対決して滅んだ人や国よりも、右頬を打たれ左頬も差し出して滅んでいった人や国の方が、人の心に強く刻み込まれるものだ。
完全なる人間にならんとする兄は、いかにも哲学者らしく、純粋に知の産物のみで生き、地上に別れを告げているように思われました。兄は、“神の国”の住人となっていました。
兄は、これまで以上に熱心に、百人隊長を付け回し始めました。角々で待ち伏せし、隊長が路地を曲がり、行ったり来たりする様子を、柱から首の半分だけ出して伺います。バッカス神のトレードマーク、アイヴィー(木づた)の環を看板に掲げた酒場の前で、酔った隊長がふらふらになって出て来るのを辛抱強く待ちます。(ソクラテスは、ディオニュシア祭の折、ディオニュソス神からアイヴィーの絡まった杖を失敬し、それを振り回しつつ行進した事を思い出した。シレノスの振り回す杖に頭を叩かれると、アテナイの市民達は『福が落ちてきた』と言って喜び、さらに叩かれようと彼の周りに群がるのだった)
兄はさながら、ストーカーの類いと化しておりました。あちこちの物陰から覗き、迷路のような路地を先回りし、この、極悪非道な、そのくせおもて面だけは愛想のいい男を、いかにして真人間に戻し、崇高な信仰者に生まれ変わらせるか、兄は思案し続けました。――百人隊長の方も、そんな兄の存在に気付いていたようです。時々、不意と目を合わせると、笑い返してきたといいます。
シーカを、隊長に手渡したらどうだろうか。兄は考えました。そして、自分はあなたの命を狙っていたと、告白したら。――隊長の良心の琴線に、触れる事は出来ないだろうか。
さらに、隊長に迫ります。――どうかその短剣で、私を刺してくれと。かつて私の母を刺し貫いたように、今度は私を刺し貫いてくれと。――そうすれば、私の罪は贖われ、あなたの罪も贖われるだろうと。――――実はこのやり取りは、ヒッピアスとの“靴屋風”の中で、ソクラテスさん、あなたの提示した、戦場でのやり取りのシーンの再現でした。打ち負かした友の仇の敵兵に、短剣を差し出し、友を刺したように自分も刺してくれと、乞うシーンです。それは出来ないと、拒む敵兵。短剣の、相手への押し付け合いが続きます。(アキレウスとヘクトルが、短剣の押し付け合いをするのかと、嘲笑うヒッピアス)
兄は、隊長と短剣の押し付け合いの問答をする幻覚に、しばらく浸っていました。そしてその一瞬、刺す側と刺される側と、古今東西、未来永劫の果てまでの、全ての両者が、同じ一人の人間に重なり合った感覚に強く捕われ、抜け出せなくなりました。
――あのガリラヤ湖の少年兵達と、少年兵に刺された者達も、また同じだったと、兄は思い返しました。少年らを愛しみつつ刺し殺されていった医師達の顔が、久方振り脳裏に浮かんできました。――被害者であり、同時に加害者である者、すなわち少年兵。そして、かつて少年兵であった者、さらに将来少年兵に成り得る者、すなわち全人類。罪人であり、同時に哀れな生贄の子羊であるという地点にまで下り立てば、全ての人々が、同じ一人の人間です。
罪と罰と救いとは、ワンセットのものです。かつてユダ少年は、あらゆる人を少年兵に貶める事を画策しましたが、全ての人が落ち切る事を自覚した先にこそ、全ての人の連帯はあり、落ち切った先にこそ、登り詰める救いはあるのです。――いわば、悪魔の浅知恵を逆手に取った、神の離れ業、とでも申せましょうか。ですから、最も重い罪に落ちた神の長男サタンこそ、将来最も高く救済される理屈です、……。
――そのためには、まず自分が率先して、罪人であり、生贄の子羊であり、罪を贖う者でなければなりません。神の次男として、奇跡など起こし得ぬ人の子として、ユダ少年に無く自分には許された選択肢とは何か。あのカファルナウムの老漁師の顔が思い出されました。その顔と、ソクラテス師のそれが、ダブりました。似ても似つかない、片や無口で長く鋭い顔、片やお喋りで丸っこいヘチャ顔、の筈なのに。我が師ソクラテスのように、不条理な死を以って両頬を差し出し、遠い愛へと人々を目覚めさせる……。すなわち、近場の奇跡以上の、世界を包み込む奇跡。――兄は、そんな事を、夢見るようになりました。
どんどん変わっていく兄イエスが、正直怖かった。私の到底理解出来ない知者、そして怪物に、律法までも変えてしまおうという過激思想の持ち主に、兄が変わってしまうことが。
そのムセイオンの学者ばかりでなく、兄はセッフォリスのあらゆる街角に佇み、文字通り門前の小僧で、聞こえてくる全てのものを吸収しました、乾き切ったスポンジのように。あらゆる学問の場、学者の集まりに、自由学生、幽霊学生よろしく、首を突っ込み、出没しました。町の図書館のあらゆる言語の書籍を、片端から読み漁りました。商館にインド人の商人が逗留していて、珍しい話が聞けると聞き込むや、すぐに訪ねていきました。何でもソクラテスさんと同世代の仏陀とかいう高名な思想家がいて、商人にその信者が多いとのことでした。仏陀の言説を教えてくれるよう乞い、それを巡って商人達と問答しました。そして、仏陀が悟る前悪魔の誘惑を受けて悟りを妨害されたと聞くと、自分も悪魔に誘惑されるんじゃないかと、兄は本気で心配しました。また、仏陀が悟った後、衆生を象頭山という山に集めて説法をしたと聞くと、自分も大勢の人に説教する時は、山上でしてみようかと楽しげに話していました。
街にはヘラスの思想ばかりでなく、ファリサイ派、エッセネ派、貧しい大衆を扇動しての暴力革命、あるいは先程話したヒレル師の思想などが流れ込み、それぞれの伸張を図る活動家達が多数潜伏しておりました。当時のセッフォリスは、往時のアテナイに似て、さながら思想の坩堝でした。兄はそれらの者達とも、付き合いがあったようです。
ヒレル師は、『バビロニア人ヒレル』の名が示す通り、離散ユダヤ人の出で、従って律法も、そのままの文言を固守せんとする古老達と違い、ヘレニズム的に逆説的な掘り下げを極め、結果制度的形骸的なものは突き破られて、神と直接向き合うものへと到達していました。そんな流儀が、兄にはシックリきたようです。ヒレル派の集会から帰った兄は、どのように触発されたのか、“神とは、強者の口実に使われる存在ではなく、弱者の傍らに寄り添う存在である。ただ、寄り添うだけである。そして、祈りを聞き届けるだけである”などと、感慨深げに話していました。
また、乞食坊主やヒッピー風の風体をして、エッセネ派の集まりにしばしば顔を出しました。フラリと仲間に加わり、共に瞑想し、貧しい食事を取り、しばらく自給自足の共同生活を送ります。神との対話を、とことん突き詰めます。やがて、彼等の思想の悉くを吸収し、論難し、崇められ、敬遠されるようになりました。
エッセネ派を突き詰めると、その正反対の、“左道”に至ります。あえて律法を破ってみせ、それを誇示することで、神に近付こうとする行者達です。こうした一派は、逆の行を行います。ブタやイカを食い、安息日に目一杯働き、淫蕩に耽り、墓場で寝起きします。洗濯のために集められた大量の尿の酷い悪臭が立ち込める洗濯屋の裏手の空き地で、サバトさながらの饗宴が連夜催されました。ガルムを絞ったあとの『アレック』と呼ばれる腐敗臭の酷い下層民の調味料が山と盛られ、ブタやイカに味を添えます。画家気取りの顕示欲丸出しの壮大な壁画が、洗濯屋の裏壁に描かれています。それに、イソップ寓話から取った風刺的落書きが、幾つか添えられています。宿屋や路地裏や、あちこちからかき集められた女どもを交え、打ち続く騒がしいミサに、耐えかねた街の者等の通報により、出張ったアンティパスの警護兵らが、棍棒の連打で宴会を解散させました。首謀者は捕まり、兄等は、叩かれ、追われ、唾棄されました。
一方革命派からは、兄はある程度距離を置き、付かず離れず付き合っていたようです。殉教と裏切りの双方が絡まり合い、この頃の革命派は、不信、背信と、相互監視による恐怖でようやく成り立つという、そんな内幕を呈しておりました。彼等は焦り、大義を共有せぬ大衆に苛立ち、“誘拐”などの新戦略に活路を見出そうとしましたが、その前途は錯綜を極めるばかりでした。
兄が一時の気まぐれで入党したセクトも、こうした風潮の例外ではありませんでした。兄は、セクトのシンボルたるシーカも返さず、さりとて命令も遂行せず、アジトにも顔を出さない、いわば宙ぶらりんの“準裏切り者”として(こうした架空会員のようなノンポリの“準裏切り者”は、やたら数が多く、セクト総員の八割にも上ったと言います)、セクトに因縁を付けられ絡まれ、付け狙われたといいます。(兄が無事でいられたのは、同じような立場の者がやたら多く、セクト中枢の手が廻らなかったためです)
他方支配者層の社会にも、兄はしばしば首を突っ込みました。ギリシャ風の風体をし、哲学者を気取り、憑依されたように理想の人の生き方を真似して見せます。突飛な、ソクラテス的ひっくり返しの論難を繰り返し、人々のヒンシュクを買いました。
開明派で解放奴隷のローマ人の別荘で開かれたパーティーに招かれた兄は、そんな格好で悪びれもせずズカズカ上がり込みました。ハイソな社交的問答がパーティー会場のあちこちで演じられ、兄はそれらの小島を次々経巡ります。(もっとも、ほとんど誰も兄に面識がありませんでしたが。ただ中々気の利いたコメントをする若者だなと、人々に好感を残しただけで)
中庭の列柱廊に相対する位置の宴会場の広い壁面には、メダイオン(円形肖像)の中に鉄筆を口に咥える一人の女性詩人が描かれていました。この邸宅の、女主人でした。メダイオンを取り巻くクリネーの島では、女主人の詩を褒めそやす世辞が、盛んに飛び交っていました。そんな中に兄は、ソクラテスの盟友・靴屋のシモンの話題を投げ込みました。詩興などとはまるで無縁の、無粋な自然哲学者・技術者の登場に、一部の者は鼻白みましたが、見え透いた世辞にうんざりしていた当の女主人始め、この意外な方向転換の趣向に虚を突かれ、新鮮な風が懐に入るように大歓迎する向きも多かったようです。兄の提供した話題に触発され、クリネー上のインテリの何人かが、靴屋のシモンの簡潔さを好む人柄を讃え、その深遠な実験の幾つかを称賛しました。話題はさらにソクラテス一党とその哲学へと広がり、宴席の場は兄の独壇場となりました。
――兄は本来、ギリシャ・ローマの体制に批判的で、貧しい人々に強いシンパシーを感じ、伝統的ナショナリズムに憧れを抱いていたようです。しかしその思考のベースはヘレニスト的で、考えはヒレル派が最も近かった。
そんな、しばしば仕事をサボり、風来坊のように街中をほっつき歩いていた兄ですが、父のヨセフは目をつぶって何も言いませんでした。もとより自分の跡を継がせる気など、毛頭無かったのでしょう」
父ヨセフの話が出て、ソクラテスも父親ソプロニスコスのことを思い出していた。なるほど、イエスは自分に似ている。家業を放り出して、自分の信じる事のために街中をほっつき歩く。それを、咎め立てしない、父。
「そんな父ヨセフが、死にました。そして父の死の直後、一家は極度の窮乏状態に陥りました。
建設労働者に与えられる賃金など微々たるもので、その日その日の暮らしを支えるのがやっとです。勿論、蓄えなど微塵もありません。
その殆どを稼ぎ出していた熟練工の父が死んだのです。大黒柱を失い、母親と、多数の幼い兄弟達は、毎日空きっ腹を抱えてギリギリ生き延び続けることとなりました。
兄がどこからか、大量のパンを抱えて戻ってきました。――とうとう盗みを働いたか、瞬間思いました。しかし、こちらの気持ちを察したようで、「心配するな。――貰い物だ」そう説明しました。
ヘレニスト(ギリシャかぶれ)のシュンポシオンの会場から掃き出された、犬パンの残飯で、つまりは犬の残り物でした(シュンポシオンで、手を拭くためのパンを床に捨てると、それを犬が食べる)。金持ちのシュンポシオンでは、犬も満腹でパンを食べ残すのです。それを、「食え」と言います。私はつい、「今の生活を続けるぐらいなら、どこか金持ちの奴隷にでも買われた方が、遥かにマシです」と、本気とも取れる愚痴をこぼしました。あわてて、「それに、『申命記』にも、「人はパンだけで生きるのではない」とあります。ましてやヘレニストの使ったパンなど、何が付着しているか知れません。禁忌に触れるものが紛れている可能性もあります」と付け足しました。
「いいから、食え」兄は強引でした。「汚れたところまで食う事は無い。――それに、さっきの『申命記』の言葉は、「まずは、パンを食え!」という教えだ。食ってから、次の事を考えろ、という意味だ」そう言って兄はこちらにウインクし、まず率先して黒くて硬そうなところにかぶり付きました。
その後も、兄がヘレニストの屋敷の門前で、召使の奴隷とギリシャ語で交渉している姿を、何度か見掛けました。掃き出された犬の食い残しを、掻き集めて、貰って帰るのです。そんな状態が、私達の次の仕事場が見付かるまで、一ヶ月近くも続きました。――いい所を丹念に選り分けて、しばしば村への土産に持って帰りました。「犬の食い残しだなんて、母さん達には言うなよ」こう言うと、兄は陽気に笑いました。
20代の半ばに達した頃には、兄はムセイオンの学者をすでに凌駕していました。兄は学者の友となり、アドバイザーとなり、ついには立場が逆転してかつての師の師となりました。
セッフォリスの道行く人々を捕まえては、ソクラテスさんの真似をし、問答を吹っかけていました。終いには、街の人々は、兄の姿を見ると道を迂回して通るようになりました。兄は、問答チャンピオンのソクラテス、その人に生き写しでした。あらゆる発想の切り返しを、譬え話を、弁舌の技術を駆使して、人々を屈服させ、魅惑し、従わせるのです。(ソクラテスさんが、靴屋や船乗りや、アテナイの工人や商人の譬え話を好んで使ったように、それに倣って兄もよく、農民や使用人や、ガリラヤの庶民の譬え話を好んで使ったものです。)各派の活動家らも、革命派のゴロツキ扇動家も、兄と問答して太刀打ち出来る者はもういませんでした。活動家らは、兄の話を聞く側に廻りました。
ニーチェのツァラトゥストラの如く、精神が膨れ上がり、とうとう兄は街から飛び出しました。と同時に、家出しました。
一番の働き手が、突然家を捨てたのですから、当然家族の者達は兄を悪く言いました。母のマリアなど、「あの、道楽者が!」と、一番口汚く兄を罵りました。そうでなくても、日頃インテリぶって家族の理解出来ない事を好き勝手に口走り、一人だけ皆から浮いていた兄は、親兄弟に疎まれていたのです。そんな状態で大家族一家の生計を支えることに、兄は疲れていたのかもしれません。
その後の事は、ご存知の通りです。30歳にして外の世界へ飛び出した兄は、まずヨルダン川に沿って南下し、エッセネ派の者達と共にしばらく暮らしました。次いで洗礼者ヨハネの弟子となりました。ユダの荒野で一人瞑想に没頭した後、捕縛されたヨハネの跡を継いで、ガリラヤ湖周辺で教えを説く活動を開始しました。
セミの喩えが、相応しいでしょうか。30年の幼虫としての長い成長期の後、3年間の成虫として鳴き通す夏の活動の日々が訪れました。
ジェットコースターのように、既に定められたコースを、兄は残りの三年間で一気に駆け抜けました。――ソクラテスさんのダイモンと、兄の神は、同一なのかもしれません。人類史を動かすために、“人の死”を生贄として欲する神です。
あなたと、『イザヤ書』の中の“主の僕”の二人の運命が、兄が世に出てからの3年間の航路を、あらかじめ定めていたのです。『イザヤ書』が預言した“主の僕”は、救い主であり、苦難の僕であり、自ら犠牲となる事で、世界を清められました。つまりあたかも、“新たなダイモンに殉教した”ソクラテスさん、あなたの事のように読めた訳です。――兄は憧れの“ソクラテスの範”を、忠実になぞりました。毒ニンジンの代わりに十字架を、最終到達点と思い定めて。そのためにわざわざエルサレムに上り、悪しき権力者どもと愚かな民衆を煽り、不当な判決と愚かな刑死という滑稽な悲劇を引き受けて、人々の心に消えることのない傷跡を残す事に成功しました」
青年イエスの辿った軌跡が、自分のそれとすこぶる似ている事には、ソクラテスもまた気付いていた。真実を唱え、悪人の讒言と愚かな民の暴発により死刑を宣告され、無実の罪で殺される。後のヘレニズム世界で、ソクラテス裁判のエピソードを知らぬ者はいない。人々は、ソクラテスとイエスを重ね、その悲劇の構造を即理解出来た。――ただ、ソクラテスが70歳まで悠々と生きたのに対し、イエスは30を少し過ぎた頃、生き急ぐようにしてたった3年で、自ら死地へと飛び込むように同じ道を突っ走っていったのだが。
「君は、兄さんの自殺するような死は、全てワシをなぞったものだと言うのかね。ワシの死のドラマを、再現したものだと」ソクラテスは、おのがムーシケーの発露を、誇らしいと思う一方、数百年を隔てた異民族の若者の死に責任を強く感じ、“済まない”という気持ちで一杯になった。
「その通りです。――ソクラテスさんの“死”は、“哲学”として問われ、兄の“死”は、“宗教”として問われました。他の、凡俗の、問われない“死”とは、まるで違うのです。――特別な、“聖別された死”、なのです」ヤコボの返答は、深い諦念を抱きつつも、満足の甘露に満ち満ちていた。――だがそれはすぐ、悲嘆の色へと取って代わった。
「この地方にありがちなファミリー・ビジネスだと、笑って下さって結構です。――たとえ刑死の寸前まで不仲であったとしても、兄が父ヨセフと母マリアの間に我ら兄弟の長兄として生まれ、そして家族が片時も離れることなくずっと一緒に暮らしてきた、――そうした30年という歳月は、動かし難い事実なのですから」ヤコボは、朴訥としたガリラヤ訛りのアラム語で喋り続けた。「兄の死後、家族の者は手の平を返したように、イエス派に帰依しました。兄の運動の成功を目撃したからです。
かつてガリラヤ湖周辺で兄が説教して廻っているという噂が耳に入った時には、家族して兄を呼び戻しに行ったものでした。いや、取り押さえて、無理やり連れ戻すつもりだった、と言った方が正しい。兄の周囲に、大勢の弟子や群衆がいて、それは実行出来ませんでしたが。
我が母マリアは、さしずめソクラテスさんのクサンティッペ、といった役どころでしょうか。我々兄弟が怒りで怒号を上げる中、それを上回る勢いで、一人目立っておりました。――兄の服をつかんで離さず、ヒステリックに息子を叱咤し続けました。「何やってんの、恥ずかしい、――」「子供の頃は、働き者の良い子だったのに、――街へ出たら、すっかり生意気な口を利く、不良になっちまった、――。街の浮かれた奴等に、染まっちまった、――」村の外を何も知らない母にとって、街は魔物と誘惑と堕落の巣窟でした。「お願いだから、村に帰っとくれよ。ちゃんとまた、畑で働いとくれよ。真っ当な人間に、戻っとくれよ。――」
母を引き摺りながら、兄はシカトし通し、「この婦人は誰か?」などと言いつつ、体裁を取り繕っておりました。群衆の中の多くの者が、苦笑を抑えられませんでした。当時の兄にとって最大の敵は、“ファリサイ派”と“実家”だったようです。――それが、“聖家族”などと持ち上げられ、エルサレムに引っ張って来られ、私始め兄弟や従兄弟達は教団の中枢に抜擢されて、――母などは人々の信仰の対象にすらなりました。
あの、理解不能だった兄の代理を務める程の恐怖が、他にありましょうか。――しかし、十二使徒筆頭のシモン・ペテロは、フラフラしていてどうにも頼りにならないし、新参者のインテリ面したヘレニストどもは、我々をガリラヤの田舎者と侮って、勝手し放題に教義を捻じ曲げて平気な顔をしています。――本当の兄を、兄の教えを、理解している者は誰もいなかったのです。ですから、無理は承知で、私は教団代表を引き受けざるを得ませんでした。
及ばないながらも、私は何とか兄に追いすがろうと、懸命に努力いたしました。思想内容までは到底無理でも、少なくとも行いだけでも正そうと、清貧と敬虔に努めました。キュニコス派の残した、ソクラテスさん、あなたの姿を参考にしたのです。おかげで『義人』と呼ばれるまでになりました」
『義人』と呼ばれたイエスの弟ヤコボは、敬虔で、質素で、貧者達と共に常にいた。身支度も沐浴も拒否し、飲食も最低限のもので済ませ、いつも跪いて神に祈り続けていた。身に付けたボロ布以外は、何も所有していなかった。彼は、誰から見ても、文句の付けようのない『義の人』だった。そして『律法』を、厳しく守った。――そんなヤコボは、キュニコス派、アンティステネスの書いた『靴屋風』のワシを、真似たと言うのか。この目の前の貧相な乞食坊主が、ソクラテスの真の姿なのだと後世の人が信じているとしたら、『靴屋風』とは何と罪作りな代物だろうか。
「我々ユダヤの民は、古来訓詁学が大好きです。すぐに聖典を引用し、「――に、――と、書いてある」などと話します。――しかし、兄の天才は、そんな萎びた学者の訓詁学などに納まり切れるものではなかった。
――トーラーをソクラテスで研ぎ澄ます。――兄はしばしば、そんなことを熱っぽく言っていました。
「どういうことですか、兄さん?」大麦の引き割り粥を啜りながら、私はよく訊いたものです。
豚イカだの、割礼だの、病人や娼婦の穢れだの、安息日だの、そういった余計なサビはとことん削ぎ落とし、鋭利な一振りの、真にトーラーであるトーラーにまで磨き上げる。ヘラスの哲学の理性による弁証法、あの天と地をひっくり返すようなアクロバチックな発想と探求力を用いて。――兄はそう、説明を加えました。
しかし、無学なガリラヤの地の民に、私や使徒達も含め、そんな地の民の集まりに過ぎぬ教団の信徒達に、兄の教えの真意など分かろう筈もありません。
ですから、パウロ等ヘレニストの唱える律法無視の方が、むしろ兄の本意には近い可能性もあります。少なくとも、ただ素朴に律法の文言通りに生きていればいいとは、兄は考えていなかった。従うだけではなく、考える事を極め真のトーラーの教える深淵にまで下りていく。それが兄の目指したものでした。
兄の天才、その意思を汲むなどとても出来ないと、懺悔するしかありません。いくら『義人』を気取ろうと、上っ面のカリスマにしか過ぎません。イエスの名を継ぎ、人々を指導していく資格など、私にあるとは到底思えないのです。
そんな、兄のようにトーラーを磨く能力の無い私は、ただ敬虔にそれに従って生きるしかなかった。ユダヤ同胞の顔色を伺い、教会の存続を図る一方で、献金や異邦人信徒の同道で示威行為を繰り返すパウロを完全に切り落とした。結果、教会を二分することとなった。(その後、ヤコボ派はユダヤの反乱と運命を共にし、キリスト教のダイバダッタに当たるパウロ派が勝ち残った。)――しかし、体制に迎合する行為は、多分最も反イエス的な行為だと思います。兄の生き方とは、まるで真逆です。もし兄が今ここに戻り、教会の指揮を執ることとなったら、兄は間違いなくユダヤ同胞への追従をきっぱりと断り、その恨みで“再度十字架に掛けられる”こととなるでしょう。……」
そう言うと義人ヤコボは、とめどなく涙を流し始めた。黒い煤とヤニだらけの顔を、幾筋もの流れが洗い清めた。
*
物語の連鎖が、ここで突然途切れた。今まで、探究心と連想の赴くまま、百を超える巻物、冊子類を開き、繰り続けてきた。その本の流れが、ここで、途切れた。
――図書館の奥深い薄暗がりから、人とも何ともつかぬ影が、ボーッと現れ、ゆっくりとこちらに近付きつつあった。
『ミノタウロス、か?』何故かそんな単語が、浮かんだ。大図書館の、迷宮のような建物、施設、蔵書群の錯綜し渦巻く内容が、そんな連想を生んだのだろう。
近付いてきたそのものは、確かに『ミノタウロス』と呼んでもよかった。ただし、年老いて、盲いて、すこぶる弱々しかった。“牛顔”をした、老人だった。杖をつき、窮屈そうな奇妙な服装をしていた。
ミノタウロスの老人は、自分はボルヘスという詩人である、と自己紹介した。――その声は、あの、懐かしいダイモンの声、そのものだった!――この老人が、あの知恵の者、ダイモンだったのか! この迷宮の主であり、アポロンの代理人、――(似非のアポロニウスではなく、)真の図書館長、その人なのか?!
『アレクサンドリア図書十進分類法』では、私は963番に分類されております、と老人はさらに語った。――盲目の詩人ということから、ソクラテスはあのホメロスを連想した。カリマコスの抄説によれば、ボルヘスとはソクラテスの時代より二千数百年後の世界の、高名な詩人であり、ストーリー・テラーであるようだ。――この者は、ホメロスの転生した姿ではないのか? 『ホメロス』『ボルヘス』という二つの名が、ヘブライの学者がよく使う、『テムラー(アナグラム)』の技法を思い起こさせた。ラテン文字で音声表記として綴ってみると、『HOMEROS』『BORHES』となろうか。あながち、的外れでもないだろう。ただし、ホメロスの心象には、文字は一つも存在しなかったが、一方三千年の時を経た生まれ変わりのボルヘスの頭脳には、この図書館の全ての蔵書が収まっているようだった。
「あなたがワシを、導いてくれたのですか?」ソクラテスは問うた。
「左様。――レファレンス・サービスは、図書館の重要な業務の一つですから」――神託が成就出来るよう、便宜を図ってくれたという訳か。「あなたのヴェルギリウス役を務められて、大変光栄に存じます」(ダンテの『神曲』を、念頭に置いての言葉だろう)
「あのイエスという若者が、ワシの産み落とした最高のムーシケー、ということになるのだろうか」
「さあ、どうでしょう。それはあなたの、お決めになる事です。――あなたの、ムーシケーですから」微笑みを絶やさず、ミノタウロスは答えた。
「ならば、さらにレファレンスの続きをお願いしたい。――ワシには余りに、知らない事が多過ぎる。このままでは、死ぬまでに到底、ムーシケーなど創り得ません」
見渡す限りの全ての胸像が、口を開き始めた。
「俺を読め! 俺を読め!」と一斉に連呼し出す。とてつもない騒乱、和声の洪水である。
ボルヘスが、コンダクターのように杖を一振りし、この騒ぎを鎮めた。
「皆、あなたに読まれたがっているようです。さすが、開祖ソクラテス師。憧憬に値する人望です。――だが、全てを読む、――『想起説』に立つならば、思い出す、訳にはいかない。書物達を繋げる、筋書きがなければ。すなわち、ムーシケーが。
それに、あまり図書司書のレファレンスに頼り切るのも、考えものです。若いエウテュデーモスさんに、他人の思考の枠に呑まれ過ぎてはいけないと説いたのは、あなた自身でしたよね」
迷宮の主ミノタウロス・ボルヘスは、杖に頼りながらヨロヨロと歩み続けた。ソクラテスのいる位置が分からず、探しているのだろうか。仕方なくソクラテスも、その後について歩く。
「『想起説』と仰られると、」とソクラテス。「この大図書館の本の中身をワシは既に全て知っていて、本を読むのはそれを思い出すための行為であると、そういう意味ですか?」
『想起説』とは、プラトン等により考えられた、認識論の一変種である。無限の輪廻転生を繰り返す内、人は全ての知識を得ることになる。しかしその殆どを、生きている内は一時的に忘却している。人が何か新しい事を思い付くのは、実は思い付いたのではなく思い出したのである。
とすると、ここは、ワシのプシュケーの記憶の集積場、という事になるんだろうか。何代も、無限に輪廻した人生の記憶が、ここに蓄積されているという訳だ。――子供の頃から、夢や白日夢の中で、ここを何度も訪れた事があると、思い出されてくる。懐かしい。確かに、ここだった。
「仰る通り。――全ての知識を有していても、ただ知っているだけでは、何の意味もないでしょう?――あるパターンに秩序付けてこそ、知識は輝くものです。
ですから、“生きる”という事に意味がある。無知な状態から生きていけば、一つの流れを掴み取ることになります。一つの人生では、複数の可能性を同時に掴む事は出来ませんからね。
今回は、私がレファレンス役を担当いたしましたが、……。御覧なさい、――」
ボルヘスは、いつの間にか到達したエリアの胸像群を、杖の柄で指し示した。そこには、ムーシケーの凝結した“軸の時代”を唱えたヤスパース、飢えたアフリカの子供達の前にムーシケーの無力を説いたサルトル、ユダヤの悲劇を増幅させたアドルフ・ヒトラー、そしてボルヘス自身など、多くの著述家の胸像があり、皆口々に小声で「俺を読め! 俺を読め!」と呟いていた。
「誰がレファレンス役を引き受けるかで、人生のパターンはまるで違ったものとなります」ボルヘスは続けた。「ヘビの脱皮の如く、想起と忘却(レーテー)の循環により、こうしたレファレンス・パターンは造られていくものです。
アスクレピオスの治療は、ご存知でしょう?」
アスクレピオスの治療とは、神殿内で眠りにつく内、夢の中にヘビが現れ患部をひと舐めすると、目が覚めた時既に治癒しているというものである。
「心の病もまた、アスクレピオス神の得意分野です。ヘビにひと噛みされると、患者は適度に忘却し、安らぎを取り戻すのです。
アポロンとアスクレピオスの父子の働きにより、想起と忘却は効率良く循環し、新しいレファレンス・パターンが創造されていく訳です」
そうなのだった。カリマコスは目録を造りながら、果たしてこの分類に固定してしまっていいものなのかと、絶えず自問していた。いつも、新しい分類基準、新しい本の流れが脳裏に浮かび、それが刻々変化していく。だが目録に書き留め、それを固定化してしまう作業を、止める訳にはいかない。あるいは、人生に余力があったら、第二、第三の分類法による目録を編纂しようかと、カリマコスは夢想することがある。だが多分、短い人の一生などでは、到底成し遂げられない望みなのだろう。
「人の一生は、一筋の流れでしかありませんが、――他の流れを擬似的にせよ体験させてくれるのも、またムーシケーの効能の一つといえるでしょう」一つの柱廊を渡り切り、新しい部屋に抜け、ボルヘスは微笑みつつ言った。ミノタウロスは、迷宮の中心に居座り、クモの如く獲物を待つものだが、この盲目の老人は鈍足ながらもよく動き回るようだった。
「他の、流れ?」平凡な一人の人間に過ぎない自分にとって、人生は一筋の流れしか許されないし、そんな自分から始まる人類の歴史も、今日レファレンスで見てきたような一筋の流れでしかあり得ないだろう。だがもし、――
だがもし、――脱獄を果たし、別の人生を歩み始めれば、――ワシの“崇高な死”や“哲学のための殉教”を取り消してしまえば、――新たなるムーシケー、新たなる人類史が、別の一筋の流れとして、そこから分岐する。
そのためには、明日朝起きて、ただクリトンに首を縦に振って見せるだけでいいのである。ただ、それだけで、……。
――ソクラテスは思った。さらに、思い続けた、……。――
……しかし、そうなれば、――かのイエスという若者も、存在し得なくなる、……。よしんば存在できても、遂にワシを知ることなく、ただ一介の過激な反乱分子として、一生を終えることになるだろう、……。
……――……。
……ワシは、あの若者一人のためだけに、……死を選んでもいいのではないか?――ソクラテスは思った。
他の弟子達は、ワシを裏切ったり、勝手に解釈したり利用したりしたが、――この四百年隔たった、最後の弟子一人のためならば、――ワシは死んでもいいのではないか?
――不思議だった。――イエスの事を思うだけで、――イエスとの交流を思い返すだけで、――“脱獄”を巡る全ての悩みや迷いが、まるで無かったもののように晴れ渡っていった。
相変わらずボルヘスの後に無意識に付き従いながら、――ソクラテスは今自分がどこにいるのか、しばし失念しかかった。
――見知らぬ者達の胸像群が続いた。これら胸像は、墓標でもある。図書館は、既に死んだ者達の魂の、集積場でもあるのだ。読まれる度、魂達は蘇り、徘徊し、語り、嘆き、叫ぶ。さながら日本の夢幻能そのままに、愚痴を言い合う亡霊達で溢れる。それは、広大な“供養施設”である。そして、本来なら話も出来なかった時間空間を隔てた者達の、告発し合いにより裁かれる、時空を超越した“裁判所”でもある。それはさながら、ハデス(冥府)の一部であるようだ。
ここにある知識を、一生の内に取り込もうとしたら、果たして何万歳寿命を必要とするだろうか。だからこそ、死ぬ間際のみ、ハデスの一部たるここを訪れることが許されるのだろう。そしてもしここにそのまま身を置き続けることが出来るとするなら、人は不死となり、神の如く全世界に同時に存在するものとなろう。――だがそれは、許されないことだ。特権的時間は、まもなく終わる。
――その時不意に、盲目の詩人が杖をコツと鳴らし、立ち止まって声を掛けてきた。「あなたのお友達に、シモンさんという方がおられましたよね」
懐かしい名を聞き、ソクラテスは嬉しかった。「ええ、おりますとも。――古い友が」
ボルヘスは、立ち止まった部屋の異様に広い空間を、見えない目で見渡すように、ゆっくりと首を振った。「この広大な空間に詰まった知識は、あなたの時代から二千年経った以降の、自然哲学に関するもの達です。――若い頃あなたを失望させたあの自然哲学は、その後二千年間、沈滞し続けました。だが二千年後、あなたに似た団子っ鼻の学者が、シモンさんの発見した水晶玉を覗き込んだ時から、突如生き返ったように急激な発展を遂げ始め、僅か数百年でこの部屋一杯の知識を生み出すに至ったのです」ボルヘスはそこで身を屈め、“ダーウィン”とプレートの附された胸像と、しばし立ち話を始めた。
「結果、シモンさんのような人が、何万人、何十万人、何百万人も生み出されることとなりました」再び、ソクラテスに語り掛けた。「究極のレファレンスの創造は、図書館の見果てぬ夢です。いわば、“生きた体系”。生物の如く柔軟に流動し、新陳代謝し、絶えず流転して止まない“体系”。全てのレファレンスを統合する“体系”。全人類の“全体知”をリンクさせ、さらに参照する“体系”。静かに固定されておらず、騒がしく動き回る図書館です。あたかも図書館自体が、一個の生きた頭脳であるような、人さながらプシュケーの宿るような、そんな図書館です。――それを、何万人にも膨れ上がったシモンさん達は、実現させようとしている。――」
やはり最後は、シモンか! ソクラテスは吐き捨てるように、憧れの光を仰ぎ見るように、言った。――この、ムーシケーを巡る図書館の探求も、――最後を締めるのは、シモンか!
かつてギリシャの伝統が文字や書物を蔑視したのは、それが一つの形に固定化されてしまうからである。それが、生物のように動き回り、人間のように頭脳を持つというのであれば、ギリシャ人の抱いた心配はさしあたりクリアーされる訳だが、しかしそれではまるで、ヘブライ人の妄想している“ゴーレム”ではないか。図書館が、ゴーレムの如くなって、動き回ったり考えたりするというのか?――だが、あのシモンが、何万人がかりで実現させようとしているのなら、――出来ない事では無い。
「このダーウィンさんの頃からなのですが、」とボルヘスは、先程の立ち話相手を指し示した。「自然哲学が、自然ばかりでなく、人間のプシュケーまでも呑み込んでしまったのです。人間だって自然の一部なのだから、当然といえば当然なのですが。――こうした着想は、既に古代ギリシャ時代、唯物論者達の間でありましたよね。――ですが、二千年を経て、それが現実のものとなりました。ソクラテスさんがテーマとした“善”や“美”や“知性”といった人間性そのものまで、アナクサゴラスの物性哲学で説明出来ることとなったのです。――いや、――そういえば既にシモンさんが、かのシュンポシオンの折、そうした“心性”と“物性”のハルモニアの真理を証明し、“生きた体系”を無限に綴り続ける自動機械の創作を、宣言していらっしゃいましたよね。――それが、二千数百年の時の蓄積を得、さらに“遺伝子工学”や“脳科学”や“AI”の発達により、シモンさんの子孫達の手で、パルテノンやムセイオンを組み立てるように、“善”や“美”や“知性”で、図書館を組み立てることが可能となりました」
ソクラテスは、多くのシモン達が寄ってたかって、あたかも諸々の素材や機械や薬品を使ってとんでもない発明品を造り上げるように、“善”や“美”や“知性”を材料にして、一個の人間のような図書館を組み立てる様を想像してみた。
「もしかすると、――それが最終的なムーシケー、という事になるのだろうか?」迷宮の主に恐る恐る問うた。
「分かりません」ボルヘスは肩をすくめた。「とても人知の及ぶ所ではありません。その遥か先の、踏み込み得ぬ世界の話です」杖の柄に両手を重ね、立ち止まったまま動くのをやめてしまった。
やがて、混乱するソクラテスを突き放すように、ボルヘスは容赦なく言い切った。「以上で、――私のレファレンス業務は終了いたします。ここから先は自分で考え、判断し、決断して下さい。――あなたに残された時間は、もうあと僅かなのですから」
「だが、我がダイモン・ボルヘスよ。――ワシはあまりに未知の、未来の深淵を覗き見ちまった。いや、見させられた」ソクラテスは、必死に懇願した。「このままでは、ムーシケーを創るどころでは無い。混乱した頭のまま、最後の朝の目覚めを迎えそうだ。――そんな、気のふれた様な気分のまま死地に赴くなど、余りにムゴい。ワシに、救いはないのか?」
その泣き言に振り向いたボルヘスは、「安心なさい。策はあります」ニヤリと笑った。「先程話した、アスクレピオスのヘビです。――このヘビの力を借りれば、適度に忘却し、癒され、うまく考えがまとまって、きっと良いムーシケーを生み出すことが出来ますよ」ボルヘスの持つ杖の上半分が、ヘビに姿を変えた。それは、ソクラテスの首にまとい付き、チクリと小さな刺激を与えた。
――これが、アスクレピオスの治癒の力か。――気分が落ち着き、余計な考えが振り落とされ、新たに思考をまとめる意欲が湧いてくる。
「それでは、良いお目覚めを」ボルヘスが軽く会釈した。
大図書館が視野から薄れゆく中、ソクラテスは一つ大事な事を思い出した。――そうだ。アスクレピオス神に、治療代の供物を奉げねばならん。死ぬ前に、忘れずクリトンに、頼んでおくとしよう。――
クサンティッペと赤ん坊が、赤ん坊を間に挟んで添い寝していた。だが、目を開けたソクラテスは、そんな二人に殆ど気付きもしなかった。クサンティッペに語り掛けられ、赤ん坊に泣かれても、上の空だった。
看守が牢に入ってきて刑務委員の到着を告げても、十一人の刑務委員に刑の執行を申し渡されても、ほぼ一ヶ月間苦しめられた重い足枷を外されても、やはり上の空だった。
自分は夢の中で、どこかにある大図書館にいた。その広大な部屋部屋も、無辺に連なった書棚の列も、よおく憶えていた。――だが、その書棚に詰まっていた筈の書物の記憶が、スッポリと抜け落ちていた。
レファレンスを受けた事は、鮮明に憶えている。広大な知識の水脈を、その本流から遥か末端のせせらぎまで、たどり尽くしたのだった。――宇宙や物質の構造・成り立ちを、知った。人や生物の身体・精神の進化と、それらを裏で支えるイデア・ロゴスの情報学的振る舞いを、理解した。全てのバルバロイを取り込んだ人類の全体像と、その歴史の大奔流を、読み尽くした。数学の不思議なパズルの極みを、味わった。“真・善・美”を成り立たせているプシュケーの仕組みを、悟った。――こうした項目とリンクの、インデックスのみ残っている。全て理解していたという、実感だけが焼き付いている。大図書館とインデックスの、抜け殻のみ頭にある。――だが所詮、夢とはそういうものだろう。
こうして夢の続きをまだ追っているようなソクラテスだったが、クリトンら仲間や弟子達が牢に現れるや、飛び付くように反応した。
「今日は、プラトン君は、来ていないか?」食い付くように質問した。
この勢いに少し面食らったが、パイドンが答えた。「プラトンの奴は、病気だったと思います。確か数日前から、熱を出して寝込んでいると聞きました」
それを聞いたソクラテスは、そのドングリまなこがいつもよりさらに大きく見開かれ、口の端がワナワナと震え、とても数時間後に死刑になる人間とは思えない、尋常でない相貌となった。――そして、言った。
「お願いだから、プラトン君を、呼んできてくれないか。――どうしても話したい事があるのだ。もう時間が無い。是非とも、頼む」
「ですが」とパイドン。「先生の最後に来られない位ですから、相当に悪いのではないかと、――」
そう聞いても、ソクラテスは引かなかった。「後生だ。――無理やりにでも引っ張ってきてくれ。君等にもだが、彼には特に、是非とも言い残しておきたい事があるのだ。――もう後数時間しか、猶予が無い。哀れな死刑囚の最後の願いだと思って、――」――そこで、数名の者がプラトンの家へ急ぎ赴いた。
クリトンが、たまりかねたように、目配せしてきた。左手に杯を持ち、右手はキトンの膨らんだ腹の辺りに当てている。――ソクラテスから覗けるよう懐を緩め、例の小壺を見せた。そして何気ない素振りで、杯をソクラテスに差し出し、小壺に右手を置いた。
ソクラテスは自らの手の平を、杯に蓋をするように、その上に被せた。そして、クリトンを見詰めつつ、大きく首を横に振った。
クリトンの落胆の色は隠せなかった。最良の友を、今日失う。その事実が、彼を打ちのめし、深い絶望の淵をしばし惚けたように彷徨わせた。
ソクラテスは、そんな友の様子に、“済まない”という気持ちで一杯になった。しかしそこに、400年後に生まれる筈の若き弟子、イエスの満ち足りた表情が浮かび出、それが鮮明になるにつれ、他の気持ちは総て打ち消されていった。
――やがて、プラトンが、フラフラしつつやって来た。――これまた、とても数時間後に死ぬ人間とは思えない喜びようで、ソクラテスはプラトンを迎え、愛弟子を自分の脇に座らせた。そして他の者達も、自分の話が聞けるよう、寝台の周囲に輪を造らせた。
弟子の容態を案じつつ、ソクラテスは話し始めた。
「今日の夕刻、ワシはこの世からひとまずオサラバする。――そしてこのグループが集まることも、今後数年の間は出来なくなるだろう。何故なら、反対派の追及が厳しくなるからだ。当分の間、多くの者がアテナイ外へ、難を逃れねばならなくなる」
グループの者等は、互いに深刻な表情で頷き合った。そうした事態は、大方想像されていたからだ。
「だがそうした成行きを、むしろ好機として捉えて欲しい。――アテナイ外へ出る事は、君達を一人前の哲学者へと脱皮させる。外で学び、かつ教え、それぞれの哲学を開花させて欲しい」この励ましは、弟子達にとって意外なものだった。何故なら、ソクラテス自身、アテナイから出たことがなく、このポリス内ですべて事足れりとしていたからである。しかしソクラテスは構わず、死期の近い者のように先を急いだ。
「代表として、プラトン君について、予言しておこう」ソクラテスは傍らの若者を、温かいまなざしで振り仰いだ。「君はワシと違って、どんどん世界へ出て、見て廻らんといかん。――例えば、東方世界だ。エジプト、ペルシア、ヘブライ、カルデア。これら古い世界で、各地の神官、賢者、預言者、マゴス達と、知恵の交換をするとよい。西方の新興地では、ピタゴラス学派達などから、新しい考えが学べよう。
そうした知恵の交換から、大きく稀有な大樹が育つ。やがて数百年後、かの地でも、君のような有為で聡明な若者が、その大樹に花を咲かせ、実を付けることとなろう」
プラトン青年は、病気で熱っぽいのか、師の励ましに上気しているのか、判別つかない顔をしていた。
「そしてこれは、プラトン君に限らず、皆の、――いや哲学全体の将来に関わることだが、――。
さらにワシは、ムーサの女神達を祭る神殿、学問の殿堂たる学園、そして多くの書物の詰まった図書館、を夢想する。ポリス中の、ヘラス中の、いや世界中の学徒や研究者を集めた学園、学究施設。そしてそれに併設された、世界中の書物という書物を、何百万巻も集積させた、大図書館。――そんな夢みたいな事出来るのか、と諸君らは疑うだろう。確かに、まだこの世のどこにもない、夢のような事どもの話だ。実現のためには、何世代にも渡る、歳月を要するだろう。
――ワシはかつて、“書き物は所詮、話し言葉の影に過ぎん”と言った。だがこの影の広大さは、“知”の総てを覆う。書物とは“想起の種”だ。つまりこの影を可能な限り展開させ得れば、想起の元たる“全知識”に現世で極限までアクセスする事が出来るということになる。
よって、『ムーシケーを創り、ムーシケーに励め』と、君達に言付けておきたい。――実はワシもアポロンからそう言付かったのだ。だがワシ一代では、到底実現出来る神託ではなかった。だから代々、この神託は、神から言付かったものとして伝えていって欲しい。
多くの影を造り、人々をその下に憩わせよ。そして彼等もまた、ムーシケーの許にいざなうのだ。……」
ソクラテスの話は、ますます熱を帯び、いつ果てるともなく続いた。皆が“ムーシケー”の話に夢中になり、それの永遠の連鎖に囚われ、物事には終わりがあるという事をすっかり忘れてしまっていた。この世界に、“夕刻”の来る気配はなかった。 了
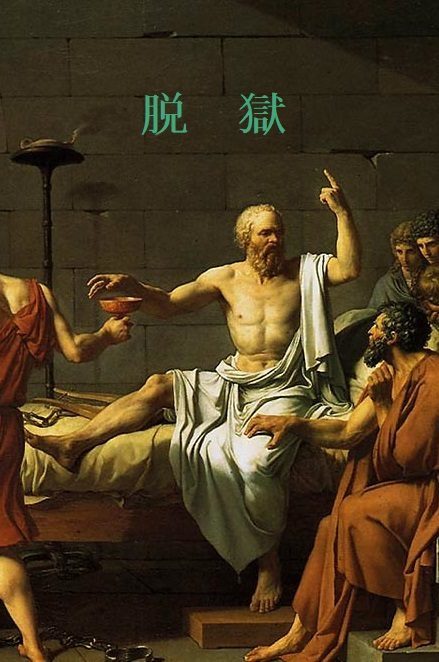






















"脱獄"へのコメント 0件