11月の上旬は、唐松の紅葉が美しい。原生林や雑木林は数多くの樹種が混在するため、紅葉はまだらでまばらなのだが、この辺りの唐松樹の植林域は、ある朝一気に色づき、一斉に散るまで、ひと山ふた山まるごと橙色に染め上げられる。秋晴れのシアンブルーとマンダリンオレンジのコントラストは素晴らしく、紅葉と呼ばれる情景の中でも特に美しいと思う。11月初旬の連休をすぎると、観光客はほとんど訪れず、その最高の風景は地元民の網膜に独占されるが、ここいらの連中は見慣れすぎていて気にもかけない。客足が減って、冬備えの支度や、収入源の確保などの方が気になって仕方がないのだろう。だから、この色彩はほぼ俺だけが、唯一心に留めて見ていたのだろうと思う。雪が降り、積り、12月半ばにスキー場がオープンすればまた人々はやってくる。それまでは「耐久月間」と呼び、住民は節約に務めるのである。そんな季節だからクルマで一時間ほど山道を下った街場への買い出しも回数が間引かれて、せいぜい週イチ程度になる。親の財布も締め付けが厳しくなり、羽振りのいい季節と違って、おねだりをしても無駄足で終わるし、そもそも同行を許されない。月イチのマンガ誌ぐらいは許されたが、それでも兄弟で1誌であり、日々奪い合いが繰り返される始末。それでも3日もすれば読み終えて飽きるばかりであるから、残りの27日間はヒマで仕方がない。昭和後期の子供の娯楽といえば、まずテレビなのだろうが、山奥に建てられた実家の宿屋は、アンテナを屋根まで目一杯上げてもうまくテレビ波を受信できなかった。まさしく、リアル『北の国から』である。テレビないから見てないけど。うちの父親は黒板氏よりは商才はあったのであそこまで淋しげな暮らしはせずに済んだが、いつでもテレビが見られて、近所に駄菓子屋があって、友達とメンコで遊べた東京に住む従兄とはまったく環境が異なっていた。俺はテレビは見られず、駄菓子屋などもなく、遊び相手も近所にはいなかったのだ。そんなメディア暗黒時代の俺の唯一の娯楽は通っている小学校の〈図書館の本〉だった。家から学校までは徒歩で1時間。正味1時間。距離にして4キロメートル。速く歩いてもゆっくり歩いても1時間だ。山道というものはそういうものだ。山中の集落は、小学校のある辺りが一番標高が低く、スキー場のある少しにぎやかな地区が最も標高が高い。だいたい縦長6キロぐらいのエリアにだいたい1,000人が暮らしている。学校から最も遠い、スキー場付近の住民の子は、バス通学が認められていたが、そこからひとつ坂を下った地区から下側は徒歩通学のエリアである。つまり俺んちである。なんのことはない、全校生徒の中で一番長い距離を歩かされているのは俺たち兄弟なのである。やってられるか。山の中の知らん奴らが勝手に決めた合理性のないルールの中で無駄に8年も歩かされた結果、俺の身体は途轍もなく頑健に育ち、20代30代の出版人の激務も余裕でこなせてしまったではないか。閑話休題。とにかくそのクソ遠い学校に毎日飽きもせず通ったのは、唯一の娯楽である図書館の蔵書が目当てだった言っても過言ではない。毎日2冊ぐらい借りて帰る。確か同時に2冊が限度だったはずだ。それが貸し出し限度でなければもっと借りていたはずだし(いくらランドセルが重くなろうとも)、1冊だけだったら毎晩ヒマを持て余していただろう。俺の読書カードは他の児童の何倍にも束ねられていたが、とくにやっかまれたりからかわれたりはしなかった。みなテレビのない俺の家庭環境に同情的であったからだ。とはいえ、山間部の僻地校であるがゆえに、都会の大きな学校の図書館とは根本的に規模が違う。その頃は団塊ジュニア時代で児童数がだいぶ多かった時期であるが、それでもピークで6学年合わせて100人いない。確か85人程度だったと思う。俺の学年(我が校では〈クラス〉なんて言わないんだ)は15人。男子9人、女子6人。中学も同じ場所にあるから、クラスメイトは9年間同じ顔ぶれである(俺は2年生からなので8年)。卒業まで色恋沙汰など無縁であった。それは別にいい。そうそう、図書館の話だ。あったのは一般の教室と大差ない寸法の図書館。図書館というよりは図書室か。狭い図書館であるから、禁帯出のもの以外は全部借りていたと思う。とくに繰り返し借りたのは、〈シートン〉と〈ファーブル〉と〈少年少女世界推理文学全集〉だったかな。あと〈少年少女世界SF文学全集〉もあったと思う。そう、ポー。ずっと〈ポオ〉だと思っていたのに正しくは「エドガー・アラン・ポー」だったんだよな。ちなみに江戸川乱歩はあまり俺の当時のラインナップに入っていない。国内のミステリはあんまりなかったんだよ、この図書館には。別棟の中学校の方の図書館にはあったと思うが、それが読めるのはもっと後の時代である。ポオは、『黄金虫』、『モルグ街の殺人』、『黒猫』はタイトルだけで内容も思い出せる。タイトルだけでピンと来ないものでもちょっと読めばストーリーは思い出せると思う。あと邦題が変わってるからすぐわからなかったりする。コナン・ドイル、ルブランは誰でもわかる、チェスタートンは〈ブラウン神父〉、ディクスン・カーは『魔女の隠れ家』か。アガサ・クリスティはもっと後になってもっと読んだな。スパイの秘密のモームはサマセット・モームだったのか。チャンドラーも『暗黒街捜査官』で読んでいたらしい。ガキだったんであんまり作者がどうとか考えてなかったんだな。作品のトリックや登場人物は覚えていても、著者のことはちゃんと覚えちゃいなかったようだ。『マルタの鷹』は知ってても作者がハメットだとはすぐに出てこない。ダシール・ハメット。そんな名前だったのか。そして『自殺クラブ』はスチーブンソン。『ジキル博士とハイド氏』は読んだはずだが、いろんなもので上書きされているので、当時の印象が思い出せない。そしてSF。〈少年少女世界SF文学全集〉もあったはずだ。装丁に見覚えがある。見覚えがあるとしたら、やはりどうしたってあの図書館で読んだのだとしか思えない。アシモフ、ハリスン、バーンズ、ムーア、ウェルズ、そしてハインライン。ああ、やはり読んでいた。ハミルトンもカミングスもあったじゃないか。ここにあったのか。ドイルの『ロスト・ワールド』などは邦題がいくつもあってもうほんとによくわからないのだが、筋立てはみな同じなので、ドイルが恐竜の話を始めたら全部『失われた世界』のことでいい。『シートン動物記』も繰り返し読んだ。世界推理や世界SFよりも読んでいる、なぜか。実は推理やSFは人気があったので、だいたいほかの児童に借りられていたのだ。読書量はずば抜けて多いとはいえ、他の子だって常に1冊は借りている。人気のシリーズはなかなか戻ってこないである。しかし、シートンとファーブルは他の子たちにはそんなに人気がないので、いつでも借りられるのであった。そしてシートンでとにかく多く読んだのは『オオカミ王ロボ』だった。『ファーブル昆虫記』なら〈フンコロガシ〉。フンコロガシといえばファーブルであるよ。それで、ポオの『黄金虫』につながってまた〈世界推理全集〉に戻り、ドイルつながりでSF全集に戻り、続きが読めないのでシートンに、あるいはファーブルというルーチンがあった。そして、これらは毎日2冊借りるうちの片方のルーチンだ。いわば、何度読んでも面白いラインナップを保険として借りておき、メインディッシュはもう片方の未知の本たちだったわけだ。塾も習い事もない山中の暮らしである。下校して1時間歩いて帰宅したら、寝るまで本当にヒマを持て余す。テレビがないのはもちろん、ファミコンも発明前、ゲーム&ウォッチができたかどうか、という頃だ。家にはまだない。宿題などはヒマつぶしにもならないし、だいたい放課後に学校で済ませたように思う(前日のを忘れて居残りのクラスメイトに付き合って一緒にその日の宿題をやっていたと思う。クラスメイトはその日のまではやらないので、また翌日居残りになる)時間が余ればもちろん図書館の本を読む。下校までに読み切れば、帰る前に新しい本に取り替えることもできた。それはラッキーなことだ。とはいえ、日没も早い。小学生のうちはそんなに遅くまでは学校に留まれないから、ほどほどで追い出される。バス通りとはいえ、人気もなく商店もない山道を1時間あるく。明るければ本を読みながら帰ることもあるが、11月はそうもいかない。標高3000メートルの霊峰乗鞍岳を逆光に眺めながら、正面から吹き下ろす寒風に向かってひたすら暗がりを1時間歩く。毎日歩く。11月下旬ともなれば、雪も降る。山は白くなる。日本アルプスと呼ばれるほどの山岳であり、国立公園内でもあるから、それはもうとても寒い。通りすがりの自家用車に、親がいれば運がいい。バス通りをずっと上がってからクルマの道を帰るとかなり遠回りになるので、途中で山道をショートカットする。が、この決断が難しい。遠回りではたっぷり30分。ショートカットなら10分か15分で森の中を上がれるが、そこはほとんど獣道であり、本当にクマがいる(この辺の小学生は熊よけの鈴をランドセルにつけている。俺はカウベルみたいなデカイのを吊るしていた)。そして、山道をチョイスしたらもう絶対に、通りがかりの家族や隣人にクルマに乗せてもらうことができなくなる。通学路として使うことは禁止されていたが、知ったことか。そういえば小賢しい後輩がゴチャゴチャ言ってきたことがあったが、今だったら殴っている。日没とともに雪が舞いはじめて寒かったし、早く帰りたかったのでランドセルから懐中電灯を取り出して点けた。光線に雪が反応して、それはライトセーバーになる。ジェダイならクマも暗闇も怖くない。これはビールサーベルかも知れない。ぼくはモビルスーツだから寒くない。アムロじゃないけど行きます。そういえばガンダムもテレビで見てなくて、朝日ソノラマのノベライズ版を読んでいたのだった。口絵のアニメ画像を元に脳内で映像を構築して楽しんでいたせいで、今本物のガンダム(TVシリーズや劇場版三部作)を見ると、記憶とだいぶ異なる。山の斜面には巨岩があり、祠もある。素通りすると祟られそうなので、パンパンと拍手して拝んでから通るようにしていた。山を上がると家のすぐ裏に出るので、走っていく。草はもう枯れているからライトセーバーを振り回しながら草原を突っ切って、全速力で森の暗闇に明るく輝く玄関に飛び込む。うちはペンションなので、おふくろの飯はプロ級であり、めちゃくちゃ美味いわけで、空気は薄いが、豊かな生活だったと思う。今は誰もいない建物だけがそこにある。END
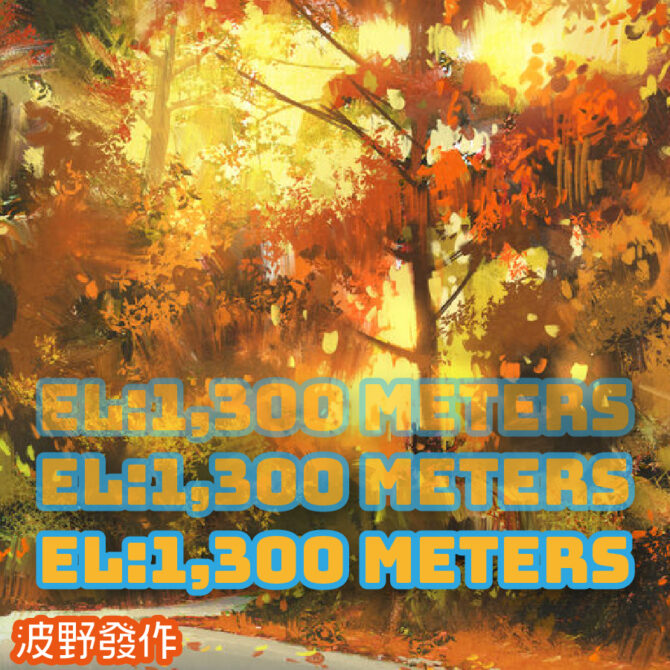






















Juan.B 編集者 | 2020-11-17 04:23
多分俺は波野氏ほど切迫してないにせよ、図書室への愛着はあったので楽しく読んだ。空気の旨そうな作品だ。
俺は意味もなく昔の少年年鑑とかを見まくって、終いには同時代の愛・地球博よりも筑波万博の方が面白いように思えてた。それにしても風俗の匂いがしないのは久しぶりだなァー
鈴木 沢雉 投稿者 | 2020-11-17 15:42
小学校の図書室といえば、自分は物語にまったく興味がなかったせいか、他の子たちが推理小説やシートンをこぞって読んでいるのを横目に、図鑑ばっかり読んでいた。お気に入りは「ダム」でした。
小林TKG 投稿者 | 2020-11-19 08:48
いいなあこういうの。こういう文体っていうんですかね?構うこたあねえ。みたいな感じ。いいなあ。構うこたあねえ。俺は俺のやりたいようにやらせてもらうぜ。みたいなやつ。いいなああ。あこがれるなあ。
松尾模糊 編集者 | 2020-11-20 23:36
前半の景色描写が好きでした。波野氏の読書遍歴が知れて良かったです。ガンダムの入りがノベライズとは、かなりの筋入り感があります。ないものねだりで申し訳ないのですが、できれば図書室の描写や兄や家族との会話、同級生との掛け合いなどがあると嬉しかったです。
Fujiki 投稿者 | 2020-11-20 23:42
読み手に息継ぎをする間を与えない段落ひとつのみからなる文章によって山地の空気の薄さを体感させる魂胆だろう。この作者は策士だからそれくらいのことは企んでいそう。それにしても、こんな無邪気な子どもが将来、性風俗のエキスパートになるなんていったい誰が想像しえただろうか? 無垢の喪失は今回のお題にぴったりのテーマだ。
諏訪真 投稿者 | 2020-11-21 02:50
読んでいて羨望混じりの幸福さを感じました。(実際の不便さを覆せるかどうかはどうあれ
大猫 投稿者 | 2020-11-21 16:40
なんて幸せな幼年、少年時代!
四キロの山道を毎日歩いて四季の美しさを満喫しつつ体は丈夫に、図書室で好きな本を借りてきては貪り読み、家にはお母さんのプロのお料理。テレビとかインターネットとかの余計なものは一切なし。
ポーの作品は子供時代に読みましたが、薄気味悪さだけが先行しました。『アッシャー家の崩壊』や『黒猫』の本当の恐ろしさが分かったのは大人になってからでした。
それにしてもド田舎の少年少女にまで世界の名作を届けた図書館図書室とは有り難いものです。
退会したユーザー ゲスト | 2020-11-21 18:16
退会したユーザーのコメントは表示されません。
※管理者と投稿者には表示されます。
古戯都十全 投稿者 | 2020-11-21 22:46
行間から、家から学校まで歩く時の息づかいが伝わってくる気がします。
少し時代は下りますが、私の通っていた小学校にも有名作家の子供向けの翻訳はまだあり、ドイルのホームズものの『ブルースパティントン設計書』が、『鍵と地下鉄』というネタバレ寸前の驚きの題名で置かれていました。
松下能太郎 投稿者 | 2020-11-22 00:17
郷愁となると、大人の自分が少年時代の自分を俯瞰するように見るという構図になりがちですが、この話は大人の自分が少年時代の自分のすぐ隣にいて、一緒に歩きながら語っているような印象を受けました。「今は誰もいない建物だけがそこにある」という締め方は「ノスタルジア」というお題に対してまさにドンピシャな言葉だと思いました。
曾根崎十三 投稿者 | 2020-11-22 11:03
波野さんの他の作品でもあるような「地元民の網膜に独占」とか「アムロじゃないけど行きます」とか面白味のある上手ないい回しが良かったです。好きです。
小説を書いている人の多くがノスタルジアを感じるであろう体験談に、私もまたまんまとノスタルジアを感じさせられました。
一希 零 投稿者 | 2020-11-22 11:56
かっこいい文体もあり、とても素敵なシーンが想像されました。冒頭の描写が本当に美しかったです。そこから段落がかわることなく「今は誰もいない建物がそこにある」までいくところに、濃密で詳細な過去の思い出が、それでも今から見れば遠い一瞬の、 記憶に過ぎないのだ、と言っているようでした。