流れ流れて、流れに流れ江戸川区。小岩。
二十代後半の拙いハナシである。
私は往時、台東区台東三丁目のカオスなアパートに住んでいて僕も含めて所謂、素敵な馬鹿野郎共と毎晩、カクテルパーティーを行っていた。四階。酔ってはジャンケンに負けた奴が窓の外。ベランダの手すりに捕まり「おいごと、やれ!」なる危険な遊びをしていた。近隣としては大迷惑である。
そんな折、僕は何故か女性に好かれる傾向が有り、無論、俗的に云わば「人生で最大級である糞な駄目人間はほっとけない」なる所謂、母性本能でしかないのだろうが二歳上の、上野のハードロックカフェで携帯番号を交換していた淑女から「小岩に一人暮らしなのだが、ウチ来る?」と誘われた。丁度、金銭的に困窮していた故「いくいく〜」と述べた。サヨウナラ、素敵な仲間たちよ。まあ、リアルタイム、ほぼ鬼籍に入っているが。
小岩は退廃的な街で、ドチンピラもどきが多かった。御徒町に住んでいる田舎者が醸し出すエレジーが皆無であった。千葉県の稲毛にある材木商社に通う、その女性を早朝、見送ってから僕は小岩と云う街に耽溺した。ピンサロとした単語を理解した。ええ、通いました……。
坂口安吾の短編に「小岩パレス」なるモノがある。昭和二十年代後期。その頃は原っぱしかない小岩に欧米風な社交クラブ的ノリだが結句は赤線が出来て筆者が通って羽目を外していたハナシだ。皆さんもそうであろうが「破滅派」に興味を抱いた人にとって「坂口安吾」は必須。僕も往時、その女性から金銭を強請っては全集をコンプリートしていた。或る日、その女性の部屋から徒歩五分のトコロにスーパーが有ってアルコールと刺身を購入しに訪れた時。
そのスーパーの真向かいには小さな公園があった。上は総武線の高架線が常にカンカンと鳴る落ち着かないチンケな公園だ。二年くらい滞在させて貰った小岩だが「酒の呑み過ぎだ。出ていけヒッピー」と至極、当然の結末で、その女性から詰められていた僕は、その公園でビアを空けた。そうしたら八十歳くらいの頬にキズだらけの老人が現れた。「こんにちは」と述べられたら僕も台詞を返すしかない。
やがて、その爺ィもスーパーでアルコールを買ってきて四方山話をしていたが或る呼吸で文學の話題になった。爺ィは図らずも詳しかった。僕は、西村賢太は大嫌いだし模倣もしていなく往時は「誰それ?」であったが「江戸川区出身で同人誌に近い内、掲載されるだろうヤバいモノホンが居るよ」とレクチャーされた追悼がある。
他に稲垣足穂とか北條民雄、何故だが未だに判らないが千昌夫の話題で盛り上がった。やがて、女性が間もなく帰宅する午後六時の「足立区チャイム」が鳴り響いた故「すみません、僕ヒモなので夕食を作りに帰宅します!」と朗らかにサムズアップしたが爺ィは粘る。「最近、誰を一等、拝読しているか?」になり前記したように「今は坂口安吾です」と返したら「小岩パレスって短編、判る?」「無論」「そこが有ったの、この公園だよ」「え!?」になり糞みたいな自称ヒッピーの餓鬼と爺ィの文學愛好者は意気投合してしまい、互いに金銭もないのに「居酒屋、居酒屋! 語りつくそう」になり挙げ句、その女性が深夜、泥酔した僕を迎えに来て三日後に「駄目だ、駄目だで助けてあげたけど最早、私のキャパを越えた」で小岩から追放された訳である。
なお、その爺ィとは、それ以来、会ってはいないが調べたら諸君も判るが「その公園が小岩パレス跡地だった」なるのは、まごうことなき真実である。
最早、二十年以上昔のハナシだからあの爺ィは他界しているだろう。僕も毎日「今が人生の最底辺」なる日々のページを捲っている。
日本特有の所謂「私文學」に嵌まる人の未来はないが、僕なんて全く力量が無いが、少し生かされて、その下らない碑の片隅には居たい所存。













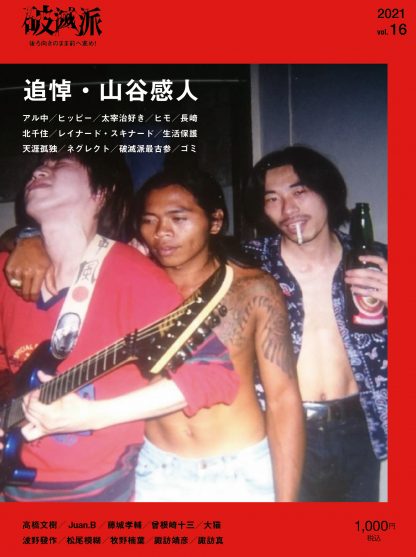













"小岩時代"へのコメント 0件