ぼくの掌のなかではスピナーがうずをつくっている。しゅるると音をたて、気流と地場の弱い力のうずが生まれる。エネルギー保存の法則はぼくのスピナーから回転力を奪っていく。奪われたエネルギーはどこかぼくの知らない次元に吸い込まれ、誰かのところへ流れ込む。それはたとえばあそこにいるあの子の、あの子が抱えている、それは大切そうに抱えている瓶(たとえばはちみつが入っているような大きめの広口瓶)の中につながっているかもしれない。かもしれないが、見えないエネルギーに色はなく、ぼくの目にも誰の目にもそれは見えない。見えない奔流は、絶えずぼくの掌から流れ出し、どこか遠くの次元を経由して、あの子の懐の瓶のなかのあいつに届いている。あいつ。あのうずしおに。ぼくのスピナーのエネルギーは、流れ込んでいるのだ。
あの子は、白い服に太陽光を反射させながら、とおくトラス構造の白い橋の下でたゆたう海面を眺めているようにぼくには見える。太陽から発せられた電磁波(光線を含む)は濁った大気を透き抜け、うずしおのない穏やかな海面で跳ねてぼくらに降り注ぐ。そのうちのいくつかはあの子の眼球に吸い込まれ、またいくつかはあの子のまとうレイヨンの表面を滑って地面にあたり、跳ね上がってぼくに届く。ぼくの瞳孔に飛び込んだあの子の体温は、視神経のシナプスをリレーしてぼくの脳裏に焼き付いていた。刹那、ぼくとあの子の間ではこのようにエネルギーの交換が絶え間なく行われていたわけで、すでにぼくたちに接点は存在した。だから、ぼくはぼくがあの子に話し掛けても赦されると判断した。その判断は正しかったが、それはぼくとあの子にとってだけであり、それ以外の世界はそれを赦さないかもしれないが、それは今考えることではなかった。とにかくぼくはあの子に話しかけなければならなかった。その機会を逃す前に、ぼくはその機会をものにする必要があった。
近づく前に声をかけるか、声をかけてから近づくか迷ったが、結局ぼくは近づきながら声をかけることに決めた。
「それ、どっち?」
少女は、振り返って警戒の色を顕にしたが、ぼくの興味が彼女自身ではなく、その手にある広口瓶、ひいてはその中で回っている(回転エネルギーを与えているのはぼく)ものにあることを悟り、表情をゆるめた。
「うーちゃんはおとこのこ」
彼女は瓶の中を覗き込みながら、愛おしそうに目を細めた。その表情はけしてぼくに向けられたものではなかったが、それはかまわない。広口瓶の中に、絶滅したはずのうずしおが回っていること、それこそがいまのぼくらにとって最も重要なファクターなのだ。
「うちに」
ぼくは勇気を振り絞って、本題に触れた。これは法に触れる行為だ。しかしぼく個人の小さな人生と、種の存続を天秤にかけるわけにはいかない。これは絶対の正義であり正当な理由なのだから、ぼくは実行しなければならない。言葉をつまらせたぼくを少女は不思議そうに眺めている。ことばを紡がなければいけない。
「うちにはおんなのうずしおがいるんだ」
「え、ほんと?」
やっとの思いで伝えることができた。それがすべてのはじまりだった。
ぼくたちは共犯者だ。世界にバレてはいけないことをしている。ほろんだ生き物をつがいにして、種を存続させようとしている。うずしおがレッドデータブックに載ってから十年が過ぎた。県の教科書には、かつてうずしおは自然現象だと思われていたところが、ノザキ博士の発見でそれはエネルギー生命体であり、広義の生物であることが認められ、乱獲されたと書かれていた。かつてこの島には世界的な洗濯機メーカーがあり、洗濯機メーカーは組織的に漁をおこなって鳴門のうずしおを根こそぎ獲り尽くし、ついには絶滅させてしまった。ぼくの父は自然保護団体の依頼でうずしおの調査を行っていたが、ある日の海難事故で還らぬ人となった。母は洗濯機メーカーの工員としてぼくを育てたが、やがて三半規管を壊して他界した。工員の多くはうずしお加工の工程で母と同じように三半規管を壊して亡くなっているが、洗濯機メーカーは因果関係が不明であるとして今でも労災の適用を拒否している。ここまでは地域の授業でこの辺の子どもなら誰でも習う。シホも知っているだろう。むかしこの海にはうずしおがたくさんいたのだ。今の洗濯機には養殖のうずしおが使われている。養殖のうずしおは天然物にくらべてどうしても性能は落ちる。工員が三半規管を壊すのも、養殖のうずしおが原因だ。養殖するには、工員がぐるぐるとかき回してやらなければならないからだ。そうやって工員が向上でぐるぐる回した養殖のうずしおは、洗濯機に収められて出荷される。耐用年数も短いし、洗濯性能も高くない。かつて世界一とまで言われた鳴門の洗濯機も、いまでは海外メーカーに追い落とされて見る影もなかった。父の警告を無視して乱獲三昧を続けた洗濯機メーカーは自分で自分の頸を締めたのだ。先日ついに工場の停止が発表された。洗濯機メーカーはこの地域から撤退するという。一定期間洗濯機の生産に全力を注いだこの地域にはもう産業基盤はなかった。みなが狂乱して洗濯機生産に夢中になっていた。気がつけば、養殖うずしおで目が回るが、借金で頸は回らないという残念なことになっていた。だから、もしぼくらが絶滅したはずの天然物のうずしおのつがいを持っていることを知られたら、大変なことになる。それはぼくが未成年幼女誘拐(わいせつ目的)で逮捕起訴されるより重篤な事態だ。地元の洗濯機メーカーは、天然うずしおの奪取に躍起になるだろうし、大陸の新興洗濯機メーカーの工作員はぼくらのうずしおたちを亡き者にしようと加油。ハッスル間違いなし。その騒動のなかでぼくは陰謀に巻き込まれて命を落とすに違いない。それは父のようであり、新たな工場に収容されて強制的に果てしないうずしおの調教に従事させられるかもしれない。それは母のようであり、いずれにしてもぼくはろくな死に方ができない。家についた。ぼくは先にあばら家の引き戸を全開に、誰でもかれでも間違って侵入できるように仕立て、きしむ階段を上がって二階の研究室(父が遺した)の暗幕を開いた。夏の光線が部屋に満ちた。
丸い水槽の中で、ぼくのうずしおが、くるくると回り始める。今日もゴキゲンのようだ。もっと機嫌をよくしてやろう。ぼくは傍らの壺から塩をつまむと、水槽の中心にファサーと振りかけた。うずしおは水滴を飛ばしながら回転を速める。ついにはフチから水が溢れ出し、研究室の床を湿らせた。もう限界が近い。
階下から、遠慮がちに音が上がってきた。そうして白い影がそっと黒い部屋をのぞきこむ。
「いらっしゃい」
ぼくが声をかけると、シホはこくりと会釈をして、すっと部屋に入ってきた。この模様は防犯カメラで録画しているので、ぼくの無実の証明に加担してくれるだろう。けっしてやましい気持ちでこの少女をここにまねきいれたわけではないのだ。ぼくがそっと彼女の傍らのテーブルを指すと、すぐに意味を悟り広口瓶をそこに置いた。シホの手を離れても、うーちゃんが瓶の中を回っているのがわかる。天然うずしおはその回転力が違う。回転への情熱が全く異なる。養殖うずしおはどうしても回されているという感覚が抜けきれず、回転力に劣るのだ。
シホは、ぼくのうずしおをじっと眺めていた。
「こんなに大きなのはじめて」
「もっと大きくなるよ」
かつて鳴門の海には二〇メートルとも三〇メートルともいわれるヌシのようなうずしおがたくさんいたという。
「お兄さんはどうしたいの?」
「ぼくのことより、きみだ」
ぼくの答えは決まっている。もうここにはうずしおを置いてやれない。
少女は少し黙っていたが、うすうすわかっていたのだろう。いつまでも少女ではいられないし、うーちゃんも瓶の中にはいられない。
「……海に還したい」
小さな声は確かに聞こえた。それはぼくの決意を後押ししてくれる声だった。
「わかった。今夜放す」
シホはだまってうなずくと、広口瓶をもう一度ギュッと抱きしめて、振り返らずに立ち去った。階段のきしむ音がゆっくりと続き、そして聞こえなくなった。ぼくはかつてぼくのうずしおが漬かっていた小水槽にうーちゃんを開け放すと、そこに塩をひとつまみ振りかけた。新人のオスのうずしおは元気に回りはじめ、水滴を撒き散らせた。ぼくの部屋は少しだけ涼しくなった。
スーパームーンが天空に輝く。潮位が最大になる。放流にはもってこいだ。やはりこの子達を放つには今夜しかない。ぼくは軽トラの荷台にローリータンクを固定し、ぼくのうずしおを二階の水槽からサイフォンで流し込んだ。少し狭いががまんしてくれ。うーちゃんはもう広口瓶には入らなくなっていたので、携帯用ポリタンクにうつして、同じように荷台に載せた。エンジンをかけてヘッドライトを点けると、正面に白い人影があった。思わず声を出してしまったが、手を振って駆け寄ってくると、それがシホだとすぐにわかった。
「こんな遅くに駄目じゃないか」
「そんなこと言う人、うちにはいないんだ」
事情はなんとなくわかるが、そういうわけにもいかない。送るから帰るように諭すと、
「わたしもお別れしたい」
と、同行を押し切られてしまった。とりあえずぼくは一部始終をすべて録音録画して身の潔白を証明できるように準備してから、シホを助手席に乗せて軽トラを走らせた。
「ねえねえ、うーちゃんのお嫁さんはなんて名前なの?」
「え、ああ、いや。名前はつけていないんだ」
「そうなの?」
「野生に返すって決めていたから」
「……そうなんだ」
シホが少し悲しそうな顔をするのが切なくなった。
「あ、ごめん、別に名前つけたっていいんだよ。ぼくはそうしたっていうだけ」
「そっか。わたしがつけてもいい?」
「つけてくれるの?」
「うん」
じゃあよろしく、と依頼してぼくは月明かりに照らされた橋へ軽トラを向かわせた。入り江の橋には先にクルマが停まっていた。地元のカップルだろうか。月が綺麗だから、月が綺麗ですねなんて言い合っているのかもしれない。ぼくは橋のたもとに軽トラを停めて、ヘッドライトを消した。狭いキャビンが月光に照らされておどろくほど明るかった。
「あ、そうだ」シホが小声で話しかけてきた。薄明かりの中では無邪気さとあどけなさは影を潜め、透き通る肌に整った鼻筋が際立って昼間見たより格段に美しかった。
「ん?」
「名前、みづきはどうかな」
「みずき、いいね。かわいい名前だね」
「海に写っている月が綺麗だから。海月(みづき)」
シホ、それはと言いかけて、先客がクルマを移動させるのが見えた。
「おっと、今のうちに行こう」
ぼくはエンジンを始動して、そっと軽トラを出した。クリーピングでじりじりと橋の中央付近まで移動すると、サイドブレーキをかけて、クルマを降りた。シホの方は欄干があって降りられないので、ぼくの側から降りてもらった。やわからく湿ったその手はやはりまだ子どものものであり、触れたことに罪悪感を覚えたが、それは劣情などではなく、清らかなるものへの畏怖である。
誰かに見咎められる前に、いそいで別れなければならないのは辛かったが、それでもやはりうずしおたちの旅立ちにシホを同席させたのは正しかったと思う。ぼくは太いホースをローリータンクに差し込み、水を吸い出して名付けられたばかりの海月をスタンバイさせた。潮の香りがわかるのか、少しはしゃいでいるようにも思える。シホはフタを開けたポリタンクをどうにか持ち上げて、欄干にひっかけた。
「準備はいいけど、どうする?」
「うん、大丈夫。わたしは平気」
「じゃあ、せーの」
せーの、でぼくたちは二匹のうずしおを、海に還した。数秒でポチャポチャと音が聞こえた。のぞきこんでみたけれど、橋の真下は暗くて何も見えなかった。
「うーちゃん、みずき、元気でねー」
シホは抑えた声で下に呼びかけた。音は届かないが、きっと聞こえるだろう。
ヘッドライトがこちらに向かっているのが見えた。やばい、つかまると面倒い。逃げなきゃとシホが言い、ぼくらは軽トラに飛び乗って、いそいで投棄現場を立ち去った。今夜は真夜中なのにずいぶん多くのクルマが橋に向かっているようだ。途中何台もすれ違った。よほど今夜の月は綺麗なのだろう。
ぼくは掌のスピナーを回しながら、遠く光る海峡の海面を眺めていた。この回転はあのうずしおたちの回転とエネルギーでつながっている。それは因果だ。あの夜、推定で一〇〇組以上のうずしおのつがいが、この近海で放流され、あっというまに野生のうずしおは生息数を増やすこととなった。洗濯機は回転式から超音波式にとって替わられ、かつてのような乱獲もなく、うーちゃんとみずきとその子孫たちは平穏無事に暮らしている。ぼくらも平穏無事に暮らしている。
「ねーねーパパ」
「どした?」
「海の月って書いてなんて読むか知ってる?」
「……ママに聞いてみな」
「わかったー」
あの日のシホそっくりに育ったミズキは母親のところへ走っていった。娘に話しかけられて、何度かうなずいていた妻は、キッとこっちを睨みつけた。掌のスピナーが激しく回り始めた。おっと怒りのエネルギーが渦になって流れ込んできたようだ。逃げるとしよう。
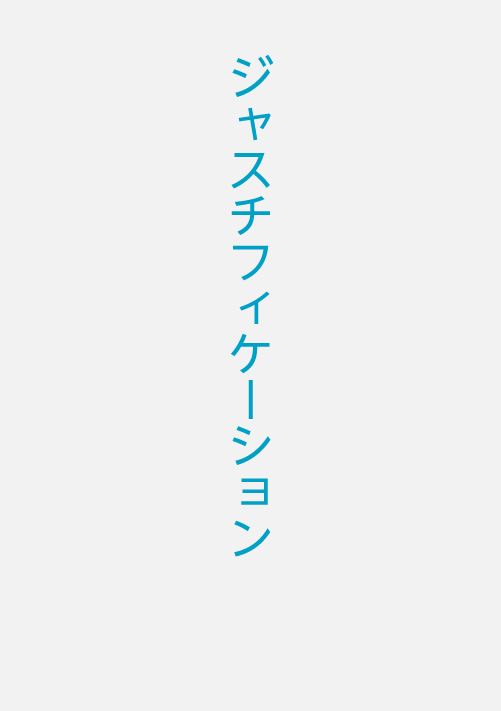


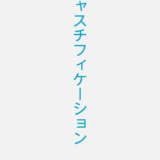




















"ジャスチフィケーション"へのコメント 0件