僕たちが住む町に外出制限が出されてから五日が経った。妻がいらだっているのがわかる。
六日目。健康のために、政府からは一日三十分程度の日光浴が推奨されている。ベランダのない我が家では、日光浴をするために一人ずつ窓枠に腰かけなくてはならない。妻は日光浴の間じゅう、スマートフォンをいじっている。ときどき通りを見下ろしては憂鬱そうに眉間にしわを寄せている。
七日目。買い物から帰ると妻が僕の古い洋服を切っていた。それどうするのと訊いたら、刺繍をするの、と鋏を動かしながら言った。この服もう着ないでしょ、はじめはそのまま刺繍をしようと思ったんだけど、大きすぎて針を動かすのに邪魔だから、切ってまずは練習台にすることにしたの。そう、と僕は言いながら、何枚かの気に入っている洋服をクローゼットからこっそり抜いた。
十日目。相変わらず自宅で過ごしている。生活必需品の買い物と犬の散歩以外は全面的に禁止されていて、しかも買い物や散歩は複数名で行ってはいけないことになっている。窓から見下ろしても通りにはひと気がない。たまに歩いている人がいても、二人以上いる場合にはきっちり間隔をあけている。向かいのアパートの窓から猫が顔を出している。猫は毎日この時間になると通りをのぞきこんでいる。彼女(あるいは彼)のその日課が、外出禁止令が出る以前からのものなのか、それとも以後の習慣なのかはわからない。彼女(あるいは彼)はいつも僕のほうはちらとも見ずに、うつろな目で誰もいない石畳を見つめている。
何て名前だろうね、僕はソファの妻に向かって言ってみる。あの猫、向かいの窓にいつもいる。妻は手元から目を上げず、かわいそうにね、と言う。うつ病なのよ、あの猫。切り刻まれた僕のシャツには、赤や青や黄色の糸で、さまざまな花が刺されている。
十四日目。妻の刺繍作品はソファ横のローテーブルから溢れ、今や床にまで散乱している。ガーベラ、カーネーション、ユリ、バラ、カスミソウ、デルフィニウム、ゼラニウム、マム、リシアンサス、アルストロメリア……。
妻の仕事は花屋だった。こんな状況だから、今は当然休業している。政府が一定額の補償をしてくれるらしいから、生活面での心配はとりあえず今のところはないのだけれど、根が怠惰にできている僕と違って、妻は仕事がとにかく好きなタイプの人間だった。こんな状況になるまでは、毎日朝の四時には起きて店の車を走らせて、市場から届いたばかりの花を町のあちこちへ配達していた。さまざまな花が町じゅうのレストランのテーブルや、店先や、窓辺に飾られた。それが終わると店にかえって、注文を受けた花束を次から次へと手際よく作った。花束はどれも客の好みや要望にあわせ、色を選び大きさをあわせ花言葉の意味まで考慮されたすばらしい出来のものだった。妻の作りだす花束は、いつでもこの町の誰かの特別な日や、特別ではない日々を彩るために必要なものだった。つい一ヶ月前までは。
僕は妻のために、NETFLIXで見ることのできる映画やドラマの情報や、部屋の中でできる簡単な体操のやり方なんかを検索しては、妻にどうかなと提案した。最初のうちは、おもしろそう、いいわね、ありがとう、やってみる、と言っていた妻だったけれど、だんだん生返事ばかりになって、やがて僕のネタも尽きた。そのうえ、状況は悪くなる一方だった。報道される言葉や数字によって喚起されるかなしみややるせなさが、日ごと僕らの心の奥底に積もっていった。医者でも政治家でもない僕らにできることは何もなかった。ただ家に閉じこもり、明日が今日よりすこしでも良くなりますようにと祈ることしかできなかった。ほんの数週間前までの世界とは、もう何もかもが変わってしまったのだと否が応でも思い知らされた。僕だってもちろんわかっていたのだ。妻がいらだっている理由は、この七十平米のアパートメントの一室に閉じ込められていることではない。
FaceTimeの画面越しに、同じく自由のない友人や両親と会話をしながら、どうかなりそうよ、と冗談めかして妻はよく言っていた。そんな妻を横目で見ながら僕は、ほんとうに妻がどうかなってしまうんじゃないかと気が気じゃなかった。テレビのニュースの音を聞きながら、刺繍針を動かす手を止めずに妻はしばしば涙を落とした。嗚咽も声も漏らさずに、まるで九月の雨みたいにぽつぽつ涙をこぼすのだった。僕はそのつどソファへ行って、妻の肩を抱いたけど、妻は何にも言わなかった。表情一つ変えなかった。刺繍枠の中、かつては僕のシャツだった、今はただの正方形の布地の上で、ユリの花弁が妻の涙を吸い込んだ。
二十日目。近所に住むミチが、ワンチャンをつれて僕らの家を訪ねてきた。
「ひさしぶり」玄関先でマスクをしたままミチは言った。僕は除菌用のアルコールスプレーを渡しながら、「ひさしぶりだね」と言った。妻が奥から出てきて、ハグをするようなジェスチャーをする。「会えてうれしい」。ミチもそれに倣って、「私もよ」と同じ動作をしてみせる。その間じゅう、ワンチャンは大人しくミチの足元でお座りをして、潤んだ黒目でこちらを見上げている。吐息は荒く、抑えきれない興奮や期待に尻尾をばたつかせている。
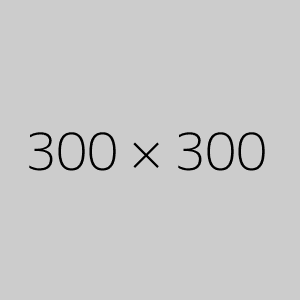





















"花を刺す"へのコメント 0件