四等客室は紅葉柄の壁紙で覆われていた。
数少ない丸窓はそれぞれカーテンで隠されていた。照明は天井からぶら下がるたった三つの蛍光灯のみであったが、それも朝の時刻に合わせて消されていた。陽の光は外の波に反射しているのか、カーテンのひだに屈折されているのか、ぼんやりとした影とともに窓際に投げ出されていた。外の様子は伺いしれないが、今日もまた海は荒れ模様だということは、船の揺れ具合と臀部にごつごつとした感じが伝わってすぐわかった。三角波は、この船底に近い四等室では波のそのひとつひとつが突っつくように伝わってくるのだった。片隅には樽が積まれていた。ワインでも入っていたのだろうが今では箍が外れたものや、転がした跡の目立つものまで様々だった。中身は当然すべてからっぽで乾いていた。海鳥の鳴く声が時々かすかに聞こえていた。
T夫人は夫の迎えに出るため、この船に乗り続けていた。T夫人の夫は正午、つまりはもう数時間もすれば、刑務所から出所するのだ。船の向かう先は独房のある小さな島であった。ただ問題なのは、この船がもう何日も出港できずにいることだった。本当の予定としては、出所の二日前くらいに島へたどり着き、そこで夫の背広など入用になるものを購入するつもりだった。島の宿の予約もとってあった。しかし連日続く大時化でその予定もとっくに宙ぶらりんになっていた。夫人の夏服はひどく汚れ始めていた。その島へは一度だけ訪れたことがあった。お金のない旅行だった。ちょっとした小旅行で、その時も船で、その時は夫は一緒じゃなかった。夫人は壁際に凭れて蹲っていた。四等室には彼女のほかには少年が一人いるだけだった。その少年は、頭から足先まで全身を毛布にくるみ反対側の壁際に蹲っていた。ただ、おかしなことではあるが、彼女の側からは少年がどちらを正面にして座っているのかが判別できなかった。まるで四方背中の彫刻のようだった。灰色の毛布がまるでコンクリートのように固まっているかのようにも見えた。紅葉柄の壁の前で、少年はじっとしていて動かなかった。
ふと夫人は思った。この部屋が紅葉の模様ということは、ほかの三等室や二等室、一等室の壁紙はそれぞれ四季を表しているのかもしれない。たとえば春の花柄や、雪の結晶や、あるいは……。しかし、彼女にはその予想を確かめる術がなかった。というのも他の客室への移動は出来ないようになっていたからだ。四つの客室をつなぐ通路の分岐点、ちょうど階段の下のスペースの端には書き物机と椅子が置かれており、常に書類整理をおこなっている白いセーラーを着た船夫が座っているからだった。出港できないあいだは、乗客の見張りが彼の主な仕事なのだった。船夫は若い男だった。こちらから話しかける用事がないのと同じように彼のほうから話しかけてくることもなかった。ただ、何か書き物に没頭しているようだった。
いつまでも出港できない、せかせかとした焦る気持ちを抑えるため、夫人は四等客室の壁に掲げられた額縁の前に立ち上がり移動していた。額に収められていたのは――おそらくこの船の――断面図だった。船長室から荷物倉庫、荷物倉庫内の猛獣用の檻まですべてが露わになっているような図だった。部屋が薄暗かったので少し見づらかったが、視認するに、残念ながら先ほどの夫人の予想を示すような、壁紙の模様までは描かれてはいないようだった。夫人は少し落胆し、それと同時に、ある全く他の感情が彼女を縛りつけ始めた。恐怖という名が相応しいかどうか彼女は迷ったが、やはり恐ろしいものとして、彼女は断面図を眺めていた。
ふと彼女は気づいたのだった。断面図に描かれているものたちは、同一の時間で切り取られてはいない。すぱっと一瞬で一刀両断されているわけではなく、寄木細工のようにお互い違う時間を生きたものたちが集まったものの集合体が断面図なのだ。さらに言えばそれらは架空の想像物とはまた違った、架空を騙ったなにかのようだと思えた。(幽霊……)という言葉が脳裡を通り過ぎていった。
絵描きが断面図を描く工程において、勿論描く順番というものが存在するが、設計図や見取り図を確認する段階や、下絵書きや、その順繰り順繰りの作業の時間のあいだに、また違った様々な時間や空間が、誰にも、画家自身にも知られずに紛れ込んでいるのだ。そしてその完成形を見た時、すべての誰もが見通せていると思うのはあくまで切断されたものの内部構造であって、誰も見通せないところでは別のなにかが縦横無尽に歩き回っている。それらの嫌な笑い顔を隠すために「奴ら」はあるひとつの仮面を一緒に被っているのだ。それが断面図の持つ恐ろしい特質のような気がした。
小さな声で夫人は脳裡に浮かんだ鮮烈な感覚をおぼろげな言葉でつぶやいた。
――もしも「竜巻」の断面図というのが世の中にあるのか、わたしは知らない。けれども、そんなものが存在したらそれは最も恐ろしいものなのではないだろうか。渦が巨大であればあるほど巻き込む物も多様で多量だろうし、子供の「地下の絵」にしばしば蟻の巣や土竜が遊び半分で描き込まれるように、同じようにして絵描きも何の考えもない冗談で竜巻の断面図の中に人間を描き込んでいたら。
――渦に巻き上げられたその高低差が、時間として、画家本人にも知られぬ空間と時間が内在する絵の中、たえず生き続けていたら。時間はきっと無限に偏在し、いつどこで本来の時間軸に戻るのかは誰も知らない。竜巻は竜巻然とした時間をもってして螺旋を描く。
――そうなるとわたしが急にいま上空に巻き上げられ、高低差に気づかされることになるのか、それすらわたしにはわからない。
――あるいは、無情にも地上から遥か上空まで巻き上げられた様に描かれ、時間が動き出して、その直後に何が起きるか気づいた時のその人物と目が合ったら。それがわたしにとっては恐怖だ。わたしは彼を見つけ、彼はわたしを見つめる。彼はわたしではない。だからこそ恐ろしいのだ。わたしは目撃者だ。
わたしは今、疲れているのに違いない。そうでなければこんなことは考えないはずだ。なぜならわたしには夫を迎えに行くという、しっかりとした役目があるのだから、と夫人は思った。しかし、ある種の解放感も彼女にはあった。そしてそれに彼女自身は気づいていなかった。暴走する思考をどうにか抑え込みながらもう一度イラストを見てみると、日が昇ってきたのか船窓からの明かりが射し込んできており、先程は気づかなかった断面図の細部がしっかりと見えてきた。四等室より少し小さめの三等室には「黒い外套」を着た男が立っていた。半個室である二等室には「淡い桃色のロングドレス」を身にまとった女性がいた。そして、この船に六部屋ある一等室の一室には、「白いシャツを腕のところまでまくった」男がベッドに腰掛けているのだった。やはり、どうやらこの船の客室は四季によって色づけされているようだと、夫人は思った。そこにどんな意味があるのかわからないが、わたしのいるこのがらんとした部屋はやはりとりあえず「秋」なのだ。急になんだか自分の「夏服」がひどく場違いに思えてきた。時間の渦。四季の渦。高低差。巻き上げられ、落っこちる。暴走した感覚がふんわりと頭をよぎった。あの少年のように「毛布」にくるまるべきなのかもしれない。それがこの部屋での在るべき姿なのかもしれないと思った。
その時、船の揺れが大きくなった。夫人は足を踏ん張り、よろよろと立っていたが、堪え切れずその場にぺたんと座りこんだ。今までのなかで一際大きな揺れで、樽がひとつ、反対側の壁まで転がった。大時化。という言葉を婦人はしばらくのあいだ喉の奥で転がしていた。そうしていれば、なんだか逼迫した気持ちを忘れさせてくれるようであった。けれどもやはり間に合わせなければいけない。出迎えの者もいない白い壁の前で、直立不動で夫が一人佇んでいるのが、婦人には生々しく想像できた。焦燥感はやはり彼女のなかに、太い血管が脈打つようにあった。夫人は再び立ち上がった。太陽が真上に昇ったのか、雲間に隠れたのか、少し陽射しが翳っていた。
もう一度、断面図の額縁を見やった。先程は見逃していた、四等室の図にも人物が描き込まれているのにその時気がついた。夫人は顔を近づけてよく見た。
やけに薄い色で描かれた、毛布にくるまった人物だった。
後ろを振り返り、また絵を確認すると、絵の人物はあの少年がいる場所と同じ所に座っていたのが分かった。
もう一度絵の方をよく見た。
すると、描きこまれた人物は毛布から顔を出してこちらを向いていた。
途端、その人物と目が合った気がした。
そしてそれと同時に、少年のいるほうから背中に視線を感じた。
凍りついたように夫人は少年のほうへ振り返ることができなくなってしまった。
その時、時報の汽笛が響き渡った。
その甲高い音に、夫人はこわばった体をほどかれた。
深く息を吸い込んだ。ついに、昼になってしまった。夫人は虚脱し、そして再び、だが今度は正確にかすかな解放感を味わった。夫はどうしているだろうなどとは、些とも思わなかった。正午を報せるサイレンはいまだに続いていたが、この音が、いつまでも続けばいいと彼女は思った。彼女はまた元の場所へ座り、壁に背中を押しつけた。いつまでも秋の部屋で、正午であればいいと思った。だが、その音は先細りしていき、彼女は眩暈に襲われ、様々な遠い記憶が体の中を巡り始めた。「悪い出来事の前兆は前の晩にやってくる――」。夫がよく口にしていた言葉だ。私は思う。あの朝、食事の最中に警官が三人やってきて夫が連れて行かれた時も、その前兆というのを前の晩、夫はどこかで感じ取っていたのだろうか。わたしが埠頭で風に帽子を持っていかれたあの暖かな午後。その前の晩も、夫はなにかを感じ取っていたのだろうか。わたしの母の訃報が届いた朝。夫が投げつけたグラスでわたしが指を切った夜。父が涙を流すのを見た日。少なくとも私にはどの出来事が起こったどの前の晩も、どの日々も、なんの予兆を捉えることなくただいつもと同じ夜と昼だった気がしたが。昼と夜は分断された境目を明らかにはせず、明るくなって暗くなる、いや、もとより昼と夜は分断されることはなく、ただ明るくなって暗くなる、ただそれだけのことではなかったろうか。季節の円環は、つづら折りに螺旋状に回り続けているだけなのだから。では、昨晩はどうだったろうか。
昨晩。
久しぶりに雨が降っていた。
海に雨が落ちる音は静かだ。風の音だけがとても強く感じられた。三つの蛍光灯がそれぞればらばらに揺れていて、隅の方だけ暗かった。夫人はやはり壁際にいて、そして横になっていた。
ぴしゃり、ぴしゃりという音がしていた。その音は少年が出しているのだった。なにか細長いものを床に叩き続けているのであった。腕を振り上げては下ろす。振り上げては下ろす。そのたびに手に持っているものが床に叩きつけられる。それはこの船の四等客室の晩の恒例となっていたのだ。少年は相変わらず毛布を頭まですっぽりかぶっている。腕だけを出してそれを行っているのだ。そしていつも決まった歌を唄いだすのだった。
(ぼくは天下のイリュージョニスト
暗い納屋で鼠を捕まえ尻尾を千切る
大人のそれは長い長い……)
ぴしゃり。ぴしゃり。ぴしゃり。ぴしゃり。
いつもはその歌が五回ほど繰り返されたところで夫人は眠りについていた。だがその晩だけは違っていた。その歌の続きを彼女は聞いたのだ。
(ぼくは天下のイリュージョニスト
暗い納屋で鼠を捕まえ尻尾を千切る
大人のそれは長い長い
僕は天下のイリュージョニスト
だけど世の中といったら
ぼくのことなど
誰が知る誰ぞ知る
火を噴く手品
魔法や技術
ぼくはなんでも知っている
わたしの夫は刑に服す
わたしは何日も船に乗る
式を挙げよう天下の式を
無理矢理にでも子供を作ろう
式を挙げよう
船は果たしてゆくのだろうか
天下の罪人独房の中でなにを思う
そんなことまでぼくは知っている)
少年はなんべんもそれを繰り返すのであった。ぴしゃりと叩き続けている音は次第に水気を帯びてきているように感じた。明らかにそれは雨や波の音とは違っていた。夫人は最初のうちは黙って目を閉じていたが、ある時すっと立ち上がった。足元の毛布を踏みつけ歩き出し、そして暗がりのほうへ行き、長い時間を掛けて形の崩れたものや大きすぎるものを選別し、その中でも一番小さなものを選び、これまた長い時間を掛けて少年の方へ後ろ手で引きずって向かっていった。少年はいまだ歌を繰り返してはぴしゃり、ぴしゃり、と音を立てていた。
少年の前に立った夫人はしばらくその様子を眺めていたが、やがて箍の部分が少年の頭頂に当たるように目測をつけて持ち上げた。すると、少年は唄うのをやめ、こう叫んだ、
「樽を投げつけたのはあなただ! ぼくを殺したのはあなただ!」
夫人は躊躇いもなく少年に向かって思い切り力を込めて樽を投げつけた。少年の振り上げた腕は、ぴしゃり、と音を立てて落下したきり動かなくなった。夫人は言った、
「樽を投げつけたのはあなただ! ぼくを殺したのはあなただ!」
夫人はその言葉を、ぴくりとも動かなくなった少年に向かって何度も復唱した。「樽を投げつけたのはあなただ!」
夫人は毛布を元通りに少年にかぶせなおした。ちゃんと生きているように見えるように――。夫人は立ち上がってからもう一度だけ叫んだ、
「ぼくを殺したのはあなただ!」
そして夫人は少年を憐れんだ。
天下の手品師が自分の死期も知らないなんて、と。
しかし、それは間違いであるとすぐに考えなおした。
死期は何人たりとも知りえないのだと。
夫人は静かに樽を片付け、また元の位置に戻り、そして眠りについた。
眩暈を伴う回想は長く続き、やっと治まったころには疲労感に満ちていた。そして、紛うこと無き解放感があった……。これが夫の言っていた前兆なのだろうか。というよりも、これは本当に昨晩の出来事なのだろうか。その昨晩、またはさらにその昨晩の出来事なのだろうか。事実――なのだろうか。夫人は混乱の渦に巻き込まれた。明かりがほしい。わたしは目撃者ではないのか。もっと明かりを。わたしは加害者だというのか。被害者ではないのか。部屋中を明かりで満たそう。夫人は恐る恐る少年の脇を通り過ぎ、カーテンをめくって外の様子を眺める決心をした。少年のすぐ近くを通るのがとても憚られ、少年とある程度の距離を保ちつつ窓へ向かおうとした。
その時であった。汽笛がうわんと鳴り響いた。一瞬、夫人は何事かと思ったがすぐに理解した。
船が出る、ついに。
そう思ったと同時に、すべてのカーテンが一斉に燃え上がった。光が差し込んで、その中に影が揺れた。汽笛がもう一度鳴らされた。一瞬目が眩んだ。部屋中は、特に窓に近い所は、ぬるいミルクのなかにいるようであった。光に溺れかけた目がじわじわと慣れたころ、夫人は影に気が付いた。
すべての丸窓の、すべての窓外には刑を執行されたばかりの主人の姿が映し出されていたのだった。複数の夫が、複数の窓に、同じように首に縄をかけられぶら下がっていた。
紛れもなく自分が迎えに行くはずの夫の姿であった。
その横顔は苦悶の表情一つ見せぬようで、それはまるで、夫人が想像した、白壁の前に佇む夫の無表情と同じようだった。いつの間にかあの若い船夫が後ろに立っていた。そしてぶん、と両手を挙げ、叫びだした、
「これがあなたの罪の結果だと皆が皆、頷くことでしょう。そうして輝きのなかの夫に誰もが賛辞を呈することでしょう。あなたはただ単に取り残されるべくして取り残されたわけではないのです! あなたは夫を憎んでいたはずです。そして義父母を。無理矢理に結婚をさせた村の人々を。同じ日々を繰り返せなくなったひとつのきっかけから。あなたの望まぬ妊娠というきっかけから。でもあなたは迎えに行くことに決めたのです。あなたは夫を愛していたからです。いいえ、愛さなくてはならなかったからです。夫となる男に無理矢理に置かされたから。あなたはこうやって、この場で、あとは船が出港すればいいだけのところまで耐え忍んできたつもりだったのでしょう。しかし、大時化などどこにあるのでしょう。あの明かりは太陽の焼けつくそれではないでしょうか! あなたの主は出所することなく死刑が執行されました。あなたは主の執行人でもあったのです! 手品師を殺したことに加えて、この場所で、そこに留まり続けることにはどんな罪と罰があるのでしょう! あなたが出港をながながと待ち続けてきた間のどこかで離船することを決めたならば、乗り続けていることで満足を味わっていなければ、あなたと主は自由の身だったかもしれません! それは誰もが思うことでしょう。あなたの主は、今も首を括られています。あなたの主は! 処刑は完遂されたのです! あなたの夫は! 処刑は完遂されたのです! 喜ばしいことにあなたみずからの手で!」
途端に窓外に変化が表れた。死刑執行の様子が、時間軸を伴って動き出したのである。それも繰り返し、何度も。ぐるんと夫の姿が窓の上に消え、落下してきては縄が軋む。再び巻き戻されては落下する。ぐるんと巻き戻されては落下する。夫の処刑がただただ繰り返されるのだった。若い船夫は窓の前、中央に歩を進め、そして窓外の全光景に向けて拍手喝采を浴びせ始めた。同時に、少年の毛布の表面が赤く滲んでゆき、溢れてきたその血はゆっくりと、しかし確実に、夫人の足元へ曲がりくねりながら流れやってきて、夫人の足をじっくりと濡らし始めた。
夫人は絶叫した。
窓のそばへは近づくことが出来ず、部屋から飛び出した。「わたしは!」と、「ああ!」と、「違う!」と叫び続けながら通路を駆け出した。夫人の通ったあとには血の足型がしっかりと残っていた。階段下のスペースで、女と男二人が談笑していた。一人は船夫の机に腰を下ろしていた。夫人は彼らを押しのけて通り過ぎた。その際、今押しのけた女が桃色のロングドレスを着ていたようだったのを、ちらりと目の端に掠めとったが、夫人は足を止めなかった。男の片方は黒い外套を着ていたし、もう一人は白シャツをまくり上げていた気がしたが通り過ぎた。目の前を尻尾のない鼠が横切った。夫人は船を出、タラップへと辿り着いた。
その先には義父母が満面の笑みで立っていた。
夫人は再び眩暈を起こした。気が遠くなって、そして転げ落ち、海底へと沈んでいった。
沈みつつあるなか、夫人は義父母の声を聞いた、
「おかえり、おかえり、愛する息子よ――!」
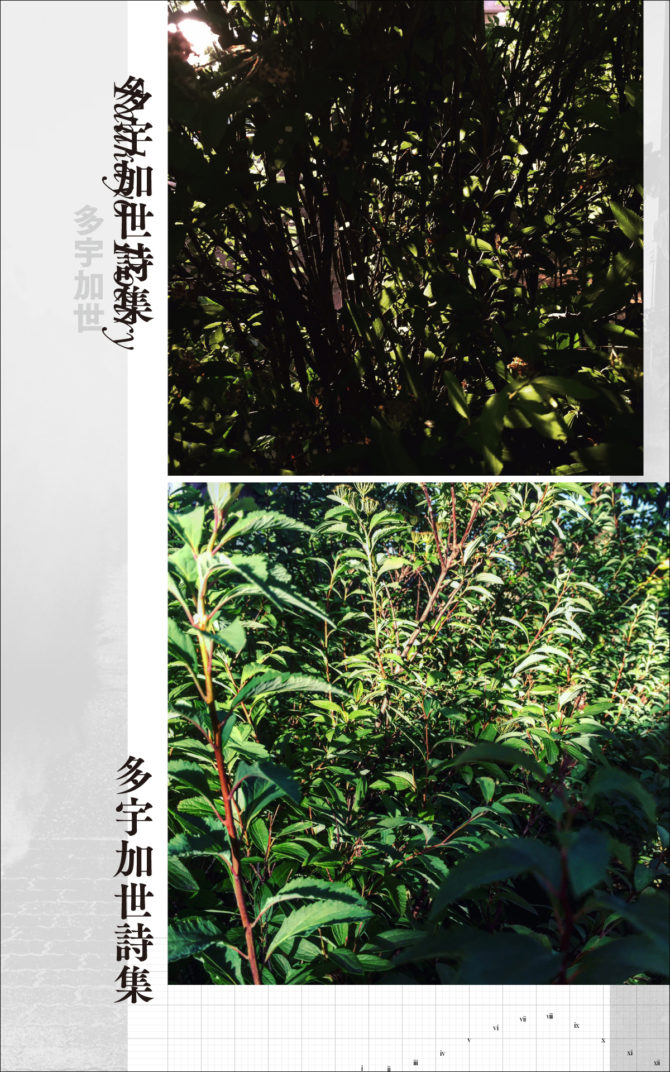






















"Theme(離船)"へのコメント 0件