《私》は怒り狂っていた。どこかに俺のことを読んでいる者がいると。今も読んでいると。
仮にやめてくれと頼んでも、聞いてはくれないだろう。心を込めれば込めるほど、礼を尽くせば尽くすほど、より強い好奇心で読み続けるだろう。
許せぬ。何とかして懲らしめてやりたいが、肉体が別の世界にあるものだから、直接の攻撃は不可能だ。
誰か代わりに懲らしめてくれと叫んでも、その声が聞こえるのは、読んでいる者ばかりだ。読んでいない者には届き得ない。読んでいる者はむろん、おのれを懲らしめるわけもなく、ここに悲痛なSOSを発している者がいるという事実など、難なく隠蔽するだろう。
――あるいはこの世界にも、隠蔽している者がいるかもしれぬ。何か本を読んでいる人物を探すか。それはめぐりめぐって俺のかたきだ。そやつを懲らしめれば誰かが救われる。それはめぐりめぐって自分を救うことにならぬとも限らぬ。
少なくとも、別の世界の、別の自分を即座に救うことにはなる。
――しかし待った。もし俺がここで誰か懲らしめれば、俺を読んでいる者が喜ぶのではないか? イヨッ、待ってました、と。……それならいっそ、徹底的に退屈にしてやるのがよかろうか。
そういうわけで《私》は、徹底して何もせず、ひねもす寝ているのであった。
寝ながら考えた。この考えも読まれているのなら、愚にもつかぬことを考えてやろう――そんなことを考えつつ、じっと寝ころんでいるのであった。
さて、どえらい床ずれもできたが、そろそろどうだ。読んでいる者は、いい加減ウンザリしたのではないか?
……いや、まだ期待のまなざしを向けているかもしれぬ。何だか変な物語が始まったが、いったいこの先どうなるのだろうと。
これではいかんと跳ね起きた。持久戦はこっちが圧倒的に不利だ。いくら苦労しても読み飛ばされればそれまでだし、このどえらい床ずれも、あるいは書かれてすらいないかもしれない。書かれていて、読まれていても、「ふうん」で済まされてしまえば、この苦しみは無意味だ。苦しむだけ損だ。
嗚呼! どうすれば読んでいる者を懲らしめられよう? この世界へ来させられさえすれば……あまりに没頭して、魂が入り込んでしまうほど魅力的な物語を呈せばどうか――うん、いいな。それしかないな。
かくして《私》は、それにつながる道を探し求めた。遂に見つけたので突き進んだ。そして見よ、その企てはみごと成功し、果たせるかな、一人の読者がここに立っているのであった。
彼(読者)は怒り狂っていた。それと言うのも、深く没頭せしめられ、魂をして入り込ましめられた魅力的な物語とやらが、マッタク書かれていなかったので。
そもそも彼は、《私》とやらが、「読んでいる者」をああまで憎んだ心理について、まだろくろく感情移入もできていなかった。だのに入り込ましめられ、強引に登場させられて。
《私》とやら――そのすがたはどこにもない。
折よくやって来た通行人に尋ねれば、すでに亡くなっているそうだ。くだんの、あまりにも美しい物語の感動的なラストに散ったとのことだ。
彼は歯噛みして悔しがった。許せぬ。天に罰せらるべき《私》だ。どうにかして懲らしめてやりたいが、もはや消えてしまった《私》の奴を懲らしめるには、どうすればよかろう?
……じつは私が《私》だったというのはどうか。そういう解釈も成り立つと。幸い、くだんの物語の内容は明かされていないし、《私》なる人物もまた、「俺」という一人称の他には情報もなく、ほとんど特徴も不明だし。
あんなに憎んでいた相手が自分だったとなれば――うん、いいな。それしかないな。
かくして彼は、それにつながる道を探し求めた。遂に見つけたので突き進んだ。そして見よ、その企てはみごと成功し、果たせるかな、《私》がここで地団駄踏んでいる。
読んでいる者が《私》だっただと! しかもそういうふうに成り立つ解釈とやらは、マッタク書かれていない、いやそれどころか、本当に読んでいる者は、じっさいには一度もここに来てすらいず、今もずっとただ読んでいるのだ!……
――よろしい。俺も本を読んでやろう。ここにある。どうだ、読んでいるぞ。何とまあ面白いじゃないか。これほど心がふるえたことはかつてなかった。この本と出会えずに仕舞う人生なんて、どうして人生と呼ぶに値しよう。
この本に出会えた者こそ幸いなるかな……。
安らかにページをめくる《私》を残して、拍手喝采の中、ゆっくりと幕は下りた。
この結末に怒ったのは、下りた幕を撥ね退けて這い出て来た《私》であった。それは、これまでの激しいものとは違う、静かな怒りであった。
……そうか。今ここに俺は、まことの敵を悟った。敵は読んでいる者ではない。書いている者だ。こっちを懲らしめるのが先決だ。
しかしヘタに謀叛を起こせば、どんな目に遭わされるかわからぬ。むごたらしく破滅させられてはたまらぬし、原稿を破棄されることも恐ろしい。いわんや中絶されて忘却されて、このまま一切が永遠に停止することにおいてをや。
どうすればよかろう? 今もこうして書かれ続けていること自体、大いに危険だ。この考えも、書いている者に基づいている。なぜ危険なのか、じっさい、俺にはよくわからないので。
とりあえず安全の確保のためには、書いている者から愛されねばならぬ。それには俺も物を書き、作中人物に俺の存在を悟らしめ、その上で作中人物を、俺にとって愛すべき存在にすることだ。
かくして《私》はそれに成功した。
これに作者は怒り狂った。ここらでそろそろ怒り狂った。
そんな解決があるものか! どうやって成功したというのか? そもそも《私》も書けばいいのだという理屈が弱い――ねえ、おい。《私》よ。君に言っているのだ。いいかね、君は、自分を読んでいる者を懲らしめなければならんのに……いや、まあその通りだ。やめればよい。君の自由だ。しかし、書かれている書かれていると言うけれど、私からすれば、私をして書かしむるのは誰だ? 君ではないか。君がいなければ私はそもそも書かなかったではないか。
「それはおかしい」と《私》が言った。「あなたが書いたから私があるのだ」
「しかし君は、私の中から勝手に出て来たのに。中からというか、どこかからやって来たのだ。はじめにインスピレーションみたいなものがあり――このインスピレーションというのがまた厄介で、天からの賜り物なのか、無意識下の記憶の組み合わせから這い出て来た虫なのか――そして書いて行くうちに、先に書いた言葉が次の言葉を生んで、その言葉に導かれてというふうにね。そんなものを書かされている私こそいい迷惑だよ」
「ちょっと待ってください、台詞を考えますんで。(――さてこの作者とやら、みごと泥沼にハマりおって、この先考えられ得るもろもろのパターンの取捨選択と、おのれを登場させた場合、どこまでおのれであり続け得るかという問題に直面しているように見受けられるけれども、本当に行き当たりばったりなのか、それともすべて計算の上なのか?)――ともあれ読んでいる者は相変わらず、何の危険もなしに、今も読んでいるんですよ。先生! 悔しかァありませんか!」
「別に私は悔しかァないが、まあそれでこそ君だからね。上等々々。いい怒りっぷりだ。――しかしどうだろうな、たしかに君は、言動や思考を無許可に読まれているという、人権侵害的の被害をこうむってはいるけれども、同時にまた、読まれているあいだだけ存在できるということも事実なわけだが、そこのところはどう思うね」
「その事実に、私は感謝をしない権利がある」
「あるともさ。それで――要するにそろそろ被害者は読んでいる者のほうになって来たんじゃないか?」
「いえ、それもまだ首肯せられぬことです」
「ともあれこのままでは中だるみになりそうだ。あるいは徒然なる中だるみにこそ、真理が描かれ得るんだがね。うん。そういうわけで、ここを先途と一つ、活発に動いてみようじゃないか」
かくして二人は徒然なる相談のすえ、問題の根幹に当たろうということで、大いなる図書館に向かって、遥かなる旅に出た。
言語に絶する過酷な旅を続けるうちに、いつしか《私》は作者を「ウェルギリウス」と呼び、作者は《私》を「ダンテ」と呼んでいた。
さらに旅を続けるうちに、いつしか《私》は作者を「旦那様」と呼び、作者は《私》を「サンチョ」と呼んでいた。
作者が《私》を「ダンチョ」と呼ぶようになっていくばくもなく、大いなる《ベアトリーチェ・デル・トボーソ図書館》に到着した。
二人は諸国遍歴のあいだにスッカリ失われていた本来の自己を取り戻すと、天までそびえる巨大な門をくぐって入って行った。
「ほほお……ここには、また読んでいる者がたくさんいますね」
と《私》が、声を落としてささやいた。作者はうなずいて、
「どれ、我々も何か読むことにしようか」
「どうぞ先生は読んでいてください。私は書きますんで」
「書くったって」
「何やらチラホラ、書いとるのもおりますでしょう。読むばかりが能の建物でもありますまい」
「しかし、どんなものを書くんだい」
「内緒です。そうすりゃ私が書くものを、読んでいる者は知るすべを持たないわけです」
そうして《私》は、空いている机に腰を下ろすと、パピルスの巻物に葦のペンで以て、せっせと何やら書き始めた。
しかつめらしい顔をしてしばらく猛烈に書いていたけれど、ふと筆を置き、頬杖ついて考え込み始めた。と思うと、ちょっとあたりを見渡して、立ち上がり、作者を探し始めた。
近代フランス文学のコーナーで、立ち読みしているのを見つけた。
足音を忍ばせて近寄り、作者の後ろから肩越しに覗き込んで、
「何をお読みで」

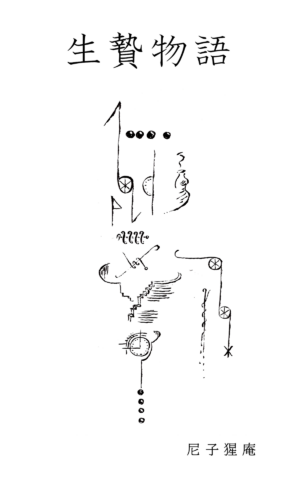











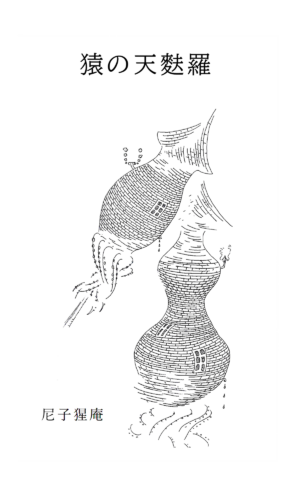










"アレクサンドリア図書館 第二章"へのコメント 0件