講座開始にあたって
なぜ作家になりたいのか。本講座の題に惹かれた人ならば、幾度となく自らに問いかけてきたことだろう。自己を客観的に確立する。生きた証を残す。社会と自分との間に流れる水をうんぬん。ただ書くのが好き。それもまたよし。
しかし、作家志望者全員が少なからず持っている動機づけはこれだ。
お金ほしい。
文章など誰にだって書ける。書くだけでは作家とは言えない。文章によって対価が得られてこそ、肩書きとしての「作家」である。読んでもらいたいだけならネットで公開していればよい。昔と違い、作家になって出版せねば人目に触れないということはないのだから。作家志望ということは、文章でお金をもらいたいということなのだ。
せっかくならたくさんもらいたい。
売れる文章を書けるようになろう。
それがこの講座の意図するところである。
どうすれば売れる小説を書けるようになるか。自分が思うところの「いい小説」はとりあえず置いておく。そんなものは売れてから好きなように書けばよいのである。一度流行作家となってしまえばなんでもできる。書店に行けば、著名人の「なんでこんな本が流通するんだ?」という本がいくらでも見つかる。小説家がサッカーを語りハローワークを語りキューバを語る時代である。お笑いタレントが健康を語る時代である。デビューしてしまえば勝ち。売れれば勝ち。まずは売れよう。
この講座では、売れている小説などを検討しながら、「どのようにしたら売れるか」を即物的に考える。
講座受講時だけでよいから、この言葉を心に刻んでもらいたい。
「売れる本こそ、よい本である」
連載終了時には、作家への道がはっきりと見えていることだろう。
なお、質問も受け付ける。寄せられた質問については真摯に答えていくつもりであるので活用されたい。
第一回 文体について
まずは文体について考えてみよう。
作家志望者のどれほどが、自分の文体に自覚的であろうか。ネット上で発表された小説など、文章の巧拙はともかく、文体と物語が不一致なものが非常に多い。文体にはそれぞれに色がある。文体の色と物語の色が一致しなければ読者は途中で本を捨てる。「市川拓司のSM小説」「原作あずまきよひこ作画井上雄彦」は無理なのだ。
一つの文体しか持っていなければ一つの物語しか描けない。多くの物語を書きたいならば、それだけの文体を持たねばならない。
選択肢としては、
・文体を統制し多彩な物語を書く(宮部みゆき)
・同じ文体で同じ物語を書き続ける(桜井亜美)
しかないのだ。
桜井もあれはあれで偉大であるが、宮部になるに越したことはない。同じ題材を書き続けると飽きる。読者以前に書く方が飽きる。書きたいことなどすぐ変わる。それに対応できるよう、常日頃から、文体を統制し物語にあった形を作れるようになっておきたい。
できることなら、売れる文体で。
そのためにも、今売れている文体はなにか、それはどういう物語に向いているのかを、常に意識し、自分のものとしていかねばならない。
参考に、現在人気のある三つのジャンルの文体を示しておく。
いずれも、超大作長編小説の最終場面と考えて読んでもらいたい。
ラノベっぽい
「ねぇ、ゆうくん、私、ゆうくんと会えてよかったよ……」
まゆは僕の腕に体をあずけ、僕を見上げる。
「ごめんな、ごめんな」
僕が泣きじゃくると、まゆは大きな目を細めて笑い、泣いた。
「ううん。ありがとう」
僕の涙とまゆの涙が交じり合った。
「大好きだったよ、ゆうくん」
彼女は静かに目を閉じた。
もう、開くことはない目を。
ケータイ小説っぽい
「ねぇ、ユウ、わたし、ユウと会えてよかった……」
つぶやくマユ……
声にならない……
「ゴメン。ゴメンな」
泣いた俺に、マユはにっこり笑った。
「ううん。ありがと……」
交じり合う、俺と、マユの、涙。
マユと俺を隔てるものはなにもない。
「……ダイスキ……ユウ……」
マユは永遠の眠りについた。
マユは生き続けることはできなかった。
マユは俺の中だけで生き続ける。
純文学っぽい
「ねぇ、勇さん。私、勇さんに出会えてよかった気がします」
真由の中には確固とした私がいるようである。
ここまで言わせられることこそが、男の喜びである。この女は自分のものとして死んでいくのだと思うと、死という現実もそのままに受け入れられる気がしてくる。天を見上げれば真由と私の運命をあざ笑うかのように厚い雲が太陽を遮る。はらはらと落ちる雨が女の髪を濡らしていく春の宵。
「すまない、まゆ」
真由をひらがなで呼んでみる。
私のほほを涙が伝ったようである。男の涙など親の死でしか許されないと思っていた私でも流す涙であるから、愛する女の死というものは、親の死以上に受け入れられないものであり、それがまた男が女を愛した証でもあるということを、私の涙から真由は受け取ってくれたのではないかという気がしてくる。
男と女の死別というものは、串焼きのようなものであるとふと思う。串と肉はばらばらにされ、肉は消滅しながらも、肉の一部が串に残る。そのはがれ残った部分を串から取りさったところで、香りは消えない。女に死なれた男の体にも、女の痕跡が残り、痕跡が消えても女の香りがいつまでも残り続ける。そうなってこそ男が女の人生を背負えたという証であって、こういう女を持ってこそ一人前の男として認められたという気がしてくる。私はよい肉を食べられた。そう真由に感謝したい気持ちである。
しかし男が死に女が生き残った場合はどうか。女は(以下略)
「っぽい」と書いたのは、その筋の愛好者から怒られないようにするための予防線である。我ながら案外弱気だ。
それぞれの文章は、ある小説の結末部分であるが、結末までの流れを想像すると、異なった物語が浮かんでくるだろう。
たとえばラノベ型では「僕(ゆう)の前に現れたまゆは、特殊なエネルギーを持ち地球の救世主となる少女であった。謎の知的生命体の攻撃を、まゆは自らのエネルギーで防ぐ。しかしまゆの命の火は燃え尽きたのであった」
たとえばケータイ型では「俺(ユウ)の前に現れたマユは、援助交際で稼いだ金をホストクラブにつぎ込む女子高生だった。俺の愛で、本当の自分を見つけるマユ。しかしマユの体はエイズに冒されていたのだった」
たとえば純文学型(仮にアイルケ型と呼んでおく)では「私(勇)の前に現れた真由は、暴力団の組長に囲われている女であった。相思相愛になった私と真由は、北の地への逃避行を決断する。しかし真由は組の若頭に撃たれた」
もちろん、こんなに単純な物語ばかり書くわけにもいかない。多様な流れが入り込むと、文体にも色の混合が要求される。
「本当の自分が見つけられずに夜の渋谷をさまよう女子高生ヒロ。ふとしたことから彼女は日本を異世界の侵略から守るために戦うことになる。激闘の末に異世界軍を撃退したヒロであったが、その反動から結核になり、愛する幸二の腕の中で死んでいく」
という物語であれば、ケータイラノベアイルケのブレンドが求められる。場面ごとに比率を変えられればなおよい。最初はケータイ色を強くし、最後は8割がたアイルケ。もちろんかなりの技術が要求される。「囲碁界ホープの青年が、麻雀にのめりこみ、雀荘を開く」物語を、小畑健で始まり自然に福本伸行になり西原理恵子で締めることを想像してもらえば、困難さがわかるはずである。困難ではあるが、この壁を乗り越えようとする気概がほしい。上達すれば、「ケータイ3ラノベ2アイルケ5に7がけして村上春樹2と綿矢0.5と川上弘美0.5を足して中原昌也でくるんだ文章で書いてみよう」と言えるようになる。
では、書きわけをどのように学ぶか。統制する技術をどう身につけるか。
それは各自の努力だ。
――(続く)


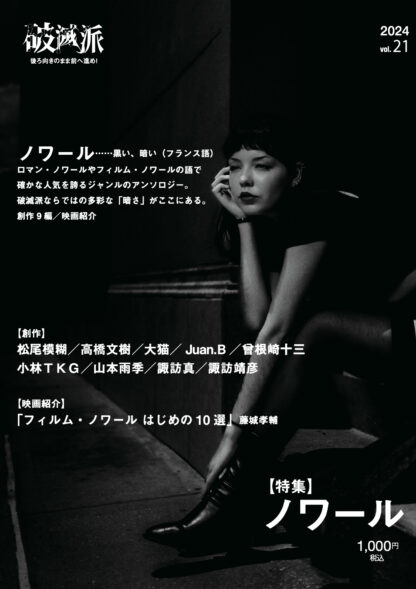
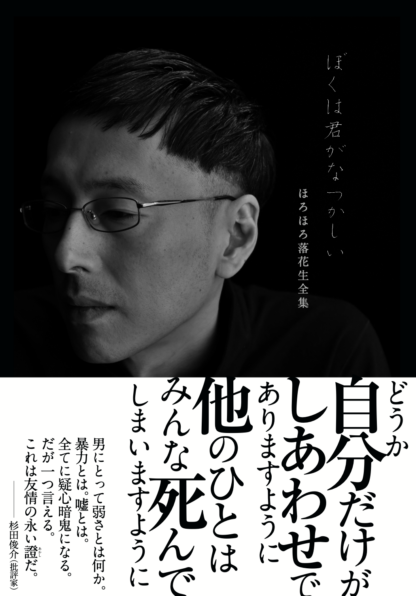
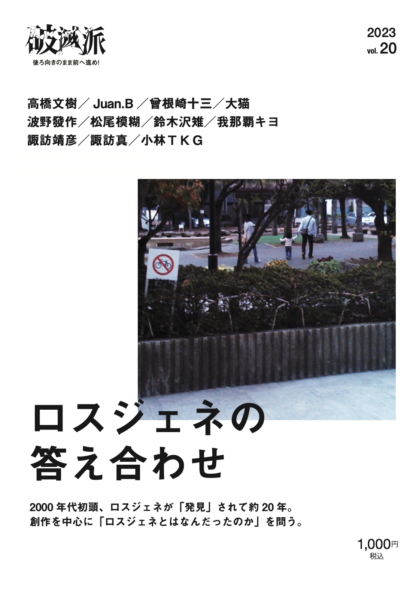
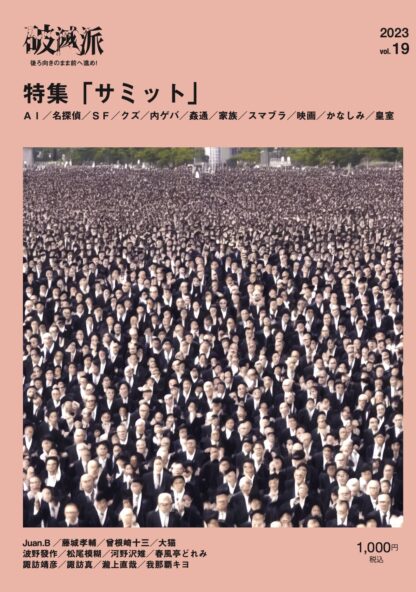
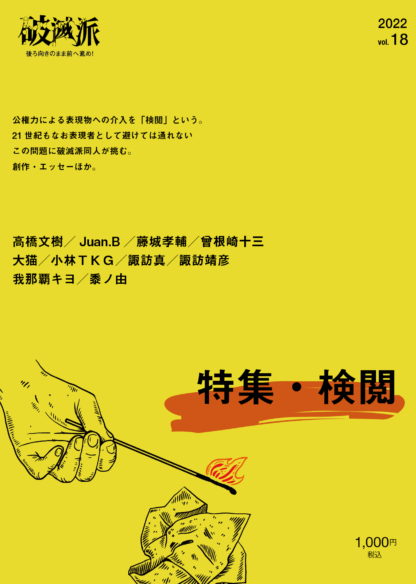
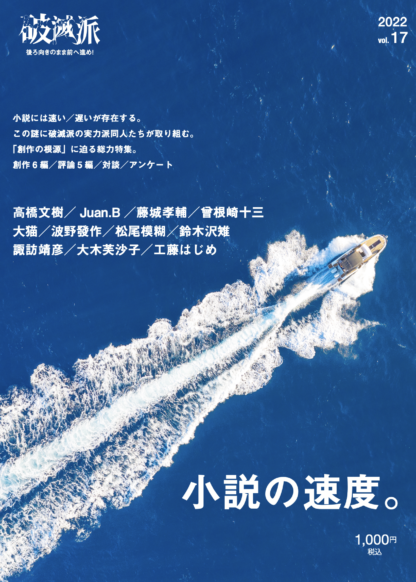












"流行作家養成講座(1)"へのコメント 0件