「ナカヨシ」
わたしを呼ぶ声がする。
「ナーカヨシ」
ああ、呼んでいる。眠い。まだ眠い。何時かな。十五時。ああ、もう、そんな時間。わたしは打ち合わせスペースのソファから身体を起こす。伸びをする。古びたソファの脚がぎしりと軋む。いつの間にか掛けられていたブランケットを払い除けて、サンダルを捜す。片方がソファの下に入り込んでいた。ひっぱり出しながら遅れて返事をする。
「——なんですかぁ」
センパイがディスプレイから顔を離して一瞬こっちを見る。
「アイス買ってきて」
「えーなんで」
「なんで?」
うっ。センパイはいま昼前までわたしが書いていたコピーをパンフレットの誌面に落とし込む作業をしている。たっぷりのマンションポエムを盛り込んだ不動産の総合パンフレット。見積額はいっせんにひゃくまんえんの大仕事。顔はまったく動かないがマウスのクリック音が激しく事務所に響き続けている。夕方クライアントに持っていく予定のパンフレット(初稿)である。わたしが二日間も滞らせたせいで、今センパイが全力疾走をしている。ならばわたしがコンビニまで全力疾走するのは当然の責務である。
「いえ、ダッシュでいってきます」
「よろしい。あずきバーを頼むよナカヨシ」
「いえっさー!」
わたしの書いたマンションポエムをニヤニヤしがら見るセンパイと同じ部屋にいるのは辛い恥ずかしい無理。さすがに無理。ニヤニヤはしてないかもしれないけど、ちょくちょく意味を聞かれるのはイヤすぎた。それで寝たフリしていたら本当に眠ってしまったのか。
浅草橋の小さなデザイン事務所。株式会社東京コンビナート。社長は小口ナリユキ。アラフィフのバツイチ。昼間はめったにいない。だいたい営業で飛び回っている。昔は大手の広告会社にいたらしいけど、あの世代にはめずらしく武勇伝を語らないタイプだから詳しいことは知らない。たぶんわたしたちにはあまり関係がない。社員はふたり。わたしとセンパイ。イサカイ先輩がアートディレクターだ。というか唯一のデザイナー。デザイナーは他にもいたけど、みんな独立しちゃって、今はイサカイさんだけの事務所になっている。印刷系のアートワークから、ウェブ系までこなせるマルチデザイナーだけど、本人はただの器用貧乏とか言っている。ケンソンだね。わたしはナカヨシ。コピーライティング担当。うちで出す発行物はだいたいわたしが書く。間に合わないときは外注だけど。あと企画書とか議事録をまとめたりするのもわたしのお仕事になっている。他に週三で来る事務さんがいる。
ビルから出るとアスファルトの熱気がモロに顔にぶつかってくる。もうこれは爆風に分類してもいいのではないか。そんな空気の実体がわたしを殺しにかかってくるが、今のわたしには任務がある。わたしのために戦っているセンパイに美味しいあずきバーを届けなければいけないのだ、わたしは足を一歩一歩溶けたアスファルトに踏み出す。クロックスの底が熱で可塑ってくるのを感じるが、無視して次のステップを踏む。死の後進。デスマーチ。コンビニまで五メートル。どうにか息絶える前に自動ドアをくぐることができた。
レジであずきバー二本(センパイとわたしの分だ)の代金を小銭で支払い、レシートを捨てるとスマホに着信があった。事務所からだ。センパイかな?
「はい、ナカヨシ」
『イサカイ。ねえ、annon買ってきて』
「はい?」
『annon知らない?』
「知ってますよ。そんなの読むんですか?」
『いいから買ってきて。そこにある?』
最近のコンビニは雑誌コーナーがない。ここも撤去済みだった。
「ないです」
『じゃあどっかで』
「えーちょまっていますげえ暑いしこの駅本屋ないしどこで?」
電話は切れた。なんでそんな女性誌を急に欲しがるんだあの人は。なんかの資料かな?
コンビニの外は灼熱地獄だ。わたしはBダッシュで別の系列のコンビニまで一〇〇メートルダッシュをした。あずきバーがアイデンティティを保つうちに戻ってこなければ、わたしのアイデンティティが危ない。
そっちのコンビニは辛うじてまだ雑誌コーナーを維持していた。女性誌もある。目が止まる。
〈最新のライフスタイル〉
〈究極のネイチャーライフ〉
〈美と健康と調和。大地の恵み〉
そんなコピーが取り囲むど真ん中に。
〈縄文スタイル〉
見覚えのあるコピーの脇で、毛皮のキャミソールを纏った専属モデルがにこやかにわたしを見つめていた。
「なんじゃこりゃ!」
わたしは二番目のラップされた方を面陳棚から抜いてレジに放り投げ、七八〇円を払って、来たときよりも速いダッシュで事務所ビルに戻った。わたしこんなに速く走れたんだ。すぐに来ないエレベーターは放棄して階段を駆け上る。
「イサカイさん! なんですかこれ!」
「おーありがとう。あずきバーはやっぱ少し緩んだくらいじゃないとね」
センパイはわたしの手から勝手にあずきバーを取って、ペリペリと開封した。わたしも自分の分を開けてかぶりつく。ちょうどよく溶けて硬くない。おいしい。
「いや、待って。あずきバーじゃなくて」
センパイはあずきバーをくわえながらすでにannonのラップを開けて中身を取り出していた。
「これか。ほんとにあったのか〈縄文スタイル〉」
「なんか聞いてます?」
「全然。社長も知らないって」
センパイがペラペラとページをめくると、見覚えのある人物がインタビューを受けていた。
「なるほどね。まああちらさんの事業だから、こちらでどうこう言える話じゃないよ、ナカヨシ」
「それはそうなんですが……」
〈縄文スタイル〉はわたしが、いや、わたしたちが作ったウェブサイトのタイトルだ。作ったと言っても、ある団体から依頼を受けて、コンセプトとデザインを考えて制作した請負仕事であるので、もう納めてしまった今となっては、わたしたちになんの権利もない。商標もその団体が登録申請したはず。どう使おうが彼らの勝手なのだ。それで、いま、この雑誌がその団体とコラボして特集をした、ということなのだろう。でも。
「でも、ひとことぐらいあってもいいと思いません?」
この仕事は本当に大変だったから思い入れも強いんだ。
「まあなあ。義務はないが義理はあってもいいかもな」
事務所の電話が鳴る。センパイがあずきバーを袋に戻して電話に出た。
わたしは雑誌を開いてみる。構成がわたしの考えたウェブサイトのまんまだ。なにこれ。パクリじゃん。別にいいんだけど。著作権とか売り渡したし。でもさー。なんかあってもいいよね。苦労したのわたしだし。とちょっと思う。ぐらいの権利はあってもいいと思う。
縄文健康法、縄文人の価値観、縄文人から学ぶ社交術、人の輪、和。土器文様からインスピレーションを得た最新ファッション。縄文メイクテクニック。縄文クッキング。縄文人の愛し方、愛され方。八〇ページに及ぶスーパー特集だった。これ結構お金動いてるんじゃないの? ウェブのときのギャラも結構よかったみたいだけど(ボーナス出た)。すごいな。コーナーの末尾にある〈PR〉と〈協力 JCR:縄文文化研究会〉の文字。やはり縄文研が関わっている。
センパイが電話を切った。すっかり溶けて棒が抜けてしまったあずきバーをあきらめて、わたしを見た。
「ナカヨシ、明日〈縄文研〉行くよ。根羽子沢さんから電話あった」
「マジすか」
根羽子沢課長は〈縄文スタイル〉ウェブサイトの発注担当者だ。どうやら社長からすぐに先方に問い合わせをしたらしく、その折電だったようだ。センパイはわたしの残りのあずきバーを奪ってパソコンに戻った。不動産パンフの仕上げを済ますために。
「縄文スタイル……」
わたしは買ったばかりの女性誌を手につぶやいた。センパイがそうだな、とうわのそらなんだかよくわからない感じで返事をしてくれた。二度と会うことはないだろうと思っていた我が子と再会したような、そんな気分だった。
「……縄文スタイル」
「ナカヨシ! うるっさい! 寝な!」
センパイがクッションを投げつけてきて、眼前で受け止めたわたしはそのままの勢いでソファにめり込み、雑誌をもみくちゃにしながら睡魔と仮面の女神とマイムマイムを踊りながら火焔式土器を回って混沌の闇に沈んだ。徹夜明けだったから。










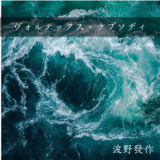




















"縄文スタイル(プロローグ)"へのコメント 0件