ネットのWebラジオから声が流れてくる。
「皆さま、明日隕石が私たちの、この母なる大地である地球に衝突し、すべてのものが破壊されます。どうか皆さま、愛する方と共に最後の時を迎えましょう」と言っている。
俺はパソコンの電源を切って、引き籠っていたボロアパートを出た。
一週間前に人類の滅亡が伝えられて、ある者は必死で生きる道を模索し、ある者は愛する人と静かに最後の時を待ち、ある者は神に縋り天国の門を開けてもらう為に教会へ赴く。出来の悪いSF小説のような展開に、それでも俺たち人類は最悪の結末を受け入れようとしている。
「恵み溢れる聖マリア、主はあなたと共におられます。主はあなたを選び祝福し、あなたの子イエス様も祝福されています。神の母、聖マリア罪深い私たちの為に、今も死を迎える時も祈ってください」
聖堂の中は多くの信者で溢れ返っているのに私語など全くなく、ロザリオを繰る音と詠唱だけが続いている。死の谷を共に歩く兄弟姉妹だ。隣には葬儀の時に掛ける黒いベールを白髪の掛けた上品な老婦人がいて、ロザリオを繰る手に目をやるとその手が小刻みに震えていた。俺はその老婦人が気の毒になって、思わずその手を取りそうになるが、思い直して自分のロザリオを拳の中に握り込み、祭壇の上で十字架上に磔つけになっておられるイエスキリストの像に目を向ける。そしてこれから行うであろう俺の罪の許しを心の中で唱える。
「罪深い私をお許しください」
許されるはずなどない重罪を。
俺は5年前にカトリックの洗礼を受けた。洗礼名は「マキシミリアン・マリア・コルベ」ナチスドイツのホロコーストで餓死室に行く囚人に「私があなたの代わりに行きましょう」とまるで買い物の列を譲るような気安さで、ホロコーストの中でも最も残忍で過酷だと言われた餓死室に入った聖人の名だ。
彼は結核を患った病歴があったにも関わらず、水も食事も与えられずに死を待つだけの餓死室で17日間を生き延びた。次々に死んで逝く囚人たちを勇気づけ天国へ送り出し、最後は死の注射で帰天された。この話を聞いたとき、俺はどんなにか胸を打たれたことだろう。俺は彼の境遇を自分の境遇に重ね合わせた。もしも母の代わりになれるなら、俺は喜んで餓死室に入るだろう。しかし、結局俺は母の足枷にしかならなかった。
あるいは、俺がいなかったら母はあの悪魔のような男の妻であることから逃げ出せたのだろうか? たぶんその答えはYESだ。
母の夫、つまりは俺の父親の暴力はいつ爆発するか分からなかった。酒を飲むわけではないのに、ふとした事で「バカにしやがって!」と突然キレて、容赦のない暴力で母を傷つける。怒りが怒りを増幅させて、殴る蹴るを繰り返し髪を鷲掴みにして、そして最後には耳元で「お前が悪いんだぞ。俺を怒らせるから」と毒の言葉を注ぎ込む。母の体はいつも青痣が絶えなかった。もちろん俺も殴られたが、母親が殴られることはその数倍、俺の中の汚物のような感情を増幅させた。
俺を形成しているものは無力感と劣等感だ。だから、教会に辿り着いたとき、俺は「許されたい」と思った。「生きていていいのだ」と誰かに了解を得たかった。そして十字架上のイエス様の前で跪き、泣き崩れたのだ。しかし、神に許されても自分が自分を許せない事への苦しみは生きている限り続くことに気付いてしまった。
詠唱の続く教会からそっと抜け出し外へ出ると寒さで息が白くなった。俺はポケットの中にある金属の冷たい感触を確かめて、自分を奮い立たせた。
ずっと患っていたうつ病の為に何年も飲み続けてた薬を、もう片方のポケットから取り出す。それを無造作に口に入れると奥歯で噛み砕き、その苦みを舌の上で味わいながらゆっくりと飲み下す。
母は昔、俺が学校でイジメられていたときこう言った。
「もし死のうと思ったらお母さんに言いなさい。一緒に死んであげるから。絶対に一人で死のうとしないのよ。約束してね」
母は俺の手を取って、少女のような笑顔で言った。母の指がまるで砂糖菓子のように白くて細くて、強く握ったらぽきっと折れてしまうのではないかと本気で心配になったのを覚えている。
駅に着いた。もちろん電車など動いていない。自転車が置いてあるので、それを拝借するのだ。もっともこの自転車も今は誰の所有物でもないのだけれど。駅の改札付近には、昨日降った雨のせいか、傘やレインコートなどがそこら中に散乱していた。
自転車で風を切って走ると、パリパリと音を立てそうな冷気が俺の頬を打った。小さな氷の混ざった雨粒が降り始めているのだ。先ほど飲んだ薬のせいか、重い鉛を詰め込まれたような胸の痛みは引いていた。そして、どこか晴れ晴れとした気持ちにさえなる。「大丈夫。俺は大丈夫だ」なんの根拠もない自信が俺を勇気づけた。
1時間ほど人のいなくなった街を自転車で疾走すると、1年ぶりに戻った実家の前に自転車を止めた。
玄関には消えかかった蛍光灯が心許なく点滅していた。車もある。あいつは、父は家の中にいる。俺はそう確信して音を立てずにドアの鍵を開け、中を覗き込んだ。目の前の廊下の先にぼんやりとリビングの明かりが見えた。物音を立てないようにリビングのドアの前に立つ。
「おい、なんとかしてくれよ。俺、死にたくねえよ」とあいつの声が聞こえて来た。俺の体に酷く原始的な怒りが沸き上がって来る。
「お母さん……」抑制できない感情の高ぶりが俺を襲う。眼球から搾り出されるような涙に、嗚咽が出そうになる。
「愛しています。愛しています。愛しています」と祈るように三回唱えた。高ぶりが潮のように引いていく。深呼吸を付いてから、ポケットの中でナイフの柄を握り、静かにドアの取っ手を廻した。
あいつは俺に背中を向けていた。椅子に座った母の腰に手を回し、纏わりつくように泣きじゃくっている。母は生気がなく、まるで美しい人形のように見えた。
リビングの入口に佇む俺に気付いたのは母だった。俺と目が合った途端、母の目には明らかに生気が甦って来た。
「まーくん」天使のような声で俺を呼んでくれる。
母の膝で泣きじゃくっていたあいつの体がピクリと震え、ゆっくりと上体を上げ振り返る。あいつは燃えるような怒りの目を俺に向け言った。
「何しに来た」俺は間髪入れずに返事をする。
「あんたを殺しに」俺はナイフの鞘を素早く取り、逆手に持って父に襲いかかった。
気が付くと足元に血溜まりが出来ていた。その中に父の屍が転がっていた。俺は自分の獣のような息遣いを聞きながらゆっくりと落ち着きを取り戻していった。深呼吸をついてから母の姿を探すと、母は多少飛び散った血を浴びているが、思ったよりも取り乱してはいないようだ。
「母さん!」俺は母を血で汚れた手のまま抱き締めた。
「まーくん。そんなに嫌だったの」
母の声が耳元でする。
「ごめんね。そんなに辛い思いをさせていたのね」母は淑女ように白く美しい手で俺の髪を撫でてくれる。
俺は母の顔を見ると母の唇に自分の唇を重ねた。こうすることが自然に思えたのだ。
最初、母の体は少し硬直したがすぐに弛緩した。母は俺の胸に顔を埋めると甘えたように両の手を俺の背中に回した。俺は、母の体を犯しながら思っていた。天からの硫黄の火によって滅ぼされたとされる都市「ソドムとゴモラ」あの罪人の魂は救われずにどこへ行ったのだろう。この世から消滅したのだろうか? それとも煉獄の火で未来永劫焼れ続けているのだろうか?
母の中に入ったまま、母の首に両手の指を絡ませて力を入れる。母の目が見開かれ、俺の意図を感じ取り小さく抵抗をする。
これから硫黄の匂いの炎がやってくる。
貴女の罪も俺が背負って行こうと思うんだ。
母の体が動かなくなると、その体を濡れたタオルで綺麗に清めてから衣服を整え、しばらく母の美しく穏やかな死に顔を見ていた。
明日、隕石が落ちる前に神父様が天国の門を開いて下さる。それまでに教会に戻ろう。俺が救われる筈などないけれど、せめて母だけは天国の門を通してあげたい。マリア様にお願いすれば、きっとイエス様に取り次いで下さる。だけど時間はまだもう少しあるのだから、母の顔をよく見ておこうと思う。時間が来たら身なりを整えて教会へ向わなければならないのに、どうしたことか酷い睡魔に抗えない。お母さん眠いよ。寝てもいいかな?
ふと段から落ちたような衝撃で俺は眠りから引きずり出された。顔を上げると先ほどの老婦人が黒いベールの下から、紙のように白い顔で俺を見て小さく微笑んだ。俺は慌ててポケットの中のナイフを確かめる。それは冷たい感触でそこに収まっていた。俺はほっとして歌うように詠唱した。
「恵み溢れる聖マリア、主はあなたと共におられます。主はあなたを選び祝福し、あなたの子イエス様も祝福されています。神の母、聖マリア罪深い私たちの為に、今も死を迎える時も祈ってください。初めのころも今も世世にアーメン」
了
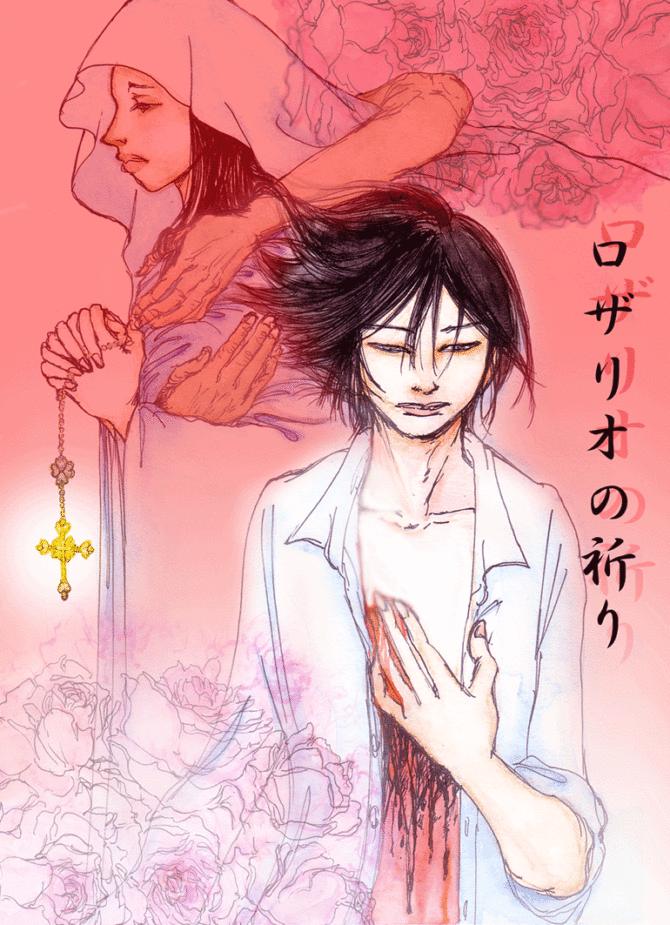






















Fujiki 投稿者 | 2018-07-27 01:26
隕石への言及はあるものの、話の中心になるのは父親殺しの物語。エディプス・コンプレックスは元型的でいつの時代にも遍在するとされる感情であるため、おそらくこの話は世界の滅亡がなくても十分に成立するのではないか? 私は『青の炎』のようなサスペンスものを思い出した。
神話や聖書といった元型を重ねるのはストーリーに普遍性を与える上で効果的な手法だが、肝心のストーリーが具体性を欠いている。父親が「酒を飲むわけではないのに、ふとした事で『バカにしやがって!』と突然キレて、容赦のない暴力で母を傷つける」ようになった経緯は説明されない。「結局俺は母の足枷にしかならなかった」と主人公は語るがそれを示す具体的なエピソードもない。語り手がどういうきっかけで、母親のどんなところに性的に惹かれるようになったかも今一つ伝わってこない。そのため、どの登場人物も類型的なパターンをなぞっているだけの一面的な存在になってしまっているように見える。
表現の面でも「砂糖菓子のように白くて細くて」「高ぶりが潮のように引いていく」「獣のような息遣い」「淑女[の]ように白く美しい手」「紙のように白い顔」といった紋切型の多用が目立つ。砂糖菓子や紙にだっていろいろな色と形があり、淑女の手が白く美しいとは限らない。せっかく母への思慕を聖母マリアに重ねているわけだから、直喩で喚起するイメージをすべて聖書的なイメージで統一するなどの工夫がほしいところだ。
あと、結末で老婆が再登場する意味が私にはよく理解できなかった。教会に引き返してウトウトしていたら老婆と再会したということか? 老婆が主人公の実家まで様子を見に来ていたということか? それとも、象徴的な何かか? ひょっとしたらキリスト教的な意味が込められているのかもしれないが、私も含めて聖書に詳しくない読み手には意味が伝わりにくいと思う。
長崎 朝 投稿者 | 2018-07-28 02:06
世界最後の日になってまで、父親を殺さなければならないというのは不幸だと思う。それを傍観する母、その母親を犯して殺す「俺」、展開が少し粗い気がしました。徹底的に読み直し、細かな言語表現についてもこだわって格闘し抜いたらもっといい感じになる気がします。
退会したユーザー ゲスト | 2018-07-29 10:54
退会したユーザーのコメントは表示されません。
※管理者と投稿者には表示されます。
一希 零 投稿者 | 2018-07-29 13:14
主人公の「母」と、マリア様を重ねているのでしょう、「母」があまりに神聖で美しく清い存在として描かれているのが印象的でした。とはいえ、母が圧倒的母性感を発揮しながら、一方でまるで少女のような存在として描かれていることには、最初少し戸惑いました。主人公はきっと、母が好きだからというよりは、母を所有する父に対し無力を感じていたのかな、と思いました。
大猫 投稿者 | 2018-07-29 13:55
心理的に、というか精神的な矛盾に溢れていてそれが独特のパワーを生み出している作品だと思います。
キリスト教徒になり、コルベ神父を敬愛して洗礼名までもらった青年が、世界終わりの日になってどうしても父への殺意を押さえられず、しかも自分はいいから母だけは天国へと願う。洗礼を受けて「許された」と確信したのに、自分で自分を許せない、しかもそれは母を救えなかった自分を許せないのであって、父を憎む気持ちを押さえられないことは微塵も考えない。カトリックらしからぬ心理の動きが逆に理想通りには行かぬ人の子の矛盾なのだと読みました。
最後のシーン、夢から覚めてほっとした、というのは、殺害をすることなく済んでホッとしたのか、これから実行する殺人が夢に消えたわけではなかったことでホッとしたのか、想像させられました。
退会したユーザー ゲスト | 2018-07-29 16:24
退会したユーザーのコメントは表示されません。
※管理者と投稿者には表示されます。
波野發作 投稿者 | 2018-07-31 02:22
親父殺るシーンをさくっと省略したのはちょいといただけないけど、滅亡に瀕して近親相姦に及ぶというのは他の人にはなかったので、そこは良かったかもしれない。ただ、ここでも「思いを遂げる人」と「つきあわされる人」が並立していて、なんだか世界はまったく平等ではないのだと寂しくなる。親父のDV説明を回想にせず、リアルタイムで書いてもよかったんじゃないかと思いつつ次へ。
Juan.B 編集者 | 2018-07-31 04:24
カトリックにそれも現代日本人が新しく洗礼を受けてなるならば、相当の教義的確信と教育を持って洗礼を受けると思うので、
終焉が迫っても、一応の恐怖はするにしても、救いについては確信していて著しく取り乱したりはしない人が多いのではないかと思う…と言うのはみみっち過ぎるか。そこが最後の描写(夢オチ派)に繋がってるなら中々だ。
俺も母親に連れられて教会(ただしスペイン語ミサ)に良く向かったが、俺にとってはミサの後にコーラとファンタが飲めて他の子とポケモンする場所でしかなかったからあまり深いことは言えないが。
高橋文樹 編集長 | 2018-07-31 12:11
世界の滅亡がなくても、この話は成立するのではないだろうか? というのも、罪の露見がそのまま語り手の世界の終わりだからだ。
聖書をモティーフにしたことで荘厳なイメージを演出することはできているか、全体的な構成にまとまりがない。