窓から射す月光に、寝台の上で丸まっている躰が蒼白く照らされている。身じろぎすらしないその塊のようなものを、黒い睛がじぃっと見ている。
窓の縁で鴉は少女の肉塊を飽きることなく、見つめつづけていた。鴉に細い背を向けて、膚のほとんどを長い髪で隠している塊の正体は少女だということを鴉はとっくに知っている。
そろそろ目覚めてくれるはずだ。今夜が明けたら、死人のように白い頬に赤みが差す――そう予感しながら、鴉は月が沈むのを待った。
そして太陽が昇ると、少女は震えるなどの前触れをいっさい見せずに起きあがったものだから、鴉の小さな心臓は跳ねた。
「お、おはよう」
鴉の聲に少女はゆっくり振り返る。黒髪の隙間から覗く頬と、薄い唇はほんのりと紅色に色づいていた。まだ眠たそうな半開きの目、黒い睛に鴉を映している。
鴉は羽を震わせた。温度を持った少女の膚に触れたいのだが、鉤爪では傷つけてしまう。自分の躰が憎くなり、悶えたのだ。朝の光を受けて、艶やかな髪のみを纏った眩く見える白い裸躰へ、鴉は寝台におりて近寄った。
自分は誰なのか、ここはどこなのか。そのような疑問を抱くのに必要な意識というものの存在自体、知らないであろう少女に鴉は云った。
「君は、この森が産んだんだよ」
窓の外、緑が光っていた。
「呼び名がないと不便だ。カラスマルでどうかな? 僕はカラスでいいから」
前から決めていた名前だった。柔らかそうな丸みを帯びた少女の輪郭からマルと思いついたけれど、それだけではなんだか味気ない。だから、少女を見つけた自分の種の名を足した。ちょうど少女の髪は行水したあとの自分の羽のような美しさで、似合うとも思ったのだ。
カラスマルが頷く。鴉は満足してつづけた。
「産まれたからには、生きなくちゃね。僕が生きる方法を色々教えてあげる。まずは外へ出てみよう。……ああ、その前に服を着て!」
寝台からおりて、ドアへ向かおうとするカラスマルを鴉は慌てて止めた。
「毛皮も羽毛もない生き物が、なにも纏わずに外へ出るのは危険だよ!」
羽ばたいてカラスマルの前に廻り、平らな胸を見ながら云う。この未熟な躰を好む獣は沢山居るのだ。
「寝台の隅にワンピースと下着が畳んであるから、それを着て。たぶん、前の少女の持ち物じゃないかな」
カラスマルは頷いて、寝台へ引き返す。意味までわかってくれているかは知らないが、とりあえず言葉は通じていることに鴉はほっと安堵した。
僕が守ってあげなくちゃ。
鴉はカラスマルを初めて見たときから、恋していた。
装飾のない白地の下着に、黒のパフスリーブのワンピース。それらを着てから、カラスマルは鴉と一緒に外へ出た。直接射す朝日の眩しさにカラスマルは円らな目を細める。
目の前には生い茂り、光沢のある葉。背後にはカラスマルが昏々と眠っていた、丸太で作られた小屋。小屋周辺は木が開けていて、晴れていればよく光が降り注ぐ位置らしい。
「ついてきて。君の生きる方法がある」
低く、ゆっくり飛んでいく鴉の後を従順にカラスマルは追っていった。草木を掻き分け、丈の短いブーツを履いた足で道ならぬ道を進んでいく。地面から迫り出している木の根は鴉が存在に気づくたび警告していったから、カラスマルは危なっかしく躓きつつも、なんとか転ばずに済んだ。
段々、鬱蒼としていく木立に光は遮られ、明るい緑はなくなっていく。暗い茂みからなにか恐ろしいものが飛び出してきそうで、鴉は神経を尖らせた。
無事にそんな不気味なところを抜けると、再び木が開けて光射す。光沢を帯びる葉と、木々に実っている艶々した真紅の玉。林檎をさげている枝に鴉がとまった。
「ひとつ、もいで食べてごらん」
頷いて、カラスマルは鴉の助云を受けながら枝に足をかけ、木を登って林檎を採った。齧ると、カラスマルの無表情が僅かに緩む。林檎についた小さな歯形から、たっぷり入っている蜜が覗いていた。
「自分で食べるのもいいけど、それを村っていう、人が沢山居るところで譲るとお金になる。お金は生きていくのに必要なんだ。前の少女もそうやって生きていた」
しゃくしゃく、と小気味よい音を立てて咀嚼し、飲み込んでからカラスマルは頷いた。初めての快楽に夢中になり、口元を果汁と細かく砕けた果肉で汚している。濡れた唇から、鴉は思わず目を逸らす。
「拭かなくちゃ、汚いよ。……村は明日行こう。今日は帰って、僕が今まで話したことをもう少し詳しく説明してあげる。あと生きるにはお金だけじゃなくて、自分のお手入れの仕方や料理や掃除、ほかも色々必要なんだ。それも全部教えてあげる」
それから小屋へ引き返し、生活がはじまった。
生きていれば汚れるし、お腹も空く。厨房に残っていた干し肉と固いパンを口にしながら、カラスマルは料理の仕方を聞いた。話しおえ、次は掃除について教えようとした鴉はある違和感を覚える。そして悲鳴をあげた。
カラスマルの股ぐらの辺り、黒いワンピースの黒が一部濃くなっている。とりあえず話すだけで鴉は教えるつもりであったが、掃除は本格的に実践させることとなった。
雑巾で床を拭かせ、ついで外へ出て、小屋のそばにあった井戸で身の清め方と洗濯をカラスマルは習った。
「ああ、あったあった。カラスマル、排泄は出来る限り、この中でするんだ」
小屋に戻り、小部屋で見つけた陶器のおまるを鴉は示す。カラスマルは裸のまま頷いた。衣類はワンピースと下着以外、見つからなかったのだ。
「……お金が手に入ったら、ほかに着るものも買わなくちゃね」
こうして一日はおわる。翌日乾いた服に身を包み、髪を二本の三つ編みにしたカラスマルが鴉を連れて小屋を出た。長い髪は綺麗だけれど、カラスマルがやや鬱陶しそうにしていたのを鴉が見かねて、革の紐を使わせて教えたのである。
バスケットを携えて林檎を沢山もぎにいったあと、林檎を採りにいく道に比べて、まだ歩きやすい獣道をカラスマルは進んだ。そのうち木立は途切れ、森を抜ける。申し訳ばかりに整えられた道を歩いていくと、まばらに人が、そして連なる建物が見えてきた。
赤煉瓦の建物が並ぶ通りへ入ると、カラスマルの少し前を飛んでいた鴉は緊張した。通り過ぎる人、壁に背を預けて地面に座り込んでいる人、みな澱んだ目をカラスマルへ向けてくる。それはみな、黒ずんだ男だった。凶暴な獣ですら目は澄んでいるものだ。
もしかしたら森の中よりも、この村の中のほうが危ないのかも知れない。そう鴉は危惧して、早く用を済ませようと急いでカラスマルを導いていった。カラスマルはどんなに厭らしい視線を貰っても、ついていこうと小走りになりつつぽかんとしている。
林檎を買ってくれるであろうビストロに着く。ドアを開けば、斑白の髪の女将が応対してくれる。化粧と皮脂が混ざったものを肌の皺の溝に溜めていた。
「ああ、林檎売りだね。商売、またはじまったんだねえ。買わせてもらうわよ、あんたの林檎は美味しいから。……ああ、もうあんたも無口だねえ」
女将の背後、水タバコを吸っている客の女二人の会話が響いてくる。無理やりコルセットで締めた、肥えた肉躰。支えがなければ垂れそうな乳房を半分以上、胸元を開いたドレスから覗かせていた。
「メメントモリのせいで商売あがったりよ」
「もう、子供でも作ろうかしら」
水タバコの煙を不自然なくらい真っ赤な口から立ち昇らせる。
ほかは民家などへ一通り林檎を売り廻ると、カラスマルは森の中の小屋へ帰ってきた。貰ったコインで得た野菜やソーセージやパンでサンドイッチを作って食べ、井戸の水を沸かして身を清め、買った下着と衣服を着て寝台へ入る。
白いネグリジェに身を包み、躰を丸めて眠っているカラスマルを鴉は目を細めて、眺めていた。
カラスマルは肥えることなく、唇の色が下品な赤に染まることもない。か弱く可憐な少女のままなのだ。僕が守ってあげなくちゃ。
頑張れば笑ってくれるかな……鴉はカラスマルの微笑を想像しながら眠りに落ちた。
しばらくするとカラスマルは鴉の助云がなくても問題なく過ごせるようになってくる。云われれば大概のことはこなせるカラスマルは器用だ。
慣れた手つきでハーブの茶を淹れて、朝食の支度をしているカラスマルを鴉は寂しそうに見ていた。
「カラスマル、今日も天気がいいね」
「……」
朝食をおえて、林檎をもぎに出かけるカラスマルに鴉は話しかける。カラスマルは頷くだけだ。
「ほら、茱萸の実がなっているよ。採っていこう」
「……」
鴉がその存在を教える一瞬前にカラスマルはチェリーに似た実へ向かい、バスケットの中へ熟した実を放っていた。
ここのところ鴉は、ある妄想に悩んでいる。
厨房で茱萸の実をジャムにしているカラスマルの後ろ姿を見ながら、鴉は余った茱萸の実を啄みつつ、また想像してしまう。膝丈のワンピースの裾から伸びているカラスマルの細く白い脛へ、じぃっと視線を注ぐ。
ワンピースの裾が鉤爪で破られた。脚に幾筋もの赤い線が走る。カラスマルが悲痛に満ちていながらも、耳障りなほどではない甲高さの可憐な悲鳴をあげる。鴉はカラスマルの悲鳴どころかまともに聲を聞いたことがないが、発達した小さな頭は可愛らしい聲色を想像した。
そのうち裾だけでなく、ワンピースはぼろぼろになってしまう。飽き足らず、もっと聲が聞きたいと露わになったすべらかな膚に鴉は傷をつける。……四肢と胸を連なる赤いビーズで飾り尽くし、ようやく鴉は満足した。カラスマルはぼろ切れを纏い、苦痛に鳴くのに疲れ果てて死骸のようにぐったりとしていた。
鴉の夢の中で、鉤爪で凌辱されているなどと露知らず、カラスマルは血のような鮮やかな真紅のジャムを黙々と煮ている。甘酸っぱい香りが満ちる。
カラスマルの血はきっとこんな匂いがすると妄想したところで鴉は現実に戻り、ひどい罪悪感に襲われた。
守ってあげなくちゃ、などと思いながら、卑しい獣慾を燻らせている矛盾。鉤爪ではカラスマルに傷をつけないように触れることは叶わないという悲しみと、いつまでたっても笑ってくれない苛立ちから、浮かべるようになったいっそ血塗れにしてやりたいという恐ろしい妄想。
いや、この守りたいという情ですら、実はただの独占慾なのではないか? 頭のいい哀れな鴉は悶える。恋というあまり綺麗ではない感情を引きずりながら、鴉はカラスマルの日常を見守った。
しかし、それはある日突然おわる。
いつもの朝。カラスマルは朝食を食べている。鴉は窓枠にとまり、カラスマルになにかを話しかけている。開けた窓からは、涼風が吹き込んでいた。
カラスマルが道を歩いているときくらいしか神経を尖らせてこなかった鴉は、野生の動物だとは思えない失敗をしてしまった。
小屋へ近寄ってくる黒い塊の存在に気づかず、そのまま窓から飛び込んでくる黒い塊に背後から襲われてしまったのである。
悲鳴をあげ、鴉は羽をばたつかせるが、しっかりと押さえつけられどうにもならない。黒い塊の爪が食い込み、苦痛に呻く。
「カラスマルッ……」
助けて! と鴉はつづけようとして、止めた。カラスマルはジャムを塗ったパンをただ口に運び、こちらを見てさえいない。
穏やかで楽しい日々ではあったが、決して笑ってくれないカラスマル。思い出が脳裏を廻りつつ、鴉は今更のように理解した。林檎売りとは残酷で、綺麗な生き物なのだ。情などという穢れやすい感情を抱くわけがない。
恋していたのに、生きる方法を教えてやったのに……そんな憎しみを覚える自分は穢いのだろうと鴉は諦めた。卵から産まれたくせに、腹から産まれる人間のように穢い。鴉の首に牙が刺さる。
黒い大柄な猫は食事をおえると、寝台にあがって鼾をかきはじめた。朝食を済ませ、茶も飲みおわったカラスマルは、汚れたら掃除しなければならないと、床に落ちている赤黒い残骸を片づけはじめた。
箒で塵取りに鴉の死骸を入れて、窓から投げ捨てる。
猫は鴉みたいに頭がよくない。喋ることができないので、カラスマルになんの助云も与えられない。カラスマルを守る気もない。それどころか勝手に小屋に住み着いた猫はたまにカラスマルを引っ掻き、食べ物を盗み食いした。
猫に引っ掻かれたとき、カラスマルは初めて痛みというものを覚えた。寝台の真ん中を陣取っていた猫が、寝台の中へ入ろうとしてきたカラスマルの頬を掻いたのだ。
カラスマルは僅かに無表情を顰めさせ、頬に感じる生温いものを手の甲で拭い、付着した血をなんとなく見つめた。
迷惑なだけの猫。しかし、助云役のいないカラスマルに猫を追い出したり、殺したりすればいいという発想はできない。
無表情の下、減っていくばかりの食料を食べられてしまうのには困っていたが、どうしようもない。
そう、カラスマルはこの頃、困っていた。
「いらないわよ、そんな不味い林檎。林檎売りだけが知っている、林檎を美味しくする特別な肥やしがあるんじゃなかったの?」
ビストロの女将がカラスマルを冷たく追い払う。膚寒くなってきたから頭巾のついた、袖のない外套を着たカラスマルは無表情のまま、肩を落とす。カラスマルは似たような外套を沢山持っていた。
村の中にいると止めてくれる鴉がいない為、カラスマルは色々な店に呼び込まれるがまま、勧められるがまま、物を買ってしまうのだった。似合っている、可愛らしい、と頻りにカラスマルをおだて、仕立て屋の小肥りな女将が押しつけてきた色取り取りのリボン、ワンピース、外套。
食べ物を扱っている店からは美味しいよと誘われるがまま、パン、ビスケット、チーズ、肉、野菜などを必要以上に買った。そして今、ビストロから踵を返す、懐の寂しいカラスマルに声をかけようとする店の主人はいない。ショコラやクッキーを並べている菓子屋の老主人が、通り過ぎていくカラスマルをちらりと冷ややかに見た。
点在している黒ずんだ男たちは相変わらずカラスマルへ厭らしい視線を送っている。……せかせかと歩いてカラスマルの横を過ぎていった厚化粧の婦人についていっている、薄汚れた子供が転んだ。
「なにチンタラしてるんだい! ああ、アンタは金にもならないし、トロいしイライラする!」
「ごめんなさい、ママ」
金切り聲をあげる婦人に子供は素直に謝る。が、婦人が背を向けると、子供は器量のよくない顔を更に歪めて、母親の背中を睨んだ。血の流れる脚で立ちあがり、自分を置いていきそうな母親を追いかけていく。カラスマルはそのやりとりをいっさい見ないまま、民家へ向かう。
一応、民家にも林檎を売ろうとしてみたが、バスケットの中の黄ばんだ林檎を買おうとする家主はいなかった。カラスマルが頭を横に振られてしまっている隣、異様に背は高いが線の細い人影がある。
隣の家、戸口に立っている婦人と綺麗なドレスを着た少女が嬉しそうに笑いながらその人影と話していた。つばの広い帽子を目深に被った人影は婦人へ金のコインを渡し、少女の手を蠟のように白い手で握る。
カラスマルがその様子のそばを通り過ぎていく。
――お金は生きていくのに必要なんだ。という、鴉の助云をカラスマルは思い出しながら森に戻り、獣道を歩いていた。なぜ産まれたら生きなければならないのか、理由はわからないがカラスマルはとりあえず亡き鴉の助云を守っている。
しかし、守るのは難しくなってきていた。バスケットの中の黄色い林檎を手に取り、齧ってみる。酸っぱくて眉間に皺を寄せる。カラスマルは林檎売りだが、ビストロの女将が云っていた、林檎を美味しくする特別な肥やしなど知らなかった。
果汁も余りない、ぱさついた果肉を咀嚼しつつ歩いているカラスマルに、音もなく、外套の長い裾と腰まで伸ばした巻き毛を揺らしながら近寄ってくる人影があった。突然、異様に背の高い人影はカラスマルをひょいと掻き抱く。
悲鳴はあげなかったが、カラスマルは齧っていた林檎を取り落とした。その人は美しい女のようにも、男のようにも見える顔をカラスマルのぽかんとした顔へ寄せる。帽子の広いつばが、カラスマルに影を落とす。
女なのか男なのかわからない人はカラスマルの薄い唇を塞ぎ、口の中の林檎を奪った。
「……なるほど、この味では買ってくれる人はいないだろうね」
聲も女なのか男なのかわからない。そっと、抱き抱えていたカラスマルをおろす。
「私はメメントモリ。ええっと、林檎売りさんに名前はあるのかな?」
めったに喋らないカラスマルが口を開く。カラスマルはメメントモリに自分の名をひどく抑揚のない調子で伝えた。
「カラスマル、林檎を美味しくする肥やしなら、私が知っている。教えてあげるから、林檎の木まで一緒に行こう」
カラスマルは頷いた。そのまま二人は獣道を進み、途中小屋でバスケットを置いてから、鬱蒼としている中へ入っていく。地面から木の根の迫り出している道ならぬ道を、メメントモリはカラスマルについていく風でもなく、肩を並べて歩いた。むしろ、カラスマルの歩幅に合わせている。
やがて、木が開ける。木々にはなんの世話をしなくてもずっと実っていたが、段々劣化していった林檎。
「なにもしなくても素晴らしい林檎を実らせるけれどね。でも実は、林檎売りがたまに与えてやらないといけないものがあるんだ。とりあえずそこの木に手をついて、後ろを向いて」
頷き、カラスマルは云われた通りにした。指示された木に掴まり、メメントモリに背中を向ける。外套がワンピースの裾とともに捲られ、膝窩から腿が冷たい外気にさらされた。
「かなり痛いけど我慢して」
「!」
聲はあげなかったが、躰に走った衝撃にカラスマルは円らな目を見開く。木を掴む指先に力がこもり、爪が白くなった。木の根元へ、血がぽたぽたと落ちる。
着衣を直してやって、こちらを向かせてから、メメントモリはカラスマルの下腹部の辺りを指差して云った。
「林檎はね、ここから流れ出る血で赤く染まるんだ」
「これから、私の店に遊びにきなさい」
血の伝う内腿をメメントモリにハンカチで拭われてから、カラスマルはひょいと横抱きにされた。
「大切なところを怪我したまま、歩くのはつらいだろう?」
そのまま、カラスマルは獣道の入り口まで運ばれる。黒い箱馬車が停まっていた。促されるがままカラスマルが馬車に乗り込むと、村でメメントモリに手を取られていた少女が座席に座っている。
「メメントモリさん、その可愛い子も僕と同じ売りもの?」
白金色の髪に淡いピンクのリボンを飾って、ドレスを身に纏った姫君のような少女。しかし、聲の聲色は少年のようだった。
「いいや、お茶しにくるだけだよ。この子は買いたくても、売ってくれる人がいない」
「なあんだ。なら、拾っちゃえばいいじゃない。元手がかからないから、いいんじゃないの」
「そんな、無知な子を。残酷だよ」
と、云いつつも、カラスマルが林檎売りではなく、人間から産まれた普通の娘であったならば、メメントモリは少年の云うようにしていた。箱馬車のドアを閉じて、メメントモリは御者台へ向かい、馬を操りはじめる。
「ねえ、メメントモリさんがどんなお店をやっているのかわかってる?」
揺れはじめる車内、少年は隣に座ったカラスマルに色々と話しかけてきた。カラスマルは頭を横に振る。
「美しい子供を売っているんだよ。ああ、これでやっとあんな萎びた女のもとから離れられる。もう、あの女は慰めなくてもいいんだ」
退屈になるのが厭なのか、返事がなくても少年は独善的に喋る。ドレスの胸元、優美なレースのひだが重なった部分に手を置いて、つづけた。
「まあ、こんな格好しなくちゃだけど……やることは別に今までとたいして変わらない」
おもむろに少年は備えつけのテーブルの上にあった革のケースを手に取り、開けた。中の紙巻きタバコを銜えると、燐寸で火を点ける。それは恐ろしく少年の身なりにそぐわなかったが、香りだけはバニラのようで甘美だ。
「一口、吸ってみる?」
少年は吸っていたタバコをカラスマルの口元に寄せた。少年の唾液で湿ったところを銜えて思いきり吸い込み、カラスマルは激しく噎せることとなった。吸い口のない両切りのものだったから、口の中に葉も入ってしまった。少年は様子を見てけらけら笑い、タバコを銜え直す。
「ごめんごめん……こんなの、吸えないほうがいいよ。メメントモリさん、はっきりと口にはしないけど、僕みたいな子供嫌いだと思う」
タバコが短くなると、少年はテーブルにある硝子の灰皿に潰した。そして唐突に、カラスマルの手を取り自らのスカートとパニエの中へ潜り込ませ、ドロワーズ越しにそこへ触らせる。
「僕はこんななりでもちゃんと男の子だけど、メメントモリさんは本当わからない。不思議な話、一回寝たことあるのにわからなかったんだよ。あの人、絶対人間じゃない。君もなんとなく、人間らしさを感じないけど。……ああ、気を悪くしないでね。君が可愛い女の子だっていうのはわかるよ。触っているもの、こんな感じでメメントモリさんのお店に着くまで弄っててよ。心地好いんだ」
村を過ぎて、森と呼ぶほどではない木立に囲われた、尖った屋根の小さな城のような可愛らしい建物の前に着く。木製の看板にはmaison memento moriと記してあった。
馬車からおりて、一同は店の中へ入っていく。薔薇柄の絨毯を敷いた上に白の猫脚のテーブルが並び、ところどころに陶器の天使やピンクの薔薇が飾ってある。何人かの子供がテーブルに着いていて、ビスチェとドロワーズのみを纏った少女が二人、水タバコを吸っていた。
曲線を描く水タバコのボトルには金の装飾がされており、煙は果物と花が混ざったような香りがする。が、煙が立ちのぼる様は頽廃的で、白とピンクを基調とした夢想的な内装に不釣り合いだった。
「お腹の中に誰か居るみたいなの」
「やぁだ、それさっさと処分したほうがいいわよ。子供がまっさきに殺意を抱くのって親よ。あたし、機会があったらママのこと殺そうと思ってるもの。殺されちゃうわよ!」
少年が階段に爪先の丸い靴を履いた足をかけつつ、メメントモリに振り向く。
「メメントモリさん、僕の部屋はどこ?」
「ああ、ドアの前に君の名前を記したプレートがあるよ」
「案内してくれないの?」
メメントモリが指を鳴らす。すると、姦しかった少女二人が水タバコを吸うのを止めて、席を立ち少年のもとへ向かう。少年はどこか意地の悪そうな笑みをメメントモリに向けてから、少女たちを伴って階段をのぼっていった。
メメントモリに促されるがままカラスマルは近くのテーブルに着く。メメントモリはその向かいに座り、また指を鳴らした。場にいた子供がやってきて、メメントモリと短く言葉を交わし、引っ込む。そしてすぐに、銀の盆を持って戻ってきた。
盆の上の、宝石のように艶々した果物が盛られたタルトと、ミルクティーがカラスマルの前に並べられる。
「メニューは適当に決めちゃったけど、お食べ。お代はいらないから」
代金の代わりなら、メメントモリは森の中で貰っている。
カラスマルは頷き、華奢なフォークでタルトを崩しはじめた。口に運び、無表情を僅かに綻ばせるカラスマルをメメントモリは微笑んで眺めた。
「普通、女の子は定期的に出血するようになるんだけどね。君はそれが永遠にないかもしれない。また林檎が劣化するから、私と逢おう。林檎の木へ、血を流させてあげる。……ああ、そうそう、食べおわったら早めに帰りなさい。日が落ちると、黒ずんだ醜い獣たちがここへやってくる。危険だ」
カラスマルは甘いミルクティーも口に含みつつ、こくこく頷いている。
それからカラスマルは、馬車では足場の悪い獣道まで再び揺られた。馬車からおりて歩いても、もう、股ぐらは痛まない。
林檎は真っ赤に染まった。
ビストロの女将はカラスマルにコインを一枚渡して、バスケットから艶めいた真紅の玉をひとつ手に取り、齧る。うっとりと目を細め、カラスマルへ更にコインを渡すと林檎を数個取った。
「あんた、昼食はもう食べたの? ……そう、なんならウチで食べていきなさい」
それから、カラスマルがほかも廻ればバスケットの中はすぐ空になる。村人たちはみな、林檎売りの真っ赤な林檎が好物なのだ。
「カラスマルちゃん、おいで。この間の林檎、アップルパイにしたから」
菓子屋の老主人が優しげな笑みを浮かべながら、カラスマルを手招きした。ほかの店の主人も負けじとカラスマルに声をかけはじめる。カラスマルは勧められるがままにコインを使い、林檎の売り上げはあっという間になくなってしまったが、とりあえず食料は買えた。
沢山の紙袋を持って、ふらふら歩くカラスマルに黒ずんだ男たちの一人がにわかに近寄る。三つ編みを揺らす後ろ姿へ手を伸ばす。通りがかる人も、そばの店の主人も見ないようにしていた。
「カラスマル、私と一緒にお茶しよう」
そのとき、どこからともなく現れたメメントモリがカラスマルの肩を抱いた。男が舌打ちする。
「メメントモリさん、その娘仕入れたら遊びいくからよ。ツケてくれや」
「夢の中で好きなだけ抱いてろ。身の程知らず」
澱んだ目が怒りで燃えるのをメメントモリが手で隠す。突然目隠しをされた男は怒鳴る前に倒れた。獣の唸り聲のような鼾をかいている。
メメントモリはそっとカラスマルに囁いた。
「気をつけて。君はなにをされても傷つかないし穢れないだろうけれど、殴られるかもしれないし首を絞められるかもしれないから。そうされたら普通に死んじゃうからね。君には出来る限り、そのままで長生きしてもらいたい。……人間は、醜いくせに綺麗なものを求めるんだ」
私と同じくね、とメメントモリは苦笑しながら付云する。カラスマルは適当に頷いていた。
「私は長生きしすぎたな。ああ、あと蓄えはしておいたほうがいいよ」
メメントモリがひょいと、細腕に抱えられていたパンのはみ出た大きな紙袋を持ってやる。そのまま二人は村を出て、停めてあった箱馬車に乗った。
「お茶の前に、林檎に血を与えてやりにいこう」
と、カラスマルに告げてから、メメントモリは御者台へ向かう。
獣道の前で馬車からおりて、二人は歩いた。メメントモリがそっとカラスマルの小さな手を大きめだけれど華奢な手で握る。
小屋に寄り、片腕で抱えていた紙袋をテーブルに置いたメメントモリの足元へ、寝台で寝ていた猫がやってきて擦り寄った。
「なんだい君は、誰も愛さなそうなのに私には媚びて……やはり私の正体がわかるのかい?」
もしも鴉が生きていたら、彼はメメントモリを恐れると同時に畏れ、慄いていただろう。黒猫か鴉なら、メメントモリがなんなのか本能で察せられる。メメントモリは細長い躰をしゃがませ、臆せず甘える猫の毛並みを愛でた。
「食料は……勝手に食べすぎないようにね」
カラスマルは相変わらず、様子に目を向けていない。
小屋を出ると、メメントモリはなにも云わずにカラスマルを横抱きし、林檎の木まで進んでいく。暗い緑の中へ入り、木の根を軽々と越えていく。木立が開け、光射す。やや冷たい風に揺れる煌めいて見える葉に、赤い林檎。
メメントモリはカラスマルを林檎の木の前におろし、木膚に手をつかせる。背中を向けたカラスマルの外套と中に着ているクリームのような黄白色のワンピースを捲った。カラスマルが眉間に皺を寄せる。血が垂れる。
その間、メメントモリは手でカラスマルの薄い胸や細い腿を愛でていた。ハア、とどこか艶めかしい溜め息を吐きながら、メメントモリは独り云つ。
「いいね、ちゃんと出血する。……ほかの林檎売りの少女は獣に殺されたり、うっかり毒草を食べてしまったりしていたのだけれど、君より前の前にいた少女はどういう訳か私を愛してしまって、それでダメになってしまったんだよ。林檎売りはそういう穢れやすい感情を抱かないんじゃなかったのかい? ああ、カラスマル、君は私を愛さないでね」
カラスマルの着衣を直してやる。血がワンピースに染みを作ってしまった。メメントモリはカラスマルにこちらを向かせて、その唇に目を閉じて愛おしげに口づける。
カラスマルはきょとんと目を開いたままだ。メメントモリはこの、少女どころか少女にすら足りていないような林檎売りしか好きになれない。
唇が離れると、カラスマルはメメントモリをよそに、ほかの林檎の木にも血を与えようと外套とワンピースの裾を両手でつまみあげ、木々を廻りはじめた。歩くたび走る痛みに、僅かに顔を顰めている。
スカートの裾をつまんで行う貴婦人の挨拶、カーテシーに似た姿勢のおかげか可愛らしく見える光景をぼんやり眺めながら、メメントモリは独り云ちた。
「memento mori……林檎売りを慾するだなんて我ながら最高の皮肉だ」
ぽた、ぽたと純粋無垢の血が、木の根元に吸われていった。
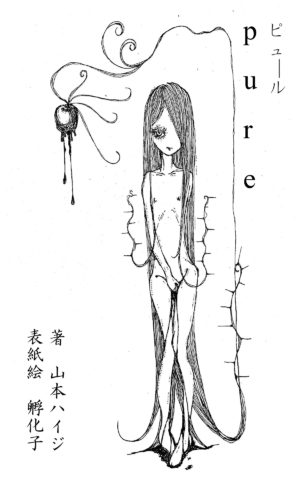









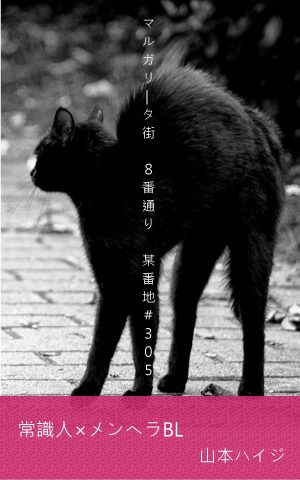











"カラスマル"へのコメント 0件