化粧を済ませ、頭にネットをかぶったまま一服。久々にめかしこむ、わずかな緊張感を煙を吸って、吐いて癒す。私のそんな姿を見た家族から「オカマみたい」と笑われたが、別にイラッともしない。
短くなったキャスターを灰皿に潰し、台所の換気扇をとめてから、身支度の続きをしようと自室へ戻る。部屋着であるロンTとスウェットパンツを脱ぎ、クローゼットを開けた。姫袖のブラウスを着て、ペチコートパンツを穿いてから、BPNのワンピースを着る。パニエを仕込む。
なんとなく気力が足りず、カジュアルめにしようとブラウスのボタンを二つ外し、開けた首元を革のチョーカーとキリストが磔刑にされている十字架のついたネックレスで飾る。ヘッドドレスをしないかわり、黒と白のツートンカラーが目立つおかっぱボブのウィッグをかぶった。
オカマみたい、などと言われたが化粧だってこれでも薄めだ。まつげが邪魔をしないから、いつもならするコンタクトをせず、黒ぶちのメガネをかける。このコーディネートなら変にならず、アクセサリーのような機能をしてくれるだろう。そろそろ私には若すぎるかと思いつつ、今は無きBPNはラインがスタイリッシュで重厚さがないから崩しやすい。ガチになるのはモワティエかアウアア。
ガチ……ふと、某アーティストが述べていた理想論を思い出す。十八世紀ゴシック趣味、耽美、退廃、薔薇や血や闇や人形を愛し、澁澤龍彦の本を忍ばせたJ・P・ゴルチエのバッグを持ち、付き合う少年はヴィヴィアンを纏った美少年がいいと。どれも好きだけど十八世紀ゴシック趣味なんて詳しくないし、そこまで意識高くはなれそうにない。ヴィヴィアンの美少年とか一度お目にかかってみたいものだが、大好きな恋人はそんなそばにいてリラックスできそうにない、実在の疑わしい煌びやかな存在ではない。
ただのエナメルのハート形のバッグにスマートフォンと財布とタバコ、その他諸々を突っ込む。玄関へ向かい、ストラップシューズを履いて外に出て、工事のおじさんを横目に住宅が並ぶ通りを歩く。駅に着き、電車を待つ。できるかぎり視線を下か斜めに遣って、ちらちら向けられる人の目を気にしないようにした。
カジュアルめと言えど、あくまで私の中ではだ。スレた純文学のような現代日本の社会じゃ私の姿は浮いているということは理解している。やってきた電車に乗り込み、くたびれた人たちが座っている前に立ち、吊り革を掴む。端から見たら相当シュールな光景だろうな。
十代の頃はこの外界との対比に気まずさなどたいして覚えず、むしろ自己陶酔できたが……アレだな、大人になってしまった。夢想を現実にコミットさせるなんて滑稽だと、ぼんやりわかりつつある。しかしやめようと思わないのは、やはり好きだから。それに尽きる。どんなにツッコミどころ満載な夢想であろうと。
この装いは現実に対する戦闘服だと、同好の士はうまい形容をしたものだ。しかし、夢想か……我々ほど壮絶ではなく、方向違えども派手派手なギャルや森ガールなどとも通底しているんだろうな、別に。これ意識高い同好の士に言ったらキレられそうだが。などと思考していると、目的地に着いた。
ビルが乱立している街中を彷徨う。やばい、迷った。勇気を出して、居酒屋の前を掃除している店員に話しかけてみる。その兄ちゃんは私の姿に引いた様子もなく、丁寧に小さなライブハウスへの道順を教えてくれた。わりと親切だ、現実。
教えてもらった場末の通りに入る。目当てのライブハウス名が記載された看板を見つけた。マイナーなバンドのライブのせいか、人だかりはできていない。スムーズに受付に電子チケットを表示させたスマートフォンを見せ、地下のライブハウスへ潜る。
女性、男性、外国人、おじさん。毎度、客たちを見回すとなんだか不思議な気持ちになる。案外、この夢想を抱えている層は広いのだ。普段着の客もいるが、こんなバンドのライブを観にきているのだから嫌いだなんてことはないだろう。
バーでカクテルを一杯頼んで、灰皿の近くに立つ。大きめな十字架のついたピアスをした、シルクハットをかぶったスーツ姿のおじさんが斜め前にいる。前のほうにはバンドのボーカリストを意識しているのであろう、薔薇をつけたヴェールを頭に飾ったややふくよかな女性が二人。
横には黒いドレスを着た、ゆるく巻いた長い金糸の髪をもつ白人女性。やべえ、エルフだ。さすが本場。タバコを吸いつつカクテルを飲みつつ、視線を泳がせているうちに照明が暗くなる。
ステージが照らされる。現れた姿に歓声。打ち込みによる妖しげな曲に闇の貴公子のようなギタリストのギターが乗り、ドラァグクイーンがマイクを握る。
薔薇が咲いた漆黒のヴェールをひらひらさせながら、コルセットを締めたしなやかな体から地を這うような低い声を発し、アリス、蜘蛛、両性具有、仮面をモチーフにした歌をドラァグクイーンは歌った。ボーカリストとギタリストの背後ではボンデージのダンサーが二人、舞い狂い、絡み合う。
客たちはリズムに乗って左右に揺れる。黒を纏っている客の黒もひらひらする。私も揺れる。数時間で、夢想は散る。
すぐにライブハウスを出ることはせず、私はタバコを吸いつつなんとなく物販のほうを眺めていた。ドラァグクイーンが黒く塗った艶やかな唇を微笑の形にして客と話している。地毛らしい、前髪をぱっつんに揃えたロングヘアー。羽根のようなまつげ。レースのタイツとエナメルのTバックを穿いた下半身は、中年の男性のものだとは思えないほど色気に溢れている。人工的であろうが美しいものは美しいのだから、それでいい。
そういえば、この夢想を広めたアーティストって男性なんだよな。それもまた不思議な気持ちになる。その方も中年のはずなのだが未だに黒や青のドレスを着て、お人形さんのように綺麗だ。その事実は私に夢想を纏い続ける勇気を与えていた。
タバコを灰皿に潰す。物販に並んでいるCDはすでにAmazonで手に入れている。重い扉へ向かい、狭い階段をのぼってライブハウスを出た。
くたびれた人たちでいっぱいの電車の中でまた浮きつつ帰宅して、夢想を脱いだら、台所の換気扇回してキャスター吸いたい。







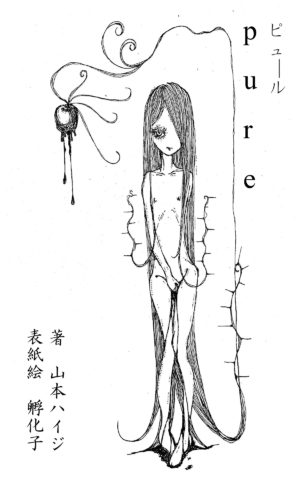
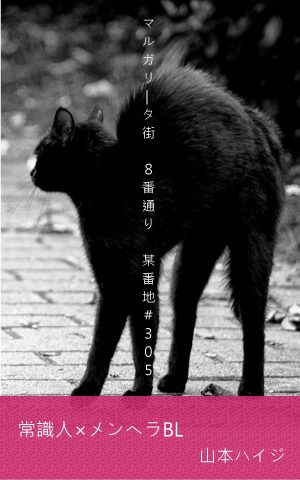










"夢想を纏う"へのコメント 0件