美濃部は何度も便所へ行っては吐いたり下したりしつつしゃべりまくった。伊知郎は美濃部の話を聞きながら、酒のせいでか話の内容のせいでか、頬の蟻がどんどん湧いた。酒のために足音のしなくなった蟻は、静かになった代わりに後頭部まで足をのばして歩き回るらしかった。
「ともあれな、『国家半壊』がじつはほんの地方というか辺境・秘境だけのことであったとしてもだ、あの多大なエナジーの確かに吹き荒れて確かに消滅した今、目下現実的な問題はだよ、本郷、お前の病気も然り、つまり虫害(神経症)は昔からあったけれども、蔓延の程度と、その公的な浸透の程度を考えれば、極めて現代的な流行だ。その虫害だけが残ったということさ。
どこかの秘境の、超生物学的な、なにか神話的な人たちが、男女一組で人間の卵の孵化する瞬間を見る……そうそう刷込み。そこの人たちは生殖能力がなくて、男女は夫婦にならずに家長と乳母になり、家長と乳母になったところへばかりひんぱんにまた卵が集まるってな。
この神話的な秘境に住んでる人たちは、みんながみんなすごく頭脳明晰で、眉目秀麗だったとか。見た奴なんかいないがね。
秘境っていえば、じつはこっちのほうが例外的な秘境だったりしてな? おお怖い。……よう、俺はちゃんと話せてるか? なんだか言葉が頭の中で先にできちゃって、しゃべるころにはもう――そうだ、映画の話なんだ。いや違う、現代的な虫害の話だったな。
ともかく本郷は、当事者でもなんでもないのに時代の流れ弾を食っちゃったんだ。でもそんなもん正常なこったよ。蟻なんかに悩まないのが一番さ。どう悩んだところで、悩み切ることなんか土台できないんだからね。
すべてはな本郷、もとをただせば、イデオロギッシュなUnknownが自己を識別できなくなったことや、古来変わらぬ手段の行使が過去からの延長でなくなったことのためなんだ。わかるか?
――わからんだろう。俺もさ。しかしな、これはわかってるよりましなんだ。間違ってわかってるよりな。けれどもやっぱり、わからないのもけっきょくは困ったもんさ……」
美濃部は粘土のような顔色をしてしゃべりまくった。
「硝煙が吹き流されて新鮮な泰平が訪れた。だのに虫害の蔓延だ。本来ならば、それは鏡のように凪いでいて、そのじつ腐った水に泳ぐミジンコたちに多い病気だったんだ。ところがそれが大難を経て、清々と澄み渡ったこの現代の清水に、じっさい蔓延している。
これはじつは、澄んだのではなく、ただ沈むものが沈んで、上澄みができただけなのかもしれないな。……そうだ、台風一過と思われているけれども、じっさいには沈みそんじた人々が置き去りにされて、虚空にいるから澄んで見えるんだ。澄んでると思い込んでるんだ。そして沈んだ底では、つまり本物の世界では、我々とのあいだにもう青空や星空まで境に立ててしまっていてな。我々を天上の人々に変えちまってさ――けれどもけっきょく、この上澄みはただの油なのかもしれないよ。清水を覆っている油なのかもしれんよ……」
ちょっと失敬と言って便所に行き、帰って来て美濃部は伊知郎に虫害の自覚症状を尋ねた。伊知郎がくわしく伝えると、ふむふむとうなずき、
「便所で考えていたんだけども、上澄みと虫害をテーマに、ひとつ短編小説を書いてだね、雑誌に送ってみるよ。いい雑誌があるんだ。ここに載りゃァもう、棺桶に入れてくれよ」
「何度もそう言ってるけど、ぜんぜん書かないじゃないか」
「そうだっけ? ……おい、そういうことは思っても言っちゃいけないよ。それが社会人の分別ってもんだぜ。わかった? 反省しなさい。――すみません、お勘定」
伊知郎が雑踏の中を歩いている。外部の様相とそれに対する感覚とがいちじるしくかけ離れている。この自覚症状が正しければ絶望的な大病だ。生きているのは間違いで、いや本当はもう死んでいて、でたらめな余命が続いているかのような。一切が嘘の世界のようだ。
今にも死にそうだった。いつ死んでもおかしくなかった。けれども、この直感が正しければ、もういく度も死んでいるから、結論として、このたびも大丈夫なのだと慰めながら歩いている。
頬から蟻がほろほろとこぼれ落ちる。これに少し安心している。夢幻的な自覚症状がにぎやかになるのに反比例して体の物質的な不調――不整脈、呼吸困難、めまい等々――は弱まるので。
幻の黄泉に片足を踏み入れているだけだ、幻の棘が眉間に刺さっているだけだ、このまま一般的な寿命を全うするまで生きられるし、寿命が来ればこれと関係なく死ぬ。昔からたくさんいたのだ、どんなにおかしなことになろうと、生き間違うということはなく、死に間違うということもないのだと慰めながら歩いている。
明らかに襲い来る苦しさも、健常者には見えない頬の蟻も、地上的には嘘だ。だから気にするこたァない。もしこれが嘘でないならば、そんな世界に未練はない。すなわちどう転んでも大丈夫だ。大丈夫でなければどうにでもなれ。この症状で死ぬならば殺せと慰めながら歩いている。
出社すると、外見的には美濃部のほうがむしろ体調が悪そうであった。美濃部は伊知郎に気づくと、不定期に寄稿している雑誌を丸めて望遠鏡のように覗きつつ、
「本郷お早う。次回はノンポリ・ナンセンスにするよ。真面目なことを書くにはおつむがパワー不足だ。俺の思考にはパッキンがないからじゃあじゃあ漏れなんだ。なにが漏れているのかは、漏れている本人には永久にわからないようなものが。それにだな、真面目な頭脳労働っちゅうものはだね、一たび足を突っ込んだが最後、果てしなく闘い続けなければならんし、時には面の皮を厚くせにゃならんし、若い女の子には嫌われるし、友だちも減ら。だからこういうのどうだろうね、なにか重大なことをさ、普遍的なメタファー的なことを、ただ無意味に書き綴る、収拾しない、いわゆるすかしだな。これからはすかしで行くよ。
――……しかし本郷ね、本物のノンポリをやるには、むしろ莫大に政治的なことや宗教的なことや哲学的なことを凝視せねばならないんじゃないか? 違うかね? その上でようやくのこと、いやしくも物を書く以上はいかなるイデオロギーからも自由であるべしというイデオロギーをかたじけなくしてだ、書く物の背骨なるものは意図するべからずという意図のもとに臨まねばなるまいよ。
斯くていよいよ有機的に、総合的になって参りまして、そやつら――すなわち網羅的になぞった真面目なことども――を空気中に散りばめてさ、一発残らず外して行く詭弁のマシンガンをぶっ放したいね。こう、裁判みたいなものでな、ふさわしくなくとも、とにかく言いまくって、たとい記録は削除され、発言をぜんぶ撤回しても聴衆に少なからぬ印象だけは植えつけ終えているわけだ。
しかも話しているあいだは陪審員どもを夢中にさせられる。これは愉快だよ本郷。いいやこれだけが目的なのさ。これが思う存分できるなら死刑にされても構わない。地獄にだって行っていいよ。嗚呼……そんなことが本当に、満足にできるならね。
――こんなことくっちゃべっているのも、そもそも俺という人間が徹頭徹尾ロジカルだからなんだなァ。理系なんだしょせんは。それか、血圧の問題だ。血圧が高いと思想家になるからな。いや小便の問題かな。近ごろ腎臓の濾過機能がどうもね。――ああ昼飯(の注文)かい。君は? 生姜焼き弁当……かゑる庵だろ? それじゃ俺は幕の内」
無職の伊知郎が歩いている。世界はぼんやりして、重力もなければ酸素もない。音も温度もない。過去も未来もない。無いということもないので、伊知郎は歩いているのであった。
伊知郎の歩く大地はぐにゃぐにゃしていた。けれどもはたから見ればたいそうシッカリ歩いていた。
私を裁いているのは誰。と考えていることに伊知郎はぼんやり気づく。答えていわく、裁いているのは深層の自我や、私の中の社会我。しかし社会我自身、心に疚しさがなければ、これほど罪人をいじめないのではあるまいか? ――生贄だ。まあ仕方がない。
私を裁いているのは神仏の概念や、幼少期の躾やトラウマや、誰か負け犬からの呪詛や、そして誰も裁いてなぞいない事実へのボンヤリとした不満だ。まあ仕方がない……。
伊知郎の頬には蟻が這っていた。通り過ぎる人々はそれに気づかなかった。ふと、向こうから歩いて来る婦人の頬には蚊がたくさんとまっていた。同病者につきお互いの虫が見えた。婦人はすれ違う時、伊知郎の蟻をちらりと見て行った。伊知郎のほうはそれがマナーだと思うから、婦人の蚊を見ないように努めて通り過ぎた。
虫害科の先生はいつもと同じことを言った。なるべく疲れないようにすること。ストレスを溜めないようにすること。あまり虫のことを気にし過ぎないようにすること。
先生も頬に明らかな虫の巣があった。けれども薬で眠らせてあるのだとか。伊知郎も薬を処方してもらっていたけれど、なんとなく飲んでいなかった。それは虫害患者にはわりに多い特徴でもあるそうな。あたかも喪に服しているかのごとく回復を拒む。楽しみや喜びを避ける。
ああ前からまた一人、同じ病の人が来る。スーツを着た女の人だ。凛とした美しい顔立ちをして、その歩き姿はいかにもハキハキしている。彼女の頬には……カブトムシがついている!
伊知郎はとっさに道を折れた。自分よりもっとはなはだしい自覚症状に襲われているのに、あの人は快活に勤労し、立派に生活しているのだ。比較してしまう。自分の情けない事実を突きつけられるのはつらい……。
伊知郎の頬の蟻はうじゃうじゃと湧いた。
ビル風が吹いている。いわく、
――空間も時間もなく、存在も不在もなく、観念の対象にもならず、表現の矛盾にも破綻にもならない世界の絵を描く時に、一番多く使う色は?……
――私のなぞなぞに答えられる人物とは誰か?……
叔父の家は都市から遠く離れた山村にあった。父の弟の叔父だった。叔父には蟻は見えなかったけれど、都市に蔓延る虫害には同情しているそうだった。
部屋へ案内してくれた際、肩をぽんとたたいて、しばらくのんびりするといいと言ってくれた。
荷物を置き、畳の上にあぐらをかいて、伊知郎は物思いした。もうすぐ美濃部が結婚するから、式には行けないけれども、祝儀を送らなければならぬ……。
このような避けられない手続きがこの先無数に待機しているのだと考えた。完全な不意討ちならまだしもマシだが、予約して来たり、折に触れて予約を匂わせて来るのだ、じっさいにはけっきょく持ち上がらないことまで含めて膨大に。いちいち耳を貸していたら不必要に消耗するだけだが、無視しても「保留されている問題」の累積が換気口を塞ぎ、排水口を詰まらせる。そしてくたくたのところに不意討ちもまた持ち上がって来る。とても乗り越えられないような重量のものでも、平気で。
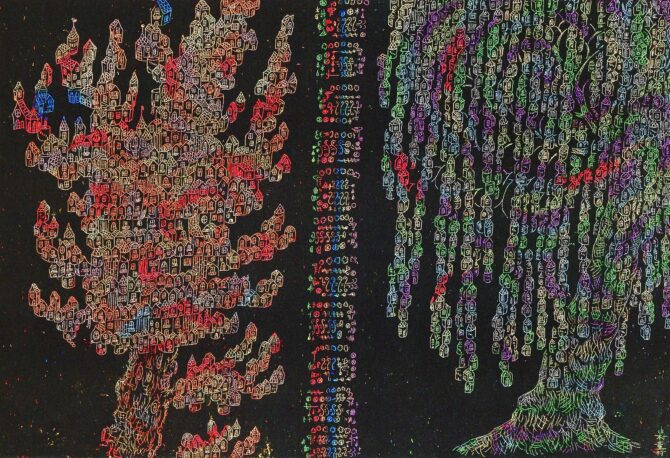
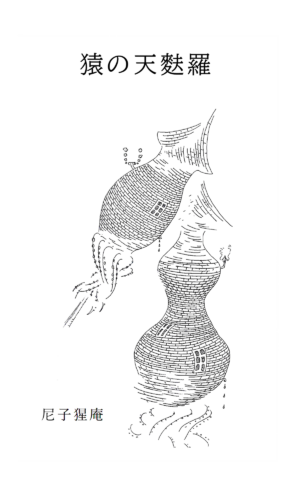











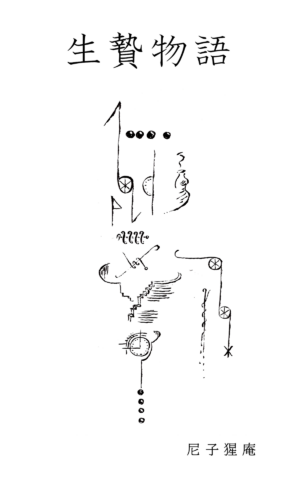










"猿の天麩羅 12"へのコメント 0件