円形に並んだ柱の中心にライトアップされた石碑が鎮座している。幅五○センチ高さ一メートルほどある石碑の中央には『日本中央』と削り書きされていた。髙井はより近くで石碑を見るために石碑を囲った柱の中に入ろうとしたところで後ろから声を掛けられた。
「お兄さん、この石碑が何か知っているか?」
髙井が振り返ると、そこには真っ白なひげを蓄えた老人が立っていた。老人の顔は眉弓が張り出し眼窩が落ちくぼんでいる。日本人には珍しい顔立ちだ。
「初代征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷を討伐したときに、大和政権に恭順しない周辺豪族に対して大和政権の威厳を示すために建てた石碑だと聞いています。藤原顕昭が編纂した『袖中抄』に記述がある『つぼのいしぶみ』がこの石碑だと」
老人は「ふん」鼻から息を漏らす。
「世間一般にはそう言われているな。坂上田村麻呂が出兵する一世紀前に崇峻天皇が近江臣満や阿倍臣を東北地方に派遣しヤマトに恭順しない豪族を調べさせた。そして桓武天皇の治世に坂上田村麻呂が東北地方に侵攻し東北地方がヤマトに組み入れた。崇峻天皇は傀儡として立てられた天皇であり、自ら政務を指揮することに不満を覚えた臣下、蘇我馬子よって殺されるが、その崇峻天皇が行った東北調査の記録は坂上田村麻呂の東北侵攻に大いに役立ったと言われている」
「ええ、その戦いで蝦夷の棟梁であった阿弖流為と母禮が捕らえられたと聞いています」
大学で日本古代史を学んでいた髙井は、この老人と話すことに興味を覚えた。
「坂上田村麻呂との戦いに敗れた阿弖流為と母禮は臣下や臣民その家族を守るために降伏し京に送られた。しかしヤマトは阿弖流為と母禮を斬首するだけではなく、捕虜になる前に交わしたこの地の豪族を国造とするといった約束を反故にし、国造はヤマトの人間が担うことになり、この地に住まう人間はヤマトに恭順していた国に送られた。それは俘囚と呼ばれ、川の近くに作られた集落で汚れ仕事に付かされた。いまだこの国に残る被差別部落の誕生だ」
「それは一つの説であって、俘囚と被差別部落民を結びつけるのは早計ではないでしょうか? 部落差別が生まれたのはもっと後の時代ともいわれています。古代朝鮮半島の騒乱によって日本に逃げてきた人々や豊臣秀吉の朝鮮出兵に連れてこられた捕虜が住まわされた場所に充てる説もあります。それに現在朝鮮部落と言われている場所の形成は近代ですよね?」
「君の言う通り朝鮮部落の形成は明々白々だ。だが、今は朝鮮部落の話をしているわけではない。朝鮮部落も謂われない差別を受けてきたことは同じだが、朝鮮部落と穢多と呼ばれ差別されてきた被差別部落を一緒に考えてはいけない。朝鮮部落民のアイデンティティは北朝鮮や韓国に見つけることが出来る。彼らにはそれが明確にあるんだ。だが穢多と呼ばれた被差別部落民は昔から日本人であるのになぜ差別される側にいるのか理解することが出来ない」
髙井は被差別部落の成り立ちを語る老人の顔をしげしげと見つめる。その堀の深い顔にはっとして老人に問う。
「もしかして、あなたはアイヌの方ですか?」
老人は髙井の質問には答えず逆に髙井に質問した。
「君はこの国の成り立ちをご存じかね?」
「大学で学んでいるのでおおよそのことは知っています。三世紀ごろに各地の豪族を束ねた中央政権が興り、天皇を中心とした大和政権が現代まで続いていると理解しています」
「それは倭と言われていた国ではないのかね?」
「後漢、ええと、ここでいう後漢とは光武帝によって興った後漢の事ですが、後漢書に倭が登場することから一世紀までに中国王朝に下賜された倭という字を長らく受け入れていたようです。ですが八世紀初頭に倭という字が蔑称であるとして、国内でも対外的にも倭から和、大和、日本と改めました。それらは当時ヤマトと読まれていたようです」
老人は髙井の目をじっと見つめる。そして白い顎ひげが下がった。
「あなたは優秀な学生のようだ。しかし、私は日本の成立について聞いているんだが」
「大和政権の成立を決定づける確たる証拠は未だ見つかっていません。邪馬台国が大和政権に繋がっていたとしても、邪馬台国のあった場所は未だ意見が分かれるところです。当時の日本は文字がありませんでしたから、魏から下賜された親魏倭王と記された金印が発掘されない限りは分からないでしょう。その金印も本来であれば印綬された者が死去すると送り返さなければならないものなので既に国内にはないかもしれません。しかし大和政権が西日本で興ったことには間違いありません。古墳が西日本に集中していることからもそれは明らかです」
「私はヤマトが西日本で興ったことに疑問を投げかけているのではない。私が言っているのはヤマトと日本が同じ国であったのかということだ」
髙井は老人の真意を測りかね聞き返す。
「すみません、おっしゃっている意味が分からないのですが」
老人は「ふう」と鼻から息を吐き出してから口を動かす。
「唐書をご存じか?」
「実際に読んだことはありませんが、名前は知っています。編纂された時代に中国は混乱期にあったため、後晋が編纂した後、北宋が後晋の旧唐書を再編纂して新唐書が作られたと聞いています」
「では、旧唐書及び新唐書の東夷伝の中に倭国伝と日本伝が分かれて記述されているのは知っておるか?」
「いえ、知りません」
「日本古代史を勉強していても他国の文献には興味がないのだな。倭国伝には倭国は昔の倭奴国であったと記されている。つまり江戸時代に志賀島で見つかった金印に記されていた倭奴国のことだな。後漢の時代、紀元一世紀ごろに北九州に倭奴国があり、倭奴国王帥升が後漢に朝貢し金印紫綬を下賜された。後漢書の記述とも整合性がとれるため、そのころ北九州一帯に大きな国があったことは間違いないだろう。問題は日本伝の方だ」
老人の話に好奇心をくすぐられ髙井は食い気味に質問する。
「日本伝には何と記述されているのですか?」
「日本伝の最初に日本と倭国は別種であると書かれている。そして日本は倭国より東に位置し、日の昇る地であるため自ら日本と呼称していると」
「当時の中国は戦乱の混乱期だったため、倭国の状況を正確に判断することが出来ずに倭国と日本が別の国だと誤解したのではないでしょうか?」
「確かに当時の中国は混乱期にあった、しかし後晋で書かれたものを再編集した新唐書東夷伝でもこの記述は残ったままだ。当時の中国で倭国と日本を別の国と考えていたのは間違いないだろう。また、日本伝の中に日本は昔小国であったが、倭国を取り込み、合わせて日本としたとも書かれておる」
「それをあなたはどう解釈されてるのでしょうか?」
「東方にあった日本という国がヤマトを征服し併合したということだよ。日本伝の中に日本は度々唐に朝貢しに来ていたが、使者が伝える事柄には偽りが多く、唐の皇帝はこれを信用していなかったと書かれている。ヤマトは当時遣唐使を送っていた。その最中にヤマトは日本に征服されたのだ。それを日本が引き継いだ。だから唐の皇帝はヤマトから聞かされていた国内事情と日本が伝える事柄に矛盾が生じるため、使者の話を信じなかったというわけだ」
老人の話をにわかに信じることはできない。唐書は大学の資料室に置いてあるだろうが、今調べることはできない。髙井が言葉を返せないでいると老人は「反論が無ければ話を続けるがいいかね?」と聞いてきた。髙井はゆっくりと首を縦に動かす。
「ここで問題になるのが、日本がどこにあったかということだが、君はどこだと思う?」
「いえ、見当もつきません」
すると老人は髙井から視線を外し、髙井の後ろを見つめ「そこだよ」と言った。老人の視線を頼りに髙井が振り返るとライトアップされた一枚岩に「日本中央」と殴り書きされた石碑がある。髙井は「あっ」と小さな声を上げて老人に向き直った。
「まさか、この石碑が?」
「そのまさかだ。この場所こそが日本だったのだ。そこに書かれている通りここが日本の中心だったのだよ。そこにあるのは坂上田村麻呂が建てた『つぼのいしぶみ』などではない。日本の王、津軽王が建てた石碑なんだ。考えてもみなさい、ヤマトの将軍が青森に『日本中央』などと書いた石碑を建てるかね?」
「いえ、それは私も不思議に思っていました」
老人は頷き話を続ける。
「日本は坂上田村麻呂との戦いに敗れた。君は坂上田村麻呂と戦ったのは蝦夷と言ったが、蝦夷はヤマトが日本に使う蔑称であって、坂上田村麻呂と戦ったのは日本だ。その戦いに敗れた将軍、阿弖流為と母禮は捕らえられ臣下とその家族は俘囚としてヤマト各国に住まわされた。そして阿弖流為がヤマトと交わした約束が反故にされ、ヤマトの人間が国造としてこの地にやってきた。日本はおとなしくヤマトに恭順したと思うかね?」
「いえ、約束が守られないのであれば、その地に残った有力者はヤマトが派遣した国造を捕らえ、ヤマトと交渉するなり反撃するなりするでしょう」
「そうだ。日本はヤマトからやって来た国造を殺し、津軽王はその石碑の前で『憎きヤマトを打倒せよ!』と高らかに宣言し反撃の狼煙を上げた。日本はこの地をヤマトから取り戻したあと、ヤマトに恭順しない東北地方の豪族を取り込み、俘囚を開放しながら南に西へと進軍した。関東以北に被差別部落が少ないのはそういうわけだ。そしてついにはヤマトを征服するに至った」
「それでは被差別部落の成り立ちが俘囚にあったことにはならないのではないでしょうか? 日本は俘囚地を開放したんですよね?」
「日本は同胞を開放していったが、すべての地域を開放するまでには至らなかった。ヤマトは征服される前に日本の進軍に合わせて俘囚が決起するのを恐れ、俘囚地を記録した書物を全て焼いたからだ。解放されずに残った現在の被差別部落の人間は本当の意味での日本人なのだよ」
たとえ唐書に書かれた日本と倭が別の国であったとしても、それは大和政権内での話だろう。さすがに津軽が大和政権を征服した話には無理がある。髙井は老人に反論しようと思ったが、津軽日本説を熱く語る老人の右手に『東日流外三郡誌』が握られているのを見て反論することを諦め、どうやってこの場から立ち去るか考えることにした。
――了










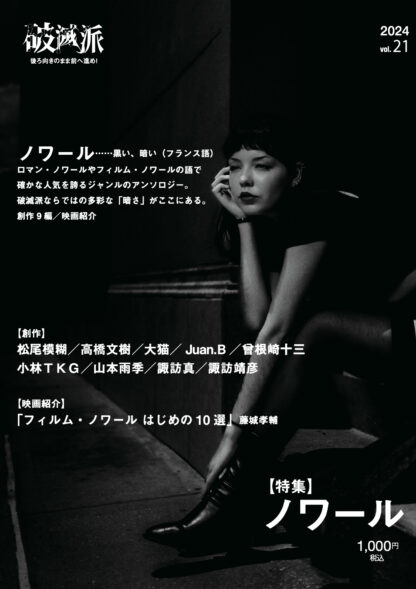
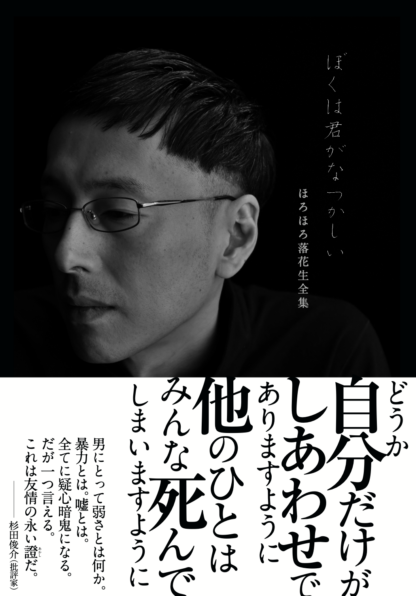
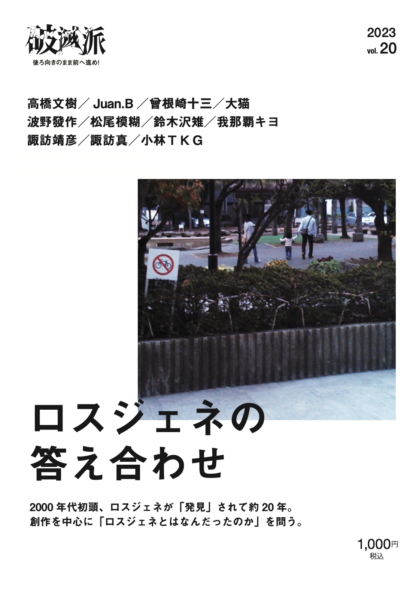
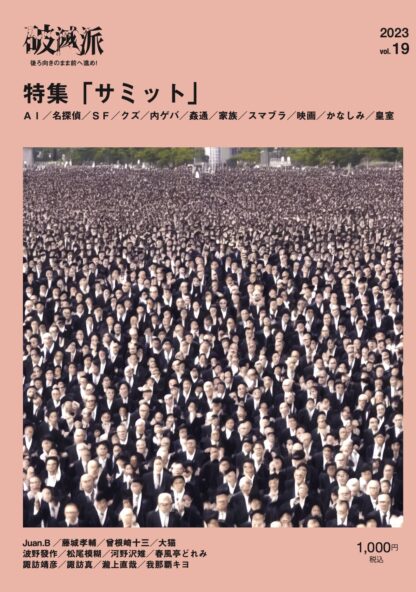
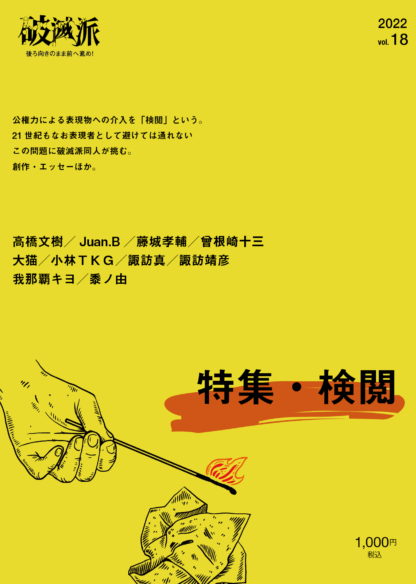
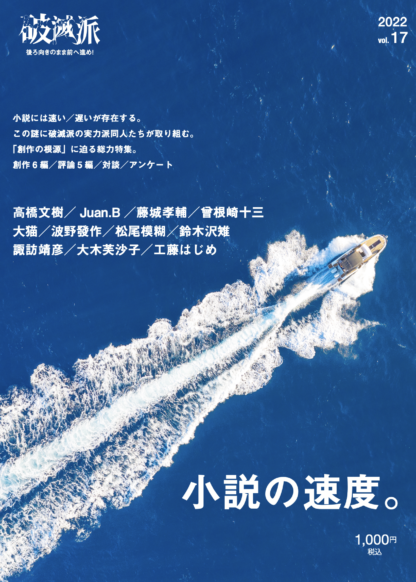












眞山大知 投稿者 | 2024-05-24 12:41
青森には釈迦の墓もキリストの墓も日本中央もある……。なんともファンタジーな県です。
曾根崎十三 投稿者 | 2024-05-24 22:25
最初、主人公をホアンさんだと思って読んでました。そういうネタじゃなかった……!
東日流外三郡誌、気になって調べました。トンデモ本なんですね。それにしても、こういうトーンの話を書けた試しがないので憧れです。教養……!
Wikipediaに紙を古紙に誤魔化すために長期間保管した尿を使っていた、みたいなのが載っていて、ぐっときました。
ただ、世界の中心ではなく日本の中心なのでは……? でも当時からすれば日本の中心は世界の中心なんでしょうか。
今野和人 投稿者 | 2024-05-25 09:53
日本古代史の知識が欠如しているため、へーとかほーとかしか言えないのですが、老人は偽史を語る人特有の謎の自信に満ちていて魅力的でした。
大猫 投稿者 | 2024-05-25 15:14
実は神武天皇は阿弖流為のことなのですね!
おじいさんは何十年もこうやって『日本中央』の傍らに立って、正しい歴史を人々に説いていたのですね。いやいや、今「偽書」呼ばわりされていても後世に覆らないとも限りません。おじいさんのよどみない熱弁が真実を語っているのです。ここに高井さんが訪れたのも何かの縁。二人で力を併せて歴史を塗り替えてください。
春風亭どれみ 投稿者 | 2024-05-26 22:40
思わず、「なっ、なんだってー!?」といいたくなりました(笑)
風呂敷の広げ方がロマン溢れていいと思います。
河野沢雉 投稿者 | 2024-05-27 16:24
日本という国名ほど由来の曖昧な国名はあまりないですよね。
偽書って今で言えばSNSで拡散されるデマみたいなもんですから、古来より日本人とデマは親和性が高かったのかも知れません。
退会したユーザー ゲスト | 2024-05-27 18:08
退会したユーザーのコメントは表示されません。
※管理者と投稿者には表示されます。
深山 投稿者 | 2024-05-27 19:03
2人の知識合戦があらぬ方向へ進んでいくのかと思って読んでいたらおじいさん1人で進んでました。世界の中心で〜というお題で「私にとっての中心とは」という解釈ではなくガチで中心について書かれるとは。こういうのって例え思いついても知識がなければ書けないもので感心しきりです。
知識がなさすぎて危うく信じそうでした。やはり無知は危険だなと変なところで反省しました。
Juan.B 編集者 | 2024-05-27 20:07
歴史・伝奇の流れが生かされている。
一緒に川越行った時にとんでもない歴史を垂れ流す酒蔵がありましたね。
あーヤバイぞヤバイぞと思ってたら、東日流外三郡誌。美しい展開。
髙井さんにはもう少し広い視野を持ってもらいたい。