あの日、夏休みが明けて、私は持ってきた銃を見せるのが恥ずかしかった。みんなが作って持ってきた銃は立派だったけど、私の作ってもらって持ってきた銃は不格好だったからだ。逆立ちした病気のアシカみたいだった。母さんが昼も夜もお水で、しかも私のぐうたらさで、夏休みの他の宿題にひーこらで、代わりにおばあちゃんに作ってもらったのだ。みんなは思い思いにカラフルな色彩に塗った銃を自分の手で拵えてきていたみたいだけど、私の銃はすごくにびいろに光っていた。本当に、逆立ちした病気のアシカみたいだった。隣の席の男の子がこそこそ隣の女の子に耳打ちして、げー、と舌を出していた。私の銃を見ていた。きっと変だと言ってたのだ。いや、変だと言ってるだけなら舌を出してげー、としない。きっと私の銃を逆立ちした病気のアシカみたいだと言ってたんだ。
「まかしどけ、ばあちゃん、革命に参加したごどあっがら、銃なら撃ったごどあるし、作れっぞ」
一人一人、教壇に立って自分の銃にまつわる話を考えて来なければならなかった。去年はおばあちゃんから聞いた、失敗したクーデターの話をしたら先生に後から呼び出しを食らって大層褒められてしまったので、今回は気をつけなければならない。褒められるのが私は何より苦手だ。「クーデターが『失敗』した」というところが先生を喜ばせたようだ。出る杭は打たれるという言葉通りでいいね、と先生はにこにこ顔で言ったのだった。
私の番だ。私は話す。
「私は周りのおばあちゃん以外の大人たちから『美咲はおばあちゃん子だね』とよく言われます。おばあちゃんだけはそう言いません。それはもしかしたら、おばあちゃん本人の照れ隠しもあるのかもしれないけれど、それよりも私が気になってしょうがないのは、自分が『おばあちゃん子』だと言われるほど、良い子ではない、ということです。これは照れ隠しではなくて、ほんとの本当に自分がそう呼ばれるほど、良い子ではないと思っていたからです。この銃も、ほんとはおばあちゃんが拵えてくれました。自分で作りませんでした。私は、私は、あんまり、あんまり、おばあちゃん子じゃなくて……、おばあちゃん、昨日死んじゃって」……
あの日私は自分の銃を見つめながら終いには泣いてしまったんだ。おばあちゃんは夏休みの最後の日、亡くなった。まだ六八歳だったという。私はいても邪魔だからというので次の日には忌引きもせず学校に行かされたのだった。私、おばあちゃん子じゃなかったの? 大人に歯向かう度胸はなかった。
隣の市に水族館があり、そこは今ではリニューアルしてクラゲがメインの展示になっているが、そうなる前、昔ははやらなかったらしい。そこでアシカを見た。芸のできない間抜けなアシカだった。その私の銃のつがいにお似合いな。それを私はおばあちゃんと見た。
男女別々の授業だったらよかったのにといまだに思う。あの発表の時に泣いたせいで、男子からいじめられることになったからだ。
父と最後にあった日のことを覚えている。父は母より三十も年上で、私が中学に入るころは老人施設に入っていた。ちなみにその頃、母はスナックのママになっていた。その母(ママ?)と最後に面会に行った時の事。父はずっとほうけたように本棚の欠けた角を気にしていた。ある夜、流れ弾が窓を破って飛んできて、跳弾した跡だと父は何度も独り言ちた。父はもともと大工で、こういった木材の「欠け」が気になってしょうがない質だった。中学生の私にとって、そんなことを気にする父の老いた姿こそが思い出に傷をつけた跳弾だった。
食事制限されている父の部屋で、わざと母は幕の内弁当や甘い和菓子を食べた。母は「これが私の仕返しなんだよ」と、いつも帰りに車を運転しながら言った。「施設の金だってばかにならない」
中学に上がってからも、私は相変わらずいじめられていたが、父が死んだ瞬間から、そんないじめのことなどまったく気にしなくても生きていけるようになった。父の部屋にはまたしても窓を破って流れ弾が飛び込んできた。前よりも強力な弾だった。流れ弾は今度は父の頭を突き破った。弾は頭の中を何度か跳弾し、飛び出して、あの本棚で止まって、あの「欠け」を丸々粉砕した。これでもう、父の憐れみを誘う姿を見なくっていいし、父自身も悩まずに済む。変なふうに試行錯誤のあとが見て取れる、「修復」された父の死に顔を見たときそう思った。気が楽になった。
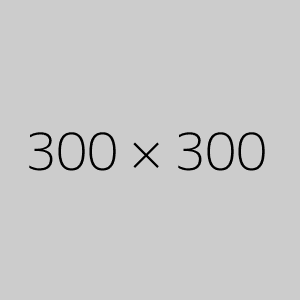























"アシカと蝙蝠とおばあちゃん子と"へのコメント 0件