あれは、わたしがまだプライマリースクールの頃のことだ。
サマバケのホームワークのフリーレポートをどうするか家族に相談したところ、パパに頼んで当時営業を始めたばかりのシミュレイテッド・エクスペリエンス・ファシリティーズに連れて行ってもらうことになった。少し費用はかかるが、うちのパパは娘の頼みならなんでも聞いてくれたのだ。
ビューローには複数のシミュレイテッド・エクスペリエンス・フレーム(SEF)が設置されていて、当時は開業から間もないはずだが体験テーマは千八百種類から選択できた。わたしは「ミドル・サードミレニアムのスカイフックテクノロジー」を課題に選んでいたので、シンガポール・スカイフック(SS)の実地体験コースを指定した。約三時間の疑似体験旅行で、今はもう解体された美しくそびえるSSを、あたかも実際にそこに行ったことがあるように体験することができるものだ。
タンポポイエローで繭型のSEFのハッチを開けて乗り込んだ。その頃はまだSEFはシートモデルだったのでコックピット状の椅子に着座し、ガイダンスに従ってコンソールに接続されたヘルメットとバイザーを装着した。ヘッドフォンからのアシスタントパーサーのコールでドリーミングがスタートする。心地よい音波で十二歳のわたしは即座に眠りについた。
コンソールのアラートがけたたましく鳴り響いて、わたしは目覚めた。
SEFのウェイクアップコールにしては音量が大きい。とりあえず「Touch」という表示を触って音を止めた。その上の正面のメインパネルには大きく「OFFLINE」の文字が点滅している。APへ異常を知らせるエマージェンシーコールのボタンを押してみたが、ヘッドフォンからプープーと小さく呼び出し音が聞こえるだけで、誰も応答しなかった。
ヘルメットを外して、コックピットの中をあちこち見て、とりあえずの電力はあるようなので外に出るぐらいはできるだろうと思い、ハッチの開閉ボタンを探した。シートバックの背面に赤いレバーがあり、EEと書いてあった。ぐっと引き抜くと、シートがせり上がり、上部ハッチがゆっくりと開いた。エマージェンシーイグジットで正解だったようだ。
金属製のレバーは抜けてしまったが、再度閉じるときには差し込むように図示してあった。わたしはレバーをヒップポケットに差し込み、MPC(多目的パーソナルコンソール)をセンターパネルから引き抜いた。MPCのバッテリーを確認するとほぼ満タンだった。三日は保つだろう。さすがにそれまでにはトラブルも解決する。
SEFの外は真っ暗で、灯りは全て消えているようだ。電源のトラブルでもあったのだろうと、コックピットのサイドシルを乗り越えて、床に立った。ギシリと不思議な音がした。床のパネルが外れかけているのだろうか?
もう一歩踏み出すとまたしてもギシリと音がした。暗闇を見渡すと、壁の方にうっすらと明かりが見えた。わたしはギシギシと歩いて明かりの近くまで移動した。どうやら壁にかけられた布のスキマから環境光が漏れ出してるようだ。布をまくり上げてみた。まばゆい光がわたしの視力を奪った。
しばらく目がくらんで何も見えなかったが、じわじわと視力が回復してくると、この部屋には何もないことがわかった。古くさいフローリングの床、シンプルな調度品、生活感のない空間、そして不快な匂い。カビの匂いかホコリの匂いか、その中にポツンとSEFが設置されていた。いつの間にこんな部屋に移動したのだろう。それともこれはドリーミング中の光景なのだろうか。以前SEFを体験したときは、ドリーミング中にSEFが登場することはなかった。いきなり疑似旅行の状態に飛び込むのが通常だ。
久しぶりなので、最近はこういう演出なのかもしれない。わたしは幼いなりにそう解釈して、この世界を探索してみることにした。
その窓の外は針葉樹林で、他には何も見えなかった。
まるで大昔の発掘映像で見たエウロペアの山岳地帯のような雰囲気だ。少なくとも近所で見られる光景ではない。ということは、ここはすでにSEFが造り出す世界なのだろうか。床をどんどんと踏みならしてみたが、見たままの安っぽい床パネル特有の弾み方で、音も感触もリアルだった。最近のSEFは結構な進化を遂げたのだな、とわたしは思った。そして、その世界はSEFの世界だと信じたのだ。
シンガポールの辺りは熱帯なので常緑広葉樹か、単子葉類の植物が中心だと思っていたのだが、必ずしもそうでもないのかもしれない。あるいは、なんらかのトラブルでSSではない別の体験コースが始まってしまったのかもしれない。だんだん様子がわかってきたので、少しこの世界の様子を調べてみることにした。SEFのフロント方向の延長線上にドアらしきものがあるので、そこから外に出てみることにしよう。データの用意されていないエリアであれば、ドアは開かないはずだ。結局ドアは開いた。だいぶ大きな音はした。
部屋の外はホールのようになっていて、紙製の大きな運搬用ボックスが乱雑に積み上げられていた。文字は読めないが、なんとなく食品のパッケージようだ。隙間からのぞいてみると中にはウェスやら、掃除用具などが押し込まれていた。手書きのコーションが書かれているので、おそらくこれらの器具類を一時的に収納するために流用しているのだろうと思った。他のボックスにもだいたい同じようなものが入っていた。
箱の森をすりぬけると、少し広いホールのような空間に出た。だだっ広い中にテーブルとチェアが山積みになっていた。ここは休業中か廃業したレストランかなにかなのかもしれない。調度品はそれ自体は新品のようだが、様式がずいぶん古い気がする。工業技術も未発達に見える。ここは当時は連合政府の首都だった。さすがにこんな田舎ではないはずなので、やはり別のプログラムが始まってしまったのだろう。
壁には水着で微笑んで炭酸飲料を宣伝する女のポスターが貼られていた。
大きなガラス戸から外に出られそうだったので下にある回転式のロックを解錠してみたが、押しても開かない。左右向きの矢印が描かれているので、横に開く扉かもしれない。思い切りこじ開けようとしてみたら、じわじわと開きはじめた。
子供がすり抜けられる隙間が開いたので、無理をするのはそこまでにして外側へ出た。
もう一枚同じようなガラス戸があったが、こちらはロックを解錠して前方へ押したら簡単に開いた。
外はむせるほどの青臭い空気で満ちていた。嗅覚までこんなにリアルなんて本当にすごい!
鳥の鳴き声も再現されている。少し気温は高いが、そよかぜがあるので気持ちがよかった。遠くで虫の声もした。遠近感がすごい。
シンガポールではないようだが、ここはここで良い体験ができそうだ。テーマは変更せざるを得ないが、宿題の心配はなさそうだ。
不意に、ガサッと草むらが動いた。
わたしは驚いてバランスを崩し、金属製の階段を踏み外して二、三段落ちてしまった。幸いケガはしなかった。慌てた声で少年が駆け寄ってきた。東洋人のようだ。
「オドカシテゴメン。ケガハナイ?」
即座にMPCの自動翻訳が起動した。どうやら彼はわたしの体を気遣ってくれているようだ。MPCの翻訳機を通して「気にするな」と伝えた。このSEFプログラムは吹き替え版ではないらしい。たぶん、ジュニアハイ用のプログラムなのだろう。少年はMPCに驚いてまるでサルが見たことないエサを与えられたときのように、珍しそうに眺めていた。そうか。この時代はまだMPCが無いというシナリオなのかな。
どこから来たのかなどと聞かれたので、外国からと答えておいた。彼は片手に紙製のノートブックを持っていた。逆折りになった紙面には、何か記号などが書き込まれていた。わたしは彼に、ノートに何を書き込んでいるのか聞いてみた。
「コノヘンノキカショクブツノブンプヲシラベテンダ」
ナニ植物と言ったのかよく判別できなかったが、何かプラントについてリサーチしていることはわかった。「ホラ」と言ってフィールドノートを見せてくれた。この辺一帯の手書きのマップになっていて、×印が何色かに分けて記録されていた。どういうことか聞いてみると、彼もサマバケのホームワークのフリーレポートで、この辺りの野草の分布を毎年調べているのだそうだ。ずいぶんドレアリーなテーマを選んだものだが、毎年エリアのプライズを受賞しているそうで、彼なりの成果を上げているようだ。
彼は「ハーダ・アキーミ」と名乗った。わたしも「マグ・ナカータ」と伝えた。彼のファーストネームは「アキーミ」の方らしいので、ここはイーストアジアのどこかなのだろう。わたしは「マグ」と呼ぶようにアキーミに伝えた。アキーミは「オッケー、マグ」とはにかみながら答えた。ちょっと馴れ馴れしいが、悪い気はしなかった。わたしはたぶん少し不安だったのだ。
階段に腰掛けてリサーチを再開したアキーミを眺めていた。
どうやらヒメジョオンやハルシオンなどの野草の植生を調査しているらしい。一株一株数えてはフィールドノートに記録していた。気長な根気のいる作業だ。よくやるよと思った。
熱心に野草を数える彼を見ていて、わたしはSSをSEFで見ただけの簡単なレポートで済ませようと思っていたので、少し恥ずかしい気分になった。
このレストランのような建物の正面には、雑草に覆われた広い空き地があった。空き地の奥の方には鉄骨を組み上げた、ロープウェイのような設備があった。脇にアームが生えたチェアが積まれているので、おそらくロープにそれを組み付けて、斜面の上の方に人員輸送をするものではないかと思った。
昔のウィンタースポーツにそういうスタイルのものがあったのは歴史の教科書で見た。なるほど、ここは古代のリゾートエリアかなんかなのだな
プログラムのテーマにしてはだいぶドレアリーだが、近隣に何か特別な文化遺跡か自然遺産があるのかもしれない。
アキーミがだんだん離れていってしまったので、なんとなく不安になった。リサーチの進捗でも見せてもらおうかと立ち上がったところで、下の方でカチャっと音がした。振り返ると、ヒップポケットに入れておいたはずのレバーが、鉄格子のステップの下に落ちていた。格子を持ち上げてみたが、ガチャガチャと少し動くだけで持ち上がらなかった。左右の端を見ると、大きなボルトナットで固定されているようだ。ステップ間の隙間に潜り込もうとしたが、わたしの体格では無理だった。
異変を感じたのか、アキーミが戻ってきてくれた。わたしは少しだけだが、うれしかった。
「ナニ? ドシタ?」
心配して様子を尋ねてくれたようだ。わたしはレバーを指して、あれが必要だと言うことを伝えた。
SEFを正常に終了させるには、SEF内に戻ってハッチを閉じる必要がある。戻れない場合、わたしはこの仮想世界から復帰することができず、廃人同様のヒューマンベジタブルになってしまう。それは非常に困る。
わたしの異常を理解して、彼も格子を揺すったり、中に潜り込もうとしてくれたが、それらは無駄だった。
ボルトナットを外す工具がないかと周辺を探してみたが、径が合うようなスパナは見つからなかったし、落ちていたバールのようなものでこじ開けようとしてみたが、キッズの力ではビクともしなかった。
アキーミが平手を拳で叩くような奇妙なポーズをとって「ヒラメイタ」と言った。何か思いついたらしい。
ポケットから菓子を取り出して噛みはじめた。だいぶ長く噛み続けてから、指で取り出して、近くに立てかけてあったバンブーポールの先端に塗り付けた。一つでは足りなかったので、もう一枚噛みはじめ、わたしにも一枚渡してきた。
奇妙な食べ物を口にするのは抵抗があったが、レバーのためだからと割り切って、思いきって口に含んでみた。
ベリー系の味と香りが口に広がった、まるで本当に食べているような感覚で驚いた。
しばらく噛んでいると、味はしなくなってしまった。口から出すと、アキーミはそれをつまみ上げて、自分の出したものと混ぜて練りはじめた。なんだかインディレクトキスのようで恥ずかしかった。まだファーストキスもしてないのに。
先端に3枚分の噛みかけの菓子を塗りつけたポールを隙間から差し込んでみた。しかし、角度が合わずなかなかレバーに届かなかった。
折って突っ込んでみたものの、結局は粘着力が不足していたのかレバーは持ち上がらなかった。
難しそうな顔で考え込んでしまったところを見ると、このヒラメイタは失敗だったようだ。
今度はヨーガのザゼンのポーズをとって、ブッダスタイルでメディテーションを始めた。
なにかブツブツと言っていたが、やがて「チーン」と言って目を開いた。
そして「ソウダ、デンジシャクヲツカオウ」と言った。エレクトロマグネットを使うというのだ。どうもわたしの名前から連想したらしい。
しかし、そんなものが都合よく手に入るのだろうか?
アキーミが言うには、このゲレンデの上の方の山中に、メジャーなユニバーシティの所有するロッジがあり、そこに行けばそこにステイしている学生らが持っているだろうとのこと。なんでそんなものを持っているのかと聞くと、地元のキッズ向けのサマースクールをボランティアで開催しているらしく、そのメニューのひとつに、電磁コイルを利用したモールスシグナルマシーンを作るというものがあったようでその材料があるはずだということだった。なるほど、それならどうにかなるかもしれない。
どのぐらいの距離か聞くと、よくわからないと言った。道順とだいたいの位置は知っているが、実際に行ったことはないのだそうだ。
学生たちは、サマースクールの会場であるアキーミのスクールまでウォーキングで来ているそうなので、そんなに遠いこともないのだろう。とりあえず行ってみることにした。
アキーミはリサーチを中断し、フィールドノートをバックパックに仕舞い込んだ。
正面の急斜面を上るのはさすがに無理なので、なだらかな迂回路を選択した。
アキーミはこのゲレンデの地形を熟知しているようだ。なぜかと聞いてみたら、このゲレンデにあるウィンタースポーツのクラブに所属しているのだと言っていた。冬になれば一面に雪が積もって、この急斜面を滑り降りる競技をやっているのだと。何が楽しいのか理解はし難い。スリルが味わえるということなのだろうか。一種のバンジージャンプのようなものなのかもしれない。
しばらく彼に付いて歩いていたら、急に振り向いて「アレ?」と首をかしげた。「ナンデイッショニクルノ」。同行がいけないのか。どうやら彼はわたしをあのレストランに待たせて、自分一人でロッジまで行くつもりだったらしい。冗談ではない。何時間かかるかわからないのに、こんなところでポツンと一人で待たされるなんてごめんだ。
でもそれを言うのは恥ずかしいので、キュリオシティを満たすために一緒に行くのだとウソを言った。彼は納得してくれて、同行することに同意した。
迂回路の緩斜面とはいえ、整地されていないところを歩くのは辛かった。急斜面の上側まで回り込んだところで休憩にした。
不思議と腹が減っていた。SEFなのに。
アキーミがさっと何かを差し出した「タベル?」。食べていいようだ。
受け取ってみると、どうやらライスボールのようだが、何か黒いシートが巻いてある。シートをはがそうとすると、「ソノママソノママ」と言って、自らかぶりついてみせた。
なるほど、このシートは食用なのだな。ライスボールは塩気があって美味だった。ヤミー!
中にはブツブツとした赤い何かの塩漬けが入っていた。不思議な食感だが、これもヤミー!
アキーミの方には海藻の塩漬けが入っていた。この地方の食料品のようだ。一人に一つずつしかなかったが、ひと心地はついた。
わたしたちは旅を続けることにした。
もう少し上ったところで、舗装された道路が見えた。ここから先は、道路を歩くらしい。歩きやすいのでありがたい。
少し楽しい気分になった。空気も澄んでいて爽快だった。
わたしはアキーミの手を引いて走り出した。彼は「チョットチョット」と声を上げた。何を言ってるかわからないが、わたしはとにかく楽しかった。
SSなんかより、きっとこの冒険の方が何倍も楽しい。そうだ、わたしもプラントの調査をホームワークにしよう。アキーミを手伝って、調査結果をコピーさせてもらえば、クラスティーチャーも驚くにちがいない。エンシェントプランツの分布リサーチなんて、なんてアカデミックなテーマだろう。ドレアリーだけどね。
ふと、アキーミが立ち止まった。じっと足元のダンデライオンを見ていたが、急にしゃがみ込んでダンデライオンの花を裏向けにして見た。「オア!」と驚きの声を上げた。MPCにはアメイジングの文字が出ていた。何か発見したらしい。
どうしたのか聞いたら「エゾタンポポダ!」と叫んだ。MPCにはホッカイドウダンデライオンと訳が示されていたが、意味はわからなかった。
彼の驚き方からして、エンデンジャードスピーシーズか何かなのだろうか。彼の長い説明を要約すると、この辺りは数年前までは在来種のエゾタイプが主流だったのだが、一世紀ほど前に他国から持ち込まれたユーロピアンダンデライオンの方が勢力を伸ばし、この高山地帯にもいよいよ押し寄せてきたのだという。エゾタイプとユーロタイプは花の裏側のケイリックスを見ればわかる。ユーロタイプはめくれるように反っているのだが、このエゾタイプはプレーンな形状をしているのだ。
この分布リサーチも彼の研究対象の一つだそうだ。
彼は一通り説明を終えると、先を急ごうと言った。調査は後日でいいと。
わたしを気遣ってくれるのがうれしかった。急に色白で細身の彼がたくましく見えたが、それはたぶん気のせいだ。
結局そこからロッジまでは二時間以上もかかった。
道を誤ることはなかったが、距離がまるで予想外だったのだ。
序盤はいろいろおしゃべりもしたが、後半は二人とも無口だった。
アキーミもリサーチは完全に諦めて、フィールドノートをバックパックに戻していた。
ロッジに到着するとアキーミが大声で「センセー!」と叫んだ。
しばらくすると中から「オ? ドウシタン」と大人の男性が顔を出した。アキーミはセンセに事情を説明した。
センセはわかったと言って中に戻り、黒くて細いワイヤーがぐるぐる巻かれたものと、クギを打ち付けた板きれ、大振りなドライセルを数本持ってきた。
センセはアキーミに三つのアドバイスを与えていた。ワイヤーはできるだけアキュレイトリーに巻くこと、AMAP巻くこと、ドライセルはシリーズに繋ぐこと、だった。
センセはシンプルなチョコレートクッキーをわたしたちに分け与えてくれた。良い人だ。
アキーミはノートにアドバイスをメモをして、このインストラクターとシェイクハンドしてわたしたちはロッジを後にした。
往路よりは復路の方が早かった。
道がわかっていたこともあるが、下り坂だったのも大きいだろう。
最後の斜面も転げ落ちるようにゲレンデの雑草の中を二人で駆け下りてきた。
息を切らしながらレバーを落としたレストランの鉄格子のステップに腰掛けた。
アキーミはコットン製のスティッチの粗い服を着ているので、全身がコックルバーまみれになっていた。わたしの服はシンセティックファイバーでマイクロスティッチなのでほとんどついておらず、彼は驚いて、そして笑った。
アキーミは「ヤッパキミハミライジンナノカナ」そう言って、バックパックからワイヤーとクギ板とドライセルを取り出した。
未来人。わたしが未来人なら、君はナニ人なんだい? そう思いながら、彼の真剣な横顔を眺めていた。
アキーミはサマースクールですでにコイルづくりの経験があるようで、手際よくワイヤーを釘に巻き付けていった。
彼がコイルを巻くあいだ、わたしはひまつぶしに階段脇のコンクリートに石片でドゥードゥルを書いて待った。
巻き上がったコイルにドライセルを繋いでマグネティズムを発生させてみたら、かなり強力な電磁コイルに仕上がっていた。
ようやく吊り上げたレバーを手に得意気に笑う少年に、わたしはちょっと恋をしてしまったかもしれない。
あたりは少し夕日が照りはじめていた。「イソイダホウガイイ」と彼はわたしをレストランの中へ押しやった。わたしはアキーミのほほに軽くキスをして、手を振ってからSEFのある部屋へ走った。
レストランの中はもうだいぶ暗くなっていたが、あちこちぶつけながらもどうにかSEFの所まではたどりつけた。
MPCをセンターパネルのスロットに差し込み、レバーを元の場所に差し込んで押し込むと、シートが沈み込み、同時にハッチが閉じはじめた。コンソールの表示はウェルカムに変わった。とりあえず正常に動くようだ。
コマンドはリジェクションを選択した。急激に眠気が襲ってきて、わたしは意識を失くした。
夢は終わった。
気がつくと、SEFのハッチが開くところだった。
アシスタントパーサーがおかえりなさいとマイク越しに声をかけてきた。パパが手を引いてくれて、わたしはSEFから引き出された。
SSはどうだった? と聞かれたが、番組が違ったみたいだと見てきた内容を簡単に説明した。
アシスタントパーサーはコンソールを確認してそんなはずはないと困惑したが、やり直しますか? と聞いてきたので、その必要はないと返事をした。とびきり楽しいプログラムだったからだ。
しかし、その後ひたすらSEFに通ってみたが、同じプログラムを見ることはできなかった。リストにもそんな内容のものはなかった。
同じマシンが台替えで破棄されるまで乗り続けたが、何度試してもSSばかりで、あの日行った高原のレストランにたどり着くことはなかったのだ。
おかげでSSにだけは異常に詳しくなり、その論文でわたしはサイエンスカレッジにAO入試で合格できたのだった。
サイエンスカレッジに上がって四度目の夏休みに、ふとアキーミの言葉を思い出した。彼はわたしを「ミライジン」と言っていた。
担当プロフェッサーに卒論テーマを「タイムマシンの非実現性の検討」に決めたと伝えると、すんなりOKが出た。わたしはプロフェッサーに怒ってリジェクトされると思ったので、むしろ驚いたものだ。
卒論ではひたすら実現できない理由を述べた。可をもらった。理由は「完全な否定にはほど遠い」というものだった。
プロフェッサーはわたしに大学院への進学を勧め、引き続き同じテーマで研究するように言った。そしてひたすら否定をしつづけて、今のウェルズRIにも雇われて、ずっとタイムマシンの非実現性の検証を続けてきた。
わたしもプロフェッサーと呼ばれる立場になったが、それでもまだその可能性を完全に否定できていない。
その傍ら、わたしがライフワークとして取り組んできたことがある。千年も昔のレジャー文化に関する遺跡発掘調査だ。
あの日SEFで見たのはなんだったのか。あの場所は実際はどこであるのか、それを突き止めてやろうと思ったのだ。
そして今回の発掘現場は、今までになく期待が持てるものだった。うっすらとした印象しか記憶には残っていないが、この現場の地形は、あのゲレンデから見た風景に似ていた。約五百年前に溶岩流に飲み込まれたエリアなので、発掘には莫大な費用がかかった。
記憶を頼りにあのレストランの位置を特定し、掘り起こした。これまでに二ヶ所失敗している。三度目の正直であり、もう資金もギリギリだった。スポンサーからはこれ以上の援助はできないと通達されている。わたしとしても最後の勝負だった。
「マグ、見て欲しいものがある」チーフエキスカベーターがテントに呼びにきた。
ジャケットを着て外に出ると、昨夜から降り続く雪であたりはすっかり真っ白になっていた。案内されるままに発掘穴に入っていくと、雪と溶岩の下から建物の土台が露出していた。二十世紀頃によくこのエリアで用いられた様式の鉄筋コンクリート製の建築基礎だ。
問題は、これがあのレストランなのかどうかだ。
確かに溶岩の下側で鉄の格子のようなものが溶けてコンクリートにこびり付いていた。
「そこなんだが……」チーフが指さす場所を見た。記憶が鮮明に蘇った。
あの日書いたドゥードゥルがそこにあったのだ。
MAG ♡ AKI
その夜、わたしは研究テーマを「タイムマシンの実現可能性の検討」に変更した。
EOF
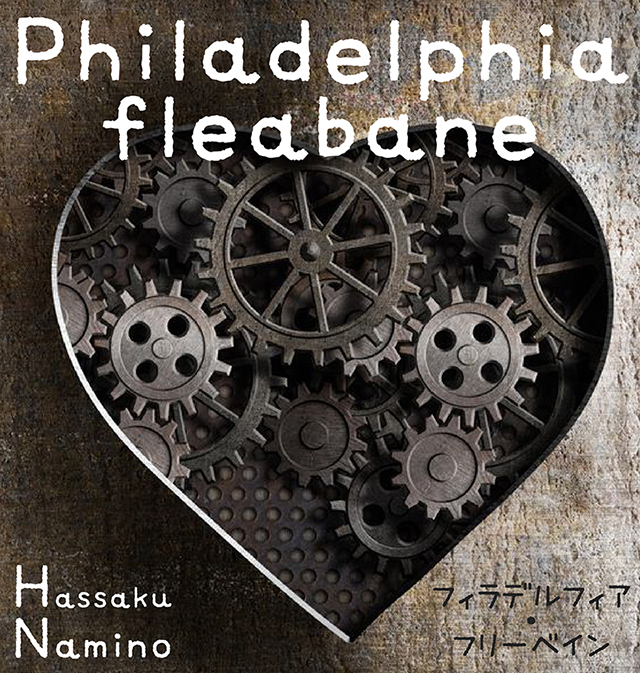





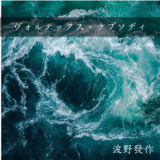




















"フィラデルフィア・フリーベイン"へのコメント 0件