伊知郎はビールを飲みながら、昼間本郷の奥さんと息子さんたちがすすめてくれたように化学肥料会社で働くかどうか考えていた。そうなれば心丈夫だ。あの親戚たちはひじょうに好意的だし。頬に蟻がうじゃうじゃ湧いた。
莫大のお金が振り込まれる口座を、明日ひらきにゆかなければならない。安永さんがついて来てくれる約束だった。
この親切な老人を如何せん。自分のことのように喜んでくれている。卑しい打算のようなものは感ぜられず、かえってなにか不用意に報いたら怒り出しそうな気さえする。
「いやァ、よかったよかった。そんじょそこらのよかったよかったじゃないよ――」
赤い顔をしてしきりにうなずいていた安永さんが、ふと着ているポロシャツを見下ろして、ため息をついた。千鳥格子のワイシャツを白いポロシャツと一緒に洗濯機に入れてしまい、色移りしてしまって、淡い千鳥格子になってしまったのだった。さらに靴下から若干ニット素材も移ってしまって、少々暑くもあるそうな。
「私は昔は灯台守でな、じつに色々な海を眺めた。旅がらすでね。異動があるもんで。灯台守は国家公務員だからさ。……あれは遠い昔だ。……遠い遠い昔だ……」
安永さんが酔いつぶれて眠ると、伊知郎は静かにアパートを出て入り江へ向かった。
夜の町なみはやわらかだった。どこかで変な声の梟が鳴いていた。
――泣いている未来が楕円、怒っている書物が鋭角、笑っている句読点が因果律である場合、眠っている発端はなんであるか?……
――一卵性双生児の片方が〈生〉でもう一方が〈死〉である場合、二卵性双生児の片方が〈ペットボトル〉ならもう一方はなにか?……
砂浜に立った。前方には夜の海が見果てなく続いていた。月はなく、澄んだ夜空に見たことのない星座がかかっていた。
ふいに、風もなければ船も通らないのにひじょうに大きな波が来た。逃げ遅れた伊知郎は腰まで濡れて、しぶきが顔にかかった。すると頬から蟻が、ぎゃあぎゃあ喚きながらこぼれ落ちた。あとからあとからひり出て来ては盛大にこぼれ落ちて行った。波は落ちた蟻たちをさらって海に引き返し、ふたたびなにもかもが静まった。
濡れて黒々した砂浜に伊知郎は立ち尽くしていた。
頬を触ると、すべすべしている。きっと鏡を見れば幻のぼこぼこした巣の痕が残っているだろうし、それは同病者には見えるだろうが、もう蟻たちの気配はどこにもなかった。
昏睡から覚めたように、猛毒が抜けたように、意識が透き通った。窓を閉めたように、鎮火したように、めまいや耳鳴りが消えた。
他人事だった心肺や胃腸が帰還し、脳髄が帰還し、手足の指先が帰還した。
自分がまだ若者であるという事実が思い出された。すべてのあいまいなる自覚症状は――症状を自覚する主体自体のあいまいさは――イソギンチャクのように一瞬でしぼんだ。
海の匂いが強い。自分はこんなに生きていたのかと思った。ひんやりと肌寒いけれど、慢性的な悪寒が去って――慢性的な悪寒に起因する慢性的の不感が去って――ただこころよく涼しかった。足の下の地面はしっかりと不動なる頼もしさを取り戻していた。
快癒した自意識の花園の中で色々なことを発見していた。いつまでも飽きなかった。けれどもいい加減のところでやめておくことにした。とにかく世界はもう一度冴え渡ったのだ。
ふと見やれば、先ほどの波で少々打ち上げられたボートが砂の上に傾いている。
空が白み始めていた。
――さて。(と伊知郎は思う。)なにもかもが解決し好転した今、ここですべてを捨てて元の世界に帰ったら、長々しかった我が青春はようやく幕を閉じ、青春ではなくなったものが漫然と続いて行くだろう。
なんとかして会社に戻り、まあ伯父か美濃部にでも紹介してもらって、結婚して子どもができればよいな。妻も子どもも作喪衣渡町での蘇生と莫大な遺産相続の話を、まあ信じてくれないだろう。それもよし。それとも最初から秘密にして、一人ほくそ笑みながら墓まで持って行こうか。それもまたよし。
あるいはある晩、一緒に眠っていた妻は穂野に起こされて、わたくし本郷伊知郎の奥部の人物(知明)の所有権について二、三の脅迫を受けるかもしれぬ。それとも二人の女性はわたくしの寝たあとに語らう仲となるかしら。
「それにしても穂野さんってば、伊知郎さんの中に閉じ込められていて可哀相ね」
と妻が言うと、穂野は軽やかに笑って、それは的外れな同情よと答える。妻はいぶかしげな顔をして、
「どうしてよ。あっ、もしかして、そっちじゃ知明さんとラブラブだったりして?」
「ううん、知明は、やっぱりずっと眠ってるの。伊知郎さんが男で、知明も男だからじゃないかな。わたしはこうやって、ひそかに分裂できるんだけどね。きっとわたしが女だからでしょうね」
「ふうん。ややっこしいのね。でもそれならどうして的外れなの?」
「それはその――……じつを言うとね、うちの知明が常々憧れてる、こんなふうになりたいなっていう理想の男性が時々通り過ぎるんだけど、わたしすごくモテちゃって。あんがい捨てたもんじゃないのよ。でもこれだったら浮気じゃないでしょ」
これを聞いて妻は目を丸くしたが、穂野も目を丸くし返して来たので、プッと吹き出し、笑いころげた。
「ちょっと、伊知郎さんが起きるでしょ」とたしなめられて、目じりの涙をぬぐいつつ、
「だって穂野さん、そんなの知明さんの父親と寝るよりヤバい浮気よ」
「ええ? そんなことないよ。だってあの人たちは知明の理想の自分なんだよ?」
「だから残酷なのよ。それ、本人には絶対ばれちゃ駄目よ」
「それができないのよね。私たちってテレパシーでつながっちゃってて。嗚呼……もめるかなあ」
「もめるもめる。まあ、その理想の姿っていうのがどういうものかにもよるけど」
「それはつまり、知明のがその、ごにょごにょで」
「あらそうなの? それじゃ理想の人たちのは大きいの」
「すごく大きい。別に気にしなくていいのにね」
「だめだめ。男にとって肩書きとサイズは切実な問題よ」
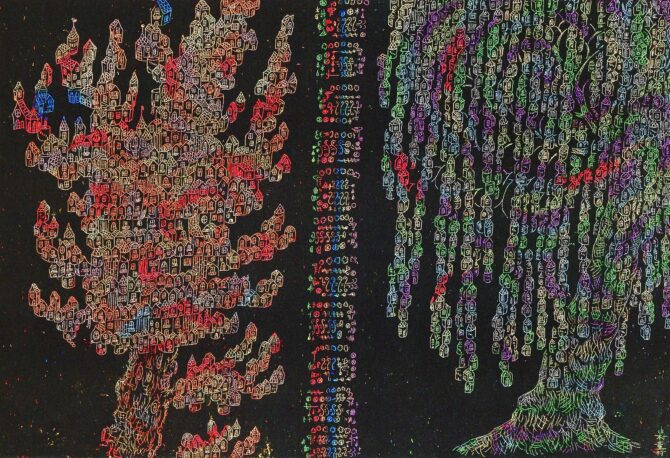
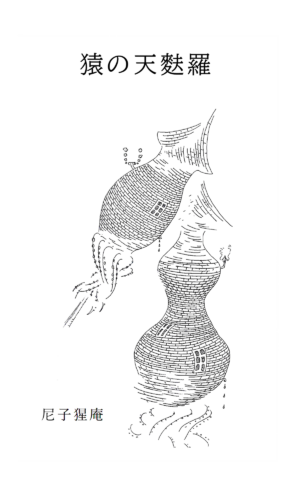











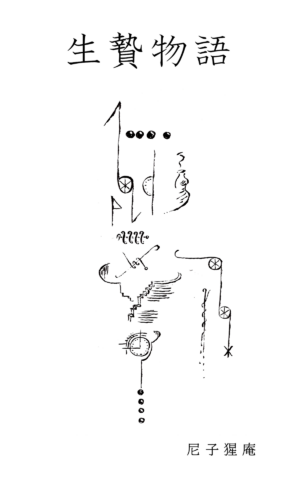










"猿の天麩羅 13"へのコメント 0件